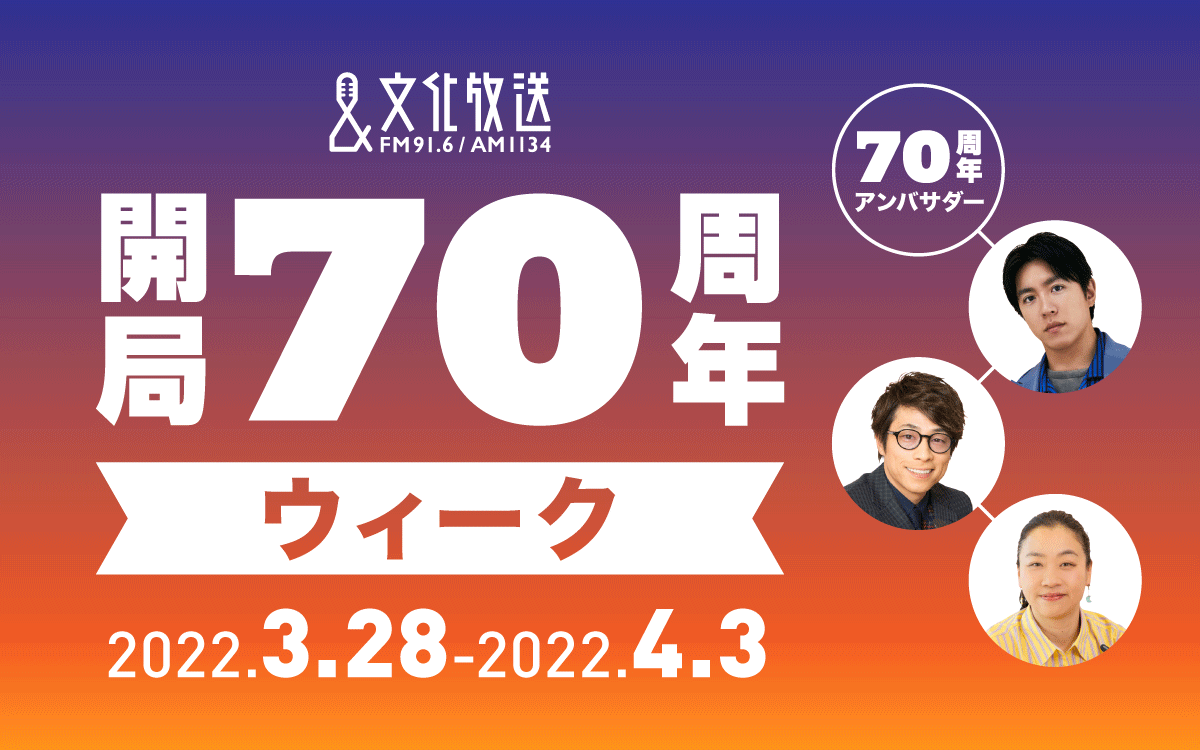「第5スタジオは礼拝堂~文化放送 開局物語」第3章 コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ
文化放送は今から70年前、イタリア人の神父たちの手によって設立されたことをご存知ですか?異国の地で東奔西走しながらラジオ局を開局させるまでの秘話を、連載形式でご紹介しています。※毎週火曜日更新
第1章:「それはチマッティ神父の買い物から始まった」はこちら
第3章「コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ」
マルチェリーノとベルテロ、そして中国に向かう2人のあわせて4人は、イタリア南東部にあるブリンディジという港町から上海に向かう船で旅立つことになった。

現在のブリンディジ 🌞 Myriam 🌞 NFT forbiddenによるPixabayからの画像
まずはローマから列車でブリンディジに向かう。小さな手荷物に中くらいの旅行鞄、そして大きめのトランクの3点セット。ポケットに入れた財布には創立者アルべリオーネから与えられた500リラが申し訳なさそうに収まっていた。駅で降りた4人は、港に近い広場に向かった。そこでコバルトブルーの海を眺めながらひたすら船を待ったのだが、待てど暮せどその船が来ない。波止場に腰かけて数時間後、ようやく大きな汽笛とともに巨大な客船が遠くに現れ、こちらに近づいてきた。のちにベルテロは、姿を見せたコンテ・ヴェルデ号を「まるでクジラのようだった」と記している。船は大勢の乗客を乗せて、イタリア北東部のトリエステ港を出発、イタリア半島の東海岸を南下し、ブリンディジ港に入港してきた。マルチェリーノたち4人は、途中乗船したことになる。
このコンテ・ヴェルデ号、1923年に就航した当時は乗客定員2430名の超大型客船だった。南米とイタリアを結ぶ船で、1930年に行われた第1回サッカーワールドカップ・ウルグアイ大会の際、ヨーロッパの選手団を運んだことで知られる。当時は、ヨーロッパから南米まで大西洋を渡るのに船で半月かかった。「なぜ往復で1か月もかけて船に揺られ、外国までサッカーの試合をしに行かねばならないのか?」というのが選手たちの本音だったようだ。関係者たちが、サッカーもこれからは国際試合の時代なのだと選手を説得し、その結果、フランス、ベルギー、ルーマニアの選手たちが、ジェノバを出発したコンテ・ヴェルデ号で海を渡ったという。最新鋭の豪華客船だということも、選手たちの心を惹きつけたかもしれない。実際、当時のFIFA(国際サッカー連盟)会長、ジュール・リメは「素晴らしい船旅だった」と書き残している。

『コンテ・ヴェルデ』の絵ハガキ (ロイドサバウド社)
ところがコンテ・ヴェルデ号は、世界的な大恐慌の影響で、1932年に客室の数を大幅に減らすことになる。恐慌は海運業界を直撃し、経営再編を余儀なくされた。客室を600人台に作り直し、残るスペースは貨物室に大改造。航路も南米行きからアジア行きに変更された。つまりマルチェリーノたちが搭乗したのは、貨物船と客船を兼ねた「新生」のコンテ・ヴェルデ号だった。
さて潮の香りを感じながら、期待に胸を膨らませて船内に入った4人だったが、少しがっかりした。小さな窓がついただけの監獄を連想させる部屋だったからだ。気を取り直して部屋を眺め直してみた。2つ並んだ2段ベッドは小ざっぱりしていて清潔そうだ。まんざらでも無い気持ちも湧いてきた。そもそも昼間は部屋にいる必要は無い。甲板でのんびりしていれば良いではないか。どうしたって、しばらくこの部屋が我が家になるのだから、無理をしてでも気に入ってみようと腹をくくった。2つ並んだ2段ベッド。下2つはマルチェリーノとベルテロの年長組がそれぞれ使用することになり、上のベッド2つは中国へ向かう若者2人が使用することになった。ようやく一段落したところで、疲れがどっと出てきた。列車の長旅と船を待つことでくたくたになっていることに気が付いた4人は、とりあえずベッドに身を横たえてみた。
「ああ、これで本当の宣教師になるのだな」 例えようの無い感慨がマルチェリーノを包む。ひとしきり寝転がった後、ゆっくりと体を起こしてトランクを開き、荷物の整理をし始めたところで、大きなモーター音とともに大型客船が波止場を離れ始めた。4人は甲板に飛び出し声を上げた。
「愛する祖国イタリア!!」
少し感傷的な気持ちで、ベルテロは離れつつあるイタリアの港を眺めていた。マルチェリーノは大きく深呼吸すると部屋に戻り、再び荷ほどきの作業を始めた。その間も船は東地中海を進む。ちなみに乗客の中には十数人のイタリア人宣教師やシスターらがいた。話してみると、彼らの行き先はインドや中国、フィリピン、オーストラリアなど様々だったが、最終目的地が日本なのは、マルチェリーノとベルテロの2人だけだ。東洋の中でも、日本はもっとも遠くなじみの薄い国なのか。少しだけ心細い気持ちにもなったが、マルチェリーノはそれをはるかに上回る冒険心で溢れていた。4人は時折、部屋の小窓から外を眺め、時には甲板に出てクレタ島などギリシャの島々を満喫した。気持ちの高ぶりは、イタリアを離れれば離れるほどむしろ強くなってゆく。遠くに幻影のように浮かんでいるのはパレスチナだ。イタリアを離れて2日後、船はエジプトのアレクサンドリアに着いた。「異国」に来たのだ。
エジプトで人情に触れる
コンテ・ヴェルデ号はアレクサンドリアから、ナイル河のデルタ地帯に沿ってエジプトの海岸線を東に進む。そしてスエズ運河の入り口にあたるポート・サイドの港に近づくと、接岸せずに沖で錨を下ろした。船も少し休憩することになり、その間、ベルテロ1人が町に向かうことになった。ベルテロは町の見物とともに「買い物」という重大な使命を兼ねていた。船はこの先、アフリカからインドへと向かう。灼熱の南国では、黒の服は見た目にも暑苦しいし、何より体が辛い。そこでベルテロが代表で町に出向き、4人分の白のカソック(神父が身に着ける平服)を買うことになったというわけだ。数人を乗せた小舟に揺られてポート・サイドの町に降り立ったベルテロは、この瞬間を「冒険の第一歩」と記している。熱風を吸い込みながら、露店が軒を並べる一角に出たベルテロは、今まで体験したことの無い雑踏、喧噪の中を歩いた。これほど強烈な香辛料特有のエスニックな香りを、イタリアでは嗅いだことがない。ようやくカソックを陳列した衣服店を見つけ、店の前で足を止めた。大声で呼び込みをしている店員にフランス語で値段を尋ねてみたが、言葉が全く通じない。普段は穏やかなベルテロだが、たまらず
「何で、通じないんだよ!」
とピエモンテ弁(イタリア・アルバ地方の方言)で叫んでしまった。すると、店員の表情が驚きから笑顔に変わった。
「何だ、あんたはイタリア人かい。俺もだよ! だったら最初にイタリア人だと言ってくれよ」
店員は、旧友に会ったかのように懐かしそうな表情を浮かべてベルテロの肩を叩いた。ベルテロは、その時初めて、エジプトで暮らすイタリア人がいることを知って驚いた。しばらく雑談した後、その店員は少し寂しそうに
「年を取ってからでいいからさ。いつかイタリアに帰りたいんだよな」とつぶやいた。そして、言葉を続けた。
「ところで神父さん! 好きなものを4人分選んでくださいな。そうそう、お代は1人分で良いよ。だって、イタリア人同士じゃないか!」
持ち金の少ない4人にとっては、実にありがたいひとことだった。店員は、旅の安全を祈りながら、丁寧に4着のカソックを包装し、最後に笑顔で声をかけてくれた。
「神父さん、長旅どうか気をつけて」
「ありがとう、店員さん。あなたも元気でお暮らしください」
旅の第一歩で、ベルテロは同胞の温かさに触れ、1着分の値段で4着分を持ち帰るという幸運にも恵まれた。ベルテロは船に戻ると3人に対し、安くカソックを買った経緯とともに活気あふれるポート・サイドの町の様子を、熱心に語り続けた。その冒険談に耳を傾けながら、マルチェリーノも次の港では必ず下船しようと誓った。
船はスエズ運河を下り、細長い紅海に出た。右にアフリカ大陸、左にシナイ半島が見える。ベルテロの頭には、エジプト人に追われ、イスラエルの子らが海の中を進んだ「出エジプト記」が浮かんでいた。モーセの十戒のシーンが、目の前で繰り広げられるのではないかと思えるほどの雄大な風景に感動した。そんな想像をしているうちに、船は紅海を抜けてアデン湾に入った。北側がイエメン、南側がソマリア。今でも極めて治安の不安定な地域だが、当時すでにイスラム過激派組織が、イギリスやイタリアの統治に激しく抵抗し、中東の火薬庫となっていた。ソマリアはイタリア領ソマリランドと呼ばれていたが、マルチェリーノたちの船が通る前の月、1935年10月2日に、ムッソリーニがエチオピア帝国への宣戦布告演説を行い、イギリスやフランスの後を追う形で領土拡張を始めたばかりだった。こういったイタリアの動きは現在のロシアと同様に各国の反発や警戒を呼び、イタリアは国際的な経済制裁のさなかにあった。あくる1936年には日独防共協定が結ばれ、1937年にはイタリアも加わり日独伊防共協定が結ばれることになる。牧歌的に見えたソマリアの景色もまた、目を凝らして見ると世界大戦に向けて暗い影が落ち始めていた。
混沌のインドへ
一方、船の中は平和そのものであった。4人部屋の窮屈な生活だったが、マルチェリーノは、いつも前向きで、船中で頻繁にミサを行い、乗客や航海士たちの人気を集めていた。コンテ・ヴェルデ号の中ですでに布教活動は始まっていたとも言える。アデン湾を抜けると、いよいよ広大なアラビア海に出た。そしてさらに広大なインド洋へと向かい、360度水平線しか見えない景色の中を進んでゆく。ついに喧騒と混沌の巨大都市、インドのムンバイに着いた(当時はボンベイと呼んでいた)。

都市圏全体で2千万人以上が暮らす超巨大都市のムンバイは、当時すでに250万人が暮らす大都会となっていた。4人は現地のカトリック修道院を目指して歩き始めたのだが、エネルギーに満ちた人いきれの中に放り込まれ、満員電車のように込み合う中を懸命に泳ぐように歩き続けるはめになった。北イタリアののどかな田舎暮らしに慣れたマルチェリーノ達には、インドの雑踏はなかなか辛い行脚となったはずだが、カトリックの鐘楼が見えた時の安堵感もその分ひときわ大きいものであったであろう。修道院にはイタリア人のシスターたちが待っていて、マルチェリーノやベルテロたちの旅の疲れを癒やし、これからの安全を祈ってくれた。話はそれるが、インドではこの4年前にガンジーによる抗議運動の「塩の行進」が行われている。インドはガンジーをリーダーに不服従という名の独立運動が燃え盛っていた。戦禍のソマリアに独立運動のインド。旅先の至るところでまさに歴史が動いていた。
少し余談になるが、当時カルカッタ(コルカタ)では、後にカトリック教会の聖人となるマザー・テレサが、聖マリア学院で地理と歴史を教えていた。マザー・テレサは、アルバニアやルーマニアの血を引く南ヨーロッパの人だ。いずれにせよイギリスの支配下にあったインドには、欧米人が大勢いた。ヨーロッパとの交易が盛んだったので、マルチェリーノたちにとっても、砂糖や塩を運ぶインド人の姿は、見慣れた光景だったはず。それでも、ムンバイの人の数の多さや喧騒、ダイナミックさはマルチェリーノたちの想像をはるかに超えるものだった。
セイロンからシンガポール
すでに故郷のイタリアを離れて2週間以上が過ぎていた。船はムンバイを離れインド亜大陸を左手に見ながら南下してゆく。そして11月の終わりには、緑豊かなセイロン島、現在のスリランカに到着した。赤道が近い国なのでとにかく暑い。太陽がマルチェリーノらの白い肌を焼いた。ちなみにセイロンは、仏教のイメージが強いが、中世にポルトガルの植民地だったこともありカトリック教徒も多い島だった。当時はイギリスが支配していたのでプロテスタントもいたであろう。セイロンはインドに比べるとずっとのどかに思えた。白いカソック姿で首都コロンボの熱帯林の中の並木道をのんびり歩き、改めて遠くに来たことを実感しながらも、マルチェリーノはこのセイロン島をとても気に入った。しかし最終目的地はあくまでも日本だ。名残り惜しさを残しながらセイロン島にも別れを告げて出発。2日後にイギリス領シンガポールに到着する。
シンガポールは、当時すでにイギリス領の貿易拠点として賑わう港町だった。4人は白い半ズボンと白いシャツで精力的に歩き回った。ジンベースのカクテル、シンガポールスリングで有名なラッフルズ・ホテルの前も通ったであろう。もちろん高級ホテルなので、泊まることはできなかったはずだ。ヨーロッパ的な街並みであったが、セイロンに負けず劣らずとにかく暑い。滝のように汗が噴き出てきた。夜には虫にも悩まされた。ちなみにシンガポールは、この7年後に日本に占領され「昭南」と名前を変えられてしまう。ラッフルズもまた日本軍の将校用宿泊施設として接収されるのだが、1935年時点ではそのような辛い未来は想像もできなかった。そのシンガポールに少しだけ停泊したのち、4人を乗せた船は、いよいよ南シナ海を北上し、景色も変わってゆく。それまでのインドやセイロンとは明らかに違う、本物の東洋に来たという思いを強くした。そして、その東洋の入り口が、やはりイギリスの植民地の香港だ。4人は、香港市内のサレジオ会の修道会を訪れて、つかの間の休息をとった。修道会の寄宿生である中国人青年たちが演じてくれた芝居で、おおいに笑うこともできたのだが、ふと財布を開いてみると、アルべリオーネ神父から渡された500リラをほとんどを使い果たしていた。不安な表情を浮かべた4人を気遣ったサレジオ会の神父が、「これでミサを立てなさい」とお金をくれた。金額は今回もまた500リラだった。
-
Profile
-
1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか