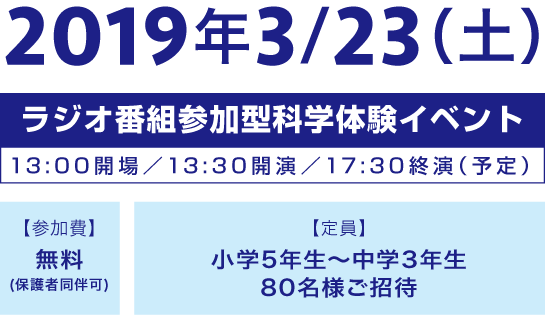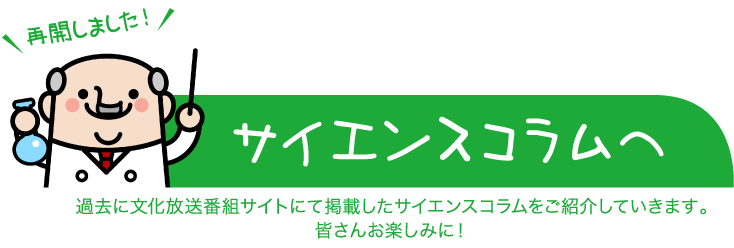MC :さあ、今週のサイコーもですね、
えーエコパブリッシングの眞淳平さんです。よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :えー眞さん。えー「21世紀はどんな世界になるのか」という本を、
えー岩波ジュニア新書から出していらっしゃるんですけれど、今世紀ですね、
今世紀世界どう変わるのか?科学的な観点から先週も伺いました。
で、まっ車が自動運転になるという、ね、近い将来
ゲスト:はい。
MC :これもう、そうかーと思いながら先週聞いていましたけれどね、
気になるのは、あと医療ですね!
ゲスト:そうなんですね、
MC :あのー、人間の寿命がどんどんどんどん長くなって、
最近ではもう90歳ってのが普通になってきていると
ゲスト:そうですね、はい。はい。
MC :いう時代だと言われていますけれど、
今年はね、あのIPS細胞っていうのからSTAP細胞ってのが世の中賑わして、
ゲスト:ええ。
MC :でもちょっとこう、流れが変わって
ゲスト:はい。
MC :やっぱり改めて、このIPS細胞
ゲスト:はい。
MC :山中教授の、ここに人間ってやっぱり可能性を求めてしまうと思うんですけれど、
ゲスト:はい。
MC :改めてこのIPS細胞、今世紀中実用化されますよね?
ゲスト:そうですね、あのIPS細胞っていうのはですね、
MC :はい。
ゲスト:えーまあ皆さんご存知の人も多いと思うんですけども、非常に簡単に作れるんですね。
MC :うーん。
ゲスト:えーお尻とかですね、まあ腕とかにですね、数センチぐらいのですね、
えー大きさで、その組織細胞というのをまあちょっと取る訳なんですけども、
MC :はい。
ゲスト:まぁ皮膚をちょっと取ったりする様な感じなんですけど、
MC :はい。
ゲスト:そこに幾つかのその遺伝子っていうのがですね、えーそういうのがあるんですね、
で、それをあのー、それを入れると、出来る特殊な細胞なんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、体のいろんな細胞になる事が出来るので、
万能細胞っていう風に言われているんですね。
MC :はい。
ゲスト:まあ、これまでは、あの人間の体っていうのは、細胞分裂というのが起こると、
いろんなその体の細胞になっていくんですね、
心臓のその心筋とかですね、心筋細胞とか、
MC :はい。
ゲスト:神経を作る神経幹細胞、神経細胞とかですね、なっていく訳なんですけども、
それに一旦なっちゃうと、他の細胞にはもうなれなく、
なれないっていう風に言われていたんですね、
MC :はい。
ゲスト:ところが、山中教授が発見した方法というのは、
幾つかの遺伝子を体のその体のお尻とかですね、
腕とか何処でもいいんですけども、取ったその細胞に入れるとですね、
IPS細胞という風になって、そこからいろんな細胞になる事が出来る
MC :はい。
ゲスト:という事が分かったんですね。これ非常にあのー大きな発見で、
MC :はい。
ゲスト:簡単に出来るっていう事が一つと。
それからあの1回そのIPS細胞になったものっていうのはですね、
いろんな細胞になる事が出来て、どんどんその細胞分裂を起こしてきて
MC :はい。
ゲスト:増えていく事が出来るんですね。
MC :うんうんうん。
ゲスト:ですから、これからのその医療で物凄く使う用途がですね、沢山あるので、
MC :うんうん。
ゲスト:これからどんどんその研究が発展していくっていう風に考えられます。
MC :うん。まあ、目とか心臓とかね、
ゲスト:ええ。そうです、そうです。
MC :その辺りが強化されると、もっともっと人生長く楽しめるというかね、
ゲスト:そうですね、
MC :そういう可能性がありますけどね、
ゲスト:あのー、心臓とかですね、目の研究っていうのは、
今どんどん進んでいて目の角膜とかですね、
MC :はい。
ゲスト:網膜のIPS細胞から作ったり、
MC :はい。
ゲスト:それからその心臓のそのまぁ鼓動、拍動ですね、
そのドキドキを僕らはその心筋細胞とかを作ろうっていう、
その研究をどんどん進んでいるんですね。
MC :うーん。
ゲスト:で例えばその、角膜なんかですと、この夏からですね、日本でも目の難病にかかった
MC :はい。
ゲスト:人にですね、体の細胞から作ったIPS細胞を元に網膜の細胞を作り出してその人に、
目に移植しようという研究、そのまあ臨床研究っていう
MC :ええ。
ゲスト:その実用化される一歩手前の研究なんですけども、
それが始まろうとしているんですね。
MC :あっもう今年からスタート?
ゲスト:そうです、そうです。
MC :その近い将来、IPS細胞というものによって人間の体のまあ、
延命というか、若返りというか、
ゲスト:ええ。
MC :再生は早い段階で、そうなってきますかね?
ゲスト:そうですね、あのー、今世紀の半ばぐらいには、ひょっとすると、
MC :ええ。
ゲスト:あのー臓器を作り出して
MC :ええ。
ゲスト:えーまあIPS細胞経由の、由来の
MC :はい。
ゲスト:臓器を作り出してそれを移植するっていうことは、
行える可能性は非常にあるんじゃないか
MC :そうか。
ゲスト:と思いますね。
MC :今世紀の半ば、2050年ぐらい?
ゲスト:ええ。
MC :あと三十数年。よし、ギリギリ間に合います、僕は。
ゲスト:そうですね。
MC :あっはっはっはっはっ。
ゲスト:そうですね。あの特に心臓なんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:私が面白いなと思うのは、その心臓っていうのは、
その面白い形をしていていますけども、
MC :はい。
ゲスト:実際にその心臓代りになる、人工臓器を作る時にはですね、
ポンプみたいなものでいいらしいんですね!
MC :あっえっ?所謂あの心臓全としたものじゃなくて?
ゲスト:じゃなくて、いいんです。
MC :ポンプみたいな、
ゲスト:ええええ。
MC :機械的なものでも、
ゲスト:非常に単純なものでもなるらしいですね。
MC :心臓になるってことですか?
ゲスト:そうですそうです。で、あの心臓っていうのは、
要するに、あのー体を・・・の血液を
MC :はい。
ゲスト:どんどん循環させるポンプの役割を果たしているんで、
MC :はい。
ゲスト:そんなに複雑な形である必要がないんですね。
MC :へぇー。
ゲスト:で、人間の形の心臓ってあれだけ複雑だっていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:まぁ言ってみれば、その進化の中でその成功や失敗をしながらですね、
MC :うん。うん。
ゲスト:あーいう形になって・・たまたまなっているだけであって、
MC :へぇー。
ゲスト:ほんとはポンプみたいなものでいいんですね。
MC :あっ実はシンプルな
ゲスト:シンプルなものでいいんです。
MC :構造なんですね。
ゲスト:そうです、そうです。で、そういうものであれば、
IPS細胞から作ることは実は結構簡単で。
まぁ簡単というとちょっと語弊ありますけれども、
思ったよりも難しくないんじゃないかっていう風に
思って作ろうとしている研究者の人は今沢山いるんですね。
MC :いやあ、今なんか凄く今人体の構造が頭の中巡りましたね、
心臓は意外にシンプルだと!
ゲスト:ええ。そうです。そうです。
MC :ああ、あとは今世紀。そうだ宇宙!
ゲスト:はい。
MC :人類は宇宙旅行がどうでしょうかね、
お金積まなくても行ける時代が来るんでしょうかね、
1回行ってみたいんですけど。
ゲスト:昔であればですね、
MC :はい。
ゲスト:えー飛行機で外国に行くっていうのは、
まあ私の小さい頃なんかもそうなんですけども、
非常にお金がかかってもうまあ夢のような
MC :そうだ。
ゲスト:感じだったんですね。
MC :だからアメリカ横断ウルトラクイズっていうものが出来たんですよ。
ゲスト:ああああ、そうかもしれないですね。
MC :だから見たんですね。
ゲスト:ええええ。
MC :羨ましいなって言って。
ゲスト:そうですね。
MC :今普通ですもんね。
ゲスト:そうですね。
MC :うん。
ゲスト:で、あとそれと同じような現象がですね、起こるんじゃないかと思うんですね。
MC :はい。
ゲスト:え、えーとその、宇宙っていうと、
大体高度100キロからそれ以上の高度なんですけども、
MC :はい。
ゲスト:そこを目指して、えー宇宙旅行を、民間でですね、
やろうっていう動きが今どんどん出てきているんですね。
MC :高度100キロっていうと、東京から熱海ぐらいの距離って事ですよね。
ゲスト:そうです。そんなに遠くない感じですね。
MC :つまり上空にして、
ゲスト:ええ。
MC :東京から熱海みたいな高さ
ゲスト:ええ。ええ。
MC :でもそれもう宇宙なんですか?
ゲスト:そうなんです。
MC :飛行機じゃなくて、それもう宇宙?
ゲスト:そうです。
MC :あら。飛行機は大体上空10キロくらいですよね、
ゲスト:ええそうですね。
MC :で、その10倍上に行ったらそこはもう宇宙なんですね?
ゲスト:ええそうですね。
MC :何か行けそうな気がしてきましたね。
ゲスト:そう、実は、結構宇宙というのは近いんですね。
MC :で、重力も無くなるんですか?
ゲスト:ええええ。あの、いや、重力はまだ・・・あっそうですね、重力は少なくなりますね。
MC :あっ体も軽くなる?
ゲスト:そうですね。
MC :えー?
ゲスト:で、えーとそこにですね、
まあ今はまだその億単位のお金がやっぱりちょっとかかってしまうですけれども、
MC :高さ熱海まで行くのに億単位
ゲスト:そうですね。これからのツアーっていうのがですね、
民間ツアーが始まろうとしています。
MC :えー?熱海ですもんね、もっと安く行きたいですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :そう!でもなんか気が楽になりました。宇宙めっちゃ遠くかと思ったら
ゲスト:ええ。ええ。
MC :意外に100キロ?
ゲスト:ええ。
MC :100キロ上空?
ゲスト:ただあのそこに行った時の光景っていうのはですね、
MC :ええ。
ゲスト:やっぱりあの違うんじゃないかと思うんですね
MC :地球丸く見えるんですか?
ゲスト:見えます見えます。
MC :あっえー?
ゲスト:で、あと大気の様子もやっぱりあの青く見えますから、
MC :ええ。
ゲスト:でそこには、その国境も無い訳ですよね。
MC :はい。
ゲスト:でまあ、あのー、あれーこんな所で争ってるんだなっていうのがですね、
MC :えー。
ゲスト:やっぱり目の下に見ることが出来るんですね。
MC :100キロでもそういう風景になる?
ゲスト:ええ。えーそうです、そうです。
MC :うーん。
ゲスト:ですからそうすると、
人間の意識っていうのは少しづつ変わっていくような気がするんですね。
MC :そっかぁ。
ゲスト:なんかこんなとこで戦争してていいのかなとか、
MC ::いやぁー。
ゲスト:何かそういう風な事を考えさせるとかですね。
MC :あーいいですね、いい話だ。
ゲスト:あと逆にその宇宙を見るとやっぱりその星にですね、
MC :ええ。
ゲスト:空気がなかったりする訳ですよね、
MC :うーん。
ゲスト:でこの空気って何か薄いような感じに見えるけれどもすごく大事なんだなと
MC :はあ
ゲスト:こういう風になんか人間の意識が変わってくる様な気がするんですね。
MC :当たり前の事を
ゲスト:ええ。ええ。
MC :有り難いと思ったり
ゲスト:そうですね。
MC :価値観変わるんですね。
ゲスト:そうですね。でやっぱりその地球が青いっていうのもですね、
MC :ええ。
ゲスト:ガガーリンが言った訳ですけども
MC :はい。
ゲスト:あれはその外から見るまで青いって分からなかった訳ですよね、
MC :うーん。
ゲスト:でその時の感動ってやっぱりあったと思うんですよ。
それと同じような感動を私達も味わえるんじゃないかなっていう気がしますね。
MC :100キロの上空でもやっぱりそういう風に見えるんですか?
ゲスト:見えると思いますね。
MC :あっじゃ、あいやぁ眞さんいつか行きましょう!
ゲスト:行きたいですね、
MC :気軽に行ける時代まで頑張って生きよう。
ゲスト:そうですね、そうですね。
MC :ちょっとまた遊びに来てください。いやぁ宇宙行きましょうよ、眞さん。
ゲスト:行きたいですね、はい。
MC :あっはっはっはっ。
ゲスト:はっはっはっ。
MC :いやあ、夢はあるけどれども、現実になるんだよ、みんな、ね、いやぁ、
今週のサイコーはエコパブリッシングの眞淳平さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。
-
「21世紀 これからの科学技術 パート2」 ゲスト:眞淳平さん
2021/01/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他 -
「21世紀 これからの科学技術 パート1」 ゲスト:眞淳平さん
2021/01/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーはですね、3回目の登場なんですが、
エコパブリッシングの眞淳平さんです。こんにちは。
ゲスト:あっ、こんにちは。
MC :よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :眞さんは、岩波ジュニア新書から
「21世紀はどんな世界になるのか」という本を出していらっしゃるんです。
これは国際情勢とか、科学技術、要は、だからあのそういったものだから、
まあちょっとサイエンスに関して伺いたいと思っているんですね。
ゲスト:はい。
MC :21世紀ってもう始まっていますけれど、ま向こうあと八十数年残ってますが、
ゲスト:ええ。ええ。
MC :この間にどんな世の中になるのか?ということをえー予想された本なんですが、
その中で科学技術どうなるのかと。
で、これラジオですからね、ラジオって聴く環境ってまあ、お部屋でもあるし、
ゲスト:うーん。
MC :お父さんの車の中で聴いているキッズもいると思うんですよね。
で、車?今世紀どうなるのかと。眞さんズバリ!
ゲスト:そうですね、あの車は本当にいろいろなえー企業とかですね、
いろんな人が開発していますんで
MC :ええ。
ゲスト:今物凄い勢いで、えー変化が進んでいますね。
MC :そう便利になっていますよね、
ゲスト:そうですよね。
MC :機能いろいろ付いて。
ゲスト:えーあのー本当ですね。
MC :はい。
ゲスト:で、例えばスマホで操作できる車とかですね、
MC :はい。
ゲスト:色や形が変わる車とか、
MC :はい。
ゲスト:実は空を飛ぶ車なんていうのもですね、
MC :ええ。
ゲスト:これから登場しつつあるんですね。
MC :えー!?それは普通免許で空飛んでいいんだろうか?
ゲスト:そうですね、そこら辺の問題、まだちょっとありましてですね、
MC :あっはい。
ゲスト:あと、その価格もかなり高いんですね。
MC :ああ。
ゲスト:今出ているやつはですね、数億するというのも
MC :はい。
ゲスト:データありましてですね、
MC :はい。
ゲスト:まあとてもじゃないですけど普通の人では買えませんし、
MC :うーん。
ゲスト:まあそのさっきの免許の問題なんかもありますんで、
MC :はい。
ゲスト:日本ではまだ全然そういうのは出てないんですけれども。
MC :はい。
ゲスト:まあこれからですね、どうなるのかというのを非常に興味深いところではあります。
MC :まあ親父世代からすると車変わったなっていうのが、先ず燃費が良くなった。
ゲスト:まあそうですね、
MC :だからハイブリッドカーの登場で、
ゲスト:ええ。ええ。
MC :その電池の持ちが良くなってすごく走行距離伸びたっていうのと、
ゲスト:ええ。
MC :あとは運転席周りが、
ゲスト:ええ。ええ。
MC :スマホありきになっているというね、
ゲスト:ええ。そうですね。
MC :いわゆる情報のシステムがナビとスマホが連動しているという
ゲスト:ええ。ええ。
MC :これがすごく大きい進化だなと思うんですけれど。
ゲスト:あっまさにおっしゃる通りで、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、これからの車っていうのはですね、
MC :ええ。
ゲスト:えースマホとかですね、まあ一つの家電のですね、
MC :ええ。
ゲスト:一つというとちょっと大袈裟かもしれないですけども、家電のですね、
MC :はい。
ゲスト:一つみたいになる可能性というのが非常に大きいんですね、
MC :あっ車は家電?はっはっはっはっ。
ゲスト:ええ。例えば、その、電気自動車であればですね、
MC :はい。
ゲスト:えーその車の燃料、まぁ電気なわけなんですけども、
MC :そうだ!
ゲスト:それをその家でですね、プラグに接続をして、
MC :はい。
ゲスト:ええ、まあ充電するっていう事も出てきますし、
MC :一部のメーカーなんか、完全な電気自動車を出していますよね!
ゲスト:そうですよね。
MC :まあ家電ですね、じゃあ
ゲスト:もう家電に近いと考えて
MC :ええ。
ゲスト:良いんじゃないかと思います。
MC :ライセンスの必要な家電。
ゲスト:そうですね。
MC :ですね!うーん。
ゲスト:だから逆にそのえー車で発電したものをですね、
MC :はい。
ゲスト:ええ今度家に今度送るとかですね、
MC :あっ。
ゲスト:で、家で使うとかいう、
MC :えーっ。
ゲスト:そういうことを出来る可能性ありますね。
MC :えっ、何?例えば何ですか?車で発電したものを家にって?
ゲスト:そうですね、だから車の電池でですね、
MC :ええ
ゲスト:えー発電をしたものを昼間走っててですね、
ええそれを貯めといて、であのー家に送るとかですね、
MC :あっ、電気をですか?
ゲスト:そうです。そうです。
MC :えーっ!?
ゲスト:将来的には出来るようになるという風に言われています。
MC :わーそうですか。で、このスマホに関してなんですけれど、
ゲスト:ええ。
MC :スマホと一体型のカーナビなんかも出ているのと、
ゲスト:はい。
MC :あとはね、オプションで車進化したなってのが、
あの、何、車線をもし、跨いじゃったら、
ゲスト:ええ。
MC :「駄目ですよ。」とか教えてくれたりとか、
ゲスト:はぁはぁはぁ。
MC :あと、前の車に追突しない?
ゲスト:ええ。
MC :ブレーキのシステム?
ゲスト:ええええええ。
MC :あれも変わりましたよね!
ゲスト:あっあのーよくご存じですね、今
MC :ぼく車好きですもん。
ゲスト:あの今ですね、えー研究開発が進んでいるのが、あのー自動走行車とかですね、
MC :あー。
ゲスト:えー自動運転車とか言われるもので、
MC :はい。
ゲスト:まあこれあのー多くの自動車メーカーが凄い勢いでえー開発競争していてですね、
MC :ええ。
ゲスト:まあこの先ですね、えー十年前後以内のですね、
MC :はい。
ゲスト:実用化っていうのがですね目指されています。
で、あのー自動走行車ではですね、車のそのコンピューターと、
それから道路なんかの設置されたセンサー
MC :はい。
ゲスト:或いはインターネット上の情報っていうのがですね、
インターネットの通信回線を経由して結び付られる事になるんですね、
MC :うーん。
ゲスト:で、そうすると、どの道が今混んでいて、
MC :ええ。
ゲスト:どの道が空いてるとか、あのどの道が工事やってますよ、
とかっていうのをですね、インターネット経由で教えてくれる様になるわけなんですね。
MC :うん、はい。
ゲスト:そうすると、「ここに行って下さい」っていう風に言った場合に、
目的地に最も早く、それから最も安全に着くことが出来るような道を車自身が判断して
MC :ほーう。
ゲスト:進んでいってくれる。といったようなことが、まあ将来的になんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:えー実現するという風に考えられています。
MC :それはなんか便利ですね。
ゲスト:そうなんですね。
MC :あのー、もうイライラして
ゲスト:ええええ。
MC :裏道裏道って走っちゃいますけど、
ゲスト:はい。
MC :そうじゃなくて、一番こうスマートな方法で
ゲスト:ええええ。
MC :早く到達出来る手段を教えてくれる。
ゲスト:あっその通りなんですよ、
MC :うん。
ゲスト:ただまだあのーいろんな問題がありまして、
MC :はい。
ゲスト:あのーなんで、完全にそのタクシーみたいにしてですね、
乗れるっていうのはまだまだちょっと先だっていう風に言われているんですね。
で、例えばの話なんですけども、急にタイヤがパンクする事ってありますよね、
MC :あっはい。
ゲスト:で、そんな時に車がコントロール出来なくなっちゃって、まぁハンドルだけ何とか切れると
MC :はい。
ゲスト:で、右にハンドルを切るとですね、えー対向車線の大型トラックにぶつかっちゃって
MC :はい。はい。
ゲスト:でも、左に逆にハンドルを切るとですね、子供連れの
MC :はい。
ゲスト:歩行者をひいてしまう、なんていうケースがあるとしますよね、
MC :はい。
ゲスト:で、そういう時に、えーコンピューターにその判断って任せていいですかね?
MC :ダメ!
ゲスト:駄目ですよね。
MC :うーん人間がやらなくちゃダメ!それは。
ゲスト:そうですよね。
そう、やっぱりそういうときのですね、問題っていうのをどうするのか?
MC :はい。
ゲスト:っていうのが、まだ中々難しいんですね、
で、もしかすると第三の道もあるかもしれませんし、
MC :はい。
ゲスト:コンピューターに任せておくと、
「うーん。二人ひくと、ちょっとまずいからじゃトラックに突っ込んじゃおう。」
なんていう風になっちゃうとですね、これ、やっぱり嫌ですよね。
MC :あっ、今お話いただいた、目的地まで最短一番
ゲスト:ええええ。
MC :短い時間で行けるっていうのは、ハンドル操作も全部車がやってくれるという、
ゲスト:ええ。
MC :そういう世界が
ゲスト:ええええ。
MC :今世紀中に来るんですか?
ゲスト:えー来ます来ます、今世紀中といわずにですね、もっと早くくると思いますね。
ここ数十年のうちには来ると思いますね。
MC :それは、便利すぎでしょ。でも でも今おっしゃった通り
ゲスト:ええ。
MC :もう不測の事態に対して回避するのは、僕らドライバーしかいないので、
ゲスト:ええ。ええ。
MC :そこはやっぱり人間がやらなくちゃ駄目ですよね!
ゲスト:そうですね、ただあのー、将来的にはですね、
えーそういうことも含めて出来るようなるんじゃないかっていう
MC :えっー!!
ゲスト:風に言われています。
MC :えっー恐ろしい今世紀、21世紀へぇー、えっ?そうすると、
じゃあ免許そのものって教習所行かなくて済んじゃうんですか?
ゲスト:うーん。そこら辺ちょっと何とも言えないんですけどもね、
あのーだからここ暫く例えばその十年二十年っていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:少なくともそのくらいの間は、そのー免許を持った人が
MC :はい。
ゲスト:運転席に座ってその補助っていうあの役割になると思うんですね。
MC :なるほど。
ゲスト:ただその後っていうのがですね、何かよく分かりません。まだ。
MC :うーん。
ゲスト:あのー本当に予想以上に技術が進歩してしまって、
MC :はい。
ゲスト:人間が運転するよりもよっぽど、その安全な自動運転の車っていうのが、
出来る可能性はあると思うんですね。
MC :はぁー。
ゲスト:で人間っていうのは、やっぱりその、居眠りしたりとかですね、
MC :はーい。
ゲスト:脇見したりとか、
MC :はい。
ゲスト:何かやっぱりちょっと問題起こしたりする事ってあるんですよね、
MC :はい。
ゲスト:例えば今その、疲れて事故を起こしてしまうなんてバスのケースがありますけれども、
MC :ええ。
ゲスト:まあもしそれが仮になんですけれども、
全部その自動運転車に切り替わった場合は
そういうことが無くなる可能性ってある訳ですよね、
MC :そっかぁ。いやーどっちもどっちな感じですね。
でも、そっか、でも車ほら、金属の塊だから、人を傷つける可能性があるからね、
ゲスト:ええ。ええ。
MC :急な子供の飛び出しとか・・・
ゲスト:はい。はい。
MC :でも、人間のブレーキ能力にも限界がある訳で。
ゲスト:ええ。ええ。ええ。
MC :だから事故が起きる。
ゲスト:そうですね。
MC :これをじゃぁコンピューターに任せれば、逆にそれが
ゲスト:ええ。
MC :回避できるって事も考えようによってはあるという事?
ゲスト:あのーそうなんですね、でその場合には、車だけの問題ではなくて、
道路にいろんなセンサーがあの付けられる事になると思うんですね。
いろんな細かいチップがいっぱい埋め込まれて、
で、それが、「あっこの子の動き何か変だぞ。」
MC :ええ。
ゲスト:とかですね、「この子が飛び出しそうだぞ。」と例えばその陰に隠れて、
えーそこから飛び出そうとしている子もいるかもしれないですよね、
それはその人間からとかですね、車からでは見えないわけなんですね。
MC :ほう。
ゲスト:で、そうではなくて、あっその時に、えーその車ではなくて、
えーと道路にあるチップとかですね、
そのセンサーがその子供の動きを察知してえー「ここに何か
MC :ええ。
ゲスト:変な動きをしている子供がいるぞ」というのを
教えてくれるようになる可能性があるんですね。
MC :そこまででもやっぱりこう整えなくちゃいけないんですね。
ゲスト:そうですそうです。
MC :インフラをね、道路の。うーん。
ゲスト:ですから、その自動運転車を走らせて本当にその免許いらなくてで
出来るっていう風になる為には、車だけの問題ではなくて、
MC :はい。
ゲスト:社会のそのいろんな仕組み全体をですね、変えていく必要があると思うんですね。
MC :なるほど。あっもうお時間ですね、まだまだあの伺いたい話がありますので、
また来週もお話を伺いたいと思います。
今週のサイコーはエコパブリッシングの眞淳平さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「電気の科学 パート2」 ゲスト:木舟辰平さん
2020/12/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今週のサイコーも前回に続きまして、
ガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんです。よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いしまーす。
MC :え、木舟さんは一橋大学社会学部をご卒業後、
電気事業制度改革や原子力政策などエネルギー問題を取材されてらっしゃいますけれど、
前回もいろいろと興味深いお話伺って、いろんなものこれ電気通すんだよ、
人間の体も通すんだよって、ちょっとおっかないお話で終わったんですけれど、
今日は僕ら、ね、首都圏の電気、これ、今、原発首都圏で動いてないから、
僕らの今の暮らし、この例えばラボとかみんなの学校とか家庭とか、
あの電気、灯これからねぇ、夕方になってくると電気つけますよ、みんな。
どっからきてるんですか?この電気は。
MC :そうですね。今あの首都圏は、ま、大きく火力発電と、ま、あと水力発電で、
まああの電気は作っているわけですけども。
火力発電はあのー今、ひとつはその東京湾の沿岸ですね。
ずぅーと横須賀の方から横浜通って、ま、千葉、
房総半島のあたりにずぅーと大きな火力発電所は並んでまして、
MC :あ、海沿いの火力発電所?
ゲスト:海沿い。はい。
MC :なんかあの辺、ドライブしてても火力発電所なのか工場なのかよくわからないんですけど。
ゲスト:工場とかあのー、石油会社の製油所だとか製鉄所だとか
MC :はい。いろいろあるけれど。
ゲスト:いろいろありますけれど、コンビナートですね、いわゆる。
MC :はい。そこに火力発電所もいくつか
ゲスト:その中に発電所もありますし、
MC :見分け方ありますか?
ゲスト:見分け方ですか?なかなか難しいかもしれないですけれどもね。
MC :カーナビ見るしかないですかね。
ゲスト:ま、でも東京電力とか書いてあったりしますけどね。
MC :ほーー。
ゲスト:何とか発電所って、結構大きく書いてあったりはします。
MC :じゃ、東京湾から来てる?
ゲスト:東京、あとあのー太平洋の方のあの茨城だとか、ま、福島あたりまでも大きな発電所はあります。
MC :すっごい変な事聞いていいですか?
ゲスト:はい、はい。
MC :電気って遠くから呼び込むとその分電気ってフレッシュな状態じゃなくなるじゃないですか。
ゲスト:まあやっぱり運んでこなきゃいけないので、送電ロスっていうものは出て来てると思います。
MC :あっ、そうですか。じゃ、100あるものが、
じゃ、福島だったら100だったものが、東京に来るまでって何割ぐらいのエネルギーに
ゲスト:どれくらいだろ、でもそんなに減る訳じゃないですけどね。
MC :あっそうですが、若干のロスがある。
ゲスト:ま、若干のロスはありますね。
MC :へぇー。だから距離が長ければ長いほどー、
ゲスト:やっぱりそれは、うん。
MC :えーっ。あっ、その電気っていうのはどっかに逃げてっちゃうんですか?
ゲスト:まあなんとなくこうー送電線からぱーっと空気中にま、出て行くんでしょうね。
だけどそれほど別に害があるようなものではないですけれども。んー。
MC :へぇー。では、僕らの電柱があって黒い電線があってそこを電気通っているわけですよね。
へぇー。お台場って電線とかないですよね。電柱とか。
ゲスト:だから、あそこはもう電線の地中化をしてるんですね。
だから日本はもともと全くそれが進んでいない国で、
多分ヨーロッパとか行くとほんと電線ってないと思うんですけれども、
MC :へぇー。
ゲスト:ロンドンとかパリとか
MC :あっそうですか。
ゲスト:あんまり意識してあるかないですけどね。
MC :そんなパリーなんてなかなか行かないからなー、
ロンドンとかーちょっとー。
ゲスト:でもないですよ、ヨーロッパの街は。
MC :あっそうですか。じゃ、日本なんか先進国で、
電柱立っているっていうのはちょっとじゃー、遅れてる感じ?
ゲスト:ちょっとまあ、遅れてる感じですね。
最近はでもそうやって特に都市部中心にこうだんだんそういう取り組みが進んでますけれども。
MC :あの、いわゆる地中に埋設するとか
ゲスト:いわゆる電線地中化っていう取り組みは進んでますけれども。
MC :昔ね、電線音頭とか僕、子供のころあったんですけどー、
最近都会じゃスズメも見なくなりましたからね。あんまりね。
ゲスト:あっそうですね。昔は、
MC :電線にスズメっていうのはあんまり風景でなくなって、
むしろカラスばっかりになっちゃってるんですけど、
ゲスト:確かにそうですね。
MC :うーん。そうか、じゃあ地下ケーブルで電気を送るシステムに今なりつつあるということですね。
ゲスト:まあ、そうですね。まあ単純に地中にあるものを地下に埋めるっていうことですけどもね。
MC :なるほどね。で、電気っていうのはその発電所、今火力発電が9割、日本。
で、ボンボン燃やしてタービン回って、で、電力になってくる。
で、これってその場ですぐ使うんですか?それともどっかに貯めること貯金出来るんですか?
ゲスト:電気はですね、やっぱり基本的には貯められないんですね。
今、ここで使っている電気っていうのはまさに今タービンが回って
発電している電気を使っているっていうのがその電気の大きな特徴というか、
専門用語でいうとそれを同時同量っていうんですけども、
常にその瞬間に同じ使うだけの電気を発電するっていうのがま、
非常にその電気の安定供給の最大のそのなんていうんでしょう、
鍵というか、そういうもんですね。
MC :今、日本では、よく夏のね、電力の使用量が過去最大になったーと、
猛暑のニュースの時にあるじゃないですか。冬と夏だったら、夏の方がやっぱり消費量は、
ゲスト:そうですね、北海道以外は。
MC :あっ、なるほど。
ゲスト:北海道は今でも冬が年間の最大が出ますけども、あとはもう夏ですね。
MC :ということは電気は貯えられないということは夏になれば夏になるほど
ボンボンボンボン電気を生まなくちゃいけないということですか?
ゲスト:そうですね。だからその夏に合わせた量の発電所を持ってるということですね。
だから冬の間はけっこう遊んでいる発電所が多いわけですけれどもね。
MC :すごい変な話ですけど、逆に夏暑い時に火力発電を使ってね、
電気を生み出すと、より日本が暑くなりません?
ゲスト:そうですね、ま、それでなるかもしれないですね。
あの、エアコン使うと外に熱い空気出しますしね。
MC :はい。発電所でも火どんどん使うわけですよね。
ゲスト:まあ、そうですね。確かにあのー熱いものは、熱くなった水は海とかに流しちゃってますから。うーん。
MC :そういう部分でね、やっぱりこう人間の持ってるエネルギーとか
いわゆる自家発電とかこれからの電力に関して火力ばっかりに頼らないやり方ってないですか?
ゲスト:そうですね、ですから、そういう意味ではそのー再生化のエネルギーやっぱりそのーま、
環境にもいいということでやっぱそういうものを増やしていこうという風には
だんだん日本もなってきてるのが現状ですよね。
MC :あのこの間僕ね、群馬の方に行ったら、埼玉の北部から群馬、高崎、前橋にかけて
太陽光パネルがすごく多いんですよ。民家の上とか、もうそれ用の共同住宅があったり、
建売でもみんな同じ建物で太陽光パネルっていう、
多分進んでるんだろうなって気はするんですけれど、
でも太陽光パネルってお天気に左右されたりする
ゲスト:そうですね。
MC :じゃないですか。日照時間考えるとどうなんですかね。確実な供給源って言えるんですかね。
ゲスト:うーん。だからやっぱりどうしても雨が降ったり、
あるいは当然夜になれば発電しないので、必ずその安定供給という面では不安がありますけども、
たださっき電気は貯められないっていう話もありましたけれども、
一方でそのー技術開発も頑張ってて、いわゆる蓄電池っていう貯める技術も、
要するにま、正確にいうとものすごく高くなるコストがかかるっていう貯めると、
何とか安くして実際使えるような技術も進んでて、
そうなれば例えば昼発電した太陽光の電気を貯めといて、
夜使えばなんとかこー同じだけの電気を供給できるような仕組みが出来ないかとか、
まあそういった取り組みも今は進んでますね。
MC :いわゆる蓄電池って電気を貯めるその蓄電池ってシステムがコストが高いってことですか?
ゲスト:高い、もともとはだからとんでもないような
そんな経済的に成り立たない話だったんですけれども、
ただそういった技術開発も今は結構さかんにやっているので、
ま、だんだんこう実用化もしてくるのかなーという感じですね。
MC :あの、最近スマートグリッドっていう、
ゲスト:はい。
MC :これー、ちょっと今日キッズたちに覚えてもらいたいんですけど、
ゲスト:はい。そうですね。
MC :この考え方、どういうことですか。
ゲスト:そうですね。今までのそのーま、グリッドっていうのは、ま、送電網っていうことですね。
英語のグリッドっていうのは。で、そのスマートっていうのはかしこいみたいな意味ですけども、
要するにかしこい送電網ということですけども、
要するに今までの電気っていうのはあのー遠くの大きい発電所からま、
はるばるあのー首都圏まで電気を運んできてただそのー電気を使っているという、
一方通行の電気だったんですよね。それが、あのー今言った震災だとか、
ま電力不足だとかいろんな問題があって、
もうちょっとそのー我々消費者の側も電気に興味を持たなきゃいけないんじゃないかっていう
動きもある中で、もうちょっとそのー一方的にただ電力会社から送られてくるだけじゃなくて、
こっちでも電気をコントロールしようという話になってて、
そこでまあ技術開発もいろいろあって、先程言った蓄電池の話だとか、
太陽光だとか、再生可能エネルギーの話だとか、
今ってその実際家のメーターまで来てみないとどんだけ使っているかわかんないですよ。
それもひと月単位でしかわかんないですよ。でも、それを今どんどんスマートメーター、
それもスマートってつくんですけども、
新しいメーターに取り替えててそれがつけば30分単位で
要するに電気をどれだけ使っているかっていうのが分かるようになるんですね。
それもそのインターネットで。そうなれば、いろんそのー節電だとか省エネだとか、
そういうこともそのー消費者の側も分かるわけですね。
あ、今こんなに電気使っちゃってるんだとか、っていうのが見えて来るので、
そういった消費者側のそのーIT技術も使って再生可能エネルギーだとか
蓄電池だとかも組み合わせてなんとかこう最適なあの省エネをなんかこう
進められないかっていうのがそのースマートグリットというイメージですね。
MC :うーん。あっ、もう時間ですか。わかりました。また是非遊びに来てくださーい。
今週のサイコーはガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんでした。有難うございました。
ゲスト:有難うございました。 -
「電気の科学 パート1」 ゲスト:木舟辰平さん
2020/12/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さあ、今週のサイコーはですね、
ガスエネルギー新聞の記者でらっしゃいます木舟辰平さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願い致します。
MC :木舟さんは私と同じ取材者なんですね。えー、そうですか。
東京八王子のご出身で一橋大学社会学部をご卒業、
電気事業制度改革や原子力政策などエネルギー問題を取材されてらっしゃる。
興味深いですねー。
秀和システムから「よくわかる最新発電送電の基本としくみ」という本も
出版されてるんですけれど、あのー今年に入って電気の自由化って言われてるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。はい。
MC :んー。まだわかんないですよね、実態が、
だって年間何千円お得っていわれてもおやじからすると、ま、それぐらいかよってので。
奥様からするとお得よって言うけど、なんか、
もうちょっと様子見たいなと思っているんですけど。
そもそも電気って、キッズたちにわかりやすく教えて下さい。
ゲスト:そうですね。
電気と言ったときになかなかイメージしづらいものがあると思うんですけれど、
電気って2つあると思うんですね。
要するにそのー、自然現象としての電気と、今おっしゃった自由化ということで、
そのー商品、商品としての電気というものがあると思うんですね。
MC :はい。
ゲスト:もともとは電気というのは自然界にあったもので、
そういう意味では自然現象なんですけれども、まちょっと、
難しい細かい原理的な話をいたしますと、
物質っていうのはもともとは原子というもので全ては出来てるわけですね。
で、原子っていうのはその中に原子核と電子というもので構成されていると、
で、原子核っていうのはプラス、電子っていうのはマイナスのこう電気を帯びていて、
MC :原子核はプラス、電子はマイナス?へー。
ゲスト:で、普通の物質っていうのはそのプラスマイナスのバランスがとれていて、
プラスマイナス0の状態にあるのが普通なんですけど、
MC :プラマイ0
ゲスト:プラマイ0。ただそれがこうなんかの拍子にけっこうそのマイナスの電子が
ぽっと外に飛び出してそのープラスだけの原子が残って、で、
マイナスが多いまた別の原子が出来たりっていうことが、
まあよく自然界ではまあ起ってしまうわけですね。
MC :プラスとマイナスのバランスがくずれちゃう。
ゲスト:バランスがくずれる、まあ物質によっては簡単にそういうことが、
そういう現象が起きてしまうわけですね。
で、だんだんそうやってプラスが一方にたまって、
マイナスが一方にたまってくると、
最終的にそのバランスをまたとろうとしてがぁーっとその電子の移動が起きるわけですね。
MC :はい。
ゲスト:それがまあ、電気が流れるということなんですけれども。
例えばそのー自然界で言うと、雷っていうのがありますけれども、
雷っていうのも空の上の方と地上の方で別れて
プラスとマイナスが分かれてそれがある瞬間になんか、
だぁーとそこの間に電気が流れるっていうのが、
MC :そうなんですかー。
ゲスト:それがまあ自然現象なんですけれども、あれはまあ電気なんですね。
MC :よく国会議事堂に雷が落ちたーってテレビでやってるじゃないですか。
じゃあそれは国会議事堂の下にマイナスか何かがあって、上空にプラスがあって行き場を失って、
ゲスト:そうですね。
MC :マイナスの所にチューって行ってるのが雷。
ゲスト:あれが雷ですね、うん。
MC :で、プラマイ0にしてるってことですね。
ゲスト:そうですね。プラマイ0になるのかならないのか、
まあ中和は取ろうとするわけですね、その瞬間に。
MC :なるほどー。はい。
ゲスト:で、まぁそりゃもう雷、皆さん見たこと、聞いたことあると思うんですけれども、
ものすごい光と音がするわけでああやってものすごいエネルギー・パワーがあるわけですね。
だからああいったあのーエネルギー・パワーを何とか人間がコントロールできれば、
もしかしたらすごい便利じゃないかということは、
これは昔っからいろんな人が考えてきたことで、
MC :バックトゥーザフューチャーでは、
それでねー、あのー過去から未来に帰ってきたんですもんね。
なんとかジゴワットで。はい。
ゲスト:そうですね。いろんな人がいろんな研究を昔からしてきて、で、
有名なのはやっぱり発明王エジソンっていう人がいましたけれども、
あの人はそのーま、電球だとか、蓄音機、ま、音を録音したりですね、
ああいうものを発明したことで知られていますけれども、
今の発電とか送電のそのしくみ、要するにあのー自然界にある電気のエネルギーを
うまくこう人間が活用できるようなしくみを発明したことでもまあ知られているんですね。
MC :へー。そうか、電気ってもともと自然界に存在するものを
人間が商利用に転換してったってことなんですね。
ゲスト:ま、転換できるようにしたってことですね。
MC :静電気なんかも、だから自然界に存在してるってことですか?
ゲスト:そうですね。あれもこやってパチッとなんかこう乾燥した日に
ドアノブさわるとバチッとありますけども、あれも電気の一種ですよね。
MC :行き場を失った電気が、人間の手がきたら、おーっつってプラスからマイナスに流れる。
ゲスト:流れる。だから人間の体も電気が流れますからね。原子で出来てるわけですから。
MC :へぇー。
ゲスト:まあじゃあ、その静電気でじゃあなんかテレビが見れるかって
言うとそれは見れないわけですね。
MC :見られない、無理です。
ゲスト:微々たる電気だし、一瞬ですし、
それは安定的にある程度の量をちゃんとこう供給できれば
やっぱりいろんなことが使えると生活の中で、
ということでエジソンだとかいろんな人が考えて今のこの豊かな生活というか、
まいろんな電化機器も生まれてきたという。
MC :それが発明王エジソンの功績なんですね。
ゲスト:まあ、非常に大きな功績だと思いますね。
自然現象の電気と今の使っているいわゆる商品としての電気という、
まあ元は同じものですけれども、大きく2つあるのかなーというふうに思います。
MC :あのーそれで、電気っていうのはじゃあ発生して今僕らの周辺に、
じゃあ多分このラボの中にもどっかで行き場を失った電気ってあるんですか?
ゲスト:そりゃもう、微々たるものは・・・ある。
MC :教室にはあるんですか?
ゲスト:そうですね。だから、昔よくこう下敷きで頭をやって
髪の毛を逆立つとか遊びをしたと思いますけど、
今の子供はしてんのかわかんないですけど。
MC :いやいや、やんないですかねー。
ゲスト:してないですかねー、最近の子供は。
MC :やれよーみんなー。下敷き頭にくっつけてー逆立ててみろー。あれ電気?
ゲスト:あれも静電気ですよね。
MC :なるほど。
ゲスト:そんなもの、簡単に作ろうと思えば作れちゃうわけですよね。
MC :つまりそれは、髪の毛くしゅくしゅくしゅーって
下敷きでこすったらプラスの電気が発生して、
ゲスト:その摩擦でプラスかマイナスにこう簡単にやっぱ移動しちゃうわけですね、物質間の間で、
MC :で、下敷きの方に行きたいよー、行きたいよーってなるから、
ゲスト:ってなったらーこうーなると。ん。
MC :へえー。さあさ電気というと東日本大震災から5年というね、今年。
再生可能エネルギーって具体的になんですか?
ゲスト:ま、主に今日本でやっているのが太陽光発電。
MC :あ、あれ太陽光のソーラーパネルいっぱいあるけれど、
あれは再生可能エネルギーっていう範疇に入るんですね。
ゲスト:そうですね。やっぱりあのー石油とか天然ガスとか
一回燃やしちゃうと終わっちゃいますけれども、
太陽光っていうのはずっと降り注いでくるので、
ま、いくら発電しても、その資源がなくなることがないということで、
ま、再生が可能ですよということですね。
MC :え、その他は、風力発電?
ゲスト:そうですね。風力も、あとま、地熱、地熱発電。
MC :地熱。なんか首都圏にいると地熱って聞かないですよね。
ゲスト:あまりないですね。
やっぱり九州ですとか、やっぱりその火山があるところ、東北だとか、
あたりはやっぱりあのー掘ってくとマグマですか?あって
その熱を利用してっていうのはありますけども、なかなか首都圏はないですね。
MC :へえー、なるほど。そのーさっきからね、人間の体に電気流れるって、
なんとなくわかるんです。わかるんだけれど、じゃあ、鉄は電気通すじゃないですか、
じゃあ人間の指は電気通すかっていうと電流流れるっていうけれど、
じゃあ電気流れないですよね、コードの代わりにならないですよね。
このー電気を通すものと通さないもの、人間の体ってのは電気流れる。
でも、鉄やその電気を通すその導線などとは違うじゃないですか。
この何を通して、何をもって通さないっていうんですかね。
ゲスト:そうですね、それはー、まーおそらくさっきの自然現象としての電気と、
商品としての電気はやっぱ違うわけで、
やっぱ商品としての電気というのはそのー安定的に送らないといけないわけですね。
そういう意味では、鉄だとかそういうより電気をまあ通すのに
すぐれた素材っていうのがあるんですね。導体っていいますけどね。
MC :導体?
ゲスト:一方全然電気を通さないのは不導体っていいますけども、
MC :不導体。
ゲスト:ありますけど、ま、その中間にいろいろあるわけですけれども、
人間の電気っていうのは確かにそこまで電気をスムーズに
鉄みたいに通すかといったら通さないですけれども、ま、通ることは通るわけですよね。
MC :なるほどー。
ゲスト:自然現象としては通ります。
ただじゃあこれで確かに送電線のかわりを人体がしろといわれたら、
それはなんかひどい話ですけども、そこまでこうなんていうんでしょうかね、
きちんと通すわけではないと、ちょっと変な言い方だけど。
MC :今、今僕、子供の頃からの40年の昔年の疑問が解消されました。
ゲスト:ほんとですか?
MC :みんななんかわかった?
ゲスト:わかったかな。
MC :わかったよ、絶対今わかっているよ、きっと。わかる。
わかった!いやー、もうこんな時間?あらー、あっという間だったな。
また来週もお話伺いたいと思います。
今週のサイコーはガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんでした、
有難うございました。
ゲスト:有難うございます。 -
「若田光一さんの帰還とはやぶさ2 パート2」 ゲスト:長谷川洋一さん
2020/11/01 Sun 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ、今週のサイコーも有人宇宙システムの長谷川洋一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :先週、ISSの船長だった若田光一さんのお話を伺いましたが、
若田光一さんがいかにね、
人柄が優れていて国際宇宙ステーションの船長になったのかというお話をうかがって、
やっぱりね、人柄だなと。
ゲスト:そうですね。
MC :心のゆとりとか、包容力とか色々ね、学ばさせて頂きました。
さぁ、今週は年内に打ち上げられると話題のはやぶさ2です。
あの「はやぶさ」と言うと、イトカワですよね?
ゲスト:ですね。
MC :で「はやぶさ2」というのはなんですか?なにが目的ですか?
ゲスト:えーっとですね、1999JU3というC型の小惑星なんですが、
こう言ってもちょっと愛着湧きませんよね?
MC :わかんない。1999JU3?名前の由来は?
ゲスト:あのー、まぁそういう天文学者のつけてる番号なんですが、
イトカワだって本当はムニャムニャムニャってそういう番号だったわけなんですよね。
それがあのイトカワと命名されて、まぁそれで皆さんあのー、
非常に愛着が湧くようになったと。
MC :そうですよ、日本人の名前だったし。
ゲスト:そうですね。
MC :日本の宇宙開発のね、先駆者の糸川先生でしたから。
ゲスト:そうですね、糸川先生の
MC :で、イトカワと言えばハヤブサ、ハヤブサと言えばイトカワという図式になったんですけど
ゲスト:そうですね、ワカタでいいでしょうかね?
MC :あぁー、1999JU3という小惑星を「ワカタ」ってつける?
ゲスト:ふふっ、怒られそうですね。
MC :いや、なんでー?つけちゃいましょうよ。だって、ダメなんですか?
ゲスト:あのーどうでしょうね。あのーそこは天文、世界天文連盟が、あのーどういう風に言うか。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:あのー、ご存命の方っていうのは中々難しいかもしれませんね。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :へぇー、じゃあ若田さんのおじいちゃんとか。
えー、グランドファーザーワカタとか?そうするとねぇ、なんか成立しそうな。
まぁいずれにしても、この1999JU3というモノの物質を採取するために
ハヤブサ2っていうのは飛ぶわけですよね?
ゲスト:そうですね、あのーハヤブサ1号ですね。
ハヤブサと同じ様に、タッチアンドゴーと言われて、
ずいぶん流行りましたけれども
MC :はいはい。
ゲスト:えー、触って物質を持って帰ってくるというその姿が、
ハヤブサがシューっと空から獲物を捕るような、
まぁそういう風に上手くいくっていうことでハヤブサ2号ですね。
MC :はい、へぇー。その、そのあれですよね、
物質を確認したのが日立ハイテクの電子顕微鏡のシステムなんですけれど、
今回もそれで上手く、こう小惑星の物質がね、確認されるといいですけど。
ゲスト:えぇ、やっぱり日立ハイテクさんの技術。
MC :そうです。さぁこの小惑星は?具体的にはどういう大きさで、
どの辺にあって、天体望遠鏡で見えるかどうかという、どういう物ですか?
ゲスト:あのー、まぁ天体望遠鏡でキッズのみんなの目で見ることはちょっと難しいんですけれども
MC :見えない?
ゲスト:あのーですね、大体イトカワとそんなに違わない所にあります。
MC :イトカワってすごい小っちゃかったって。ここのグラウンドぐらいだっていう
ゲスト:イトカワはですね、600mぐらいでしたから。
で、今度はですね、大体900mと言われてますけど、
まぁこれも実際行ってみてですね、観測してみないとまた分からないところがありますね。
MC :あ、やっぱりイトカワみたい、イトカワの1.5倍ぐらいの?
ゲスト:イトカワよりは大きいと言われていますね。
MC :ちょっと大きいぐらい?
ゲスト:それでですね、あのー、C型の小惑星という風に、あのー、出てますけれども、報道が。
MC :なんだ、そのC型のという
ゲスト:このC型って、カーボンっていうじゃないですか。炭素。
MC :はい、炭素ね。
ゲスト:えー、みんなもあのー、多分キッズのみんなも理科で習うと思いますけど、
生物って炭素で出来てるじゃないですか。
MC :はい、Cですね?
ゲスト:Cですよね。それで、実はこの1999JU3、ハヤブサ2が行く小惑星はですね、
太陽系が46億年前に出来た頃のその頃の姿が
大体残っているんじゃないかって言われているんですね。
MC :えー、えぇ?太陽系、生まれて46億年前だけど900m程度の小惑星で、
46億年前のこう歴史が確認できるかもしれないということですか?
ゲスト:かもしれないですね。ていうのは、地球はあのー、川が流れて、
火山が噴火してってこう、当時の面影がなくなっちゃってるわけですね。
ところが、このーこういう小惑星というのはですね、
その出来た当時のまんま宇宙を漂っているかもしれないわけですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:ですので、そこに期待してですね、そのむかーしのふるーい物を持って帰って、
それでですね、あのーここからちょっとロマンなんですが
MC :ロマン行きましょう。
ゲスト:それに生き物の原料が入っているんじゃないかなと科学者は思っているんですね。
MC :ほぉー。ほぉー。
ゲスト:えー、生き物の原料は水、それから有機物、炭素なんですね。
MC :はい。
ゲスト:あのー炭素、炭素の有機物ですね。こういった物がおそらく入っているんじゃないかと、
そういう期待をしてます。
MC :へぇー、やるもんですね。えっ、46億年前って、
まぁほんとに人類ってどうして生まれたのかっていうそこに行っちゃうんですけど
ゲスト:えぇ。
MC :まぁ、その物質っていうのは地球上では確認できないんですね?
地球の研究では46億年前の、あのー、宇宙はどうなってたのかとか、事はわからない?
ゲスト:ちょっとわからないですよね。あのー、そのー、そんな古い物はですね。
MC :なるほど。
ゲスト:それで、まぁ地球なんかはあのー、大きすぎて中は溶けてますよね。
ドロドロに。圧力で。
MC :はぁー。
ゲスト:ところがこういった所に行きますと、46億年前に冷えて固まった物が、
それがそのまんまあるかもしれない。
MC :ほぉー。
ゲスト:そこに炭素ですとか、あのー有機物、それから水。
これ、水もですね、あのー、岩の中に入っているんですね。
MC :えぇ。
ゲスト:そんなものが、あのー、見つかってくれば、
それが私たちの原料になったのかなっていう研究が進みますよね。
MC :うーん、なるほどー。いやー、何か見つけてくれるといいですね。
タッチアンド形式、だからまた今回もハヤブサの様に上から、
上空からパッと行って、バッと物質を取って来る。でもその取った物質次第では、
イトカワとは違うものが発見されるかもしれないってことですか?
ゲスト:そうですね。あのーイトカワとはタイプが違う、あのむしろそのー、
炭素が多いと言われている所を目指しているんです。
MC :は、そうか。それで狙いをつけてるんですね。
ゲスト:そうなんです。この1999JU3っていうのに行かなきゃなんなかった理由というのは、
そういう、あのー炭素、あのー有機物ですね、生物の元がありそうだから、狙ってるんですね。
MC :だけど、この手の小惑星って、何億とあるわけですよね?
ゲスト:もう何個あるかとてもわかりませんね、えぇ。
MC :そこに、あのー地球人がこの大体900mぐらいの
ちっちゃな惑星に当たりを付けるっていうのもすごいですね。
ゲスト:あ、そうですね。天文学者は大したもんですね。
MC :この辺は、いわゆる求めている炭素の研究に適してるぞって事で、
その小っちゃい小惑星に当たりをつけて
ゲスト:そうですね。
MC :で、そこに向かってハヤブサ2は行くわけですよね?
ゲスト:そうですね、えぇ。しかもハヤブサ2はですね、
あのー新機軸を持ってましてね、あのーですね、えっとなんとですね、
クレーターを作っちゃうと考えてるんですよ。
MC :クレーター。月にもありますよね、クレーター。
ゲスト:そうですよね、まずあのー、そのータッチアンドゴーで小惑星の物質を持って帰る前にですね、
クレーターを掘るんです。
MC :え、あ?タッチしないで穴、掘るんですか?レーザービームか何かで?
ゲスト:先にですね、レーザーじゃ無いんですけれども、あのー、これがですね、
えっと、衝突、衝突体というんですけれども、まぁ要するにあのー、
球をボーンとぶつける様な事をするんです。
MC :えー。
ゲスト:秒速2キロのすごいスピードで、まずあのー、球をですね、
ボーンとぶつけてそれで掘るんですよ。
MC :すごーい。
ゲスト:掘るとあのー、この小惑星の表面の物が吹っ飛ばされて、
中がちょっと出て来るじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:その中こそ、欲しいんですよね。
MC :あー、はいはい。
ゲスト:だって表面は、あのーですね、46億年掛けて太陽の光に照らされて割れたり、
なんかこう変化したり、してる可能性がありますね。だからちょっと掘った所に、
きっと目指すものがあるんじゃないかと。
MC :へぇー、いやー、すごい。
ゲスト:わざわざ掘っておいてから、えー、ハヤブサ2はタッチアンドゴーで、
その中の物質を取って帰ってくると。
MC :いやー、イメージできました。グラウンドに、なんかこうグラウンドにこう、
石灰のしろーいのが撒いてあって、上空から球がボーンと落ちて来る。
すると石灰がフワフワフワと舞って、石灰の下の赤土とか関東ローム層とか出て来て、
モワーッと舞い上がった所を日本のハヤブサがパクッと来て
ゲスト:そうそうそう、そうですね。パクッと捕る。さすが、大村さん。その、そのイメージです。
MC :それで地球に持ち帰る?
ゲスト:はい。
MC :すごい、ロマン。
ゲスト:そうですねー。しかも帰ってくるのが、2020年という予定なんですよ。
MC :えー、6年経つ?待たなくちゃいけない?
ゲスト:えー、そうですね。
MC :完全に僕らおじいちゃんですね。
ゲスト:あははっ、いやー。オリンピックとどっちが早いか。
MC :そうだ、オリンピックの年だ。また楽しみに増えるじゃないですかー。
やってるかなこの番組、やってるかもしれませんねー。
ゲスト:やりましょう、ぜひぜひ。
MC :いやー、その時お互い頭、真っ白でがんばりましょう。
ゲスト:はいはいはい、でも呼んでくださいね。
MC :はい、もちろんですー。いやー、ロマンですね。
2週に渡ってお話伺いました、
今週のサイコーも有人宇宙システムの長谷川洋一さんでした。
また来てください。
ゲスト:はい、ありがとうございます。
MC :ありがとうございました。 -
「若田光一さんの帰還とはやぶさ2 パート1」 ゲスト:長谷川洋一さん
2020/11/01 Sun 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ今週のサイコーは半年ぶりでございます。
有人宇宙システムの長谷川洋一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちはー。
MC :長谷川さんはね、宇宙に関して何でもご存じなんですけれど、
えー、今月の話題はやはり若田光一さんですよ。
半年前、若田光一さんが国際宇宙ステーションの船長さん?
日本人として初めて船長になるよっていうお話だったんですが。
ゲスト:そうですねー。
MC :ずーっとやってらっしゃったんですよね?
ゲスト:あのー、そうですね、正確にはあのー、
2014年の3月9日から大体2か月間船長を勤めるということで立派に。
はい、ずいぶん立派に。
MC :そっか、飛び立ったのは半年前だけど、船長は2か月間ていうことですか?
ゲスト:そうなんですね。前の船長がいらしたので、交代式っていうのを宇宙でやるんですね。
MC :すごーい。え、じゃあ3月から2か月間、船長?
ゲスト:そうですね。そうです、そうです、そうです。
MC :さぁ、国際宇宙ステーションですけど、具体的にはどこにあってどういう物でしょう?
ゲスト:あ、そうですね。もういちどおさらいの様に。
MC :はい。
ゲスト:あのー、高さが400キロぐらいの高さの所を90分で1周してます。
だから、時速2万8千うにゃにゃにゃ...ぐらいのキロメーターぐらいの、
要するにのぞみの100倍ですね。えへへ。
MC :あはははは。
ゲスト:というスピードで地球をまわってます。
MC :でもタイミングが合えば、その軌道?日本の上空であることもあるわけですよね?
ゲスト:そうですね。あのー、そうですね。若田さんもですね、
例えば東北の夜の灯りがよく見えて、もう復興のエネルギーを感じて私も勇気づけられたと、
こんなことを言っていますね。
MC :すごいですねー。えー、90分で地球の上を1周するということで、
もしかしたらみんなもね、今夜見上げてみたらその軌道、
人工衛星としてこう見えるかもしれないですね。国際宇宙ステーションが。
ゲスト:うん、そうですね。ものすごく明るく見えますので、
あのー、見える日にはもう金星ぐらいの明るさ。
MC :えぇ。あ、そうですか。
ゲスト:ぜひ、見て。
MC :ね、この春は金星で盛り上がりましたからね。
ゲスト:ぜひぜひ。
MC :さぁ、この国際宇宙ステーション、ISSと呼ばれていますけれど、
この船長になるってのはどれくらい凄い事なんですか?
ゲスト:あ、そうですね、まぁ、あのー、言ってみればあのー、
世界にいま現役の宇宙飛行士ってひゃく、百人前後いますけれども、
その頂点の1人になったと言えるわけですね。
MC :はい。
ゲスト:ですので今宇宙ステーションに居る6人の宇宙飛行士が
いつも暮らしているんですけども、
まぁそのキャプテンであって地上に控えている
宇宙飛行士達のトップでもあるということで、まぁ大変です。
MC :ふん。
ゲスト:今まであのー39番目の船長なんですけれども、
今まではアメリカ、アメリカ、アメリカ...ロシア、ロシア、ロシア、ロシア。
でカナダ1人、ヨーロッパ1人、で日本人若田ーという風になってます。
MC :うー、そうですか。
じゃあ、アメリカとロシア以外はカナダと
ちょっとヨーロッパの方とあとは日本人、若田さん
ゲスト:そうですね。
MC :ふーん、じゃあアジア人初ということになりますね。
ゲスト:あ、そういうことですね。
MC :2回目の船長あるんですかね?
ゲスト:あ、あのーそれはもちろんあるかと思います。
MC :あ、そうですかー。さぁ、その船長の役割なんですが、宇宙の上で何やってるんですかね。
ゲスト:そうですね、あのー船長さんは、
あのー宇宙飛行士達の健康やそれから仕事のスケジュールの管理、
それから緊急事態が起こった時にもうバババっと現場を仕切って、
みんなの命や宇宙ステーションを救うと。特に例えばですね、
一番怖いのは火事ですね。
MC :ふん。
ゲスト:あの狭い宇宙船の中で火が出たら逃げ場がまた、ないですから。
MC :はい。
ゲスト:ですから、どこからいつ火が出て何が原因だっていうのを、
パパパっとみんなで手分けして調べて消さなきゃいけない。
めったにないですね。
MC :実際起きては無いけれど、そういう万一に備える舵取り役をしなくちゃいけない。
ゲスト:そうですね、そういう訓練をものすごくやってます。
例えばですね、火災報知器鳴ることあるんですよ。
MC :えぇ
ゲスト:で、あのーほんとの火事だったら大変なんですが、
あのー、まぁ、あのーセンサーが何かを感じて鳴ったとか、
そういう事ありますので原因をちゃんと突き止めて
大丈夫かどうかっていうのを確かめる。
MC :なるほど。
ゲスト:それからあのー、キッズのみんなは多分最近あの、
よく聞く言葉で「デブリ」ってありますよね。
「スペースデブリ」宇宙のゴミみたいなやつ。
MC :あ、デブリ。言葉、面白いけど太っちょじゃなくて宇宙のゴミ?デブリ。
ゲスト:そうです、そうですね。宇宙デブリとかよくあのー、
最近あのーアニメなんかにも出てきますけど、
ああいうモノがもし宇宙ステーションにぶつかったら穴が開くかもしれません。
穴が空いたら空気が出て行っちゃいますから、もうえらいことになります。
MC :はい。
ゲスト:で、あのーそういう時がもし起こったらどうするかっていうのを
ものすごく訓練してやってます。
MC :へぇー。あの国際宇宙ステーションには希望というね、
日本のスペースがあるじゃないですか。
ゲスト:えぇ。
MC :あのスペースも若田さん、ちゃんとこう面倒みてるわけですよね?
ゲスト:あ、そうですね、仰る通り。あのー、船長さんはこう威張ってればいいんじゃなくて、
全然威張る暇ないんです。
MC :はい、うふふふ。
ゲスト:あのー実験も仕事も他の人と同じようにやって、
更にそれをやった上でみんなに目配りをしたり、
管理をしたりという責任が上に乗っかるんですね。
MC :なるほどー。いわゆる宇宙開発の研究、実験なども日々行い、
プラス、えー責任者でもあるということですね。
ゲスト:そうですね。
MC :なんで若田さんが選ばれたんだと思います?そこですよ。
ゲスト:あ、そうなんですよ。ほんとにあのー、私もうれしいんですが、
あのー今まで若田さん3回宇宙へ行って今度4回目ですね。
その過去の活躍が非常に良かったという事と、
MC :はい、へぇー。
ゲスト:それからあのー宇宙ステーションの船長になるためにはですね、
リーダーシップがなきゃいけない、自分の管理が出来てなきゃいけない、
更にですね、フォロワーシップもなきゃいけないですね。
MC :えぇ。
ゲスト:つまりあのリーダーに上手くこう人をフォローする、
だからあのークラスで言えばリーダーやりたい子、よくいますよね。
でもあのリーダーなれなかったときに、
そのリーダーをこう盛り立ててチームが上手くいくようにするっていう、
これって中々難しいですよね。
MC :すごい。すごい、ちょっと待って。
いわゆるサッカーとか野球のレギュラーになれなかった人達を盛り上げる役割?
ゲスト:そうそう、そうですね。それも出来なきゃダメなんですよ。
MC :すごい、すごい。いや、すごい。マネージャーみたいな感じですか?
ゲスト:そうですね。余裕がないとできないですよね。
MC :いやー。若田さんはそういうのに長けているということですか?
ゲスト:そうですね、やっぱりあのー若田さんの余裕とか、あのーまぁ人柄の良さ、
まぁこういう所でですね、他の人を包容力、他の人をこうフォローしながらまぁ、
あのリーダーとしても引っぱって行くこともできるという事ですね。
MC :ほぉー。そういえば長谷川さん、これね、ぼくね、
もう5年前ですかね。5、6年前かな。若田さんというと宇宙桜ですよ。
ゲスト:はぁー。
MC :宇宙にね、長谷川さんの依頼された有人宇宙システムの依頼のね、
桜の種を持ってって
ゲスト:はい。
MC :それが国際宇宙ステーションに滞在して、それを持ち帰ってきたじゃないですか。
ゲスト:若田さんが持って帰ってきた。
MC :そう。それを長谷川さんて全国に植えたでしょ。
ゲスト:そうですね。
MC :あれがどうなってるか気になる。
ゲスト:あ、はい。あのー、その後元気に芽が出たんですが
MC :あれ5年前ですよね。
ゲスト:えっとそうですね、2009年、10年に芽が出て
MC :4年、5年前?
ゲスト:そうですね。4年、5年前。そうしてですね、
今年になって花が咲いたというニュースが結構出てますね。
MC :2014年の今年の春、桜の花が咲いたんですか?
ゲスト:いよいよ桜の花が。はい。あのーぼちぼち咲き始めてまして、宇宙桜ですね。
MC :えぇ。
ゲスト:あのーずいぶん報道して頂いて、もう嬉しい限りです。
MC :え、その桜咲いたってのはどうなんですか。速いんですか?普通なんですか?
ゲスト:えっとですね、あのー速いという風に報道もされてますけれども、
あの実はですね、あのーまぁ一生懸命育ててますので、そういう事もあるんですね。
MC :あ、ちゃんと育てれば速く咲くこともある?
ゲスト:ある、ありますね。
MC :あ、今、手元に写真が来た。おー。
ゲスト:あぁ。
MC :あぁ、長谷川さんが預かった若田さんに委ねた、託したね、桜。
種まいて、えー、高知県あるいは、岐阜県あるいは、山梨県の北杜市などで花が咲きましたよ。
といういわゆる桜の便りというか、えー、
写真が今、手元にあるんですが綺麗なお花が咲きましたね、今年。
ゲスト:そうですね、えぇ。
MC :これ宇宙を旅した桜
ゲスト:そうですね、希望の桜という風に私は考えています。
MC :はい。これはもうちょっと今年は見るチャンスはないけれど、
えー、近ければ来年の春?山梨県北杜市の神社?これなんて言うんですかね?
どこ行けばいいんですか?
ゲスト:そうですね、北杜市の実相寺という所ですが
MC :実相寺というお寺
ゲスト:そうですね。えぇ、まぁ北杜市へ行けばですね、
あのーいっぱい、あのー、札が出てます。
MC :はい。
ゲスト:その花の時期は、大変ですので。
MC :実相寺に行くと、来年の春、宇宙に行った桜の花を見る
ゲスト:を、見ることができます。
MC :見ることができるわけですね。
ちなみに僕の住んでる北海道は今、桜前線が到達しました。
ゲスト:あははははは。
MC :良かったら明日にでも、札幌来てください。
ゲスト:いいですね、ぜひぜひ。
MC :さぁ、えー、今週のサイコーは有人宇宙システムの長谷川洋一さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「巨大ウィルス パート2」 ゲスト:武村政春さん
2020/10/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :さあ、今週のサイコーもですね、前回に続きまして、
東京理科大学教授の武村政春先生です。よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願い致します。
MC :武村先生はブルーバックスから巨大ウィルスと第4のドメイン、
生命進化論のパラダイムシフトという本も出版されていて、
前回もウィルス、ほんとにちっちゃい1ミリの1000分の1を
さらに1000分の1にしたっていうってウィルスっていうのは
いわゆる細菌とは違うんだよっていう、あの細菌は生物なんだけれど、
ウィルスは生物じゃないんだよ
ゲスト:はい
MC :だけどノロウィルスとか
ゲスト:うん
MC :エボラ出血熱ウィルスとか、ジカ熱とか、
最近ねニュースですごくこわいイメージのある
ゲスト:ええ
MC :その、病気をもたらすもの、とってもちっちゃいものなんだけれど、
こわいよって話も伺ったんですけど、巨大ウィルスを発見されたという先生が、
これ巨大さというのはまずどれぐらいの大きさのウィルスですか。先生が
ゲスト:ああ、まず
MC :みつけられたのは
ゲスト:ああ、まず、僕がみつけたのは
MC :はい
ゲスト:まあ、これまで見つかってるものの、
一つの仲間っていうだけの話だけなんですがね
MC :はい
ゲスト:あの、一番最初に見つかった2003年に見つかったのが
ミミウィルスというのがフランスの研究者で見つかったんですけれども、
MC :はい
ゲスト:大体500ナノメートルぐらいの大きさなんですね。
MC :それは1
ゲスト:それは1マイクロメートルの半分ぐらい
MC :ていうことは
ゲスト:で、ノロウィルスとかのもう何十倍大きい
インフルエンザよりも2・3倍大きいかな。
MC :ああ
ゲスト:で、これも電子顕微鏡を使わなくても見えるぐらい
MC :おお
ゲスト:非常に大きなミミウィルスというのが見つかりました。
MC :それは16年前に発見された
ゲスト:2003年ですね
MC :はい。だから13年前
ゲスト:13年前、発見された
MC :で、それミミウィルス
ゲスト:それミミウィルス
MC :それが巨大ウィルスってことですか
ゲスト:そうなんですね。
MC :はい
ゲスト:で、500ナノメートルもでかい、ま、今申し上げたように、
電子顕微鏡じゃなくても見えるもんですからね
MC :はい
ゲスト:あの、最初見つけた研究者は、とてもばい、その細菌だとは思わずに
MC :はい
ゲスト:研究しててもその細菌に特有のあるべき遺伝子がなくて困ってて、
ずーと困ってて、で、2003年になってようやく実はこれ
ウィルスだったんだということがわかって
MC :ああ、
ゲスト:で、ミミウィルスのミミっていうのはもう真似しているとか、
もう、あのよく似てるっていう意味のミミックリーっていう英語があるんですけど、
そこからこう名付けられたのがミミウィルスなんですね。
MC :細菌みたいなウィルス
ゲスト:細菌みたいなほど大きいし、
MC :ああ
ゲスト:あと遺伝子も調べると細菌ほどではないんですけれども
MC :はい
ゲスト:かなりそれまでのウィルスに比べるとたくさんのウィルス、遺伝子があると、
MC :はい
ゲスト:いうことがわかってきて、だからほんとにその、
ほんとに細菌ぽいねってというような
MC :はい
ゲスト:そういうようなウィルスが2003年に見つかったんですね。
MC :へぇ
ゲスト:ええ、で、それ以降いろんなウィルスが、
こう、それよりももっと大きなのが見つかってきました。
MC :ええ、
ゲスト:これまでに
MC :たとえば
ゲスト:たとえば、あの一番有名なのが2013年に発見された
MC :はい
ゲスト:パンドラウィルスっていうウィルスがいるんですけれども
MC :パンドラの箱ですか
ゲスト:そうそう、あのパンドラの
MC :えっ、ええ
ゲスト:まぁあれから名付けられたんですけどね
MC :ええ
ゲスト:あの、それがもうほんとに驚くべきことで
1マイクロメートル以上の大きさをもっていました
MC :それは1ミリの
ゲスト:1ミリの1000分の1です。
MC :1000分の1
ゲスト:そう、それです。
つまりそれまではウィルスはそのさらに1000分の1だったでしょ。
MC :はい。
ゲスト:でも、その1000、1ミリ、1、昔は1ミクロンと言っていたぐらい
MC :はい
ゲスト:の大きさで、これはほんとにこのバク、
この細菌とほとんど同じ大きさというですね、
非常に大きいのが見つかって、これは
MC :パンドラウィルス
ゲスト:パンドラ
MC :どこで見つかったんですか。
ゲスト:これはですね、ええ、2ヶ所で見つかってんですけども
MC :はぁ
ゲスト:その時は、その時はチリの川の、まっ、河口付近の泥の中と
MC :ええ、
ゲスト:あと、ええオーストラリアのどっかの淡水の沼地
MC :南半球ですね、いずれも
ゲスト:まあどっちも南半球なんですけど、
MC :はい
ゲスト:ただ、あの、実は、あのう、コンタクトレンズされてる方は、
MC :はい
ゲスト:あのコンタクトレンズをこう洗浄液に
こう漬けてることがあると思うんですけれども
MC :はい
ゲスト:実はあれは汚くしてるとアメーバが、こう増殖して、
で、それをこう知らずにこう付けると
MC :はい
ゲスト:あの炎症を起こすことがあるんですけど、
MC :はっ
ゲスト:実は
MC :細菌がよくあると言いますよね
ゲスト:そうそうそうそう
MC :あれ、それは細菌ですよね。ウィルスでなくて。
ゲスト:それは、いえ、それがですね。
MC :ええ
ゲスト:で、今アメーバが増殖すると言いましたでしょ。
MC :はい
ゲスト:実は、パンドラウィルスの3つ目が
MC :はい
ゲスト:見つかったのがですね、そういう所から見つかったんですよ
MC :あっ、コンタクトレンズの
ゲスト:そうそうそう、
MC :はい
ゲスト:コンタクトレンズ洗浄剤から
MC :はい
ゲスト:それに感染しているアメーバが見つかったんですね。
MC :へぇえ
ゲスト:ただ、それはパンドラウィルスが見つかる前に実は見つかってたんだけども
MC :はい
ゲスト:最初は巨大ウィルスという概念がなかったもんで
MC :ふうん
ゲスト:なんだこれっていう、
つまり新種の小ちゃな微生物として片付けられていたのが実は今になって
MC :はい
ゲスト:これパンドラじゃんということがわかった
MC :はあ
ゲスト:というふうにして、大体今のところ3種類ぐらいのパンドラがみつかって。
MC :へぇえ、ひょんなきっかけで見つかったわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :それはあのウィルスと定義されたのは、ええ、生物じゃないということが
ゲスト:うん
MC :わかったからですよね。生きてないという
ゲスト:ええ、そうそうそう、あのう、つまり自分自身で増殖できない
MC :うん
ゲスト:というのが実はまず生物じゃない一つの
MC :うん
ゲスト:証拠で、あとは自分で、こうタンパク質を作れないというのが
MC :ほうう
ゲスト:ええ、で、ただ作れるんですけれども
それはどこかの細胞の中に感染しないとできない
MC :はい
ゲスト:だから、自立してそういうことができないというのは
生物じゃないという一つの指標なんで、
パンドラも実はそうなんだということなんですね。
MC :そのミミウィルスにせよ、パンドラウィルスにせよ
ゲスト:ええ
MC :人間の体にはどういう影響を及ぼすものなんでしょうか
ゲスト:今のところですね、あまり、
あのどちらも大体アメーバ―に感染するウィルスとしてみつかっているので
MC :はい
ゲスト:あまり人間に対してなんか病原性を持つとか
MC :はい
ゲスト:そういったことはあまりないとは思うのですが
MC :ほぉ
ゲスト:ただ、実はミミウィルスに関して言いますと、
たくさん摂取すると肺炎を起こすとか
MC :はい
ゲスト:そういう方の、まぁ実験動物レベルの話なんですけども、
そういう実は論文も出てるので
MC :へぇ
ゲスト:ひょっとしたら多くとりすぎると、
なんか変なことが起こるかもしれないです。
MC :それが、でも発生しやすい環境というのはもうわかっているんですか
ゲスト:いや、わからないと思います、まだ
MC :わからない
ゲスト:生態学的にまったくわかってないので、
このへんの巨大ウィルスというのは
MC :へぇえ
ゲスト:ええ、で今言ったように、いろんな所にいるんですよね
MC :はい
ゲスト:おそらく
MC :あの、ウィルスの研究って今、聞いてると、
その、いろんなものを研究している中で、
たまたま見つかったものが、これが、じゃ、細菌だった
ゲスト:はい
MC :これが実は新しいウィルスだったって
ゲスト:ええ
MC :そういう学問があるということですよね
ゲスト:まぁそういうふうにして見つかってきていますのでね、
巨大ウィルスなんかは特にね。
MC :ということですよね。じゃ今まで地球上にあるもので、
あのう、いろんな物質が研究されている中で
ゲスト:うん
MC :先生なんかやっぱり新しい、
これまだ未発表のウィルスじゃないかっていうものを
ずっと探してらっしゃるんですか。
ゲスト:まぁ、今は私はその日本のいろんな所から、
にも、絶対いると思っているので、
MC :はい
ゲスト:で、日本のその巨大ウィルスを実はちょっと探そうということをしてまして、
いま、研究をしています
MC :それ、どこでどんなことをやるんですか
ゲスト:まぁとにかくいろんな所からサンプリングをしましてね
MC :へぇ
ゲスト:水、水を、いろんな池とか沼とか海とか
MC :はい
ゲスト:川とか、
MC :はい
ゲスト:いろんな所からサンプリングして、片っ端から、
こうアメーバにそれを添加してウィルスがいるかどうかを
調べるということを今やっています
MC :すごい
ゲスト:ええ
MC :それは北は北海道から南は沖縄まで行っちゃう
ゲスト:ほんとはそこまで行きたいですね。
今のところはまだ、あの、東日本のちょっといろんな所ぐらいしか
まだやっていませんけどね
MC :ふうん
ゲスト:ええ
MC :たとえばいろんなじゃ、この湧き水とか
ゲスト:はい
MC :日本の水百選とかの所から水汲んできたりとか、
あっちこっちからサンプルをとってきて
ゲスト:それはありえ、ありえますね。今のところ日本の水百選はやってませんけれども
MC :ええ、ええ、いろんな沼とか
ゲスト:沼とか
MC :へぇ、それをアメーバにくっつけるってどういうイメージですか
ゲスト:あっ、つまり、アメーバというのは、あの、こう実験室で培養できますのでね
MC :はい
ゲスト:それをこう培養しておく、
MC :はい
ゲスト:で、そこにあの例えば、荒川とかそういった川から取って来た水を
MC :はい
ゲスト:まぁ、ちょっとある程度いろんな操作をして
ウィルスがいそうなものをちょっとこう濃縮するんですけれども
MC :ふうん
ゲスト:ウィルスをね。濃縮したものをそのアメーバの培養している液にこう、
ぽちょぽちょっと振りかけるみたいな
MC :ふうん
ゲスト:実際にはもうちょっと詳しくは、あの複雑なんですが
MC :はい
ゲスト:で、しばらく置いておきますとね、ウィルスがもしそこにいれば
MC :はい
ゲスト:アメーバに感染します
MC :はい
ゲスト:と、アメーバは大体ウィルスに感染しますと、
まぁ、ちょっと形が変になって、あの具体的にいうと、
ちょっとこう丸っぽくなって
MC :はい
ゲスト:浮き上がってきちゃうんですね。
MC :はい
ゲスト:で、やがてバーンと破裂してなくなっちゃう、消えてしまうと
MC :それは何時間っていうレベルですか
ゲスト:それはウィルスによって違うんですけれども
MC :うん
ゲスト:たとえばさっきのミミウィルスの場合は大体もう1日おけばもうバーンと破裂して
MC :へぇ
ゲスト:アメーバ死んじゃいますね。
MC :それを顕微鏡で見るわけですね。
ゲスト:はいはい。で、そういうふうになったアメーバをちょっとこう、
いるかどうかを探しまして
MC :はい
ゲスト:それをちょっと電子顕微鏡で見ますと
MC :はい
ゲスト:あっ、新しいウィルスがアメーバの中にいる様子を見ることができると
MC :へぇえ
ゲスト:はい
MC :先生の学問ってね、たぶん医療の中でも薬の開発とか
ゲスト:はい
MC :いろんなふうにこれたぶん役立ってだっていくもんだと思うんですよね。
ゲスト:ああ、僕の場合はまあ今のところ一個の巨大ウィルスが
なにか人に役立つかといったら役立たないと思ってまして
MC :あっそうなんですか。
ゲスト:ええ、僕自身はなんていうんでしょうね、
この生態、生物の世界にこういう巨大ウィルスがなぜいて、
なにやってるんだろうと
MC :はい
ゲスト:僕達にどういう影響を与えてるんだろうと、
これまったくわかってないといってもいいぐらいなんで
MC :はい
ゲスト:そこをちょっと解明していきたいなと思うんですね。
ただ、まぁそれやっていくうちに、
ひょっとしたらこうしたら人に役立つんじゃないかとか、
医療に役立つんじゃないかとアイデアは出て来るかもしれないんですけれども、
今のところまだ全然僕はノンアイデアですね。
MC :いやぁでも、それでいいと思いますよ。その欲のなさが
ゲスト:うん
MC :やがて、なんか、こう、実を結ぶような気がします。
ゲスト:ああ、それだとうれしいんですけれども。
MC :はい。またじゃぜひ遊びに来て下さい
ゲスト:ああ、どうもありがとうございます。
MC :はい。今週のサイコーは東京理科大学教授の武村政春先生でした。 -
「巨大ウィルス パート1」 ゲスト:武村政春さん
2020/10/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :さぁ今回のサイエンスコーチャー略してサイコーは2度目のご登場です、
6年ぶり、東京理科大学教授の武村政春先生です、こんにちは
ゲスト:こんにちは、よろしくお願いします
MC :えー、よろしくお願いします
ゲスト:ごぶさしております
MC :ええ、6年前です
ゲスト:そうですね、早いものです
MC :6年前は、えー、おヘソはなぜ一生消えないかの
ゲスト:はい
MC :人体の不思議をうかがったんですが
ゲスト:そうでしたね、ええ
MC :うん、もうそれ、もう1回聞きたぐらいなんですけど
ゲスト:ははは
MC :先へ進みましょう、6年経ってしまいましたから
ゲスト:もう忘れてしまいましたね
MC :ははは、今回は巨大ウイルスというのをテーマにしたいと思います
ゲスト:はい
MC :みんなウイルスって、ね、なんか悪者っていうイメージだと思うんだけど
ゲスト:うん
MC :ウイルスについて聞きます、
武村先生はブルーバックスから巨大ウイルスと第4のドメイン、
生命進化論のパラダイムシフトという、
とっても難しいタイトルの本を出されてらっしゃいます
ゲスト:はい、そうですね
MC :はい、
ゲスト:はい
MC :で、その前にウイルス、
これウイルスってそもそもどういうものをウイルスって定義するんですか
ゲスト:まぁ、そもそも、そのう、最初に見つかった時にですね
MC :はい
ゲスト:そのラテン語で、まぁ毒という名前がつけられた、
まぁバイオレンスってそういう意味なんですけれども、
そのもともとはそのう、あのう人間とか
MC :はい
ゲスト:動物とか、植物とか、そういうものに、まぁ病気をもたらすものとして、
こう、見つかったんですけども、最初はあのう、つまり目に見えないものですからね
で、しかも細菌よりもぐうっと小さいものですから、
あのう、例えば、その昔は病原体をろ過器で、こう、ろ過してですね
MC :はい
ゲスト:あのう、なくして
MC :はい
ゲスト:で、まあ、それがいわゆる滅菌というか殺菌というかですね、
滅菌というんですけれども
MC :ああ
ゲスト:やっていたんですけど、それを実は通り抜けちゃうほど、
つまり、細菌とかそういう病原体よりもちっちゃいものであると、
MC :ほう
ゲスト:まず、そういうものですね、だから、あのう、
まぁ、あの具体的な単位を言いますと、数十ナノメートルという、
ナノというのは、ミリの1000分の1のミクロンの、
さらにその1000分の1がナノメートルなんですから
MC :えっ、1ミリの
ゲスト:ええ
MC :1000分の1の
ゲスト:の1000分の1
MC :さらに1000分の1
ゲスト:はい、その
MC :っていうのがナノ
ゲスト:ナノですね、そのレベルの、つまり大きさであると
MC :あの、よくウイルスというと、
ゲスト:うん
MC :たぶんラジオの前のキッズはインフルエンザとかノロウイルス
ゲスト:ええ、ええ、ええ
MC :っていうものを、
ゲスト:うん
MC :イメージするけれど、そのノロウイルスなんかもそんなちいちゃいものなんですか
ゲスト:そうですね、ノロウイルスは何十ナノメートルというぐらいの非常にちっちゃい、
まぁインフルエンザウイルスは、もうちょっと大きくてですね
MC :はい
ゲスト:100ナノメートルとか、200ナノメートルぐらいあるんですけども、
まぁそんなレベルのもので、これはもう、あの、ほんとに目で見えないし
MC :へぇ
ゲスト:当然普通の顕微鏡でも見えないくらいの
MC :日立ハイテクトの電子顕微鏡だったらばっちり見える
ゲスト:ああ、もうそれはもうばっちり見える
MC :あはは、そうなんですか
ゲスト:ええ、ええ
MC :あっ、そういう、えっ
ゲスト:それはばっちり見えますね
MC :じゃウイルスってのは、もう、めちゃめちゃ、ちっちゃい
ゲスト:ええ
MC :よく、よくほら、ウイルス飛ばしたるぅなんて言ってるけど、
ゲスト:うん
MC :それは、そう、もうほんと見えてないっていうことですね
ゲスト:見えてないですから、この辺にもいますよ、たぶん絶対
MC :いるう、ラブリにもウイルスいます
ゲスト:います、います
MC :先生はプロだから見える
ゲスト:見えません、ははは
MC :見えない
ゲスト:ははは
MC :やっぱり人間は見えない
ゲスト:人間は見えないです、うん
MC :へぇ、そんなちぃっちゃいものが人間の体に入りこむと、
とっても悪い害をもたらすわけじゃないですか
ゲスト:そうですね
MC :こわいですね
ゲスト:まぁ、目で見えませんからねぇ
MC :うーん
ゲスト:目で見えないからこそ、その仕組みもよく分かって無くてですね
MC :はい
ゲスト:まぁ、今でもほとんど、わかってない部分が多いと思うんですけれども
MC :はー
ゲスト:うん、だからこそこわいのかなという話ですね
MC :うーん、その小さなウイルスなんですけれど、
さっきね、細菌っておっしゃっていたですよね
ゲスト:ええ
MC :細菌
ゲスト:ええ、ええ
MC :だから、細菌とウイルスってイコールじゃないんですか
ゲスト:あっ、全然違いますですね
MC :どう違うんですか
ゲスト:まずは、あのう、細菌というのは私達と同じ生物ですね
MC :細菌は生き物
ゲスト:生き物なんです、で、私たちは何十億、何十兆という、
こう細胞、細胞というものからできてますけども
MC :はい
ゲスト:細菌だって、一つの、あれ、細胞なんですね
MC :はい
ゲスト:でも、実はウイルスとは、その細胞よりももっとちっちゃくて、
細胞というものとは言えないほど、もっと単純な形をしていると
MC :うん
ゲスト:ええ、で、世の中の、あのう、生物学者の話はですね、
たいてい、細胞からできてないと生物とは言わないというのが常識なんですね
MC :はい
ゲスト:ですから、ウイルスは細胞からできてなくて、
それよりももっと単純なものなので、生物というよりも、
むしろ物質、で、しかも、生物には限りなく近いんだけども
まぁ、生物の仲間入りはしてくれない、させてくれない物質であるという、
大体そういう位置づけのものですね
MC :細菌もウイルスも体に入ったら悪いものですよね
ゲスト:はい、はい、はい
MC :だから悪さするのは同じ
ゲスト:まぁ、悪さするのは同じですね
MC :じゃ、例えば、ウイルス、ノロとか
ゲスト:ええ
MC :インフルエンザとか
ゲスト:うん
MC :あれも悪くなる
ゲスト:うん
MC :細菌で体に影響をおよぼすものって何ですか、たとえば
ゲスト:たとえば、病原性大腸菌とかね
MC :ああー
ゲスト:あと、赤痢菌とかですね
MC :あああー
ゲスト:うん
MC :あれは細菌
ゲスト:そうそう
MC :で、もうちょっと大きいものですか、細菌は
ゲスト:もうちょっと大きいですね
MC :で、ウイルスは、インフルエンザとか
ゲスト:うん
MC :ノロウイルスとか
ゲスト:ノロウイルス
MC :あと何かあります
ゲスト:あとですか、あとヘルペスウイルスとかですね
MC :ああー
ゲスト:えー、アデノウイルスとか
MC :あああー
ゲスト:まぁ、いろいろありますね、あとなんだろう、
最近有名な、になってきたエボラ出血熱、エボラウイルス
MC :あっ、あれもウイルスか
ゲスト:ジカウイルス、ジカ熱
MC :うん、うん、
ゲスト:みんなウイルスですね
MC :なるほどね、じゃ、細菌よりかも、もっと、こう、やっかいなもの
ゲスト:まぁ目で見えないだけにやっかいですね
MC :はぁ
ゲスト:ええ、で、あまりその研究もですから細菌とかに比べると
MC :ふうん
ゲスト:まだまだっていう感じもしますのでね
MC :ふうん
ゲスト:ええ
MC :で、1ミリの1000分の1
ゲスト:ええ
MC :さらにその1000分の1の大きさしかないっていう
ゲスト:うん、まぁ実際にはそれよりももうちょっとでかいですかね
MC :大きいのもある
ゲスト:大きいものもありますかね
MC :いや、すごいですね、
いやこのウイルスに関して先生ずっと研究されてらっしゃると思うんですけれど
ゲスト:はい
MC :このウイルスを、じゃ今この、いい、あの、
ラボの中にもいるっておっしゃってたけど、いいウイルスもあるんですか
ゲスト:あのう、たとえば、僕達が生きている間に、
あっ、こいつはいいウイルスだなぁというふうに実感することはないんですけど、まず
MC :はい
ゲスト:まずないんですけど
MC :はい
ゲスト:たとえば、いいウイルスというと、
まぁ最近多少その有名になってきているんですけども
MC :はい
ゲスト:僕たちの進化
MC :はい
ゲスト:生物の進化に実は重要な役割を果たしてきている、
そういうウイルスっていうのが最近知られてまして
MC :へえ、たとえば
ゲスト:あのう、遺伝子、今、完全に人の遺伝子で調べられてるんですけども、
あのう、4割ぐらいがですね、人の遺伝子の
MC :うん
ゲスト:実はウイルスがもってきたんじゃないかというふうにさえ言われてるほど
MC :へぇ
ゲスト:実はウイルスってのは私たちに、こう、非常にこう、
まぁ貢献してくれたっていうとね、言い方あれですけども
MC :ふうん
ゲスト:僕たちの進化、今、
進化して今ここにあるのは実はウイルスのおかげだともいえる
MC :ふうん
ゲスト:ですね
MC :で、僕ら人間のもつ免疫力とか
ゲスト:うん
MC :あのう、体力とか、いろんなものをつかさどっているものは、
ウイルスによってもたらされて、
人間の進化を手伝ってくれてるってことですか
ゲスト:まぁ、一部でしょうけどね、
MC :へぇえ
ゲスト:あの、その全てではないと思いますけども
MC :へぇえ
ゲスト:ええ
MC :へぇえ、いやぁ、なんか、夢ふくらむ、宇宙とはまた違ったロマンがありますね
ゲスト:ああ、ありがとうございます、そうなんですよ、
ミクロの世界はまたロマンがあるんですよ
MC :ううん、ただ、そんな中で先生、巨大ウイルスってのが今回の
ゲスト:はい
MC :テーマだったんですけど
ゲスト:はいはい
MC :ウイルスってのはすごくちっちゃいって聞いたんですけど
ゲスト:ええ
MC :巨大ウイルスってどれぐらいの巨大さなんですか
ゲスト:巨大といっても、それまでのウイルスにとって巨大という意味なので
MC :ええ
ゲスト:だから、われわれが巨大なダイオウイカみたいな、
そんなに、でかくはないですね
MC :あっ、どんなかんじですか
ゲスト:あのう、ウイルスにとってみると
ダイオウイカだなぁというのがウイルス、巨大ウイルスで
MC :はい
ゲスト:つまり、大体細菌と同じぐらいの大きさをもつ、
MC :ほう
ゲスト:ウイルスというのが
MC :はい
ゲスト:最近みつかってきてるんですね
MC :はい
ゲスト:だから細菌は、でも、もっとちっちゃいのがそれまでのウイルスだったのが
MC :はい
ゲスト:細菌レベルにまで大きくなったもの、大きいやつがいると
MC :ふんふん
ゲスト:で、サイズだけじゃなくて、
その遺伝子の数も非常に多かったりするんですね
MC :はい
ゲスト:つまり、それまでのウイルスに比べてサイズもデカいだけではなくて、
遺伝子も多様で複雑であると
MC :うん、それが発見されたことによって
ゲスト:うん
MC :先生の研究では、何が、こう、プラスになってくるんですか
ゲスト:まぁ、私の研究そのものが巨大ウイルスの研究なもんですから
MC :はい
ゲスト:あれなんですけれども、その巨大ウイルスの研究をしていくことで、
ひょっとしたら、つまり巨大だということそのものが
結構その常識破り的なものだったので
MC :はい
ゲスト:ウイルスと生物との垣根がですね、
ちょっとこうボーダーラインが、なんかゆらいできてるような
MC :ほう
ゲスト:そういう実はイメージがありますね
MC :さきほど、細菌は生物だっておっしゃってましたけれど
ゲスト:はい
MC :巨大ウイルスをみつけたことによって
ゲスト:ふん
MC :じゃあ、これ生物というカテゴリーにはいっちゃうんじゃないかと
ゲスト:そこの実は議論がはじまってるんですね、あのう、まだごく一部なんですけれどね
MC :はい
ゲスト:ひょっとしたら今までのウイルスと生物を分ける、
その、たとえば、その細胞からできてないとか
MC :はい
ゲスト:まぁ、ほかにもいろいろあるんですけども、
そういったこれまでの概念だけを適応、概念をつかうだけではちょっと、
あの、ものたりないないような連中がその巨大ウイルス
MC :うん
ゲスト:であると
MC :ふーん
ゲスト:いうことで、そもそも生物ってなんだろうとかですね
MC :うん
ゲスト:ウイルスってなんだろうという、えー、まぁ、そもそも論っていうやつを、
われわれは、そういう、その生物とは何かというところにまで、
こう、なんか、こう突き詰めていくというね
MC :うん
ゲスト:そういうきっかけになるような存在が
この巨大ウイルスだというふうにわれわれは考えてるんですね
MC :へぇえ
ゲスト:だから、高校や中学で学ぶ生物というものはね
MC :はい
ゲスト:ひょっとしたら、変わってくるかもしれないなぁという
MC :あっ、そうなんですか
ゲスト:だいぶ先ですけどね
MC :場合によっちゃあ、じゃあ
ゲスト:場合によっては
MC :あの10年後20年後
ゲスト:うん
MC :教科書の内容が変わってくるかもしれない研究をされてると
ゲスト:あのう、まぁ、数十年後はムリかな、百年後ぐらいには
MC :あっ、そうなんですか
ゲスト:変わってくるかなというふうには、僕自身は思っていますけども
MC :へぇえ
ゲスト:ええ
MC :もうちょっと詳しい話を、またね、週またいで来週うかがいたいと思いますけど
ゲスト:はい
MC :ウイルス、また来週です
ゲスト:はい
MC :今週のサイコーは東京理科大学教授の武村政春先生でした、ありがとうございました
ゲスト:ありがとうございました -
「ニュートリノってなに? パート2」 ゲスト:多田将さん
2020/09/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :今回の「サイコー」もですね、
高エネルギー加速器研究機構の多田将さんです。
こんにちは。お願いします。
ゲスト:はい。よろしくお願いします。
MC :えー、多田さん、先週伺いました
ゲスト:はい。
MC :えー、そうですね、ニュートリノの研究されてらっしゃる、
今年はニュートリノってのは、もう、ほんとキーワードですよ。
ゲスト:はい。
MC :あのー、五郎丸さんかニュートリノですね。
ゲスト:はあい。はは。
MC :なんとなく。
ゲスト:はい。
MC :はい。ニュートリノみんな覚えたと思います。
ゲスト:はい。
MC :で、そのニュートリノを研究
ゲスト:はい。
MC :されている
ゲスト:はい。
MC :これが、宇宙の起源につながる話だっていうのが、先週までのお話です。
ゲスト:はい。
MC :なんでですか、これが
ゲスト:はい。実はですね、世の中には、
MC :ええ。
ゲスト:僕たちの体を作ってる普通の物質に対して、
全くそれのペアとなっている、反物質なるものが存在するんですよ。
MC :えっ。
ゲスト:この反物質は、
MC :右があったら、ひ、左がある。
ゲスト:みたいなものですね。
MC :裏と表みたい
ゲスト:そうです。
MC :はい。
ゲスト:鏡の中の相手みたいな感じですね。
MC :はい。
ゲスト:でも、この反物質というのはですね、
あの、これ実際、SFの世界じゃないんですよ。
MC :はい。
ゲスト:実際に、人工的に作ることができるんです。
MC :ええ。
ゲスト:ところが、天然には存在してないんです。
MC :ふーん。
ゲスト:で、この反物質と物質の実はペアになってる、
単にペアになってるだけじゃなくて、
MC :はい。
ゲスト:面白いのは、この二つがペアになってるものが出会うと、
消滅してエネルギーになってしまうんです。
MC :はい。
ゲスト:で、また逆にエネルギーからその物質、反物質を作ることができるんですけども、
それも必ず物質と反物質のペアで出来るんですね。
MC :へえ。
ゲスト:例えば、電子の話をしましたけども、電子には陽電子というペアがあって、
その、よ、電子と陽電子が出会うとエネルギーに変わるし、
強いエネルギーがあれば、電子、陽電子のペアが出来上がるという、
必ずそういうふうになってるんです。それで、
MC :ふーん。
ゲスト:ところがですね、ここで不思議なことがあるんです。
つまり宇宙は最初エネルギーの塊みたいなものから、
あらゆる物質が出来上がったと考えられていますが、
MC :はい。
ゲスト:もしそうだったら、ペアで出来るんだから、
ぜっ、実際にはですね、物質と同じ数だけ反物質がないといけないんです。
MC :はい。
ゲスト:ところが、みなさんの周り反物質ないですよね。
MC :言われてみると
ゲスト:ぶつかったら、消滅してしまうんですよ。
みなさんが何か、何かにぶつかった途端に消えてしまったとかいうことは、
MC :ふん。
ゲスト:そんな事件はありませんよね。
MC :はい。
ゲスト:これは、つまり、これはあの、宇宙の、
例えば地球にはなくても宇宙にあるかとか、
MC :はあー。
ゲスト:そういう探索をやってる人達もいるんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:その探索の結果、やはり反物質は天然にはないことがわかってるんです。
MC :へえー。
ゲスト:一方で、人工では作ることができるんですけどね。
MC :ふん。
ゲスト:と、いうことで、なぜ、同じ必ずペアで出来て、
必ずペアで消えるはずの物質と反物質が、こんなに物質だけが残って、
反物質がないか、これの説明は、従来の理論では説明できなかったんです。
MC :ふん。
ゲスト:そこで、それを何とか説明しようという、その対称性がちょっと狂ってる
MC :うん。
ゲスト:ちょっとだけ物質が多く残った理由ですね、
それを、あの、考え出した理論ていうのが、色々ま、考えて来たわけですね、
物理学者が。で、それをですね、実は僕達は、えー、ニュートリノ、
色んな素粒子についてそういうのを調べる、ことができるんですが、
MC :はい。
ゲスト:僕たちはニュートリノについて、
ニュートリノとその反物質である反ニュートリノと、
それがどう違いがあるかっていうのを調べよういうわけなんです。
MC :その、反ニュートリノっていうのは、
ゲスト:はい。
MC :もう、見つけられたんですか?
ゲスト:これはですね、僕らは、簡単に作ることが出来るんです。
MC :ええっ。
ゲスト:この、茨城県東海村の設備では、
MC :はい。
ゲスト:もう、ほんとに、あの、ちょっと、あの、機械をいじるだけで、
MC :はい。
ゲスト:ニュートリノを作ったり反ニュートリノを作ったり
MC :ふん。
ゲスト:切り替えることが出来るんです。
MC :自然界には、今のところ見つかってないけれど
ゲスト:はい。
MC :人工的には、出来る
ゲスト:作ることが出来るんです。
MC :ということですね。はい。
ゲスト:もし、それを調べるとですね、調べたら、そしたら宇宙は、
なぜ僕たちは物質だけ、我々がなぜ存在してるのかという根本的な理由がわかるんです。
MC :僕らて存在してるけれど、
ゲスト:はい。
MC :それに反物質があると存在しないっていう、
ゲスト:ええ。
MC :反対側のも考えられるってことですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :で、僕ら、でも、存在してるわけですよね。
ゲスト:ええ。
MC :で、それが立証されるとどうなるんですか。
ゲスト:やっぱりですね、あの、ま、あの、僕たちっていうのは、
ま、確かに、あの、僕達は存在してるんだから、
そんな、も、理由なんかいらないんだって
MC :はい。
ゲスト:考え方もあります。
MC :はい。
ゲスト:でもやっぱり、あの、本来であれば存在してるはずのない僕たちが
MC :はい。
ゲスト:なぜ、存在してるのか、やっぱり興味がありませんか。
MC :ある。
ゲスト:やっぱりそれはね、人類の、今んところ、究極の問いなんですよ、理論なんですよ。
MC :うーん。
ゲスト:なぜ、僕たちは存在してるのかって、
やっぱり、究極の問いなんです、質問なんですよね。
MC :うん、うん。
ゲスト:それにやっぱり、答えるっていうのは、重要なことだと僕たち、僕は思っています。
MC :うーーん。
ゲスト:で、あの、またそれ以外にも、やっぱり、ニュートリノって、
ものすごい天然には存在している訳ですよ。
MC :はい。
ゲスト:太陽からもいっぱい来てる訳ですね。
MC :はい。
ゲスト:ですから、それを、やっぱり、性質はない、わからないままだと、
MC :はい。
ゲスト:今んところ、全部捨ててる訳ですよね。
MC :そうですよね。
ゲスト:性質が分からないから。これがもし、性質が分かれば、
それの利用方法だって分かるはずですよね。
MC :あっ、今のところ、な、なんの、変な話、何の役にもたってない訳ですよね。
ニュートリノ
ゲスト:そういうことです。
MC :これが、
ゲスト:残念なことに
MC :体を通過することで、体に悪いってことも言われてないし、
ゲスト:そうです。
MC :特に害もないし、
ゲスト:ええ。
MC :得もないということですよね。
ゲスト:そうです。
MC :ただ、場合によっては、その、得の部分が発見されるかも分からない。
ゲスト:そうです、そのためには、まず、性質を知らないと。
MC :うーん。
ゲスト:性質の知らないものは、利用できない、ですからね。
MC :はーい。
ゲスト:だから、そういうために僕達は、
ニュートリノの性質を解明しようっていう訳なんですよ。
MC :あのー、すごく、僕、僕ね、宇宙でビッグバンが元々始まって
ゲスト:はい。
MC :その過程の中で、僕らいるわけじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :だから、もしかしたら、
ゲスト:はい。
MC :そのビッグバンの中心からまだ地球上に届いてない物質とか、
あるんじゃないかと思ってるわけですよ。
ゲスト:ええ。
MC :だ、ちょっとダメですか、そんな
ゲスト:いいですよ。
MC :えっ。
ゲスト:これはですね、
MC :ええ。
ゲスト:そこがね、まずね、みなさんのたぶん、おお、多くの人が勘違いされてる
MC :ええっ。はい。
ゲスト:つまり、ビッグバンは宇宙のどこかで起きて、
というふうな考え、これがね、実は違うんですよ。
MC :ええっ。
ゲスト:ビッグバンは、宇宙のすべての空間で同時に起こってます。
MC :ええっ、そうなんですか?
ゲスト:そして、あともう一つはね、このビックバンていう名前を聞くと、
なんか爆発が起こったように考えますね。
MC :おお、思ってます。
ゲスト:これはね、名前を付けた人が、あの、
ついそういう名前を付けちゃったんですけど
MC :ええっ。
ゲスト:ほんとはそうでないんです。
MC :何だったんですか、ビッグバンは。
ゲスト:ビッグバンていうのは、宇宙が、宇宙ってのは初期は、
ええっと、ある非常に狭い所に、一点に集まってたと考えられています。
MC :へえー。
ゲスト:これは、実際観測によって、宇宙はだんだんと広がっている膨張している、
このことが観測されたんですね。これなんか、1929年です。
MC :はい。
ゲスト:最初に発見されたの。
MC :おー、もう100年近くなるんですね。
ゲスト:そうです。それで宇宙が今どんどん広がっていってると考えれば、
MC :はい。
ゲスト:時間を逆戻しにすると、て、ということは、
昔は一か所に集まったという意味ですよね。
MC :うん。言われてみりゃ、
ゲスト:つまり、
MC :そうですね。
ゲスト:そうです。そして、えーっと、つまり、えーっと、
同じ宇宙にある物質の量だとか、或いはエネルギーの量だとか、
そういう総和は同じです。宇宙から出る事は出来ませんから。
その全部のものが、一か所に集まってたということは、
MC :うん。
ゲスト:同時にこれは、宇宙自体が、えーと、非常に、高い温度、
高温であったということが考えられるわけです。
その非常に密度が濃くて、温度が高くて、
その状態のことをビックバンと呼んでるだけなんです。
MC :へえー。
ゲスト:だから、
MC :密度が高くて高温?
ゲスト:そうです。
MC :はい。
ゲスト:高温高圧の状態ですね。
MC :ほー、例えば
ゲスト:その、
MC :僕らの生活のなかでそういうものって、何ですかね。
あの、電子レンジの中に入ってるじゃがいもとかそんな感じですか?
ゲスト:じゃがいもじゃ、まだまだですね。
MC :あは。えへ。
ゲスト:じゃがいもでは、まだまだです。
MC :電子レンジにある石とか
ゲスト:ええ。これぐらいじゃまだまだです。
電子レンジでつくれるのっていうのは、例えばじゃがいもだったら、
あの、爆発するぐらいあっても100度とかその程度ですよね。
MC :はい、はい。
ゲスト:実は、人間が、あの、作ることができるっていうのは、
えーっとですね、1兆度の10万倍。
MC :なんですか、それ。
ゲスト:そこまでは人間は再現できてます。
でも、それでも実はですね、宇宙年表の半分ぐらいまでしかできないんです。
MC :1兆度の10万倍っていう温度があるんですか?
ゲスト:そうです。それは、あの、人類が作ることができた最高温度です。
MC :はあー。
ゲスト:それは、あの、もしかしたらご存知かもしれませんが、
あの、ヒッグス粒子を発見したと言われる
MC :おお、はい。
ゲスト:あの、セルンといわれる
MC :はい。
ゲスト:まあ、ヨーロッパにある
MC :はい。
ゲスト:実験施設の、エルエイチシーという
MC :へえー。
ゲスト:その加速器で作られたのが、そこなんですね。
MC :はい。
ゲスト:それはもう、あの、人類の到達した最高温度なんですけど
MC :1兆度の10万倍
ゲスト:そうです。
MC :すごい。
ゲスト:それでもなお、宇宙の一番最初までは行ってないんですね。
MC :あ、それほどもうチンチンの状態だったんですね。
ゲスト:そうです。最初は
MC :宇宙は最初は
ゲスト:そう、そうです。
MC :それがはじけて、
ゲスト:ええ。
MC :いろんな、宇宙空間てものが誕生した。
ゲスト:そうです。段々、広い空間に広がっていくことで、
MC :はあー。
ゲスト:あの、ま、温度が冷めていったわけですね。
MC :ふーん。えっ、冷めてった。
今、じゃ、僕ら冷めてる最中、過渡期ですか?
ゲスト:そうです。だいぶ冷え、冷えてますよ今
MC :え、でも今、地球温暖化って言われてるけど
ゲスト:あははは。
MC :それとは、全然違うんですね。
ゲスト:地球が温暖化しようとですね、
MC :はい。
ゲスト:宇宙の平均温度にしたら、低い低いものです。
MC :ひゃー。ということは、
ゲスト:はい。
MC :じゃ、なに、これからやがては、地球が冷えてしまって、
ゲスト:ええ。
MC :氷河期が来るかもしれないんですか。
ゲスト:そうですね、氷河期よりもっと寒い時代に
MC :そうすると、人類滅亡するじゃないですか
ゲスト:そうですね、あのー、宇宙はほんとに、
あの、冷えてしまって、死んでしまうという考えの、説もあります。
MC :それは向こう何年ぐらい先の話なんでしょう。
ゲスト:まあ、あの、僕達の寿命より長いですからね
MC :そうですか。
ゲスト:そうですね。
MC :今、キッズ達、きっと青ざめてますよ。
ゲスト:あはははは。
MC :僕達がおじいちゃんなったら、もう、死ぬんだっていう
ゲスト:そう、そう。おじいちゃんよりももっと長いです
MC :もっと先
ゲスト:もっとはるか先ですからね
MC :今のところ、その兆候はないということ
ゲスト:兆候というか、あの、実際にはなるんですけど
MC :はい。
ゲスト:何百億年とかそういうレベルですので
MC :あっ、そうですか
ゲスト:だから、安心して下さい。
MC :一安心です。
ゲスト:はい。
MC :いやー、すごい話だったなあ、ロマンを感じますねぇ。
今週の「サイコー」は高エネルギー加速器研究機構の多田将さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「ニュートリノってなに? パート1」 ゲスト:多田将さん
2020/09/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今回のサイエンスコーチャー略して「サイコー」はすごいお方が来てる。
えー、私の目の前に、茶髪ロン毛の、はははは。でも、科学者。
え、高エネルギー加速器研究機構の多田将さんです。こんにちは。
ゲスト:こんばんは。あのですね、
MC :ええ。
ゲスト:あの、一応一つ訂正させて
MC :はい。
ゲスト:もらいましょう。
MC :はい。
ゲスト:茶髪ではなく、金髪です。
MC :金髪。
ゲスト:ははははは。
MC :そう、すごいんです。まぶしい、まぶしいですねー、金髪、ロン毛、の科学者。
ゲスト:はい。
MC :いやー、何か映画に出てきそうな
ゲスト:ははは。
MC :感じの方なんですけれど、
ゲスト:ありがとうございます。
MC :多田さんは、
ゲスト:はい。
MC :1970年
ゲスト:はい。
MC :大阪の生まれ、
ゲスト:はい。
MC :関西の方。
ゲスト:そうです。
MC :えー、京都大学理学研究科博士課程終了。
ゲスト:はい。
MC :すごいですね。
ゲスト:こう見えても理学博士です。
MC :すごいですねえ。
ゲスト:はい。
MC :で、高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所准教授という
ゲスト:はい。
MC :長いけれど、
ゲスト:はい。
MC :ま、すごい方なんですよ。
ゲスト:あははは。
MC :も、今年はなんといってもニュートリノの年。
ゲスト:はい、そうですね。
MC :はい。えー、ノーベル賞とられた梶田さんのお話なんですけれど
ゲスト:はい。
MC :梶田さんと同じような研究されてるてことでよろしいんですよね。
ゲスト:そうです、はい。
MC :うーん、さあ、この梶田さん改めて、
ゲスト:はい。
MC :受賞から
ゲスト:はい。
MC :ちょっと時間経ったんですけれど
ゲスト:はい。
MC :分かりやすく梶田さん何をされたんでしょう。
ゲスト:ええ。まずはですね、その、受賞理由だったニュートリノの研究の、
MC :はい。
ゲスト:その、ニュートリノとは何かってお話をしてみます。
MC :興味深い。
ゲスト:ええ。ニュートリノっていうのは、何か、名前は聞いたことありますよね。
MC :あります。
ゲスト:結構ね、日本人の方は名前だけは聞いたことがあると思うんですよ。
MC :はい。
ゲスト:うちの母親なんか何十年間も主婦やってた人ですけど
MC :はい。
ゲスト:名前だけは知ってるんですね。
MC :うん。
ゲスト:どんなものか知りませんけれども。
MC :小柴先生の影響じゃないですか?
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:たぶん、あの、その、次々とニュートリノの分野で、
MC :はい。
ゲスト:色々受賞される方が多いので、それで報道も特にされてるから、
MC :はい。
ゲスト:だと思います。それで、ニュートリノっていうのはですね、
素粒子といわれるものの
MC :はい。
ゲスト:一種です。素粒子というのは
MC :はい。
ゲスト:何かといえばですね、例えばぼくたちの体をバラバラにしていきますよね。
MC :うん。
ゲスト:僕たちの体をまずバラバラにすると内臓になりますよね。
MC :うん。
ゲスト:内蔵バラバラにすると、細胞になりますよね。
MC :はい。
ゲスト:細胞バラバラにすると分子、アミノ酸とかの分子になりますよね。
MC :はい。
ゲスト:それを、分子をバラバラにすると、原子になります。
MC :分子、原子。はい。
ゲスト:原子。原子をバラバラにすると、原子核になります。
MC :分子、原子、原子核。
ゲスト:原子核。さらに原子核をバラバラにすると素粒子といわれる、
も、これ以上はバラバラにできない、究極の一番小っさい粒子から出来てる。
MC :分子、原子、原子核、素粒子。
だから山手線ゲームみたいになってきたけど
ゲスト:そうですね。
MC :覚えました。
ゲスト:ええ。
MC :はい。
ゲスト:この素粒子というものが組み合わさって
世の中の全てのものが出来あがってるんですね。
MC :素粒子何種類あるんでしたっけ。
ゲスト:素粒子はですね、12種類。
MC :つまり、
ゲスト:あります。
MC :人間、バラバラ、世の中にあるもの
ゲスト:はい。
MC :物質も全部バラバラにすると、
ゲスト:はい。
MC :たった12種類にしかならないてこと
ゲスト:そういうことなんですね。
MC :その12種類のものから、
ゲスト:はい。
MC :地球上にあるもの全てが構成されてる。
ゲスト:宇宙すべてです。
MC :宇宙すべてが
ゲスト:はい、そうです。
MC :わぁお。
ゲスト:そうです。
MC :一ダース。
ゲスト:そうです。それだけなんですね。
MC :12種類。
ゲスト:たった12種類です。
MC :はい。
ゲスト:その内の、いっ、一種類がニュートリノといわれるもの。
MC :12分の1がニュートリノ。
ゲスト:えーとですね、ニュートリノは、実際には3種類ありますので、
MC :えっ、12分の3
ゲスト:12分の3ですね。
MC :てことは、宇宙の
ゲスト:はい。
MC :4分の1がニュートリノ
ゲスト:そうですね、数としてはですね、
MC :はい。
ゲスト:実はですね、僕たちの体を作ってる素粒子は他にも電子なんてあります。
電子なんてよく聞きますよね。
MC :はい。
ゲスト:電気の元ですよね。
MC :電気
ゲスト:電子みたいなものよりも、ニュートリノの方がね、1億倍多いんです。だから、
MC :物質としてものすごく多いんですね。
ゲスト:数としては多いんですね。
MC :へー。
ゲスト:それで、あの、ニュートリノはさっきも言ったように、
その、元になるものですから、
MC :はい。
ゲスト:あらゆるものに入ってて、例えば、あの、
原子核が反応すると絶対出てくるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:例えば、あの、原子炉なんかでもニュートリノ出てきますし、
MC :はーい。はい。
ゲスト:皆さんもっと身近なんで言ったら、太陽ありますよね。
MC :はい。
ゲスト:太陽は核が反応して、それで、あの、ま、光ってるわけですけども
MC :はい。
ゲスト:あそこは光以外に、ニュートリノもバンバン出てくるんですね。
MC :ふん。
ゲスト:だから、今僕たちは、ニュートリノ、
太陽から来てるニュートリノを今現在もバンバン浴びてるんですよ。
MC :ちょっと待って下さい。僕ら、これ、ラボ、屋内ですよ。
ゲスト:ええ。
MC :屋内で太陽光入ってないけれど、
ゲスト:ええ。
MC :それでもニュートリノ来てるんですか?
ゲスト:そうです。
MC :あ、そうか、建物も通過しちゃうってことですか?
ゲスト:そうです。で、ニュートリノはですね、
MC :すごい話
ゲスト:僕たちがどれぐらい浴びてるか、
MC :はい。
ゲスト:1秒間当たりに太陽から来るニュートリノの量っていうのは、
MC :はい。
ゲスト:一人あたり、ですね、1秒間あたり600兆個です。
MC :え、1秒間で600兆
ゲスト:600兆
MC :ピッったら600兆
ゲスト:そうです、そうです。浴びてるんです。
MC :えっ、600兆浴びてるけれど
ゲスト:ええ。
MC :体に感じない。
ゲスト:何か、浴びてる感がないでしょ
MC :全くない。
ゲスト:何か、今日はちょっとニュートリノきついわとか
MC :えー。
ゲスト:そういうのないでしょ。
MC :ははは。
ゲスト:そういうの。あんま、無いでしょ。
MC :ない。
ゲスト:なぜかというと、それが先ほどちょっと、おっしゃった、
MC :ええ。
ゲスト:つまり、ニュートリノは反応性が乏しいんですよ。
MC :うん。
ゲスト:例えばね、太陽から来る、今、来てますって言いましたよね。
MC :はい、はい。
ゲスト:そのニュートリノが地球に、まあ、入りますよね、当たりますよね。
MC :はあ。
ゲスト:その時に、地球に1回でもコンと当たる確率、
MC :はい。
ゲスト:普通考えたら地球なんてみっちり詰まった岩石の塊ですよね。
そんなん絶対地表でガンガン当たると思うでしょ。
ところが、ニュートリノは、あの、ほとんど反応しない粒子なので、
この非常に巨大な1万3000キロメーターぐらい直径がある、岩石の塊ですら、
MC :はい。
ゲスト:途中で1回でも当たる確率は、10億分の2程度なんです。
MC :うーん。
ゲスト:つまり5億個、地球を並べたら、ようやく1回当たるぐらい
MC :えーっ。
ゲスト:さんなん、それに比べたら、僕らの体なんて、全然小っちゃいですから、
MC :うん。
ゲスト:もう、ほとんど全部通り抜けちゃうわけですね。
MC :それ以前に通り抜けちゃうんだったら、
ゲスト:はい。
MC :ない、無いに等しい訳じゃないですか
ゲスト:そうです。
MC :それ、それがなんで有るってわかったんでしょうか。
ゲスト:ですからね。
MC :うーん。
ゲスト:ニュートリノっていうのは、実は初めて提唱されてから、
MC :はい。
ゲスト:あの、発見されるまでに
MC :ええ。
ゲスト:あの、二十数年かかってるんです。
MC :ある、あるって言われながら
ゲスト:そうですね。
MC :えっ、確認されるまで二十数年?
ゲスト:かかってるんですよ。
MC :はっ、へへへ。
ゲスト:そして、実は、ニュートリノ、そこ、発見された後もですね、
MC :ええ。
ゲスト:あの、その性質、
MC :はい。
ゲスト:その性質がわかるかどうか、う、あの、性質ですらですね、
えっと、なん、何十年にも渡って、謎、のまま調べるのも大変なんですね。
MC :うーん。
ゲスト:あることは分かっても。
MC :はい。
ゲスト:例えばね、物の重さ
MC :はい。
ゲスト:重さっていうのは、もの、物事の一番基本じゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:その重さですら、ニュートリノは、重さがあるかないか、
ていうそういう当たり前の一番基本的な
MC :ふん。
ゲスト:第一歩のところですらですね、20世紀の終わりになるまでわからなかったんです。
MC :で、あの、梶田先生は、
ゲスト:はい。
MC :そのニュートリノに質量、重さがあることを発見したことによって、
ノーベル賞取ったってこと
ゲスト:そうです。
MC :ですよね。
ゲスト:梶田先生はですね、あの、大気で作られる天然のニュートリノ
MC :はい。
ゲスト:それをですね、研究することで、どうもニュートリノには質量があるというのを
MC :はあー。
ゲスト:発見しました。でも正確に言うとですね、
MC :うーん。
ゲスト:実は質量があるっていう事が、本質的なことではないんです。
MC :ち、え、何ですか、本質は。
ゲスト:一番重要なのは
MC :はい。
ゲスト:先程ニュートリノっていうのは、3種類あるって言いましたよね。
MC :はい。
ゲスト:これが、実は、お互いに変化するというそのことを発見したんです。
MC :あ、
ゲスト:これは、
MC :へー。
ゲスト:何かあの、え、だから何?と思うかもしれませんが、
MC :はい。
ゲスト:結構素粒子が変化するって重要なんですよ。
MC :へー。
ゲスト:例えばさっき、電子の話しましたけど、
MC :はい。
ゲスト:僕らの体、電子で出来てますよね。
MC :うん。
ゲスト:ところが、これが他のに変わるってのは、大事件だと思いませんか?
MC :うん。
ゲスト:これは、大きなことですよね。
MC :そういうことです。
ゲスト:だから、非常に、これ、重要なことなんですね。
MC :はい。
ゲスト:あの、それが普通の標準的なこれまで信じられてきた、
20世紀で信じられてきた理論では、説明がつかないようなことなんです。
MC :うーん。
ゲスト:それを発見されたんですね。
で、実際にはですね、これを理論で一番最初に提唱したのは、
なんとこれも日本人なんですね。
MC :へえー。
ゲスト:日本人の、あの、か、物理学者の方々が、
あの、牧先生、中川先生、坂田先生という3人の先生がですね、
MC :はい。
ゲスト:1962年とかなり昔
MC :50年以上前、
ゲスト:そうです。
MC :53年前か。
ゲスト:そうです。
MC :え。
ゲスト:それに、そういうニュートリノがお互いに変わるかもしれない、
そういうふうな理論を考えられたんですね。
でも、さっきも言ったようにニュートリノって、全部通り抜けちゃうから
MC :はい。
ゲスト:もう、調べようがなかったんです。
MC :うん。
ゲスト:それが、あの、ようやく20世紀の終わりになって、
初めて、その、ニュートリノを詳しく調べることができる、
それがスーパーカミオカンデです。
MC :へえー。
ゲスト:それを検出することによって、それを発見することができた。
本当にそうだってのを確かめる事ができたんですね。
MC :ふーーん。
ゲスト:その原子、みっ
MC :3種類に変化することによって
ゲスト:はい。
MC :何が、メリット、デメリットがあるんですか。
ゲスト:これはですね、あの、ニュートリノ、
ようするに先ほども言った、素粒子が変わるなんていうのは、
MC :はい。
ゲスト:これは、だから普通ではまず考えられないのが1つと
MC :はい。
ゲスト:もう1つ重要なことはですね、これね、あの、
ちょっとこれはあの、次回にちょっと詳しくやりますが、
MC :あっ、はい。
ゲスト:えーっと、宇宙の始まりに関わってくるんです。
MC :うわ、興味深。
ゲスト:あははは。
MC :ちょっと待って、もう、とっとこ、とっとこ。
ゲスト:そうですね。
MC :もう、
ゲスト:とっときましょ。
MC :もう、その話したら、
ゲスト:はい。
MC :一晩、ちょっと、僕、あの、伺いたいくらいです。
ゲスト:そうですね。
MC :宇宙の始まりまで、行くわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :いやー、興味深い、眠れないよ。
さあ、え、じゃあ、もう時間なっちゃったんですけれど
ゲスト:はい。
MC :いやー、すごいな。今週の「サイコー」は、
高エネルギー加速器研究機構の多田将さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「夏のスキマ植物 パート2」 ゲスト:塚谷裕一さん
2020/08/01 Sat 12:00 カテゴリ:植物MC :今週のサイエンスコーチャーも前回に続きまして、
東京大学大学院教授の塚谷裕一先生です。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :おねがいします。
ゲスト:おねがいします。
MC :塚谷先生は隙間植物、だからあのー、皆の、えー、
雑草呼ばわりするような植物に対して、も、大変な愛情注ぎながら、
えー、写真集を出すぐらいの感じなんですけど、
先週聞いてくれたキッズ達は1週間隙間植物探してくれた?
色んなところから植物生えてますけれどね。
さあ、えー、先生おすすめの夏休みの自由研究ズバリ、
身の回りで見られる隙間の植物の戸籍調べということを今日は
ゲスト:そうですね。
MC :ご提案下さるということです。
ゲスト:はい。
MC :どういうことですか、これは。
ゲスト:え、やつぱりですね、あの、今までに2冊隙間の植物の本を出しましたけども
MC :はい。
ゲスト:それでまあ、200種ぐらいあるんですね。
MC :はい。
ゲスト:なんですけども、
いまだに僕自身が街を歩いていて少なくとも1か月に一回ぐらい、
いままでこんなの見たことないぞっての見つけるんですよ。
MC :うん。へえ。新たな発見があるんですか?
ゲスト:はい。
MC :へええ。
ゲスト:今まで隙間にいたのを見たことが無かったけど、
ああ、これも隙間に生えるんだねってやつ
MC :ああ。
ゲスト:いるんですよ。
MC :植物は知ってるけれど、
ゲスト:はい。
MC :隙間にいるところが大事ってことですね。
ゲスト:そう、そう、そう、そう、そう、そう。
MC :ああ、わかりました。はい、はい。
ゲスト:ですので、
MC :はい。
ゲスト:あの、ま、それだけ見ててもまだまだ次々と隙間にいる顔ぶれって増えてくるので、
MC :はあー。
ゲスト:たぶんですね、
MC :はい。
ゲスト:夏休みに徹底的に
MC :はい。
ゲスト:まあ、皆さんの家の周りにいる隙間植物をリストアップしていくと
たぶん相当の数いると思うですよ。
MC :いいですね。
ゲスト:うん。
MC :おー、そして先週の続きじゃないけど、
その植物がなんでここから生えているのかってことを
ゲスト:うん。
MC :とことん調べると
ゲスト:そう、そう、そう、そう。
MC :虫が運んだのか鳥が運んだのか風が運んだのかとか。
ゲスト:うん。
MC :いいですねー。えー、例えばちょっとなんかこういうのあります?例えば
ゲスト:はあ。
MC :ヒントで
ゲスト:ヒントですか。えっとね、面白いのは、
あのさっき雑草が生えるっておっしゃったんですけど
MC :はい。
ゲスト:雑草だけじゃなくって皆花壇で大事に植えるような植物も結構隙間にくるんですよね。
MC :えっ、例えばなんですか?
ゲスト:夏だとまあ、よく花壇に植えてるペチュニア、
花の色が赤だったり紫だったり結構派手なやつで
MC :はい。
ゲスト:今いっぱい品種改良されて
MC :小学校の花壇にもよくありますよね。
ゲスト:よくありますね。
MC :はい。
ゲスト:うん、うん。で、最近は黄色いのだったり
MC :はい。
ゲスト:あと、ペチュニアの近縁種の別のやつと掛け合わせて出来たサフィニアとか
MC :はい。
ゲスト:新しいやつが次々生まれてんですけど、
MC :はい。
ゲスト:それが出来る傍から新しい品種ができる傍から隙間に逃げ出してるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:なのでそういうのを見てるだけでも結構な顔ぶれがあると思うんですよね。
MC :じゃあ、それが花壇じゃなくて
ゲスト:うん。
MC :隙間から生えてたら
ゲスト:そう。
MC :そっから研究スタートさせるっていうこと
ゲスト:で、もともとどこにいたんだろうねってたどって行くことも多分できると思うんですね。
MC :あ、そのもともとの母体がどこにあったかってことですね。
ゲスト:そうです、そうです。たぶん、近所に植えてる家があったり、
MC :ははあ。
ゲスト:花壇があったり、すると思うんですよ。
MC :いやー、ちょっと探偵みたいで面白いじゃないですか。
ゲスト:そう、そう、そう。
MC :隙間探偵。
ゲスト:そう。
MC :いやー、あと夏は海ですよね。
ゲスト:海ですね。
MC :海では隙間植物って、あの、砂浜は植物ないですよね。まずね。
ゲスト:うん。砂浜もね。あることはあるんです。
MC :ある!
ゲスト:うん。
MC :へえ。
ゲスト:砂浜でも砂を被っても砂を被っても耐えられるような植物ってやっぱりいて
MC :へええー。
ゲスト:うん。そういうのもいるんですけど、
MC :何ていう植物ですか?
ゲスト:あのー、ただハマヒルガオなんかは
MC :ハマヒルガオ。
ゲスト:うん。あれ蔓なんですけども
MC :はい。
ゲスト:まあ、砂に埋もれてもすぐその蔓を上の方に伸ばしてっていうことを繰り返すので
MC :へえー。
ゲスト:ちゃんと、あの、砂浜でもやれるやつがいます。
MC :岩場だったら結構いそうですよね。
ゲスト:そう、磯がいいですね。磯んとこがね。
MC :磯、磯ね。
ゲスト:はい。
MC :足切らないようにしなくちゃ。
ゲスト:そう、そう。ちゃあんと足を
MC :ええ。
ゲスト:保護しながら・・・
MC :はーい。それ、例えばどんなものがいるんですか?
ゲスト:うん。磯だと今回、あのー、載せてますけど
MC :はい。
ゲスト:あの、タイトゴメって黄色い花が咲くちっちゃーい植物があるんですけど
あれ良く磯の近くの、えー、あの、護岸工事されたり
MC :はい。
ゲスト:汐留に
MC :はい。
ゲスト:石垣作ったりしますけど、ああいうところに結構生えてたりしますよ。
MC :はあー。何かあれですね。先生の話聞いてると、
あの、ほんと自然界に生えてる植物の方がほんとは健全なんだろうけど、
人間が人工的に手を加えたところから生えてくるとまた、先生興奮しちゃうんですよね。
ゲスト:そうですよ。うまく使ってるなあって
MC :ですよね。
ゲスト:うん。
MC :そこですよね。たがら今護岸工事でちょっとすごく、あのー、
海の風景が損なわれるかなっと思ったんだけどそっから隙間植物くると逞しいっていう
ゲスト:うん。まあ、そういうのがいてくれればね
MC :いいですね。
ゲスト:まあ、ちゃんと風景になりますね。
MC :うーん。先生2か月に1回新しい発見ての最近でありました?
ゲスト:ありますね。やっぱりねー。
MC :何処でどんなシチュエーションで何が生えてたんですか?
ゲスト:いや、それはね。
MC :うん。
ゲスト:企業秘密ということでね。
MC :ええー。教えられない?
ゲスト:ふふふ。
MC :えー。
ゲスト:まだまだいっぱい出るんですけどね。
MC :ええ。
ゲスト:はあい。
MC :えー。
ゲスト:ただ、未だに見つからないのが
MC :はい。
ゲスト:夏だと皆さんも夏の花っつったらヒマワリじゃないですか。
MC :うん。
ゲスト:ヒマワリがね、ちゃあんと綺麗な形で隙間から咲いてんのまだ見たことがないんですよ。
ぜひ見つけて欲しいな。
MC :いやー、僕もないです。ヒマワリは、
ゲスト:うん。
MC :僕が去年までいた北海道はヒマワリ畑があって
ゲスト:あー、有名ですね。
MC :最高だったんですよ。
ゲスト:うん。
MC :で、ヒマワリは団体植物って僕の定義なんです。ヒマワリとか菜の花とかは
ゲスト:ああ、
MC :もう、だいたい
ゲスト:群れでいないと
MC :そう、群れてる植物で、隙間にいるのは気の毒なんだけど、
先生的にはそれが隙間にいたらたまらないっていう
ゲスト:うん。
MC :ふふふふふふ。
ゲスト:ヒマワリの仲間でちょっと小柄なコヒマワリってやつは、
MC :はい。
ゲスト:生えてるの何回か見たことがあって、
MC :へー。
ゲスト:ま、前回の本の方に載せてるんですよ。
MC :おお。
ゲスト:ほんとの、大っきい方のヒマワリはね、
MC :ほー。
ゲスト:まだないんですよね。
MC :僕も見たことないですね。
ゲスト:うん。
MC :それどういう条件で生えるんでしょうか。もしあるとしたら。
ゲスト:や、でも条件としてヒマワリの種、ちょっと大き目なんで、
隙間にポロッと入るのは難しいでしょうけど、ま、入りさえすれば後はね、
いけるはずなので、うん、絶対探す目が増えれば、誰か見つけると思うんですけどね。
MC :うん、確かにそうですね。
でもね先生ふと思ったんですけど2週に渡ってこんな話してるとね、
ラジオ聞いてるキッズが人工的に隙間に種を植える可能性があるわけですよ。
ゲスト:ありますね。
MC :ええ、それは、どうなんだろうか。この隙間植物としての定義としては。いいんですか?
ゲスト:えーまあ、自発的ではないけど
MC :ええ。
ゲスト:隙間に入れられた植物
MC :はい。
ゲスト:になりますよね。
MC :ええ。
ゲスト:うん、でも園芸とか
MC :ええ。
ゲスト:あのー、農業の世界ではやっぱり隙間ってそれなりに植物にとっていいところなので、
MC :ええ。
ゲスト:それを利用して畑を作るときとか、
あの、苗を作るときにわざと隙間を作っといてそこに植えるってやり方するんですね。
MC :あー。
ゲスト:うーん。
MC :じゃ、ラジオの前の君だけの隙間を見つけたら君だけの隙間植物を
ゲスト:うん。
MC :作ることは可能ですね。
ゲスト:そう、可能ですね。
MC :すごい、それで、また先生が写真とって本にしたら
その子は後からなんて言えばいいんだろうか。
ゲスト:何ていえばいいんでしょうね、
MC :僕がやりましたって言うべきか、先生が勝手にこれ虫が運んだって書いちゃったら
ゲスト:そうですね、まあ、ね、手足の数が6本はない虫が運んだんでしょうね。
MC :そういうことにしときますか。
ゲスト:はい。
MC :んふふふ。隙間は植物だけじゃなくてキノコなんかも隙間生えるって
ゲスト:はい。あの、キノコもやっぱり地下で暮らしてて
いつか地上に出てこないとキノコにならないじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:で、ちょうど周りが固められちゃっていてうまいこと
アスファルトとかコンクリートの割れ目があれば、そこからやっぱり出たいですよね。
MC :確かに、あの、山梨の方にいくとね
ゲスト:うん。
MC :あの、舞茸とかなめこなんかは
ゲスト:ああ、はい。
MC :人工的な木のところで植物そだててるじゃないですか。キノコ
ゲスト:うん、うん。
MC :あれこそほんと隙間的な生え方してません?
ゲスト:まあしますよね。
MC :うん。
ゲスト:やっぱりだって間が空いてるとこから
MC :はい。
ゲスト:やっぱりキノコの頭出した方が彼らにとってもね、
MC :そういうことですよね。
ゲスト:うん。
MC :それ、やっぱり環境としてやっぱりキノコも隙間にふさわしい、
ゲスト:そうですね。
MC :植物の一種ということ
ゲスト:ま、植物が、あの、隙間に生えるのとはちょっと違った、あの、光合成したい訳じゃなくて
MC :はい。
ゲスト:胞子を飛ばしたい
MC :ほー。
ゲスト:胞子を飛ばして増えたいからやっぱり隙間から出て外に傘を広げたい。
MC :目的が違うんですね。
ゲスト:うん、うん。
MC :そっか、隙間植物は光合成のために
ゲスト:うん。光浴びたいんだけど
MC :浴びたいけどキノコは胞子を飛ばしたい。
ゲスト:そう、そう、そう、そう。
MC :いやー、ちょっと、これって大ヒントだよ。自由研究の。みんな。
これ、もう、ちょっともうお仕舞?早いねー。そうか、そうか。
でもこれをきっかけにまた夏休み、みんなさぁ、
研究ちょっとモチベーション上がったんじゃないの?
いや、また先生遊びに来て下さいね。
ゲスト:はい。ありがとうございます。
MC :はい。今週の「サイコー」は東京大学大学院教授の塚谷裕一先生でした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「夏のスキマ植物 パート1」 ゲスト:塚谷裕一さん
2020/08/01 Sat 12:00 カテゴリ:植物MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は1月以来のご登場です。
東京大学大学院教授の塚谷裕一先生です。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :塚谷家先生は1964年神奈川県のお生まれで、しょ、えー、
御専門は葉っぱの発生分子遺伝学、えー、中公新書から「スキマの植物図鑑」
そして「スキマの植物の世界」などの本も出版されていまして、
これがねー、評判が大変らしいですね、反響が。
ゲスト:おかげ様で。
MC :おめでとうございます。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :いやー、でも、面白い本ですよね。
ゲスト:はい。
MC :前回もご紹介させていただいたんですけどー、色んな都会のコンクリートの割れ目
ゲスト:はい。
MC :あらゆるところから植物が、
ゲスト:そう、そう。
MC :しかもこれがまた可憐に咲いてるという。
ゲスト:はい。元気に咲いてます。
MC :はい。さあ、隙間植物これまず定義から教えて下さい。
ゲスト:ああ、はい。これはまあ、勝手に付けたものなんですけども、
MC :はい。
ゲスト:まあ、いまおっしゃっていただいたとおりで、まあ、コンクリート、
MC :はい。
ゲスト:あるいはアスファルトそれから石垣?そういったところの隙間から生えて、
まあ、ちゃんと花を咲かしてる。いうそういった植物をまとめて、まあ、隙間植物と呼んでいます。
MC :まあー、掃除当番のキッズだったら雑草としてね、ひっこ抜いちゃうかも知れないっていう、
ゲスト:そうですね。
MC :そういう植物なんですけど、先生はこういう植物に注目されて、本まで出しちゃったという。
ゲスト:はい。
MC :すごいですよねえ。さあ、えー、塚谷先生が好きな隙間植物っていうのは
実はみんな好きだって言うんですけれど。
ゲスト:はい。だって、あの、生えてるところが面白いですよね。
MC :はい。
ゲスト:あのー、普通に花壇とか、畑だとか
MC :はい。
ゲスト:そうきなら、まあ、全然驚きませんけれども、
MC :はい。
ゲスト:隙間植物はやっぱり思いもかけないとっからニュッと生えて、
で、花もピッタリちゃんと咲いてる、まあ、
そういったところがやっぱり楽しいですね。見ててね。
MC :今がもうシーズンでよすね。
ゲスト:フルシーズン
MC :フルシーズンですよね。
ゲスト:はい。
MC :もー、だからみんなもう、あのー、お家の周辺でもいいし、
学校の校庭の周辺でもいいですけど、もうあちこちに実は隙間植物が生えてて、
ちょうど今お花の見ごろという
ゲスト:はい。
MC :そういうタイミングですかね。
ゲスト:そうですね。色んな種類見られますよね。
MC :はい。さあ、で、変わったところではね、配電盤の囲いっていうのがあるんですけれど
ゲスト:はい。あのー、
MC :そう、そう、そう。
ゲスト:うん、町を歩いてると
MC :はい。
ゲスト:ところどころ配電盤がありますよね。
MC :はい。
ゲスト:で、囲いがあって普通は人が手がされないようになっているんですけど、
MC :はい。
ゲスト:そこに結構穴が開いたり、あのー、やっぱり隙間がある。
MC :はい。
ゲスト:そっからあの、蔓がでているっていう
MC :ふん。
ゲスト:ケースがあって、まあ、今回、あのー、本の方に載せてるのは昼顔なんですけども、
MC :はい。
ゲスト:あれ蔓植物なんで、
MC :はい。
ゲスト:そういったちょっとした穴があれば、ヒュルヒュルってそっから抜け出してくる。
すごく、あのー、実は誰もいじらないし、日当たりはいいし、
結構いいところだと思うんですね。
MC :ところで
ゲスト:いいとこを見つけたなと。
MC :配電盤というのはね、実はキッズ達はよくわかんないと思うんですよ。
ゲスト:ああ、はい。
MC :これが配電盤なのか。
ゲスト:ふん、ふん。
MC :いわゆる金属で囲われた箱ですよね。
ゲスト:そう、そう、そう、そう。
MC :で、金属で囲われた箱の隙間から
ゲスト:うん。
MC :昼顔の花が咲いちゃってる写真が載ってるんですけど
ゲスト:そう、そう。
MC :そもそもなぜこの配電盤の中にね
ゲスト:うん。
MC :植物が生える仕組みがあるんですかね?
ゲスト:多分配電盤を、えー、道路沿いに設置する時に、
MC :はい。
ゲスト:やっぱり配電盤の箱があるでしょ。
MC :はい。
ゲスト:箱と道路間はやっぱり隙間がありますよね。
多分そっからまず生えて、で、そっからいきなり生えても蔓、
面倒くさいので多分中に入ったんだと思うんですね。
MC :配電盤の中に入っちゃう。
ゲスト:そう、そう、そう。うん、箱の中に入っちゃって
MC :うん。
ゲスト:でもちょうど良いことに、えーっと、手入れができるように、あと、通気のために
MC :はい。
ゲスト:沢山隙間があって光が中にたぶん入るんだと思うんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、昼顔はその光を受けながら中で茂って所々で自分の好きなとこへ
外に顔を出すってことやってんじゃないですかね。
MC :今ね、キッズ達は小学校低学年だったら、朝顔をさぁ、持ち帰ると思うんですよ。
ゲスト:うん。
MC :夏休み入る時に。
ゲスト:うん。
MC :ていうことは昼顔も朝顔も蔓科の植物だから、場合によっては蔓を
ゲスト:うん。
MC :当たり前に伸ばさないで
ゲスト:うん。
MC :ちょっと変わった
ゲスト:あー、そうそう。変な所にちょっと
MC :育て方をすると
ゲスト:入れてみると楽しいかも
MC :楽しいですね。
ゲスト:はい。
MC :例えばなんだろう?ベランダの
ゲスト:うん。
MC :柵とか、
ゲスト:うん。
MC :まず普通に
ゲスト:普通に生えますよね。うん。
MC :で、極端な話、だから配電盤も生えるし
ゲスト:うーん。
MC :あとはー、
ゲスト:とか下手をするとスダレみたいなもんに絡ませるとうまくしたら
スダレの間を、こう、縫って蔓が、
MC :おーー。
ゲスト:いくかもしれないですね。
MC :上へ上へとね。
ゲスト:うん。
MC :いいですね。
ゲスト:うん。
MC :なんか例えばじゃあ、もう皆がじゃあ使わなくなったふるーい自転車とか
ゲスト:あー、そうそうそうそうそう。
MC :その下に朝顔の鉢
ゲスト:スポークのところ
MC :そう、ははははは。
ゲスト:うん、うん。
MC :あー、いいですね。こういうのが配電盤の写真から派生して
ゲスト:はい。
MC :皆もイメージして隙間植物を育てる楽しみってのもあるかもしれない。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。なるほど。それから、そう屋根の隙間っていう写真があって
ゲスト:そうなんです。
MC :屋根瓦からニョキニョキと緑が出てるっていう
ゲスト:はい。
MC :最近瓦の屋根も少なくなりましたけれど、
ゲスト:うん。でも
MC :これはすごい写真だな。
ゲスト:そうそう。お寺さんとかね
MC :はい。
ゲスト:あの、公園にいったりするとあの、瓦屋根の建物があったりするんで
MC :はい。
ゲスト:そういうところで見てると結構あるんですよこれが。
MC :うーん。
ゲスト:あの、東京都の都内でもね、あのー、割と古くからあって、
でもあんまり手入れてないところだと割と植物たちがハッピーにそこで暮らしてます。
MC :変な話でもー、土がないのに生えていいのって思うんですよ。
なんで瓦から土?土から栄養取るっていうじゃないですか
ゲスト:はい。
MC :だけど土がないのになんで生えるんですか?
ゲスト:手入れが悪いとちゃんと隙間に雨と一緒に土埃ふってきますし、
MC :へー。
ゲスト:周りに大きい木があれば、
MC :はい。
ゲスト:落ち葉も溜まるじゃないですか。特に雨樋なんかよく溜まる。
MC :あー。
ゲスト:で、そういうところをうまく使って根を生やしてるんです。
MC :いわゆる土壌ができるってことなんですね。
ゲスト:ちゃんとできてるんですよ。
MC :へー、あ、そうか、じゃ、古い神社とか
ゲスト:うん。
MC :手入れされてない古い建物
ゲスト:うん。
MC :たぶん、みんなの家の周辺にあると思うけれど朝のラジオ体操の会場なんかいいかもしれないですね。
ゲスト:ああー、そういうのもありそうですね。
MC :うーん。えー、先生のお気に入りはどこですか。こんなところから生えたっていう
ゲスト:ええっとね、やっぱり変なのは
MC :ええ。
ゲスト:隙間ってやっぱり足元の歩いてるとこに対外多いじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:なんですけど時々見てると、うーんと、膝ぐらいの高さの隙間に生えてるものって時々見つける
MC :高いところ
ゲスト:そうです、そうです。こんな高いところまでよく来たねっていうのは時々あるとやっぱり楽しいですね。
MC :それどうしてそんな高いところに来たかっていう
ゲスト:うん。
MC :風がやっぱり巻き上げたり
ゲスト:うーん。一つは、うーん、風とか雨とかで、種が行ったっというのもあると思いますけど、
時々あるのはやっぱり虫が運んだげたっていうケースでしょうね。
MC :いやー、これがいいですね。
ゲスト:うん。
MC :虫がね
ゲスト:うん。
MC :そうだ。あの、前、あのサイエンスコーチャーの方が、鳥とか虫?
ゲスト:うん。
MC :って鳥は赤い物運ぶ習性があるって話をされて
ゲスト:はい、そういうの好きですからね。
MC :だから、赤い種を持つ植物ってのは
ゲスト:うん。
MC :あちこちに繁殖するんだよっていう話を
ゲスト:うん。うん。
MC :虫はどういうものがすきなんですかね?
ゲスト:虫はねやっぱり種の周りに何か食べるものがついてると
それが欲しいもんですから集めるんですよ。
MC :じゃ、スイカの種なんかおいしいとこで
ゲスト:スイカの種はたぶんあんまりスイカの実の方が無くなっちゃえばダメなんですけども、
あのー、仏の座とかすみれとか割と小さい植物で小さい種つけるやつって種に、
あのー、餌がついてるんで
MC :はい。
ゲスト:蟻はその餌が欲しいもんだから
MC :ええ。
ゲスト:例えばありですけどね、あのその餌んとこ欲しいけどすぐに種とは切り離せないので、
MC :はい。
ゲスト:とりあえず家に持ってというか巣に持っていく
MC :蟻の巣に持って行って、
ゲスト:そう、そう、そう。
MC :で、おいしいところ食べて
ゲスト:種いらないから
MC :はい。
ゲスト:その辺に捨てると、そんときに、まあ、蟻の巣が高い所にあったり
MC :はい。
ゲスト:まあ、割と蟻の巣ってブロック塀の割と案外あれですよね
MC :はい。
ゲスト:地面から離れたところにも巣穴作ったりするじゃないですか
MC :はい。
ゲスト:そういうところでやられるとちょうどそこにすぽっと種が
はまったりするっていうようなことがありますよね。
MC :ちょっと、ロマンがありますね。
ゲスト:うん。
MC :じゃ、例えば僕らの例えばもう、宇宙人からするとね、人間の髪の毛が大好物だと。
ゲスト:うん。
MC :それで、人間の体は興味ないんだけれど
髪の毛を食べるために宇宙人に僕ら一旦拉致されちゃうと。
ゲスト:うん。
MC :で、髪の毛だけ食べられて、でも、いつの間にか僕ら宇宙に連れて行かれてるって感じですか。
ゲスト:まあ、そんな感じですね。
MC :無理やり#
ゲスト:髪の毛無くなっちゃったけど、まあ、あのー、他の星に行けたって#
MC :まあ、そういうことですよね。
ゲスト:うん。そうです。
MC :ハゲても他の星に行けてラッキーじゃない?
ゲスト:まあ、考え方#
MC :はぁー。楽しい、ちょっと夏休みを前にしてちょっとハッピーなお話を、
また来週もお話伺いたいと思います。
今週の「サイコー」は東京大学大学院教授の塚谷裕一先生でした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「キッズからの質問特集 パート2」 ゲスト:寺門和夫さん
2020/07/01 Wed 12:00 カテゴリ:その他MC :さ、今週もおなじみの科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。
こんにちはー。
ゲスト:こんにちは。
MC :すーごくね、あのこの番組もう8年近くやってるんだけれどー、
ゲスト:はい。
MC :僕もー聞きたかった質問がきてる。
ゲスト:はい。
MC :八王子のせいやくんから。小学校5年生。ありがとう。
きりんは高い所にある木の葉を食べているうちに
首が少しずつ長くなって今のようになったんですよねー。
これは本当なんですかー?
もしもそうだとしたら、僕たち人間はこの先どんな進化を遂げると思いますか?という、
前段のきりんの首が何故長いのか、これはいつか聞きたいと思っていたんですけれど、
ゲスト:そうですねー。
MC :はい。
ゲスト:これ、基本的なあのー言ってみればそのーえーと遺伝とか進化のね、
あの謎のひとつですね。それであのー、きりんの首は長いんですけども、
あのーそのー首の骨の数はですね、他の動物とみんな同じなんですね。
MC :ふーん、あっ、首の骨の数?
ゲスト:うん、そうなんです。
MC :えっ!
ゲスト:そうなんです。きりんの首は骨の数がいっぱいあってー長くなってるわけじゃなくてー、
ひとつひとつの骨の長さが長くなってる。
MC :人間も同じですか?
ゲスト:えー、そうです。脊椎動物特にこの哺乳類とかね
そのへんで他の動物とはまったく同じなんです。
MC :ほぉー。
ゲスト:で、じゃなんできりんだけがああいう風になったのかっていうことが
ひとつの大きな謎になっているわけですね。
MC :え。その葉っぱの高い・・・
ゲスト:そうです。あのーそれでまあ、いわゆる古典的なっていうか
昔からのダーウィンのあのー進化論っていうのはまああのー適者生存とか、
あのーいうことで言うと、そのーだんだん高い所の葉っぱを食べられるような
きりんが生き残って、えーと結局首の長いきりんだけが残って今、
えー今のきりんはすべて首が長いと。
つまりだんだんその高い所の葉っぱを食べているうちに、
えー首が長くなってきたというのが基本的な進化論の考え方なんですね。
MC :はい。
ゲスト:でー、ま、確かにあのーなんかそういったきっかけあったでしょうね。
おそらくむかーしはあのーきりんと他のあのーまあ野生の鹿とかね、
いっしょに草食をしている動物たちってのはー
アフリカでーあのやっぱり地上にはえてる草食べてたのかもしれませんね。
そのうち多分餌の取り合いになって、
あのーきりんの祖先はあのー地上の葉っぱなかなか食べられなくなって
それで高い所の木の葉っぱ食べるようになったっていうことはあったかもしれませんね。
ただ一番あのー今その進化論で問題になってるのはー、えーとですねー、
あのー難しい言葉でいうと移行化石っていうんですけど、
つまり首の短いきりんと、の祖先と、
それから今の首の長いあのーきりんの間の中間のですね、
化石がないんですね。
MC :ほーぉ。
ゲスト:つまり首の長さが中間ぐらいの
MC :ほほほ。
ゲスト:化石がない。でこれはあの
MC :進化の過程ってのがわからない。
ゲスト:そうです、そうなんです。でこれは実は他の進化でもいろいろあってですねー、
あのー祖先から形が変わってくるときにその中間的な形態の実は
あのー化石って実はあまり見つかってないんですね。で、これがひとつの謎でー、
そうするともしかしたら進化ってのはそのーすこーしずつ
あの例えば首が長くなるとかー、えーいう事がですね、
あるいはその脳が大きくなるとかっていうのが、
ちょっとずつ変化していってそれで今の例えばきりんの首が
できたという風に考えるのか、それとも何かあるきっかけがあってー、
割と短い期間に急に首が長くなったのか、もしれないと。
考える人も実はいるんですよ。
MC :えーー、急に首が、
ゲスト:そうです、あのー
MC :なんでだろう。
ゲスト:つまりそれはあの一つの突然変異っていうか、
MC :へぇーー。
ゲスト:大きくそのある事で変わった時の遺伝子がそのままあのー広い集団に伝わって、
えーとードラスティックに首の短い仲間から首の長い仲間にそのーま、
言ってみれば勢力が変わってしまったっていう考え方ですね。
MC :さ、質問の後半だけど、僕たち人間はこの先どんな進化をとげるか。
ゲスト:そうですね。
MC :このあたりどうですか?
ゲスト:ですから、あのーその考え方でいくとね、
例えば人間も少ーしずつ進化していくのかもしれませんね。
でも何か例えばそのー環境が変わったりしてー
例えばその地球がものすごく熱くなっちゃったとかですね、
あるいは何かえー大きなあのー別な原因で自分達が
あの今の環境ではない形であのー生活しなければならないような状況になった時に、
え、それに対応する時にですね、あのーある程度ゆっくり対応するんじゃなくて、
なんかえー別な能力を持った人たちが突然出現して
その人たちによって今後の地球が担われていくみたいな、
MC :えーー。
ゲスト:そんな風になるかもしれない。
MC :科学ジャーナリストの、さすが寺門さん。別の、別次元の人だ。
ゲスト:えー、そうです、えー、あのそういう事です。ま、もちろん同じ人間ですよ。
それから同じ遺伝子は持ってるんだけれども、
遺伝子の発現の仕方がーあの変わるわけですね、あのー進化っていうのはね。
ですからその時にえーと、少ーしずつ例えばあのー背が高くなるとかいうことじゃなくてー
急に背が高くなった人たちがいっぱいでてくるとかですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:うん。そういったこともあの過去の、ですからその生物のあの進化、
それから化石の分析などから見るとね、
あのそういったことも実は考えられるわけですね。
MC :江東区のまりえちゃん、中学校1年生、女の子。犬は頭がいいといいますよね。
でもうちの犬はそうでもないです。はっはっは。
お手やおすわりを教えようと何度が挑戦したけれど、覚えませんでした。
そこで質問なんですけれど、人間以外で頭のいい動物はなんですか?
まりえちゃんの家のワンちゃんがまずお手、おすわりを覚えないと、これはそういうー
ゲスト:あの、そいでねー、僕はねー、あのーそうじゃないと思ってるんです。
MC :違う。
ゲスト:あのー、まりえちゃんの家の犬もね、
MC :はい。
ゲスト:あの多分頭いいんだと思うんです。
MC :あっそうですか。
ゲスト:そいでね、おすわりをするとかお手をするっていうのはー、
あのー訓練によって実はあの犬たちはしてるんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですからそのー、あの訓練の仕方があのー上手だったりうまくいくとー、
あのそういう風にしますけれども、
それはあのー頭の良さとはあまり関係のないことです。
MC :ん、ん、ほほ。あっそうですか。じゃこれ気にしなくていいんですね。
ゲスト:あ、そうですね。あの多分ねー、ですからあのー
MC :えっへっへ。
ゲスト:まりえちゃんの家のワンちゃんもね、
おそらくあのー例えばお腹がすいたなーとかね、
MC :はい。
ゲスト:散歩に行きたいよとか訴えたりして、
MC :はい。
ゲスト:多分ね、家族の人とコミュニケーションとってると思うんですよ。
MC :はー。
ゲスト:そういった意味ではね、やっぱりそのーそれなりにやっぱり知能があって、
あのー家族の一員として生活してる、
ですからそのーお手をしないから頭が悪いっていうふうには考えないで欲しいですね。
MC :はい。まりえちゃん、まあ、わかりましたか?
そこで質問、人間以外で頭のいい動物はなんですか?
ゲスト:はい。あのー哺乳類はですねー基本的にみんな頭いいですね。
MC :さっきのきりんも頭いいですか?
ゲスト:うん、そうですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:それから、もちろんあのーペットになっている犬とか猫は
やっぱりあのー家族との交流ができますよね。
MC :猫はでもなつかないっていいません?
ゲスト:でもちゃんとコミュニケーションとれますよ。
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:例えばうちの猫そうですよ、ちゃんとわかりますよ。
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:うんうんうん。
MC :寺門さんと8年お付き合いしてるけど、
愛猫家だって初めて知りましたね。
ゲスト:ふっふっふ。
MC :猫飼ってらっしゃる。
ゲスト:今、そうですね。
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:昔は犬も飼ってましたね。もちろん、もちろん。
MC :あっ、そうですか。いやいや。
ゲスト:ふふふ。それからね、例えばチンパンジーとかサルの仲間、
MC :あー、
ゲスト:これは当然やっぱりあのー知能はかなり発達してますね。
MC :チンパンジーはやっぱり頭いい。
ゲスト:そうですね、はい。あのー、まー、文字がある程度認識できたりとか、
計算ができたりとか、人間の言葉がわかるという、
ま、そういった実験の例まであるくらいで、
やはりあのーかなりあのー知能が高いのは事実だと思いますね。
MC :ふーん。イルカ頭いいっていいますね。
ゲスト:そうですね。あのーまあそういうふうにあのーなんていうんでしょ、
イルカも哺乳類ですね。
MC :そうか、あっそうだ、くじらー
ゲスト:そうです。で、哺乳類の仲間は基本的にやっぱりあのーいろんな声だとかジェスチャーで、
仲間で通信してることもあります。
だからあのーイルカなんかは人間とコミュニケーションできるっていいますけれども、
確かにイルカが人間のこと自分の仲間だとあの認識してくれれば、
何らかの形でこう会話っていうんですかね、あの心通じ合うことも多分出来ると思います。
MC :ほぉー。
ゲスト:うん。ですからそのーかなりやっぱりあのーま、
特に哺乳動物って言ってるものについて言うと、
多分あのーみんな知能はそれなりに高いものがあるんじゃないかと思いますね。うん。
MC :じゃあ、ワンちゃん、ねこちゃん、家庭でペットとして飼われている哺乳類は、
ま、かしこいといえばかしこいわけですねー。
ゲスト:みな、かしこいですよ、うん。
MC :昔、なんかチンパンジーでオリバーくんっていたじゃないですか。
あの子は天才だったんですか?
ゲスト:えーと、よくわからないですねー。
MC :あ、
ゲスト:もう昔の話で、僕も当時不思議だなぁーって見てました。
MC :なんか、僕あれはもうオカルトブームの中で、UFOとか
ゲスト:そうです、そうです。えー、そうです、そうです。
MC :天才のなんか超能力とかね、
ゲスト:えー、
MC :あと、オリバーくんとかねー、
ゲスト:そうです、そうです。えー。
MC :今にしてみるとあれはあれで真偽はどうだったのかなと思うんですけれど。
ゲスト:あのー、僕も知りたいですねー。
MC :あっははははは。
ゲスト:あの頃僕もねー、そこまで調べるっていうことが出来なかったんですけど、
MC :えー。
ゲスト:不思議だなぁーと思いながらテレビ見てましたね。
MC :はーい。いやー、子供の頃のそういう思い出って
大人になってからなんかちょっともう1回検証したいなと思いましたけれど。
ゲスト:そうですね。
MC :いやー、質問有難うございました。いやー、新年度ですね。
こうやってまたキッズの質問でえー新年度幕開けしました。
また、あの質問ありましたら、寺門さん来てくださいね。
ゲスト:はい、わかりました。
MC :はい、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。有難うございました。
ゲスト:どうも。失礼しました。 -
「キッズからの質問特集 パート1」 ゲスト:寺門和夫さん
2020/07/01 Wed 12:00 カテゴリ:その他MC :さ、今週のサイコーはおなじみ科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。
こんにちは!
ゲスト:どうも。
MC :寺門さんですから、キッズからの質問ですよ。
ゲスト:はい。
MC :いきますよ。面白い質問なんだ。埼玉県のななえちゃん、小学校6年生。
少し前に小惑星イトカワの自転がわずかずつ早まっているという記事を見ました。
僕、知らなかったなぁー。
そこで思ったんですが、地球にも同じ事が起こるんじゃないかということです。
もしそうなったら一日が短くなったりするんでしょうか、と。
今僕ら24時間で生きてますけれど。
ゲスト:そうですね。
MC :20時間になったりとか、
ゲスト:うーん、そういうことですね。
MC :10時間になっちゃうんですか?
ゲスト:えーとですね、僕もこのニュースあまり知らなかったんですね。
それで調べたんですけど、確かに観測するとすこーしあのー、
一日の長さが短くなってる、ということをあの報告があったようなんですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:で、あのーもうご存知だと思いますけど、
あのイトカワというのは、細長い形してるんですね。
MC :はい。
ゲスト:まあ、らっこの形に例えられたり、それからピーナッツの、
あのあーいうなんていうんですか、細長い形ですね。
MC :ちっちゃいのね、スケートリンクぐらいのかたち
ゲスト:そうですね、ちっちゃいの。そう、そう、そう。
ですから言ってみればいびつな形なので、
あのーまあ言ってみれば不自然な回転をしてるので、
まああのーそういう風に自転の速度がえーと
短くなるってこともあるのかなという感じなんですけど、
MC :はーはーはー。
ゲスト:ただしこれ実はね一般的に言うとすごく不思議なことでね、
MC :え、
ゲスト:あのー太陽系のいろんな天体っていうのは他の星からもー、
引力の影響を受けてー、えー運動してるんですね。
そうするとですねー、一般的にはだんだんだんだん回転がゆるくなってくる、
遅くなってくるっていうのが普通なんですね。
で、例えばあのー地球もですね、あのーまあ今から40数億年前にあのー
えー地球とそれからお月さまですね、これがまああのー出来たわけですけども、
その頃っていうのはえーと月というのは地球のすぐ近くにあってー、
地球もものすごい速さで回転してて、
あの一日のスピードが5時間とか6時間ぐらいだったと言われてるんです。
MC :えっ、えっ、地球?一日5時間か6時間!
ゲスト:そうです。ものすごいスピードで通ってましたね。
MC :朝来て、夜来て、朝来て、夜来て。すご。
ゲスト:え、それがだんだんとあの、まあ太陽とか月の引力の影響でー、
えーとーまあ回転がゆるくなって、それからあの月は地球からだんだん離れてって、
それで今のあの地球と月の距離とそれから地球の自転の
24時間というのになってるわけですね。
MC :何十億年も前は?
ゲスト:そうです。だからだんだんゆっくりとなってくるのが普通なんですね。
MC :あ、いやー、じゃまだゆっくりになるかもしれないってことですね。
ゲスト:あ、今もう、あのごく僅かですけども測ってみるとー長くなってるはずですね。
MC :4年に1度2月29日までのうるう年ってあるじゃないですか。
ゲスト:はい、はい。ありますね。
MC :何年かにい、1回ね、うるう秒があるよって新聞やテレビに載るわけですよ。
それがそういうこうあれですか?ちょっとこう
ゲスト:そうです、まあ厳密24時間ではなくて、あの端数がでますね。
それを調整してるってことですね。ただし、あのー国立天文台なんかによると、
あの地球のあの自転の速度をものすごく正確に測ると、
あのー多少速まったり緩まったりしてる、それから例えばあのーえーあれですよね、
あのー地震、巨大な地震が起こるとちょっとだけスピードが落ちたりとか、
いろんな事があるので、あのずぅーっと一定のスピードで
あのー緩やかになってるってわけではなくて、
ま、それなりにあのー僅かずつだけれども速くなったり遅くなったりしながら、
大きな長い時の流れでいうとー、だんだんゆっくりしてるというのが
まあ天体の動きというふうに考えていいんじゃないんでしょうかね。
MC :そうですか。いや、ちょっとでも、すごい。
ゲスト:うん、ですからまああのーおそらくあの地球の1日の長さっていうのは、
えーとまあごく長い時間でみるとあの速まるっていうよりは
あのーむしろゆっくりになって1日の長さは少しずつ伸びてるというふうに
考えていいんじゃないかと思いますね。
MC :僕らは24時間ていうのは常識として生活してるんでこれがちょうどいいと思ってたけど、
ゲスト:そうですね。
MC :1日24時間で足りないよ!っていう声聞くと、
ちょっとゆっくりになると嬉しいかもしれないですけど。
ゲスト:あはは、そうかもしれませんね。
MC :でも1日が5時間、6時間時代だったら、
学校なんで成立しなかったかもしれないですね。あっはっはっはっは。
ゲスト:大変ですね。そのころ生きてたらね。
え、今人間に限らずね、地球上の生物ってみんなね、
あのいわゆるバイオリズムってありますね、
MC :はーい。
ゲスト:体内時計、それが基本的にやっぱり24時間なんですよ。
MC :はい、そうですね。
ゲスト:だから、まあここんとこずぅーっと生物はそういうふうにして
進化してきたわけですけど、
これがやっぱり1日の長さが5時間とか6時間の世界で生物が生きてたら、
これ大変なことですよね。やっぱりね。
MC :そうですよねー。こういう話はいいですね。
あのいやーななえちゃんの質問から膨らんだなー。
なんか24時間、いやー。さあ、千葉県流山市のかずまくん、中学校1年生の男の子。
ビッグバンによって宇宙は生まれたといいますが、
それよりも前この世はどんな感じだったのですか。
ビッグバン以外に宇宙誕生の説があったら是非聞きたいです。
だって、すべてはビッグバンがスタートだったんですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :その前の話を知りたがってる、かずまくん。
ゲスト:そうです、あのねー。あのかずまくんの質問すごいいい質問ですよ。
MC :ね!
ゲスト:うん。今に、今のその科学者がね一番解明したいと思ってる謎なんですね、これがね。
MC :ちなみにビッグバンは何年前ですか?
ゲスト:えーとー、正確な観測が出来て今迄137億年って言われてたのが、
正確に測って約1億年延びてですね、
今は今から138億年ぐらい前に起こった事件だというふうに言われてますね。
MC :はい。で、じゃあ139億年ぐらい前の話を寺門さんはご存じなのでしょうか?
ゲスト:えーとつまり、科学者はそれを調べようとしているんですね。
で、ビッグバンが起こったのがまあ138億年、
でその直前にいろんなことが起こったっていうところまではわかっているわけですね。
MC :何が起きたんですか。
ゲスト:で、そのビッグバンっていうのはですね、宇宙の大爆発で、
あのちっちゃな火の玉が爆発してですね、あのそいで膨らんで今の宇宙になった、
それまでに138億年かかっているわけですけども、
実はそのビッグバンが起こる前についてもー、えー、
こんなことがあったんじゃないかっていうのは
もうこれはあのー望遠鏡とかで調べること出来ないのでー、
あの理論で研究するしかないんですけども、あのわかってることがあるんですね。
それは、あのインフレーション宇宙という時代があったというふうに言われているわけです。
MC :インフレーション宇宙?えーっ、
ゲスト:あのインフレ、インフレってよく言いますよね。
MC :経済用語みたいですねー。
ゲスト:そうそうそう、そこから
MC :なんだかなぁー。
ゲスト:そこからきてるんです。
MC :えーえー。
ゲスト:で、経済用語でインフレっていうのは物価の価値が、
値段がどんどんどんどんこうえー高くなっていく、
まあそれと同じでこう膨張していくっていう意味ですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:で、つまりあのーえービッグバンの前にですね、
宇宙の本当の種が産まれてそれは小さな小さな種だったんだけれども、
それがあの極端に膨らんでいく、あのインフレ状態になっていく、
そういったあの段階があって、その段階がある段階まできたところでビッグバンが
起こったというふうに言われているんですね。
MC :ほ。ほっほ。いわゆる破裂する寸前の空気
ゲスト:そうです。
MC :が、ぷーぷー膨らんで、もう膨張していくイメージ?
ゲスト:そう、まあそういうふうに考えていただいていいですね。そうです、そうです。
MC :インフレーション宇宙時代
ゲスト:で、極端に膨らんでそこで爆発が起こってそこでビッグバンが
あの始まったというふうに考えられているわけですね。
MC :そもそも僕はね、宇宙のその空間みたいなものって、
昔は何だったのかなと思ってるんです。
ゲスト:そこがね、あのー誰も今わからないところです。
MC :あっ、
ゲスト:つまり我々はーあの今いる宇宙にしかいないわけですね。
MC :はい。
ゲスト:で、その隣の宇宙があるといっても、観測の手段がない、調べる手段がない、
つまりあのー我々の宇宙の中でしか通信することができないわけですね。
で、科学者によっては、あのーここでも何度かお話したことありますけど、
マルチバース宇宙っていって、別などっかに別な宇宙があるんじゃないか、
いう考え方もあるんですけども、その宇宙があったとしても、
我々はその宇宙を知ることができない、
MC :うん。
ゲスト:ということで、これはまあほんとにあのー理論物理学の世界なんですね。
ただそこではいろんな可能性があるわけですけれども、
あのーただ要するにあのー我々が感覚で知ることが出来るのは
今のこの宇宙しかないということなので
あとはそのーまあ数式だとか理論で考えていくしかない世界なんですね。
ただし、あのー宇宙ってのは今我々が住んでる宇宙だけではなくて、
その他にも宇宙はいっぱいあるんじゃないかというのが
今の大きな考え方として出て来てますね。
MC :やー、なるほどー。
ゲスト:そういった意味ではね、やっぱり科学の進歩ってすごいことでー、
あのビッグバンの前の宇宙まで大体ねほぼ確からしいところまできてるんですね。
MC :そのやっぱり説得力というかね、それは大事ですよね。
ゲスト:そうですね。あの調べていかないといけないですね。
MC :こういう話、そうですよねー。
神話にはないやっぱりこう奥行きがある科学やっぱりいいね!
えー、いやー、キッズたちの質問からおじさんたち熱くなったわ。
もう時間だー、次週もよろしくお願いします。
ゲスト:はい、わかりました。
MC :寺門さんでした。 -
「花粉症の科学 パート2」 ゲスト:石井保之さん
2020/03/01 Sun 12:00 カテゴリ:人体MC :今週のサイエンスコーチャー「サイコー」もですね、前回に続きまして、
理化学研究所の石井保之さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :石井さんは、 独立行政法人理化学研究所統合生命医科学研究センターの
チームリーダーでらっしゃいます。
えー、岩波科学ライブラリーから「花粉症のワクチンをつくる!」という本も
出版されているんですけれど、前回の話面白かった。
うーん、で、いよいよじゃ、その本のタイトル
「花粉症のワクチンをつくる!」そこなんですよ。
ゲスト:そうですね。
MC :うん。 万策尽きてるんですよ、ほんと僕なんかは。
あらゆることやってるんだけれど、目はかゆい、鼻水は出る、
ゲスト:はい。
MC :体温も上がっちゃう、喉も痛くなる。ほんと、色んなことやってますよ。
だからもう、か、花粉のために、僕、何十万使ったか分かりませんよ。
だけど、なかなか決定打が出ないわけじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :それをでもご専門に研究されてらっしゃるんですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:で、私の研究では、
MC :ええ。
ゲスト:そのアレルギーの原因物質を
MC :はい。
ゲスト:あの、根本的に、
MC :はい。
ゲスト:えー、排除して、えー、ま、いわゆるこう、治療効果をですね
MC :はい。
ゲスト:長くこう、おー、出したいと
MC :はい。
ゲスト:いうふうに思って研究してますので
MC :はい。
ゲスト:ま、今の医薬品ではない、もう全く新しい考え方で、
MC :ええ。
ゲスト:えー、薬を作ろうと思っていて、
MC :ええ。
ゲスト:一つはワクチンて考え方もあって、
MC :はい。
ゲスト:えー、やってます。
MC :そのワクチン
ゲスト:はい。
MC :ワクチンというのは、
ゲスト:はい。
MC :ウィルスに対するワクチンですよね。
ゲスト:で、ワクチンと聞きますとみなさん、あの、インフルエンザであるとか
MC :うん、ワ、はい。
ゲスト:いろんな麻疹であるとか
MC :はい。
ゲスト:ああいうワクチンがあって、あれは元々、その、か、免疫を高めておいて
MC :はい。
ゲスト:えー、そういうウィルスに対する体が、を、ま、作っておくと
MC :うん、うん。
ゲスト:いう考え方ですけど
MC :そ、インフルエンザのワクチンなんかね
ゲスト:はい。
MC :インフルエンザのなんか成分を
ゲスト:はい。
MC :体に入れるっていいますもんね。
ゲスト:そうですね。
MC :うん。
ゲスト:で、成分を入れるっていう点では、
MC :ええ。
ゲスト:花粉症のワクチンも花粉症の成分入れるんですけど、
MC :へえー。
ゲスト:こっちは、免疫を下げなくちゃいけないので
MC :はい。
ゲスト:免疫を下げるワクチンを作ってます。
MC :ほー。
ゲスト:つまり花粉症の成分、原因の成分が体に入っても
MC :うん。
ゲスト:免疫が高まらないように
MC :はい。
ゲスト:IgEってその、原因の
MC :はい。
ゲスト:抗体が上昇しないようにするワクチンを作っていて、で、それは本来、
体の中にあるシステムなので、それを誘導するような化合物を今、
あのー、研究してます。
MC :ま、先週のお話だと
ゲスト:はい。
MC :僕たちの体の中には、IgE抗体というそういう抗体があって、
花粉症の方はそれが過剰に反応してしまう為に、
体に不調をきたすという話だったんですよね。
ゲスト:はい。
MC :で、今のワクチンだと、そのIgE抗体の過剰反応を抑えるという話でよろしいんですか?
ゲスト:はい。ワクチンの場合ですと
MC :ええ。
ゲスト:IgE自体の、おー、産生を抑制したり、
MC :はい。
ゲスト:えー、IgEの働きを、こう、マスクしてしまうというんですかね
MC :ほー。
ゲスト:いうような方法が、あの、考えられていて
MC :はい。
ゲスト:えー、我々今研究している方法ですと、
MC :はい。
ゲスト:そのIgEの産生を、えー、抑制すると、体の中のIgEをですね、
特に花粉症に反応するIgEだけ、抑制すると
MC :ほー。
ゲスト:いう免疫関与っていう方法なんですけど、ちょっと難しい言葉ですけども
MC :IgEの
ゲスト:はい。
MC :産生というこの産生は
ゲスト:はい。
MC :どういう意味ですか?
ゲスト:あ、この産性は分泌ってことなんですけど
MC :分泌
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:IgEを、あのー、生産している
MC :ええ。
ゲスト:体の細胞があって
MC :はい。
ゲスト:Bリンパ球ってやつで
MC :はい。
ゲスト:これが、あのー、問題なんですけども
MC :ええ。
ゲスト:このBリンパ球は、Tリンパ球っていうもっとちょっと難しい
MC :はい。
ゲスト:免疫の細胞があって
MC :はい。
ゲスト:その働きでIgEが出るんですけど
MC :はい。
ゲスト:そのTリンパ球の働きを、えー、抑制してあげて
MC :なるほど。
ゲスト:で、それをスギ花粉に特異的に抑制するので、
MC :うん。
ゲスト:えー、他の免疫系は抑制されない
MC :うん。
ゲスト:えー、非常に安全なワクチンになるという風に考えてます。
MC :Tリンパ球という体の中にある、えー、細胞を抑える
ゲスト:はい。
MC :でもそれを抑えると、その他の、えー、
外からのばい菌なんかに対する耐性は守られるんですね。ちゃんと
ゲスト:そうなんです。
MC :うん。
ゲスト:すべてのTリンパ球の働きを抑制するのは、例えばステロイドっていう
MC :うん、うん。
ゲスト:お薬があって、
MC :はい。
ゲスト:これは全部のTリンパ球が抑制されるんですけども
MC :ええ。
ゲスト:あの、そうすると、あのー、生体防御っていわゆる
MC :はい。
ゲスト:ウイルスの感染とかにも弱くなっちゃうんですけども
MC :はあー。
ゲスト:僕たちが作ってるワクチンは花粉なら花粉、
MC :はい。
ゲスト:えー、他のアレルギー、ダニだったらダニ、
MC :はい。
ゲスト:それに特異的な
MC :はい。
ゲスト:免疫を抑制するので、他のリンパ球は全然抑制されない
MC :へえー。
ゲスト:すごい安全なものが
MC :ほぉ、ほぉ、ほぉ。
ゲスト:できそうなんですね。
MC :い、いわゆるその、僕らの持ってる、アレルギー持ってる人達の一番弱いところ、
ウィークポイントだけにアプローチできる
ゲスト:そうです。
MC :ワクチンを石井さん今開発されてらっしゃる。
ゲスト:はい、やっております。
MC :は、僕に早く試して下さい。
ゲスト:あはは。
MC :なんぼでも、僕実験台になりたいです。この症状が楽になるんであれば
ゲスト:あのー、現在動物実験
MC :あ。
ゲスト:やっとります。
MC :ええ。
ゲスト:はい。あの、もうすぐですね
MC :ええ。
ゲスト:あのー、人の、おー、
MC :えー。
ゲスト:臨床試験の方もスタートできるように
MC :ええ。
ゲスト:ま、段階的に進めてるんですけれども
MC :うん、うん。
ゲスト:やっぱりあの、人に打つためには、色んな安全性の、おー、ハードルがあって
MC :はい。
ゲスト:それを今、あのー、試験してるわけですけども
MC :ほー。
ゲスト:それがクリアできれば、いよいよですね、人の試験が始まりますので、
そういった時には、またご案内できるかなぁというように思います。
MC :えー、いわゆるTリンパ球の花粉症のアレルギーの方だけの為のワクチン
ゲスト:そうです。
MC :で、他のウィルスに対しては、ブロックできる
ゲスト:できます。
MC :すごい。え、それは注射ですか、飲み薬ですか、どんなふうにして出来るんだろうか。
ゲスト:えーと、最終的には飲み薬にしたいんですけども
MC :飲み薬
ゲスト:あの、試験のデザインから考えると、まずは注射剤で
MC :はい。
ゲスト:あの、試験をして、それで効果があれば次は飲み薬
MC :はぁー。
ゲスト:というふうに、あの、どんどん、あの、良くなっていくと思います。
MC :はぁ。それは楽しみですけれど、そもそも日常生活からね、
花粉症を少しでも和らげる方法とか、も、色々謳われてるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :だけど、症状がある人ってみんな一応やってはいると思うんですよ。
ゲスト:ええ。
MC :で、ま、マスクしたり、メガネしたりって工夫はしてると思うんですけれど
ゲスト:はい。
MC :花粉症って一回なるとね
ゲスト:はい。
MC :治んないんですか?これ。すごく重要なところだと思うんですけど
ゲスト:そうですね、あのー、治んないと思います。
MC :ええーっ、へへへ。
ゲスト:あの、自然に治るケースってあるんですけど
MC :ええ。
ゲスト:あのー、原理的に言うと治らないと思います。
MC :えー、もう一回なったらおしまい。
ゲスト:はい。一生
MC :お付き合いする?
ゲスト:はい。なると思いますね。
MC :うわぁー。
ゲスト:ま、症状を抑える薬はありますけど
MC :ええ。
ゲスト:こん、あの、問題になってんのは、そのIgEって抗体なので
MC :はい。
ゲスト:それが出続けてる限りは、
MC :はい。
ゲスト:も、治らないですね。
MC :つまり、老化してIgEという抗体が生産しづらくなったら、
ゲスト:はい。
MC :若干、その
ゲスト:はい。
MC :花粉症の症状が鈍るかもしれない。
ゲスト:可能性ありますね。
MC :てことは、花粉症治ったと思ったら、それ老化の始まりと
ゲスト:んは。
MC :いう風に言わなくちゃいけないんですね。
ゲスト:ま、花粉症そうかもわかんないですけど。
MC :ええ。
ゲスト:なにかそういう変化があったということですね。
MC :そうですか。
ゲスト:ええ、それはIgEが産生、あの分泌されるB細胞の方な、Bリンパ球の
MC :はい。
ゲスト:問題なのか、それをサポートしてるTリンパ球の働きなのか分かんないですけども、
その変化があって自然に治るってケースはあるんですけど
MC :うん。
ゲスト:基本的にはそれはもう、ずーっと記憶細胞になってるので
MC :はい。
ゲスト:一生涯、お付き合いすることになると思われてます。
MC :いやー、あの、日常生活してるとね、やっぱり花粉症の人って、
花粉症自慢じゃないですけれど、俺はこれやってる、私はこれやってんだと、
あの日常生活とか、あとアイテムだとか、後、はては薬の種類とかの話でね
ゲスト:うん。
MC :どっちがひどい症状かっていう、軽く自慢話始まるじゃないですか
ゲスト:はい。
MC :不幸話が。でもそれももしかしたら、なくなるかも分からないという
ゲスト:そうですね。そのワクチンがきちんと機能すれば
MC :はー。
ゲスト:もう杉林も走って通れる
MC :はい。
ゲスト:通過できるような状況になると思います。
MC :はー。ちなみに今日本人のね、何割ぐらいがいわゆる花粉症と言われるんですかねぇ。
ゲスト:そうですね。お、おおざっぱに言えば、も、治療受けてるっていう患者
MC :うん。
ゲスト:あの、人から言えばもう3割ぐらいと言われてますけども、
MC :はあー。
ゲスト:治療を受けてなくて、
MC :うん。
ゲスト:その症状が出てる方は、もっと多いんじゃないかって
MC :うん。
ゲスト:言う風に言われていますね。
MC :うーん。3割でも十分ですけどね。
ゲスト:十分多いと思います。
MC :3500万人から4000万人てことですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :えー、その人たちが、でも、その今のお話聞くとねぇ、こんな辛い話、
だって、なんにも悪いことしてないのにね、
ゲスト:そうです。
MC :季節が来ると、た、体調悪くなるってこんないやな話ないですもんね。
ゲスト:そうですねぇ。
MC :え、ちなみに石井さんは花粉症ですか?
ゲスト:えーと、杉はないんですけども
MC :ええ。
ゲスト:他の、おー、
MC :あっ、
ゲスト:花粉症持ってます。例えば、白樺
MC :ああー。
ゲスト:であるとかですね、
MC :うん。
ゲスト:これはあの、まあ、あの北欧とかですね
MC :はい。
ゲスト:日本ですと北海道とか
MC :うーん。
ゲスト:あのー、白樺の木の花粉なんですけども
MC :うん。
ゲスト:そういったものに反応する花粉症ですけども
MC :うん。
ゲスト:ま、杉は私持ってないんですけども
MC :あ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :今度僕がその辛さを
ゲスト:あっはは。
MC :今度、あの、研究室にお邪魔して、語りに行きますから、
来年私を是非実験台にして、また、この番組で報告させて下さいよ。あっはは。
ゲスト:承知しました。
MC :はい。えー、どうでした?あの、花粉症に悩む皆さん。
ちょっと一縷の光明が差して来てる感じがしませんか?
え、今週の「サイコー」は、理科学研究所の石井保之さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「花粉症の科学 パート1」 ゲスト:石井保之さん
2020/03/01 Sun 12:00 カテゴリ:人体MC :さ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
理化学研究所の石井保之さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :えー、石井さんはですね、
独立行政法人理化学研究所統合生命医科学研究センターのチームリーダーで、
岩波科学ライブラリーから、「花粉症のワクチンをつくる!」という本も
出版されています。普段どんな研究をされてるんでしょうか。
ゲスト:はい。えー、私は、あの、体を
MC :ええ。
ゲスト:ま、外敵から守る免疫システムというのがあるわけですけども
MC :はい。
ゲスト:ま、それはあの、通常、おー、ウィルスであるとか
MC :はい。
ゲスト:さい、えー、細菌に対して
MC :はい。
ゲスト:えー、防御、お、活動してるわけですけども、その制御機構を
MC :はい。
ゲスト:勉強しております。
MC :はあー。
ゲスト:で、その制御機構が、実はアレルギーの、
MC :ふん。
ゲスト:発症の原因にも、
MC :ふん。
ゲスト:おー、繋がっとりますし、で、そのアレルギーの、えー、抑制、えー、機構でしょうか、
MC :はい。
ゲスト:それにも応用できるということでですね、
MC :うん。
ゲスト:えー、免疫を基本から、あー、基礎からですね、学んでいるということでございます。
MC :まあ、アレルギーなんて
ゲスト:はい、はい。
MC :僕、子供の頃あんまり聞かなかったけど、もう、今はアレルギーという言葉は、
あー、なんかもう、極めて日常的で、
ゲスト:そうですね。
MC :何らかのアレルギーを僕ら持って生きてるというか、あは。
ゲスト:そうですね。
MC :それと付き合いながらどうやってそれを凌ぐかっていう生活だと思うんですけど
ゲスト:はい。
MC :特にこの時期、まあ、今もう終盤ですけど、杉の花粉、今年は東京多かった。
ゲスト:そうですね。
MC :クシュクシュみなさん言ってましたけれど、
で、これ、えー、これもアレルギーなわけですよね。花粉症。
ゲスト:そうですね
MC :うん。
ゲスト:原因が、あー、花粉の、おー、成分
MC :はい。
ゲスト:になってますけども、それに反応している、ア、アレルギー反応ですね。
MC :はい。
ゲスト:はい。それが原因だと
MC :そもそも
ゲスト:な、
MC :なん、なんでこのね、杉の花粉を吸いこむと、
くしゃみとか鼻水とか目がかゆくなったりとか、
喉が痛くなったりとか、若干微熱が続いたりとか、
ゲスト:そうですね。
MC :色んな症状が起きるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :なんで、たかだか杉の花粉ごときにそんなふうにやられなきゃいけないんだと、
僕も30年、
ゲスト:あは。
MC :ずっと戦ってるんですよ。
ゲスト:はい。
MC :おかしくないですか。
ゲスト:ま、本来ですね
MC :ええ。
ゲスト:あの、体には有害なものではないので、
MC :えっ。
ゲスト:はい。
MC :杉、杉の花粉が?
ゲスト:ええ、本来は体が反応する必要はないわけなんですよ。
MC :ああ。
ゲスト:で、元々その、例えば杉花粉の
MC :ええ。
ゲスト:え、せい、えーと、アレルギーの原因になってる物質っていうのは、
MC :はい。
ゲスト:花粉の、えー、細胞壁です。花粉の外側を作っている、
えー、成分あるんですが、それを酵素で、えー、溶かす働きがあるんですけども
MC :うん。
ゲスト:その酵素が、えー、アレルギーの原因になってます。
MC :それ人間の体にある
ゲスト:はい。
MC :酵素ですか?
ゲスト:これはもう花粉にしかないです。
MC :あ、花粉にある
ゲスト:はい。
MC :酵素が、
ゲスト:はい。
MC :アレルギーの
ゲスト:原因だってこと
MC :原因になってる。
ゲスト:はい。
MC :花粉そのものじゃなくて、
ゲスト:ええ。
MC :花粉に
ゲスト:中にある
MC :中で
ゲスト:酵素ですね。
MC :酵素
ゲスト:はい。その酵素は、その、細胞壁を溶かす酵素なので、
つまりあの花粉が受粉した後にですね
MC :うん。
ゲスト:花粉管ていうの伸ばすんですね。
MC :はい。
ゲスト:そのために細胞壁を壊さなくちゃいけないんですが、
その壊す時にその酵素が必要なので、花粉の中に沢山入ってるんですね。
MC :はい。
ゲスト:でもそれは全然、体に、人間にとっては害ではないものなんですが
MC :はい。
ゲスト:外敵だと思って、人間の体が攻撃してるのがアレルギー反応ということになります。
MC :すごい。
ゲスト:はい。
MC :あの、酵素っていうと最近ねぇ
ゲスト:はい。
MC :あの、洗濯物がきれいになったり
ゲスト:はい。
MC :人間取り込むとね、健康になったりって言われてブームじゃないですか
ゲスト:ええ。
MC :酵素ブームだけれど
ゲスト:ええ。
MC :その花粉に含まれる酵素に関しては、
人間はどっかで受け入れないってことがあるってことですか?
ゲスト:そうなんですよ。本来は、受け入れていい、いい
MC :ええ。
ゲスト:ま、無害な物なのに、
MC :ええ。
ゲスト:何か勘違いをしてですね
MC :ええーっ。
ゲスト:外敵だと思ってるフシがあるんですね。
MC :いやー、分かりやすいですねぇ。
ゲスト:ははは。
MC :じゃ、それはいいものだと思えればいいんだけれど
ゲスト:はい。
MC :僕らの体はそういうふうに言うこと聞いてくれないってことですか?
ゲスト:アレルギーの方はそう思ってるってことですね。
MC :あっ、アレルギーじゃない人は、
ゲスト:はい。
MC :その酵素を
ゲスト:ええ。
MC :ちゃんと取り込んでも
ゲスト:ええ。
MC :体に
ゲスト:外敵じゃないので、単に消化してるだけなんですね。
MC :なんでぇ、俺の体は
ゲスト:はい。
MC :その酵素を嫌うんだよぉ
ゲスト:あははは。
MC :受け入れてやってくれよって
ゲスト:そうですね。
MC :僕なんか花粉症だから、そう思っちゃうんですけど
ゲスト:だから、かなり、こう、過剰防衛してる部分があるわけですよね。
MC :敏感すぎるってことですか
ゲスト:はい。で、その背景には、なんか、寄生虫感染が関係してるって言われていて
MC :寄生虫!
ゲスト:はい。今、あのー、うん、ま、先進国の方で、
MC :ええ。
ゲスト:体の中に寄生虫持ってる方いらっしゃらないんですけど
MC :はい。
ゲスト:ま、昔はですね、体の中に寄生虫があって
MC :はい。
ゲスト:で、その寄生虫を攻撃するシステムがアレルギーの、
えー、本体であるIgEっていう抗体の、あの、役割なんですね。
MC :IgE
ゲスト:はい。これよくあの、アレルギーのなんかで出てくるんですけども
MC :はい。
ゲスト:アレルギー症状を引き起こす、体の中の生体物質なんですけども
MC :はい。
ゲスト:これはその、寄生虫をやっつけるために本来あったシステムなんですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:ところが、今、寄生虫がないじゃないですか
MC :昔ありましたもんね。
ゲスト:はい。で、え、寄生虫を退治するために体に用意されてたんですけども
MC :ええ。
ゲスト:もう、それが無くなったので
MC :へえー。
ゲスト:もしかするとですね、これかなりあのー、えー、想像なんですけども
MC :ええ。
ゲスト:寄生虫だと思って、えー、アレルギー、
応答してるんではないかって言うのが一説であります。
MC :はぁー。
ゲスト:例えば、あ、寄生虫のある成分が、
MC :ええ。
ゲスト:その花粉の成分と似ていて、
MC :はい。
ゲスト:で、それを花粉の成分入って来たのに、寄生虫が入って来たと思って、
体の中でIgEが作られてんではないかとかですね、
そういうような発想も、あの、されているということなんですね。
MC :てことは、敏感なんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :で、うん。
ゲスト:で、基本的に体の中の免疫系っていうのは、ま、外敵に対して守る、
あのー、システムなのでなるべく性悪説っていうんですか?
MC :はい。
ゲスト:あのー、敏感な方がいいわけですね。
MC :はい。
ゲスト:敏感じゃないと、どんどん侵略されて
MC :はい。
ゲスト:しまいますので
MC :はい、はい。
ゲスト:なるべく疑わしきは、もう
MC :はい。
ゲスト:罰すると
MC :はい、はい。
ゲスト:いうようなシステムなもんですから、
MC :うん。
ゲスト:ちょっとなんか寄生虫に似てるとかですね
MC :はい。
ゲスト:外敵風な物に対してはもう、過剰に反応するっていうのが
MC :うーん。
ゲスト:基本のシステムになって
MC :うん、うん。
ゲスト:おります。
MC :なるほど。関東地方の場合は、もう杉は、もう4月の半ばになると
ゲスト:そうですね。
MC :終わりですよね。
ゲスト:ピークがもう終わりつつあって、次は、檜が
MC :来るわけですね。
ゲスト:そうですねぇ。
MC :で、杉のアレルギー持ってるけど檜大丈夫の人もいるし
ゲスト:はい。
MC :逆の人もいるわけですよね。
ゲスト:いますね。
MC :うん。
ゲスト:でも、あの、幸か不幸か、分からないんですが、
ま、不幸の方かもしれませんが
MC :ええ。
ゲスト:杉と檜の、えー、アレルギーの原因の
MC :はい。
ゲスト:その、成分は非常に似てます。
MC :あ、ほー。
ゲスト:ま、花粉自体違うんですけども
MC :はい。
ゲスト:酵素であるっていう点では同じで
MC :はい。
ゲスト:で、酵素の、そのー、なんですかね、
成分のなんかですね、配列っていうかですね
MC :はい。
ゲスト:アミノ酸で出来てんですけども
MC :うん。
ゲスト:その配列がすごい似てるんですね。
MC :うーん。
ゲスト:ですので、えー、大抵スギ花粉症の方はヒノキ花粉症でもあるので
MC :はい。
ゲスト:えー、今、杉の花粉がピークですけど
MC :はい。
ゲスト:檜の花粉が飛んで来ても反応される方が多いと
MC :ほおー。
ゲスト:思っていただいて
MC :なるほどね。
ゲスト:いいんじゃないでしょうか。
MC :ほー。あのー、この花粉に関して、僕、30年ぐらい前の時に発症してですね、
あのー、戦後ね日本が国策として杉を植林して、今その杉がですね、
成長のピークを迎えてるんで、やがてはこの花粉は減ると、
僕は30年前そう聞いたんですよ。30年経ったけどちっともそれが進んでないんですけど、
な、なんでなんですか。
ゲスト:僕もあのー、最近また調べたんですけども
MC :ええ、ええ。
ゲスト:そしたらですね、大体ですね
MC :うん。
ゲスト:日本のその杉林の10%に当たる
MC :はい。
ゲスト:えー、植林をしてるってことが、毎年、毎年ですね、
毎年植林してることが分かったんですね。
MC :えっ、杉植えてるんですか?
ゲスト:植えてます。
MC :誰が植えてるんですか?
ゲスト:これはやっぱりですね、住宅の為の建材としては優秀なので
MC :そうか。
ゲスト:で、しかも成長早いじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:杉に置き換わるものがなかなかないので
MC :ええ。
ゲスト:あのー、毎年植えてるんですね。
MC :あら。
ゲスト:しかも、10%ぐらい植林してるらしいんです。
MC :じゃ、住宅用の建築資材として伐採されては、そこにまた植林され
ゲスト:はい。
MC :伐採されては植林されるという
ゲスト:はい。
MC :うん。っははは。
ゲスト:一方で、あの、花粉が飛ばない
MC :はい。
ゲスト:杉っていうのもね
MC :うん。
ゲスト:あの、開発されてるんですね。
MC :ほんとですかぁ。
ゲスト:はい。
MC :いや、疑ってますよ僕は。
ゲスト:で、無花粉杉っていうですね
MC :うん。
ゲスト:それも実際に植林されてます。
MC :うん。
ゲスト:で、全部それに替えたらいいんじゃないかなと僕思ってたんですが
MC :はい。
ゲスト:どうもそのー、えー、植林はいいんですけども、
木材になった時の、品質がまだ分からないんです。
MC :へえー。
ゲスト:あの、20年とか30年経って伐採するじゃないですか
MC :はい。
ゲスト:で、木材にしてみないとその質が分かんないですね
MC :ええ、ええ。
ゲスト:だから、花粉が飛ばないのはいいんですけど
MC :ええ。
ゲスト:役に立たない物植えてもいけないってことで
MC :ああー。
ゲスト:10%のうちの、また10%ぐらいしか無花粉杉は、
植林されてないようだっていうことが分かりました。
MC :あっ、一応業界はそうやって品種を替えるなどして工夫はしてる訳ですね。
ゲスト:そうなんです。
MC :だけどなかなか
ゲスト:行政が頑張ってます。
MC :頑張ってはいるんですね。
ゲスト:はい。
MC :日本人の健康に対しての
ゲスト:はい。
MC :だけど、必ずしも、じゃ、建築資材として
ゲスト:はい。
MC :それが適してるかっていうとまた、別っていう
ゲスト:そうなんです。
MC :いたしかえし
ゲスト:そうですね、だからその、業界の方に
MC :いやー。
ゲスト:してみるとやっぱり、あのー、保証できるあの、
木材を使いたいというとこなんでしょうか
MC :そうですか。いや、まあ、もーこんな時間。いやー、勉強になりましたねぇー。
これ、今日は多分、同じ悩みを抱える人たち、ま、キッズ達だけじゃなくて、
なんでもうあと2ヶ月早く来てくれなかったんだろか、石井さん。
ゲスト:あはは。
MC :あはは。
ゲスト:呼んで頂ければ
MC :ああー。
ゲスト:いつでも参りますよ。
MC :いやいやいやぁー。よし、ちょっと来年に向けて備えなくちゃ。
また来週、今度対策について伺いたいと思います。
えー、今週の「サイコー」は、理化学研究所の石井保之さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございます。 -
「ビッグデータって何? パート2」 ゲスト:西田宗千佳さん
2020/02/01 Sat 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーもフリージャーナリストの西田宗千佳さんです。
こんばんは。
ゲスト:はい、こんばんは。よろしくお願いします。
MC :はい、情報技術の先駆者、フリージャーナリストといわれているんですけれど、
あの講談社からですね「顧客を売り場に直送するビッグデータがお金に変わるしくみ」という
本を出版されていて、ビッグデータ興味深かったですね。
ゲスト:そうですかね。
MC :スマホを手にした瞬間、あなたはビッグデータのキャリアになるという・・・
ゲスト:はい、そうです。
MC :そしてそのデータがいろんな風に活かされているという・・・
ゲスト:はい、自分のプライバシーを人に渡して、
その代わりに便利な機能をもらういう形になってるわけですね。
MC :いやでも、持ちつ持たれつで悪い話じゃないなと思いましたね。
この狭い日本ですから利便性は大事ですからね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :そんな中で、カーナビって、大体の車最近付いてますよね。
ゲスト:そうですね。
MC :あれもビッグデータになるんですか?
ゲスト:あれももちろんビッグデータになりますね。
例えば、えっとーどこでブレーキを踏んだかっていう情報が分かると
「あっ、この辺の道はこういう風に走るのが、一般的なんだな。」って
分かってくるわけです。そうすると、車の中に、で、
えっとブレーキの使い方だとかエンジンの使い方をコントロールして、
よりエコに走れるように、えー、技術開発をすることができるようになる訳なんですね。
MC :カーナビと運転の仕方って別問題かと思ってるんですけど・・・
ゲスト:はい。
MC :そ、それもカーナビのコンピュータの中にこの人の運転癖みたいなものが・・・
ゲスト:分かります。
MC :分かる。
ゲスト:ええ、あのーどこでブレーキを踏んだかであるとか、
どのくらいのスピードでその道を走ってたかっというのは分かるので・・・
MC :そうですねー。
ゲスト:そうすると、ここはこう快適に走ってるからエコに走れてる。
でも、ここは渋滞してるからブレーキ踏んでばっかりでエコになってないだとか、
そういう事が分かってくるわけですよね。
で、それが車のメーカーに渡されると車メーカーはじゃあこういう特性に合わせて、
ブレーキを変えましょうだとか、エンジンを変えましょうだとか・・・
そういうふうに調整してエコな車がどんどん出来ていくことになるわけです。
MC :すごい。じゃ、例えば、交通事故がやけに多い交差点とかも
データとして残ったりするんですか?
ゲスト:もちろん。
MC :残ってる?
ゲスト:ええ、あのー、急ブレーキを踏んだ所っていうのは、
急ブレーキを踏んだってことでデータが残るので、
事故に至らなくてもどうもこの交差点は急ブレーキが多いと、
急ブレーキが多いって事は事故が起きやすいって事なので、
「何で起きやすいのかな?」っていうことで、今度は地図と組み合わせてみると
「あっ、ここは右に曲がる所が例えば、木で隠れてて見づらいんだ。」とわかったら、
その木を切ってブレーキが少なくなるようにする。
そうすると、その交差点は事故が起きづらくなるので、安全性が増すって事になりますね。
MC :今、車運転しているお父さんの目の前でね、
ものすごく目立つ標識とか「止まれ」なんてね路面に書いてあったりとか、
あと路面が凸凹になって注意を喚起したりとか、そういうような工夫がなされていたら、
場合によってビッグデータから導かれた注意信号かもわかんないですね。
ゲスト:そうですね。昔はそれを経験に基づいて、
例えば、警察の方が「ここは危なそうだな。」っていうので、
経験に基づいてやってたんですけど、それに加えてビッグデータを使って、
「あっ、この道は事故は起きてないけど、事故の一歩手前はすごく多いな。」
というふうなことを理解した上で、え、町並みをこう改善するといった事が進んでる訳です。
MC :すごい。あと、あと、まあスマホではないけれど、あのー携帯以外でね・・・
ゲスト:はい。
MC :あのー、インターネット・・・
ゲスト:うん。
MC :例えばインターネットでショッピングするのが最近増えてるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :そうすると、例えば自分がこの商品買ってもないのに、
この、この商品買った人はこんなのも買ってますよっていう風に、
何か一つ買い物すると次に10個くらい尾ひれがついて紹介・・・
ゲスト:出てきますね。
MC :あ、あれもひょっとしたらデータなんですか?ビッグデータの一種・・・
ゲスト:はい。あれも正にビッグデータのやり方ですね。あのー昔は、あのー昔、
今もそうですけど、コンビニエンスストアに行くと、実はコンビニで買った時に裏で、
この人は40代の男性でこれ買ったみたいにボタンを押してるんですね。
MC :あっ、聞いた事あります。
ゲスト:はい。で、インターネットのショッピングではそれがもっと精密に行われてて、
この人は週に何回買う人でしかも30代で、男性でとかっていう風に細かく分かるわけですね。
MC :登録しますもんね。
ゲスト:ええ、で、こま、そうすると、この男性はきっと例えば、
えー、ゴルフが好きな方だから、ゴルフのクラブを買ったら、
ゴルフの本も出すだろう・・・でも、ゴルフの本を一生懸命読むような方は、
仕事でも色々悩んでるだろうから、えー、仕事のやり方の、
要は最適化の本も出そうとか、そんなふうに今までだと、
こう思い及びもつかなかったような商品も一緒に出してくる、
それによって売り上げが上がるわけですね。
で、もっといえば、僕らとしては思いもよらなかった物が出てくるので、
商品との出会いの演出にもなってるわけです。
MC :えええーーーー。
ゲスト:「こんな面白いもの出てくるんだ。」っていうのが、一つ面白味でもあるわけですよね。
MC :とりあえず表向きはだから個人情報の流出ではなくて、
あくまでも、表面上の先週話したけど、「イエス」「ノー」とか「はい」「いいえ」とか、
「いいね」「悪いね」とか、「グッド」「バッド」とか
そういうものに基づいてのジャッジなんですよね。
ゲスト:はい、そうですね。そこんとこで見てるのは、
例えば、西田だとか大村さんっていう人を見てるんじゃなくて、
例えば40代の男性で、えー例えば映画が好きな人とか、
そういう属性で見てる・・・属性で見てるからこれはあなたではなくて、
あなたみたいな人々っていう塊ですよっていう分析の仕方をしてるわけですね。
だから、プライバシーの侵害ではないですよ。と彼らはいっている。
MC :えーあとは、あとはもう色々詳しいから色々聞きますけど・・・
ゲスト:ええ、ええ・・・
MC :いやあ、今なんか諸手を挙げて「いいね、いいね」なんていってましたけど、
でもよくないこともあるんじゃないかと心配なってきましたけど・・・
ゲスト:ええ、あのー一番問題なのは、あのーこういった許諾ものって
許諾に基づいて色々なデータを使ってるわけですよね。
でも許諾の中身をきちんと読んでる人って多分ほとんどいないわけですよね。
MC :先週話してた、スマホに変えた時に同意するっていうあの部分ですよね?
ゲスト:そうです、はい。
MC :正確には、何に僕は同意したんでしょうか?
ゲスト:そうなんですよ。あれは、えーっと、
個人に基づかないデータを全部吸い上げてマーケティングに使いますよ、
ビジネスに使いますよっていうことが書いてある。
MC :そんなこと書いてあった・・・かなー?
ゲスト:で、使うのは位置情報と例えば移動情報と何々とみたいな条件書いてあるんですね。
MC :えーーーー。
ゲスト:でも、そんなのいちいち読んでられないわけですよ。
MC :ええええ。
ゲスト:で、それを悪用すると、要は自分はそんな情報を出したつもりがないのに、
えー例えば電話帳の中身を全部取り出して、
「この人とこの人は関係があるから、この人に対してダイレクトメールを出せば、
売れるんじゃないか・・・」みたいな使い方が、されないとも限らない。
MC :なーるほどねー
ゲスト:便利なことをやる為に許諾とっちゃって、
もういいからとにかく「みんな「オッケー」押しましょう・・・
「許諾します」を押しましょう。」っていっているんだけども、
その中身をほんとは精査しないと危ないということですね。
でも、中身をきちんと理解することって、一応専門家といわれる僕でも無理なんですよ。
MC :ちなみにあのー、ほとんどの方がやっぱり許諾に関してはオッケー出してるわけですか?
ゲスト:はい、殆ど、殆どの方、99%出してると・・・
MC :あっ、99%が・・・
ゲスト:というのは、出さないと機能の要は半分以上使えないですね。
MC :あっ、スマホの本来の・・・
ゲスト:ええ。
MC :機能が使えない。
ゲスト:使えないから・・・
MC :確かにそうですよねー。いやあーーーすごいですねーーー。
ゲスト:だからこそ、自分が何を出してるかと、出してるものに対してきちんと、
えー何というか・・・同じ価値のある利便性、
それは機能だとかサービスだとかってことなると、
それを提供してくれるんじゃないと出せないよねっていう話に多分、
最終的にはなる・・・だろうと思います。
MC :そっかぁ。でもここまで、国民が参加してくれるところからよりね、
参加者が増えてくるわけで・・・
ゲスト:はい。
MC :例えば、選挙ですとか・・・んんーまあほんと、国民投票が場合によっちゃあ、
夢じゃないんじゃないかなと思いますよ。やっぱり選挙の場所に行くのが大変だから・・・
ゲスト:そうです、そうです。
MC :ねー。投票率ってどうしても下がっちゃうわけじゃないですか。
だったらもうこういうものを使って、あのー国を動かすような
そういうデータになってくれるといいですね。
ゲスト:そうですね。あのー実は今もう、選挙の結果ってですね、
要はビッグデータ、いわゆるネットの検索履歴から、
大体、そうですね97%ぐらい当たるんですね。
MC :マスコミの出口調査以上にですか?
ゲスト:以上です、はい。
MC :えーーー。そうなんですか?
ゲスト:はい、そうです。
MC :あら。
ゲスト:マスコミの出口調査っていうのは、
マスコミの人のこれまでの知識だとか経験で予測してるんですけども、
えービッグデータの場合はそういうのなしに
どれだけたくさんのえー候補者の名前が検索されたかで、やってるんですね。
それでもう今、大体97%ぐらいですかね、当たるようになってきてます。
MC :すごいですねー。
ゲスト:更には、例えば、えー景気、次の景気が良くなるか悪くなるかも、
えー概ね大体わかるようになって来てる・・・
MC :ズバリどうですか?
ゲスト:今のところは、プラスだって聞いてますけども・・・
MC :あっ、そうですか・・・
ゲスト:え、あのー、突然落ちるかもしれません。
MC :あっ、そうですか・・・
ゲスト:ええ、はい。
MC :いやいや、まあまあ、これからね、春になって携帯の買い替えの時期ですから、
スマホにされる方は一応こういうものがあるっていうことを読んだ上で、承諾してみて下さい。
あー、もう時間ですねー。いやーー、面白かった。
ゲスト:いいえ。
MC :また来て下さいね。
ゲスト:はい。是非よろしくお願い致します。
MC :ええ、今週のサイコーはフリージャーナリストの西田宗千佳さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「ビッグデータって何? パート1」 ゲスト:西田宗千佳さん
2020/02/01 Sat 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーはフリージャーナリストの西田宗千佳さんです。
こんばんは。
ゲスト:はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
MC :西田さんは福井県のご出身で、
えーITや先端技術で第一人者のフリージャーナリストというで、
ま、とてもそのー今のあのー情報社会の先駆者みたいな方なんですよねー。
ゲスト:だといいんですけどねー。
MC :はい、講談社から
「顧客を売り場に直送するビッグデータがお金に変わるしくみ」という、
ちょっと難しいタイトルの本も出されているんですけれど・・・
ゲスト:はい、そうですね。
MC :今日のテーマは「ビッグデータ」
ゲスト:はい。
MC :ビッグダディーはね、有名ですけれど・・・
ゲスト:有名ですね、はい。
MC :ビッグデータって、簡単にいうと何ですか?
ゲスト:ものすごく簡単にいうと、「大きなデータ」それ以上の・・・
MC :そのまんま。
ゲスト:まんまなんですけれど、僕達が日常的に暮らしていると例えばですね、
お店に数千件デー・・・あのーおー品物があると・・・で、
そうすると数千件分の名前と値段があるわけで、これ「データ」ですよね。
MC :スーパーに行くとあります。
ゲスト:スーパーに行くと・・・はい。
でも、本当は僕たちがスマートフォンであるとかを持ち歩き始めると
もっと桁の違う大量のデータがネットの中に蓄えられることになるんですね。
で、その分析すると僕らはどういう風にえー、行動しているかであるかとか、
次どんな事がしたいかであるとか、どんな商品を求めるか、
てるかであるとか・・・・そういう事が読めるようになってくる・・・で、
その読む為のデータを集めてえー分析するビジネスのことを
「ビッグデータ」と一般にはいいます。
MC :この場合は、スーパーの商品、ラーメンがいくらとか、枝豆がいくらとか、
そういうものではなくて、僕らの行動そのものがデータ化されて
ビジネスに使われるっていうことですか?
ゲスト:そうですね。すごく簡単にいうと、あのー今のスマートフォン、
えー振動を感知するセンサーがついているので、
持って歩いていると1日に何歩歩いたかとか、
もしくはどのくらい走ったかとかって分かるんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、例えば1日1万歩歩いたとしましょう。
MC :はい。
ゲスト:でも、歩いた場所もある訳ですね。
今、GPS付いてますから、どの辺歩いたかも分かります。
そうすると、何分にどこにいたか全部わかる・・・
そうすると1万歩歩いたデータから実際にはその人がどういう所に行ったかだとか、
どのぐらい止まったかだとかっていうデータは・・・くっつくことになるので、
1日当たり数万件のデータが集まることになるんですね。
MC :ほーーー。
ゲスト:で、スマートフォンが日本国内だけでも大体2000万台くらいありますかね、
2000万台くらいあることになると、2000万台かけることの2万・・・
ということで、それだけで、4億・・・件のデータになりますよね。
で、それが毎日、毎日蓄積されることになるので、
ひと月だけで1兆とかそのぐらいのデータが集まることになるわけ・・・
そうすると例えば、えー昼間の12時にこの駅前にいる人はどっちに行くかとか、
どんな物を欲しがってるかだとか、そういうことがわかってくるようになるんですね。
MC :あっ、じゃあ例えば僕が浜松町の駅に行った。山手線の内回りか外回りどちらに乗るか、
キオスクで何を買うか、立ち食いそばを食べるかとか・・・
ゲスト:そうです。
MC :あるいは、モノレールに乗って羽田まで行くかとか・・・そういうの全部、じゃあ・・・
ゲスト:分かるわけです。
MC :わかる。
ゲスト:例えば・・・朝、えーっと、東京の離れたところから来た人が
一番最初に飲むのがコーヒーなのか、それとも例えばえー、コーンスープなのか・・・
そういう事から、じゃあコーンスープを朝に飲んだ人は昼何を飲むかとか
そういうことも全部分析できるようになるんですね。
MC :えっ、ちょっと待って。僕が札幌から東京着いた。
で、浜松町でハンバーガー屋さんに入った。
で、頼んだハンバーガーの種類もデータとして分かるんですか?
ゲスト:分かる、まあある程度分かります。それで例えば携帯電話でお金払いますよね。
携帯電話でお金払うと、この人はハンバーガー屋さんに入って何を買ったかって、
分かるわけですから、ぜーんぶ組み合わせていくと・・・
MC :へぇーーー。
ゲスト:東京から、東京に今、昼間にいる人が食べたいと思っているハンバーガーは
ちょっと今日は寒いから、温かめのハンバーガー、
要は辛いハンバーガーがいいんじゃないかみたいなことまで
分析しようと思えば分析できちゃうということです。
MC :すごい!!ちょっと、えっそれは今、今スマホとおっしゃったけど、
あのースマホが今、急速に普及していて
去年大体ガラケーとスマホが半々くらいになりましたよね。
ゲスト:はい、そのぐらいになりましたね。
MC :これ間違いなく今年はスマホの方が超えてくる・・・
ゲスト:はい。
MC :はずですよ。
ゲスト:おっしゃる通りです。
MC :データとるのはスマホだけなんですか?
ゲスト:あのー、実はいわゆるガラケー、フィーチャーフォンでもとれてます。
MC :とれてる。
ゲスト:でも、通信する量であるとか、
例えばガラケーの時代って移動しながら自分がどこにいるかだとか、
地図ってあんまり見なかったと思うんですね。
MC :んーー。
ゲスト:えーもしくは、え、ソーシャルネットワーク、
例えばツイッターだとかフェイスブックみたいなものを見ながら
移動する人も少なかった・・・なので、
ガラケーからとれるデータよりもずっと見ながら動いている。
例えば地図見ながら動いている、えーツイッターやりながら動いている
スマートフォンの方がたくさんのデータが集まる傾向にはあります。
MC :すみません、これは、えーまあラジオの前のキッズ、
あるいはお父さん、お母さん、スマホ持ってらっしゃる方多いと思うんですよ。
ゲスト:はい。
MC :そうすると、「えっ自分の行動全部、勝手にデータになっちゃってんの?」って
思ったりしないですかね?
ゲスト:そうですね。あのー、実はスマホ使い始める時に、
えーこのデータほにゃほにゃほにゃほにゃに使いますのでいいですか?っていう
「許諾」をとる画面て出てこなかったですか?
MC :知らないですーーー。
ゲスト:そこで、とにかく「はい」を押してくださいっていわれたと思うんですけど、
そこで「はい」を押すと、データは全部えー、記録される。
MC :あ、初期設定の段階でそういう・・・
ゲスト:そうです、はい。
MC :そういう文言があるんですね、あったわけですね。
ゲスト:そうそう。でも逆にいうと、マイナスのことばっかりじゃなくて、
その為に僕らは例えば、えー次、電車が今混んでますと、電車が遅れていくので、
あなたはこっちのルートに行った方がいいですよ。ってことを教えてくれたりだとか、
えーっとメールをタダで使えたりだとか、もしくはえー、例えばえー、
この本を買ってる人は他にもこの本買っているのでどうですか。
だとか自分に対してプラスの情報もくれるわけですね。
自分のプライバシーをお金みたいに人にあげるかわりに
自分に対して利便性も返してくれる。
それがえーっとスマートフォンになってから現れたえー、
「ビッグデータ」っていうものの一つの本質なんですね。
MC :んーーーーー、なるほど。SNSってさっきおっしゃってましたけど、
例えば今流行っているライン?今ライン若い子みんなやっるじゃないですか?
ゲスト:やってますね、はい。
MC :あれもやっぱりビッグデータの一つと考えていいわけですか?
ゲスト:そうですね。あのー、会話してる内容そのものは分析してないと思います。
でも、例えば10代の子がどんなえー例えば、スタンプをたくさん使っているかであるとか、
どこでたくさんしゃべっているかであるとか、
そういった情報は集計されて、例えば10代の子はどんなキャラクターが好きか、
とかえー、10代の子が集まっている場所がどこかだとかそういった事は
当然他のビジネスに当然活かせるわけですよね。
MC :ほーーー。
ゲスト:物はじゃあ、次何売れるかっていうのを読む為には、10代の子が何が欲しいか、
何が好きかっていう情報がみんな欲しいわけですよ。
で、それには一つの方法としてラインみたいなものをつか、
タダで使ってもらって、でも、どこにいるか、どこに行ってるか、
どんな物をスタンプを使っているかというような事が
情報として手に入ってくる事が重要なんですね。
MC :あとは、ツイッターやフェイスブック、この辺りはやっぱり同じような・・・
ゲスト:同じですね。例えば、えーっと、テレビ番組。
テレビ番組のスポンサーをしている人が今、テレビ番組観ている人の中で
このテレビ番組についてツイッターでつぶやいている人がどんな話をしているか、
面白いっていってくれてればいいけどつまんないっていってくれてるかもしれない・・・
その時にどっちの話をたくさんしているかであるとか、
他のチャンネルの番組に比べてどんな風な反応をしているか・・・
面白いっていっているのか、ここがいいっていっているのか、
そういう事分析する為にも使ってたりするんですね。
MC :でもそれって、いいとか悪いってのはアナログ的なね、
あのー人間が読まなければ評価にならないわけですか?
ゲスト:いや、ところがですね、人間の言葉って大体決まっているので、
例えば「これ、面白い」って書いてあったらこれプラスです。
「前の週よりよかっ、な、悪い」っていってたらマイナスです。
言葉に入ってる単語のえーっと意味であるとか、
前後のえー使ってる言葉であるとかの関係で分析すると、
この人はこの番組にプラスの感情を持っているのか、
マイナスの感情を持っているのかっていうのは、コンピュータで計測できるんですね。
でも、逆に人が読んじゃうとプライバシーの侵害になるので、
一切人が関わらないでコンピュータが解析する、解析した結果、
えー多いと、いいと思っている人が何人、悪いと思っている人が何人みたいな
数字にしちゃうわけですね。そうすると・・・
MC :そうか・・・
ゲスト:人のも・・・人が読んでると、「ああーこの人こんな事思ってるんだ」ってことで、
ちょっと気持ち悪くなっちゃうんですけど、全部コンピュータがやっているので、
えーこれはプライバシーの侵害ではないですよっと
コンピュータ関係の会社は主張してるわけです。
だから、僕らはタダでいろんな事が出来る。
その代りプライバシーを人に、ある程度あげる、という形になってるんですね。
MC :そのあたりですね。いやー、あっという間に時間過ぎちゃいました。
このプライバシーを人にあげるという、
このあたりに関しても色々思うところもありますのでね・・・
ゲスト:はい。
MC :来週もまた是非お越しいただいて、より詳しい話を伺いたいと思います。
ゲスト:はい、よろしくお願いします。
MC :はい、今週のサイコーはフリージャーナリストの西田宗千佳さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「鹿の科学 パート2」 ゲスト:石井陽子さん
2020/01/01 Wed 12:00 カテゴリ:生き物MC :さ、今週の「サイコー」も、
先週に続きまして、鹿写真家の石井陽子さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :お願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :石井さんは、2011年、奈良市内で早朝、明け方、誰もいない路上で、
カップルの鹿を見て、感動して鹿写真家になったということですけれども、
ほんとにね、リトルモアから写真集「しかしか」という本出されてるんですけれど、
68枚の鹿の写真、これ全部素晴らしいんだ。可愛い。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :で、先週勉強になったのは、鹿は春から夏にかけては、斑点が付くんだけれど、
でも段々冬になると、毛が濃くなってくるという。
と、これを聞くと、この「しかしか」に出てくる、鹿たちも、季節感がありますね。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。あとね、鹿がね笑ってるんですよ。
ゲスト:あは。
MC :表情があるんですねぇ。
ゲスト:はい。
MC :これは何、笑わしたんですか?
ゲスト:いや、あのー、何か機嫌がよかったんですかね。
MC :えーっ。
ゲスト:はは。
MC :何でこんな笑ってるんだろう。
ゲスト:まあでも、一般的には他の動物に比べると、
MC :はい。
ゲスト:あの、犬や猫よりは表情少ないんですけれども
MC :はい。
ゲスト:な、なかなか、あの、こういう風に笑ってるところを撮るのは大変です。
MC :結構
ゲスト:はい。
MC :はい、あの、石井さんのカメラを見てくれてるんですよ、
ゲスト:うーん。
MC :この鹿ちゃん達が。でも、よくね、あの、最近の子、使わないかも知んないけど、
無視する事、「シカト」っていうんですけど
ゲスト:ああ、そうですね。
MC :「シカト」っていう語源は鹿から、端に発するって言われてて、
鹿をこっち向かない動物だって考えてる人も多いと思うんですよね。
これ、鹿の目線もらうには、何かポイントはあるんですか?
ゲスト:ま、基本初めて会った時とかは
MC :はい。
ゲスト:向こうも気にしてるのか見ますね。
MC :はあー。
ゲスト:で、あの、これは安全だと思ったら、すぐに草を食べ始めて、
もう、可愛げなくなってしまうので、「シカト」されます。
MC :ああ、はははは。あ、じゃなんとなく、この人間が
ゲスト:はい。
MC :ちょ、ちょっと自分にとって
ゲスト:はい。
MC :危険とか、
ゲスト:はい。
MC :危険な臭いがしたら、こっち向くってことですか?
ゲスト:そうですね。
MC :じゃ、何、石井さんは危険な臭いを醸し出しながら、
しっかりファインダー向けてるんですか?
ゲスト:う、は、あの、
MC :レンズ
ゲスト:そんなことはあんまりしないんですけれども
MC :ええ。
ゲスト:あんまり、危ないと思われたら逃げられてしまうので
MC :はい。
ゲスト:はい。
MC :じゃ、絶妙の
ゲスト:待ってます。
MC :距離感で
ゲスト:はい。
MC :へえええ。そうですか。さあ、鹿なんですけれど、
鹿、えー、先週伺いました。基本的に日本にいるのは、
全部ニホンジカという、一種類しかいない
ゲスト:そうですね。
MC :ただ、その中で北海道から沖縄まで、
7種類の亜種に分かれるというお話だったんですけど、
鹿って主に、僕らの目の前にいる鹿、奈良公園の鹿って、何歳なんですか。
大人、子供とかそういうの分かるんですか?
ゲスト:そうですね。あの、な、だいたい、
鹿の平均寿命っていうのは、雄で4歳から6歳で
MC :へ、
ゲスト:雌が6歳から8歳まで
MC :そんな
ゲスト:生きると
MC :う、若い。
ゲスト:そうですね。
MC :かわいそすぎる。
ゲスト:まあ、あの、野生だと、まあ、雄で14歳、雌で18歳ぐらいまで生きるともう、
最高寿命ぐらい
MC :は、はかない。
ゲスト:はい。ただ、奈良公園では、24歳まで生きた雌の記録があると
MC :へー。
ゲスト:いうことで、ま、結構野生動物なので生活厳しいみたいですね。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :へー、いや、意外だったな、鹿結構長生きかと
ゲスト:うーん。
MC :思いましたけど。そうかぁ。鹿の年齢ってどうやって調べるんですか?
ゲスト:あのー、ま、学術的には歯にできる年輪を数えて、調べるそうなんですけど
MC :お口開けてですか?
ゲスト:はい。
MC :へえー。
ゲスト:あの、ただ、雄の場合は、もう、外見で角の形でだいたい分かります。
MC :あ、雄、角生えてますよね。
ゲスト:そうです。
MC :そうだ、そうだ。
ゲスト:はい。
MC :鹿の角のお土産とか、よくありますもんね。
ゲスト:そうですね。
MC :そうだ。角
ゲスト:はい。
MC :で、つ、角で
ゲスト:はい。
MC :どうやって見分けつけるんですか?
ゲスト:角は、満一歳になると、
MC :はい。
ゲスト:雄鹿は、一本角が生えてきて、まだ小っちゃい角なんですけど
MC :すっごいはっきり言いましたね
ゲスト:はい。
MC :満一歳で角が生える
ゲスト:んふふ、はい。一歳
MC :すごくないですか
ゲスト:ぐらいになると
MC :えっ。ぐらい
ゲスト:はい。
MC :アバウトで
ゲスト:アバウトで
MC :とにかく、一歳になると角が
ゲスト:はい。そうですね。
MC :はい。
ゲスト:で、その次の年は、一本角に1本枝が増えて、二枝の角になります。
MC :あ、Y字型になってるのは
ゲスト:そうです。
MC :2歳
ゲスト:2歳ですね。
MC :はい。
ゲスト:で、満四歳までそういう形で、枝が増えてって、
その後、数は変わらないんですけれども、段々大きくりっぱな角になっていきます。
MC :へえー。おお。
ゲスト:で、ま、最終的に、ん、ん、7~8歳になると、
もう、60センチぐらいの大きなりっぱな角になって
MC :はい。
ゲスト:3つに分かれて、4つの枝角がある、三又四尖っていう形になります。
MC :三又四尖。
ゲスト:はい。
MC :あ、それ鹿の
ゲスト:三つ又で四つ
MC :角の形状?
ゲスト:尖ったっていう形の字ですけど
MC :三つの又
ゲスト:又で
MC :の
ゲスト:四つに尖ってる
MC :ほぉほぉほぉ。
ゲスト:はい。
MC :はい、はい。
ゲスト:で、三又四尖。
MC :枝分かれみたいなね
ゲスト:そうですね。
MC :人生と同じですね。
ゲスト:んふふ。そうですね。
MC :君たちは、何度分かれたか、まだ一つも分岐点ないよね。
これから一つ目の分岐点、二つ目の分岐点、鹿の場合、三つまであるってことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :へー。そうかぁ。あの、でも鹿の寿命考えると、
その、たまによく、奈良公園の鹿の角、き、切りが行われましたって、
ゲスト:はい。
MC :ニュース見るじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :ちょっと可愛そうになってきました。
ゲスト:まあ、でも鹿っていうのは、あの、春から夏にかけて
MC :ええ。
ゲスト:段々角が伸びてきて、
MC :はい。
ゲスト:あの、翌年の春3月4月ぐらいになると、自然にポロッと落ちるんですね。
MC :あ、鹿の角は落ちるんですかぁ。
ゲスト:そうです。はい。
MC :知らなかった。
ゲスト:ええ。
MC :えっ、ちょっと待って下さい。
ゲスト:はい。
MC :え、だってさっき、一年目は
ゲスト:はい。
MC :一つ、
ゲスト:はい。
MC :二年目で二又っていうじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :でも、じゃ、一回、ポロッと落ちたら、
ゲスト:はい。
MC :二歳の子はいきなり二又が生えるってことですか。
ゲスト:また、あの、段々生えてきて、最初春先とかは、
袋角って言って、ちょっと皮を被ったような
MC :えーっ。
ゲスト:柔らかそうな角が生えてきて
MC :はい。
ゲスト:で、あの、6月7月ってどんどん、ニョキニョキ
MC :あ、
ゲスト:長くなってくんです
MC :それで、二年目になると二又に分かれるってこと?
ゲスト:そうですね、はい。
MC :いや、知らなかったぁ。えっ、知ってたみんな。は、みんな知らない?
いやはは。みんな知らないです。ありがとうございます。
ゲスト:いえいえ。はい。
MC :あ、そう、
ゲスト:はい。
MC :ポロッと落ちるんですか。
ゲスト:はい。だから、あの、別にあのー、角が
MC :うん。
ゲスト:売られてても
MC :うん。
ゲスト:全部死んだ鹿のものとは、限らなくて
MC :えー。
ゲスト:自然に落ちたものを売ってるとか、
角切りしたものを売ってる可能性もあります。
MC :うん、うん、うん。なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :へえー。そうか、そうか。何でも一番
ゲスト:はい。
MC :ビックリしたのは、
ゲスト:はい。
MC :鹿、鹿の求愛行動に驚かれたという
ゲスト:そうですね、あの、雄は秋になると、あの、発情期
MC :うん。
ゲスト:恋の季節になるんですけれども
MC :はい。
ゲスト:あの、アピールするために、沼田場っていう泥の、
あの、ある水溜まりみたいなところに
MC :へえー。
ゲスト:行って、そこで、排尿するんですね。
MC :ええ。
ゲスト:で、その泥の中で自分がゴロゴロころがって、
自分の体をその泥とか臭いとか全部付けて
MC :ええ。
ゲスト:で、それが、もうすごく雄鹿にとっては、
真剣にオシャレしてるんですけれども
MC :はい。
ゲスト:まあ、人間の雌である私にとっては、
もう体臭もアンモニア臭もして、全然魅力的ではないんです。
MC :え、何、それが求愛行動?
ゲスト:そうなんです。
MC :ま、いわゆるオーデコロンみたいな感じですか?
ゲスト:そうみたいですね
MC :えへへへへ。
ゲスト:はい。
MC :それ、おかしいですわ。
ゲスト:そう。フェロモンみたいですね。
MC :あはははは。
ゲスト:はい。
MC :そりゃ、それまではずっとこう、
ゲスト:はい。
MC :写真撮りながらつぶさに見てこられたんですか。
ゲスト:はい。そうですね。
MC :見たことあるかな、みんな、そんなの。
ゲスト:うーん。
MC :秋の修学旅行行ったら、見られるか
ゲスト:はい。
MC :もし、来年の秋ぐらいに修学旅行行くキッズいたら、
是非チェックしてよぉ。何、沼田場
ゲスト:そうですね。
MC :沼田場で、
ゲスト:はい。
MC :いやー、もう、もう
ゲスト:泥ん中で転がってます。
MC :いやー。はははは。何かね、鹿って、あのー、
僕ほんと鹿児島と北海道で暮らしてたんで、
もう、ほんと鹿のメッカみたいなものですよ。
ゲスト:そうですね。
MC :そうすると、鹿と人間の共生ってすごく難しくて、
ゲスト:うーん。
MC :鹿はいわゆる害獣、
ゲスト:うん。
MC :人に危害加える
ゲスト:うん。
MC :後は、あの、が、害獣っていうか、ま、人間のね、農作物食べたりとか
ゲスト:うん。
MC :鹿がみかん食べちゃったとか
ゲスト:うん。
MC :いわゆる害獣の範疇になってるん
ゲスト:うん。
MC :ですけど、
ゲスト:うん。
MC :鹿と人との共存て
ゲスト:うん。
MC :ずっと撮影されて何か
ゲスト:はい。
MC :考えることあります?
ゲスト:そうですね。今、全国で36万頭ぐらい鹿が、
こう、害獣駆除や猟で殺されてまして
MC :はい。
ゲスト:で、ま、そういう意味で、非常に、あのー、同じ鹿なんですけれども、
奈良公園だと特別天然記念物になっていて、
あのー、それ以外の地域では、ちょっと害獣として
MC :うーん。
ゲスト:扱われるっていうのは、
MC :あ、そうか
ゲスト:鹿目線に立つと、同じ動物なのになって、
思ってんじゃないかなと思いますねぇ。
MC :格差が
ゲスト:そうですね。
MC :あるわけですね。
ゲスト:はい。
MC :あーー、なるほどね。
ゲスト:うーん。
MC :鹿には悪気はないのにねって
ゲスト:そうですね。
MC :感じですよね。いや、勉強になりましたね。
ただ、一番の驚きは、鹿の角が勝手に落ちるっていう
ゲスト:んふふふふ。
MC :基礎情報知らなかった。もう、10年やってんのに、この番組。
また、よろしくお願いします。
ゲスト:はい。ありがとうございます。
MC :はい。今週の「サイコー」は、鹿写真家の石井陽子さんでした。 -
「鹿の科学 パート1」 ゲスト:石井陽子さん
2020/01/01 Wed 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
鹿写真家の石井陽子さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :鹿写真家。鹿専属ですか。
ゲスト:そうです、鹿専門です。
MC :ほー。鹿専。
ゲスト:うっふふ。
MC :えー。
ゲスト:はい。
MC :石井さんは山口県のお生まれで、青山学院大学文学部をご卒業後、
あ、4年前から、奈良や宮島など広島県ですね。
人の町に住む鹿を写真に収めてらっしゃるということで、
リトルモアから写真集「しかしか」という、写真集おめでとうございます。
これ、すばらしいですね。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :拝読しました。いや、拝見しました。すごいですねぇー。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :あのー、奈良いくでしょみんなね。修学旅行は、中学になったら行くか?みんな。
とりあえず小学校は日光?ほいで中学でだいたい奈良行く?そしたら奈良公園の鹿見るよね。
宮島はまだ行ったことないかもしれないね、みんなね。
あのー、東海道新幹線でずーっと、広島まで行って、そっから宮島ってね、
フェリーで渡る島なんだけど、この奈良、それから宮島。ふーん。
さあ、これ写真、何点ぐらい、入ってるんですか?この「しかしか」には。
ゲスト:68点。
MC :68点。
ゲスト:はい。
MC :色んな特徴のある、
可愛いものもあれば、ちょっと迷惑なものもあるんですけれど
ゲスト:あはっ。
MC :だって、ともすれば、ひ、鹿がね、
お店の物食い散らかしそうな写真もあるんですけど、
ゲスト:うふふ。
MC :でも、実際、奈良公園で見ると、そういう被害ないですよね。
ゲスト:そうですね。やっぱり
MC :ほー。
ゲスト:あのー、鹿せんべいの
MC :ええ。
ゲスト:売店とか、
MC :ええ。
ゲスト:お土産物屋さんの言うことは聞くー、感じですね。
MC :あっ、何、
ゲスト:はい。
MC :鹿はちゃんと教育されてるんですか?
ゲスト:そうですね、共犯関係みたいな
MC :人間が金払って
ゲスト:うーん。
MC :買ったせんべいしか食うな!ってことですかね。
ゲスト:そうですね。躾られてます。
MC :あっははは。分かってんだね。
ゲスト:でも、野生動物なんですけど、
MC :ええ、ええ。
ゲスト:はい。
MC :あ、基本野生なんですか?
ゲスト:野生ですね。
MC :あっ、あの奈良公園
ゲスト:はい。
MC :の鹿は、
ゲスト:はい。
MC :あのー、もう、な、何、奈良市民とか、
ゲスト:はい。
MC :修学旅行生の
ゲスト:はい。
MC :共有財産じゃなくて、あくまでもあれは、野生なんですか。
ゲスト:そうですね。位置づけとしては
MC :人間界に降りてるけど野生。
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。そもそも、その、鹿専になった、鹿写真家になったきっかけは何でしょうか。
ゲスト:あの、2011年に、
MC :はい。
ゲスト:あのー、仕事で奈良に行ったんですけれども
MC :はい。
ゲスト:せっかくなので、写真を撮ろうかなと思って
MC :はい。
ゲスト:朝、出かけてったところ、偶然交差点の真ん中に、
鹿のカップルがいるのを見かけまして、
MC :あ、鹿のカップル。
ゲスト:はい。誰もいなくって、鹿だけがいて
MC :交差点の真ん中に
ゲスト:そうなんです、
MC :えー、鹿のカップルが
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:で、それを見たら、何かこう、人間がいなくなった街を鹿が占拠したような、
MC :はい。
ゲスト:イメージが見えて、何かそのビジョンを、
写真でずっと表現できたらいいな、と思って、撮ってます。
MC :来ました、今。僕も今、入ってきました。
もう、人っ子一人いない、その街に、人間が造った街に野生の鹿が、
ゲスト:はい。
MC :カップルで
ゲスト:はい。
MC :うーん。それでいいなぁと思ったんですか。
ゲスト:うーん、はい。
MC :う、それまで、写真の心得はあったんですか?
ゲスト:そうですね、あの、写真を始めたのは、10年前
MC :はい。
ゲスト:なんですけれども、あのー、初めてマダガスカルに、旅行に
MC :おー、
ゲスト:行くことにした時に、
MC :はい。
ゲスト:せっかく、そんなに遠くに行くことになったので、
MC :はい。
ゲスト:一眼レフカメラを買おうと思って、
MC :はい。
ゲスト:で、あの、旅行の3日前に、カメラ屋さんに行って、
で、行って現地で撮ったら、意外と、あの、今のカメラ優秀なので、
MC :はい。
ゲスト:楽しく撮れて、それ以来、写真にはまってます。
MC :へっ。マダガスカルってアフリカの
ゲスト:そうですね。
MC :あのー、大陸の
ゲスト:はい。
MC :右斜め下の方にある、
ゲスト:はい。そうです。
MC :細長い島ですよね。
ゲスト:そうですね。はい。
MC :そこは、えっ、観光で?
ゲスト:はい。あの、ワオキツネザルとか、シファカとか
MC :あ、
ゲスト:あのー、固有種の動物がすごく多い島で、
MC :ええ。
ゲスト:で、あの、当時から動物は好きだったので、
MC :ああー。
ゲスト:撮影に、まあ、当時は撮影は意識してなかったんですけども
MC :ええ、ええ。
ゲスト:あの、行ってみたら写真に夢中になっちゃったんです。
MC :なるほど。
ゲスト:はい。
MC :そうか、そうか。
ゲスト:はい。
MC :あの、島だから、
ゲスト:はい。
MC :そこの島にしか生息していない、
ゲスト:はい。
MC :動物がいた。
ゲスト:そうですね。
MC :これ、写真
ゲスト:アイアイとかもいる島ですね。
MC :うーん。その中で
ゲスト:はい。
MC :鹿になったのは、
ゲスト:はい。
MC :奈良に行ったことが、きっかけ。
ゲスト:そうですね。
MC :きっかけっていろんなところにあるんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :で、4年前ていうと、つい最近じゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。
ゲスト:4年半ぐらいになりますね。
MC :はい。
ゲスト:2011年3月からです。
MC :うーん。で、鹿、鹿のよさ、ま、
ゲスト:はい。
MC :ほんと写真見ると、この可愛いなぁっていう、
これ、よく小鹿のバンビっていうじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :で、白い斑点ついてますよね。
ゲスト:はい。
MC :だけど、大人の鹿って斑点ないですよね。
ゲスト:いや、実はあるんです。
MC :ええっ、そうなんですか?
ゲスト:はい。あの、季節によって
MC :ええ。
ゲスト:毛の色が変わるんですね。
MC :あ、季節によって色
ゲスト:はい。
MC :変わるんですか?
ゲスト:はい。
MC :鹿?
ゲスト:そうです。
MC :へえー。
ゲスト:あのー、春から夏にかけては、
MC :ええ。
ゲスト:こう、あの、毛並みが、だんだん明るい茶色で、 白い斑点が出てきて、
MC :はい。
ゲスト:雄とかでも、おっきい大人の雄とかでも、そういうバンビ柄んなってます。
MC :へえー。
ゲスト:で、
MC :小鹿が斑点じゃないんですね。
ゲスト:はい。
MC :へえ、おっきな大人もバンビ名乗ってるやついんるですね。
ゲスト:そうですね。
MC :俺、バンビだよって。
ゲスト:ははは。
MC :春から夏は
ゲスト:はい。
MC :俺もバンビだぜって
ゲスト:はい。で、
MC :へえー。
ゲスト:秋から冬になると毛の色が、もっと濃い茶色になって
MC :うん。
ゲスト:で、あの、もっと落ち着いた感じになってくるので、
MC :へえー。
ゲスト:こう、見せると、初めて見せ、見せた方は違う種類?って聞かれ
MC :あ、
ゲスト:るんですけど、季節の違いです。
MC :ちょっとすみません。
ゲスト:はい。
MC :基本的なことなんですけど、
ゲスト:はい。
MC :鹿の種類ってどれぐらいあるんですか?
ゲスト:あ、えっと、鹿の種類はですね、現在世界で生きてる鹿の種類が、
17属から19属で、三十数種、がその中に属してるんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、日本にいるのは、外来種のキョン以外は、
あの、すべてニホンジカという種類で、で、その中にエゾシカとか、
ホンシュウジカ、キュウシュウジカ、マゲシカ、ヤクシカ、
ケラマジカ、ツシマジカっていう、7つの亜種がいます。
MC :おおー。あっ、えっ、ちょっと待って下さい。
ゲスト:はい。
MC :僕、僕、春まで北海道にいたんですけど
ゲスト:はい、はい。
MC :エゾシカを見てて、
ゲスト:はい。
MC :これ、エゾシカと思ったんですけど、
ゲスト:はい。
MC :それは、ま、エゾシカっていう名前は付いてるけれど、
ゲスト:はい。
MC :基本はニホンジカっていう、一つのカテゴリーで
ゲスト:そうですね。
MC :北海道から
ゲスト:はい。
MC :沖縄までニホンジカ。
ゲスト:そうです。
MC :知らなかったです。
ゲスト:はい。
MC :えーっ。ケルマジカってあったけど、
ゲスト:はい。
MC :ケルマって日本の一番南側の
ゲスト:そう、沖縄ですね。
MC :はい。ですよね。
ゲスト:はい。
MC :その鹿まで、含めると
ゲスト:はい。
MC :全部ニホンジカのカテゴリーになってる。
ゲスト:そうですね。その中で、亜種に
MC :ほー。
ゲスト:また分かれてるんです。
MC :亜種によって特徴が違うんですか。
ゲスト:そうですね、
MC :うん。
ゲスト:あの、やはり北海道のエゾシカは非常に大きくて、
MC :はい。
ゲスト:あの、140kgぐらいあるんですけれど
MC :どっしりしてました
ゲスト:そうですよね。何か。
で、あの、南九州のマゲシカとか、ヤクシカは40キロぐらいですし、
MC :はい。
ゲスト:沖縄のケラマジカだと30キロぐらいしかないんです。
MC :ほ、あ、ちっちゃい。
ゲスト:ちっちゃいですね。
MC :え、南に行くと発育が悪いんですかね。
ゲスト:あはは、あの、何か、こう、恒温動物だと
MC :ええ。
ゲスト:同じ種類でも、寒い地域に住んでいるものほど、
動物の体重が大きくなるっていう、ベルクマンの法則というのがあるそうなんです。
MC :え、寒いじ、場所に
ゲスト:はい。
MC :行くと、
ゲスト:はい。
MC :体重、大きくなる?
ゲスト:はい。
MC :ベルクマンの法則?
ゲスト:はい。
MC :北海道はそんなデブいたっけなぁ。
ゲスト:うふふふ。
MC :あんま印象ないなぁ。あれ?
ゲスト:んふふ。
MC :で、でも、何か
ゲスト:うーん。
MC :そう、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :で、南の方に行くと
ゲスト:はい。
MC :やせてる?
ゲスト:そうですね。
MC :ほー。
ゲスト:あの、痩せてるっていうか、小さくて、
MC :ちっちゃい。
ゲスト:はい。
MC :おーー。
ゲスト:ま、結局、温暖な所にいると、あの、体温を維持する時に
MC :うーん。
ゲスト:あの、放熱をしていかなければいけないんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:体重当たりの体表面積が大きくないといけないので、小型な方がいいんですね。
MC :なるほど、はい。
ゲスト:ですけれども、寒い地域に行くと
MC :うん。
ゲスト:今度、熱は簡単に奪われてしまうんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:体温を維持するためには、あの、
体自体が大きい方が有利になるっていうのが、この法則だそうです。
MC :なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :だから、エゾシカは140キロ
ゲスト:そうですね。
MC :ケラマジカは30キロ
ゲスト:はーい。
MC :後ね、カモシカっていうじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :カモシカっていうのは、その、だからニホンジカとは違うってこと
ゲスト:あれは、何か鹿科ではなくて、牛科なので、
MC :うそでしょ!
ゲスト:鹿じゃないから
MC :ちょっと待って下さい。
ゲスト:はい。
MC :えーっ!ちょっと、えーっ。だって、えっ、
何となくカモシカって、何かこう、美しい女性の代名詞に、な、なるじゃないですか。
ゲスト:ああ、ああ、そうですね。
MC :でも、牛科?
ゲスト:らしいですよ。
MC :ええっ。
ゲスト:ま、あの、ま、鹿も反芻動物で、そういう意味では牛と同じで
MC :あ、そう
ゲスト:胃が4つあって、あの、構造は似てますね。
MC :鹿の胃が
ゲスト:はい。
MC :4つあるんですか?
ゲスト:はい。
MC :牛と同じで?
ゲスト:はい。
MC :鹿、モグモグしてますね、確かに
ゲスト:してます、してます。あれは、反芻してるんです。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :あ、そうなん
ゲスト:はい。
MC :ですか
ゲスト:うん。
MC :でも、カモシカは、
ゲスト:はい。
MC :牛科だから、
ゲスト:はい。
MC :ニホンジカの
ゲスト:はい。
MC :カテゴリではちょっと違う
ゲスト:違うんですね。
MC :へえー。まあ、勉強に
ゲスト:はい。
MC :なりましたねぇ。
ゲスト:いえいえ。
MC :えっ、もう、お仕舞?今日。あ、そうですか、分かりました。
じゃまた来週お話伺いたいと思います。
今週の「サイコー」は、鹿写真家の石井陽子さんでした。ありがとうございました。 -
「テニスの科学 パート2」 ゲスト:柄川昭彦さん
2019/12/01 Sun 12:00 カテゴリ:その他MC :今週のサイコ―もですね前回に続きまして
科学ライターの柄川昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:あ、こんにちは。よろしくお願いします。
MC :お願いします。前回テニスに関してね、
色々詳しい話伺いましたけどいかに過酷なスポーツか、
いかに錦織圭選手が大変かと、伺ったんですけれど。
ちょっと具体的な数字で見ていきたいと思います。
ゲスト:うん
MC :まずあのー、スピードですね。
ゲスト:はい
MC :あのー、スマッシュとか
ゲスト:うん
MC :あとサーブ
ゲスト:うん
MC :サービスエースなんてありますけど
ゲスト:はい
MC :あれ早いなーって思いますけど
ゲスト:早いですね。あのープロの大会を見てると、
よくあのー、球速が表示されてますよね。
MC :おお、はい
ゲスト:サーブなんかですともう、200キロを超える選手はざらですね。
MC :あれ他のスポーツと比べるとよく分からないんですけど
200キロってどんな感じなんですか?
ゲスト:200キロ、あのー、プロ野球の大谷投手の
MC :おー
ゲスト:あのー、球が160キロとか
MC :はい
ゲスト:161キロですよね。
MC :はい
ゲスト:それに比べるとサーブはもう200キロを超えてますから
MC :そうか
ゲスト:そのー、最初にボールが飛び出した時の速さは圧倒的に早い訳ですね。
MC :ほお、それをラケットで打ち返してるって事ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :大谷投手よりも早いボールを
ゲスト:そうですね
MC :ラケットで打ち返してる。
ゲスト:あのー、早い選手になると220キロとか
MC :へー
ゲスト:230キロとか
MC :えーうおー
ゲスト:でも錦織選手はリターン上手いですからそういうのでも返せるわけですよね。
MC :よく返せるなと思って。だってバッターはバッターボックスにいるからね。
ゲスト:ええ
MC :そのストライクゾーンのボールを振ればいいんだけど
ゲスト:はい
MC :サーブってどこに来るか分からなくて
ゲスト:そうですね
MC :つまりそれで移動しなくちゃいけない訳ですよね。
ゲスト:ええ、確かに野球でいえば右打ちと左打ちどっちに来るかも分からない状態で
MC :そうなんですよ
ゲスト:移動しなくちゃいけないと、なんか難しいですよね。
MC :うわあ、それすごいですね。
ゲスト:ただ、そのー、テニスのその、球速の表示ってのは
MC :はい
ゲスト:ラケットで打った直後のあのー、ところ測定してますから
MC :はい、はい
ゲスト:実際その、えっと、野球のボールに比べるとテニスのボールってのは軽いですし
MC :はい
ゲスト:まわりがフェルトですし、えー、空気の抵抗大きいので
MC :うん
ゲスト:飛んでる間にもまあ、野球のボールに比べるとブレーキは大きいんですね。
MC :ほお
ゲスト:で、なおかつ、一回バウンドしますから
MC :あー
ゲスト:あの、地面に接した時には相当大きなブレーキがかかるんですね
MC :な、なるほど
ゲスト:ですから、あのー、もうみな、こう、そういう物だと思って見てるので、
あの、バウンドしたボールが遅くなったようにはとても見えない
MC :見えない、見えない、
ゲスト:見えないですよね
MC :同じように見えます。
ゲスト:実際に測定するとですね
MC :ええ
ゲスト:ま、かなり遅くなって
MC :あ、どのくらいですか?
ゲスト:なんか半分近くまで
MC :えっ、そうなんですか
ゲスト:ええ
MC :じゃあ200キロだったら
ゲスト:ええ
MC :100
ゲスト:100何十キロ
MC :100キロちょっと
ゲスト:そうですね。
MC :ま、かといってでもその
ゲスト:ええ
MC :最初の200キロに対して、あのー、
レシーブするポイントに移動しなくちゃいけない訳ですから
ゲスト:ああそうですね、それにバウンドするまでは、
まあ相当なスピードで飛んで来る訳ですし
MC :うーん
ゲスト:バウンドしてから打つまでの距離ってホント短いですから
MC :そうですよね。
ゲスト:そこはちょっと遅くなっててでもですね、ま、大変なのは間違いないと
MC :へえー
ゲスト:いう事だと思いますね。
MC :そうかそうか。
ゲスト:うん
MC :後はあの、スマッシュとかあるじゃないですか
ゲスト:はい
MC :あれ思いっきりポンって
ゲスト:そうですね、スマッシュもやっぱりあの、早くなりますね。
MC :うーん
ゲスト:やはり普通のストロークは
MC :はい
ゲスト:相手の選手がそれこそ百何十球と打ってきた球を
MC :はい
ゲスト:打ち返しますから、なかなかスピードが出ないんですね
MC :はい
ゲスト:あのー、えー、たいていひゃく、早いときでも160キロとかですね170キロ台
MC :はい
ゲスト:ぐらいで大体ストローク勝負がつく感じなんです。
サーブとか、あるいはゆるい球があがってるスマッシュとか
MC :はい
ゲスト:を、叩くときの方がスピードは速くなるみたいですね。
MC :うーん
ゲスト:でも普通のストロークの時も160キロですから
MC :はい
ゲスト:大谷投手が力一杯投げた球ですから
MC :そうですよね
ゲスト:それをコートのはじに打たれたら
MC :いやあ
ゲスト:まあ辛いですよね。ハハ
MC :ですよね。選手って、え、サーブ打ってポンポンって決めるまでの間って
ゲスト:ええ
MC :何秒くらい
ゲスト:そうですね
MC :考える時間ていうか、反応時間ていうんですかね
ゲスト:はい。もしほんとに200キロの、
時速200キロのボールが200キロのまんま飛んでくるとですね
ベースラインからベースラインまでは、確か0.3秒もかからないくらいの
MC :へえー
ゲスト:ただ、バウンドしますしスピード遅れていますから、
相手が打ってからですね、ま、サーブの場合ですと大体0.6秒とか0.7秒くらいで
打ち返さなくちゃいけない、っていう事ですね。
MC :いや、そ、そうか、いや、でもほんと野球と同じですね。
ゲスト:そうですね、もう考えてる暇はないって
MC :ほおー、おー
ゲスト:いう事でしょうね。見た瞬間何かを判断するか、あるいはですねその、
打つフォームですとか、あのー、ま、ストロークであれば
MC :はい
ゲスト:相手がまあ、こう打ってくるときに、
どこに打ってくるのかを、ま、大体予測が付くと
MC :はい
ゲスト:で、予測が付くと選手達は一から何かを考えて体を動かすよりも、
この辺りに飛んできたボールは、こういう運動をすればラケットに上手く当たって
上手く飛んでくっていうのを、もう覚えてる訳ですね。
MC :勘どころで打ち返す感じですかね
ゲスト:そうですね、だから脳からの指令が全て出てるっていうよりも、反射的に
MC :はい
ゲスト:体が動いてる、ま、その位まあ、トレーニングを重ねてると思いますね。
MC :だからいわゆるバレーボールとはちょっと違う訳ですね。
ゲスト:ええ違う訳です、えっとそうですね、はい
MC :おーー
ゲスト:で、あのー、そういう、それに加えてこの辺りに来るだろうとかですね
MC :はい
ゲスト:この位の速度のボールが来るだろうってのも、まあ、予測してますから
MC :はい
ゲスト:あの、反対側に打たれた時とかですね
MC :はい
ゲスト:あの強い球が来ると思ってたのにドロップショットを打たれたとかっていうと
MC :はい
ゲスト:えー、ま、一歩も動けないという状態がありますね
MC :はい、はい、はい
ゲスト:あれは明らかに予測していたのが違ったっていう事ですね。
MC :うーん
ゲスト:ですからその予測があるからこういう早いスピードのボールにも打ち返せてるんだ、とも
MC :なる、なる、なるほどなるほど
ゲスト:いえると思いますね。
MC :ある程度の事をイメージし予測して
ゲスト:ええ、ええ
MC :それに構えてるっていうことですね
ゲスト:それに構えてるんですね
MC :あー
ゲスト:一番予測してそうなのはあのサーブの時ですよね
MC :はい
ゲスト:特に相手がすごいビッグサーバーで二百何十キロくる
MC :へー
ゲスト:なると、もう、どちらかに来るだろうと予測して
MC :うん
ゲスト:構えてるので
MC :うん、うん
ゲスト:あの、そういうビッグサーバーのサーブがもう一歩も動けずに決まるっていうのは、
予測がはずれてる
MC :なるほど
ゲスト:とも言えそうですよね。
MC :ゴールキーパーの
ゲスト:ただ早い訳じゃなくて
MC :PKと同じですね
ゲスト:はは、PKと同じです
MC :動けないっていう
ゲスト:逆に飛んじゃったとかですね
MC :はい、へー
ゲスト:そうですね
MC :後なんかテニスの見方として、これからどうやって見ていけばいいですかね、
ポイントとしては
ゲスト:えーと、私はやっぱり錦織選手のファンですから
MC :はい
ゲスト:錦織選手の技術っていうのは、やっぱりちょっとなんか興味深いと思いますね。
MC :うんうん
ゲスト:例えばあのエアーケイって
MC :はい
ゲスト:簡単に打てそうな気がしますよね。
MC :はい
ゲスト:あの、ただ飛んでるだけで
MC :はい
ゲスト:やってる事はえーと、コート上で打ってるのと同じだろう
MC :はい
ゲスト:と、思いますけども、実際にこう体が空中に浮いてるのとですね
MC :うん
ゲスト:両足が地面についているのとでは全く違って
MC :はい
ゲスト:地面に両足がついてると足でコートに力を加えてその反作用で体を回したり
MC :はい
ゲスト:する訳ですね
MC :はい
ゲスト:ひねる訳ですね
MC :はい
ゲスト:空中に上がってますとその反作用が使えませんから
MC :はい
ゲスト:基本的に、あのー、飛び上がった錦織選手の重心はですね、
きれいな放物線を描いて交点を落ちるだけなんですね
MC :うん
ゲスト:間に出来る事はそんなにないはずなんですけれども
MC :はい
ゲスト:あれだけ強い球をを打てるのは
MC :はい
ゲスト:あのー、ラケットをですね、こう、まあ、とりあえず後ろから前に振る訳ですけども、
振る時には何かはですね、前から後ろに動いてないと重心が変わっちゃいますから、
前に倒れてしまうとかですね、なるんですね。
あるいは早く振れないとかって事になるんですけども、
錦織選手のエアーケイはですね、左足で踏み切るんですけども
MC :うん
ゲスト:踏み切った時に、右足が少し前に出てるんですね
MC :はい
ゲスト:でその、み、その右足をですね、後ろに引きながら右手を前に振ってるんですね。
MC :はい
ゲスト:で、その足を後ろに引くって動きと、腕を前に引くって、
あのー、動かすっていう動きがですねちょうどバランスが取れてるので、
力強くあのー、スイング出来るんですね。
MC :ちゃんとやっぱりエアーやっても意味がある力強い
ゲスト:そうですね
MC :ボールが打てるんですね。
ゲスト:はい、あれが、あの、足の動きがですね
MC :ええ
ゲスト:前から後ろにっていう動きがないと
MC :はい
ゲスト:あれだけするどいスウィングはとても出来ないので、
あんなすごいショットは決まらないんですね。
MC :じゃあ地面に設置してる方が実は強いショット打てるんじゃないかと僕は思ってたけど
ゲスト:あ
MC :錦織選手のエアーはやっぱり
ゲスト:そうですね
MC :あの、足の動きを見ると
ゲスト:はい
MC :意味のある
ゲスト:そうなんです
MC :ほー
ゲスト:だから普通だったら空中に浮いたら強い球打てないんですけども
MC :はい
ゲスト:そこで強い球を打つ為に、えー、錦織選手は上手く体を使ってる訳ですね。
MC :うーん
ゲスト:その、前に出して右足を後ろに振るっていうのが、
その打った瞬間の、その、技術なんですね。
MC :なるほどね
ゲスト:エアーケイって
MC :うーん
ゲスト:簡単そうに見えて
MC :いや、出来ないですよ。
ゲスト:ははは
MC :いや、よくやってる子
ゲスト:そうそう
MC :真似してる子いるけど、ろくなボール打てないですから
ゲスト:そうなんです。
MC :やっぱりあれは錦織選手だから、まあいわゆる体幹とかバランスとか
ゲスト:ええ
MC :そういうのがあって出来てるんですかね。
ゲスト:見てると出来そうですけど
MC :うーん
ゲスト:やってみると出来ないんですよね。
MC :ねえー
ゲスト:今のコツで
MC :ええ
ゲスト:きっと出来るようになると思います。
MC :はい、なんかやってみたくなってきました。みんなもやってみて。
ええ。あ、お時間ですね。今週のサイコ―は科学ライターの柄川昭彦さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「テニスの科学 パート1」 ゲスト:柄川昭彦さん
2019/12/01 Sun 12:00 カテゴリ:その他MC :さ、今週のサイエンスコーチャー略してサイコ―は、
スポーツを取り上げる時はですよ、お馴染みになりました
科学ライターの柄川昭彦さんです。こんにちは
ゲスト:どうかよろしくお願いします。
MC :お願いします。去年お見えの時は野球の話伺いましたけれど、
今回テニスですよ。
ゲスト:うーん
MC :テニス
ゲスト:テニスもね
MC :ええ
ゲスト:あのー最近錦織選手が大活躍ですから
MC :ええ
ゲスト:しばらく私、あのーテニスあんまり見てなかったんですね。
MC :ほおー
ゲスト:あの、昔、あのテニスのラケットが木だった、木で
MC :木、おー僕始めた時木でした、木。
ゲスト:あの、プロの、えーとウィンブルドンとかですね
MC :はい
ゲスト:大会見るの、テレビ見るのが大好きでしたけど
MC :はい
ゲスト:しばらく見てなくて
MC :うん
ゲスト:で、ここ数年錦織選手が
MC :うん
ゲスト:活躍するようになって、ま、にわかファンですね、ははは。
MC :でもしっかりとこう語って頂くという事ですけど
ゲスト:はい
MC :あれ、ほんと今ラケットの話ですけど
ゲスト:ええ
MC :今のキッズは木のラケットなんか知らないですよね
ゲスト:そうでしょうね、木のラケットって見ようと思ってもどこにもねえ
MC :うん
ゲスト:まず無いですし。で、私はテニスのラケット木で打ったことがありますね。
MC :はい
ゲスト:あの、最初にテニスやった時はラケットが
MC :はい
ゲスト:木でした。
MC :僕はなにを隠そう小学校、中学校とテニス習ってました。
ゲスト:あ、そうですか
MC :はい、テニススクールで習ってて
ゲスト:はい
MC :多分当時としては
ゲスト:ええ
MC :あのー、ちょ、ちょっとこう
ゲスト:ええ
MC :あの、ハイカラな
ゲスト:そうですよね
MC :小学生だったかもしれませんね。
ゲスト:その頃、その頃っていうか、
あの、小学生でテニスって今はねすごく増えてるって話ですけど
MC :そうなんです、はい
ゲスト:へえー、強かったんですか?
MC :うん、そこそこ強かったんで。
ゲスト:ああ
MC :千葉県の大会にも出して頂いてですね
ゲスト:あ、そんなに
MC :ええ、そうなんです。ちょっとこれ軽く自慢なんですけど
ゲスト:ええ
MC :だからあんまりそのテニスを科学的な見方をした事無いんですけれど
ゲスト:はいはいはい
MC :でも今にして思うとね、僕ねテニスやってる時に何が一番興奮するかって
ゲスト:ええ
MC :新しいボール開ける時にね
ゲスト:はいはい
MC :缶を開けるんです。
ゲスト:あ、そうですよね
MC :で、多分ねスポーツの中で
ゲスト:ええ、ええ
MC :あんな大事に缶に入ってる
ゲスト:そうですよね
MC :無い、無いですよね、テニスボールくらいじゃないかなと思って
ゲスト:缶からボールが出てくるって
MC :そうなんです
ゲスト:缶詰ですからね
MC :そうそうそう
ゲスト:ふっふっふっ
MC :そうなの、ボール二個、たかが二個のボールが
ゲスト:ええ
MC :缶詰になってるんで、すごく高級感があるじゃないですか
ゲスト:ええ
MC :あれそもそもなんでですかね
ゲスト:そうですね、あれ、ほんとにテニスだけですね。
MC :ええ
ゲスト:テニスのボールっていうのは、あのー中がゴムのボールで
MC :はい
ゲスト:まわりにフェルトが
MC :はい
ゲスト:黄色いフェルトが張ってあるんですね。
でそのゴムの中の気圧がですね大体2気圧になってるらしい。
ま、窒素っていうあの気体が入ってるんですけども
MC ::あ、中に?ボールの
ゲスト:はい、はい。で、2気圧になってるんですね
MC :はい
ゲスト:で普通のこの大気っていうか、まあ空気中の圧力っていうのが1気圧ですから
MC :はい
ゲスト:えっとボールの中の空気がですね、
そのままほおっておくと少しずつ、ま、どこにも穴はないんですけども
MC :はい
ゲスト:少しずつ漏れちゃって
MC :へえー
ゲスト:あの、気圧が下がっちゃうんですね。
MC :ええ
ゲスト:そうするとボールの弾みが悪くなるので、それじゃ困る訳ですね。
それでその缶詰の中に入れて、缶の中の空気を2気圧にしたんです。
ボールの中と同じにしたんです。
MC :へえー
ゲスト:そうするとボールの中の空気が外に出てこないので、
いつまでもこのフレッシュな状態が保てると
MC :そこまでやっぱりこう慎重なあれなんですね
ゲスト:すごいですね
MC :ボールの扱いっていうのは
ゲスト:だからボールがなま物ってことですか
MC :そういうことですよね
ゲスト:あのー、冷蔵から出しとくと傷んじゃうみたいな感じで
MC :うーん
ゲスト:缶から出してそのままにしとくと、傷んじゃうんですね。
MC :そうそう、だから不思議や。でもやっぱりあの一回開けちゃうと
ゲスト:と、
MC :若干こう空気漏れてくるってことなんですね。
ゲスト:そうなんでね
MC :あの、ボールでも
ゲスト:はい、あと中の気圧が高いので
MC :はい
ゲスト:ゴムがずーっとこう、えー、内側から押されるので
MC :ふん
ゲスト:ま、伸びちゃうんですね。
MC :はあ
ゲスト:なんでそれもわずかに関係するって言われてますね。
MC :確かにテニスボールはあれー、ソフトテニスは空気
ゲスト:空気入れる
MC :入れられるけれど
ゲスト:はい
MC :あのー
ゲスト:無いんですよね
MC :普通のボール、無いですもんね
ゲスト:ええ
MC :ピンポン玉とかと
ゲスト:はい
MC :同じですもんね、空気入れられない
ゲスト:入れられない
MC :中空気入ってるのに
ゲスト:ええ
MC :そもそもじゃああれは、フェルトの中がゴムになってて
ゲスト:ええ
MC :じゃあその、えー、気圧を安定させる為にわざわざ缶に入ってると
ゲスト:缶に入っていると、それで
MC :うーん
ゲスト:そうそうそう試合の時に、あの、
錦織選手達の試合見てても途中でボールがニューボールに
MC :ほお
ゲスト:変わる時がありますね
MC :はい
ゲスト:で、そのニューボールに変わった時は、
なんかその時にサーブを打つ選手が有利だって言われてんですね。
MC :へえー、フレッシュな時に
ゲスト:ええ、それが
MC :なんでですか?
ゲスト:やっぱりボールが
MC :うん
ゲスト:一番よく弾む時なので、早いサーブが打てるって事なんですよね。
MC :あ、やっぱ新しければ新しいほど
ゲスト:ほど
MC :開けたての方が
ゲスト:良いと
MC :えへへへ
ゲスト:その時にサーブをやる選手の方が有利だ
MC :うん
ゲスト:いう事みたいですね
MC :それはその試合中にやっぱりボールが劣化してくって事なんですか?
ゲスト:あ、そうなんでしょうね。
ですから私もテニスのボールってのはまわりがフェルトですから
MC :はい
ゲスト:フェルトが擦り切れてボールが傷むんだと思ってたんですけども
MC :はい
ゲスト:そうじゃないんですね
MC :ええ
ゲスト:それよりもやっぱ中の空気が、あのー、少しずつ出たり
MC :うん
ゲスト:ゴムがゆるんだりする事で、えー、ちゃんとした、
こう、弾み方をしなくなるっていうのが
MC :へえー
ゲスト:ポイントらしいんですよね。
MC :じゃあスコアにも影響してくる訳なんですね。
ゲスト:してくる。だからもう定期的にボールが、ニューボールが使われる訳ですね。
MC :いやー、これちょっと、よーくテレビ見とくとそれおもしろいですね、だから
ゲスト:そうですね、見てると
MC :うーん
ゲスト:あ、ニューボールですっていうのは
MC :ですね
ゲスト:アナウンス入りますね。
MC :そうそう、フェルト汚れたからじゃないんだ
ゲスト:じゃない
MC :ちょっとボールの中の
ゲスト:そうですね
MC :気圧が変化してるんで
ゲスト:ええ
MC :もういわゆる鮮度が落ちてるから変わったんだってこと
ゲスト:そうですね
MC :ははは
ゲスト:鮮度ですよね、野球みたいに泥が付いたからじゃないんですね。
MC :ですよね、へえー
ゲスト:あれはおもしろいですね。
MC :だから結構サーブ打つ前にポンポンポンポンやって
ゲスト:あー
MC :弾み具合とか
ゲスト:確かめるんでしょうね
MC :なるほど、いやあボール、いやあよく分かりました。
ゲスト:テニスのボールはほんとに特殊ですね。
MC :うん
ゲスト:はは、色んなスポーツのボールの中ではね
MC :そう考えるとテニスボールって
ゲスト:ええ
MC :テニスボールじゃない、テニスの時間って意外と長いので
ゲスト:長いんで、はいそうですね
MC :ボール交換も結構やらなくちゃいけない
ゲスト:あー、そうですね。特にプロ達はすごい勢いであのボールを打って
MC :はあい
ゲスト:打った瞬間こうなんか潰れてるって
MC :はい
ゲスト:いう状態ですからね。
MC :へえ、テニスってちなみに何時間ぐらい、
長い試合ってすごい長いですよね。
ゲスト:そうですね、あのー、去年の全米選手権ですかね
MC :はい
ゲスト:錦織選手も4時間何分って試合が
MC :そうそう
ゲスト:2回か3回あって
MC :腰が痛くて途中もうね
ゲスト:そうですね
MC :棄権する選手もいるくらい
ゲスト:ええ
MC :タフなスポーツですよね。
ゲスト:もう、なんか3時間を超えるのはざらですし
MC :はい
ゲスト:なんかあの5セットマッチの試合で世界で一番長い
MC :はい
ゲスト:試合が11時間05分っていうような
MC :ええっ
ゲスト:数年前のウィンブルドンらしいですよ。
MC :そう、11時間
ゲスト:ええ、結局なんか3日間に
MC :ええ
ゲスト:渡って
MC :ええ
ゲスト:夜やって、昼間やって、まあそれでも終わらず次の日になったっていう試合が
MC :へえ
ゲスト:あるらしいんです。それが一応世界最長という事になってる
MC :よ、よくね、プロ野球で6時間超えたっていうのが
ゲスト:はいはいはい
MC :ちょっとそれはねえ、全然、あの、人数が違うんで
ゲスト:あ、そうですね、はは
MC :一対一のスポーツで11時間とか
ゲスト:そうですね、まあずっと動いてるわけですからね。
MC :そうですよね
ゲスト:ええ
MC :かなりじゃあ、エネルギーも消費する訳ですよね。
ゲスト:そうですね、なんかあの、
テニスでどのくらいエネルギーを消費するかっていうのをこう調べてみると
MC :はい
ゲスト:ま、1時間あたり大体500キロカロリーから
600キロカロリーって言われてるんですね。
MC :ほおー
ゲスト:で、マラソンを1レース走るとですね
MC :はい
ゲスト:大体2000から2500カロ、キロカロリー位消費するんですね。
MC :え、マラソン1レースでもその位なんですか
ゲスト:そうなんです、ですから
MC :4000とか5000位いくかと思ったけど
ゲスト:あ、マラソン、まあ大体体重60キロで40キロメートルとかけると
6×4=24(ろくしにじゅうし)で2400と、ま、大体その位の
MC :あ、そんなもんですか
ゲスト:体重1キロ当たり、えー1キロメートル走ると1キロカロリーですかね
MC :ほお
ゲスト:消費するんで、ま、計算するとそう出るんですね。
MC :そっか、そっか、まあそれはでも、あと膝への
ゲスト:あはは
MC :負担ていうのもあるから
ゲスト:そうですね
MC :もっとなんか色々と
ゲスト:はい
MC :消耗しそうな気がしますね。
ゲスト:そうですね
MC :カロリー上はそれ位
ゲスト:位って事なんですね。まあテニスの選手は、
こう、コートを交換する時にまあ、ベンチに座って休めたり
MC :はい
ゲスト:とかしますけれども、マラソン選手は全力で走るシーンというのは
どこにも無い訳ですよね。
MC :はい
ゲスト:最初から最後まである一定の強度の
MC :ふんふんふん
ゲスト:えー走り方をずっとしてる。
でもテニスの選手たちはベンチで座ってる時間も確かにあるんですけども
MC :はい
ゲスト:でも走る時はもう全力で走ってますし
MC :はい
ゲスト:全力でサーブを打って全力でストロークを打つ訳ですよね。
そうすると運動の種類はマラソンとはかなり違うんですよね。
時間は同じ位としても。そう。
MC :そうとう瞬発力で、筋肉に負担かかりますよね。
ゲスト:そうですね、筋肉の損傷っていうのも全然違いますし、
使うエネルギー源ってのが
MC :うん
ゲスト:だいぶ違うんですね
MC :はい。もう、ひょっとしたらテニスってそう考えてみると最も過酷な個人スポーツ
ゲスト:そうですね
MC :かもしれないですね。
ゲスト:あの、スポーツの時間て短くなってますよね。
MC :はい
ゲスト:例えばラグビーも、あのー、フルにやると、
なんかテレビの枠に入らないから7人制ラグビーは
MC :うん
ゲスト:えーと、クォーターで、1クォーター
MC :15分とかですもんね。
ゲスト15分ですね
MC :はい
ゲスト:その点テニスはずーっと変わってないんですね、これ
MC :ルールもね
ゲスト:はい、4大大会5セットマッチっていうのはですね
MC :そうですよね
ゲスト:なかなか頭が固いというか
MC :うん
ゲスト:伝統を重んじるっていうんでしょうかね、はは
MC :うーん、いやあ
ゲスト:ウィンブルドンのせいだと思いますけど
MC :ははは
ゲスト:5セットマッチは変わらないので
MC :いやあ
ゲスト:すごいですね
MC :ちょ、ちょっと錦織選手もうちょっとしっかり見てかなくちゃ。
いやあ。あ、もう時間ですね。
ゲスト:はい
MC :また来週もお願いします。
ゲスト:あ、はい
MC :今週のサイコ―は科学ライターの柄川昭彦さんでした。 -
「水族館 パート2」 ゲスト:中村元さん
2019/11/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :さ、今週のサイコーもですね、日本でただ一人です、
水族館プロデューサーの中村元さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちはー。
MC :えー、日本唯一の水族館プロデューサーとして活動されている中村元さんは、
カラー出版から「水族館に奇跡が起きる七つの秘密」という著書をはじめ、
多くの出版物出してらっしゃるんですけれど、ま、前回伺ったのはー、
水族館プロデュース、実は目線は大人の女性の目線。
ゲスト:はい。
MC :大人の女性が興味を持つってことは、小学生の高学年ぐらいになるとみんな食いつくぞ!と。
ゲスト:絶対そうですね。はい。
MC :うーーん。いいお話でしたねー。
ゲスト:しかも男も全て
MC :はい。
ゲスト:食いつくんですね。
MC :はーい。だって結構だからそういう人たちが
世の中のブームみたいなものをだから牽引してく、いるのかもわからないですね。
ゲスト:そうですね。あの気持のいいものっていうのを一番先にわかる人達っていうのが、
あのー我々にとっても指針になりますよね。
MC :あー。
ゲスト:あっちの方向っていうのがこれからいいんだなっていうのがわかりやすいですよね。
MC :えー。大人の女性、みんなのお母さん方、というのもそういう世代だと思いますよ。
お母さんの言う事聞こうねって話かもわかりませんね。
ゲスト:ははははは。
MC :さあ、えー東京代表する水族館っていうと、やっぱりサンシャインの水族館ですよね。
ゲスト:有難うございます。そうですねー。
MC :ぼ、うーん、僕がね子供の頃からあったんですよ。僕小学校の頃にサンシャイン60が出来て、
ゲスト:はいはいはい。
MC :その頃から水族館あったと思うんですよね。
ゲスト:えー。
MC :で、3年前の夏ですか?
ゲスト:はい。
MC :2011年
ゲスト:はい。そうですね。
MC :にリニューアルしたと。これが中村さんのプロデュースということなんですよね。
ゲスト:そうなんです。
MC :ぼくね、リニューアルしてから北海道在住になったんでー、
ゲスト:えー。
MC :行ってないんですよ。
ゲスト:行ってないですか。それは残念ですねー。
MC :行ってない人のために是非じゃあどういう魅力があるか
ゲスト:なる、なるほどー。行ってない人のためには言わないほうがいいんですけどね。
MC :あーーー。
ゲスト:ははは。
MC :そうですよね。そうなんですよね。
ゲスト:あっと驚くようになってるんです。
MC :え、はい。
ゲスト:あの、エレベーター上がった時からがもう違いますからー
MC :うん。
ゲスト:上がった途端にですね、あそこえっとサンシャインシティーの60の方じゃなくって
10階、11階のところのビルの方にあるんですね。
MC :低層階のところですね。
ゲスト:はい、はい。で、上がると10階の屋上の前に出るんですけど、
もうそこでいきなり南国の、あのーなんですかリゾート地のような雰囲気になってます。
MC :はい。
ゲスト:えっとまあホテルにあるような滝がザァーと落ちていても、
音と緑色と空の青の色があれば、もうそれだけで「あっ来てよかったな」と思うような
雰囲気になってるんですね。
MC :じゃ、かつてのサンシャインの水族館とは全然違うってことですよね。
ゲスト:全然違います、
MC :はい。
ゲスト:あのそもそもこちらはね天空のオアシスと名付けたんです。
MC :サンシャイン水族館は、今、天空のアオシスという
ゲスト:はい、そうです。
MC :別名が
ゲスト:そうです。そういう風にこうみんなから呼んでもらってます。
MC :でも今のその冒頭のね、入った瞬間のおもてなし感、
まさに天空のオアシス、そんなイメージですね。
ゲスト:そうなんです。だいたい水族館って海の横にあるから楽しいんですけれど、
もう池袋って海から遠すぎるじゃないですか、何にもないです、自然も、
それで、いやそうじゃなくて、もっと手軽に行ける海より
もっとオアシス感の強い場所を作りたいなっていう風に思ったんですね。
MC :はぁー、はい。
ゲスト:ちょっと疲れたらあのサンシャイン水族館に行こうか、
天空のオアシスを楽しもうっていう風に思って頂けるような感じにしたかったんですね。
MC :うーん。あーイメージ湧きましたね。
ゲスト:はい。で、特に都会の人って大人も子供も疲れてるじゃないですか、いろんなこう
MC :はい。
ゲスト:人が多すぎてとか、
MC :ごみごみしてて
ゲスト:ね、喉が渇くように、体が渇くんですよ。
MC :はい。
ゲスト:その渇いた体を潤す場所がサンシャイン水族館、ですねー。
MC :実際まもなく3年経ちますけれど、ま、来られる方、どういう世代の方が多いですか?
ゲスト:あ、もうすごく大人の方多くなったんですね、
昔は大人の率が75パーセントだったんですけど、今は85パーセント近いですね。
MC :あ、大人が10、1割増えてる。
ゲスト:そうなんです。
MC :はぁー。
ゲスト:で、子供さんも増えてます。キッズも増えてます。
でも、そもそもあのー日本の10パーセントぐらいしか子供どうせいませんからー、
だから大人が9割、子供が1割ぐらいになってくのが普通だと思ってるんです、僕は。
MC :はぁー。
ゲスト:で、みんなが水族館好きなのが大切ですよね。
はい。で、そうしないことにはお客さん増えないですね。
この水族館ももともと70万人ぐらいだったのが、
リニューアルして224万人、3倍になりました。
MC :3倍以上
ゲスト:はい。
MC :ほぉー。あっすごいことですねー。
ゲスト:はい。
MC :年間224万人
ゲスト:そうなんです。あんなちっちゃな水族館に大変なことです。ははは。
MC :いやー、そうですかー。あのこれからの方のためにちょっといくつか
ゲスト:あーそうですねー。
MC :ヒントとか魅力を教えて下さいよ。
ゲスト:はい、はい。
MC :ちなみに
ゲスト:はい。あのー、一つ結構有名なのがあのーその屋上でですね、
空を飛んでいるアシカ、アクアリングっていうんですけど、
そのリングの中にアシカの仲間がですね、くるくるくるくる
MC :えーっ。
ゲスト:これはねー、あのドーナツ、透明なドーナツ水槽が頭上にあるって考えて下さい。
MC :あーわかりました。で、アシカが泳いでいるのが見えるわけですね。
ゲスト:そうです。で、アシカたちは割と上からで見ると、
上から人を見ると人を怖がらなくって、中にはね人が、人を追いかけるアシカもいるし、
MC :ほぉー。
ゲスト:すっごいスピードで泳いでくれるのもいるんですよね。
MC :はぁー。
ゲスト:あとこれから夏にかけてはですね、夕方はアシカ寝ちゃうんでー
MC :えー。
ゲスト:その時にペンギンをあのそこで泳がせることもよくありますし、
MC :はぁー。
ゲスト:どちらも面白いですよ。
MC :とにかく頭上のリングに注目しろと、アシカかペンギンがいるよってことですね。へぇー。
ゲスト:そうですね。あと、室内に行きますとやっぱりあのー、
一番有名なのがーえーっと、サンシャインラグーンという、ま、ラグーンっていうのは
MC :ラグーン
ゲスト:はい、はい。ラグーンっていうのはサンゴ礁の海の
MC :はい。
ゲスト:うーんとサンゴ礁に囲まれた浅瀬のことなんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、海底が真っ白な砂でその輝くような真っ白な砂とそれとこう
コバルトブルーからエメラルドグリーンに広がっていくような、
そういう南の島の雰囲気をそのままにこう目の前に表しているという
MC :ほぉー。
ゲスト:これがね、サンシャイン水族館なんてビルの中だからちっちゃいと思って入るじゃないですか。
「えーっ!」っていうような大きさがあってみなさん驚かれます。
MC :サンシャインラグーンですね。
ゲスト:サンシャインラグーン。
MC :そこはその魚を見るんではなくて、空間を楽しむという
ゲスト:そうですねー。
MC :ふーん。
ゲスト:あの、魚はもちろんたくさん入ってますよ、面白い魚もいるんですけれど、
あのーでもちっちゃな子供は魚とかカメだとかに目が行くんです。
だんだんだんだん大きな子供になってくるとやっぱりその水中にいるっていうことが
楽しくなってくるんですね。
MC :はい。
ゲスト:でその水中にいて自分もま、
人魚かなんかになってそこに入っているんじゃないかっていう
そういう気持ちになった時に初めて僕の作った水族館の良さというのが出てきますね。
MC :なるほどー。
ゲスト:えー。
MC :いやー都会にいながらじゃあそのラグーン体験、
ゲスト:はい。
MC :空間を楽しむ
ゲスト:はい。
MC :いやー、あとは、あとはなんですか。ちょっと行きたくなってきたな。
ゲスト:あと、
MC :この足で行っちゃおうかな。
ゲスト:そ、そうですね。あとね、くらげのトンネルというのがありましてね
MC :くらげのトンネル
ゲスト:はい、あのくらげー割とーもう最近人気のアイテムなんですよね。
MC :あー癒し効果があるんですよね。
ゲスト:癒し効果がすごくあるんです。
MC :ヒーリングとか
ゲスト:はい。これもね実はね小学校高学年にならないとくらげの良さがわからないんですよ。
MC :あー。
ゲスト:ちっちゃな子はね、顔がない生き物ってあんまり好きじゃないです。
でもだんだんだんだんこう大きくなってくるとその顔がなくっても生きている、
しかも何にも考えてなくっても生きているその素晴しさっていうのが
だんだんわかってくるんですよね。
MC :いや、そうですね。
ゲスト:はい。
MC :うーん。
ゲスト:これ以上しかも、もう特に中学生ぐらいになってくるともっとわかってきますよ。
一番悩みが大きい時にくらげを見ると癒やされますよ、
「あ、これでも生きていられるんだ」と。ね、そんなあせくせ考えなくても、
そんなねかけっこ速くなくっても、そんなね100点取れなくっても
MC :え、
ゲスト:生きていけるんちゃうかと思た時に水族館の良さ、くらげの良さがわかるんです。
MC :いや、いやもう今、今の言葉に今入りました。
いや、く、今僕の頭の中のくらげがですね、もう今すごーくふわふわと、
あー、い、癒やされました。
ゲスト:癒されました?
MC :えー、ケ・セラ・セラで生きて行こうと思いました。
ゲスト:そうです。水族館に行くとそうなれるんですよ。
MC :えー。
ゲスト:で、しかもそれ、それがね美しいんです、何故か知らないけど。
例えば動物園に行ってライオンとかヒョウが寝てるのはそんなに美しくもかっこよくもないです。
MC :はーい。
ゲスト:でも、水族館の生き物はなんかそのたらーんとしてても美しいんですね。
動きがあるから。そこがね水族館の良さですよね。
MC :いやいいですねー。
でもあれですね、えー、なんか中村さんあのキラキラされてました、すごく。
ゲスト:あっそうですか。
MC :えー、すごくやっぱりそのー水族館を語るその目力というか、
優しくてー、力があってー、とてもいいお話を2週に渡って伺うことができました。
ゲスト:それはどうも有難うございました。
MC :えっ、是非又お邪魔さして下さい。
ゲスト:はい。
MC :今週のサイコーは日本ただひとりの水族館プロデューサー中村元さんでした。
どうも有難うございました。
ゲスト:有難うございました。 -
「水族館 パート1」 ゲスト:中村元さん
2019/11/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :さ、今週のサイコーは水族館プロデューサーの中村元さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちはー。
MC :中村さんは成城大学、東京の成城大学をご卒業後、
三重県の鳥羽水族館に入社され、あのーすごく有名なね、
あのー鳥羽水族館のリニューアルを手掛けて副館長として活躍されたあと、
現在は日本で唯一の水族館プロデューサーとして活動されてらっしゃる。
えーカラー出版から「水族館に奇跡が起きる7つの秘密」という著書をはじめ、
本をたくさん出していらっしゃるんですけれども。
水族館ていうとまあ、キッズたちはなじみが深いですよね。
ゲスト:ま、そうでしょうね。
MC :必ず行きますもんね。
ゲスト:はい。ま、動物園の次に行くところですよね。
MC :ですよね。ま、幼稚園ぐらいで遠足、あるいは家族と、水族館と親しんで、
ま、小学校、中学校行っても多分友達同士で行くだろうし。
ゲスト:そうですね。小学校のね、高学年になってくると
多分動物園よりも水族館の方が面白くなってくると思いますね。
MC :はー、そうですねー。東京ではサンシャインが有名ですね、
でもそれ以外でも葛西臨海公園にも水族館が
ゲスト:はい、大きいのがありますよね。あの東京は結構水族館多い所なんですね。
MC :あ、そうですよね。
ゲスト:はい。
MC :中村さんが手がけたのはちなみにどちらでしょうか?
ゲスト:えー、東京ではサンシャイン水族館ですね。近くではあのー新江の島水族館
MC :あーー
ゲスト:神奈川県の江の島にある水族館ですね。
MC :えーえー。あ、リニューアルしましたものね、何年か前に。あれは中村さんのプロデュース。
ゲスト:そうなんです。僕がプロデューサー、
水族館プロデューサーとして独立して最初の仕事が新江の島水族館です。
MC :新江の島水族館。あら、そう考えるとちょっと改めて行きたくなってきましたね。
ゲスト:そうでしょう。ははは。
MC :リニューアルされた後、行きましたよ。
ゲスト:あ、そうですか。はいはい。
MC :うーん。すごくおしゃれな建物でー、
ゲスト:えー。
MC :あのー非常にきれいな展示でしたけれども。あー。
ゲスト:もともとあの日本における最も古い水族館のひとつでしたから、
MC :えー
ゲスト:それでずぅーっと古いままでやってこられてたんで、
MC :はい。
ゲスト:もう完全に新しい時代を築く水族館として
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :あっ、じゃちょっと是非あのラジオの前のキッズが
お父さんに連れて行ってもらいたくなるようなお話を
ゲスト:そうですね。
MC :どういうふうに変わったんですか?ちなみに、新江の島水族館
ゲスト:うーん、あのね、実は水族館ってもともとはなんかこう、
じとじとべたべた暗そうな雰囲気じゃなかったですか。湿気があってね。
MC :あっ、湿気多いですね。なんとなくイメージ。
ゲスト:なんかきた、汚れそうな気もあったと思うんですよ。
やっぱり今水族館っていうのはー、あのー大人の人が行くところ、
大人の人が行きたがるところなんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、さっきね、小学校高学年は水族館をって言いましたけれど、
多分小学校高学年ぐらいになってくると、
子供達も大人がやっていることをやりたくなってくる、
あるいはセンスも大人のセンスとほぼ同じになってくるころなんですよね。
なのであの大人の人、特に例えば若い女性だとかがー、
あのすごく行きたいなっていう場所にした方がみんな喜んで見ていただけるようになるんですね。
MC :いわゆるちびっ子向けじゃないということですね。
ゲスト:はい、そうです。
MC :もう、若い女の人ターゲットにする
ゲスト:はい。で、幼児向け、幼児向けじゃないんですよね。
でもちびっ子は若い女性をターゲットにしたものの方が喜ぶんです。
MC :なるほど。そういうことですか。
ゲスト:はい。少年ジャンプを読む子に、年になったらそれはもう大人の感覚といっしょなんですよね。
MC :ほぉー。
ゲスト:小学校高学年からまあ結構初老の人まで、
MC :はい。うん。
ゲスト:少年ジャンプって読んでるんですよ。
MC :はい、はい。
ゲスト:だからー、その世代になったらもうみんな半分大人と考えていいと思ってるんです。
MC :なるほどね。あー、じゃあそっか新江の島水族館はま、
いわゆる子供達が喜ぶようなものじゃなくて、
ゲスト:大人が喜ぶものです。だから子供達も面白いんです。
MC :へぇーー。
ゲスト:で、ちょっとね、あの水族館にはしかけがしてありまして、
あの少し海が怖いように見せてあるんですよ。
MC :海が怖いように?えっ!
ゲスト:日本の水族館っていうキャッチコピー僕作ったんです。
MC :えっ
ゲスト:で、日本の海とか日本の川って妖怪住んでるでしょ?
MC :はい。
ゲスト:だからその今妖怪は怖いけれど、えー、
その海とか川に感謝もしているから妖怪なんですね、化け物じゃないんですね。
MC :はい。
ゲスト:妖怪だったり、神様がいてー、海に悪い事をしてはいけない、
何故ならそこには命を頂くしくみがあるからです。
MC :はい。
ゲスト:で、魚たちの命を我々は戴いて生きてます。
でもー、そこからうーんと海で遭難して亡くなっちゃったりとかー、
嵐が来てーとかま、大きい津波が来たりもします。
そういった様々な現象それぞれをですね、
日本人っていうのはあのー感謝と畏敬の念を込めて畏れっていう言葉ありますね、
畏れていたわけです。で、その気持ちを水族館から思い出してもらいたいと思って。
MC :いやー、そりゃ興味深いです。
ゲスト:うん。
MC :これもう、具体的な説明もういいですよ。
ゲスト:そうですか、はい。
MC :これもう是非行って下さいってことですよね。
ゲスト:そうなんです。なんか、なんか潜んでいそうな水槽っていうのを全部作ったんですね。
MC :へぇー。行きたくなってきましたー。
ゲスト:でしょ!
MC :うーん。
ゲスト:きれいなだけじゃダメなんですよ、
日本人の気持の中には海とか川には何かが潜んでなくちゃダメだと。
そういうのやってみましたね。
MC :僕ね、お邪魔した事あるんですけれど、
ゲスト:えー。
MC :その話を聞かないで行ったので
ゲスト:うん。
MC :鈍感でしたね。
ゲスト:はははは。
MC :いやいや、ちゃんと今、もっと早くお会いしとけばー、
そういう意識で行けたな、改めて行こうかな。
ゲスト:あー、でもまあそれは僕がもっと、もっとそういう風に見せるべきだったんですよね。
MC :えー。
ゲスト:何も知らずに来ても、
「あっ、ちょっと海、怖い事思い出した」っていうぐらいに仕掛けておくのが大事なんです。
MC :はーい。
ゲスト:それが水族館プロデューサーの大切なとこですよね。
MC :へぇー、すごい。
ゲスト:教えなくっちゃいけないっていうのは、ぼ、僕の失敗や、それ。あはははは。
MC :あはははは。そうですよ、いや、そう、そういうー、
そういうのって水族館のホームページを見れば書いてあ、あるんですか?
今の話ってだって、初耳ですもん。
ゲスト:いー、今はもう書いてないでしょうね。
MC :ですよねー。
ゲスト:プロデューサーによっては早ね3年もしたら違うもんになっちゃいますからねー。
MC :あーそうですかー。ははははは。あ、あと北海道、
ゲスト:えー。
MC :あ、ちょっとキッズ、あのー、
是非ねーこれ調べて貰いたいんですけど、北海道に北見市という市があって、
そこにね山の水族館っていうのが2年程前にリニューアルオープンしたんですよ。
で、今そこがものすごい観光客でにぎわってるんですが、
その北海道北見市の山の水族館も中村さんのプロデュース。
ゲスト:はい。
MC :あら。
ゲスト:やりました。
MC :これは僕は北海道の番組でー、紹介さして頂きました。
ゲスト:あっ、そうですか。
MC :そして、現場にも行きました。
ゲスト:有難うございます。
MC :あっ、そうなんですねー。
ゲスト:え、え、え。
MC :ちょっとこれは北海道、夏の北海道に来てもらうためにお話を伺いたいですねー。
ゲスト:うん。これ
MC :はい。
ゲスト:もともと水族館あったんですよ。
MC :そうだって、年間何千人しか来ない
ゲスト:そうです。
MC :もうもう超オンボロ水族館だったんですよ。
ゲスト:はい、一万九千、年間一万九千人ね、
MC :何千人はちょっと少なすぎましたね。
ゲスト:ちょっと少なすぎますね。別にそんな超オンボロでもないけれどー、
MC :あっそうですか。
ゲスト:誰も来なかったですよねー。
MC :そう、だって、だってもうこんなところに水族館あっても意味ないじゃんってところ
ゲスト:そう、そうなんです。そもそも水族館って海の横にないとだめなんですよ。
MC :山の中にありますからねー、
ゲスト:山の中ですからねー。
MC :北見市の
ゲスト:はい。でー、そこをちょっとねー建て替えるんでやってほしいって言われまして、
厳しいなーって思ったんですよ。なぜかって言うと、周りに人もいないですよね、
MC :人いない、もう超過疎地。
ゲスト:ですよね。
MC :もう高齢者ばかり
ゲスト:キタキツネの方が多いですよ。
MC :はい、はい。
ゲスト:そんなとこですから、で、しかも道路も全然車走ってないし
MC :はい。
ゲスト:で、何よりもね、厳しいのがその淡水魚の水族館だからその川の魚ってみんな魅力ないからー、
いくら新しい水族館作ってもすぐ飽きるじゃないですか。
MC :川の魚確かに、単調ですもんねー。
ゲスト:でしょう。で、結局はね、あの温根湯というところのあの気候、ま、
すばらしさというたらあれで、すばらしさというよりもすごい気候というのをこう出そう!と。
MC :すごい気候ってのは寒さとかですか。
ゲスト:めちゃ寒いんすよ。
MC :はい。
ゲスト:あのー冬になったらね、マイナス20度っていう日が続くんですよ、結構。
MC :そうです、え。
ゲスト:なので、その寒さを見せようということで冬になったら凍る水槽というのを作ったんですね。
で、夏はすっごい川の勢い、あの川、渓流の勢いになる川が流れていて、
これもね、日本初なんですけど、
MC :はい。
ゲスト:それが冬になったら凍っちゃうからもうこれ世界初ですよね。
で、凍って下で魚が生きているという姿を見ていただきたいと。
MC :そうか、氷の下で
ゲスト:はい。
MC :あの生きてる魚を
ゲスト:そうなんです。
MC :水槽、見ること出来るんですね。
ゲスト:はい。こんな水槽は世界中にないですから、
北の大地のあの魅力がそのちっちゃな水族館ですけど、
もうパンパンに詰まってますんで是非行かれると楽しいと思いますよ。
MC :いやいやいや、有難うございました。
ま、とにかく多分ね凍ってる川の下で魚が冬、
泳いでいること知らないキッズも多いと思うんですよ。
ゲスト:そうです、あの北海道の方、大人の方も知りませんでした。
MC :あっそうですか。ははははは。
ゲスト:ははははは。ビックリしてました、みなさん。
MC :いや、是非。いやーちょっと来週もまたお話伺いたいと思います。
今週のサイコーは水族館プロデューサーの中村元さんでした。どうも有難うございました。
ゲスト:はい。有難うございました。 -
「リップクリームの科学 パート2」 ゲスト:柴田雅史さん
2019/10/01 Tue 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーも、東京工科大学教授の柴田雅史先生です。こんばんは。
ゲスト:こんばんはー。
MC :先生はですね、「リップ化粧品の科学」という本を出版されているんですけれど、
えーリップクリームの重要性、このね、乾燥しやすい時期にえー、
非常にえー繊細な唇のケアのお話を先週していただきましたけれど、
あのー先生やっぱり唇をずーっと研究している、
リップクリーム研究しているということは、いろんな方の唇を見てるわけですよね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :今、一番輝いている唇は誰ですか?
ゲスト:えーっと、どなたでしょうかね?あのー石原さとみさんとかですね、井川遥さんとかですね。
MC :あーーーーー。ミセスでは井川遥さんですね、じゃあ。
ゲスト:そうですね。
MC :若い女性では、石原さとみさん?そういうのばっかりやっぱり見ちゃいますよね。
ゲスト:つい、そういったとこにまあ目が行ってしまいがちですねー。
MC :男の人の唇で、この人の唇ってのはあります?
ゲスト:えー、男の人は見てるかもしれないんですけど、あんまり頭に残らないというのが・・・
MC :あっ、そうですか。あーー。
ゲスト:はい。ミックジャガーですかね・・・
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:ていうことはないですけど・・・ハハハ・・・はい。
MC :ハハハ・・・いやいやいや。あのー、ほんとにリップクリームというもので、
保湿をするというのがとても重要であるという話を伺いました。
そもそもリップクリーム、まあ大概バッグの中に1本、男の人はポケットに1本、
もう入れる時代ですよね。
ゲスト:そうですねー。
MC :ただ、小学生、中学生なるとまだちょっと持たない子も多いかもしれませんけれど、
えー、まあ100円前後から買えるものもありますからね・・・
ゲスト:そうですね。
MC :あのー、因みに安いものと高いものありますけれど、成分に関してはどうなんですか?
あ、やっぱり高いものがいいんですか?
ゲスト:そうですねー、あのー高いものはそれなりにですね、やはりあのー、
唇にいい成分っていうのは色々とですね、含まれているということで、
まあ工夫されて作られているというのはまあ、えー実際のところですけれども、
ただまあどのえーリップクリームだってもね、えー、基本的にはあのー口から、
唇からですね水分を逃さないと、まあそういう役割をこう担うということから、
まあ基本の成分としてはあの、オイルというまあ液体のですね、えー成分が主成分となってます。
MC :液体なんですか?リップクリーム元々の成分・・・
ゲスト:そうですね。はい、主成分は液体です。
MC :液体・・・それは油?
ゲスト:油ですね。
MC :油ですか。オイル・・・
ゲスト:そうです。あのー、いつも我々が食べているようなサラダオイルとかですね、
あの天ぷら油とか・・・まあそのものではないですけども、
それの仲間のような性質を持っている、えー、ものですね。それが成分です。
MC :おーーー。なんか、オーソドックスな一番ベーシックなあのー、
リップクリーム見ると、白い棒ですけど、スティック状ですけどね、あれは油が主成分?
ゲスト:そうですね。その油をですね、ワックスと呼ばれているまあ、固形のですね、
えー物質で固めているということで・・・あのワックスというのはですね、
まあ身近な所でいいますと、えーチョコレートとかですね、或いはあのーろうそくとかですね、
まあちょっとああいうようなえー物質というのが、まあ身近なとこにあって、
まああれと似たようなえー性質を持っている物質です。
MC :ワックスが入ってくるんですか?チョコレートは食べられるけど、
ろうそくは食べられないじゃないですか・・・
ゲスト:はーい。
MC :でもやっぱり、そのそれらのそれぞれワックス?固める為の成分てのは入ってるんですよね。
ゲスト:そうですね。あのー油に対してですね、まあ10%から20%ぐらいとまあ、
極少量ですけども、えーこういったものを加えてあげて、
あのー作る時はこう加熱しますと、えーまあ溶けますので、
まあこれを冷やして固めると・・・そうするとあーいったようなちょっと固い感じのえー、
リップクリームが出来ます。
MC :確かに、ろうそくと似てますね。なんとなく・・・あのー、色も・・・
ゲスト:はい。
MC :あーーー。じゃあ白い、白く見えてるのはワックス成分なんですか?固める成分?
ゲスト:そうですね。あのーワックス成分っていうのは、結晶性の物質なので、
えー外観はこう透明ではなくって、白っぽい色になりますね。
MC :はい。大体あのー、リップクリームのスティックの油分の含有量は同じですか、
お値段に関係なくして・・・
ゲスト:いや。あのーーーお値段とは関係ないんですけども、あのー例えば塗り心地がですね、
あのーすごくべっとりとした、えー塗り心地をまあ好むような製品か、
或いはあのー水みたいにですね、サラサラとしたつけ心地ですね、
こういったものを望むのかによって、まあそのワックスの種類、油の種類、
そしてそれぞれの量というのが調整されて作られています。
MC :おーー。大体、基本的には何割ぐらい油でできているんですか?
ゲスト:そうですね。まあ油っていうか、まあワックスと油混ぜればもうほとんどがえー、
それ、その成分・・・
MC :あっ、もう主成分・・・
ゲスト:主成分ですね。
MC :そのものですか・・・そうか、油を塗ってるんですね、我々は。
ゲスト:そうですね。
MC :あーーー。あのー、僕は男だから口紅塗りませんけれども、女性達って口紅塗るじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :あれ、リップクリームと口紅、或いは色のついたリップクリームとか最近売ってますよね。
あれは口紅はリップクリームの成分はないんですか?油成分てのは・・・
ゲスト:あのー、口紅もですね、基本的にはあのー、
リップクリームと同じようにオイルとワックスから作られてます。
MC :そして、紅が入っているということですか?
ゲスト:そうですね。まあ後は色を付けるような成分ていうのがえー、
ついてるということでまあ基本的な構成はですね、
リップクリームもあの口紅もあんまり変わりません。
MC :あっ、そうなんですか。じゃああのー、お母さん方はリップクリーム塗らなくても、
基本的に口紅塗っておけばある程度乾燥は防げるという・・・
ゲスト:そうですね。あのーただ、口紅はですね、
あのーリップクリームとおんなじように水分を逃しにくいという性質ももちろん
まあ望まれてはいるんですけども、まあそれ以上にですね、
色がこうきれいに赤い色があの唇に塗れるとかですね、それからあの艶がですね、
艶々としたあのー仕上がりになると、まあこういう事が望まれてますんで、
やはり中身はですね、リップクリームとはちょっと変えまして、
そういったような色の部分、艶の部分っていうのが良くなるように作られてますんで、
その潤いを逃さないっていう性能はリップクリームよりはまあちょっと劣るというのが実情ですねー。
MC :なるほどー。あのー、最近の芸能人の方とか、
もう唇がプルンプルンにこう・・・なんて・・・光ってる女の子多いじゃないですか・・・
ゲスト:はい。
MC :あれは何ですか?
ゲスト:あれは、リップグロスですね。
MC :リップグロス。
ゲスト:はい。
MC :これ、これは何ですか?
ゲスト:あのーリップグロスもまあ基本的にはですね、
あのー口紅なんかとおんなじような形でまあ油で出来た製品なんですけども、
えー、そういったようなスティック状のものとはちょっと違いまして、
ともかく艶が出るという事をまず第一にこう考えてる製品です。
ですので、まあ違いとしましてはあの固める成分、
先ほどワックスというものでスティックにしていると言ってたんですけども、
リップグロスの場合は、それとはちょっと違いまして、そのプルプルとしたですね、
ちょっとえー何と言いますか、寒天みたいなですね、
まああんなような固まり方をするようなえー、固める剤を入れてるという事で、
まあそういったような違いがあります。
MC :おーー、いやーほんと、唇、色つけちゃうとね、食事したりとか、やっぱり色落ちるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :あのー、いや、最近落ちにくい物も増えてるんですか?
ゲスト:そうですね。あのーやはり、そのー特に口紅ですけども、
色が落ちなくするというのがやっぱり永遠のテーマていうかですね、
技術者としては、あの塗った時の色がそのままずっーとまあ夕方まで続くとかですね、
それから艶が長くもつっていうのはですね、まあ技術者是非ともこれを実践し、
まあ実行しようということで、まあ日々ですね取り組んでるんですけど、
やはりなかなか難しい技術ですね。
MC :んーーー。
ゲスト:まあ特にその潤いの部分とどうやって両立するのかと、どうしてもですね、
持続するタイプのものっていうのは、潤いの部分に欠けてしまうというのが、
今のやっぱり技術的なちょっとえー問題点ですね。ですので、まあ色々なタイプのですね、
製品において、そういったまあ新しい技術を開発するという取り組みがされています。
MC :へえーーー。出来ますかね?
その落ちない、朝つけたら夜まで落ちない口紅とかリップクリームとか・・・
ゲスト:そうですね。是非とも実現したいということで、私の研究室もですね、
まあそういったような目標にですね色んなものにチャレンジしています。
MC :いやー、先生なんで唇に興味を持ったんですか?
ゲスト:いやー、別にあのー唇に興味があったというわけじゃないんですけど、
あの元々の私のまあ研究テーマというのが、あの先ほどちょっと、
油を固める剤という話が出たんですけど、そういったようなゲル化剤と呼ばれてます、
水とか油をですね、こう固める剤、このあのー研究というのが私のメインの仕事なんですね。
MC :ほーー。あっ、じゃあ台所用品も含めてなんですね。
ゲスト:はい。そうですね。で、まあ特にそのーまあ特に油を固める剤の場合、
一番よく用いられているのが、このリップ化粧品とまあ、こういう分野なんで、
まあそこにおいてまあ色々応用の研究としてですね、
まあ実際に唇に塗るようなことをやってみるとやはり、唇というのは先ほども話ありましたけど、
よーく動く場所でありますし、また水も気体するということがありますので、
まあすぐに落ちちゃうということでですね、なかなかいいものが出来ないということで、
じゃあまずはあのーまあ敵を知るという訳じゃないですけど、唇の正体というもの、
特に皮膚との違いというものはどんなことなのかということをまあえー、調べてですね、
まあそれを使っていいゲル化剤を作ろうとまあこういうな取り組みをしてるんですね。
MC :んーーーー。いやーー、興味深かったです。
え、今週のサイコーは東京工科大学教授の柴田雅史先生でした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「リップクリームの科学 パート1」 ゲスト:柴田雅史さん
2019/10/01 Tue 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーは、東京工科大学教授の柴田雅史先生です。こんばんは。
ゲスト:こんばんは。よろしくお願いします。
MC :お願いしまーす。えー、柴田先生はですね、応用生物学のご専門で、
日刊工業新聞社から「リップ化粧品の科学」という本も出版されているんですね?
で、大学で肌や唇にやさしい化粧品の開発研究を行っていらっしゃると・・
ゲスト:はい、そうです。
MC :これは、今日はキッズよりもお母さん方は是非聞いて頂きたいですね。
ゲスト:そうですね、お母さんにも是非聞いてもらいたいと思います。
MC :えー、あのー、多分ラジオの前のキッズ達もお絵かきで自分の顔描く時、
必ずほっぺたは肌色で、クレヨンで赤使うといったら、唇ですよね?
ゲスト:そうですね。
MC :絶対、唇は赤ですよね、子供達・・・
ゲスト:そうですね、はい。
MC :そんな人間の唇、赤々してないんですけれど、赤にしちゃうと・・・
ゲスト:はい・・・
MC :でも、やっぱり顔のパーツの中で一番こう赤いのって、
やっぱり今先生と向き合ってますけど、唇ですよね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :なんで、唇は赤いんですか?
ゲスト:えっと、唇が赤いのはですね・・・あのー、「血の流れ」ですね。
あの毛細血管の中を流れてます、あの「血の流れ」というのがですね、
透けて見えるから唇が赤いんですね。あのー、唇というのはですね、
ちょっと変わってましてですね、皮膚と粘膜のちょうど中間の性質というのを持ってるんですね。
MC :ほーーーー。
ゲスト:ですので、あのー、普通の皮膚とはですね、まあ色々違った所がいくつかあるんですけども、
最も特徴的な点というのは、角層と呼ばれますね、皮膚の一番外側の部分、
その部分がですね、極めて薄いという特徴があります。
で、角層はですね、えー外から有害なものがこう体の中に入ってきたりですね、
或いはあのー、体の中からですね、水がこう抜けてしまうとカラカラになってしまうと、
こういうのを防ぐと、まあこういったような役割をしている、
まあ言わばあのー、最強のですね、防御壁といえる、といえるようなですね、
そういったようなものなんですけれども、この角層がですね、
非常に薄いというのがあのー、唇の特徴です。
MC :じゃあ、唇が赤いのは・・・えっ血が透けて見えるってことですか、変な話。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :そうなんですか?
ゲスト:そうですねー。
MC :えー、そういうことですか。
ゲスト:はい。
MC :えー、皮膚っというのは口の周りの皮の部分、まあクレヨンだったら肌色で塗りますよね。
ゲスト:はい、そうですよね。
MC :で、粘膜というのは口の中の湿った部分ですよね。
ゲスト:あーそうです。はい。
MC :その中間点が唇。
ゲスト:そうです。
MC :はーーーーー。そして、唇が赤いのは、血が透けて見える・・・
ゲスト:そうですね、はい。
MC :結構、生々しい話ですけど・・・・
ゲスト:そうですね、あの・・・
MC :わかりやすいですねー、うーん・・・
ゲスト:はい、あの角層っていうのが、まあ外側にあるといいましたけど、
あのー角層っていうのはこう、紫外線とかですねまあ、
有害な光ってたくさんあるんですけども、こういったような光がですね、
中にこう入るというのをまあ防ぐとまあ散乱させるという効果があるんですけども、
唇はその角層がまあ非常に薄いと・・・いえる・・・
MC :角層が薄い・・・
ゲスト:はい。
MC :んーーー。皮が薄いとイメージですかね?
ゲスト:皮が・・・まあね、一番外側のですねまあ一番大切なですね、部分が非常に薄いと・・・
MC :でも確かにこの時期だと、あのー、乾燥したりね冬寒い時だと、
急にペリッて割れたりして血が出ちゃうじゃないですか・・・
ゲスト:あーはい、そうですね、はい。
MC :非常にデリケートな部分でもあるわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :その反面柔らかい所でもあるという・・・まあ表裏一体ていうか、不思議なものですねー。
あのー、先生、リップクリームを研究されているということなんですよね?
ゲスト:はい、そうですね。
MC :「リップ化粧品の科学」という本も出してらっしゃって・・・
ゲスト:はい。
MC :これ、僕らって多分、今リップクリームって男の子も持ってると思うんですよね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :あのー、保有率って、昔に比べると随分高くなりましたよね。
ゲスト:そうですね、あのー、化粧品の中ではあのーやっぱり、
リップクリームの使用率・・・特に若い人ですね、はもう、非常に高いということで、
まあ化粧品の中では一番高い、えー、物の一つですね。
MC :どうも、デリケートなところを守る為のクリームということなんですよね。
ゲスト:はい。
MC :なんで、寒い時期だとすぐ荒れちゃうんですか?唇って・・・
ゲスト:あのー、それもさっきのですね、あの角層が薄いということもえー、絡んでる・・・
MC :薄っぺらいから・・・
ゲスト:そうですね。まあその、角層の所からこう水分がですね、えー逃げていくというのを
抑えるというのがまああの、角層の役割なんですけども、
まあそこがどうしても薄いということで、まあ外気がですね、
少しこう乾燥してくると、どんどんこうえー、
湿り気が抜けていくということで唇が乾燥してしまいます。
MC :ほーー、なるほど。あのー今、冬ですけど、じゃあカサカサしちゃう、乾燥してる。
でも、夏は夏で冷たいプール入ったりすると唇、紫になるじゃないですか・・・
ゲスト:あっそうですね、はい。
MC :でも血は流れてるわけですよね?
ゲスト:はい。
MC :同じ血が流れているのに、じゃあ紫の血に変わるかってそうじゃないわけですよね・・・
ゲスト:いやーそういうわけではないですね。
MC :なんで紫になるんですか?
ゲスト:やっぱりあのー、血管がですね、あの透けて見えるというのが、まあ特徴ですね。
血の巡りが悪くなるとえーその流れのえー、
悪さから段々ちょっと紫色になっていくということで、あのーまあ、顔全体もですね、
あの寒くなるとあの少しは顔色も悪くなるんですけど、
唇は特にその血の流れが悪くなるとすぐにわかってしまうと・・・・
MC :はー、顔青ざめたりするじゃないですか?あれも血行によって顔が青白く見えたり・・・
ゲスト:あっそうですね、はい。
MC :赤く火照って見えたり、で、唇も同じなんですね?
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :じゃ、健康的な時の唇って赤々しているっていうイメージでいいんですか?
ゲスト:そうですね。
MC :どういう時ですかね?
ゲスト:そうですね、赤ちゃんなんかがですね、やっぱり一番こう血の巡りがいい状態で、
まあ血管も一番元気な状態ですね、そうしますとあのー、
非常にきれーな赤い色しているんですけど、まあ残念ながらですね、
まあ私達の歳ぐらいになってくるとまあ血の巡りが悪くなってくる、
血管も脆くなってくるということがですね、段々とその血の巡りの悪さから、
あの、色がまあ紫色とはいいませんけども、ちょっと茶色っぽいような色に変わっていくと・・・
MC :年齢と共に唇は色が変化してくるんですか?
ゲスト:しているんですねー。
MC :じゃあ、こうやってから、今ねラボの中に男の人3人なんですよ。
で、なぜかね唇見ちゃうんですね。なんか変な話なんですけど、
でも、先生の唇が一番赤々してますよ。
ゲスト:いやあ、あのー私の唇もあまり褒められた、褒められたものじゃあないと思います。
MC :何かやってるんじゃないですか?えっ、なにかつけてますね、先生。
ゲスト:まあ一応商売上ですね、あの自分達の作ったような製品ですね、
まあそういったようなものを塗ったりしてますんで・・・
MC :あっ、やっぱりリップクリーム常にこう使って、
唇の保湿とかケアに力入れてらっしゃるんですね?
ゲスト:まあやっぱり、一応そういう研究やってますので・・・
MC :ああやっぱり、唇ケアすれば唇は若々しくいられるという・・・
ゲスト:そうですね。
MC :老化も防げるということですか?
ゲスト:そうですね。やっぱり老化では、老化をするというのは、
あのー乾燥するというのはですね、非常に唇にとって悪いということで、
まあ乾燥はえー、絶対防がないとですね・・・
MC :ほー、そうですか。僕なんかやっぱりリップクリームを持つのってここ数年なんですけれど、
若い時はね、唇乾いたら唾つけりゃいいやって、
いう何かペロペロペロペロ舐めてたんですけど、あれはどうなんですか?
ゲスト:あのーそうですね、あのー、乾燥するとですね、ついこうペロペロと・・・
MC :やりますよねー。
ゲスト:今もやってますけど、やってしまいがちなんですけど・・・
これはあの唇にとっては最悪というかですね、まあ非常に悪い行為なんですね。
MC :えっ、なん、唇に唾つけるのって、よくないんですか?
ゲスト:あっ、そうですね。あのーどんどん荒れていきますね、はい。
MC :えーーーー。そうなんですか?いやいや、やっちゃいけない事なんですね。
ゲスト:そうですねー。
MC :いやーーー、そうか、絶対やりますけどねー。
ゲスト:あのー水分をこう補給するという意味では舐めた時にはですね、
まあ水気がこうあのー、加わりますんでまあある程度は潤うんですけども・・・
MC :はい。
ゲスト:もう乾燥はすぐあのとんできますよね。で、そうしますと、残ると、
残る成分としてあのー、塩分とかですね、
タンパク質とかこういったようなものがあるんですけど、
こういったものがこう唇に刺激を与えてしまいますので、
もう舐める前よりも確実にこう唇は悪くなってしまって・・・
MC :あっ、唾液に含まれている本質がまた、唇を悪くちゃうってことですか・・・
ゲスト:そうそう、そうですね。はい、そうですね。そうですね、はい。
MC :で、水とかお茶で潤すのどうなんですか?
ゲスト:水とかでしたらまあ、それ程はですね、影響はないですけども、
まあただ、あのー、水で上からですね覆っても基本的には内部が潤うわけではありませんので、
やっぱりその場合はリップクリームとかですね、油の成分を使ってまああのー、
蓋をするような感じで中から水は逃げて行かないようにする・・・
まあこういうことが一番あのー、唇にとって大切なケアの仕方です。
MC :いやーー、参考になりましたねー。今のこの時期って、一番乾燥もしてますし・・・
ゲスト:そうですね。
MC :場合によっては、スキーなんか行くと海よりも紫外線の反射というか、
反射多いっていうじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :唇傷みやすいですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :海のよりもスキーに行った後の方が、唇傷むような気がするんですよね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :んーーー。この時期はやっぱりリップクリーム大事ということですね。
ゲスト:そうですね。是非あのー、忘れずにポケットに一つ入れといてください。
MC :いやあーーー、分かりました。
いや、来週じゃまたより詳しくリップクリームの話を伺いたいと思いますので、
またよろしくお願いします。今週のサイコーは東京工科大学教授の柴田雅史先生でした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「表面の科学 パート2」 ゲスト:板倉明子さん
2019/09/01 Sun 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今週のサイコーもですね、
前回に続きまて物質材料研究機構そして日本表面科学会の板倉明子さんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :すっぴんなのにツルツルしている板倉さんですけれど、
その話をね週してたら内の妻がね「若い時はツルツルしてね風呂とか上がった時に
ツルツルってこう水滴が落ちてったのに、最近ないんだよ」って僕もそうなんですよ。
ベチャーってこう水滴とがお湯がねまとわりついたものがはがれていく感じ?
これ年齢とともにやっぱりこれ表面ってやっぱり劣化してくんですよね?
ゲスト:そうですね。あの、赤ちゃんはすぐ油っぽくなる、汚れちゃうのもそうなんですけど、
新陳代謝が激しくて、体の脂分。すぐ体の表面についてくるので
MC :あー。新陳代謝なんですね。
ゲスト:そうですね。赤ちゃんとか子供はそうですね。若いころは
MC :だから弾いてくるんですね。
ゲスト:はい。
MC :生き物にもやっぱり表面っていうのはあるわけですね。やっぱり。
ゲスト:あります。
MC :生き物の表面科学って何か?具体的にあります?
ゲスト:面白いのはですね。あの、砂漠の甲虫、甲虫っていうか甲羅をもったあの虫がいるんですけど、
その虫は背中の甲羅の一部に脂を出してで、脂を出さない部分もあるんですね。
そうすると脂のところで弾かれたわずかな水分が、
その脂をはじかない部分の道筋を通って口のところにやってくる。そういうスゴイ昆虫がいます。
MC :超合理的
ゲスト:はい。
MC :見えない雨どいを身にまとった虫みたいな感じ
ゲスト:そそそそ そうです。そうですそうです
MC :は~そこは、砂漠にそういうのがいるんですね
ゲスト:砂漠にいます。
MC :わずかな水を全身でキャッチして、全部自分の口に来るように。すごい
ゲスト:そうです。自分に持ってくるように
MC :すごいですね。
ゲスト:そうですね。水をコントロールできる植物とか動物っていうのは多いですね。
MC :それはもう天然表面加工ってことですね。
ゲスト:そうです。
MC :あとは?あとは?
ゲスト:あとはですね。蓮って水の上に
MC :池に浮いてる大きい葉っぱの蓮。
ゲスト:あの上にあの結構大きめの水滴がコロンって乗ってるの見たことあると思うんですけど。
MC :ある。そこの横にだいたいカエルがいるんですよ。
ゲスト:はい。あれも、わずかな油分を表面に出して、しかもそれだけじゃなくてあの、
そうですね虫眼鏡とかで、あの、蓮の葉っぱの表面とかいろんな植物の表面を
見てみるとちっちゃい毛が生えてたり。
MC :そうそう。毛。毛。あの、日立ハイテックの電子顕微鏡でね、
毎年ね葉っぱを見るキッズがいるわけですよ。
そうすると、毛が生えてるの見えるわけですね。
僕その毛のおかげで水をはじくのかと思ってるんですけど。
ゲスト:そうですね。そのちっちゃい突起、凹凸もだいたい10ミクロン。
あ、1ミクロンが1000分の1ミリなので、10ミクロンだと100分の1ミリくらいですね。
100分の1ミリくらいのちっちゃな凹凸があります。
で、その凹凸のせいで、蓮の上では水がくっつかないで、コロコロ転がります
MC :あ。油じゃなくてやっぱりその細かい凹凸のおかげ
ゲスト:そうですね。両方ですね。
MC :両方。油と凹凸。それで蓮の葉っぱっていうのは水を弾く。
ゲスト:あんなにきれいに弾きます
MC :で、時にはね傘にもなるくらいですからね
ゲスト:そうですね。
MC :んー。植物も。そっかそうか、アブラナなんかはどうだろ。水弾きますよね。油分もあるし。
ゲスト:そうなんですかね。アブラナ身近に生えてたかな。
MC :いやない。あんまりない。あんまないけど、子供の頃よく見てアブラナの種弾けるの見て。
あとは、そうそう。植物油なんかもそうだから。その油分もあるし。えあとは
ゲスト:あとはですね。あ。実用化されてる。人間がその動物を、動物?をまねて実用化しているものもあります。
MC :え。何ですか?
ゲスト:えっと、サメ。
MC :サメ肌水着。
ゲスト:そうそうそうそう。その、あれは、サメの肌っていうのは、あのザラザラ。
サメ肌ってザラザラしたものを言いますね。で、あれはサメの表面。サメの肌の表面に、
あのじゅうりんっていう。あのすごくちっちゃな尖がったウロコが生えてるんですね。
で、その細かなウロコのせいで、水がその周りでちっちゃなちっちゃな渦をつくります。
で、その渦があるせいで、あの全体的な水の抵抗が少なくなって、
何パーセントくらいだったかな?8%くらいの水の抵抗が減るので、早く動ける。
MC :だから世界記録がでるわけですね。
ゲスト:そうですね。同じ様な形してますね。
MC :でも、サメ肌ってあの~サメの肌ってサメ肌って肌のきたない人のこと。
お前サメ肌だよっていうけど。それは逆に泳ぐ分にはその表面はプラスになってるということ
ゲスト:はい。ザラザラしてる。で、ザラザラ。ザラザラ加減があの上手くコントロールすると、
スピードをより一層コントロールできると。あの、最近あの、
サメがすごい早い速度で泳ぐときにそのジュンリン。あのそのウロコを逆立てたり、
寝かしたりして、そのコントロールをするっていう話が分かってきてます。
MC :へ~。水着はそこまでは再現できないかもしれないけれど、
やがて科学が進歩するとその表面の技術を活かした何らかのものが生まれるかもしれないですね。
あと、あの表面で僕なんかま、ツルツルしてると触ってると気持ちいいですよね。
なでなでしてると。ザラザラしたものよりは。なんだろうな。ツルツルしてるもの。
ゲスト:ツルツル。スケートリンクの氷。
MC :あー。あー気持ちいい。冷たいけど。僕去年まで北海道にいたので。
やっぱりスケートリンク良くいきました。ほー。
ゲスト:あのスケートって。ま、水の話をさっきからちょっとしてますけど、
氷っていうのもものすごく不思議なもので、普通結晶。
ま、氷も水の結晶ですけれど、結晶とか、固体っていうのは
その中に固まった分子が動かない状態なんですね。
分子が規則正しく組み合わさって動かない状態なんですけど。
水は、特殊でその表面の一層。一番上の一層だけ溶けてる状態なんですよ。
MC :あ、スケート中は。
ゲスト:0℃以下でも、一番上の層だけ水と同じ様に分子が動く状態。
MC :アイススケートの選手。バババババってやるじゃない。最初スタートダッシュ。
あの一瞬でも、全部氷溶けてるんですか?
ゲスト:はい。表面だけは溶けてる。あの、0℃以下の氷も表面一層だけは動く状態なんですね。
MC :スケートリンク見るとスケートリンクの氷。
ガチガチに固まってるけれど、滑ってるときは溶けてるってことですか?
ゲスト:滑ってる時っていうか、あれも、そこの上にいえば一層分だけは動ける。
そういう状態なので、他の固体に比べて氷の上っていのは滑りやすいんです。
MC :ほ~。スケートリンクが鏡だったらダメなんですね。
ゲスト:ダメですね
MC :やっぱり溶けるから
ゲスト:表面がちょっとあの状態になってるのが。
MC :なるほど
ゲスト:滑れる。良く滑る。ま、表面って言ったらいいか
MC :製氷したあとのね、スケートリンクとかそれからカーリング。
すっごい気持ちいいんですよ。だけど、微妙に溶けてるわけなんですね。
ゲスト:溶けてる。溶けるっていう言い方なのかな水。分子が動く。
MC :分子が動くってね。ほ~。この表面のジャンルの研究ってこれからどうなっていくんですか?
ゲスト:そうですね。車の表面を固くするとか、機能を持たせるっていうのもそうですし、
今、スマートフォンとか携帯電話とかそうですけど。
MC :みんな持ってるでしょ。
ゲスト:はい。その表面って手でカリカリ触るし。
MC :傷つく
ゲスト:傷つきやすいし。油もつくし、水滴も付きやすいし、
そういう表面をどうやってきれいなまま保っていくかっていうのを、研究している研究者は多いです。
MC :へ~。あれ、僕フィルム貼ってるんだけど、それ貼らなくても良い時代が来ますかね。
ゲスト:きっと来ますね。
MC :いや~。1000円得するかも。笑
いや楽しみだな。はーい。ということで、もうお時間ですね。また是非遊びに来てください。
今週のサイコーは物質材料研究機構そして日本表面科学会の板倉明子さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「表面の科学 パート1」 ゲスト:板倉明子さん
2019/09/01 Sun 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今年初めてのサイエンスコーチャー略してサイコーは物質材料研究機構難しいね。
そして日本表面科学会の板倉明子さんです。あけましておめでとうございます。
ゲスト:あけましておめでとうございます。
MC :え、何?これ、日本表面科学会っていうのがあって、
実は板倉さんはブルーバックスから「すごいぞ身の回りの表面科学」っていう
本だしてらっしゃる。表面科学って何ですか?
ゲスト:えっとですね、表面科学っていうのは分かりやすく言うと、
例えば人と人が握手するときに何処で触ってるかというと肌っていう人間の表面ですよね。
MC :はい。
ゲスト:で、表面っていう、例えばガラスのコップを触ってるにしても、
ガラスの材料の内側を触れるわけじゃなくて、ガラスの最表面を触るわけですよね。
で、そういう最表面一番表の部分。その、物質と物質が触れ合ったり、
反応したりするっていうのはその表面なんですよ。で、その表面を科学的なあのアプローチ。
科学的な見地で研究してそこに色んな特性を出したり、
いろんなそういういい働きをするように持って行くっていうのが表面科学っていう研究分野です。
MC :へ~。なるほどね。良く僕なんか先生に子供の頃上っ面だけで謝るな。そういう上っ面の科学ですね。
ゲスト:そうですね。上っ面の科学。でも世の中上っ面がすべてです。反応は上っ面で始まります。
MC :そりゃ~。
ゲスト:始めは奥にと、奥と触れ合いたいって言っても一番初めにに触れるのはその表面で。
MC :表面
ゲスト:表面から奥に進んでいく。一番初めの部分
MC :僕今年の仕事はじめで表面で上っ面。板倉さんとお会いして、
何かいい感じの人だなって思ってましたよ。表面上ね。表面上。
ゲスト:ありがとうございます
MC :でも上っ面だけで、表面上第一印象いいということで、表面上OK。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :あ、そういう事研究されてるんですね。
で、第一印象っていうと上っ面だと、例えば見た目とかあるじゃないですか。
女の人なんかも、この人綺麗だなとか。綺麗にしてるなとか。
お化粧とかもあるじゃないですか。それも表面科学ですか
ゲスト:はい。そうですね。ファンデーションとか化粧品ありますよね。
化粧品の中の粒子の中に、粒子っていうのはその粒々ですけど、
その中に板状のもの、そのフレーク状のものがあってそれを肌に塗りつけることによって、
その板状のものがきれいに揃います。そうすると板状の粒子、光うまく反射しますよね。
肌艶がよく見えますし、色が明るく見えます。で、その中で、肌に悪くないもの、
でしかもきれいに反射するものを選んでいくのが化粧品の研究になりますね。
MC :あ。あ。お化粧もじゃやっぱり表面科学の一端として
ゲスト:そうですね。
MC :そこをつるーんと、スムーズにして、しかもお肌に悪くないもの。
っていうこの2つを揃えて相手に好印象を与えるとか。ほう
ゲスト:あ、ほとんんど化粧してないですけどね。私今日。
MC :あ。板倉さん、すっぴん。
ゲスト:すっぴん笑
MC :あそうですか。いや、私それわからなかったんですけど。
あ、研究されてるだけあってお肌すごくきれいですね。
ゲスト:ありがとうございます。あの、そうですね、
研究分野 表面科学っていうものはやっぱりあの表面の中にちょっとでも、
他のものが混じり込むと嫌なので研究するときに化粧品は使えないんですね。
MC :なるほど。
ゲスト:なので、しないクセが付いてしまいました。
MC :すばらしい。逆にあのお化粧研究してる方はお化粧してないという。
ゲスト:そうですね。クリーンルームっていうほこりのない
ゴミの入っちゃいけない部屋に入って仕事をするときは、そういうものは難しいです。
MC :そう。クリーンルームあの下町ロケットの佃製作所5ですよ。
ゲスト:はいはい。そうです。
MC :あーいう感じですよね。
ゲスト:あーいう感じですね。
MC :そういえば、表面研磨してましたもん。手作業で。
ゲスト:そうです。
MC :あーいうのも表面科学?
ゲスト:あれです。はい
MC :なるほど。じゃ、ツルツルしてるものっていうとじゃ、イメージ出来てきた。
表面ね。このラボに表面ある?いろんなもの表面あるけれど、
紙なんかもねザラザラしてる紙もあればツルツルしてる紙もし、
今手元にあるあの板倉さんのね「身の回りの表面科学」っていう本は、
すごく コーテイングされていてツルッツルじゃないですか。これも表面科学ですか?
ゲスト:はい。表面科学というかそれもコーテイングで表面をツルツルにして
汚れを付けないという意味では科学の分野といっていいのかなと思います。
MC :なるほど。見栄えが良くなるだけじゃなくて、汚れが付きにくくなるというメリットもある。
逆にこのラボにあるちょっとあのコピー用紙みたいな紙はじゃこれは汚れが付きやすい。
ゲスト:そうですね。手の油が付いたときにそのツルツルの本だったらちょっと拭けば油、
汚れは取れますけど、こういう紙だと油がしみ込んでしまって油がとれなくなりますね。
MC :となると。台所のね流し台とか、
それからダイニングテーブルなんかも表面科学が結構活きてるわけですね。
MC :そうですね。コーテイングというのが、広い意味での表面科学の分野のひとつだと思います。
MC :確かに。同じ木の机だってね、ログハウスの前の木の机だったら
食べ物こぼしたらそれ拭くの大変ですけど
ゲスト:そうですね。
MC :みんなの上の木の机だったら、コーテイングされてる。
ゲスト:そうですね。
MC :いやあとなんだろ。コーテイングって。僕らの身の回りの表面科学何ですか?
お正月にふさわしい表面科学。
ゲスト:お正月にふさわしい。正月の表面科学?何かあるかな
MC :鏡餅。かがみ、かがみ。そっから鏡。鏡だってツルツルしてて、
そう、鏡はねあのお風呂場の鏡すぐ曇るじゃないですか。
だけど、お母さんがお化粧するときの鏡ってくもんないじゃないですか。
それは環境の問題ですか。
ゲスト:はい。あのひとつはお風呂って湿気がいっぱいあるので、
ちょっと冷たい面があればそこに結露します。結露水滴が。
あのそもそも鏡がどうして人を映すかとかきれいに物を映すかっていうと、
表面がツルツルで、あの光をきれいに反射するからですね。
MC :へ~。
ゲスト:デコボコしてたら乱反射しちゃいますよね。
MC :確かに
ゲスト:で、それなので。例えば湖なんかで、表面がきれいに波うってなければ月が映りますけれど、
そこに石1個ポーンって置いて表面が波打つと月の形消えちゃう。
あのグダグダになりますよね。で、それとおんなじようにツルツルの鏡の表面に水滴がつくと、
表面がデコボコになって乱反射するので曇っちゃって人が見えないっていうことになるんですね。
MC :は~。
ゲスト:で、だからきれいにしたいためには、あの、その、デコボコにならないように。
水が付かなくすればいいんですけれど、ひとつは冷たくしないで熱い状態で
結露を防ぐっていうのがあります。
MC :なるほど。温めておく。
ゲスト:温めておくっていうこと。でも、表面科学としてもう一個おっきい
大きい曇らせない方法っていうのがあって、それは表面に薄ーく水をはじく加工をしてあると。
MC :はい。
ゲスト:あの、撥水。水をはじくと書いて撥水っていうんですけど。
その撥水加工をすることで、水滴がくっつかないで、
あの、ま、粒になってコロコロ転がり落ちるような。
MC :いや、きたきたきた。
私車好きですから、私、液体ワイパーっていうものをものすごく長いこと使ってるんです。
たぶん液体ワイパー使って25年くらい。ん。いろんなメーカーのいろんな名前のもの試してますけど、
あれ、あれの原理って事ですね。そうですね。撥水加工して。
ゲスト:そうですね。はい。あの基本的に油系のものとかワックスとかなんですけど、
水と中の悪いもの薄ーく塗ってしまうことによって、水が付かなくなります。
MC :え、じゃ家庭のお風呂場なんかも、じゃ液体ワイパーみたいなものあの、変な話。
カー用品店に行って買ってきて、あれ塗ったら以外に曇らない。
ゲスト:曇らないです。
MC :へ~。あれ、何ですか?物質油ですか?
ゲスト:え、あれなんだろう。車のワックスって、私ちょっと調べてないけれど、たぶん油系のものか、
えーっと例えばプラスチック系のものとか、
あと、付かないものの代表ってフライパンのフッ素コートなんかもそうですね。
MC :すっごい身近なものを研究してる人なんですね。
ゲスト:そうなんですかね。キッチンとか化粧品とか主婦の味方みたいですね。
MC :心強いですね。新年一発目、またちょっと来週もお話を伺いたいと思います。
今週のサイコーは物質材料研究機構、そして日本表面科学会の板倉明子さんでした。
ありがとうございました。 -
「ホルモンの科学 パート2」 ゲスト:伊藤裕さん
2019/08/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :さ、今週のセンスコチャー略して「サイコー」は前回に続きまして、
慶応義塾大学医学部教授の伊藤裕先生です。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。よろしくお願いします。
MC :伊藤先生の御専門は内分泌学高血圧糖尿病抗加齢医学ということで、
まあ、お父さんお母さんが非常に気になるジャンルのお勉強されてらっしゃる方なんです。
朝日新書から「何でもホルモン」という本も出版されているんですけれど、前回伺いました。
成長ホルモンは大人も出る、一生出る。で、性ホルモンと成長ホルモンがマッチングすることによって、
思春期の男の子女の子が成長するというお話。
色々伺ったんですけれど、あのー、男性モルモンとか女性ホルモンついて
まだやっぱり興味のある方多いと思うんでね、
ゲスト:うん。
MC :この性ホルモンの影響が指の長さに現れる。
ゲスト:そうですね。
MC :興味ぶかいですね。
ゲスト:はい。
MC :このお話。
ゲスト:あのー、女性の方はですね、自分の右手を見ていただいたら分かるんですけれども、
MC :うん。
ゲスト:人差し指と薬指の長さがほぼ同じぐらいかですねむしろ人さし指の長さが長い方が多いんですね。
MC :人差し指と薬指。ああ、はい。
ゲスト:ところが、
MC :あの。うん。はい。
ゲスト:男性の方はそうじゃなくって、
MC :うん。
ゲスト:薬指の方が、あの、人差し指よりも長い方の方が多いんですね。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:はい。で、この薬指の方はどれだけ長いかっていうのは、
その方がどれぐらい今、生まれる前からなんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:男性ホルモンが多いのかという事の指標になるのんですね。
MC :えっ、えっ、ちょっと待って下さい。えっ、
その薬指と人差し指の長さで、男性ホルモンの指標になる。
ゲスト:そうですね。
MC :もう一度教えてください?薬指の方が長いと、
ゲスト:男性ホルモンの量が多い。
MC :おっ。長いっす。
ゲスト:ねぇ。大村さんの場合、すごい典型的な男性型ですね。
MC :で、
ゲスト:女性の方はそうじゃなくって、指が人差し指の方が長いんですね。
MC :はい。
ゲスト:ところが中には、女性の方でも薬指の方が長い方もいらっしゃって、
MC :はい。
ゲスト:その方は男性ホルモンが、あのー、普通の女性の方よりも大目の方だということになる訳です。
MC :ほぉー。女の方はじゃぁ、人差し指が長い方が女性ホルモンが活発ってことになります。
ゲスト:うん、まあ、いわゆる女性らしさが
MC :ほ、ほ、ほ。
ゲスト:あるということなんですね。で、あのー、ですから薬指がどれだけ長いかっていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:その方の、まあ、あの、男性、男らしさといいますかね、
MC :ええ。
ゲスト:例えばチャレンジしていこうという、性、そういう気持ちが強いとかという、
MC :はい。
ゲスト:性格判断にも、これ、使われてるぐらいなんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですが、女性の方でも薬指の方が長い方いらっしゃいますけども、
MC :はい。
ゲスト:これはいわゆる、まぁ、男前な女の子だっていますか非常に、
こう、男勝りなそういったシャキシャキっとした方が、ま、多いとという、そういうことですね。
MC :へえー。さあ、それから最近注目集めてるのが、愛情ホルモンという
ゲスト:はい。
MC :これいいですね?
ゲスト:うん。
MC :どういうホルモンですか。
ゲスト:あのー、ま、最近すごい注目されているオキシトシンというものがあるんですね。
MC :オキシトシン。
ゲスト:はい。で、これはね、我々が医学部の時に習ったのはですね、
まあ、女性が妊娠そして分娩するときに沢山分泌されて子宮を収縮させて、
ま、赤ちゃんが生まれやすくするそういう作用があると思われたんですね。
MC :はい。
ゲスト:ところが、そんな分娩する時だけにこのホルモンがある訳じゃなくって、
男性にも女性にもあることが分かってきて、何だろうということになってたんですね。
で、これは実は脳に作用してですね、特に女の人が赤ちゃんを産んだ時に
沢山分泌されることで実は自分の産んだ子供を非常に愛おしいていいますか
何事にも変え難いというそういう愛情を作りだしてくれるホルモンです。
MC :お母さんが赤ちゃんを産んだら可愛がる。
ゲスト:男性でもこのホルモンがあるんですけれどもこのホルモンが、
このホルモンは、あのー、体に触ったりとか
MC :はい。
ゲスト:抱き合ったりすることで沢山出るんですね。
MC :うん。
ゲスト:で、そのことによってその相手の方を非常に愛おしいていますか、
まあ、そういう気持ちにさせてくれるという、ですから愛情ホルモンと呼ばれてるんですね。
MC :へえ。これは分泌するのは女の人が主ですよね。
ゲスト:いや。ところが男の人にもあるのでどうして男の人にあるんだろうと思われていたら、
MC :はい。
ゲスト:ま、実はそういうことでなくて男女がお互いのことを
非常に愛おしく思えるためのホルモンということですね。
MC :へえー。
ゲスト:ですから、こう、あのー、体に触れたりとか抱き合ったりとかそういうことで非常に沢山出、
分泌される訳です。
MC :スキンシップ。
ゲスト:そうなんです。スキンシップはすごく沢山出るんですね。
MC :ほー。スキンシップは愛情ホルモン
ゲスト:はい。
MC :というものが分泌されるんですか?ホルモンて、
どっから出て体のどの辺意識したらホルモン出てくるんですか?
ゲスト:まあ、あのー、ちょっとこれもう冗談っぽくなりますけど
ホルモン焼きって体のどの臓器でも食べられるっていうことで
どの臓器でもホルモン焼きになりますよね。
MC :はい。
ゲスト:あれと同じようにホルモンを作る臓器っていうのはもう体のあらゆる臓器で作ってるんですね。
MC :へぇー。
ゲスト:で、特にはこのオキシトシンていうのはやっぱり頭の方からでるホルモンなんですけども、
MC :愛情ホルモン?
ゲスト:はい、そうですね。
MC :頭
ゲスト:はい。
MC :脳から?
ゲスト:はい。
MC :で、成長ホルモンはどこから出てくる。
ゲスト:成長ホルモンはやっぱり同じような近い所から、やっぱり脳からですね。
MC :脳?
ゲスト:はい。だから脳から出るばっかりじゃないんですね。
MC :#
ゲスト:それは。例えば性ホルモンていうのはやっぱり精巣とか卵巣とかいうところから出ます。
MC :あ、下腹部から出る。
ゲスト:そうですね。
MC :胃から出るホルモンとかもあるんですか。
ゲスト:あるね。グレリンていうこれも日本人が見つけたホルモンなんです。
MC :グレリン?
ゲスト:これはお腹が減るとこのホルモンが沢山出るんですね。
MC :お腹が鳴るのも。
ゲスト:そう、グウとなるのもグレリンの作用です。
MC :ええええ。そうなんですか。
ゲスト:で、脳に作用してお腹が減ったからもっと食べてくれという命令をだすホルモンなんですね。
MC :はあ、よくじゃあ、お腹すいてグルグルグルってなるけれど、
ゲスト:はい。
MC :それ、だらしないんじゃなくてホルモンの叫びってことなんですね。
ゲスト:そうそう。まさにそうですね。
MC :グレリンが呼んでると。
ゲスト:そう、そう、そう。
MC :よく、あの、給食の前とかに「誰だお腹すいてんのは。」なんて
「朝ちゃんと食べてきたか。」って先生言うかもしれないけど
ゲスト:はい。
MC :ホルモンの叫びですと
ゲスト:そうですね。
MC :グレリンですと
ゲスト:でもね、グレリンは僕らの研究で、あの、体を元気にさせる作用もあるんですね。
MC :お腹鳴るのが?
ゲスト:ええ。ですから、やっぱり、あの、空腹でグレリンが
沢山出ることは実は生き生きするためにすごい大事で、
MC :ほぉー。
ゲスト:まあ、若返りホルモンて最近言われているところもあります。
MC :お腹が鳴るのはあんまりかっこ悪いことじゃないですね。
ゲスト:うーん。むしろいつもなんかお腹がいっぱいになってて、
あのー、グウっと鳴らないっていう人の方がやっぱり老けやすいっていいますけど、
MC :へえー。
ゲスト:そういうことだと思うんですね。
MC :ハングリー精神持ってる人の方がいいって言いますもんね。
ゲスト:そういう感じですね。
MC :あぁ。
ゲスト:はい。
MC :それから伊藤さんは、大切な決断は朝がいいという風に著書に書いてらっしゃるけれど
ゲスト:はい。
MC :これどういうことですか?
ゲスト:あのー、先ほど指の長さのところでお話ししました、これはやっぱり男性ホルモン、
テストステロンというのが関係してるんですね。
MC :テストステロン。
ゲスト:テストステロンはやっぱり朝に分泌が多くって
MC :ふーん。
ゲスト:夕方に少なくなるんですね。
MC :ふん、ふん。
ゲスト:で、あの、やっぱり男性ホルモン、テストステロンていうのは男性らしくこうパッと判断して、
MC :はい。
ゲスト:で、あのー、グジャグジャ迷ってなくってスパッとこう考えられるて
そういう力を与えてくれるので、ですから大事で重要な決断というのは
やっぱり夜するよりも朝した方がいい決断ができるということですね。
MC :最近やり手のビジネスマンなんか朝活って言って、
ゲスト:はい。
MC :早朝集まって色んな勉強したりされてるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :ああいうのも、じゃあ朝ってのはいいのかもしれないですね。
ゲスト:男性ホルモンが多い方の方が、あの、いわゆる証券の取引なんか
MC :はい。
ゲスト:ああいう売買で成功される方が多いですね。
MC :おお。なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :そうかぁ。あと煙草やめると太るのもホルモンが原因だっていう。
ゲスト:そうなんですね。あのー、実は女性ホルモンていうのは男性ホルモンから作られるんですね。
MC :女性ホルモンは男性ホルモンから作られる。
ゲスト:はい。で、男性ホルモンから女性ホルモンに、
えー、変換させる作用があるのがアロマターゼっていう
MC :はい。
ゲスト:酵素があるんですけれども、
MC :アロマターゼ。
ゲスト:はい。で、これは煙草の中に含まれているニコチンはですね、
MC :はい。
ゲスト:このアロマターゼの働きを、あのー、ま、抑制すると言いますかこれを妨げる作用がある訳なんです。
MC :はい。
ゲスト:ですから、煙草を吸わなくなると、
MC :うん。
ゲスト:女性ホルモンが出来易くなるんですね。アロマターゼ作用が下がりますので、
MC :うん。
ゲスト:そうすると女性ホルモンがいっぱい出来るわけなんですけれども、
女性ホルモンは体に脂肪を貯めて女性らしい体をつくる訳です。
MC :へえー。
ゲスト:だから、煙草を吸わなくなると女性ホルモンが多くなるためにちょっと女性っぽくなって、
だからポチャッとしてしまうというそういうことなんですね。
MC :はー。よく煙草止めて太った言い訳で、食べ物がおいしいから太ったんだっていうのは。
ゲスト:うん。まーそういうのはあるのかもしれなませんけど
MC :あ、そうですか。
ゲスト:実は、本当はこのホルモンの作用っていうのは大きいんですね。
MC :アロマターゼだよということですよね。
ゲスト:そう、そう。はい。
MC :お父さん、いい月曜日からの会社のネタになりますよ。
煙草止めるとアロマターゼっということで女性ホルモンが増加することによって
太るということですね。その他キッズやお父さんお母さんに知ってもらいたい
ホルモンっていうのは何かあります?
ゲスト:まあ、あのー、我々の心臓からもやっぱりホルモンが出ているんですね。
MC :ほー。心臓ね。
ゲスト:心臓ホルモン。これはやっぱり運動するとなぜ我々の体にいいのかっていうと、
MC :はい。
ゲスト:この心臓ホルモンが沢山出るからなんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、心臓ホルモンが沢山出るとこれは血管を広げて血の巡りがよくなるんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですから血圧も、あの、下がってまいりますし、
MC :はい。
ゲスト:それから血の巡りがよくなるっていうのは、
基本的にはいろんな臓器が非常に活発する元気になる訳ですから、
MC :はい。
ゲスト:ま、いわゆる活き活きすると、だから、運動が何故いいのかっていうと、
あの、実はこの心臓ホルモンが沢山出るからだと思うんですけど。
MC :ほー。
ゲスト:やっぱり、ですから運動するっていうのは大事ですし、それから先ほどの話ですけれども
MC:ええ。
ゲスト:グレリンを沢山出すためにはやっぱ沢山食べてはいけない。
MC :はい。
ゲスト:ですから言われているような食べ過ぎはよくない運動しようというのは
実はホルモン的に説明できるんですね。
MC :このホルモンを培養するというか体の中で育てるには、例えばポイントは何かあります?
ゲスト:そうですね、あの、やっぱりあのホルモンていうのはほとんどのものが、
やっぱり脳のコントロールを受けているので、
MC :はい。
ゲスト:脳がリラックスするといいますか、
MC :ははー。
ゲスト:楽しいと思えることが大事なんですね。
MC :ああ、いいですね。
ゲスト:で、私が言ってるいつも四つの楽しさというのが大事で、
一つはあのー、楽しく食べるということ、
MC :食べる。
ゲスト:それから楽しく動く、
MC :動く。
ゲスト:そして、楽しく眠る、
MC :寝る。
ゲスト:そして、楽しく誰かとお話をする。
MC :ほー。
ゲスト:そういうことが大事だと思うんですね。
MC :あ、もう時間ですか?いやー、ホルモン出まくったぁ十数分だったな。
ゲスト:はい。
MC :また来てくださいね、先生。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :今週の「サイコー」は慶応義塾大学医学部教授の伊藤裕先生でした。 -
「ホルモンの科学 パート1」 ゲスト:伊藤裕さん
2019/08/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :今回のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は
慶應義塾大学医学部教授の伊藤裕さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは、よろしくお願いします。
MC :慶大の医学部の教授っというとすごいですね。すごい、すごくないですか?
ゲスト:いやどうでしょう。ぼく関西出身なんであんまりその実感がわかないんですけど。
MC :あーいわゆる肩書きで はあまりこーこだわりがないという。
ゲスト:そうですね。
MC :私なんか畏れ多くてひれふしてしまっておりますけれど。
ゲスト:いえいえ。
MC :伊藤先生のご専門は内分泌学高血圧糖尿病抗加齢医学、
いわゆる年齢をとることに抗う医学これお母さん方興味あるでしょ?
朝日新書から「何でもホルモン」という本も出版されています。
ホルモンというとね、香ばしい、こー、いい匂いがしそうなんですけれど、
そうじゃない。体のホルモンですね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:ま、やはりあの皆さんホルモンていいますと
MC :うん。
ゲスト:ホルモン焼きを
MC :そう。そう。
ゲスト:想像する方が多いと思いますがそういうものではございません。
MC :ええ。
ゲスト:あのー、今からやっぱり100年ほど前にイギリスの生理学者によりますとですね、
ギリシャ語の、ま、興奮するとか
MC :うんる
ゲスト:刺激するという言葉からこの名前がつけられた訳なんですね。
MC :ん?ホルモンの語源はギリシャ語?
ゲスト:そうですね。ホルマオというそういうそのー、
刺激するという言葉から出ているんですね。
MC :へ~。ホルモンは刺激するという意味なんですか。
ゲスト:ま、あのー、ホルモンは我々の体が実際作ってるわけなんですけども
MC :はい。
ゲスト:そして我々の体に働いて、我々興奮させてくるもんなんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、まー私たちの体っていうのは細胞と呼ばれている
小さく仕切られた部屋が沢山集まっているわけですけども、
MC :ええ。
ゲスト:何かこう体に刺激が与え、与えられますと、そのある細胞が興奮するわけですね。
MC :はい。
ゲスト:そうするとその細胞がホルモンを作り出して体の外に出す。
これが分泌っていうんですけども、で、
出てきたホルモンが血液の中を流れて違う細胞のとこまで行き着いて、
そこで作用して、その細胞をま、興奮させてくれる。ま、そういう物質なんですね。
MC :なるほど。じゃ、じゃあほんと刺激を受けて泣いたり笑ったりという人間の喜怒哀楽なんか、
ゲスト:はい。
MC :これもホルモンの分泌に関係あるんですか?
ゲスト:そうですね。あのー、ま、そういった感情でホルモンの分泌はあの、
コントロールされていますし、
MC :うん。
ゲスト:逆にホルモンが出ることで我々の感情も動いていくというまあそういう感じですね。
MC :はあー。ホルモンて、色々聞くけど何種類ぐらいあるんですかね?
ゲスト:まあ、あのー、本当に20世紀の終わりに沢山見つかりつかりまして、
MC :ええ。
ゲスト:ま、実際現在知られているもんだけでも100種類以上ある、
MC :へぇ?
ゲスト:ということなんですね。
MC :えっ、僕分からない。男性ホルモン・女性ホルモン・成長ホルモン、あとは、ええっ?
ゲスト:まあ、あの、そういったいわゆる、まあ昔に使ったホルモというのはそんなに沢山なかったんですけども
MC :はい。
ゲスト:ほんとに最近爆発的に使われるようになってきまして、
MC :ええ。
ゲスト:まー我々の体のいろんな活動というのは、
このホルモンがほとんど司っているという風に、ま、考えられてきた訳ですね。
MC :じゃー、もー、僕らの知らないホルモン名というのはお医者様の世界では、
相当、もう、知ってらっしゃるということですか?
ゲスト:我々医学部の時に習ったホルモンの数からは今どんどん増えていってますので、
あの、今のお医者さんも実際には沢山その、
沢山あるホルモンの名前全部解かっておられる方は少ないのかも知れません。
MC :そうですか。
ゲスト:はい。
MC :でも、なんか、僕言ったけど男性ホルモン・女性ホルモン・成長ホルモン、
ゲスト:はい。
MC :キッズ達にとって重要なのはやっぱり成長ホルモンだと思うんですけど、
ちょっと成長ホルモンから伺っていきたいと思います。
ゲスト:はい。まあ、あのー、成長ホルモンというのは文字通りやっぱり子供さんに働いて、
MC :はい。
ゲスト:そのー、成長を助けていってくれるホルモンということなんですけども、
実はまあ、あのー、寝る子は育つっていう言葉がよくあると思うんですけど
MC :言う。言うよ。
ゲスト:これは、もう、本当にそうなんですね。
ですからこれはホルモン的に説明できるんです。
寝てる間にこの成長ホルモンが沢山分泌されるんですね。
MC :はい。
ゲスト:なんであの寝ている間に沢山分泌されるかというと、
寝ている間はものを食べることができないのでどしても、あの、血糖ですね、
MC :うん。
ゲスト:血液の中の糖分が下がってしまう訳です。
MC :うん。
ゲスト:で、脳っていうのはこの糖分が非常に大事ですので、寝てる間にもし、
低血糖になってしまいますと、まあ二度と、二度と起きられないといいますか、
ぼけてしまうわけですね。
MC :へえ。
ゲスト:で、それをま、助けるといいますかそうならないようにしてくれるのに
この成長ホルモンが、ま、役割がありまして、
ですから寝てる間に沢山分泌される。だから、
MC :ちょっと待って下さい。
ゲスト:はい。
MC :寝てる間に低血糖にならないために成長ホルモンが分泌される。
でも寝てる間に低血糖になってしまうと脳が死んでしまう。
ゲスト:そうですね。もう二度と起きられなくなってしまう訳ですね。
MC :ということは、なに、大人にも成長ホルモン出てるんですか?
ゲスト:そうですらしいです。
MC :えー!!
ゲスト:だから、我々にとって朝起きられるのは、成長ホルモンが夜出てくれているからなんです。
MC :えっ。ちょっとまって、先生おいくつですか?
ゲスト:57です。
MC :57歳で成長ホルモン出てる。
ゲスト:皆出てるんですね。
MC :げー。えへへへ。知らなかった。あはははは。そうなんですかぁ。
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。
ゲスト:若い時はですねもちろんこのホルモンが沢山出る、
つまり、寝ている人の方がより、あの、成長しやすいんですけども
MC :はい。
ゲスト:もちろん大人になってしまいますと、我々はもうこれ以上成長できないんですが、
MC :はい。
ゲスト:逆に、あの、このホルモンの作用が大人になって弱くなってしまうと
太ってしまうんですね。それは今大人にとっても大きな問題なんですね。
MC :ちょっと、太りやすい人は成長ホルモンの分泌が弱いとうことですか?
ゲスト:そういった方ばかりじゃないんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、成長ホルモンの働きを大人になってずっーと弱いままである人っていうのは
実は中年太りになりやすいということも知られているんですね。
MC :へえーーー。何か、何かすこやかにすくすくと
子供をね成長させるのが成長ホルモンと思ったら、万人に一応出てると、
ゲスト:そうですね。
MC :へえーー。
ゲスト:まぁ、我々の脂肪分というのを、まぁ、燃やして血糖を上げようする訳ですけども、
MC :はい。
ゲスト:その作用がなくなってしまうどうしても脂肪が溜まってしまい易くなると、
MC :うん。
ゲスト:まぁ、そういうことなんですね。
MC :いーやぁーーー。ビックリしたですね。
ゲスト:ま、逆にね、成長ホルモンが、の働きが強くなりすぎると、
MC :はい。
ゲスト:ま、どんどんどんどん成長していくといいますか、ま、
我々自身の体が大きくなりがちですので、
MC :はい。
ゲスト:逆に寿命も短くなるんですね。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:はい。ですから、あの、癌にもなり易くする。
MC :へー。
ゲスト:ということなんですね。成長ホルモンは大人になっても
非常に寿命との関係でも大事なホルモンですね。
MC :で、あの、年齢によって分泌量は違ってくるんですか?
ゲスト:そうですね。やっぱり子供の間っていうのは、やっぱり出やすい、
MC :うん。うん。
ゲスト:わけで、それは子供の成長を助けるためなんですけども
大人になってもある一定の量がでているわけなんですね。
MC :ええ。これが過剰に出てしまうと癌になったり?
ゲスト:癌になりやすい。そういうことなんです。
MC :ほーー。この成長ホルモンて変な話人間ドックでは調べないですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :だからどれぐらい分泌しているかどうかというのを、
例えばキッズのお父さんお母さんが気になったら
調べてもらうにはどうすればいいんですか。
ゲスト:あ、それはもう普通にあのー、採血することによって、あのー、分かる訳ですね。
MC :あ、それじゃぁ調べる項目もある。#
ゲスト:あります。はい。
MC :へえ。成長ホルモン。勉強になりました。じゃ、100歳の人でも出るってことですか。
ゲスト:そうですね。
MC :ひゃー。じゃ僕たちが朝目覚めるのは成長ホルモンのおかげ?
ゲスト:そうですね。ま、その出が悪い人は
少し目覚めが悪いということもあるかもしれないと思いますよね。
MC :そっかー。いやー。その他、人の成長を調節するホルモンていうのは何かあるんですか?
キッズに関わる
ゲスト:そうですね、やっぱりいわゆる性ホルモンさきほど言われました
男性ホルモン・女性ホルモンですね。
MC :おー、男性ホルモン・女性ホルモン
ゲスト:で、まー、こういった性ホルモンはもちろん、あの、思春期の時に沢山出る訳ですね。
MC :はい。
ゲスト:そして、男性らしい体とか
MC :うん。
ゲスト:女性らしい体とか作っていくんですけれども、
MC :うん。
ゲスト:ま、思春期にどんどん我々体、背が伸びていきますよね。
MC :はい。
ゲスト:あれっていうのは、このー、あのー、性ホルモンが沢山分泌されるからで、
MC :うん。
ゲスト:性、性ホルモンというのは、この成長ホルモンの
MC :はい。
ゲスト:働きを助ける作用がある訳ですね。ですから、
思春期にどんどん体自身も大きくなっていけるということです。
MC :性ホルモンが分泌されると成長ホルモンと結託して、人間の成長
ゲスト:そうですね。
MC :いわゆる十代の成長を
ゲスト:はい。
MC :一気に促すということなんですね。
ゲスト:そうですね。ですから、男性らしさ女性らしさ作りながら
もちろん体全体も大きくなれるのはそういった仕組みなんですね。
MC :なあるほど。身長がぐいぐい伸びる時期ってあるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :これは成長ホルモンが活発に活動してるんではなくて、性ホルモンというものも
ゲスト:はい。
MC :一緒に手伝ってくれてるということ?
ゲスト:そうですね。
MC :だから、十代で一気に身長伸びる子がいるっていうことなんですね。#
ゲスト:そうですね。まあ、いいタイミングにうまく出ることがやっぱ大事だと思うんですね。
MC :なるほど。この性ホルモンというのもやっぱり大人になっても出続けてるわけですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :これも一生もの。
ゲスト:そうですね。まぁ、女性の場合は、あの、
女性ホルモンがいわゆる閉経期になってしまいますと
MC :ああ。
ゲスト:一気に少なくなっていまう訳ですけども。
MC :へー。男の人ってそういうのっていうのは、
何か、何かきっかけあるんですか。出なくなっちゃう。
ゲスト:ま、今もこれ非常に問題になってて、
女性の場合は、ま、更年期としてはっきりとしたストップする時期ってあるんですげども
男性ホルモンはこれだんだんだんだん出が悪くなっていくんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですから気付かれないことがあるんですけども
MC :はい。
ゲスト:どうも、やる気がないとか
MC :はい。
ゲスト:最近どうも人生はかなく感じるとかいうそういうのが実はこの男性ホルモンの、
あの、分泌が少なくなってくるからそういうのが
起こってくるということが最近非常に注目されています。
MC :ちょっと待って下さい。今、あの、キッズ達のために今ね、
お話していただいてると思いきや、
結構、お父さんの中で心当たりある方いらっしゃるんじゃないですか。
今のお話。
ゲスト:そうですね。ですから、あのー、ほんとに今までは年のせいだと思われてたんですけども、
MC :えぇ。
ゲスト:あの、ほんと、男性ホルモン測ってみてそれが少ない方っていうのは
MC :うん。
ゲスト:いわゆる男性更年期の可能性が高いんですね。
MC :うーん。いやこれ、今日は幅広い世代の方にちょっとホルモンに関して、
勉強になりましたよね。でも、100位ホルモンがあるということなので、
来週またさらに詳しいお話を伺っていきたいと思います。
今週の「サイコー」は慶應義塾大学医学部教授の伊藤裕先生でした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「レアアースって何? パート2」 ゲスト:加藤泰浩さん
2019/07/01 Mon 12:00 カテゴリ:環境MC :さ、今週のサイコーも、レアアースに大変お詳しい東京大学大学院教授の加藤泰浩先生です。
こんばんは。
ゲスト:こんばんは。
MC :先生は3年前ネーチャージオサイエンスというとても有名な雑誌で、
太平洋の海底、先週聞きましたね、東京都の南鳥島の周辺の海底からレアアースを含むどろ、
泥の大鉱床があることを発表されました。ま、このレアアース、えー泥ではあるけれど、
えー加工していくと銀の延べ棒みたいになるよっていう、
それがいろんな形でえー日本を救うというお話をしてくださったんですけれど、
ちなみにこの海底というのは深さ何メートルぐらいのところから、泥は。
ゲスト:え、えーとね、これがね実はねすごく深いんですね。南鳥島の周辺だとですね、5600メートルとか。
MC :けっこう深い
ゲスト:5700メートル。
MC :素潜りじゃ無理ですね。
ゲスト:あー、とても無理ですねー。はい。
MC :ふっふっふ。どういう風に採取するんですか。
ゲスト:え、これはね、実はあの今あの深海の石油のですね、資源っていうのが、
だいたいですね、えーと2000メートルとか、ま、3000メートルぐらいにある資源がですね、
えー海底から掘られてるんですね。
MC :海底油田っていいますけどね。
ゲスト:そうですね。石油についてはねそこまではいってるんですが、2000メートル超えるとこまではいってる。
MC :はい。
ゲスト:でねそのえーただね2000メートルの海底から
実はね5000メートルぐらいさらに堀り進んでるんです、石油の資源って。
MC :はい。
ゲスト:だからえー、差し渡し7000メートルぐらいのね、えーと地下からま、
石油は、あげ、採ってるわけですよね。でね、そういう技術を世界は持ってるわけですね。
MC :ほー。
ゲスト:で、日本にもですね、実はこういう深海の石油の開発をやってる会社があってですね、
あの三井海洋開発っていう会社があります。でね、
そういう会社がえーと5000メートルをね、超えるような非常に深い所にあるこの泥もね、
採れるんじゃないかって言ってくれてるんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:それとか後はねフランスの企業ってのは、実はフランスってのはねーあの海洋の資源開発、
石油の資源開発の世界のトップはねフランスなんですよ。
で、フランスの企業なんか、もですねこの泥は採れるぞってことを言ってるんですね。
MC :あ、そうですかー。ただ、なんでもレアアース、
地球上あちこちにあるっておっしゃっていましたけど、
何と世界の生産の97パーセントが中国なんですって。
ゲスト:はい。そうです、あのー
MC :97って大変な数字ですよ。
ゲスト:え、要するにほとんどすべてが中国なんですよ。
MC :な、な、だって日本の海底にもあるわけですよね。
ゲスト:ま、あります。でもそれは採ることはね、今の段階では出来てないですよね。
MC :出来てない。
ゲスト:で、レアアースのですねーあのー資源っていうのはですね、世界中に実はあるんですね。
中国だけにあるわけじゃない。アメリカとかねオーストラリアにもあるですよ。
ところが、そういうアメリカもオーストラリアも中国もですね、
全部そうなんですが、陸上にあるですね、レアアースの資源っていうのは
レアアースを含んでいるだけじゃなくてですね、
トリウムとかウランっていうですねー放射性の元素をいっぱい含んでるんですね。
MC :なるほど。はい。
ゲスト:だからそれをねレアアースを採ると、何をしなくちゃいけないかっていうと、
トリウムとかねウランっていう放射性元素をなんか処分しなくちゃいけないんですよ。
MC :ふーん。
ゲスト:最後にそれ残っちゃうから。
MC :うん、うん。
ゲスト:それがアメリカとかオーストラリアのね環境基準では無理なんで、
そういう国々では殆ど開発が出来ないんですね。
MC :中国はその辺の、ま、ハードルが低いというか
ゲスト:そうです、え、要するに環境基準が著しくこう低いわけですよね。
MC :はい。
ゲスト:ま、ないに等しいってところがあって。
MC :ふーん。
ゲスト:でね中国だけはこう開発する、しかも安く開発するってことが出来て、
それで、ま、中国が独占する形をとってるわけですよね。
MC :それを例えば中国に技術提供することは出来ないんですかね、
日本のその非常にルールに従った、レアアースの使用の仕方みたいなものを、
逆に技術援助とか出来ないんですかね。
ゲスト:え、えーとね、これはね私達が見つけたそのー泥の資源、
要するに深海にある南鳥島沖にあるですね、資源ていうのはですね、
実はトリウムとかウランっていう放射線元素がね殆ど入ってないんですよ。
MC :あっ、そうなんですか。
ゲスト:え、非常にねクリーンな資源なんですよ、だからこれを開発できればね、
そういう放射性元素の問題起こんないんですよね。うん。だからそれをね、
早く開発して要するに環境に配慮した形で開発すればですね、
非常にこう日本のためだけではなくて、中国のためにもなるし、世界中のためになるんですね。
MC :ふーん。あの先生の発見されたね、その南鳥島周辺のレアアース、
ぼくら日本人が「あっ、これのことか!」って認識するのは
いつ何時どういうタイミングできますかねー。
ゲスト:えーとね、ぼくはね、なるべくね、
MC :えー。
ゲスト:私達は実はねこれはね、あのー資源が何処にね、
南鳥島中心に何処にありそうかっていうのはだいたいもう絞り込んでるんですね。
MC :はい。
ゲスト:あとはねその泥を引き上げる技術開発ってことさえ出来ればですね、
私達は、えーなんて言うんですかね、最初のね泥をね、例えばえー5年後、
ね、5年後ぐらいにはね、もちろんそれ手にあのー、引き上げること出来るんじゃないかと、
日本が本気になれば5年じゃなくてね、3、4年で出来るはずなんですよ。
MC :はい。
ゲスト:うん。そうするとねーえーとねー、3、4年後にねそういう泥が採ることができればね、
東京オリンピックでねそういうクリーンな資源を使ったハイブリットカーを走らすとかね。
MC :はー。
ゲスト:あのオリンピックのね体育館のLED電球ぜーんぶね、
日本の国産のね資源で賄うことも実は可能なんですね。
MC :はぁー。
ゲスト:そういうね、夢は持ってる。うん。
MC :いやー、いいですねー。
ゲスト:え、あとはねそれをね、本気で進めるかどうか、とうことが、あのー肝心なんですね。
MC :んー、東京都はねほんとにオリンピックのねー、
招致のプレゼンテーションに環境に配慮したってことは充分打ち出してたじゃないですか。
それ現実問題としてレアアースによってその環境に関しては、
絵に描いた餅じゃなくなる可能性はあるわけですよね。
ゲスト:もちろん、そうです。だから例えばね、さっき言ったみたいに風力発電、
えーと風力発電機にね、レアアースは使われるわけですから、
えーとそういったものにね、配慮してね、風力発電機いっぱい作れば、
えーそういう供給するエネルギーもねクリーンに出来るわけですよ。
MC :うーん、楽しみだなぁ。先生ってもともとこういうそのレアアースのご専門ですか?
ゲスト:いや、ぼくはねー、実はね、地質学者っていって
MC :あっ、地質学の先生でー
ゲスト:そうです。
MC :まあ、地質と言えば地質ですよね、レアアース。
ゲスト:そうですね。あのねー、あの地質なんですけど、もともとね僕はね、
何に興味をもってね研究してたかというとね、地球の歴史って46億年あるんですね。
MC :はい。
ゲスト:でね、46億年のね、地球のあい、地球がまぁ46億年ある間にね
地球の環境ってのがねどうやって変わってきたのか、今私達は地球の温暖化とかね、
MC :はい。
ゲスト:そういったことが非常に問題にしてるわけだけど、地球の環境ってはたしてね今と同じじゃ、
まあ昔と全然違うわけですよ。そういうことがぜーんぶわかってくると、
これからの環境どうすべきかってことに関してもね、
あのいろんな知識が増える、大事なことなんでそういうことをもともと研究してました。はい。
MC :あのー、今のお話でもしかしたらこのレアアースってね、
これから先すごく日本をしょってく非常な貴重な資源かなと思ったんですけれど。
ゲスト:はい。
MC :これからの子供達にもこういうの託したいですよね。
ゲスト:そうですね。レアアースってね、今こういろんなハイテク製品にね
MC :はーい。
ゲスト:入ってるわけだけど、まだまだねいろんな機能が開発する余地がいっぱいあるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:だからそういったものを次々にね日本でハイテク製品を作る、
レアアースのそういう素材開発をしてけば、日本はねますますそういったものを売ってね、
海外に売って、豊かになること出来るんですよ。
だから是非ね、えーみなさん、あのー子供達のねみなさんもね、
こういったことを目指してねあのいろいろやってもらうとね、有難いなって思いますよね。
MC :ほんとですねー。ちなみにレアアースって言葉を僕ら日本人が知ったのって
10年ぐらい前かなーと思ってるんですけれど、この言葉いつごろからあるんですか?
ゲスト:いや、レアアースっていう言葉自体はねぇ、もう非常にもう、1900年、
もう今からですねー、もう100年以上前ぐらいからですね、
MC :えっ、そうなんですか?
ゲスト:え、レアアースって言葉自体はですねー、あるんですねー、はい。
MC :あら、専門家の間ではもうすでにポピュラーな言葉?
ゲスト:あ、もちろんです。あの
MC :浸透してたんですか?
ゲスト:え、レアアースって言葉自体はですね、別にその不思議な言葉ではなくて、
あのー元素のですね、いろんな元素のま、17元素の総称としてね、
私達ふつーに使っている言葉なんで。
MC :へぇー、そっか。あのー、レアアースの実用化技術を確立するのは
日本はトップランナーに、これはなりますかね?
ゲスト:え、僕は充分なれると思ってます。
日本とにかくね、そういうものを作らせたらね世界一の国だったわけですから。
MC :うん。
ゲスト:それをね、やっぱり継続してくためには、レアアースをねどんどん使っていろんな物を創ると、
ものづくり国家として、あのー依然としてこう生きていくんだ!
世界のトップであるんだ!ということをね、あのー日本としてはやるべきだと思いますね。
MC :いやー、2週に渡って、非常にあれですね、ちょっと僕も楽しみになってきましたね。
うかうか年取ってる暇ないですね。また、先生是非遊びに来てくださいね。
ゲスト:あ、どうも有難うございました。
MC :はい。今週のサイコーは東京大学大学院教授の加藤泰浩先生でした。有難うございました。
ゲスト:有難うございます。 -
「レアアースって何? パート1」 ゲスト:加藤泰浩さん
2019/07/01 Mon 12:00 カテゴリ:環境MC :今週のサイコーは、東京大学、東大ですよ、
東大の大学院教授の加藤泰浩先生です。こんばんは。
ゲスト:あ、よろしくお願いいたします。
MC :先生、東大の、大学院の先生、
ゲスト:はい。
MC :周りはみんな頭のいい人ばっかりですね。
ゲスト:いえいえ、全然そんなことはないと思いますね。
あのー、いやいやそんなこと言っちゃたらまずいのかもしれませんが、
えーっとですね、東大のね、先生っていうとね、
みなさん非常に身構えるんですが、そんなことはなくてですね、
私は単なるおじさんですから。
MC :いやー、ほんとに柔和な感じのあのーなんか俳優さんみたいな感じの先生が
ゲスト:いやとんでもないです。
MC :私の目の前にいらっしゃるんですけど。先生はですね、
3年前とても有名なネイチャージオサイエンスっていう雑誌で、
太平洋の海底にレアアースを含む泥の大鉱床があることを発表して
大きな反響を呼んだ方なんですよ。
PHP新書からの本、え、「太平洋のレアアース、泥が日本を救う」と、
いう著書も出していらっしゃるんです。
実は僕年末にレアアースというものに大変興味を持ったんです。
あのー、海の底に眠るダイヤみたいなイメージかと思ったら実は
泥、土?そういうお話を聞いて、ま、レアアースの第一人者の方に
お越し頂いたんですけれど、希少な土っていうイメージですよね、レアアース。
ゲスト:そうですね、レアアースっていうのは訳すとね、稀な土っていうー
MC :あっ、稀な土、
ゲスト:はい。
MC :砂場の土とは全然違う?
ゲスト:まあ、そういう名前がついてるんですが、実際にはね、
レアアースっていうのはえーっとね、みなさんが良くご存じのね、
元素、酸素とか水素とか炭素とかいろんな元素ってありますよね、
あの中のですね17個の元素の総称をレアアースって呼んでるんですね。
MC :全部で元素っていくつあるんですか?
ゲスト:えーっとね、元素っていうのはね、100個以上あって、いろいろあるんですが、
MC :100個以上、そのうちの17、
ゲスト:はいはい、え。でねそれをね、えーっとねだからこれはね、
泥の事をレアアースって言ってんじゃなくて元素の事をレアアース、
その元素群ですね、17個の元素をレアアースって総称してるんですね。
MC :あっ、じゃあ泥じゃないんですね。
ゲスト:そうです。
MC :いわゆる物質、元素。
ゲスト:そうです、元素です。はい。
MC :ほー、それは目に見えるものでもあるんですよね。
でも泥みたいなイメ、泥そのものが調べて見るとその元素、17の元素が含まれていると。
ゲスト:そうです、そうです。その泥の中にすごく濃度の高いですね、
レアアースのいろんな元素が含まれているってのを僕ら見つけたんですね。
MC :自然界では海の底にしか存在しないんですか?
ゲスト:いや、そうではなくてね、この元素ってのは基本的には陸上のね、
例えばみなさんのあのー周りにあるね、岩石を取ってきても必ずねレアアースって入ってるんですよ。
MC :えっ!
ゲスト:入ってる。だけどね、量は少ないんですね。で、えーとね、
今ねそのレアアースの資源ってのは主にもう殆ど中国で採られていて、
それは中国の陸上の鉱山からですね、そういうそのレアアースを含んだ石をですね、
採ってきてそれを精錬して17個の元素に分けてそれをいろんな製品に使ってるわけですよね。
MC :あっ、じゃ地球上のいろんなところにはそのレアアースを含む物質はあるんですね。
ゲスト:あります。それはね、もう普遍的にある。例えばね、金だってそうなんですよ。
あるんですよ。みなさんね、だからねどんな石拾ってきても必ず金は含まれてる、
だけどーすごーく微量なんですよ、だからーそれはいくら集めてもね、あの光り輝くね、
金の金塊にはならないわけですよね。
MC :面白ーい。じゃその辺の石拾って、
「お母さん、この中に金があるよ!」って言っても、それは嘘じゃないですね。
ゲスト:嘘じゃないですよ。全然ね。
MC :あらー。あはははは。
ゲスト:それはね、あのーちゃんとしたね、あのー事実として全ての元素は殆ど含んでいるんですね。
MC :でも、それはやっぱり含有量とか割合みたいなもの
ゲスト:そう、量が違うんですよ、はい。
MC :が、その日本の太平洋の底にあるというのが先生の発見なんですね。
ゲスト:そうですね。私たちはね、2011年にあのネイチャーって雑誌で論文書いたんですが、
そこにはね、実はハワイ、えーとかタヒチ沖にですね、そういう泥が一杯あるぞってことを
MC :南太平洋
ゲスト:はいはい。そうです。そういう所にね、あの一杯あるぞってことを論文に書いたんですね。
で、実際にはねそういった泥は日本の近くにある、あの日本のですね、
ちょうど東京からですね1800キロ南東に離れた所に南鳥島っていう島があるんですね。
MC :あー、ありますねー。
ゲスト:はい、で、それはね、三角形、正三角形の形をしたね、
非常に変わった形をした島なんですが、えーとね、その周辺のね海、
あのー排他的経済水域って言いますが、南鳥島を中心に半径370キロのですね、
半径の円を描くとですね、そこは全部日本が優先的にね、
あのなんか利用できるエリアが、それをね排他的経済水域って言うんですね。
MC :はい。あの地図で見ると小笠原の果ての果て、
ゲスト:果ての果てですよ。
MC :日本に一番東ですよね。
ゲスト:え、最東端、一番ね、東の端
MC :無人島ですね。
ゲスト:え、えっとね無人島じゃないんですね。
MC :自衛隊のなんかあるんですよね。
ゲスト:無人島じゃないんですね。実はねーそこはね自衛隊のね、
えーとね方々がまずね常駐してるんですね。
あのーそれともう一つはね、えーっとね気象庁の人達も常駐してます。
MC :観測地点があるんですねー。
ゲスト:最近はね、国土交通省の人達もー、えーそこに常駐しててですね、
それはね南鳥島の周辺のえーとね、
湾を作ろうとしていて今埋め立てをやってるんですね、はい。
え、だから無人島ではないんですね。
MC :そっかそっか。で、そこにレアアースが眠っているわけですね。
ゲスト:え、その周辺に眠ってる。はい。
MC :先生、泥が日本を救うという著書でらっしゃるけど、
このレアアースがなにゆえ日本を救ってくれるんでしょうか?
ゲスト:え、レアアースってのは、実はですねみなさんにとってね、
非常になじみの深いものなんですね。
というのはねどういう事かって言うと、
今ねあのーみなさんスマートフォンとかテレビを見てると、
見たりとかねいろいろしてると思いますが、
テレビとかスマートフォンとかですね、あるいはえーとね、
家の電気LED電球とか全部レアアースがまず入ってるんですね。
それからハイブリットカーとかね、
これから出てくる電気自動車とかそういうものにはぜーんぶレアアースが
使われているね磁石が入ってるんですよ。
だからね、軒並み我々の身の回りにあるですね、
ハイテク製品には殆ど全てレアアースが入っているんですね。
MC :例えばこのースタジオのラボの中にも、
マイクがあったり時計があったりスピーカーがありますけれど、この中にもレアアースが
ゲスト:もちろん、そうです。入っています。
MC :あ、そうですかー。
ゲスト:え、だからね、そういう意味では非常に身近なものなんですね。
で、ただそれはとにかく日本がね、そういうもの、実はこういうハイテク製品ってのは
日本が作ることはすごく得意なわけですよね。
で、私たちはそういうレアアースの泥を使ってですね、
そこからレアアースを取り出せば様々なねハイテク製品を作れるから
すごく日本にとってねいいじゃないかっていう風に考えてるわけですよね。
MC :そのレアアースっていうのは、ま、
泥たとえばバケツ一杯泥取り出しますよね。どうやって分別するんですか?
ゲスト:あっ、それはね、実はね私たちの泥のすごくいいところは、
えーとね泥の中からレアアースを採る、採りだし方ってのは、あー実はですね、
うすーい塩酸、薄い塩酸にですね短時間こう泥、泥に塩酸つけてるとぜーんぶね泥がね、
泥の中からレアアースが全部塩酸にうつっ、出てくれるんですよ。
つまり溶け出す、その溶け出したね塩酸の溶液をいろいろえーと工業的なプロセスで、
分離してくとレアアースが簡単にできちゃうんですね。
MC :それほど簡単にできるってことは、肉眼で見えるものが出来るんですか?
ゲスト:最終的にはね、レアアースって金属の塊なんで、例えばさっき言ったね17元素のうち、
ランタンとかね、セリウムとか、ネオジムっていうね元素に全部分けること出来るんですよ。
それはね、分けて出来たものはねもうすごい銀色、ピカピカの銀色をしたね、
元素、マテリアルっていうか物質が出来るんですね。
MC :泥なんだけれど、塩酸につけて加工すると、板、銀の延べ棒みたいになってくる。
ゲスト:そうそう、そういうものが出来てくるんですね。
MC :で、それがいろんな形でハイテクしたものに使われてく。
ゲスト:製品に使われてくんですね、はい。
MC :ふーーん。いやイメージできました、だいたい。
しかも私達の泥とおっしゃったけど、やっぱり私達の泥なんですね。
ゲスト:いや、これはね、だからね南鳥島のね、周辺っていうのは日本のね、
が優先的に開発できるとこなのでこれはまさにえーとね、日本の泥、私達の泥なんですよ。
MC :日本の資源
ゲスト:ついでに言うとね、えーとね、江戸前っていうには距離が離れすぎてるけど、
1800キロ離れてるけど、南鳥島ってね東京都なんですよ。
MC :うん、はい。
ゲスト:だからね、南鳥島のね東京都の周りにある海なんだから、これはね江戸前だろうと、
だからねこれは江戸前の資源だ、これはほんとに開発した方がいいぞと、
それが東京都のため、さらに日本のためになるんだっていうね、
つもりでやっていただくのがいいんじゃないかと思いますよ。
MC :これからの時代、もう絶対必要になってきますよね。
ゲスト:あーその通りです。だからね、まさにこれからの時代を担う
あのーそういうね物質なんですね、レアアースっていうのは。
MC :はぁー。あっという間にお時間が来てしまいましたよ。
またちょっと詳しくこのレアアースと日本の可能性、
これから将来も含めて来週伺いたいと思います。先生また来週お願いしますね。
ゲスト:あ、よろしくお願い致します。
MC :はい、今週は東京大学大学院教授の加藤泰浩先生にお越しいただきました。有難うございました。
ゲスト:有難うございます。 -
3月23日イベントレポート②
2019/06/01 Sat 13:00 カテゴリ:イベント「ネクストサイエンスジャム」の目玉の1つ、高校生によるプレゼンコーナー。
今回は「科学技術立県を支える次世代人材育成プロジェクト」の
埼玉県立川越高等学校・生物部のみなさんが
クマムシや魚、虫の触覚などの細部を電子顕微鏡
で観察した結果を報告してくれました。
『クマムシ』のとてつもない環境適応能力に会場の子どもたちはもちろん
大人達も驚きながらプレゼントを聴いていました。
『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
科学ジャーナリストの寺門和夫さんが登場。
子どもたちから寄せられた様々な質問の中から
『宇宙人がいたとしたら、どういうふうに
コミュニケーションを取れるのでしょうか?』、
『地球上の人口が増え続けると、
酸素が足りなくなる可能性はあるのですか?』
などについて解説してくださいました。

今回はここまで。
現在次の企画を進めています。詳細が決まったらこのホームページでお知らせしますので
楽しみにしていてください! -
3月23日イベントレポート①
2019/06/01 Sat 13:00 カテゴリ:イベント子どもたちの「科学する心を育む」プロジェクトとして、
日立ハイテクノロジーズと文化放送が協力して、
科学実験とラジオ公開録音が一体になったイベント
「ネクストサイエンスジャム」
5回目、そして平成最後の公開録音となった今回は文化放送メディアプラスホールで開催され、
たくさんの子どもたちが参加してくれました。
ここではそのイベントの様子を少しだけご紹介します!
今回のナビゲーターは、
おなじみの俳優でタレントの照英さん!
番組の企画で世界を各地旅していて、なんと北極にも行ったことがある照英さん。
その照英さんでさえ行ったことの無い場所、南極。
今回はその南極とそこに生息している生き物たちにフォーカスを当てます。
まずはこの公録イベントの目玉のひとつ、ネクストサイエンストークショー。
今回のテーマは「南極と生き物たち」。南極はどんなところ?という基本的な所から始まり、
厳しい環境の南極で暮らす生き物たちのリアルな生態を、子どもたちにわかりやすく紹介してくださいました。ゲストは国立極地研究所 助教の田邊優貴子さん。
田邊さんが実際に南極で着ていた服の凄さに会場が驚き、
さらにその装備でも乗り切れない寒さを記録する場所がまだ南極には存在していることに
会場全体が驚きました。
そこから『南極でのお仕事』『南極を一言で表わすと・・・』などの
田邊さんの経験談を交えて丁寧に説明してくださいました。
そしてみんなが知りたいペンギンやアザラシの生態についてお話していただきました。
ペンギンやアザラシのリアルな生態や豆知識に会場のみなさんからは何回も驚きの声が上がっていました。
そして南極に関するクイズにみんなで挑戦しました。
個性あふれる予想を出す子どもたち。そしてその予想を超える正解に
田邊さんは的確に、そしてわかりやすく解説して頂きました。
田邊さんが子ども達に送った「自然を見て純粋に『凄いな』と思った気持ちを
一番大事にして欲しい」という言葉。会場のみなさんの心に響いているようでした。 -
「コウモリの科学 パート2」 ゲスト:大沢啓子さん
2019/06/01 Sat 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ今週のサイコーもですね、コウモリの会評議員の大沢啓子さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :もー前回、とっても興味深いコウモリのお話、
えー日本にいるコウモリの話とか、世界1300種類のコウモリの話、で、
コウモリはなんと哺乳類でおっぱいがあるという話色々伺いましたけれど、
大沢さんはご主人と世界中を周りながら、
コウモリの写真ご主人が撮ってらっしゃるということで、
この今手元に「身近で観察するコウモリの世界」という写真の本があるんですが、
これご主人が全部撮ったんですね。
ゲスト:あっはい。そうです。
MC :様々なコウモリ
ゲスト:はい。
MC :これまた、ご主人の名前が大沢夕志さんという、
夕方の夕(ゆう)に志(こころざし)。もう夜行性にぴったりな名前ですね!
ゲスト:あっそうですか、考えた事なかったです。
MC :あっはっはっはっ。でもあの、コウモリって夜行性だから
ゲスト:はい。
MC :もう夜な夜な、だから世界行っても、世界の観光地の風景じゃなくて、
ゲスト:はい。
MC :もう夕方になると、コウモリ撮りに行く訳ですね!
ゲスト:はい。あの夕方そうやって、
MC :ええ。
ゲスト:夕方からまあ夜中ぐらいまでかけて
MC :ええ。
ゲスト:撮ってまわってますので、
MC :ええ
ゲスト:こう普通の人が例えば沖縄へ行ったら、海へ行って
MC :はい。
ゲスト:泳ぐと思うんですけど、
MC :はい。
ゲスト:えー我々沖縄へ例えば40回ぐらい多分撮影で行っていると思うんですけど、
MC :ええ。
ゲスト:そういうこう夜の撮影と昼間遊ぶことって中々両立しないんですよね。
MC :はい。
ゲスト:だからもう沖縄で泳いだのは、何回だ?2、3回かなって感じです。
MC :かなり、変人に近い動きですね、
ゲスト:はい。ビーチへ行かないで沖縄これだけ通ってて
MC :あっはっはっはっ。もう世界は例えばどんなところをコウモリ撮影して周られたんですか?
ゲスト:えー我々オオコウモリって呼ばれる仲間が好きなんですけれど、
MC :ええ。
ゲスト:日本だと2種類しかいないので、
MC :ええ。
ゲスト:まあオオコウモリ、あの他の国のオオコウモリを観るためにですね、えー太平洋の島、
MC :はあ。
ゲスト:えー例えばサイパンとか、グアムとか
MC :うーん。
ゲスト:或いはえーパプアニューギニア
MC :うーん。
ゲスト:とか、フィージーとか
MC :ほーう。
ゲスト:そういう所に行ってますし、
MC :南半球も行くんですね。
ゲスト:はい。
MC :ほう。
ゲスト:あとオオコウモリが生息している所では、
まあ比較的オオコウモリってあのアフリカとか太平洋の島に多いんですけれど、
MC :ええ。
ゲスト:比較的安全で行きやすいところっていうとオーストラリアなんですね、
MC :オーストラリア
ゲスト:はい。
MC :はーい。
ゲスト:オーストラリアはえー1年間かけてぐるっとこのキャンピングカーで一周したことあります。
MC :へえー。でもコウモリ、この写真で見るとね、
コウモリが意外にオーストラリアで思い出したんだけど、
コアラみたいな顔をした、可愛いんだこれがまた。
ゲスト:はい。
MC :ですよね。
ゲスト:可愛いと思いますが。
MC :だって夜行性だからね、目が退化していると思ったら意外にコウモリの目ってくりっとしてまん丸なの。
ゲスト:あっそれはコウモリによるんです。
MC :あっそうなんですか。
ゲスト:あのー、いわゆる超音波を、コウモリっというと、超音波を使って
MC :ええ。
ゲスト:その音を頼りにえー虫を捕ったりとか、
それから周りにぶつからないようにしているっていうイメージがあると思うし
MC :ええ。
ゲスト:実際にそうなんですけれど、えーオオコウモリの中でも、
このオオコウモリの仲間っていうのは、えー殆どがエコロケーション、
あの超音波を使わないんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、その代わり、えー他のムササビやなんかの夜行性のあの獣と
同じように目が大きくてそのえー非常に視力が良くて
MC :ほーう。
ゲスト:その視力で物を見ていますのでくりんとした
MC :あっ。
ゲスト:こう目をしているんですね。
MC :オオコウモリの
ゲスト:はい。
MC :仲間は目が大きい。
ゲスト:はい。
MC :いわゆる超音波でコミュニケーションを取るコウモリは目が小さい。
ゲスト:小さいというか、大きくする必要はそれほどなかったんです。
MC :そういう事ですね。コウモリの超音波で会話するってのはなんか聞いたことがあるんですけれど、
ゲスト:はい。
MC :これ人間の耳では聴こえないんですか?
ゲスト:えーとーあの割とえー低い音声を使って
MC :うん。
ゲスト:えーそのエコロケーションっていうんですけど、
こう音声をぶつけて返って来た音を聴いてるってのをやるやつもいますから、
MC :うん。
ゲスト:そういうコウモリだと聞こえることもありますが、
MC :あっ人間の耳にも?
ゲスト:はい。
MC :どんな感じで?
ゲスト:我々は大体20KHzぐらいまで聞こえるっていわれていますけれど、
MC :ええ。
ゲスト:低い声のコウモリだとそれより更に低いあの超音波域も使うけど、
それより低い我々が聞こえるような音声を使うやつもいます。
MC :耳鳴りみたいな音ですか?
ゲスト:あのー、えーと聞こえる音としては我々にとっては非常に高いですから
「ツンツンツン」というような金属的な音に聞こえますね。
MC :へえーコウモリの声?
ゲスト:あっそれはただあの小さいタイプのそのエコロケーションするタイプでは、
どっちかっていうと少数派で
MC :はい。
ゲスト:ほとんどのコウモリはえー我々は聞こえない、
非常に高い超音波域の声を出しますので、何も聞こえないです。
MC :何も聞こえない。それででもコウモリ同士のコミュニケーションは取れている訳ですね。
ゲスト:あのー、うん。コミュニケーションも取りますけど、
普段はそのエコロケーション、えー超音波は何のために使うかっていうと
MC :ええ。
ゲスト:先ずは、えー夜飛んでる時にぶつからないようにするために、
MC :ええ。
ゲスト:えーその口から出した、或いは、鼻から出した超音波を周りの景色に
ぶつけて返ってくるくるエコーを聞いているんですね。
MC :えー!?はーい。
ゲスト:で、お互い同士ももちろんそれで、えー親子のコミュニケーションとかもしますけれど、
普段飛んでる時は、その、何ていうか、周りの障害物とか、
MC :うん。
ゲスト:それから餌の虫がいるかとか、そういうのを調べる為に出している事が多いです。
MC :最新の車のブレーキシステムみたいな感じですね!
ゲスト:あっそういう、そんな感じですね。
MC :すごーい。そういう為に超音波出しているんですね。
ゲスト:はい。
MC :へえー。いや知らなかった。
ゲスト:いや潜水艦とかみんなそういう風にするじゃないですか?ソナーを出して
MC :うん。
ゲスト:返ってくる
MC :はいはい。
ゲスト:海底の地形を調べたりしますよね。
MC :へえー。あと白いコウモリ?シロヘラコウモリっていう写真があるんですけど
ゲスト:はい。
MC :コウモリってどうしても黒いイメージで日本では昔コウモリ傘なんて言われてね、
最近はもう流石にコウモリ傘って言う人はいないけれど、白いコウモリもいるんですね。
ゲスト:白いコウモリもいますし、
MC :はい。
ゲスト:あとはもっと派手派手のあのオレンジと黒の模様とかもいますし
MC :えっー?外敵から襲われたりしないんですか、そんな派手な・・・
ゲスト:白いコウモリっていうのは、
MC :ええ
ゲスト:あのー葉っぱの裏にねぐらを取るコウモリなんで、
MC :ええ。
ゲスト:こう太陽の光が上から来て
MC :ええ。
ゲスト:地上性の捕食者っていうのは下にいますよね。
MC :はい。
ゲスト:そうすると葉っぱの裏からあの白いコウモリがいると、
太陽の光が透けると緑色に染まって見えるですね
MC :うん。はい
ゲスト:その写真もそうなってると思うんですけど、
MC :そうですね。うん。
ゲスト:そうすると意外と保護色になります。
MC :うん。今この写真は何かグリーンと白のコウモリ、
だから葉っぱのなんか一部みたいな、同化している色にも見えるので
ゲスト:それはそれでちゃんと保護色にちゃんとなっていると思います。
MC :なるほど。その生息する場所に
ゲスト:はい。
MC :色を合わせているということなんですね。コウモリ因みに何食べるんですか?
ゲスト:えー7割位は虫を食べている
MC :虫。ほう。
ゲスト:種類が殆どですけれど。
MC :はい。
ゲスト:あのオオコウモリの仲間などは、えー果実、
MC :ええ。
ゲスト:果物の実を食べますし、あとは花の蜜をなめるコウモリもいますし、
MC :うーん。まあそこまで可愛いけれど僕らコウモリというと
人間の生き血を吸うドラキュラっていうのは、
なんかなんかコウモリのイメージじゃないですか?
ゲスト:はい。
MC :あれはちょっと専門家から見るとどうなんですか?
コウモリイコールドラキュラみたいなこういうイメージというのは?
ゲスト:うん。それは残念ですけど、
MC :ええ。
ゲスト:あの血を食べる、吸うっていうイメージとはちょっと違うんですけど、
血を食べるコウモリはその世界の1300種弱のうちの3種類はいますよ。
MC :えっ?やっぱり血を食べるコウモリっているんですか?
ゲスト:はい。
MC :えっ1300分の3しかでも、いないんですか?
ゲスト:で、日本にはいませんので、
MC :あっ、えーっ!?それがイメージなんですかね、ドラキュラのイメージ?
ゲスト:ドラキュラは、でも物語がヨーロッパですから。
MC :ええ。
ゲスト:えーヨーロッパの方には、その血吸いコウモリは住んでいませんが。
MC :あっ血を吸うコウモリというのは何処に住んでいるんですか?
ゲスト:えー中南米ですね、
MC :それ、人間の血じゃないんですよね。
ゲスト:あのー3種類の内の2種類は鳥の血を食べます。
MC :えー。
ゲスト:1種類だけ哺乳類の血を食べるナミチスイコウモリってのがいるんですけど、
MC :ええ。
ゲスト:これは、こう野外で夜動物が寝てる、
哺乳類が寝ている時に、こうそっーとその体の上に乗って
MC :はい。
ゲスト:歯が非常に鋭いんで、
MC :はい。
ゲスト:で、歯で傷口を開けて流れ出る血を蛭みたいにこう舐めるんですね、
MC :えー分かりました。いやコウモリってちょっとあんまり知識なかったけど、
このね、あのご主人が撮った写真の本を拝見していると、
羽を広げる姿も美しいし、その羽越しに血管がしっかり見えてね、
ゲスト:はい。
MC :おっと哺乳類だなっていうなんか、こうちょっとイメージ変わりましたね。
ゲスト:その翼は皮膚というかあの要するに皮ですから、
MC :うーん。
ゲスト:表面に皮膚があって、筋肉も通ってて血管も通ってます。
MC :うーん。美しいですね。
ゲスト:はい。
MC :いやあ凄い、ちょっとコウモリの見方変わった、皆もそうでしょ、
いやあもうお時間ですね、ありがとうございました。
えー2回に渡ってお話を伺いました、
今週のサイコーはコウモリの会評議員の大沢啓子さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「コウモリの科学 パート1」 ゲスト:大沢啓子さん
2019/06/01 Sat 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ今週のサイコーは、コウモリの会評議員の大沢啓子さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :コウモリの会というのがあるんですか?
ゲスト:はい。あるんです。野鳥の会は知られていまけど、
MC :ええ。
ゲスト:でもコウモリの会というのもちゃんとあります。
MC :えー大沢さんは、コウモリに詳しくてご主人と一緒に、
誠文堂新光社から「身近で観察するコウモリの世界」
ゲスト:はい。
MC :それから「コウモリの謎」などの本も出版されていると。でコウモリの専門家なんですね、
ゲスト:えー研究者ではありませんけど、
MC :ええ。
ゲスト:そのコウモリ、あまり身近な割に知られていない、そのコウモリというのを
MC :はい
ゲスト:皆にアピールする為の、えー親善大使みたいなものだと思っています。
MC :多分ねラジオを聴いているキッズ、
「コウモリ知っている人?」って言ったら100人中100人手を挙げると思うんですよ。
ゲスト:はい
MC :じゃあ「コウモリ見たことある人?」って言ったら、
恐らく殆どのお子さん方が手挙げないでしょうね。
ゲスト:そうですね、まー私なんか、観察会とかお話会で話す事があるせいか、
MC :ええ。
ゲスト:多少関心を持っている人が多いですから
MC :ええ。
ゲスト:もうちょっとあの見たことあるって人のいうパーセンテージ上がりますけど
MC :ああー。
ゲスト:完全に一般の人だったら見たことないって言うかもしれないですね。
MC :でも身近で観察するコウモリの世界という本がある。
それで、このコウモリって身近な物なんですか?
ゲスト:はい。あのー東京周辺だったら家に入るコウモリも居ますから
MC :ああ。
ゲスト:ひょっとしたら知らないけどお宅の家にも入っているかもしれないです。
MC :あっ、皆の家にもコウモリ入っているかもしれない?
ゲスト:はい。
MC :あの、僕、日原鍾乳洞。
ゲスト:はい。
MC :奥多摩のコウモリ見たことあるんですよ。30年ぐらい前ですかね。
ゲスト:はい。
MC :あっこれがコウモリか!って。
ゲスト:うん。あの洞窟のイメージっていうのは、普通の人持っているかと思うんですけど、
MC :はい。
ゲスト:また洞窟は
MC :うん。
ゲスト:この辺のあのー家に入っているのとは別の種類が入っています。
MC :えっ?家に入るコウモリって
ゲスト:はい。
MC :例えば?例えば?
ゲスト:はい。
MC :東京のど真ん中でも
ゲスト:はい。
MC :コウモリって生息してる?
ゲスト:普通にいます。
MC :普通にいるんですか?
ゲスト:はい。
MC :浜松町にもいるんですか?
ゲスト:あのー東京湾の周辺の埋立地とか
MC :ええ。
ゲスト:普通に居ますから
MC :えーえ!?
ゲスト:あのーえっと夫が撮影するのに一緒に私同行して
MC :ええ。
ゲスト:例えばお台場の辺りとか、
MC :ええ。
ゲスト:えー東京タワーの周辺とか
MC :ええ。
ゲスト:えー或いは、えっと観察会で浦安とか
MC :ええ。
ゲスト:あの辺に結構行きましたよ。
MC :お台場とか、東京タワーとか、
ゲスト:はい。
MC :まあ変な話、ディズニーランドにも
ゲスト:あっディズニーランドも飛んでます。
MC :ああそうですか?結構じゃあ身近なところにコウモリはいるんですね!
ゲスト:はい。
MC :えーっ!?何コウモリですか?
ゲスト:それはアブラコウモリっていって
MC :うんうん。
ゲスト:まあこの辺だと、多分アブラコウモリ。
文化放送の辺りだったらその一種類しかいないと思います。
MC :文化放送の周辺にアブラコウモリがいる。
ゲスト:多分
MC :アブラコウモリってどんなコウモリですか?
ゲスト:えー翼を広げると20センチぐらいあるんですけど、
MC :うん。はい。
ゲスト:あのー鳥もそうですけど、空飛ぶ動物っていうのは、翼閉じちゃうと割と小さく見えるんですね。
MC :はい。
ゲスト:だから頭から胴体までは、頭からあのー体の末端までは、5センチぐらいしかないコウモリですね。
MC :うーん。まあ小っちゃい。でも翼を広げると20センチ。
ゲスト:はい。
MC :体長は?5セン・・・5センチぐらい?
ゲスト:5センチぐらいですね。
MC :小っちゃい。
ゲスト:そう。
MC :凄い小っちゃい。
ゲスト:あーだからあのー、たまにえー落っこちてるというか、
あのー寿命がきたのか、或いは暑さにやられたのか、
落ちてるコウモリがいたとかいう人に聞くと、
MC :はい。
ゲスト:子供の・・・子供のコウモリが落ちてましたと言うんですよね。
MC :ほーう。
ゲスト:飛んでるイメージからするとすごく
MC :うんうん。
ゲスト:すごく小さく感じます。
MC :あっそうか、そうか。
ゲスト:はい。
MC :もうコウモリ羽を縮めるともう物凄く小っちゃい感じですか?
ゲスト:そうですね。
MC :はー子供に見えちゃう。
ゲスト:うん。あのー飛んでる姿しか多分殆どの人は知らないと思うんですけれど、
MC :はあー。
ゲスト:それからすると凄く小さく感じます。
MC :えっそのアブラコウモリって、ねぐらは何処なんでしょうかね?
ゲスト:えー普通の家のーえー屋根裏とか、
MC :ええ。
ゲスト:瓦の下とか、
MC :ええ。
ゲスト:或いはビルだったらあの屋上のところによく、
あの屋上の一番ふちのところにパラペットっていう、
あの出っ張ったなんか低い塀の様な物が
MC :うん。ありますね。
ゲスト:ぐるっと一周あると思うんですね。
MC :うん。
ゲスト:あれの上に金属カバーがよく付いていますよね。
MC :はい。
ゲスト:その下に結構入ります。
MC :コウモリが?
ゲスト:はい。
MC :コウモリって巣を自分で作ったりしないんですか?
ゲスト:巣っていうイメージとちょっと違いますけど、
MC :うん。
ゲスト:ねぐらはアブラコウモリの場合はそういう所にいます。
MC :所謂隙間とか、所謂スペースをねぐらにしているってことですね。
ゲスト:アブラコウモリはそういう隙間が大好きですね。
MC :ふーん。カラスみたいに巣を作ったりする訳じゃないんですね。
ゲスト:別に自分で巣を作ることはないです。
MC :へえー。
ゲスト:というか、世界にはそういう、自分でねぐらを作るコウモリもいますけれど、
MC :ええ。
ゲスト:日本のコウモリにはそういうのはいないですから。
MC :へえー。いやーアブラコウモリ、
ゲスト:はい。
MC :都会の真ん中にいるんですね。
ゲスト:はい。
MC :へえー。見たことありますか?
ゲスト:別に毎日見てます。
MC :いやあーそんなの見たことないよ。
ゲスト:ふふ。
MC :いやあーえっ。
ゲスト:やっぱりあの夜行性なんで
MC :ええ。
ゲスト:そのねぐらから出てくるのがちょうどその日没時間ぐらいで
MC :はい。
ゲスト:その時はまだ姿見られますけど
MC :はい。
ゲスト:そのあともう10分か20分すると暗くなっちゃいますよね、
MC :はい。
ゲスト:だから多分ほとんどの人は見たことがないって言うんだと思います。
MC :わー意外にじゃ日常にコウモリのねぐらはあるんですね!
ゲスト:はい。
MC :都会の真ん中にも
ゲスト:はい。で特に古い家でなくても
MC :うん。
ゲスト:それこそビルのパラペットカバーの
MC :うん。
ゲスト:下にもいるぐらいですから、新しい家だって結構隙間っていうのはあるものです。
MC :いや見たいなあ。やっぱり自由研究でコウモリってのもありだと思うんですけれど。
ゲスト:はい。
MC :コウモリってどんな生き物か?と
ゲスト:はい。
MC :そもそもですけど
ゲスト:コウモリ全体についていうならば
MC :ええ。
ゲスト:世界に1300種弱いますから、
MC :うん。
ゲスト:それこそ様々です。食べ物もえー虫を食べるものが多いですけれど、
植物の果物だの、えー花の蜜吸うやつもいますし、
MC :はい
ゲスト:えーあとは少ないですけど、あの小さい小動物捕ってる肉食のものもいますし、
MC :はい
ゲスト:魚捕るやつもいますし、
MC :ええ。
ゲスト:あとねぐらもそうやって隙間に入るのもいるし、
MC :はい
ゲスト:イメージ通り洞窟に入るやつもいますし、
MC :はい
ゲスト:あとはオオコウモリの仲間なんかは、木からぶら下がっているだけですから。
MC :えっ?木からぶら下がってるだけってのは、飛ばないという事ですか?
ゲスト:あっいや、ねぐらです。
MC :あっねぐらね、
ゲスト:はい。
MC :へえー日本には何種類くらい、いるんですか?
ゲスト:えー絶滅したといわれているのが、2種いて、
MC :ええ。
ゲスト:で、まあ多分現在いると思わるのが、35種います。
MC :結構いるんですね。
ゲスト:はい。
MC :最初大沢さんがコウモリをご覧になったのは、どこですか?
ゲスト:えー沖縄の南大東島というところに、
MC :わー。
ゲスト:えーダイトウオオコウモリ、あのー、
種でいうとクビアオコウモリですけども、
それの亜種のダイトウオオコウモリというのが、
MC :ダイトウコウモリ
ゲスト:ダイトウオオコウモリです。
MC :ダイトウオオコウモリ
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:でそれを観に行ったら、えー何日目だか、ちょっと忘れましたけど、
MC :ええ。
ゲスト:まあ見られて、で凄く可愛かったです。
MC :えーっ、えっ大東島?
ゲスト:はい。
MC :めちゃめちゃ遠いところですよね!
ゲスト:台風のあのー、えー情報や
MC :そうだ!
ゲスト:何かでお馴染みがある場所ですね。
MC :大東島沖をとかゆっくり
ゲスト:そうです。
MC :北上しとか言ってますよね。
ゲスト:はい。
MC :あっえっと地図でいうと、沖縄の本当があって、そこから東の方に数百キロ行ったところですね。
ゲスト:はい。ずーっと行ったところです。
MC :うーん。飛行機もね、毎日飛んでないんで、ここはね、凄い、
あー絶海の孤島と呼ばれるこの大東島で、
ダイトウオオコウモリを観たことがきっかけですか?
ゲスト:はい。
MC :うーん。
ゲスト:まあ意外と簡単に見られたのと、あとまあ動物皆私好きですけど、
その哺乳類の中では比較的姿が良く見られるんですね。
MC :哺乳類?
ゲスト:はい。哺乳類です。鳥ではありません。飛びますけど。
MC :コウ、コウモリが哺乳類?
ゲスト:はい。
MC :これ、皆知ってた?いやいや知らないですよ。
ゲスト:あのー赤ちゃんを産みますし、
MC :ええ。
ゲスト:卵じゃなくて、赤ちゃんを産みますし、
MC :ええ。
ゲスト:あとお母さんがおっぱいあげて育てますし、体に生えてるのは
MC :あっ!
ゲスト:あのー羽毛じゃなくて、毛ですし、
MC :コウモリおっぱいあるんですか?
ゲスト:有ります。脇の下に。
MC :しゃー!!えーちょっとお時間になっちゃいましたね、
また更に大沢さんのこれ、ご主人が撮影した写真ですか?
ゲスト:はい。そうです。
MC :「身近で観察するコウモリの世界」こういったその撮影されたお写真などを
見ながらコウモリに関して詳しく見ていきたいと思います。
今週のサイコーはコウモリの会評議員の大沢啓子さんでした。
どうもありがとうございました。 -
「宇宙の話 パート2」 ゲスト:長谷川洋一さん
2019/05/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は前回に続きまして、
ワンアースの長谷川洋一さんです。よろしくお願いいたしまーす。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :長谷川さん
ゲスト:はい。
MC :今日から10年目に入りました。ありがとうございます。
ゲスト:おっと。
MC :番組。ありがとうございまーす。
ゲスト:おめでとうございます。
MC :えー。いやいやいやいや。
ゲスト:ふふふ。
MC :で、壮大な宇宙のお話。
ゲスト:いやー。
MC :先週、油井公也さん、のミッションのお話など聞いたんですけれど、今週はね、
ゲスト:はい。
MC :あのー、夏休みだったから、みんなも見てたと思うんだけど、
ロシアから油井さんて、国際宇宙ステーションに行ったんですよね。
ゲスト:はい。
MC :そのあと、「コウノトリ」っていうのが、
ゲスト:はい。
MC :国際宇宙ステーションに着いたじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :と、「コウノトリ」は
ゲスト:はい。
MC :どっから飛んだんですか?
ゲスト:「コウノトリ」は日本の種子島からですよ。
MC :種子島か。
ゲスト:ええ。
MC :えっ、じゃあ、えっとロシアから
ゲスト:ええ。
MC :油井さんは行ったんだけど、
ゲスト:ええ。
MC :ええと、宇宙で、
ゲスト:ええ。
MC :日本から来た
ゲスト:ええ。
MC :「コウノトリ」と
ゲスト:ええ。
MC :出会ったってことですか。
ゲスト:ああ、そうですね。
MC :すごいですね。
ゲスト:ええ。
MC :え、その「コウノトリ」を国際宇宙ステーションに持ってくのは、
人乗ってないわけですよね。
ゲスト:あ、そうですね。はい。
MC :だから、ロケットで、
ゲスト:ええ。
MC :積んで、
ゲスト:ええ。
MC :「コウノトリ」を、
ゲスト:ええ。
MC :ISSにくっつけたってこと?
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :よく、出来た話ですね。
ゲスト:あはは。
MC :だってさ、だってすごくないですか、人がコントロールするわけじゃないのに、
ゲスト:あ、そうなんですよ。
MC :うん。
ゲスト:これがですね、あのー、あのー、ま、今回、あのー、油井公也さんが宇宙で、
MC :はあ。
ゲスト:ロボットアームを操作して、
MC :はい。
ゲスト:「コウノトリ」を捕まえたんですね。
MC :はい。
ゲスト:それでこれはですね、あの、ま、私はコンチェルトって呼んでるんですけども、
MC :コンチェルト。
ゲスト:ええ、協奏曲?
MC :はい。
ゲスト:あのー、指揮者がいてオーケストラがいて、
MC :はい。
ゲスト:もう一人、あの、バイオリンとかピアノで、
こう、あの、ソロをやるソリストがいますよね。
MC :はい。
ゲスト:こういうふうに、あの、考えると分かりやすいんですが、
MC :はい。
ゲスト:あの、ヒューストンで若田さんがいてですね、
MC :あ、アメリカで?
ゲスト:ええ。
MC :若田光一さんが。
ゲスト:アメリカヒューストンで若田さんが、あの、大ボスみたいな感じで総合リーダー
MC :ほー。
ゲスト:やってたんですね。
MC :はい。
ゲスト:それからつくばの、あの、
MC :はい。
ゲスト:宇宙センターJAXAの、宇宙センターには大勢の管制職員がいて、
MC :うーん。
ゲスト:そして管制していた管制、あの、Operations controlですね。
MC :はい。
ゲスト:をやってたんです。そして、宇宙では、油井公也さんが、
MC :はい。
ゲスト:いたと。
MC :はい。
ゲスト:で、これを例えるならならば、若田さんが指揮者、
MC :はい。
ゲスト:そして、つくばの、あの、みんなが、あの、オーケストラ、
MC :はい。
ゲスト:そして、そこでワーッとやりながら、あの、一番かっこいいのがソリストですよね。
MC :はー、
ゲスト:で、宇宙で油井公也がロボットアームで、「コウノトリ」を捕まえたと。
MC :へー。
ゲスト:この、あの、三つの役者が全部、
あの、うまく頑張ったから、あの、連携して、うまくできたんです。
MC :えー、じゃ、宇宙とつくばとアメリカヒューストンの
ゲスト:そうですね。
MC :トライアングルが、
ゲスト:そうです、そうです。
MC :奏でた、
ゲスト:ええ、日米宇宙、うふふ。
MC :いやー、すごい。それで、
ゲスト:ええ。
MC :えっと、「コウノトリ」が
ゲスト:ええ。
MC :国際宇宙ステーションにうまく、
ゲスト:はい。
MC :ドッキングして、
ゲスト:はい。
MC :で、この「コウノトリ」は何やってるんですか。これは。
ゲスト:あ、「コウノトリ」、あ、そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:「コウノトリ」はですね。あの、ま、荷物の運び屋なんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:あのう、いろいろな実験装置とか、
MC :はい。
ゲスト:それから、ま、食べ物もそうですよね。
MC :はい。
ゲスト:とか、宇宙飛行士たちが必要な物資を運んでいくんですね。
MC :うん。
ゲスト:そして、ま、特にあの、今、あのー、「コウノトリ」は、あの、
MC :ええ。
ゲスト:世界で一番、あの、沢山物運べる、
MC :はい。
ゲスト:あの、ま、超巨大輸送機なんですよ。
MC :はい。
ゲスト:10トンくらい運べちゃうんです。
MC :はい。
ゲスト:これはあの一番すごいですねえ。
MC :ほー、そこにどんなものが積まれてたんですか。
ゲスト:ええと、今回例えばですね、あの実験の、あ、新しい実験装置。
MC :ええ。
ゲスト:これがあの、沢山積まれていきました。
MC :へー。
ゲスト:それとか、あの、ちょっと話題になりましたけれども、あの、ウイスキーなんかも
MC :おー。
ゲスト:これは実は、残念ながら宇宙飛行士が飲むためじゃないんですよ。
MC :ええ。
ゲスト:あの、実験のために、宇宙でウイスキーを熟成したら美味しくなるかどうかを、
MC :いや。
ゲスト:確かめるための
MC :すごい、すごい。
ゲスト:あの、ウイスキー。これ宇宙で絶対開けられないようになってます。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:はい。あの、残念ですね油井さん。
MC :いやー。
ゲスト:んふふふ。
MC :ちょっとなめるぐらいもダメ?
ゲスト:それダメってことですね。
MC :ってことですね。
ゲスト:開けたらすぐわかっちゃいますから。
MC :え、でも、ど、どうなんだろ。よくね、焼酎とかも、
ゲスト:ええ。
MC :あのー、クラッシック聞かせて、
ゲスト:ええ。
MC :熟成するといいんじゃないか
ゲスト:あっははは。あ、そうそう。
MC :そうそう。やってますよね。よく。
ゲスト:ええ。だから、
MC :そんな感じですか。
ゲスト:おいしくなるかもしれませんね。
MC :宇宙行ったウイスキーだったら高く売れるんじゃないですか?
ゲスト:あ、そうですね。きっと、その、どっかの会社が儲けるかもしれませんけど、
MC :今、何か
ゲスト:ええ。
MC :中国とかで、ウイスキーブームが来てて、
ゲスト:あははは。そうですか。
MC :もーのすごく高く売られてるんですよ?
ゲスト:ははは。ああ、そうですか。
MC :上海とかでも、
ゲスト:ええ。
MC :ウイスキーのセリで、
ゲスト:ええ。
MC :1000万超えたウイスキーがあるっていって。
ゲスト:あ、そうですか。
MC :も、とんでもない値段が今、今ブームなんですよ。
ゲスト:あー、じゃこれも
MC :中国で
ゲスト:高いかもしれませんね。
MC :だからこれね、宇宙ウイスキーで
ゲスト:ええ。
MC :ちょっと長谷川さん、僕らでなんか一儲け、あと、日立ハイテクさんも交えてですね、
ゲスト:ええ、ええ。
MC :ちょっとビジネスをじゃあ
ゲスト:すごいですね。
MC :あははははは。
ゲスト:あの、キッズのみんなはなんか怒ってるかもしれないですね。
MC :いいよね。
ゲスト:あはは。
MC :うまく、うまくね。ちょっと、
ゲスト:ええ。
MC :お父さんも巻き込んで、
ゲスト:ウイスキーボンボンぐらいで
MC :おほほ。
ゲスト:キッズのみんなにもちょっと、ま、そんなのとかですね。
MC :ええ。
ゲスト:それからですね、エルフっていうとキッズのみんなたぶん、あの
MC :エルフ?
ゲスト:エルフってなんか、あの、よく、あのー、昔のファンタジーに出てくる
MC :僕の中でトラックなんだけど
ゲスト:あははは。
MC :あるよね?
ゲスト:実は、そのエルフっていう実験装置が日本から、あの、宇宙に上がったんですが、
MC :へえ。
ゲスト:これは面白いですね。あの、静電気で
MC :ええ。
ゲスト:物が、物を浮かせる
MC :へえー。
ゲスト:ま、そんな、あの、あの、そして焼く、電気炉なんですね。
MC :へー。
ゲスト:これはきっと新しいですね、あのー、材料っていうんですか?
MC :うん。
ゲスト:新素材が生まれること間違いないと
MC :へー。
ゲスト:思いますね。
MC :へー。ええー。これ、日本の技術開発で、
ゲスト:そうです。
MC :日本初の
ゲスト:ええ。
MC :新しい繊維?
ゲスト:ええ。
MC :素材が出来るってことですか。
ゲスト:そうですね。このー
MC :へえー。
ゲスト:浮かせる、電気で浮かせる
MC :ええ。
ゲスト:あの、エルフという実験装置は、
これはもう日本が世界最強なので1番進んでるので、
MC :へー。
ゲスト:きっとこれ、面白い実験が行われますね。
MC :エルフね。
ゲスト:エルフ。
MC :覚えて#
ゲスト:覚えときなさい。みんな。
MC :へー。
ゲスト:それから、ダークマターってみんな知ってると思いますけど
MC :あ、ダークマター、はい。
ゲスト:はい。
MC :ブラックホールみたいな
ゲスト:あのー
MC :まだ解明されてない
ゲスト:そうそう、そうなんです。なんか、あのー、ねえ、信じられないんですけど
MC :ええ。
ゲスト:我々見えてる世界って5%なんですってねえ。
MC :ええ。
ゲスト:そして、僕らの周りにもダークマターはあって
MC :はい。
ゲスト:それから、ダークエネルギーとかいうのもあって、その95%は、
MC :ええ。
ゲスト:なんだか、よくわかってないみたいですね。
MC :はい。
ゲスト:これを見つけるための新しい実験装置が、
MC :へー。
ゲスト:あの、この「コウノトリ」に乗って、宇宙へ行きました。
MC :へー。ダークマターは解明されるんですか?
ゲスト:さあー、どうでしょう。期待できますね。
MC :へえー。夢は膨らみますね。さあ、今年も残りあと3ヶ月?
ゲスト:はい。
MC :あっという間ですねー。
ゲスト:そうですね。もう。
MC :え、これから何かこう楽しみなことあるんだろうか、空を見上げながら
ゲスト:そうですね。あの、12月ぐらいにですね、
あのー、金星の、あの探査機「あかつき」というのがですね
MC :おっ。5年前に飛んだやつ?
ゲスト:そうです。
MC :日本の
ゲスト:これが、あの、ドラマを起こしてくれると思いますよ。
MC :えっ、年末に「あかつき」が
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:ていうのは、ちょうど5年前の12月ですね、
MC :はい。
ゲスト:「あかつき」は「はやぶさ」みたいに、あの、故障しちゃったんです。
MC :あ、「はやぶさ」
ゲスト:なんか
MC :イト、イトカワにいった「はやぶさ」
ゲスト:行った「はやぶさ」ですね、ああ、そうですね。
MC :トラブルが
ゲスト:「はやぶさ」1号の
MC :はい。
ゲスト:「はやぶさ」。
MC :はい。
ゲスト:あれも、壊れて壊れて、頑張って頑張って、地球に還ってきましたよね。
MC :はい。
ゲスト:で、「あかつき」は地球には還ってこないんですが、
あの、なんたって、メインエンジンが壊れちゃったんです。
MC :へえー。
ゲスト:メインエンジンが壊れちゃって、よくそれで頑張るなっていうんですが、
MC :うん。
ゲスト:これが日本ですよね。
MC :どう、どうやって
ゲスト:はい。
MC :どうやったんですか?
ゲスト:そしたらですね、メインエンジンは壊れましたけれども、
MC :うん。
ゲスト:あの、姿勢制御用の、ま、ちっちゃいちっちゃいエンジンがついてるんですね。
MC :ええ。
ゲスト:これ、あのー、これ屁のツッパリぐらいの、
MC :ふん。
ゲスト:ふっとしたぐらいしか出ないんですが、それを四つまとめて、
ふっと出すと少しは、あの、動くんですよ。
MC :へえー。
ゲスト:これで、ふっふっふって頑張ろうと
MC :ええ。
ゲスト:いうところで、ほんとにうまくいくかどうかわかりませんけど、
これを12月の7日に、トライします。
MC :へえー。
ゲスト:そうすると、あの、この、「あかつき」は金星に、
えー、金星の周りを回る軌道に入ることができるんですね。
MC :あの、「あかつき」って5年前に金星探査機として打ち上げられたけれど、
ゲスト:ええ。
MC :一旦、金星には近づいたんだけれど、
ゲスト:ええ。
MC :エンジン壊れちゃった。
ゲスト:ええ。それで金星のまわりを回る軌道に入れなかったんですよ。
MC :で、12月7日に
ゲスト:ええ。
MC :ちょとおならみたいな、
ゲスト:ええ。
MC :エネルギーをプッて出して、金星の軌道に乗っかろうとしてるんですか
ゲスト:乗っかろうとしてんるんです。はい。
MC :楽しみですね。12月7日
ゲスト:これ、うまく行ったら、「はやぶさ」以来のドラマですね
MC :えー。それニュースになりますか?
ゲスト:もう、あ、なると思いますね。
MC :へー。
ゲスト:うまくいけばですけどねえ、
そして、意外と内側に行くのってね、あの、難しいんですよ。
MC :はー、そうですか。
ゲスト:ええ。止まるのが。
MC :あー。
ゲスト:はい。行くのは簡単なんですが、
そこで止めるのに、ものすごいエンジンがいるんですよね。
MC :そうです。ギリシャ神話でイカロスは、蝋で作った翼で
ゲスト:あははは。
MC :太陽に向かって行ったら、
ゲスト:そうですね。
MC :蝋が溶けて
ゲスト:溶けて
MC :落ちて死んじゃったって、もう可愛そう。
ゲスト:落ちて死んじゃいましたね。
MC :いやー、夢は膨らみますねー。
ゲスト:ええ。
MC :いやー、もう時間ですか。
ゲスト:ああ。
MC :あっという間ですね。やっぱり宇宙系の話は。
えー、あと3か月あるから、また是非遊びに来て下さいね。
ゲスト:はい。ありがとうございます。
MC :今週の「サイコー」はワンアースの長谷川洋一さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「宇宙の話 パート1」 ゲスト:長谷川洋一さん
2019/05/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は久しぶりの登場です。
ワンアースの長谷川洋一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :あの、ワンアースってなってるけど長谷川洋一さんは、これまで何度も出ていただいたんだけど、
有人宇宙システムっていうね、そこにいらっしゃって、
今度はワンアースという会社を立ち上げたということですか?
ゲスト:はあい。そうです。
MC :もう、宇宙の専門家で、実は、この番組10年やってるんだけど、
最も出ていただいた、えーっと、ワンツーの方なんですよ。
ゲスト:あー、はー、そうですか。
MC :寺門さんと、
ゲスト:ああ、
MC :長谷川さんていうね、もう、
ゲスト:あー。
MC :えー、で、このワンアースていう、これなんですか。
ゲスト:はい、あのー、一つの地球という意味でのワンアースですけれども、
MC :ええ。
ゲスト:ま、いままで、あの、こう、大村さんと語らしていただいたような、
MC :はい。
ゲスト:宇宙から見た地球だとか、ま、そういった考え方というのも、
MC :さ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は久しぶりの登場です。
ワンアースの長谷川洋一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :あの、ワンアースってなってるけど長谷川洋一さんは、これまで何度も出ていただいたんだけど、
有人宇宙システムっていうね、そこにいらっしゃって、
今度はワンアースという会社を立ち上げたということですか?
ゲスト:はあい。そうです。
MC :もう、宇宙の専門家で、実は、この番組10年やってるんだけど、
最も出ていただいた、えーっと、ワンツーの方なんですよ。
ゲスト:あー、はー、そうですか。
MC :寺門さんと、
ゲスト:ああ、
MC :長谷川さんていうね、もう、
ゲスト:あー。
MC :えー、で、このワンアースていう、これなんですか。
ゲスト:はい、あのー、一つの地球という意味でのワンアースですけれども、
MC :ええ。
ゲスト:ま、いままで、あの、こう、大村さんと語らしていただいたような、
MC :はい。
ゲスト:宇宙から見た地球だとか、ま、そういった考え方というのも、文化にしてみんなで楽しんじゃおうと、
いうふうな、文化、文化を広げるための組織として、財団法人として、
MC :はい。
ゲスト:作ったんです。
MC :そもそも長谷川さんは何年前でしたかね。若田光一さんに、
ゲスト:ええ。
MC :有名な、
ゲスト:はい。
MC :日本のね、各地の桜の種を、スペースシャトルに乗っけてもらって、
ゲスト:はい。
MC :宇宙を旅した、桜。
ゲスト:はい。
MC :を、全国各地にね、植えて、
ゲスト:ええ。
MC :それが、苗木として育ってく様を、
ゲスト:ええ。
MC :語っていただいたんですけど、
ゲスト:ええ。そうですね。
MC :その桜の木の長谷川洋一さんなんです。
ゲスト:え、へへはは。
MC :ははは。
ゲスト:そうです、宇宙桜の。
MC :宇宙桜ね。
ゲスト:宇宙桜の、はい。。
MC :で、これを、
ゲスト:はい。
MC :今、何、ワンアースで、宇宙桜を展開してるわけですね。
ゲスト:あ、その通りです。あのー、実はあのー、皆様ご記憶に新しい、あのー、2011年のですね、
MC :ええ。。
ゲスト:あのー、えー、大震災、
MC :はい。
ゲスト:そして、津波、これで大きな被害を受けた東北の、あの、海岸特に沿岸の方ですね。
MC :はい。
ゲスト:この沿岸の地域に、この宇宙桜こそ、復興希望のシンボルとして、
MC :はい。
ゲスト:ふさわしいんじゃないかと思いまして、あのう、今ですね今年ワンアース作ってからこの夏は、
MC :はい。
ゲスト:あのー、真っ黒日焼けするまでですね、沿岸の各市町村
MC :はい。
ゲスト:歩いて回りました。そして全部の市町村にお話をしたんですが、
MC :ほお、
ゲスト:この宇宙桜を、ま、市町村にお送りして、
そして津波のシンボルですね、津波から逃げる避難のシンボルとして、
MC :ええ。
ゲスト:植えましょうって話をしてるんです。
MC :はー。
ゲスト:あのー、あ、宇宙桜ですけどね、あのー、これは日本の、あの一番大きな桜を集めた、
MC :はい。
ゲスト:三春の滝桜ですとか、
MC :福島県のね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:はい。こういうあのー、1000年以上生きて、
MC :はい。
ゲスト:大きさも、あの、公園の桜の何倍にもなるような巨大になるような桜、
MC :はい。
ゲスト:この桜の子孫なんですね。
MC :はい。
MC :山梨県北杜市の山高神代桜ですとか、
ゲスト:はい。
MC :岐阜県本巣市の根尾谷の薄ぎみ桜です
ゲスト:薄墨
MC :薄墨桜
ゲスト:はい。
MC :とか、
ゲスト:はい。
MC :あと、北海道のミヤマ桜?
ゲスト:はい。
MC :それから、
ゲスト:岡山県の
MC :秋田のね、角館の武家屋敷の枝垂れ桜
ゲスト:ええ、
MC :あとは、岡山真庭市の醍醐桜、あーこれも有名な桜ですよね。
ゲスト:そうですね。ええ。
MC :あと、京都の祇園枝垂れ桜
ゲスト:はい、はい。
MC :こういった日本を代表するような樹齢1000年以上の桜の、
ゲスト:はい。
MC :種を、
ゲスト:そうですね。
MC :宇宙を旅して、
ゲスト:そうですね。
MC :若田光一さんが持ち帰ったものを、
ゲスト:そうですね。ええ。その子孫が今やっと、苗になってきてるんですね。
MC :ほー。
ゲスト:それで、これを植えておけば、あのー、1000年以上生きますから、
MC :はい。
ゲスト:しかも、大きくなりますから、次の津波がこようがなんだろうがあそこまで逃げればいいんだと、
MC :へー。
ゲスト:いうふうな、目印になりますよね。
MC :あ、そうか、津波の到達地点、今回15メートルとか、
ゲスト:あ、そうです。
MC :言われてますけれど、
ゲスト:ええ、ええ。
MC :津波のここまで来たよっていう、
ゲスト:ええ。
MC :あれ、三陸の沿岸部に行くと、過去の、あの、昭和のね、
ゲスト:ああ。
MC :三陸の地震の津波とか、あと、明治の、
ゲスト:ええ。
MC :津波とかって、実は白いペンキで結構沿岸部にねえ、
ゲスト:ええ。
MC :印があったんですけど、
ゲスト:ええ。
MC :東日本大震災の後っていうのは、ちょっと僕もよく分かって
ゲスト:ええ。
MC :なかったけど、じゃ、そういう津波の最高到達点に、
ゲスト:ええ。
MC :宇宙桜を植えようっていう。
ゲスト:植えようと。はい。
MC :すごい。
ゲスト:そうすると、あのー、向こう1000年、
MC :はい。
ゲスト:守ってくれる、あの、道路標識やコンクリートは段々壊れていきますけども、
MC :ほー。
ゲスト:桜ならば1000年頑張ってると思います。
MC :なるほど。そうか、で、結構今、被災地行くと、
ゲスト:ええ。
MC :あのー、津波の被害のあったところに、家が建ったりしてるじゃないですか。
ゲスト:ああー。そうですね。嵩上げして今、
MC :はい。
ゲスト:やろうとしてますけれどね。
MC :はい。嵩上げしてるところもあれば、してないところもあって、
ゲスト:そうですね。
MC :嵩上げしてるところはまだ大丈夫だと思うんですけど、
ゲスト:ええ、
MC :元の暮らしに戻るの大丈夫かなと僕は心配しちゃったんですけれど、
ゲスト:そうですね。ええ。
MC :そういうところに、こう、シンボルとして、
ゲスト:ええ。
MC :桜植えると、
ゲスト:ええ。
MC :ここまで逃げれば大丈夫とか。
ゲスト:そうですね。忘れない。
MC :はあ。
ゲスト:あのー、親から子へ伝わってきますよね。
MC :はい。
ゲスト:伝説が。
MC :え、例えば、岩手だったら、
ゲスト:ええ。
MC :どことか決まってるんですか?
ゲスト:あ、
MC :宮城だったらどこ
ゲスト:そうですね、あの、全部の市町村に植えるつもりですが、
MC :はい。
ゲスト:あのー、ま、例えばあのー、ま、釜石ですとか、
MC :はい。
ゲスト:あの、もう市を上げてですね、あのー、活動に入っていて、
MC :はー。
ゲスト:ま、そういうところではやっぱりあのー、津波でこう、あの、壊されてしまった学校
MC :ええ。
ゲスト:今それを建て直してるんですね。
MC :うん。
ゲスト:あのちょっと高台に
MC :はい。
ゲスト:ですから、そういったところに学校ができたあかつきには、是非、宇宙桜をお送りして、
MC :はー。
ゲスト:そしてほんとに、きぼ、希望のシンボルにしてって欲しいと思います。
MC :なるほど、そうですよね。あの、学校によっては、
ねえ、あの、宮城県の石巻市の大川小学校なんかは
ゲスト:ええ。
MC :結構ね、震災の、ま、取り壊しをめぐって、色々言われてますけれど、
ゲスト:ええ。
MC :ま、残ってるものもありますけど、
ゲスト:ええ。
MC :子ども達、行けないじゃないですか。
ゲスト:ええ。
MC :でも、復活してる学校もいくつかあって、
ゲスト:ええ。
MC :じゃ、そういうところに
ゲスト:ええ。
MC :希望の桜を植えるってことですか?
ゲスト:そうですね。
MC :そしたら、学校の木になりますよね、シンボル
ゲスト:そうですね。
MC :ほー。
ゲスト:また、できればあのー、観光名所に、
MC :ええー。
ゲスト:なるんじゃないかと思いますね。
MC :へー。
ゲスト:宇宙桜珍しいですし、
MC :ええ。
ゲスト:桜そのものが、あの、もともと素晴らしい桜ですので、
MC :へええ。
ゲスト:それがまた観光っていうことでも、あの、復興のお手伝いになれたらと
MC :はあー。
ゲスト:思っています。
MC :宇宙というと今、
ゲスト:はい。
MC :国際宇宙ステーションに油井公也さんが滞在してます。
ゲスト:はい。
MC :油井さん初めての、
ゲスト:ええ。
MC :宇宙ですけど、
ゲスト:ええ。
MC :いきなり、
ゲスト:ええ。
MC :5ヶ月いるわけですよね。
ゲスト:そうですね。まあ、そうですね。
MC :けっ、結構酷じゃないですか?いきなり初めての宇宙で。
ゲスト:まあ、本人は大喜びのようですけれども。
MC :ええ。
ゲスト:ま、もともと、あのー、油井さんは、あのー、パイロットですね。
MC :はい。
ゲスト:航空自衛隊のパイロットだったので、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、ま、戦闘機とか、もーのすごい、こう、あのー、Gというんですか?
MC :はい。
ゲスト:重力かかりながら、こういう訓練してた人だ、人なので、
MC :はい。
ゲスト:あのー、宇宙飛行士の訓練もなかなか、あのー、楽々パスしたようですね。
MC :ええ。
ゲスト:そして今は、あの、ま、彼、あの、色々Twitterですとか、
MC :はい。
ゲスト:あのー、一所懸命、こう、あの、発信してます。
MC :はい。
ゲスト:でもそういった物見ますと、楽しんでるなあって感じですね。
MC :ふーん。
ゲスト:そのぐらいの
MC :宇宙を。
ゲスト:ええ。あの、初めてにしてはずいぶん楽しんで、
MC :はい。
ゲスト:あの、余裕がある、ゆとりがある。
MC :油井さん、そもそも何をしてるんですかね。
ゲスト:あ、あのー、いろんな実験をしてるんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:ま、ちょっと珍しいのが、あの、この前、あのう、レタスを食べたってのが、ちょっと
MC :ああ。
ゲスト:この夏話題になりましたけれど
MC :レタス食べた。
ゲスト:はい。
MC :うふふ。
ゲスト:ああいう、ま、あれは遊びじゃなくてですね、
MC :はい。
ゲスト:実験なんですね。
MC :みんな食べてましたね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:で、実は驚くなかれ宇宙で、あの、野菜を作って食べるというのは、
MC :うん。
ゲスト:あの、NASAは初めてやったんですね。
MC :それは日本の、あのー、実験棟の「きぼう」で栽培したレタスなんですか?
ゲスト:えっとー、レ、レタスはですね、あの、NASAのあの実験装置で作ったんですが、
MC :NASAで作ってる。
ゲスト:はい。日本が作った訳じゃないんですが、NASAの実験でやったのは、初めて。
MC :ほー。
ゲスト:それで、あの、実は宇宙で野菜なんか食べてないの?という話が、
MC :はい。
ゲスト:あるんですけどね、あの、ロシアの人達、ロシアの人達って宇宙ステーションミールの時代から、
MC :はい。
ゲスト:随分長いこと宇宙やってますよね。
MC :そっか。
ゲスト:そして、ええ。その頃からですね実はあの、野菜作って食べてたんです。
MC :へー。
ゲスト:で、どんなものかっていうと、あの、ミニトマトっていうんですか、
MC :はあ。
ゲスト:チェリートマト、
MC :はい。
ゲスト:それから水菜。
MC :ほー。
ゲスト:それから、ま、そういった物を作って食べて、
MC :ええ。
ゲスト:やってたんですねえ。
MC :ええ。
ゲスト:それから、食べてはいないですけど、稲とか、
MC :うん。
ゲスト:麦。
MC :うん。
ゲスト:こんなものも宇宙で作っていました。
MC :栽培してたんですか?
ゲスト:そうです。
MC :稲、麦を?
ゲスト:はい。
MC :穀物を、はい。
ゲスト:はい。ま、あの、それなんですが、NASAは実は今まであんまりやっていなかったと。
MC :へえー。
ゲスト:それで
MC :なんなんですか?
ゲスト:なんでかっていったらですね、
宇宙で作ったものを食べて安全かどうかがよくわからないっていう、
あの、ちょっとややこしい理由をつけてたんですよね。
MC :へー。
ゲスト:ま、だけどレタスはレタスじゃないですか。んふふふ。
MC :ほー。
ゲスト:いうことで、やっと許可が出たんです。
MC :へー。でも、ロシアはミールだからじゃないですか?
ゲスト:まあ、
MC :ミール、食事だからね、英語でね。
ゲスト:なんでもあって、あっ、ミール。あははは。
MC :だから、
ゲスト:さすが。
MC :早く開発すすんで、
ゲスト:あははは。
MC :NASAは、ちょっとミールにあまり興味がなかったっていう、
東西冷戦時代をちょっと、思い起こさせる感じ。
ゲスト:あああ。
MC :の、オチがついたところでお時間ですか?
ゲスト:はい。
MC :あらー、あっという間ですねえ。いやいやいや。宇宙桜。
ゲスト:はい。
MC :東北で。すごいなあ。じゃ、またちょっと来週も長谷川さんにお話を伺いたいと思います。
あっという間にお時間きてしまいました。
今週の「サイコー」はワンアースの長谷川洋一さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。文化にしてみんなで楽しんじゃおうと、
いうふうな、文化、文化を広げるための組織として、財団法人として、
MC :はい。
ゲスト:作ったんです。
MC :そもそも長谷川さんは何年前でしたかね。若田光一さんに、
ゲスト:ええ。
MC :有名な、
ゲスト:はい。
MC :日本のね、各地の桜の種を、スペースシャトルに乗っけてもらって、
ゲスト:はい。
MC :宇宙を旅した、桜。
ゲスト:はい。
MC :を、全国各地にね、植えて、
ゲスト:ええ。
MC :それが、苗木として育ってく様を、
ゲスト:ええ。
MC :語っていただいたんですけど、
ゲスト:ええ。そうですね。
MC :その桜の木の長谷川洋一さんなんです。
ゲスト:え、へへはは。
MC :ははは。
ゲスト:そうです、宇宙桜の。
MC :宇宙桜ね。
ゲスト:宇宙桜の、はい。。
MC :で、これを、
ゲスト:はい。
MC :今、何、ワンアースで、宇宙桜を展開してるわけですね。
ゲスト:あ、その通りです。あのー、実はあのー、皆様ご記憶に新しい、あのー、2011年のですね、
MC :ええ。。
ゲスト:あのー、えー、大震災、
MC :はい。
ゲスト:そして、津波、これで大きな被害を受けた東北の、あの、海岸特に沿岸の方ですね。
MC :はい。
ゲスト:この沿岸の地域に、この宇宙桜こそ、復興希望のシンボルとして、
MC :はい。
ゲスト:ふさわしいんじゃないかと思いまして、あのう、今ですね今年ワンアース作ってからこの夏は、
MC :はい。
ゲスト:あのー、真っ黒日焼けするまでですね、沿岸の各市町村
MC :はい。
ゲスト:歩いて回りました。そして全部の市町村にお話をしたんですが、
MC :ほお、
ゲスト:この宇宙桜を、ま、市町村にお送りして、
そして津波のシンボルですね、津波から逃げる避難のシンボルとして、
MC :ええ。
ゲスト:植えましょうって話をしてるんです。
MC :はー。
ゲスト:あのー、あ、宇宙桜ですけどね、あのー、これは日本の、あの一番大きな桜を集めた、
MC :はい。
ゲスト:三春の滝桜ですとか、
MC :福島県のね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:はい。こういうあのー、1000年以上生きて、
MC :はい。
ゲスト:大きさも、あの、公園の桜の何倍にもなるような巨大になるような桜、
MC :はい。
ゲスト:この桜の子孫なんですね。
MC :はい。
MC :山梨県北杜市の山高神代桜ですとか、
ゲスト:はい。
MC :岐阜県本巣市の根尾谷の薄ぎみ桜です
ゲスト:薄墨
MC :薄墨桜
ゲスト:はい。
MC :とか、
ゲスト:はい。
MC :あと、北海道のミヤマ桜?
ゲスト:はい。
MC :それから、
ゲスト:岡山県の
MC :秋田のね、角館の武家屋敷の枝垂れ桜
ゲスト:ええ、
MC :あとは、岡山真庭市の醍醐桜、あーこれも有名な桜ですよね。
ゲスト:そうですね。ええ。
MC :あと、京都の祇園枝垂れ桜
ゲスト:はい、はい。
MC :こういった日本を代表するような樹齢1000年以上の桜の、
ゲスト:はい。
MC :種を、
ゲスト:そうですね。
MC :宇宙を旅して、
ゲスト:そうですね。
MC :若田光一さんが持ち帰ったものを、
ゲスト:そうですね。ええ。その子孫が今やっと、苗になってきてるんですね。
MC :ほー。
ゲスト:それで、これを植えておけば、あのー、1000年以上生きますから、
MC :はい。
ゲスト:しかも、大きくなりますから、次の津波がこようがなんだろうがあそこまで逃げればいいんだと、
MC :へー。
ゲスト:いうふうな、目印になりますよね。
MC :あ、そうか、津波の到達地点、今回15メートルとか、
ゲスト:あ、そうです。
MC :言われてますけれど、
ゲスト:ええ、ええ。
MC :津波のここまで来たよっていう、
ゲスト:ええ。
MC :あれ、三陸の沿岸部に行くと、過去の、あの、昭和のね、
ゲスト:ああ。
MC :三陸の地震の津波とか、あと、明治の、
ゲスト:ええ。
MC :津波とかって、実は白いペンキで結構沿岸部にねえ、
ゲスト:ええ。
MC :印があったんですけど、
ゲスト:ええ。
MC :東日本大震災の後っていうのは、ちょっと僕もよく分かって
ゲスト:ええ。
MC :なかったけど、じゃ、そういう津波の最高到達点に、
ゲスト:ええ。
MC :宇宙桜を植えようっていう。
ゲスト:植えようと。はい。
MC :すごい。
ゲスト:そうすると、あのー、向こう1000年、
MC :はい。
ゲスト:守ってくれる、あの、道路標識やコンクリートは段々壊れていきますけども、
MC :ほー。
ゲスト:桜ならば1000年頑張ってると思います。
MC :なるほど。そうか、で、結構今、被災地行くと、
ゲスト:ええ。
MC :あのー、津波の被害のあったところに、家が建ったりしてるじゃないですか。
ゲスト:ああー。そうですね。嵩上げして今、
MC :はい。
ゲスト:やろうとしてますけれどね。
MC :はい。嵩上げしてるところもあれば、してないところもあって、
ゲスト:そうですね。
MC :嵩上げしてるところはまだ大丈夫だと思うんですけど、
ゲスト:ええ、
MC :元の暮らしに戻るの大丈夫かなと僕は心配しちゃったんですけれど、
ゲスト:そうですね。ええ。
MC :そういうところに、こう、シンボルとして、
ゲスト:ええ。
MC :桜植えると、
ゲスト:ええ。
MC :ここまで逃げれば大丈夫とか。
ゲスト:そうですね。忘れない。
MC :はあ。
ゲスト:あのー、親から子へ伝わってきますよね。
MC :はい。
ゲスト:伝説が。
MC :え、例えば、岩手だったら、
ゲスト:ええ。
MC :どことか決まってるんですか?
ゲスト:あ、
MC :宮城だったらどこ
ゲスト:そうですね、あの、全部の市町村に植えるつもりですが、
MC :はい。
ゲスト:あのー、ま、例えばあのー、ま、釜石ですとか、
MC :はい。
ゲスト:あの、もう市を上げてですね、あのー、活動に入っていて、
MC :はー。
ゲスト:ま、そういうところではやっぱりあのー、津波でこう、あの、壊されてしまった学校
MC :ええ。
ゲスト:今それを建て直してるんですね。
MC :うん。
ゲスト:あのちょっと高台に
MC :はい。
ゲスト:ですから、そういったところに学校ができたあかつきには、是非、宇宙桜をお送りして、
MC :はー。
ゲスト:そしてほんとに、きぼ、希望のシンボルにしてって欲しいと思います。
MC :なるほど、そうですよね。あの、学校によっては、
ねえ、あの、宮城県の石巻市の大川小学校なんかは
ゲスト:ええ。
MC :結構ね、震災の、ま、取り壊しをめぐって、色々言われてますけれど、
ゲスト:ええ。
MC :ま、残ってるものもありますけど、
ゲスト:ええ。
MC :子ども達、行けないじゃないですか。
ゲスト:ええ。
MC :でも、復活してる学校もいくつかあって、
ゲスト:ええ。
MC :じゃ、そういうところに
ゲスト:ええ。
MC :希望の桜を植えるってことですか?
ゲスト:そうですね。
MC :そしたら、学校の木になりますよね、シンボル
ゲスト:そうですね。
MC :ほー。
ゲスト:また、できればあのー、観光名所に、
MC :ええー。
ゲスト:なるんじゃないかと思いますね。
MC :へー。
ゲスト:宇宙桜珍しいですし、
MC :ええ。
ゲスト:桜そのものが、あの、もともと素晴らしい桜ですので、
MC :へええ。
ゲスト:それがまた観光っていうことでも、あの、復興のお手伝いになれたらと
MC :はあー。
ゲスト:思っています。
MC :宇宙というと今、
ゲスト:はい。
MC :国際宇宙ステーションに油井公也さんが滞在してます。
ゲスト:はい。
MC :油井さん初めての、
ゲスト:ええ。
MC :宇宙ですけど、
ゲスト:ええ。
MC :いきなり、
ゲスト:ええ。
MC :5ヶ月いるわけですよね。
ゲスト:そうですね。まあ、そうですね。
MC :けっ、結構酷じゃないですか?いきなり初めての宇宙で。
ゲスト:まあ、本人は大喜びのようですけれども。
MC :ええ。
ゲスト:ま、もともと、あのー、油井さんは、あのー、パイロットですね。
MC :はい。
ゲスト:航空自衛隊のパイロットだったので、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、ま、戦闘機とか、もーのすごい、こう、あのー、Gというんですか?
MC :はい。
ゲスト:重力かかりながら、こういう訓練してた人だ、人なので、
MC :はい。
ゲスト:あのー、宇宙飛行士の訓練もなかなか、あのー、楽々パスしたようですね。
MC :ええ。
ゲスト:そして今は、あの、ま、彼、あの、色々Twitterですとか、
MC :はい。
ゲスト:あのー、一所懸命、こう、あの、発信してます。
MC :はい。
ゲスト:でもそういった物見ますと、楽しんでるなあって感じですね。
MC :ふーん。
ゲスト:そのぐらいの
MC :宇宙を。
ゲスト:ええ。あの、初めてにしてはずいぶん楽しんで、
MC :はい。
ゲスト:あの、余裕がある、ゆとりがある。
MC :油井さん、そもそも何をしてるんですかね。
ゲスト:あ、あのー、いろんな実験をしてるんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:ま、ちょっと珍しいのが、あの、この前、あのう、レタスを食べたってのが、ちょっと
MC :ああ。
ゲスト:この夏話題になりましたけれど
MC :レタス食べた。
ゲスト:はい。
MC :うふふ。
ゲスト:ああいう、ま、あれは遊びじゃなくてですね、
MC :はい。
ゲスト:実験なんですね。
MC :みんな食べてましたね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:で、実は驚くなかれ宇宙で、あの、野菜を作って食べるというのは、
MC :うん。
ゲスト:あの、NASAは初めてやったんですね。
MC :それは日本の、あのー、実験棟の「きぼう」で栽培したレタスなんですか?
ゲスト:えっとー、レ、レタスはですね、あの、NASAのあの実験装置で作ったんですが、
MC :NASAで作ってる。
ゲスト:はい。日本が作った訳じゃないんですが、NASAの実験でやったのは、初めて。
MC :ほー。
ゲスト:それで、あの、実は宇宙で野菜なんか食べてないの?という話が、
MC :はい。
ゲスト:あるんですけどね、あの、ロシアの人達、ロシアの人達って宇宙ステーションミールの時代から、
MC :はい。
ゲスト:随分長いこと宇宙やってますよね。
MC :そっか。
ゲスト:そして、ええ。その頃からですね実はあの、野菜作って食べてたんです。
MC :へー。
ゲスト:で、どんなものかっていうと、あの、ミニトマトっていうんですか、
MC :はあ。
ゲスト:チェリートマト、
MC :はい。
ゲスト:それから水菜。
MC :ほー。
ゲスト:それから、ま、そういった物を作って食べて、
MC :ええ。
ゲスト:やってたんですねえ。
MC :ええ。
ゲスト:それから、食べてはいないですけど、稲とか、
MC :うん。
ゲスト:麦。
MC :うん。
ゲスト:こんなものも宇宙で作っていました。
MC :栽培してたんですか?
ゲスト:そうです。
MC :稲、麦を?
ゲスト:はい。
MC :穀物を、はい。
ゲスト:はい。ま、あの、それなんですが、NASAは実は今まであんまりやっていなかったと。
MC :へえー。
ゲスト:それで
MC :なんなんですか?
ゲスト:なんでかっていったらですね、
宇宙で作ったものを食べて安全かどうかがよくわからないっていう、
あの、ちょっとややこしい理由をつけてたんですよね。
MC :へー。
ゲスト:ま、だけどレタスはレタスじゃないですか。んふふふ。
MC :ほー。
ゲスト:いうことで、やっと許可が出たんです。
MC :へー。でも、ロシアはミールだからじゃないですか?
ゲスト:まあ、
MC :ミール、食事だからね、英語でね。
ゲスト:なんでもあって、あっ、ミール。あははは。
MC :だから、
ゲスト:さすが。
MC :早く開発すすんで、
ゲスト:あははは。
MC :NASAは、ちょっとミールにあまり興味がなかったっていう、
東西冷戦時代をちょっと、思い起こさせる感じ。
ゲスト:あああ。
MC :の、オチがついたところでお時間ですか?
ゲスト:はい。
MC :あらー、あっという間ですねえ。いやいやいや。宇宙桜。
ゲスト:はい。
MC :東北で。すごいなあ。じゃ、またちょっと来週も長谷川さんにお話を伺いたいと思います。
あっという間にお時間きてしまいました。
今週の「サイコー」はワンアースの長谷川洋一さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「民間薬の科学 パート2」 ゲスト:船山信次さん
2019/04/01 Mon 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー、略して「サイコー」も前回に続きまして
日本薬科大学教授の船山信次先生です。こんにちは。
ゲスト:こんにちは
MC :お願いします。
ゲスト:どうぞよろしくお願いいたします。
MC :船山先生は宮城県仙台市のご出身で、薬剤師それから薬学博士として活躍されていらっしゃいます。
で、サイエンスアイ新書から「民間薬の科学」という本も出版されているんですけれど、
「民間薬」聞きなれないけれど、あの日本の独自の薬みたいな、
昔から伝わる野生のものを使ったお薬のお話。
生薬を発展させて民間の薬っていうこう定義って伺ったんですけれど。
いろんなこう街歩いたりね、原っぱを歩いていると薬になるようなものたくさんあるんだけれど、
今日はねみんなの家にあるようなもの。例えば、理科の研究であじさいとかさ、
理科あさがおか...あれは。今は、あじさいはもうシーズン終わっちゃうな。
あじさいとか キャベツとかね台所のきゅうりとか。あと夏スイカとか。
こういったものも先生の本には民間薬として登場してくるんです。
スイカが薬だよ?先生、まずあじさい。シーズンちょっともう終わりますけれど。
このあじさいは何の薬ですか?
ゲスト:これはあの昔ですね。解熱薬として使われたことがあるんですよ。
MC :熱さまし?
ゲスト:熱さましです。
MC :今みんなシートおでこに貼るけれど。あじさい貼っちゃうんですか
ゲスト:いやいや。服用するんですね。
MC :飲む
ゲスト:これちょっと毒性がありましてですね。薦められるものではありません
MC :今はあまりお薦めできない
ゲスト:はい。はい。
MC :昔の人はあじさいを
ゲスト:そういうことを試してですね、実際にあの実験的にですけれど、
あの体温を下げるということはわかってます。
MC :あじさいの花ですか?
ゲスト:花も葉っぱもですね。両方あるんですよ。その下げるアルカルド成分なんですけれど。
ただ数年前に大阪とつくば市で、実際の葉っぱをですね料理に出されたのを食べちゃって
中毒死したかたもいます。そのくらい、ま、毒性もありますからね。
あまり薦められるものではありませんね。
MC :毒も薬も紙一重ですからね。お薬になるか毒になるかというね。
あ、じゃあじさいは民間薬の一種だけれど、先生はあまりちょっとお薦めしない。
ゲスト:そうですね。今は薦められるものじゃないと思います。
MC :実際食べよって子いないから。いいや。キャベツこれは冷蔵庫にあるでしょみんなキャベツ。
これも民間薬。
ゲスト:まー、民間薬っていうか民間でね。あのやっぱり体にいいと思いますよね。
あの抗潰瘍活性があるという。
MC :こうかいよう
ゲスト:なんか胃あの胃があのこう痛くなってくるとかですね。そういった。
ま、でも今はそういうものいい薬がありますからね。
MC :だから、だから胃薬にキャベがつくんですか?
ゲスト:あの、話しは別なんですけれど、それはちょっと。
MC :また別の。また違うへ~
ゲスト:違ったですね
MC :キャベツは胃に効く?
ゲスト:そうですね
MC :胃に優しい?
ゲスト:いいって言われてますね。昔からはい。
MC :ほう~。キャベツは胃にいい。
ゲスト:はい
MC :きゅうり
ゲスト:きゅうり
MC :きゅうりも冷蔵庫にあるね。
ゲスト:そうですね
MC :きゅうり。何にいいんですか?
ゲスト:これもあの一般的に体にいいって言われてます。
MC :きゅうり?
ゲスト:えーえー
MC :えー
ゲスト:夏場の野菜としてね。あのーやっぱり冷涼感もようぢゃないですか。
MC :まーまー
ゲスト:そういったこともあるし。それからあのミネラル部分とかですね結構多いと思うんですね。
MC :冷やし中華に添えるとかね
ゲスト:そうですね
MC :きゅうりとかそういうものは。酢の物にしてもおいしいし。
ゲスト:そうですね
MC :でも、きゅうりってね。なんか栄養あんまりないよ。
っていう風に僕ずっと育ってきたんだけれど。薬にもなる
ゲスト:そうですね。あの積極的な薬ではないかもしれませんけども。
一般的に体にいいという風に考えてもいいなと思いますね。
MC :そうですか
ゲスト:だから薬くいなんていいますね。きゅうり食べる子ってね
MC :え?そうなんですか?
ゲスト:そんなこと言われるくらい
MC :きゅうり食べる子 薬くいっていうの?
ゲスト:えーえーそんなこといわれるくらいです。
MC :ほー。きゅうり嫌いなキッズ。きゅうり食べて薬ぐいだぞ
スイカ。これは大好きです。
ゲスト:あー。
MC :これからのシーズンたまらないですね。
ゲスト:よろしいですね
MC :スイカは何が?でもスイカいっぱい食べるとおなか壊すといわれてましたけど
スイカの種飲んだら、へそから芽がでるよ。って子供のころ言われたけど。
スイカはどういう効果があるんですか?
ゲスト:スイカはね。あの利尿作用があってですね。まさにあのストルリンっていうんですけれども。
まさに利尿成分がとられてるんですよ。ただ、スイカを食べてですね。
そんの成分を取ろうとすると。お腹の中ジャバジャバになっちゃいますから。
ですから、それをあの化学的にですね。とってそれが、あのまー利尿作用成分として
使われることもあるくらいですね
MC :なるほど。夏のお父さん。
ビール飲んでないでスイカ食べたほうがいいよってことかもわからないですね。
ゲスト:あー。あはは。ちょっと厳しいところです。両方いきたいところですけどね
MC :いやいや。まーでもスイカとることは水分の補給にもなるし、
利尿作用もあって、体の巡回には良いということですね。
ゲスト:やっぱり夏野菜っていうかですね。いいものなんですよね。
やっぱり日本の民族がずっと長いことかかってですね。
そういったような習慣を作ってきて、まー私達が夏を過ごすというか。
夏を乗り切るというか。そんなことですね
MC :夏にスイカ食べるって日本の文化も一つの民間薬のプロセスの中にあるんですね
ゲスト:そうですね。そういう風に考えてもいいかもしれません。
MC :えー。それから動物や微生物由来の民間薬もあるということで。
ちょうど気持ち悪い話なんだけどね、あのね、トカゲに似たイモリ。
これイモリ。これも民間薬だっていう。
ゲスト:そうなんですよ
MC :イモリ見たことないキッズ多いとおもいますけれど。イモリをどうやって食べ
ゲスト:あの。池なんかで。こう うにゅうにゅというヤツですね
MC :そうそうそうそう。やわらかいトカゲのイメージ。
ゲスト:あれはちょっと。あの。お腹を裂いてですね。広げて、乾燥して。
で、オスとメスと一対にして売り出すという。ま、ちょっと。あの
MC :あ。。どっかの海外で見たことあります。
ゲスト:ところがね。おそらく大村さんが、あの、例えば中国で見たとして。
それイモリぢゃなくてヤモリなんですよ。
MC :ヤモリってお腹赤いほうですね。
ゲスト:いえ。あの。家の中に。
MC :家の中にいるやつね
ゲスト:あっちは爬虫類ですね。
MC :爬虫類
ゲスト:イモリは両生類ですけど。
MC :はい
ゲスト:で、どこでどう間違ったのかですね。
もともとはヤモリを使って実はゴウカイっていうあの生薬があるんですよ。
中国に。それがどこで、どう間違ったか日本に入って来て、イモリの黒焼きとかですね。
そういう風に変わってきたんですね。
MC :ほんとはヤモリの方がいいんだけれど、
イモリを今民間薬として小用してるということですか?日本人は
ゲスト:ま、ほんとに効くかどうかはわかりません。私は保障しませんけれども。
あの、でもあのイモリっていうのはなかなか求愛活動っていうんですか。
あのオスがメスを追っかけるって、そのそこがかなりですね、
ねー熱烈で複雑なんだそうなんですよ
MC :イモリが?
ゲスト:はいはい。そういったところからですね。日本ではイモリを使うようになったんじゃねーかなと。
MC :イモリはなんの薬ですか?
ゲスト:惚れ薬みたいなかんじ。あはは
MC :惚れ薬。えへへ
ゲスト:知らないように相手のあんまり薬を誰かのところに入れるなんてあんまりよくないんでしょうね。
相手に気づかれないように。飲み物やなんかに入れると自分に惚れてくる
MC :好きになっちゃうの?そんな薬あるんですか
ゲスト:あはは
MC :面白い
ゲスト:ま、信じる者は救われるの類かもしれませんが
MC :民間薬。えイモリを煎じて乾燥したイモリを煎じて惚れ薬にするっていうのも
民間薬の考えであるっていう。
ゲスト:そうですね
MC :へー。イモリ知らないキッズ。今度イモリ見つけてきて。
お薬について2週間にわたって勉強してきたけど、面白いですね。
あの実は日本の土壌にはいろんな薬の元ってあるんですけれど、ね。
これから歩くの楽しみになってきたな。
先生また来てくださいね。ありがとうございました。
今週のサイコーは日本薬科大学教授の船山信次先生でした。 -
「民間薬の科学 パート1」 ゲスト:船山信次さん
2019/04/01 Mon 12:00 カテゴリ:その他MC :今週のサイエンスコーチャー、略して「サイコー」は二度めのご登場でらっしゃいます。
日本薬科大学教授の船山信次先生です。よろしくお願いします。
ゲスト:こんにちは。
MC :先生は6年前に出ていただいたんですけど、毒と薬は紙一重だよって話を伺ったんです。
すごく、あのいいお話だったんでよく覚えているんですけど。
僕らもよいよいと思って薬を飲んでるけれど、ま、それが場合によっては毒にもなるしっていう。
ただ、そのね体にどう作用するかっていうのが
本当に紙一重なんだなっていうお話を伺ったんですけれど。
先生はですね、薬剤師・薬学博士ということなんですが。
サイラスアイ新書から「民間薬の科学」という本も出版されてます。
「民間薬」民間の薬と書いて先生これなんですか?民間薬。
ゲスト:まー民間でも言い伝えによって病気や傷に対してですね、
ちょっとケガしたとか、ちょっと頭痛いとか。そういうときに使ってきた。
民間で使ってきた薬ということになりますよね。
MC :蚊にくわれたら 僕らってね。チューブのね白い軟膏をぬったりするぢゃないですか。
あれは民間薬ぢゃない?
ゲスト:え。あの今はもうそういう大変いい薬がいろいろ出回ってますからね。
今はあの虫にくわれたときその辺の薬草でどうのこうのということはないですけど。
なかった時は役にたったときもあったでしょうね。
MC :あー昔の薬のことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :よくね時代劇なんかみると葉っぱをこう煎じて口の中でぐじゅぐじゅってべって。
やって薬にするとか。そういうシーンあったけれど。それ民間薬?
ゲスト:まー。そうですね。ぺってやったら唾のほうがよく効くかもしれませんけれど。
まーあと一方ではですね。ケシとかですね。
MC :ケシ
ゲスト:コカ。あーいったものもいわゆる海外での民間薬だったという。
そういうものですよね。いわばね
MC :日本では禁止されてるけど。
ゲスト:今でもですね。コカは扱われてるところがあるんですよ。
MC :はい
ゲスト:あの南米のボリビアなんかは、あのえー高山ですよね。高山病によーく効くんだそうです。
MC :コカっていうのは
ゲスト:コカの葉っぱですね。
MC :コカインっていう。それでもですねやっちゃダメなんですよね日本ぢゃ。法律で。
だけど南アメリカ大陸のボリビアという標高の高い所ではそれを薬として。
ゲスト:そうです。いわば民間薬ですよね。
MC :ん~。高山病に効くということなんですよね
ゲスト:あれも今まで問題はなかったんですけども、コカの葉っぱからコカインという
アルカロイド成分を純粋に取り出して大量に服用することによって、
今みたいな問題が非常に大きくなってきたんですね。
MC :は。は。は。
ゲスト:それまでだとどってなかったと思います。
MC :いわゆる自然界に存在するコカの葉っぱを薬としてやっとく分には
それほど体に悪い事なかったんだけれど、
抽出して濃くして大量に取り込むからいけない風になっちゃう。
ゲスト:とんでもない量は違うと思います。そういうことでですね。
あの民間の血合いだった長い長い間血合いもの。
こわしているようなところもある懸念もありますよね。
MC :なるほど。なんか今のイメージだと僕らでいうと漢方薬。
のイメージなのかなとおもったんですけど。民間薬っていうのは
ゲスト:まーあの漢方薬っていうのはもともとはいわば中国の民間薬ですよね。民間からできてきたもので。
中国から日本にわたって来てロシアに漢方薬っていう言葉が出来たんですね。
MC :へ~。
ゲスト:それまではその言葉はなかった。で、漢方薬っていうのは日本だけで使う言葉ですよね。
MC :あ。そうか。あ~。中国では別にそんな漢方薬っていわない。
ゲスト:いいませんね。ま。草の薬と書いて「草薬」とかですね。日本流に発音すると。
そんな風にいいます。
MC :中国から伝わったものは漢方薬として今市場に出回ってますけど、
「民間薬」っていうのは市場には出てないですか?
ゲスト:えー。あの出てます。あのゲンノショウコとかですねセンブリとか。ドクダミとか。
そういったものは今でもあのそれぞれ出てますね。で、単味でつかうんです。あの混ぜ合わせないです。
漢方薬っていうのは混ぜ合わせて使いますよね。
しかも、あのえーっと実は中国から漢方薬っていうのは伝わったとは言いますけど、
だいぶ日本向けというか変わってるんです。改良されてるんです。
ですからいわば、独特のものだと言っていいと思います。
かつて「チャイニーズハーバルメデシン」ってね。中国のって言ってたんですけど。
そのあの翻訳ってのは違ってまして、漢方って言います。英語でも。
MC :へ~。
ゲスト:そのくらい変わってますね。
MC :そうなんですか。ぢゃその中国の薬。
[カンポウ]っていう風に英語でも言われるから日本人が頼るようになって
アメリカとかヨーロッパでも「カンポウ」っていう形で中国の薬は流通しているということ
ゲスト:というか。日本で作られた配合のあの。物は「カンポウ」と。
MC :なるほど。そうか。中国からそのノウハウは伝来したけれど、
日本の製薬会社が「カンポウ」という形で世界に発信しているということですか。
ゲスト:ま、そういうことですね。その漢方というのを作り出したのは日本の江戸時代の人たちですね。
MC :あ。そうなんですか。
ゲスト:あの、ずっといろんなことを研鑚してその、調べながら作り出したと。いうことで。
MC :江戸時代にそういうもともとの漢方の民間薬の原点みたいなものもあったと。
ゲスト:そうですね。材料というのは中国大陸のものであってですね。日本の民間薬というのは、また違う。
MC :また違う。それがさっき 日本の民間薬はセンブリとかドクダミとか。
センブリとかドクダミ たぶんキッズ達知らないとおもうんです。どういうものですか?
ゲスト:あはは。センブリはとにかく。。センブリっていうのは1000回振り出してもまだ苦いっていう。
とっても苦いものなんですね。で、これは胃の薬ですね。
ケンヤクっていうんですけれども。に使いますね。
MC :これは草ですか?もともと。
ゲスト:そうです。
MC :どの辺に生えてるんですか?
ゲスト:えーと。あのちょっと日陰っぽいような草原みたいなところに生えてますね。
MC :東京都内にもありますか?
ゲスト:あると思いますよ。
MC :へ~。
ゲスト:ちなみに私のあの勤めている大学のキャンパス内にもあります。生えてきます。
MC :日本薬科大学に?へ~。センブリ?
ゲスト:あのリンドウの仲間なんですよ。
MC :リンドウ
ゲスト:小さいんですけど、小さいかわいい花を白い花をつけます。
MC :へ~。1000回振っても苦い。
ゲスト:そうですね。
MC :良薬は口に苦し。って
ゲスト:まさにその
MC :センブリってそのイメージ。胃腸の薬なんですね
ゲスト:そうですね。その苦いっていうのが体に良いわけですね。
だからセンブリをオブラートに包んで飲んじゃいけませんね。
MC :なるほど。そういうことですか
ゲスト:そういうことです。
MC :え。でも体の中にはいったらオブラートは溶けて効果同じかと思ったんですけど。
苦いことを味わはなければセンブリの意味がないということですね。
ゲスト:そういうことですね。
MC :え?オブラートだめ?
ゲスト:ダメですね。
MC :えーー。先生笑いながらおっしゃってるけどそうとうセンブリを飲む人って
直に飲まないでオブラートで飲んでる人多いと思いますが
ゲスト:そうですか。あーまーあの気持ちを壊してしまったらごめんなさい。
でも、苦いっていう味がいいんですよね。
MC :なるほど
ゲスト:そういった薬っていうのがあるんですよ。
MC :薬って気持ちの部分も作用するし
ゲスト:もちろんそうです
MC :これを飲んだから治るんだっていう。苦いから治るんだ
ゲスト:そうですね。
MC :そういうのもある
ゲスト:苦いから治るっていうことと、飲んだから治ると思ってる人にとっては、
別にオブラートで包んでもかまわないと思います。
MC :なるほど。おまじない的なお話にもなってきましたけど。
ゲスト:まちょっと。人間って考えちゃう動物ですからね。ですから非常にあの。複雑ですよね。
MC :いやいや。すごい良くわかります。でも。
で、今のセンブリとかドクダミを飲む習慣っていうのは、
これは江戸時代よりももっと前にさかのぼっていくんですか?
ゲスト:そうですね。これは、古いかもしれませんね。
ただ、どこっていうのはわからないわけですよね。
それが民間薬の民間たる曰くたるゆえんで。ま、親から子へとかですね。
そんな形で伝わっていったんだと思いますね。
MC :やっと今入口にはいったとこですね。
あ、でも薬の世界の奥深いものでまた来週詳しく伺いたいと思います。
もう時間ですものね。はい。今週のサイコーは日本薬科大学教授の船山信次先生でした。
ありがとうございました。
ゲスト:失礼いたしました。 -
「火薬の科学 パート2」 ゲスト:松永猛裕さん
2019/03/01 Fri 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今週の「サイコー」もですね、火薬をご専門としてらっしゃいます、
産業技術総合研究所の松永猛裕さんです。よろしくお願いいたしまーす。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :先週、火薬ってのは、中国の狼煙?遠くの人に物を知らせる、そういう信号から始まったんだよ、
1300年以上の歴史があるんだよって話伺いました。
ところが最新の物では、みんなのお父さんの運転する車のエアバック、
エアバックを膨らますってちょと穏やかじゃないけれど、万一の時に、
命を守ってくれるエアバックってのは、実は膨らむのは火薬の瞬発力だっていう、すごいお話伺いましたね。
だから、最先端の技術にも、火薬は活躍してるというお話ですけど松永さん、他にも火薬のすごいところ。
例えば僕らの身近で、今この、文化放送のラボの中には、ま、ここには火薬はないでしょうね。
ゲスト:ないでしょうね。
MC :ないですね。
ゲスト:はい。
MC :え、マイクですとか、
ゲスト:はい。
MC :音響機器には、火薬はない、ですね。えっ、じゃあ身の回り?車にはエアバックこれは火薬使われてる。
ゲスト:はい。
MC :周辺の街の中で、例えば小学校、学校には火薬ってのはあるんですか。
ゲスト:学校には、ないでしょうねぇ。
MC :学校にはない。えーっと、研究所、理科室には火薬
ゲスト:も、ないでしょうね。
MC :ない。理科室にはない。
ゲスト:うん。
MC :そうなると、じゃ、バスに戻ってバスはエアバック、鉄道には?火薬は
ゲスト:例えば、面白いのはそのー、飛行機
MC :飛行機?
ゲスト:飛行機の、と、あの、乗る時にあのー、説明があるじゃないですか。
あの、とっさの時には酸素、の、あの、マスクが
MC :ああ、はい、はい。
ゲスト:降りてきますよと。あれを発生させるのもやっぱり火薬なんですよね。
MC :あれも発生、あれ、あれ降りて来たら怖いけど
ゲスト:だから、使ったことが
MC :うん。
ゲスト:ある人はまずいないと
MC :うん。
ゲスト:思うんですけども、
MC :でもあれは、バッと降りてくんの
ゲスト:はい。
MC :火薬なんですか?
ゲスト:いや、あのー、降りてくるんじゃなくて、酸素を発生させるのが火薬なんですよ。
MC :えっ、じゃあ、火薬を吸うってことですか。
ゲスト:いや、
MC :緊急時。
ゲスト:火薬であっためられた
MC :うん。
ゲスト:あのー、酸化剤、まあ、さ、酸素が入ってる粉があるんで
MC :はい。
ゲスト:そいつを温めることによって、酸素がジワジワ出てくると
MC :うん、うん。
ゲスト:あれは、あの、決してその、酸素ボンベがあるわけじゃなくって、
MC :なるほど。
ゲスト:あの、酸素入ってる粉を火薬があっためて、それでジワジワ酸素が発生するんで、
まあ、一定時間生きてられますよと
MC :すーごく今分かりやすかったです。
ゲスト:うん。
MC :多分、みんな誰もが飛行機の緊急時には
ゲスト:はい。
MC :海猿みたいな酸素ボンベが、機内にいっぱい装填されていて、
ゲスト:うん。
MC :乗客何百人用のね
ゲスト:はい。
MC :酸素を賄ってくれる、ボンベが搭載されてるんじゃないかと、僕今思ってたんです。
ゲスト:うん。
MC :そしたら、火薬の力をもって酸素を発生させる装置が稼働するってことなんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :だから、軽量化できるってこと。
ゲスト:うん。だから、酸素を固体で持ってるっていうのは、すごくいいことなんですよ。
MC :ほー。
ゲスト:で、固体で持ってるからやっぱり、あの、そういう火薬になったりしますし
MC :はい。
ゲスト:酸素発生させて、まあ、長時間生かすっていうことが出来るんですね。
MC :はい、はい、はい。なるほど。これ飛行機だけですか。
ゲスト:飛行機もそうだし、まああの、そうですね、あの、うちの研究所なんかもあります、
労働者の環境にもあるけどなんかあった時には、酸素マスクってのが
MC :はい。
ゲスト:だいたい労働環境の中では、あのー、置いてありますね。
MC :あ、それは火薬ですか、やっぱり
ゲスト:うん。
MC :酸素ボンベじゃない。
ゲスト:酸素ボンジェ、ベじゃない。
MC :へえー。
ゲスト:だから、長持ちするんですよ。
MC :おー、ですよねぇ。
ゲスト:うん。
MC :なぁる、いやぁー、すごい、システムが全然ちょっと違うことに、今、初めて気付きました。飛行機。
ゲスト:はい。
MC :へえ、あ、あとあります?
ゲスト:あとはねー、あ、面白い例としては
MC :ええ。
ゲスト:最近、その、えー、鹿とか
MC :はい。
ゲスト:熊とかが、あのー、増えてるじゃないですか
MC :はい。
ゲスト:国内に
MC :はい。
ゲスト:これの、あのー、生態をあのー、調べるために
MC :はい。
ゲスト:GPSが入った、あのー
MC :うん。
ゲスト:首輪を付けるんですね。
MC :付けてる、付けてる。北海道でも盛んです。
ゲスト:見たことあります?
MC :あります。
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:あれ、付ける時は麻酔でやるんですけども
MC :はい。
ゲスト:もう、取り終わったからいいやというので、外す時に、火薬で外すんですよ。
MC :バキュンて?
ゲスト:うん。
MC :バンて?
ゲスト:いや、あの、遠隔から信号を送ると、その、首輪が外れるような、あの、火薬の装置が入ってて
MC :で、動物は死なない。
ゲスト:死なない。
MC :あの、イメージ的には、あの野生動物の行動を研究する
ゲスト:はい。
MC :そういう研究機関があるんだけど、その研究機関が野生動物に麻酔かけて、あの、輪っかはめるんだね。
ゲスト:はい。
MC :で、それを、じゃ、外す時ってのは、
ゲスト:はい。火薬
MC :火薬で
ゲスト:火薬で外すんです。
MC :外してあげる。
ゲスト:はい。
MC :優しいじゃないですか。
ゲスト:うん。ま、ちょっとびっくりするかもしれませんけどね。
MC :ああ、確かに。へえー、あ、僕それに、あの、見たことある、
立ち会ったことあるので、あ、今初めて知りましたそれは
ゲスト:うん。
MC :外し方。
ゲスト:あんなのも火薬ですね。
MC :へえー。え、あと、火薬、あっ、ほっ、あれは?あの、ほ、使い捨てカイロはどうですか?火薬ですか?
ゲスト:使い捨てカイロは、まあ、火薬の一部ですね。
MC :ほー。
ゲスト:あれは、あの、火薬、ちょっと違いますね。
MC :違う。
ゲスト:うん。
MC :あれ、でも分解すると黒いじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :でも、あれは火薬じゃないんですね。
ゲスト:火薬じゃないですね。
MC :へえ、えっ、あとは、煙発生、あっ、部屋の中のゴキブリ退治
ゲスト:はい。
MC :あれは、煙出るやつは、火薬ですか?
ゲスト:あれは火薬です。
MC :ええっ、あれ、だって水と一緒に調合しますよ?
ゲスト:あのねぇ、水を混ぜるやつと、マッチでシュッとこするやつがあるじゃないですか。
MC :いや、僕水しか知らないです。
ゲスト:マッチでシュッと、こうあのー、なんだろ、えー、こするやつは
MC :うん。
ゲスト:火薬ですね。
MC :へっ、それ、マッチでこすって
ゲスト:はい。
MC :火を付けて
ゲスト:うん。
MC :煙発生さして
ゲスト:はい。
MC :それ、水使わないやつですよね。
ゲスト:あ、でもね、水を使うやつも、あのー、一番最後はやっぱ火薬になっちゃうんですよ。
MC :うん。
ゲスト:あのー、水で、を入れると熱が発生するような
MC :はい。
ゲスト:あの、薬があって、それであのー、最初の、あの、あっためる効果があるんですけど
MC :はい。
ゲスト:いざ、その、なんだろな、えー、殺虫剤を撒く時には
MC :はい。
ゲスト:もっともっと高温にして、えー、そういう殺虫剤を、あのー、
振り撒く必要があるんで温度上げるんですよね
MC :へえー。
ゲスト:その時に、あの、火薬の原理を使ったような粉が、あの、入ってます。
MC :へえー、えっ、あとお父さんのね、ワンカップみたいな、お酒ですよ。
ゲスト:はい。
MC :昔お酒で、
ゲスト:うん。
MC :なんか、線引っ張ると
ゲスト:はい。
MC :熱燗になるっていう、もう無いかな?
ゲスト:もう無いかもしれない。
MC :あ、あと駅弁でも
ゲスト:はい。
MC :山形の方に行くと
ゲスト:はい。
MC :駅弁の、う、裏に水入れると
ゲスト:はい。
MC :駅弁があったまるっていうのがあるんです。あれも火薬ですかね。
ゲスト:あれはちょっと違いますね。
MC :あれ違うんですか。
ゲスト:うん。
MC :いや、分かんなくなってきた。
ゲスト:いや、なんで違うかっていうと、あれは空気中の酸素を吸いて、あのー、発熱するからですよ。
MC :へえー。空気中の酸素に触れて発熱するシステムと
ゲスト:はい。
MC :火薬のシステムは違うんですね。
ゲスト:そうそう。あのー、火薬の場合は、その粉の中にすでに、あの、酸素が入ってると
MC :うん、うん。
ゲスト:で、ホッカイロとかなんとかは、空気中の酸素吸いながら発熱してんるんで、あれは火薬と言わないと
MC :なるほど、なるほど。
ゲスト:うん。
MC :だから、火薬に熱持たせるには、何らかの刺激を与えなくちゃいけないってことですね。
ゲスト:えー、
MC :マッチとか
ゲスト:まあそうですね。はい、はい。
MC :エアバックのあれ、
ゲスト:はい。
MC :電流流すとか
ゲスト:うん。
MC :なんかの刺激で、発火点に達した時にドカンと来るってことですね。
ゲスト:はい。
MC :はあ、いいですね。で、今、今の子供たちって火薬の事知らなくて、
僕なんか子供の頃、駄菓子屋さんで普通に鉄砲の火薬っていったら買えたんですよね。
ゲスト:はい。
MC :い、今の、多分、子供たちほとんど知らなくて、で、爆竹でも遊んだり、
ゲスト:うん。
MC :火薬遊びって結構やって怒られたんですけど、い、今のお子さんたちが、
身近なところで火薬を学ぶには何をすればいいですかね。
ゲスト:やっぱり花火でしょうね。
MC :花火を見て、この火薬を楽しむ。
ゲスト:はい。普通に買えるって言ったらもう、花火しかないですね。
MC :そう、そうですか。
ゲスト:うん。
MC :火薬はこれから、社会にとってね、エ、エアバックとか酸素ボンベに使われて、
これからまた進化して、役に立って行きますかね。
ゲスト:もちろんです。
MC :ああ。
ゲスト:やはり、もう、人を傷つけるというものから人を助けると、
MC :はい。
ゲスト:いうような用途に変わってますから
MC :うーん。いや、いいですよね。
ゲスト:うん。
MC :先週話したけど、ほんと武器ってイメージが強い火薬が、
ゲスト:はい。
MC :今や、命を守るための
ゲスト:はい。
MC :セーフティな物に
ゲスト:はい。
MC :変わってるってのが
ゲスト:うん。
MC :二週間に渡ってすごく勉強になりました。いやー、いやまたじゃぁ、
ちょっと今度火薬を使って何か、あのー、実験をして下さいね。
ゲスト:はい。
MC :あの、私たちラボで実験もやってますので。
ゲスト:あ、そうですか。
MC :はい。
ゲスト:是非、あのー、つくばに来て下さい。
MC :あー、そう。今度公開授業、つくばでやろうよ、火薬で。
ゲスト:やはりね、火薬は運ぶことがなかなか出来ないので、
MC :うん。
ゲスト:お越しいただいて、
MC :はい。
ゲスト:見ていただくのがいいと思います。
MC :そうですよね。
ゲスト:うん。
MC :またよろしくお願いいたします。
今週の「サイコー」は、産業技術総合研究所の松永猛裕さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございます。 -
「火薬の科学 パート1」 ゲスト:松永猛裕さん
2019/03/01 Fri 12:00 カテゴリ:科学MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
産業技術総合研究所の松永猛裕さんということで、
えー、この産業技術総合研究所、これはどういう機関ですか。
ゲスト:まあ、あの、簡単にいえば
MC :ええ。
ゲスト:あのー、産業の発展とその安全を研究するところですね。
MC :はい。
ゲスト:えー、経済産業省が所管する、え、研究所で、
MC :うん。
ゲスト:えー、そういう、あのー、立ち位置からも産業を、あの、育成させるとか
MC :うん、うん。
ゲスト:あの、保安を維持すると、
MC :うん。
ゲスト:いうようなところを研究するところです。
MC :も、僕達の身近にあるものはすべてここを通ってるようなものですよね。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :あはは。ですよね。だから、松永さんのお墨付きをいただいて、世に出てるようなものですね。
ゲスト:まあ、そう、でも
MC :んふふ。
ゲスト:まあ、そういって構いません。
MC :ええ、でもそういうことですよね。
ゲスト:はい。
MC :松永さんは、火薬や爆発性物質の安全研究に携わる方ということで、ここでこうまた、
専門性が違ってくるんですけれど、講談社から「火薬のはなし」という本も出版されてます。
で、僕らの身近にあるものは、松永さんの研究機関を通ってるんですけれど、
そんな中で火薬とか爆発性物質、ここにも携わってらっしゃると
ゲスト:はい。
MC :火薬、今のキッズ達は、火薬っていうと身近な物、なんですかね?
ゲスト:花火でしょうね。
MC :あー、シーズンやってきますねぇ。
ゲスト:はい。
MC :僕は、花火は分解して遊びましたけど、それはやっていいことですか。
ゲスト:絶対いけません。
MC :ですよね
ゲスト:はい。
MC :書いてありますよねぇ。
ゲスト:はい。
MC :なんで花火って、こんな綺麗になるんだろうと思って、子供心にやっぱり調べたくなるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :そしたら、つまんない、し、し、黒ーい物が出てくるわけですよ。なんでこんなものがね、
綺麗になるんだろうと思って、不思議でならなかったんですけど
ゲスト:はい。
MC :やっちゃいけないんですね。
ゲスト:絶対分解してはいけません。
MC :ごめんなさい。
ゲスト:はい。
MC :はい。で、火薬、じゃ、花火、今のキッズ達は多分、こういうことはしてないと思うんですけれど、
火薬って物は、花火にも使われてます。
ゲスト:はい。
MC :その他に何に使われてますか?
ゲスト:ま、例えばロケットの打ち上げの、あのー、煙が出ますよね。
MC :うん。
ゲスト:あれ、全部火薬なんです。
MC :えーっ、あれは、燃料って言われてるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :燃料タンクが切り離されてって言うじゃないですか
ゲスト:はい。
MC :だから僕らの中には、特別な燃料、何か液体が入ってるイメージですね。
ゲスト:H2ロケットはど真ん中は、そのー、そういう液体のロケットなんですけども
MC :うん。
ゲスト:両脇抱えてるのが、やっぱりあの、火薬ですね。ほとんど花火とおんなじような、
あの、火薬が入ってます。
MC :いいや、すごい、え、火薬って粉のイメージですよね?
ゲスト:うん。
MC :じゃあ、あの、打ち上げられる、種子島から打ち上げられた、
ゲスト:うん。
MC :あのロケットの両サイドは、
ゲスト:はい。
MC :粉末。
ゲスト:粉末です。粉末
MC :粉火薬。
ゲスト:火薬です。
MC :で、真ん中は液体。
ゲスト:はい。
MC :燃料。
ゲスト:はい。
MC :非常に古典的な物で、じゃあ、宇宙に向かって行くわけですか?
ゲスト:古典的と言ったらきっと失礼ですが、
MC :あ、違う。
ゲスト:あそこは、あの、もう、最先端の
MC :ええっー。
ゲスト:ハイテクの塊ですから、
MC :あっ、火薬も進化してるんですか?
ゲスト:はい。
MC :すごい。えっ、火薬の歴史ってそもそも、
ゲスト:はい。
MC :いつごろからですか?
ゲスト:火薬の歴史一番古いのは中国で
MC :はい。
ゲスト:あの、狼煙を上げるような、あの、黒色火薬の、えー、組成ですよね。
あれが大体あの、8世紀ぐらいの話です。
MC :8世紀。1300年ぐらい前
ゲスト:いや、あ、そうですね。前ですね。
MC :うん。で、キッズ達多分狼煙知らないと思いますね。
ゲスト:ああ、そうでしょうね。
MC :狼煙教えて下さい。
ゲスト:狼煙と言いうのは何かこう、何かあったぞーというので煙をあの、
えー、発生させることで、えー、連絡するような
MC :はい。
ゲスト:あの、物ですね。
MC :はい。だから、何十キロ何百キロ離れたところで、煙が見えたら、あっ何かあったんだって。
ゲスト:何百キロは多分
MC :それは見えない
ゲスト:見えないと思いますよ。
MC :何十キロ。
ゲスト:まあ、何キロぐらいの話じゃ
MC :何キロ
ゲスト:ないですか?
MC :て、それがサインですね。じゃあ。
ゲスト:はい、はい。
MC :発煙筒みたいな感じですか?
ゲスト:うーん、敵が来たぞーって言うかもしれないですし
MC :ほー。なるほど。
ゲスト:はい。
MC :それに火薬が用いられていて
ゲスト:はい。
MC :じゃ、敵が来たぞって、遠くにいる人が教えて、で、こっちの陣地にいる人達が準備をするとか
ゲスト:はい。
MC :そういう信号として使われてたのが、1300年前。
ゲスト:そうですね。
MC :で、僕らからすると花火。で今はロケットの打ち上げ。でも、同じ原料と考えてよろしいですか?
ゲスト:ほとんど同じ原料ですね。
MC :えー。
ゲスト:ま、げん、原理は、もう、まったく同じです。
MC :えー。原料何ですか。
ゲスト:原理は、あ、というかまあ、原料は、そのー、いわゆる燃えるための酸素、
MC :うん。
ゲスト:普通は、あの、酸素っていうとこの辺舞ってるような気体なんですけども、
MC :はい。
ゲスト:固体の中に詰まってるものもあるんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、それはあの酸素を含む、えー、化学物質で酸化剤って言うんですけども、
MC :うん。
ゲスト:そういう酸化剤が入っていると、あの、固体で燃えることが出来ると
MC :ほー。えっ、それは酸化剤というのは、僕らの身の回りでは何をもってどういうものですかね。
ゲスト:うーん。あ、オキシドールとかの消毒に使う過酸化水素
MC :ほぉ、ほぉ、ほぉ。
ゲスト:これはあの、酸素持ってますよね。
MC :へー。
ゲスト:だから、あの、消毒して、あの、ブクブク言いだすし、
MC :えっ。
ゲスト:あれで、発生するの酸素なんですよね。
MC :ほー。消毒液ね。
ゲスト:はい。
MC :それが、
ゲスト:うん。
MC :酸化剤。
ゲスト:はい。
MC :で、火薬の原料というのは?
ゲスト:火薬の原料は、まあ、そういう、あの、オキシドールじゃなくって、
あのー、例えば黒色火薬でいうと硝酸カリウムと
MC :うん。
ゲスト:いうものを使いますし、え、ロケットでいうと過塩素酸カリウム、
過塩素酸アンモニウムというような物質、ちょっと難しくなるんですけどね
MC :いわゆる
ゲスト:そういうものを使います。
MC :ちょ、調合して出来る物なんですね。
ゲスト:調合して出来る物ですね。
MC :自然体、自然界に勝手に存在する物でなくて、科学的なもの調合して火薬が出来る。
ゲスト:そういうこともあるんですけども
MC :はい。
ゲスト:黒色火薬でいうと、チリ硝石っていうのが昔あって、
それはあの、硝酸が入ってる鉱石なんです、石ですよね。
MC :へえー。燃える石?
ゲスト:はい。
MC :へえ。へえー。日本にはまだあるんですか?そういうの。
ゲスト:いや、
MC :もうない?
ゲスト:もちろんありますよ。
MC :ええっ。
ゲスト:あのー、ね合掌造りで知られているああいう建屋ってのは、
もう、ほとんど昔の江戸時代の軍事工場だったんですよね。
で、何がっていうと、その、の、あの、何だ?えー、地下に
MC :はい。
ゲスト:そういう、えー、バクテリアを飼ってて、で、それであのー、
硝酸カリウムを作るというような製法が昔あったんですよ。
MC :合掌造りって飛騨高山とか
ゲスト:はい、はい、はい。
MC :ああゆう
ゲスト:あれは
MC :山の中の?
ゲスト:そうです。あの、大名のいわゆる軍事工場ですよ。
MC :へえー。
ゲスト:うん。
MC :それは
ゲスト:で、バクテリアの、あのー、作用をもってそういう硝酸
MC :うん。
ゲスト:カリウムを作るというようなやり方があったわけですよね。
MC :へえー。それは、日本でもそういう風にして火薬をそっから作っていたわけですか。
ゲスト:もちろんですよ。
MC :火薬って何か武器のイメージが強いですよね。
ゲスト:はい。
MC :鉄砲とか
ゲスト:はい。
MC :だから、もう、そもそも鉄砲が伝来して、470年ぐらい前ですかね?
ゲスト:うん。
MC :種子島に伝来して
ゲスト:はい。
MC :その時はやっぱり火薬の力でボンと出るっていう
ゲスト:そうですね。
MC :うん。今の鉄砲、ピストルなんかも火薬は使われてるんですか?
ゲスト:火薬を使います。
MC :おっ。同じなんですね
ゲスト:はい。
MC :じゃあ、原理は。へえー。じゃあ、武器に使われる。花火にも使われる。
後は、何に使われてるんですかね。
ゲスト:今一番、あのー、身近にあるのは、エアバックですね
MC :あっ。
ゲスト:車の、車の安全
MC :ええ。
ゲスト:装置ってのは、今、あの、
MC :ええ。
ゲスト:高級車になると30個ぐらい、色々付けて、られてるんですけども、
あのー、とっさの時に大きな力を出すというのは、やっぱ火薬なんですよね。
MC :ちょっと待って、え、今ほとんどの車、今
ゲスト:付いてますね。
MC :全部、もう全車ほとんど
ゲスト:うん。はい。
MC :ですよね。
ゲスト:うん。
MC :今の車って。
ゲスト:あの、薬のようなタブレットみたいなのやつがゴロゴロ入ってて、
それが瞬間的に、その、燃えるもんですから、
MC :うん。
ゲスト:火薬で、ですからね。それであのー、ああいうバックが膨らむということになってますね。
MC :は
ゲスト:ガスなんかじゃ間に合わないよというので、火薬が使われてます。
MC :あー、すっごい古典的なものだけれど、
ゲスト:うん。
MC :火薬がガスを上回った、今トークですね。
ゲスト:うーん。
MC :ガスには間に合わねえぞと。
ゲスト:だから、100分の何秒でやる、やるなんて話になると
MC :ええ。
ゲスト:もはや火薬以外では出来ない。
MC :瞬発力は火薬が一番。
ゲスト:はい。
MC :いやー、今火薬ドヤ顔ですね。
ゲスト:うん。
MC :色んな科学の進歩があるけれど
ゲスト:はい。
MC :1300年前の中国で、
ゲスト:うん。
MC :生まれた火薬って物が、今の最先端のテクノロジーにも生かされてるってことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :いやー、今ちょっと松永さんの顔も神々しいものに見えてきましたよー、
もっともっと火薬の話伺いたいですねぇー。あ、もう時間ですか?いや、また来週もお願いしますね。
今週の「サイコー」は、産業技術総合研究所の松永猛裕さんでした。どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございます。 -
「冬の虫 パート2」 ゲスト:谷本雄治さん
2019/02/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :今週のサイエンスコーチャー、略してサイコ―は前回に続きまして
プチ生物研究家の虫が大好き谷本雄治さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
ゲスト:こんばんは、よろしくお願いします。
MC :先週何が衝撃って、蝶々がこのシーズンもいるよって話で、いなかったですよ、なかなか。
ゲスト:あ、そうですか、あははは
MC :いないですけど、ま、冬の間も、あのー虫は活動してる虫もいるよってお話を伺いました。
ゲスト:そういうことですね、はい。
MC :とても興味深かったです。さあ今ね助手からミノムシって冬の虫ですよねって言われたんですけど
ゲスト:はい
MC :ほんとですか?
ゲスト:そうですね、あのー一番目立つ時期がやっぱり冬になるっていう事で
MC :でしたっけ
ゲスト:ええ、ほんとか嘘かっていうとですね
MC :うーん
ゲスト:まあいわゆる初夏の頃に
MC :はい
ゲスト:あのー幼虫がですね
MC :はい
ゲスト:えー母親の、母親っていうか、あのミノの中で
MC :はい
ゲスト:ミノムシっていうのは不思議な習性がありまして
MC :はい
ゲスト:ミノムシの雌は一生ミノの中から出る事がないんです。
MC :へえーー
ゲスト:それで雄がですね、成虫になった雄が、あーそれは蛾になるんですけども
MC :あ、ミノムシ最後蛾になっちゃうんですか
ゲスト:そうなんですね
MC :あーがっかり、あははは
ゲスト:ミノムシのですね
MC :はい
ゲスト:親になった蛾はですね
MC :はい
ゲスト:大体、あのーミノガっていうんですけども
MC :あ、聞いた事あります。
ゲスト:ミノ、ありますか。
MC :はい
ゲスト:それにまあ、それぞれオオミノガとかチャミノガとか
MC :はい
ゲスト:こう名前が付いてるんですけども。そういう風になるんですが、
雄は羽が生えて飛んで行けるんですけども
MC :はい
ゲスト:雌は一生ミノの中に入ったままなんです。
MC :すごいですね。
ゲスト:すごいです。
MC :ある意味可哀そうですね。
ゲスト:そうですね
MC :下界を見る事無く一生を終えちゃう雌と
ゲスト:そうですね。それで体の形もですねあのー、幼虫の、ま簡単に言うとイモ虫のままなんですよね、雌は
MC :はあー、また切ないですね、ふふふ。
ゲスト:切ないです。そいでそのミノムシの雌がミノの中で産んだ卵が
MC :はい
ゲスト:まあ夏の初めですよね、あのー繭、あ、ミノの中でかえ、かえりまして
MC :はい
ゲスト:そいでそれがみんな散らばって行くんです外へ
MC :はい
ゲスト:それで散らばって行ったほんとにまあ、何ミリというような小さなミノムシがそれぞれ、
こうせっせと葉っぱを集めて
MC :はい
ゲスト:小さなミノを作るんです。
MC :はい
ゲスト:そこがまあミノムシの始まりで
MC :はい
ゲスト:それが段々大きくなっていって、冬になるとある程度大きくなるもんだから人の目につくと
MC :なるほど
ゲスト:はい
MC :あっそうか、じゃあもうミノを制作してるのは夏場からやってるってことですか?
ゲスト:そうですね、はいそうです。もう一生懸命食べてですね
MC :ええ
ゲスト:葉っぱをくっつけて、それで段々大きくしてってるんですね。
MC :で冬場になるとその集大成で
ゲスト:はい
MC :一番巨大なミノになって
ゲスト:そうですね
MC :人間の目に留まるから
ゲスト:はい
MC :ラボの助手が言う、ミノムシってのは冬の虫ですよねってこと
ゲスト:そうですね。
MC :で、それ冬の後どうなるんですか?
ゲスト:あの、冬の後はまたそれの繰り返しになりますんで
MC :め、雌は
ゲスト:はい
MC :一年で死んじゃうんですか?
ゲスト:雌はですね、これほんとに儚いんですけども
MC :はい
ゲスト:卵を産んだらですね、体がまあ、体の中ほとんど卵だと思うんですね
MC :はい
ゲスト:それで産んだ後はもうガリガリに痩せてしまって
MC :ええ
ゲスト:ミノの下からですね、ポトンと落ちて死んでしまうと
MC :かわいそ過ぎる
ゲスト:可哀そう
MC :そんなの聞きたくない
ゲスト:ほんとに可哀そう過ぎるんですけど
MC :可哀そうだ
ゲスト:はい、そのかわり、まあ
MC :ポトンと落ちちゃう
ゲスト:そうですね
MC :やだ、見たことありますか?その瞬間は
ゲスト:いや、その瞬間はさすがに無いんですけども
MC :ポトンと落ちるのは何月位ですか?
ゲスト:たぶんそれ卵があれなんで初夏じゃないかなと思うんで
MC :初夏、
ゲスト:はい
MC :あー
ゲスト:夏、でその次の冬を見る事なく死んでしまいますからね
MC :はあー
ゲスト:はい
MC :それで次のそのお母さんが産み落とした雌の方の
ゲスト:はい
MC :幼虫が
ゲスト:はい
MC :ミノを作って
ゲスト:はい
MC :また一年近くたつとポトンと落ちちゃう
ゲスト:そうですね。
MC :かわいそう
ゲスト:ま、単純に半分が雄だとすれば雄は飛ぶ事ができますけどもね。
MC :ふーん
ゲスト:はい
MC :でもね、あの、成人して蛾になって
ゲスト:はい
MC :もう全然人間はかわい、かまってくれないわけじゃないですか
ゲスト:はい
MC :蝶々になるか蛾になるかでやっぱりその虫の人生って変わってくると思うし、
蛾になってねなんかみんなにうっとうしがられる、あの、巣立ちも切ないし、
雌は雌で世間を見る事無く死んじゃうのも切なくて、ミノムシに産まれた不幸ってのはよく分かりました。
ゲスト:そうですね
MC :ああ、ミノムシ見つけたら儚さをちょっとみんな、はあ、切ない。
ミノムシでなんか一本ドラマ作りたくなってきました。。
ゲスト:そうですか。
MC :ラジオドラマ作ろう今度、緊急企画。
ゲスト:楽しいかもしれませんね。
MC :ねえ30分、ねえ、行くぞ。ようし、ミノムシの一生、ねえ。
ゲスト:はい
MC :誰かでナレーションお願いして、文化放送のアナウンサーの人に。そっかあ。
えー、後は冬ちょっと僕ら何をチェックしましょうか?鳴き声をあげる、だから前回来て頂いた時に秋のね
ゲスト:はい
MC :鈴虫の音色とか
ゲスト:はい
MC :そういう聞いたけど、冬、音を出す虫ってのはいます?
ゲスト:冬はですね、さすがに音を出すっていうか鳴く虫は
MC :ええ
ゲスト:いないんじゃないかなって思うんですよね。
MC :あー
ゲスト:あの、いるかもしれないんですが
MC :ええ
ゲスト:まあ、み、身近にはいないってゆう意味で
MC :ほおー
ゲスト:はい
MC :谷本さんでもね、プチ生物研究家として
ゲスト:はい
MC :やっぱりこの時期虫が近くにいなくて切ないじゃないですか
ゲスト:そうですね
MC :虫を求めてどこに行くんですか?
ゲスト:あのー虫を求めてですね、近くに雑木林があれば
MC :ええ
ゲスト:雑木林へやっぱり行きます。
MC :どんなのがいますかその
ゲスト:あの、そこでですね、これも冬ならではの虫なんですけども、あの、フユシャクというのがいまして
MC :フユシャク
ゲスト:はい
MC :読んで字の通り?
ゲスト:これがなかなか読んで字の通り分かっていただけるか
MC :違う?
ゲスト:分かんないですけども
MC :冬の
ゲスト:冬に
MC :シャクトリムシ
ゲスト:そういうことです。ああ
MC :おお
ゲスト:その通りです。
MC :シャクトリムシ
ゲスト:シャクトリムシのまあ、親になったもの
MC :ふん
ゲスト:シャクトリムシのなれの果てっていうのがシャク蛾っていうものなんですけども
MC :やっぱりそれも蛾ですか。
ゲスト:蛾です。
MC :いやだなあ、あ、そう、はい。
ゲスト:これは冬しか出てこない蛾なんで
MC :ええ
ゲスト:あの、結構なマニアがいるんじゃないかと思うんですが
MC :フユシャクマニアが?
ゲスト:フユシャクマニアが
MC :初耳ですよ
ゲスト:そうですか
MC :えへへへ
ゲスト:それでこのフユシャクっていうのがですね
MC :ええ
ゲスト:ほんとになぜ冬にいるのかってっていうのがいまだにはっきりした答えは出てないんですけども
MC :うん
ゲスト:ま、一番有力じゃないかと言われているのが、冬になれば、ま、
先ほどからお話しているようにあんまり他の虫がいないですよね
MC :うん
ゲスト:そういう中で、生きていくことが出来ると。ようするに天敵になるものがいないとですね、
自分達がまあ、あの、暮らすには都合が良いわけですね。
MC :はい
ゲスト:そういう中でこのフユシャクというグループは、冬に活動することを選んだんじゃないかと、
そんな風にみられています。
MC :それはあの、雑木林行ったら大体関東地方います?
ゲスト:あの、大体はいないっていうかなかなか見つけにくいんですが
MC :あら
ゲスト:関東じゃなくてもですね北海道でもやっぱ、まあ雪が積もってしまうと大変だと思うんですが
MC :あ、全国にいるんですか
ゲスト:全国にいるんです
MC :フユシャクは
ゲスト:はい
MC :それはシャクトリムシの動きをするんですよね
ゲスト:あ、もうその時には
MC :ええ
ゲスト:成虫なんです
MC :あ、蛾でいるんですか
ゲスト:蛾でいるんです。
MC :それは分かんないですね
ゲスト:分かんないですよね
MC :あ
ゲスト:で地味すぎて
MC :ええ
ゲスト:はい。それでこれもですね、このフユシャクの面白いのは
MC :はい
ゲスト:やっぱこう雄と雌で違いがありまして
MC :はい
ゲスト:雌の方はですね、羽が退化してるんです。
MC :ええ
ゲスト:で、退化していて、この退化の仕方にもまあ、二種類大きくありまして、
あの、よく言われるのがホルスタイン型っていうのと
MC :ええ
ゲスト:蝶ネクタイ型
MC :ホルスタインっていうのは乳牛ですね。
ゲスト:そうです、まあ北海道の牧場なんかによくいる白と黒の
MC :はい
ゲスト:ぶちになったような
MC :はい
ゲスト:あの牛ですよね、あの牛の模様に似ている、えー
MC :蛾がいる
ゲスト:フユ、はい、フユシャクの雌
MC :へえー
ゲスト:それと蝶ネクタイ型っていうのは羽は退化してるんですが、退化していて飛べないんですけども、
ま、蝶ネクタイ位の、ま、小さい羽があると
MC :うん
ゲスト:いう、そういうグループに大きく分かれるんですね。
MC :それは蝶ネクタイ型の雌は飛べないんですか?
ゲスト:やっぱり飛べない。
MC :ミノムシと同じじゃないですか。
ゲスト:同じです。で、どちらも雌は飛べないんですけども、もうお腹の中にはですね卵が
やっぱり一杯詰まってるんですね。で、あのー、フェロモンっていうんですけども、
そういう性フェロモンていうあのー、仲間にしか分からない特別な匂いがあるんですけども、
それを出して、そうするとまあ近くにいる雄がですね
MC :ええ
ゲスト:雄はあの、羽があって飛べるもんですから、あっちにいるぞっていうのを、
あのー感じ取って、それで寄ってくると、そういう生活をしているような、
あのー、シャク蛾なんですね。シャクトリムシの、まあ、あの成虫ですね。
冬はそういう風でなかなか目を付けるところが良ければ楽しめるんですね。
MC :へえ、な、なんか二週にわたってね冬の虫の話聞いたけど
ゲスト:はい
MC :色彩がほとんどないんですよ。
ゲスト:あ、そうです
MC :茶色っぽいんです、全部、全体的に。でもそれはそれでイメージも膨らんだし
ゲスト:そうですね
MC :もの悲しくて
ゲスト:はい
MC :でもいるってこととね
ゲスト:はい
MC :あのー、観察をする、な、なんかすごくレアなお話で、
これ興味あったらぜひちょっと雑木林行きたくなりますよこれ
ゲスト:そうですね、ぜひ
MC :行ってよ、みんなもね
ゲスト:そうですね、行った方が楽しくなると思います。
MC :へえーー
ゲスト:はい
MC :もしかしたらみのもんたさんに会えるかもしれませんね
ゲスト:あはは、そうですね、はい。
MC :はははは、いやー、もうお時間?おもしろかったなあ。
いや、またぜひなんか今度は標本とか持って遊びに来てくださいよ。
ゲスト:あ、そうですね。今度は、はい。
MC :はい
ゲスト:あの、また持って遊びに来ますんでよろしくおねがいします。
MC :はい、えープチ生物研究家の谷本雄治さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「冬の虫 パート1」 ゲスト:谷本雄治さん
2019/02/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ今週のサイエンスコーチャー、略してサイコ―は虫に関してものすごくお詳しい
プチ生物研究家の谷本雄治さんです。こんばんは
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、一昨年の秋だったかな、鈴虫の鳴き声を、あのースタジオで聞いて頂いたら、
怒られたんでね、なんかラジオ局にある、ラボにある、あの鈴虫のサンプルを出したら、
これ違うだろっつって。それくらいあの虫の鳴き声にもう非常に精通してらっしゃる。
よろしくお願いします。
ゲスト:はいよろしくお願いします。
MC :へへへ、さあ今日のテーマはね、今冬なんですよ。
冬って多分ね虫と一番縁遠い季節だと思うんですけれど、虫は冬どこで何してるのかと。
これ意外に知らないですよ、みんな。谷本さん、何してんですか虫
ゲスト:そうですね、やっぱ冬は寂しい時期ですね。
MC :寂しい
ゲスト:ええ、で、虫たちもですねまあ、やる事が多分無いと思いまして
MC :ああ
ゲスト:で、大体じーっとしてるものが多いですね。
MC :ま、家庭に変なハエがいるとかね
ゲスト:ええ
MC :そういうぐらいですよね。
ゲスト:そうですね
MC :うーん
ゲスト:あの、今ハエの話出ましたけども
MC :ええ
ゲスト:あの冬にも蚊がいるんですよね
MC :ええっ、ええっ、見た事ない
ゲスト:あのー、特に都会ですと、ま、地下街っていうか発達してますよね
MC :えー
ゲスト:そういう中にいるほんと名前もね地下家蚊っていう
MC :地下家蚊?
ゲスト:地下にいるまあ、家蚊っていう
MC :へえー
ゲスト:仲間っていう事なんですけどね
MC :へえー
ゲスト:そういうのもいるんですよ
MC :それはなに、都会の暖かい所
ゲスト:はい
MC :にずっと生息してる
ゲスト:している
MC :蚊がいるんですか?
ゲスト:はい、だから気を付けないと蚊に刺されたって言う人もいますよね。
MC :なるほど
ゲスト:はい
MC :いやあ、いきなりのっけからつかみはオッケーですよ。
ゲスト:いえ、へへ
MC :さすが。さあ基本的に冬
ゲスト:はい
MC :多くの虫はでもやる事がない
ゲスト:はい
MC :やる事がない虫はどこで何してるんですか?
ゲスト:あの、ま、種類によって色々なんですけども
MC :はい
ゲスト:まあ成虫で生き残っているものもいるし、後幼虫とかですねサナギであったり卵だったりと、
ま、色んな形をとりながらもなんとかまあ冬をしのごうと、
色々まあ知恵を絞るっていうか考えてますよね。
MC :あ、そこには儚いけれど
ゲスト:ええ
MC :成虫で生き残っている、まあ代表的なセミ
ゲスト:はい
MC :セミは一週間で死んじゃうって言うじゃないですか?
ゲスト:そうですね
MC :だけど成虫になったまんま、なんとなく冬、
冬の前に虫ってね死んじゃうんじゃないかってイメージですけど
ゲスト:ええ
MC :越冬する虫もいる
ゲスト:いるんですね。あの成虫でですねまあ、
越冬出来るっていうのはまあ数そんなにあるとは思えないんですけども
MC :はあ
ゲスト:例えばまあ、あのよく皆さんお好きな蝶々でいうと、
成虫で冬を越すってのがタテハチョウっていうのがまあ代表的なんですけども
MC :タテハチョウ
ゲスト:はい
MC :うん
ゲスト:あのー、ま、名前の通りですね、羽を立てるから、ま、タテハチョウと
MC :はい
ゲスト:いうんですけども、その中で私が特に好きなのはルリタテハという
瑠璃色っていうのはまあ、青色ですよね
MC :はい
ゲスト:青っぽい羽の色を持った、あのー、タテハチョウっていうのがいるんですけども、
それはまあ冬になるとですね、成虫のままでじっとしていて、あったかい日には時々あの、
フワフワって飛んでますね。
MC :へえー。でも同じ蝶々でも
ゲスト:ええ
MC :冬を越せない蝶々と
ゲスト:ええ
MC :冬を越せる蝶々とのその差はなんですか?
ゲスト:さあ、そこまでちょっとよく分からないんですけども
MC :ええ
ゲスト:やっぱりそのー、進化の歴史の中でですね色々自分たちは、
やっぱ卵でいた方が良いのかそれとも幼虫でいた方が良いのか、
その先のまあ繁殖というか自分たちの仲間を維持していく為にね、
どうやったらいいかっていう中で多分、あのー選び出した方法だと思うんです。
MC :なるほど。そっか、虫は卵
ゲスト:はい
MC :それから幼虫
ゲスト:はい
MC :まあそして成虫という
ゲスト:はい
MC :三段階
ゲスト:はい
MC :変化していくじゃないですか。
ゲスト:はい
MC :大体これ1年サイクル
ゲスト:そうですね、で、ものによってはですね1年のうちに2回とか3回こう、
あのー卵から成虫になる世代を繰り返すと
MC :はい
ゲスト:そういうものもいるんですよね。
MC :ただ今のタテハチョウ
ゲスト:はい
MC :などは1年サイクルじゃなくて、実は年を越して
ゲスト:え、あのー、あったかい地域に生まれたものはですね
MC :ええ
ゲスト:卵からやっぱり成虫になっちゃうんですが、秋口に成虫になって、ま、あの、冬を越すと
MC :はい
ゲスト:いう形ですね。
MC :はあはあはあ
ゲスト:だからあのー、1年中ずーっと長い事生きてるっていう風ではない
MC :やっぱり儚い話なんです
ゲスト:儚いといえば儚いですね
MC :いやあ、切なくなってきた
ゲスト:はい
MC :谷本さんの顔もなんか悲しげになってきた。
ゲスト:いえーそんな事もないですけど
MC :まだ1月なんだけど
ゲスト:はい
MC :すごく切ない。やっぱり、やっぱり1年サイクルなんですね。
ゲスト:そうですね
MC :いやー、そっかあ
ゲスト:後、まあ成虫でいうとですね、あのウラギンシジミっていうのがいまして
MC :シジミ?
ゲスト:ええ、シジミチョウっていう小さい蝶々なんですが
MC :おー
ゲスト:あ、で
MC :蝶々
ゲスト:はい、そのシジミチョウっていうのはあの、シジミ貝ってありますよね。
MC :はい
ゲスト:そのシジミ貝のようにまあ小さな蝶々
MC :あー
ゲスト:っていうグループなんですけども
MC :はい
ゲスト:あの、そのシジミチョウの多くは卵で冬を越す事が多いんですけども
MC :はい
ゲスト:このウラギンシジミっていうのはですね、あの、これも名前の通り裏っ側、
羽の裏っ側が銀色をしているシジミチョウというもので、
それがあの、冬の間は葉っぱにとまってですね、やっぱり成虫のままで越すんですよね
MC :ふうん
ゲスト:はい。そういった所がまああの成虫で冬を越す蝶々
MC :しゅ首都圏でどっかで成虫の蝶々今や見つける事できますか?
ゲスト:あ、今言ったこのウラギンシジミとかですね、ルリタテハなんかは多分見つかると思います。
MC :どこにいるんだろうか
ゲスト:あのー都会でも東京でも大きな公園がありますよね
MC :ええ
ゲスト:そういった所は木が沢山植わってますんで
MC :ええ
ゲスト:いわゆる常緑樹、冬でも葉っぱを落とさない木ですよね、
そういった所にとまっていいたりするんですよね。
MC :へえーー、知らなかったですね。みんな夏使った網持ってこれば、あの昆虫採集出来るかもしれないけど
ゲスト:そうですね、へへへ、はい
MC :卵で
ゲスト:はい
MC :越冬する
ゲスト:はい
MC :あるいは幼虫で
ゲスト:はい
MC :越冬する。あのーそれは虫が自分で選んでるんですか?本能的に
ゲスト:ええ、もう、あの今となってはというか
MC :ええ
ゲスト:もう何年何万年ていう歴史の中でですね
MC :ええ
ゲスト:それで先ほど言ったように選び出した方法だと思うんで
MC :ふうん
ゲスト:そういう意味では選んだという、その虫の種類毎にですね、
選んだ冬越しの仕方という事になると思います。
MC :まず卵の代表格はなんですか?
ゲスト:卵はまあ先ほど言ったシジミチョウ
MC :蝶々
ゲスト:はい。それが多いですね。あ、後ですねカメムシ
MC :カメムシ?
ゲスト:カメムシもう卵で
MC :あー、ちょ、ちょっと、一番や、や、やだなあれ
ゲスト:あはは
MC :まとわれたら最悪ですけど、カメムシは今頃なに、卵で越冬して
ゲスト:ええ
MC :るんですね
ゲスト:これもですね、あの、ひとくくりに虫の場合出来ないところが
MC :ええ
ゲスト:またすごいところで、カメムシっていうとまあ臭い虫の代表
MC :ええ
ゲスト:みたいに言われますけども、そのカメムシの中でもまた種類によって違ってくるんですよね。
MC :ふうん
ゲスト:で、卵であのー、冬を越すカメムシがいますし、成虫でですね冬を越すものもいます。
MC :ほお
ゲスト:で、この成虫で冬を越すカメムシですね、これーあのー私も好きなものがいるんですけども、
オオキンカメムシって言いましてですね、かなり大きく、大きなカメムシで大人の指2枚分というか、
2つ分くらいの
MC :へえー
ゲスト:結構大きなカメムシがいるんですよ。
MC :カメムシ指に乗せたくないですよねえ、ええ。
ゲスト:乗せたくない、え、でもそのカメムシはね、あのー黄色と黒の、ま、模様でして、
これはある程度集団でですね、集団といってもま、何十匹はなかなか見つからないと思うんですけども、
何匹かずつですね葉っぱに固まって冬を越すんです。
MC :ふうん
ゲスト:ですんでこれはあのー、私は冬にはですね、毎年一回は探しに行くんです。
で、年によって良く見つかる事もあるし、ま、見つからない事もあるんですけども、
ですんでカメムシも成虫で冬を越すものと、それから卵で越すもの、それからさらに言うとね
MC :ええ
ゲスト:幼虫のままで、あのー、冬を越すですねカメムシもいるんです。
MC :ちょっと待って下さい。卵で冬を越す虫の代表格で最初にカメムシ出したたんだけど
ゲスト:はは
MC :全然違う方向いっちゃったじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :ははは
ゲスト:カメムシはあのー、なかなか楽しくってですね、あのー色々いますよ。
MC :そうですか
ゲスト:ええ
MC :分かりました。じゃあ、さん、3種類あるんですね
ゲスト:そうですね
MC :卵・幼虫・成虫
ゲスト:とありますね。
MC :えー、じゃあ今頃卵見つかるとしたらなん、なんですか、カマキリの卵なんかは
ゲスト:あ、カマキリの卵はですねあのー、おもしろいですね。
MC :今、今
ゲスト:今、まあまさに今、まあほとんど産んでますよね。
MC :あ、やっぱりそうですよね
ゲスト:はい
MC :ただ、あの、ねえ、アブラナの葉っぱの下あたりに
ゲスト:ああ、あったりしますね
MC :いますよね
ゲスト:はい、それからまあ木の枝の所に
MC :はい
ゲスト:産んであったりとか
MC :え、じゃあカマキリは今、今の時期は、だ、大体卵でいる
ゲスト:そうですね、はい。カマキリは成虫では冬は越せないと思います。
MC :はあー
ゲスト:あの、かなり遅くまでですね、生き残ってるカマキリもいるんですけども、
最終的にはやっぱり卵を残して死んでしまうと
MC :うん
ゲスト:というのがまあ、正しいカマキリさんの生き方ですよね。
MC :はあ。え、もう時間?あら、そう、あらちょっと今冬の虫に思いを馳せちゃった、いやあ。
さあ来週もまたお話伺いたいと思います。今週のサイコ―はプチ生物研究家の谷本雄治さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「理系あるある パート2」 ゲスト:小谷太郎さん
2019/01/01 Tue 12:00 カテゴリ:その他MC :今週の「サイコー」も前回に続きまして、サイエンスライターの小谷太郎さんです。
よろしくお願いしまーす。
ゲスト:よろしくお願いしまーす。
MC :小谷さんご専門は、宇宙物理学と観測装置開発ということなんですけれど、
全然関係ないお話を伺っていきます。
ゲスト:ははは。
MC :大学の先生として、科学の面白さを伝えるライターとしても活動されてらっしゃいまして、
幻冬舎新書から「理系あるある」という本も出されてるんですが、
先週ドップラー効果のお話だけで終わっちゃったんですけど、この本の中にね、
あるあるっていうので、4桁の数字を見ると10を作りたくなるって、
ゲスト:ありますよね。
MC :僕ね、子供の頃っていうか、今、もう、さあ、PASMOとかSuicaになっちゃって、
ゲスト:はい、はい、はい。
MC :切符を手にしないじゃないですか。
ゲスト:ああ、はい、はい、はい、はい。
MC :で、今、切符買うと4桁の数字載ってるんですよ。
ゲスト:ああ。
MC :4682とか。
ゲスト:はい、はい、はい、はい。
MC :で、4桁の数字見ると、10、10を作りたくなるって、今、キッズ達ないから、こういうのって
ゲスト:あっはっは。じゃ、ちょっと失われてしまった楽しみですね。
MC :ええー。小谷さんやった?ですか?やっぱり。
ゲスト:いやー、もちろん夢中になってやりましたよ。
MC :な、何でやりたくなるんですかね、これ。
ゲスト:まあ、人間の習性ですかね?
MC :習性ですか?えーへへ。これ、やりたくなる子は、きっと、科学とかね、
算数、物理とか色んなジャンルで伸びると思うんですけど
ゲスト:いや、それは、それはどうですかね。
MC :えー。
ゲスト:そういう
MC :頭の回転速くなると思うんですけど。
ゲスト:ん、あの、まあ、やることは是非お勧めしますけれども、しかし、
MC :あー、
ゲスト:それで役に立つかどうかは、ちょっと、私自信が
MC :え、絶対立ちますよ。
ゲスト:ないんですよ。
MC :あとね、車内広告の数学パズルについ、集中しちゃうって。
ゲスト:ありますよね。
MC :ありますよね。
ゲスト:いやー、難しいのありますよ。あれ。
MC :はい。
ゲスト:こ、こんなの小学生解けるのかなって問題あります。
MC :えー。
ゲスト:尊敬しちゃいます、あれ。
MC :ああいうのもね、ついつい僕もだから、だって、例えば山手線で僕、よく品川から新宿まで乗るんだけど
ゲスト:あー。
MC :だいたい18分ぐらいかかるんだけど、たまに長く感じる。
ゲスト:ああ。
MC :でも、車内にたまにね、あの、今なんか塾の広告とか見るわけですよ。
ゲスト:ふんふん、ありますよね。
MC :ふふふふ。クイズあると、や、は、あっという間に新宿着いちゃって
ゲスト:あははは。
MC :あれ?なんて、ちょっと高田馬場まで行っちゃおうかみたいな、
ゲスト:あははは。もうちょっとで解けるのにみたいな
MC :はい。
ゲスト:はははは。
MC :あと、意外に星座を知らない。
ゲスト:あ、これはちょっと痛いな。いや、あの、もちろん、あの、えーと、これはあの僕は専門が
MC :はい。
ゲスト:宇宙なんですけども
MC :はい。
ゲスト:あの、宇宙関係の研究者は、
MC :はい。
ゲスト:意外に星座知らない人がいるんですよ。
MC :そうなんですか?
ゲスト:そうなんですよ。
MC :なんでですか?
ゲスト:いや、それは例えば、あの、もちろん、あの望遠鏡で、その、空を見るのが大好きとかですね、
MC :はい。
ゲスト:暇さえあれば、空を見上げてるっていう人もいらっしゃるんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:そうではなくて、今の観測装置っていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:例えば人工衛星を使っていたり、
MC :はい。
ゲスト:すると、そうすると、仕事はですね望遠鏡を覗くことではなくて、
MC :ええ。
ゲスト:それでもって、コンピューターの前で、その計算をしたりすることだったりするんですよ。
MC :ああー。いわゆる何座の何とかって関係ないってことですか。
ゲスト:そうなんですよ。
MC :ああ。
ゲスト:で、人工衛星ってのは、夜も昼も関係なく観測できるし、
MC :はい。
ゲスト:地球の裏側にいても観測できますよね?
MC :はい。
ゲスト:で、例えば、その、人工衛星が新しい星を検出したってなことがあったりすると
MC :はい。
ゲスト:そうすると、みんな喜ぶんですけども、いざ、その星がどっちの方角にあるんだってなると、
ちょっと、うっ、と一瞬詰まっちゃったりすることがあるんですけど
MC :えー。
ゲスト:はは。
MC :そう、そんなもんですか。
ゲスト:そうなんですよ。
MC :へー。何でも知ってると思いきや
ゲスト:いや、そんなことなくてですね、ですから、その星座が一番聞かれるのっていうのはま、
MC :ええ。
ゲスト:例えば、その、新しい星を発見しました、というような、その、発表があったとして、
MC :はい。
ゲスト:そうすると、記者さんに聞かれることが多いんですよ。
MC :はい。
ゲスト:あの、その星は何座にありますか?
MC :はい。
ゲスト:そこで、ちょっと困っちゃったりするわけですよ。
MC :ああー。
ゲスト:はは。
MC :なるほどね。
ゲスト:で、そういうことがないように、普通は予め、その、予習して
MC :へえ。
ゲスト:記者会見とか
MC :へえええ。ああ、あと、測定誤差にこだわる。
ゲスト:ああ、ありますよね。
MC :はははは。いるよね細かい人。
ゲスト:ははは。
MC :ラクダは一度に134リットル水を飲むという豆知識を聞いたら、沢山飲むなあ、
というのが一般的な考え方なんだけれど、すごくこだわる。やっぱそういうもんですか。
ゲスト:いやー、この、やっぱ、この、その有効数字は何桁なの?って聞きたくなりますよ。
MC :あはは、そうですか。
ゲスト:ええ。
MC :あははは。でも、ラクダ、134リットル一度に水飲めるんですか?
ゲスト:いや、それはあの、僕がうろ覚えの豆知識なんですよ。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:ほんとなのか分かりませんが。
MC :たいしたもんだけどね、100
ゲスト:100リットルぐらい飲めるみたいですよ。
MC :一気に?
ゲスト:はい。
MC :それ、だからスタミナというか、水飲まなくて済むんですよね?
ゲスト:たぶんそうなんですけども、
MC :あと、そう、もう、ちょっと夏終わっちゃうけど、液体窒素でバナナを凍らせる、
ゲスト:あ、
MC :こういう実験参加したキッズいっぱいいると思うんですけど、あれは定番ですよね、液体窒素の
ゲスト:液体窒素は、あの、人気のある実験道具ですよね。
MC :はい。
ゲスト:あれは、実は役に立つんですよね。
MC :はい。
ゲスト:あのー、と、実験とか研究なんかでも使いますけども、例えば食品工場なんかでも使われてるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、その、食べ物を冷凍すると、そうすると、ま、家庭で冷凍すると味が変わっちゃいますよね。
MC :はい。
ゲスト:味が変わるのってのは、実は、その、細胞の中に氷の結晶が出来ちゃって、
MC :うん。
ゲスト:細胞が壊れちゃうっていうのが、あるらしいんですよ。
MC :凍らせると。
ゲスト:はい。
MC :肉なんかも。
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:だけど、あの、液体窒素を使って急速冷凍すると、氷の結晶が大きくならないので、
細胞が壊れなくて、で、味も変わらない、というようないい点があるらしいんですよ。
MC :ほー。
ゲスト:まあの、液体窒素だけじゃなくて、ドライ窒素とか冷凍機の大がかりなやつを使うってことも
もちろんあるんですけど、えー、液体窒素はそういうふうに、あの、役立ってると。
MC :え、えー、結構旅行行くと、僕冷凍ミカン必ず買うんですけど、
ゲスト:ああ、はい、はい、はい、はい。
MC :駅でね。
ゲスト:はい。
MC :で、冷凍ミカンて冷凍じゃないですか。
ゲスト:はいはいはい。
MC :じゃ、液体窒素で凍らせたミカンと冷凍ミカンは違うんですかね?
ゲスト:あ、それは違うと思いますよ。何かっていうと
MC :そっかー。
ゲスト:固さが違うと思いますね。
MC :カチカチになってるってことか。
ゲスト:はい。たぶん、あの、液体窒素で凍らせた冷凍ミカンは、釘が打てると思います。
MC :ああ、そうかそうか。カチカチで食べられないし、
ゲスト:はい。
MC :でも、冷凍ミカンて、こお、こおっ、凍ってカチカチに凍って解けていく過程の
シャリシャリ感を楽しむものじゃないですか。
ゲスト:ありますよね。はい。
MC :じゃ、液体窒素で一旦カチカチにした物って、あの、元に戻る、常温に戻るまでの間、
どんな食感になるんですかね?
ゲスト:いや、あの、それも試さない方がいいと思いますよ。
MC :あ、そうなんですか、危ないですか。
ゲスト:液体窒素温度のものを口に入れたら、やっぱ、凍傷になりますよ。
MC :あれ、でも、液体窒素バナナ入れると、バナナは元に戻したら、バナナの風味は、
の、残ってるってことですよね
ゲスト:はい、あの、完全に戻してから、食べて下さいね。
MC :そうですよね。
ゲスト:はい。
MC :で、冷凍バナナは、あんまり聞かないじゃないですか。
ゲスト:ああ、確かに。
MC :だ、冷凍バナナおいしくないからたぶんやらないんですよね?
ゲスト:いや、それはわからないですね、なぜだろう。
MC :だって、れい、みんなの家でさ、バナナを冷凍してる家ある?
ミカンは冷凍するけど、バナナあんまり凍らせないですよね。
ゲスト:バナナは熱帯の食べ物ですからね。
MC :うーん。
ゲスト:凍らせるとおいしくないかもしれませんね。
MC :そういう、何か空気で、パインは凍らせると思うんだよね。冷凍パイン。
ゲスト:やったことないです。
MC :ないですか?
ゲスト:ないです。
MC :えっ、大村家ある。
ゲスト:ああ、そうなんですか。
MC :えっ、えっ。僕ねあと、桃は凍らせないですね。
ゲスト:あれは、食感を楽しむものですよね。
MC :ええ。ゼリーは凍らせる派、冷やす派どっちですか?
ゲスト:あれ、ゼリーは、だって凍らせたら凶器じゃないですか。あんなもの。
MC :僕、ゼリーは凍らせる派。
ゲスト:えっへへ、怪我しちゃいますよ。
MC :ゼ、ゼリーは凍らせるなあ。ああー。いやいやいや、いいですね。
ゲスト:いや、液体窒素っていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:その、例えば、あの、あの、食べ物なんかは、その、凍る、
氷が出来る温度で保存しても、液体窒素温度でしても、その
MC :はい。
ゲスト:味が変わる程度ですけど、あの、液体窒素温度じゃないと保存できないってものも、
やっぱりあるんですよ。
MC :え、例えば何ですか?
ゲスト:例えば、医学的な資料とかですね、あのー、
MC :あーー。
ゲスト:細胞を凍らして保存する。
MC :はいはい。
ゲスト:これは、あの、ちゃんとその保存条件さえよければ、
MC :はい。
ゲスト:あとで、解凍した時にちゃんと細胞を生き返らせることができるんですよ。
MC :うーん。
ゲスト:それから、例えばその、えーと、僕の専門の、に、近い話ですけども
MC :はい。
ゲスト:ある種の放射線検出装置っていうのも
MC :はい。
ゲスト:やっぱり液体窒素温度で保存しないといけないんですね。
MC :あー。なるほどね。
ゲスト:これ、保存、あの、使わない時でも冷やしておかないと
MC :はい。
ゲスト:一旦常温にすると、あの、性能が悪くなっちゃうんですよ。
MC :はい。
ゲスト:そういうことがありますね。
MC :はい。
ゲスト:で、そういう理由があるから、その、研究室とか、それからまあ、
大学とかでは液体窒素は結構、おもちゃにされてますね。
MC :確かに。液体窒素の実験面白いですもんね。
ゲスト:いやー、僕も遊びましたよ。んふふふ。
MC :あらー、でも、こ、あの、先月ねクマムシの専門家の先生が来られて、
ゲスト:ああ、ああ。
MC :クマムシってのは、実は乾燥してても生きてるんだと、生き返るんだっていうんです。
ゲスト:あー、そうなんですか。
MC :はい。あのー、乾燥期は、あ、ただ眠っている、乾眠といって眠ってるだけで、
ゲスト:はあはあ。
MC :水をたらしてやるとクマムシってのは、動き出すんですって。足が
ゲスト:ほー。
MC :だから、液体窒素は人工的に保存しなくちゃいけないじゃないですか。
ゲスト:はいはい。
MC :クマムシは、干からびた状態で保存できるって、#
ゲスト:はははは。楽ですね。
MC :そうなんですよ。
ゲスト:ははは。
MC :ちょっとそういうのコラボして、ちょっと、ますます、ちょっと、科学の発展で、
考えていこうじゃありませんか。
ゲスト:いや、ミカンもバナナも乾燥して保存した方が楽ですね。
MC :そうなんですよ。
ゲスト:ははは。
MC :いやー、ちょっと、色々あるある、あるものですね。もう時間ですか?
いやいや。また是非遊び来て下さい。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :今週の「サイコー」はサイエンスライターの小谷太郎さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「理系あるある パート1」 ゲスト:小谷太郎さん
2019/01/01 Tue 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は
サイエンスライターの小谷太郎さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。よろしくお願いします。
MC :小谷さんは大村さんと同じ、67年生まれ。東京に生まれて東京大学理学部を卒業して、
これ大村さんと違いますね。はい。東京大学を卒業後、理化学研究所を経られて、
えー、アメリカのNASAゴダート宇宙飛行センターにいらっしゃった。
これなんですか?宇宙飛行センターって。
ゲスト:あ、これは、あの、別に宇宙飛行の研究だけをしている訳じゃなくて、
MC :ええ。
ゲスト:一つの広いキャンパスなんですけど、
MC :ええ。
ゲスト:そこにいろんな研究室があって
MC :うん。
ゲスト:いろんなことやってます。
MC :NASAにいらしたってこと。
ゲスト:あ、そうです、あの、NASAは大変広い大きな研究施設ですから、
MC :ええ。
ゲスト:あの、まあ、別にその、アメリカで、天文の研究したり、宇宙の研究してる人ってのは
MC :ええ。
ゲスト:かなりのパーセンテージがNASAなんですよ。
MC :へえー。ああ、そうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :で、え、その後日本に戻られて、大学の先生と、さ、としてですね、
科学の面白さを伝えてらっしゃると。
あと、ライターとして、これ、幻冬舎新書から「理系あるある」という本も出版されてます。
ゲスト:おかげさまで。
MC :ええ。この「理系あるある」、あのー、これ科学番組9年やってると、
あるよねっていうの結構書いてあるんですよ。
ゲスト:はははは。そうですか。
MC :た、例えば、例えばね、あのー、そうですね、そうそう。
救急車のサイレンを聞いてドップラー効果!っていうの
ゲスト:あー、はい、はい、はい、はい。
MC :いう、言いますよね。
ゲスト:あ、いいます
MC :あっ、ドップラー効果!
ゲスト:あは、言いますよね。
MC :うん。
ゲスト:知らない人キョトンとするんですけどね。
MC :そう、でも
ゲスト:はい。
MC :やっぱり、この、9年ねサイエンスキッズやってると、おー、ドップラー効果!って絶対いう訳ですよ。
ゲスト:あははは。
MC :ほほほ。これに関してドップラー効果ちょっと詳しく伺っていきたい。
ゲスト:いや、あの、えーと、救急車のサイレンのお話からした方がいいですよね。
MC :はい。
ゲスト:救急車サイレン皆さんご存知ですよね。
MC :ええ。
ゲスト:あの、ピーポーピーポーってやつ。
MC :はい。
ゲスト:あの、あの音ってあの、えっと、ピアノの何の音だかご存知です?
MC :ええっ。
ゲスト:あれ、あれはですね、
MC :うん。
ゲスト:「シ」と「ソ」なんですよ。
MC :シーソーシーソー
ゲスト:そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。
MC :シーソー?
ゲスト:あははは。
MC :えーっ。
ゲスト:で、だけどあれは近づいてくると、えー、遠ざかる時に音が変わるのって
MC :変わる。
ゲスト:変わりますよね。
MC :はい。
ゲスト:あれ、不思議ですよね。
MC :はい。
ゲスト:あれ、実は名前が付いていて、
MC :ええ。
ゲスト:ドップラー効果っていうんですよね。
MC :そうですよね。
ゲスト:はい。
MC :で、僕らはドップラー効果だって言って、喜んでますよね。電車で踏切通過する時も
ゲスト:そう、そう、そう、そう、そう。
MC :キンキン、カンカンで、ドップラー効果でギョンガンガンカン
ゲスト:あははは。
MC :て、なるんですよね。
ゲスト:うまいですね。
MC :ええ。
ゲスト:はは。ドップラーっていうのは、
MC :はい。
ゲスト:人の名前なんですね。
MC :えっ、そうなんですか。
ゲスト:はい。ヨハン・クリスチャン・ドップラーっていう
MC :へえー。
ゲスト:200年ぐらい前にいた、あの、学者さんなんですよ。
MC :ええ。
ゲスト:で、この人がですね、あの、当時、その発明されたばっかりの
MC :はい。
ゲスト:汽車で、それでもってその、汽車に楽器を乗せると
MC :はい。
ゲスト:音が変わるって事を研究したんですよ。
MC :へえー。その通過する時の音が変わるってこと?
ゲスト:はい。あの、当時は蒸気機関車で、
MC :へー。
ゲスト:速度も今みたいに速くないんですけど、
MC :はい。
ゲスト:そこに楽器を乗せてですね、あっこれ、実験したのは、これ、
ドップラーさん本人でなくて別の人なんですけど、
MC :はい。
ゲスト:で、その、ちょうどその「ソ」の音をですね、楽器で出してもらって、で、走らせると。
MC :はい。
ゲスト:で、それを地上にですね、ま、絶対音感のある人に聞いてもらって
MC :はい。
ゲスト:で、この振動数、音の波長を記録して研究したみたいですね。
MC :シーソーシーソーって来るのを、
ゲスト:はい。
MC :絶対音感の人が、
ゲスト:はい。
MC :聞いたら、
ゲスト:はい。
MC :何になったんです?
ゲスト:それはですね、あの、その、半音上がって、
MC :ええ。
ゲスト:「ソ」のシャープになるんですよ。近付く時には
MC :「ソ」のシャープになるんですか?
ゲスト:はい。
MC :「ソ」のシャープと、「シ」は変わらないんですか?
ゲスト:「シ」は「シ」は変わるんですけども、あ、普通のやっぱり半音変わります。みな半音変わります。
MC :「シ」、「シ」のシャープと「ソ」のシャープ?
ゲスト:はい。
MC :へー。
ゲスト:で、遠ざかる時には、半音下がるんですね。逆に。
MC :ほー。で、その半音であんなに音違って聞こえるんですか?
ゲスト:いやー、あのー、それはそうなんですよ。あはは。人間の耳は
MC :へえ。
ゲスト:周波数に敏感ですからね。
MC :はー。
ゲスト:えーっと、音の正体っていうのは、これ、あの、空気の振動な訳ですよね。
MC :はい。
ゲスト:で、楽器が鳴らすと楽器が空気を震わせますと、
MC :はい。
ゲスト:その、空気の振動が伝わって来て、耳の鼓膜を震わせますと。
MC :はい。
ゲスト:そうすると、あ、サイレンが鳴ってるなとか、列車が汽笛鳴らしてるなとか分かる訳ですよね。
MC :はい。
ゲスト:で、例えば、「ソ」の音っていうのは、1秒間にこれがあの、392回振動するんですよ。
MC :えーっ。み、鼓膜がですか?
ゲスト:はい。そうなんですよ。
MC :鼓膜が1秒間に392回振動って決まってるんですか?
ゲスト:はい。そうなんですよ。そう、
MC :え。みんな?
ゲスト:あ、はい、そうすると我々は、あ、「ソ」の音が聞こえたなって思うんです。
MC :いやー、すごい。えっ。知らない。
ゲスト:はははは。
MC :えっ。ピアノの、「ソ」、「ソ」をやると392回っていうのが「ソ」の音。
ゲスト:そうなんです。
MC :それは、あのー、高い「ソ」も低い「ソ」も
ゲスト:はい。
MC :同じなんですか。
ゲスト:それは、中間の「ソ」の音。
MC :中間の「ソ」
ゲスト:あの、救急車で使われてる「ソ」の音。
MC :おー、はい、はい。
ゲスト:はい。
MC :へ、じゃあ、392回って決まってる。
ゲスト:はい。
MC :救急車の「ソ」は、1秒間に392回
ゲスト:はい。そうなんですよ。ま、シャレを言ってるみたいですけど、そうなんですよ。
MC :はい。そうなんです。
ゲスト:はは。
MC :え、「シ」は?
ゲスト:で、それでですね、あの、ま、「シ」の音は飛ばしてですね、
MC :はい。
ゲスト:「ソ」の話を続けます。
MC :はい。
ゲスト:ところが、これ、近づいて来る時には、そうすると、あの、音を出すものが動いてると
MC :はい。
ゲスト:振動数が、変わって聞こえる。
MC :はい。
ゲスト:近づいて来る時には、高く聞こえて、
MC :はい。
ゲスト:で、これが415回なんです。
MC :えっ、え、ちょっと待って。てことは何、23回増えるってことですか?
ゲスト:あー、そうなんですよ。はは。
MC :振動数が?
ゲスト:はい。
MC :近づいて来ると、392回の「ソ」の音が415回に振動数増える。
ゲスト:これは、あの、あの、72キロメートル、時速72キロメートルで、走ってると考えた時の話です。
MC :救急車がもし、ゆっくり通過したら、ドップラー効果来ませんよね。
ゲスト:あー、そう、その通りですね。
MC :はい。
ゲスト:あの、音の、あの、動く物の
MC :うん。
ゲスト:速度によってドップラー効果は、大きさが変わるんですね。
MC :なるほど。
ゲスト:はい。
MC :時速何キロ以上で通過したときに、ドップラー効果が現れるんですか?
ゲスト:いや、それはあの、ほんのわずかな動きでも、ドップラー効果はあるんだけど、
我々の鼓膜には分からないですね。
MC :へー。じゃ、ある程度一定の速度で走ってないと、
顕著なドップラー効果を感じることはないってことですね。
ゲスト:はい。
MC :ふーん。
ゲスト:で、この、実は、その、速度の最大っていうのがあって、あの、ドップラー効果がもう、
そこでお仕舞っていうような高い速度もあるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:それは、実は、音速なんですね。
MC :F1。
ゲスト:あはははは。
MC :ヴィーィョン。
ゲスト:はは。そう、だいぶ近いです、それ、音速に。
MC :はい。
ゲスト:で、もしも物が、楽器が音の速度で近づいて来ると、
MC :はい。
ゲスト:そうなると、楽器と音が同時に耳に届いちゃうんで、
MC :あ、
ゲスト:うん。
MC :ドップラー効果は現れないと。
ゲスト:ドップラー効果そこでお仕舞なんですよ。
MC :ほー。
ゲスト:そこまでしか、ドップラー効果は計算出来ないんですね。
MC :へー。音速って時速300
ゲスト:あ、それ時速330メートル
MC :330。
ゲスト:約、時速1000キロメートルです。
MC :秒速330メーター
ゲスト:ああ、そうですね。
MC :ですね。
ゲスト:はい。
MC :時速1000キロ
ゲスト:はい。
MC :こうなると
ゲスト:はい。
MC :ドップラー効果はもう消滅するんですね。
ゲスト:はい。
MC :低速に関しては、
ゲスト:これはもう、いくらでも
MC :ありそうですね。
ゲスト:まあ、聞き取れないですけどね。
MC :へーー。ここの僕ら、今ラボにね、マイクあるけれど、
ゲスト:はい。
MC :マイクで救急車の音を拾うと、ドップラー効果はどうなるんですか。
ゲスト:出ますよ。あの、
MC :出る。
ゲスト:はい。出ます。人間の耳と同じように振動数高くなったってことが分かりますよ。
MC :ほー。
ゲスト:ま、
MC :すごいなー。
ゲスト:あ、実はあの、機械の方がドップラー効果には敏感で
MC :うん。
ゲスト:で、それを利用した機械が沢山あるんですね。
MC :うん、うん。
ゲスト:え、例えばですね、その、えっと、エコー治療器、エコー診断機というのがあって、
MC :お腹とかのエコー
ゲスト:はい。そう、あの、エコーをかけると、体の中で反射して戻って来て、
それを機械で拾って、体の中の、えー、ことが分かると。
MC :おー。
ゲスト:あれにですね、ドップラー効果を聞き取る装置を組み合わせると、
そうすると、すごく色んなことが分かるんですよ。
MC :あのー、よく、あの、赤ちゃんのね、エコー取ったり
ゲスト:あ、そう、そう、そう、そう、そう、そう。
MC :お母さんが
ゲスト:おー。その、普通の、ただのエコーだと
MC :ええ。
ゲスト:赤ちゃんの写真が、体の中、お腹の中の赤ちゃんの写真がとれますよね。
MC :ええ。
ゲスト:ところが、それにドップラー効果を付けると、
MC :はい。
ゲスト:そうすると、赤ちゃんの血液の動きが分かっちゃうんですよ。
MC :血の流れが出るんですか?
ゲスト:それは、あの、な、こっちに向かって流れてる血と、
に、反射されて戻って来た音ってのは振動数が変わってるんですね。
MC :え、行きと返りで
ゲスト:はい。
MC :振動数が違うんですか。
ゲスト:はい。そうなんですよ。
MC :そういうのも、ドップラー効果って言うんですか?
ゲスト:それも、ドップラー効果なんですよ。
MC :へー。
ゲスト:救急車のサイレンが近づいて遠ざかってくと、あ、ドップラー効果だっと思うけど、
MC :ええ。
ゲスト:実はこれ、結構、その、色んな科学に応用されてるんですよ。
MC :ほー。
ゲスト:ふふ。
MC :へー。いやいやいや。先行こう。えっ。もう終わっちゃった?
ゲスト:んふふ。
MC :ちょっと待って。ドップラー効果だけで終わっちゃったじゃないすか。
ゲスト:ふふ。
MC :いや、ちょっとありがとうございました。
ゲスト:へへ。
MC :さあ、来週もお願いしようと思います。あっという間に時間が来てしまいました。
今週の「サイコー」はサイエンスライターの小谷太郎さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございます。 -
「首都高速の科学 パート2」 ゲスト:川辺謙一さん
2018/12/01 Sat 12:00 カテゴリ:乗り物MC :今週のサイコーも前回に続きまして交通技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは
ゲスト:こんにちは
MC :よろしくお願いします
ゲスト:はい、よろしくお願いします
MC :えー、首都高速、さまざまな
ゲスト:はい
MC :科学が含まれていると伺いましたけれど、
ゲスト:はい
MC :今、ゴールデンウィークになってくると、渋滞が気になりますよね
ゲスト:そうですね
MC :ひとときの、たぶん、あのー、地獄みたいな渋滞って少なくなったと思うんですけれど
ゲスト:そうですね
MC :あれ、たぶん渋滞予測とか
ゲスト:はい
MC :渋滞のリアルタイム予報とか
ゲスト:はい
MC :ドライバーも今、スマホなんかで、こうね、みんなでこう、確認できるようになったから
ゲスト:ええ、ええ、なってますね
MC :回避しようとか
ゲスト:はい
MC :いろんな意識がたぶんあるんでしょうね
ゲスト:はい
MC :そもそも、あー、でも、あー、渋滞のね
ゲスト:はい
MC :あの、今何キロっていうのは
ゲスト:はい
MC :何をもって何キロって、どうやってはかってるんですか
ゲスト:あっ、あれはですね
MC :ええ
ゲスト:ええ~、各箇所で
MC :ええ
ゲスト:通る車のですね、スピードと台数をチェックしてるんですね。
そういう計測する機械があるんですね
MC :あのね、高速を走ってると
ゲスト:ええ
MC :全部警察の設備だと思ってびびりながら
ゲスト:ははは
MC :走っちゃってるんだけど
ゲスト:ははは、まぁ、それね一部もありますよ
MC :一部もね、その、その通過する
ゲスト:はい
MC :のを、確認する機械っていうのは具体的に
ゲスト:ええ
MC :どんな形でどんな
ゲスト:ええ、それは名前がですね
MC :ええ
ゲスト:車輌感知器という名前がついてまして
MC :車輌感知器
ゲスト:はい、で、首都高を、あの、走ってるとですね、その道路の両側にですね、
お椀のような白ーい、あの、ものがですね、二つペアで並んでいるのを
MC :うん
ゲスト:が、あるんです
MC :空、空中にありますよ
ゲスト:そうです、空中にあります、それです
MC :うんうん
ゲスト:あれは実は超音波を出して
MC :はい
ゲスト:車をですね、通過を計ってるんです、してるかどうか計ってるんです
MC :あー、白いやつですよね
ゲスト:そうです、そうです
MC :聴診器のあれみたいな
ゲスト:そうです、聴診器の形をしてて、あそこから超音波を出して
MC :ふーん
ゲスト:で、それが車に跳ね返ると、丁度、返ってくるので
MC :あれ、壁にあるものもあれば
ゲスト:はい
MC :上の方にあるものもないですか
ゲスト:そうです、だから場所はいろんな所にあるんですが
MC :あー
ゲスト:結果的にやってることは、そこに車が通ってるか
MC :あっ
ゲスト:どれぐらいのスピードで通ってるか
MC :ええ
ゲスト:どれぐらいの頻度で通ってるか
MC :あっ
ゲスト:というのを、あれで見てるんですね
MC :あっ、あれがそういう機械なんですか
ゲスト:そうなんですよ
MC :けっこうありますね、そうしたら
ゲスト:ええ、かなりの、あのう、場所によっても違いますけども
MC :ええ
ゲスト:かなりの、あのう、そうですね、間隔としては
MC :ええ
ゲスト:えー、300メートルから600メートル間隔
MC :あっ
ゲスト:ですね
MC :へえー、あっ、じゃあ大体わかりますね
ゲスト:ええ
MC :ドライバーの方もきっと、あぁこれかぁって、あれで何をもっての渋滞ってなるんですか
ゲスト:あっ、あれですね、その平均速度ですね、
MC :ええ、はい
ゲスト:車が流れている、流れている車の平均速度が20キロ、時速20キロを下まわったら渋滞と
MC :はい
ゲスト:みるわけですね
MC :はあ
ゲスト:で、その区間がどれだけの区間あるかというので、ここ、大体約2キロ渋滞してるとか
MC :はい
ゲスト:約5キロ渋滞してるとか
MC :はい
ゲスト:そういうことを、ええ、まあ、計算してですね、掲示板に出したりとか
MC :はあ
ゲスト:またインターネットを通じてスマートホンだとかパソコンで報告してると
MC :はあ
ゲスト:いうようなですね
MC :渋滞でもね、
ゲスト:はい
MC :あのう、首都高速の電光掲示板見ると
ゲスト:はい
MC :赤くなるのとオレンジ色があるじゃないですか
ゲスト:ありますね
MC :あれは、どういう違いですかね
ゲスト:ええ、赤がですね、渋滞ですね時速20キロ以下
MC :あっ、20キロ以下はもう全部赤
ゲスト:赤、で、
MC :ええ
ゲスト:オレンジのやつは混雑ってことで
MC :おお、
ゲスト:時速40キロ以下
MC :ははあ
ゲスト:これが混雑
MC :へえ
ゲスト:だから二段階で
MC :はい
ゲスト:通常、あのう、順調に流れている時と
MC :はい
ゲスト:混雑と渋滞
MC :はあ
ゲスト:三段階で表示してるんです
MC :なるほど、わかりました、じゃ、赤いのはもう、赤いのはがっちがちに動かないのかなって思うけれど
ゲスト:ええ
MC :実は20キロ以下ってことですね
ゲスト:そういうことですね
MC :だからケースバイケースで緩やかに動いている赤もあれば
ゲスト:はい
MC :完全に止まっちゃってる赤もある
ゲスト:そうですね、だから事故がおきてもう全然動かないっていう場合もありますし
MC :はあ
ゲスト:ええ、ただ単に流れが悪くなって
MC :はい
ゲスト:ゆっくり走っている場合もあります
MC :なるほど、そうかそうか、バツがあるとちょっと気を付けようってなりますよね
ゲスト:ああ、バツは事故ですね
MC :ですもんね
ゲスト:ええ、ええ
MC :バツに伴う赤い帯が出たら
ゲスト:はい
MC :これちょっと動かないなぁとか、そういうふうに予測した方がいいかもしれない
ゲスト:そうですね
MC :はあ
ゲスト:で、今はその掲示板でもですね、今渋滞の距離が長くなっている
MC :はい
ゲスト:短くなっているっていうのを表示している
MC :へぇ
ゲスト:のが、三角形のマークがついてまして
MC :へえ
ゲスト:それが三角形が右に、右上がりであれば今渋滞が延びてるよ
MC :へぇ
ゲスト:右下がりであれば渋滞がだんだん緩和されつつあるよっていうのを表示しているですよ
MC :それ、それ知らなかったです
ゲスト:あっそうですか
MC :へえ
ゲスト:ええ、そういうのも表示しているんです
MC :あっ、渋滞増加傾向か、
ゲスト:はい
MC :あのう、減少傾向かっていう
ゲスト:そうです、だから時間がこれから、あのう、今渋滞にはまってしまったけど、
これから渋滞で時間が延びるのか、縮むのか
MC :はあ
ゲスト:で、それを見て、あっやっぱり途中で降りようかなとか
MC :はい
ゲスト:判断する方もいらっしゃると思うんですね
MC :なるほど、あっ、首都高速っていうと、あのう、
僕は、たぶん東京で一番高速に乗ってて気持ちいいなと思うのはレインボーブリッジを渡る時なんですよ
ゲスト:ああ、あれは気持いいですね
MC :これねぇ、どっち方向でも気持いいんですよ
ゲスト:気持ちいいですね
MC :ですよね
ゲスト:ですね、あれは何回でも行きたいですね
MC :ああ、そうですか
ゲスト:ええ、ええ
MC :ああ、うれしいな
ゲスト:ええ
MC :あの橋はやっぱり独特ですね
ゲスト:そうですね
MC :うーん、レインボーブリッジに何か秘密はありますか、科学は
ゲスト:で、あのレインボーブリッジは、まぁ、その都市部とですね、えー、臨海部を結ぶ橋なんですけども
MC :ええ
ゲスト:ちょっと変わった、あのう、橋なんですね
MC :はい
ゲスト:で、単にですね、その陸地とその埋め立て地を結ぶだけではなくて、
真下がですね、ええ、東京港、港の航路になってるんです
MC :たしかに
ゲスト:ええ、で、船が通るんです
MC :はい
ゲスト:で、船っていっても大型客船といっても背の高い客船ありますよね
MC :はい
ゲスト:あれが通過できるようにですね、下に、あの、50メートル以上空間があけてあるんですね
MC :あっ、レインボーブリッジはけっこう高い所に、じゃあ
ゲスト:そうですね
MC :橋を渡しているってことですね
ゲスト:そうです
MC :ふうん
ゲスト:ですからお台場だとか
MC :ふうん
ゲスト:えー、芝浦の方から行くとものすごい坂、登りますよね、長ーい時間かけて
MC :たしかに、はい
ゲスト:で、ちょうど、こう、ええ、橋の真ん中のあたりで、あのう、一番高い所を迎えますけど
MC :おお、はいはい
ゲスト:ちょうどあの一番高いところが、真下が航路なんです
MC :50メートル
ゲスト:50メートル以上
MC :高さをとってるってことですね
ゲスト:はい
MC :下、一般道を走ったり、ゆりかもめ走ってるから
ゲスト:ええ、
MC :あのう高速のレインボーブリッジは、じゃ、もう60メートルぐらいの高さ
ゲスト:そうですね
MC :あるかもしれない
ゲスト:あのう、首都高の台場線っていうんですけども
MC :はい
ゲスト:あそこは、台場線の路面に関しては60メートル以上になってますね
MC :ああ、そうですか
ゲスト:ええ
MC :あれは吊り橋なんですよね
ゲスト:そうですね
MC :レインボーブリッジは
ゲスト:はい
MC :珍しいですか、高速で吊り橋っていうのは
ゲスト:あのう、高速道路で吊り橋はですね、まあ、ええ、たとえば瀬戸大橋とかもありますから
MC :ああ
ゲスト:特別は珍しくないんですけども
MC :はい
ゲスト:あのう、あえて珍しいといえばですね
MC :はい
ゲスト:高さが低いということなんです
MC :あっ、えっ、吊り橋にしては高さが低い
ゲスト:高さが、そうなんです、高さが低くて
MC :ええ
ゲスト:ええ、まぁ、同じようなもので、あのう横浜ベイブリッジに斜張橋っていうものがあるんですども
MC :はい
ゲスト:それよりもですね、低いんですね、タワーの部分が
MC :ほお
ゲスト:で、それはなぜかというとですね
MC :はい
ゲスト:羽田空港が近いから
MC :あっ
ゲスト:はい
MC :ああ、いわゆる道路の高さじゃなくて
ゲスト:はい
MC :吊り橋の支柱の高さが低いってこと
ゲスト:そうです、そういうことです
MC :あっ、へぇ、それは羽田空港があるからあまり高くしちゃいけない
ゲスト:そうなんです、あの羽田空港の滑走路のですね
MC :はい
ゲスト:延長線上には、ではですね、高さ、建物の高さが制限されているんですね
MC :へぇ
ゲスト:なので、あまり高くできない、そのタワーの、あのう、搭の部分は
MC :はい
ゲスト:搭は高くできないけど、下の、ええ、船は通れるようにしなくちゃいけないということで、非常に難しい
MC :あ、かなりハイテクな、じゃあ
ゲスト:そうなんです
MC :技術が
ゲスト:そうなんです
MC :23年前でしたかね
ゲスト:そうなんです
MC :デビューしたのが
ゲスト:ええ、ええ
MC :はぁ、えっ、ちなみにあの高さ何メートルですか、レインボーブリッジの支柱の
ゲスト:ええ、支柱の高さはですね126メートルでして
MC :あっ、126メートル
ゲスト:で、東京、あっじゃない、横浜ベイブリッジに関しては175メートルなんで
MC :あっ、じゃ50メートル低い
ゲスト:そうです、50メートル近く低いんですね
MC :低いけれど
ゲスト:ええ
MC :しっかりとつっぱって
ゲスト:はい
MC :あの豪華クルーズ船も往来できるうような
ゲスト:そうなんです
MC :高さまで
ゲスト:はい、そういうことですね
MC :相当の、じゃあ技術を使って
ゲスト:はい
MC :できているわけなんですね
ゲスト:そうなんですね
MC :へぇえ
ゲスト:吊り橋としては変わった特殊な構造ですよね
MC :ああ、そうですか
ゲスト:はい
MC :へぇえ、いやでも首都高速も、あのう、いいですね、こうやって話を聞くとね、あの、たぶん
ゲスト:ええ
MC :お父さんの世代になると首都高速、抜かしてぐるっと一周できるのって
ゲスト:ええ、ええ
MC :あのう、環状線しかなかった
ゲスト:そうですね、真ん中の都心環状線しかなかったですよね
MC :はい、で、あれをね、よく走りやなんかは何分で一周できるかなんてのが
ゲスト:ええ、ええ、
MC :漫画にも載ったりしてたじゃないですか
ゲスト:ありましたね、ええ、ええ
MC :それが今ね、中央環状とか
ゲスト:はい
MC :ぐるっと一周できると、あと外環道も
ゲスト:はい
MC :できたりすると
ゲスト:はい
MC :なんか、ドライブの楽しみって増えますよね
ゲスト:そうですね、で、まださらにその外側には圏央道っていうのを作ってますから
MC :あっ、圏央道
ゲスト:はい
MC :はーい
ゲスト:ですから、もう迂回ルートとかですね、
MC :はい
ゲスト:いろんなルートが通れるようになったので、それで、まぁ、首都高全体がですね、渋滞が減ってるんですね
MC :はい、なるほどね、まぁ、首都高も進化しながら、えー、渋滞も減って
ゲスト:はい
MC :利便性も高まって
ゲスト:はい
MC :あとは、事故だけ気をつけると
ゲスト:そうですね
MC :いうことですかね、はい、もう時間ですね、はい、じゃまた川辺さんぜひ遊びに来て下さい
ゲスト:はい
MC :今週のサイコーは交通技術ライターの川辺謙一さんでした。ありがとうございました
ゲスト:ありがとうございました -
「首都高速の科学 パート1」 ゲスト:川辺謙一さん
2018/12/01 Sat 12:00 カテゴリ:乗り物MC :今週のサイエンスコーチャー略してサイコーは久々のご登場です。
交通技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは
ゲスト:こんにちは
MC :川辺さんは去年の3月だったかな
ゲスト:はい
MC :北陸新幹線
ゲスト:はい
MC :が、開業したことを記念して
ゲスト:はい
MC :新幹線の科学を伺いしましたけれど
ゲスト:はい
MC :まっ、新幹線も僕、川辺さんの話を伺って
ゲスト:はい
MC :3回乗りに行ったの
ゲスト:ほう
MC :やっぱり、雪対策とか
ゲスト:そうですね
MC :あのう、騒音対策とか
ゲスト:そうですね、はい
MC :勉強になりました
ゲスト:はい
MC :今日は速い乗り物なんだけど、ちょっと新幹線よりもスピード落ちます
ゲスト:はい
MC :高速道路
ゲスト:はい
MC :うん、しかも首都高速
ゲスト:はい
MC :首都高速って
ゲスト:はい
MC :横浜も首都高速に入るんですか
ゲスト:そうですね、横浜も入りますし、あの、埼玉も入りますね
MC :ああ、全部で、東京、埼玉
ゲスト:はい
MC :神奈川
ゲスト:はい
MC :千葉は、ぎりぎりないか
ゲスト:んー、千葉は一部ありますね
MC :一部
ゲスト:はい
MC :じゃあ、1都3県におよぶ
ゲスト:はい
MC :高速
ゲスト:そうですね、首都圏にまたがる、ええ、高速道路と
MC :ほう、
ゲスト:で、一般的な高速道路というと
MC :はい
ゲスト:都市と都市を結ぶ、街と街を結ぶ高速道路というのが、まぁ、一般的に多くの方がイメージするものだと
MC :はい
ゲスト:思うんですね
MC :はい
ゲスト:たとえば、東京から名古屋まで結んでいる、東名高速道路とか、
MC :はい
ゲスト:そういうのを、ええ、イメージする方が多いと思うんですけども、首都高速というのは、街の中だけ
MC :うん
ゲスト:首都圏だけを走る
MC :うん
ゲスト:高速道路
MC :うん
ゲスト:なんですね
MC :あのう、くしくも4月から
ゲスト:はい
MC :料金が距離制になりまして
ゲスト:そのようですね、変わりましたね
MC :こりゃねぇ
ゲスト:ええ
MC :あの 乗り方次第では安くなるし
ゲスト:ええ、ええ、ええ
MC :今までどおりの、感覚でいると意外に高くなっちゃったり
ゲスト:そうですね
MC :するんですけど、あれ、全部で何キロぐらいあるんですか、首都高速の総延長
ゲスト:総延長はですね、あのもう、300キロ越えてまして
MC :えっ
ゲスト:ですから、さっき言いました東京から名古屋、東京から名古屋だと大体350キロぐらいなんですけども、
それよりちょっと短いぐらいの
MC :って、まぁ
ゲスト:ものが
MC :豊橋ぐらいまでいっちゃう感じですか
ゲスト:そうです、そういう感じです、ちょっと、そうですね。それぐらいのものが、
高速道路が、まぁ首都圏に、がっとあると
MC :そんな長いですか
ゲスト:ええ
MC :300キロ越え
ゲスト:全部合わせるとですけれどもですね
MC :へぇえ、ああ、ぐるっと一筆書きでいろいろね、まわってドライブ
ゲスト:ええ、ええ
MC :今もできるようになったじゃないですか
ゲスト:なりましたね
MC :遠回まわりしても料金同じって
ゲストあっ、そうですね、ええ、ええ
MC :その300キロ一筆でかけないですけどね
ゲスト:はい
MC :ただ全部で総延長は300キロ超える
ゲスト:はい
MC :ということですね
ゲスト:はい
MC :さぁ、この首都高に対してどんな科学が使われてるんでしょうか
ゲスト:はい、首都高にはいろんな工夫があるんですけれども
MC :はい
ゲスト:大きな工夫の一つとしてはですね、やはり騒音対策というのがあります
MC :うん
ゲスト:で、やはり車が、多くの車が通ってますから、音が発生するんですね、騒音がね
MC :はい
ゲスト:で、それが周りの沿線の、ええ、ビルだとか、建物、ええ、まぁ住宅とかに
MC :はい
ゲスト:えー、悪影響を及ぼしてしまう可能性があるので、音が広がらないようにする工夫がされています
MC :うん、言われてみるとあの、首都高の沿線って会社が多いので
ゲスト:はい
MC :そこの近くに住んでる人って意外に少ないかもしれないけれど
ゲスト:はい
MC :それでも音に対しての工夫はされてるんですか。
ゲスト:そうですね、あの、まぁ、オフィスビルも、もちろん多いですけども、
MC :ええ、
ゲスト:やはり、その住んでる、もともと住んでるらっしゃる方もたくさんいて
MC :はい
ゲスト:ええ、騒音っていうのは問題になりやすいんですね
MC :どこから音漏れる、横ですか、下ですか
ゲスト:特に横ですね
MC :横
ゲスト:ですので、横から音が漏れないようにするために
MC :はい
ゲスト:まぁ、遮音壁、音を遮る壁と書くんですけども
MC :はい
ゲスト:遮音壁というのを、ええ、道路の左右両側に付けて、音が広がるのを防いでいます
MC :たしかにありますね
ゲスト:ええ、ええ
MC :あるけれど、ないところもありますよね
ゲスト:そうですね、ないところもありますけども
MC :ええ
ゲスト:まぁ、特に問題が起きやすいところ
MC :はぁあ
ゲスト:に、まぁ、置いているわけですね
MC :あっ、じゃ、その遮音壁
ゲスト:はい
MC :あの、両方のちょっと灰色の壁ね
ゲスト:はい
MC :ちょっと薄汚れた壁がありますけれど
ゲスト:そうですね、なりますね
MC :あの壁の向こうは
ゲスト:はい
MC :で、人の家があったりとか
ゲスト:そうです
MC :騒音対策を講じてるっていうエリア
ゲスト:そういうことなんです
MC :で、景色が見えるところ、ビルが見えるところは
ゲスト:はい
MC :そうでもないよっていうエリア
ゲスト:そういう、そういうことなんですね
MC :はぁあ、ああ、わかりました
ゲスト:ええ、ええ、で、特にこの遮音壁の高さっていうのが実は、あのう、高くすればするほど
MC :はい
ゲスト:音を遮りやすくなるんですね
MC :おお、高いところありますね
ゲスト:ええ、でも、できないところもあるんですね
MC :ふん
ゲスト:で、それはなぜかというと遮音壁が高くなるとですね
MC :はい
ゲスト:日陰ができてしまうと
MC :はい
ゲスト:そして、ビルのところが日陰なってしまい、家が日陰になってしまうということで、
ええ、日照の問題、太陽の光が、あのう、当たらないことで問題になるということがあるので
高くできないところもあるんですね
MC :ふうん、じゃ、ほんとは、騒音なんとかしたいんだけれど
ゲスト:はい
MC :太陽の光を採るっていう
ゲスト:そうです
MC :こともあるんですね
ゲスト:そうですね。ですから、あのう、まぁ低くして
MC :はい
ゲスト:その上にですね突起をつけて、できるだけ効果を、えー、低い遮音壁でも音を遮る効果を高くして
MC :へぇ、突起ってどんなやつですか
ゲスト:あのう、まぁ、走って、車走ってるところがありますけれども
MC :ええ
ゲスト:ええ、上にですね円筒形、丸い
MC :ふうん
ゲスト:ものがついたりとかですね
MC :ふん
ゲスト:ええ、マッシュルームみたいな形をしているものがですね、
MC :マッ、へぇ
ゲスト:遮音壁で、あのう遮音壁の上についているんですね
MC :何色ですかそれ
ゲスト:それは白ですね
MC :へぇ、それまーるいやつ
ゲスト:そうです。丸いのが、こう上についてるんです
MC :うん
ゲスト:それがつくことによって高さが低くても音を遮りやすくなると
MC :壁のてっぺんに
ゲスト:はい
MC :壁のてっぺん、そんなに高くない遮音壁の上に
ゲスト:はい
MC :マッシュルームみたいなやつみつけたら
ゲスト:はい
MC :これはより防音効果が高くなるための工夫がされてるということですか
ゲスト:そういうことです
MC :どこのポイントだろう
ゲスト:ええと、もう、いや、いろんなところに
MC :けっこうある
ゲスト:ありますね
MC :ええ、チェックします
ゲスト:ええ、ええ、で、またそういうのがつけ、あのう、つけてもやっぱり効果が、
あのう、十分な効果が得られないところに関しては
MC :はい
ゲスト:高くしてあるんですけれども
MC :ふん、
ゲスト:そのかわりですね、壁を透明にしてあるんですね
MC :それどこですか
ゲスト:これはですね、いくつか、例えば六本木とかですね、渋谷のあたりに
MC :ほう
ゲスト:結構ありますね
MC :六本木、渋谷、3号線
ゲスト:ええ、3号線
MC :首都高速3号線
ゲスト:3号線
MC :そうだ透明だアクリルみたいになってる
ゲスト:そうです、そうです、そうです。ところがね、あっちこっち、あのう、透明になってて
MC :はい
ゲスト:で、外が見えるようになってるんですけれども
MC :はい
ゲスト:あれは、あのうドライバーが外を楽しむためにあるわけではなくて
MC :ええ
ゲスト:光がとおりやすくなってる
MC :なるほど、抜けは確かにいいんですよ
ゲスト:そうですね
MC :六本木ヒルズ、3号線からね
ゲスト:ええ
MC :都心の方に行くと真正面に六本木ヒルズ
ゲスト:そうです、見えますね、見えますね
MC :やがて東京タワーが見えて、たまりませんけれど
ゲスト:たまりませんね
MC :そう、たまんないですね
ゲスト:ははは、ははは
MC :その横、たしかにアクリルのはあるけれど
ゲスト:ええ、
MC :あれはドライバー用じゃなくて
ゲスト:はい
MC :遮音壁なんだけれど
ゲスト:はい
MC :太陽の光も確保するってことで
ゲスト:そうですね
MC :へぇえ
ゲスト:だからあの近辺、例えば六本木とか渋谷でもけっこう民家、住んでらっしゃる方もいるんですね
MC :そうか
ゲスト:だからそこにもちゃんと光が当たるようにするために、壁を透明にしてあるんです
MC :へぇえ、なんか、ちょっと山手線の内側だからすごいお金持ちのイメージですけれども
ゲスト:そうですね
MC :意外に人いるんですね
ゲスト:いますし
MC :ああ
ゲスト:そうですね
MC :なるほどね
ゲスト:昔ながらの方が
MC :そうか、さぁ、それ以外にどうですか、首都高の科学、どんなものあるのでしょうか
ゲスト:そうですね、道路のトンネルとは、道路のトンネルは、あのう、鉄道のトンネルと違いまして、
中の空気がですね、汚れやすいんですね
MC :あー、たしかに
ゲスト:排気ガスによって、えー、中の空気がだんだん汚れやすく
MC :壁とか真っ黒になりますよね
ゲスト:そうですよね、なりますし、
MC :はい
ゲスト:また温度が上がりやすいんですね
MC :はい
ゲスト:で、冬はあまり問題にならないんですけれども
MC :はい
ゲスト:夏は熱くなるんですよ
MC :はい
ゲスト:山の手トンネルの中は、で、車に乗ってると、まぁエアコンが効いてる車では、
あまり問題は起こらないんですけど
MC :はい
ゲスト:二輪車、バイクの人にとっては、熱くて
MC :はい
ゲスト:困ると
MC :はい
ゲスト:いう苦情もあるそうです
MC :はい
ゲスト:ですから、えー、その汚れた空気と
MC :はい
ゲスト:温度を下げるために
MC :はい
ゲスト:換気を行っているんですね
MC :あっ、トンネルの中で換気扇が回ってるんですか
ゲスト:そうです、まわってます。で、その換気扇をですね、見れるとこもあるんですけれども
MC :ええ
ゲスト:外側についるものがあって
MC :はい
ゲスト:えー、車からは見えないところもあります
MC :ふーん
ゲスト:で、これで実は問題なのは
MC :ええ
ゲスト:その空気が汚れているだけではなくて、音が含まれているということなんですね、先ほどの、騒音の問題も
MC :はい
ゲスト:ありますけども、音が含まれているために、そのままその空気をですね、外に、地上に出すことができない
MC :はぁ、あっそうか、いわゆる、じゃ、その山の手通りの上
ゲスト:はい
MC :上、走っている
ゲスト:はい
MC :人たちに
ゲスト:はい
MC :その換気扇つかって、騒音も上にきちゃうってことですか
ゲスト:そういうことです
MC :地上に、
ゲスト:はい
MC :空気を外に出すんじゃ、だけじゃなくて、音も
ゲスト:そうです
MC :出てくるってことですか
ゲスト:音も出てきてしまう
MC :へぇえ
ゲスト:だから音を小さくして
MC :はい
ゲスト:なおかつ有害な、えー、排気ガスの中に含まれている有害なものを取り除いてから、
外に出さなくちゃいけない
MC :そんな細かいことやってるんですか
ゲスト:そうなんです。けっこうやってるんです
MC :へぇ、それどういうシステムですか
ゲスト:ええ、そういう換気システムがですね、そうです、あのう、山の手トンネルの周囲に
MC :はい
ゲスト:あのー、そういう換気システムがあるんですね、たくさんあるんですね
MC :へぇえ、いやぁこれちょっと、また首都高を走る楽しみが増えましたね
ゲスト:そうなんですね
MC :ええ、やっぱりお金かかって
ゲスト:ええ、
MC :ちゃんと快適に走れるように
ゲスト:はい
MC :周辺の住民とも
ゲスト:はい
MC :しっかりとこう、生活共存できるように
ゲスト:そうなんですよね
MC :気を使って道路ってできてるんですね
ゲスト:そうですね
MC :はぁ、ちょっと、とりあえず1週間、毎日首都高に乗って勉強したいと思います
ゲスト:あっ、はい
MC :また来週お話うかがいたいと思います
ゲスト:はい
MC :今日のサイコーは交通技術ライターの川辺謙一さんでした。ありがとうございました
ゲスト:はい、ありがとうございました。 -
「日本海の科学 パート2」 ゲスト:蒲生俊敬さん
2018/11/01 Thu 12:00 カテゴリ:環境MC :今週のサイコーも、前回に続きまして、東京大学大気海洋研究所教授の蒲生俊敬先生です。
よろしくお願いいたします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :蒲生先生は、講談社から「日本海 その深層で起こっていること」という本を出版されているんですけれど、
先週終りの方でね、この日本海で起こっていること、30年間で酸素ガスが10%減っているという・・・
これは何か重要なサインじゃないかな?ってところで先週終ったんですけれど、
先生はこの30年で10%、酸素ガスが減っている事どういう風に考えていらっしゃいますか?
ゲスト:はい、あのー、えーっとその前にあの、酸素ガスってものは基本的にどんな物質かというのを
ちょっとお話したいと思うんですけどね・・・
MC :はい、お願いしまーす。
ゲスト:海の中の酸素ガスというのは、海の表面だけで作られているんですよ。
酸素ガス・・・陸上では、あのー、緑の葉っぱを持った木が光合成というあのー、
二酸化炭素と水からあのー、そういう生合する、植物体を作るその副産物として酸素ガスが出来るというね、
光合成反応というのを知っている人も多いと思うんですけども、
同じ事が海の中でも、えー植物プランクトンという目には見えない微生物が海の表面にたくさんいて、
太陽光線を使って、光合成をしてます。それで酸素ガスをたくさん作ってる、
だけど、光合成っていうのは太陽光線がないとできないので、そういう海の中で明るい部分というのは、
ごく表面だけなんですね。深さ100メートルから200メートルぐらいの所までしか太陽光線入ってこれない。
だから、海の表面だけで、酸素はどんどん作られている・・・で、あのー先週もお話しましたけども、
海の中で水が循環している。表面と下の水が入れ替わるということが、起こらないと、
その表面でせっかく作られた酸素ガスは深い所に入っていけない訳です。
で、あのー、深い日本海でいえば、2000メートルより深い所のような、今ちょっとお話があった、
過去30年の間に酸素が減っているという話をしましたけども、
その減っている酸素の元々は表面の水が沈み込んで、日本海の深い所に酸素を供給していたわけですね。
で、それが、もし定常的に減った分だけちゃんと補給が続いていれば、
酸素ガスは減らずにずっと同じ濃度を保っているはずなんですが、減ってきているということは、
多分これは、そのー、減った分を補充する、そういう水の動きですね、
表面の水が沈み込んで日本海をかき混ぜるようなプロセスが、少し弱まっているんじゃないかという事が、
まあ心配されるわけです。で、これどうしてそういう事が起こるのかという事なんですが、
そもそも海の中で、そういう表面の水が深い所迄、入り込んで行く為には、表面の水を十分冷やして、
重たくして、海水というのは冷やせば冷やす程、重くなるので、
重くなった水は要するに重力でズブズブっとこう、海の深い所へと沈んでいける訳ですね。
で、日本海の北の辺り、あのー、ロシアとの国境、ロシア、日本海北部接していますけども、
ああいう所では冬の非常に寒い時期、北西季節風がビュンビュン吹きつけるような、
そういう寒い時に日本海の表面の海水が冷やされて、重くなって、
それが日本海の中へ沈み込んでいくという・・・そういう、あのー、プロセスが起こっているんですね。
それが、あのーえー定常的にえー、力強く起こっていれば、表面の酸素をたっぷり含んだ海水が
日本海の深い所へ送り込まれて、きっとその酸素が減ってくるというのが起こらないと思うんですけども、
実際に今、調べてみると、酸素ガスが減っている、これは多分そういう日本海の冬の時期に起こっている
日本海の北部の北の海域で表面の水を冷や、重くして、冷やして重くするというプロセスが、
少し以前に比べると弱っているんではないかと・・・で、水を冷やす為には十分冷たい、
あのー、気温のそういう北西季節風が吹く必要があるんですけども、
あのー皆さんも知っていると思いますが、最近はまあ、地球温暖化と言われるようにじわじわ気温が
上昇している、いろんな気候、気象の現象についてもいろんな影響がそれが表れていて、
そのー全般的に冬の温度、気温が上がってきてるということなんですねー。
で、おそらく、まあ、単に気温が上がるだけかどうかわかりません。いろんな現象が複雑にか、
組み合わさってることかもしれませんが、そういう日本海の北部の海域の表面の海水を冬の時期に、
十分に冷やすという事が段々起こりにくくなっていて、それが日本海の中のそういう、
海水の循環を弱めてきているのではないかな、という、そういう可能性を考えています。
MC :なるほどー。
ゲスト:それが、まあ日本海のそういう深い海水の化学組成にまあ、
見え始めてきているということかなあと思うんですね。
MC :僕らの暮らしにどんな影響があるんですか?
ゲスト:えーっと・・・それは明日明後日とか、そういうスパンの話ではないので、
えー、多分長い時間かけてそういう海の循環にえー、じわじわと変化が生じるということなので、
まあただ、あのいろんな副次的なですね、例えば、海の中での生物の動き、生物の生息環境に、
えー、長い時間かけて影響が出てくる、そうすると魚たちの生息エリアが変化するとか、
えー、まあ、水産漁獲量に何か変化が出てくるとか、まあいろんな、
あのまあ全体に関わるようなあのー話と結びつく可能性がありますね。
MC :本来、日本海というとね、海の幸ですよね?だって、太平洋を海の幸とあんまり言わないじゃないですか。
日本海はなんか、海の幸がおいしいっていう定説がありますよね。
多分、お母さんなんかもきっと、ブリ、あのー富山の寒ブリっていって、とても有名なんですけど、
実は何年か前からもうブリがあまり、富山獲れなくなってしまって、
そのブリの潮の漁、漁場が北洋の方に北上したって話があるんですよ。
これも今先生がおっしゃっている話、海水温にやっぱり影響してるんじゃないですかね?
ゲスト:えー、どうでしょうね・・・あの、えー恐らく、いろんな原因があるんだと思いますが、
あの、簡単にこうだからって言われる・・・えー、ちょっとあのー、わかりませんが、
多分、あのー、魚は生息しやすい状況が変わって、これまではない別の場所にそういう、
えー、より魚達にとって暮らしやすい場所が動いたというような、そういうことだと思いますね。
MC :やっぱりここ何十年かで、やっぱり気候変動というか、
海水温の上昇っていうのはやっぱり研究されていると、ここ確実なものとして捉えていい訳ですよね?
ゲスト:はい、確実というか、少し上がっているということは、あのー、むしろ我々よりも例えば、
気象庁とかそういうあのー、毎年のように調査をしてあのー、長い時間のデータを積み重ねてるという、
のを見ますとやはり、少しずつ温度が上がってる、まあまあ世界中のあのー、海、いろんな所で、
同じような結果が得られていますから、これはまあ、全、全地球に関わる環境の変化の一環だと思います。
MC :さて、その日本海なんですけれど、何でもこれ日本海っていうのは、元々無かったんですって?
ゲスト:元々日本海っていうのは、日本列島そのものがあのー、ユーラシア大陸の一部でしたから・・・
MC :くっついてた。韓国とか中国とピタッと・・・
ゲスト:もう全部一緒でした。それがまあ日本海の所にユーラシア大陸の一番東の所に、
まあ裂け目が出来たといいますかね、じわじわと日本海の分が広がって、今のような姿になったという・・・
MC :最後はちょっと、歴史の方のお話で・・・もうお時間ですか、いやー、今日は意外ですね、
ちょっとあのー、今一度、ラジオの前のキッズ達も地図を見ながら、
この日本列島と大陸との距離感、それから日本列島の閉鎖性、間宮海峡或いは、
そのね、韓国と福岡との距離感、まあこんなものを見ながら、
是非日本海今一度、考えてみてはどうでしょうかねー。いやー面白かったです。
先生、また是非遊びに来て下さい。
今週のサイコーは東京大学大気海洋研究所教授の蒲生俊敬先生でした。ありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「日本海の科学 パート1」 ゲスト:蒲生俊敬さん
2018/11/01 Thu 12:00 カテゴリ:環境MC :今週のサイエンスコーチャー略してサイコーは、東京大学大気海洋研究所教授の蒲生俊敬先生です。
こんにちは、お願いしまーす。
ゲスト:こんにちは。どうぞ、よろしくお願いします。
MC :東大の先生ですね?
ゲスト:はい。
MC :恐れ多いです。すみません、よろしくお願いします。
えー、大気海洋研究所という・・・これは何を研究されているんですか?
ゲスト:はい、まあ、その名の通り、あのーまあ、大気と海洋を研究対象でありまして・・・
MC :大気と海・・・
ゲスト:え、え、まあ海ですからあのー、いろんなあらゆる研究テーマがその中にあります。
その中、表面から一番深い所まで、もちろん海の事、研究しますし、
ま、海に接している大気も当然研究対象になるし、え、海底の固い地球とかですね、
或いは陸との境界とか、まあそういう海に関する或いは海が関わってくるあらゆる研究をまあ、
やっている研究所ってところです。
MC :なんと、海のない長野県のご出身・・・ですね。
調査航海歴40年ということで、長い事色々やっていらっしゃるけれど、
あのー長野県のご出身でやっぱり海に関心があったんですかね?
ゲスト:えーまあ、あったんだと思います。
でもまあ、私、生まれたのは長野県ですが、あのー、主に育ったのは東京・・・
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:あのー、長野県と東京とはいろんな意味で縁が深くて、ですから山の事も興味あるし、
えー海の事も興味があったという・・・そんな感じでした。
MC :えー、蒲生先生は講談社から「日本海 その深層で起こっていること」という本を
出版されているんですけれど、今日、日本海のお話を伺いたいと思います。
えー、ラジオの前のキッズにとって、海っていうとやっぱり、太平洋の方が印象深いし、
海水浴行くにしてもやっぱり太平洋、ねえ湘南行っても九十九里浜行っても、
大洗の方行ってもまあ、基本的には太平洋に属してる訳ですよね。
で、日本海。新潟とか富山県とかあの辺になりますよね?
ゲスト:はい、そうですね。
MC :日本海って、広さでいうとどれぐらいの規模の海なんですかね?世界的にはどんなもんなのかな・・・
ゲスト:えー、まあ小さい海ですね。まああの日本地図や世界地図を思い描いてもらうと、
よく分かると思いますけれども、あのー面積でいうと、
あのー世界中の海のほんの0.3%ぐらいという非常に小さなあの海です。
えーただまあ、色々あのー、この後、話しようと思いますが、大変面白い海で、
場合によっては世界中の海と肩を並べるようなあのー、大変科学的に面白い海だという、
そういう場所なんですね。
MC :世界の海の0.3%ながら、世界レベルの面白さを備えてる海?
ゲスト:はい、そう思います。
MC :すばらしいですねー。具体的な特徴は何でしょうか?
ゲスト:えー、まーあのー、地形的な事からお話しますと、
あのー、日本列島とそれからユーラシア大陸に囲まれた、
まあ非常に閉鎖的なあのー閉鎖性が強い海域ですね。
MC :閉鎖的・・・あー、地図見て、みんなー。あーイメージ出来ましたね。
ゲスト:えー。日本海の地図ってね、みなさん、多分、毎日のように天気予報見れば必ず目に入ってくるし、
あのーイメージしやすいかと思うんですが、大変小さい海で、
ただあのーものすごく閉鎖的なまわりを陸に囲まれた・・・
ただ、全く閉鎖して湖みたいな海ではなくって、ちゃんと外側の海ともまあ、
浅いけれど繋がっているというそういう表面の水はまわりの海と入れ替わってるけれども、
日本海の深い方ですね、日本海大変深いんでして、
あのー一番深い所は3800メートルくらい深さがある・・・
平均でも1670メートルというにいわれてますけれども、大変深い海です。
MC :へー。
ゲスト:だけど、表面のその、他の海と繋がってる、あのー、海峡ですね。
対馬海峡とか、津軽海峡、そういう所は深さが100メートルちょっとぐらいしかないですから、
ごく上だけで繋がって、本体の深い日本海というのは周りの海から完全に孤立した海です。
だから、その中で日本海独自の、いろんな現象が起こっていると・・・
MC :へぇー。
ゲスト:はい。それは世界の海とも色々比較できる大変面白い場所だという、そういうことになるんですねー。
MC :地図見ると、福岡県の北はもうすぐそこは、韓国がありますよね?
ゲスト:はい。
MC :で、北の方へ行くと、北海道の稚内からずーっと千島列島という、ロシアの方まで、ずっと島がありますよね?
ゲスト:はい。
MC :はい。何とかあの間を日本海ですかね?
ゲスト:えーっと、千島列島の方まで行っちゃうと、あっちはオホーツク海が入ってきますから・・・
MC :じゃ、もっと日本海って・・・
ゲスト:え、北海道のまあ、北の所に、間宮海峡というのが・・・
MC :間宮海峡。
ゲスト:はい、かつてのあの日本の・・・
MC :間宮林蔵さん
ゲスト:が、見つけた、あのー、海峡。
あそこにほそーくこう切れ込んでいくんですけども、あれが日本海の北のはずれ・・・
MC :なるほどー。はい。
ゲスト:ということになりますね。
MC :はい。じゃあ、あのエリアですね。ただ、意外に深い所は3800メートル?
ゲスト:はい、はい。
MC :おー、で、青函トンネルってか津軽海峡ていうのは、青函トンネルで新幹線通るぐらいだから、
100メートルぐらいってことなんですね?
ゲスト:はい。あそこは、それぐらいしかありません。あそこも深かったらやっぱり大変でしょうね。
MC :新幹線であのー、北海道まで行けませんからね。
ゲスト:行かないですね。
MC :あと、特徴は何ですか?閉鎖的・・・
ゲスト:えっ、でー、まあ、他の海の影響を受けにくい、まあ、そういう孤立した海なんですが、
実は日本海の中で、えー、大変まあ、活発に海水がまあ動いているって言いますかね、
まあ世界中の海どこでも水はあのー、海って言うと、みなさん大体あのー、海水浴行ったとかあのー、
海岸べりの風景が思い浮かべてしまうので、こう海の表面しかなかなかイメージしづらいんですけども、
海っているのは、日本海もそうですが、世界の海、大抵の所は、厚さを持ってますね。
あのー、大変あの、深い海がその下に広がっている訳です。
で、世界中の海では、その一番深い所と言えども、えー、水がゆっくりとかき混ぜられて
表面の水とその深い水がまあ、ちょっと難しい言葉を使うと「循環している」というような
言葉を使いますが、水がもう混ざってる、もしそれがないと世界中の深い海の中は
どんどん古くなってしまって、まあ水が腐ってしまうと言いますかね、
もう酸素も無くなってしまうようなことになりますが、決してそうなってないのは、
表面の新しい水が、えー大変時間をかけて、えーまあ、いるんですが、
世界中の海をまあ巡っているという、そういうことがあの、起こっています。
で、それと同じことが日本海という非常に閉鎖的な海の中でも世界の海とは、
別に独立して起こっていて、しかもその水のかき混ぜるまあ、表面の水とその深い日本海の水とが、
あのー、ある時間をかけて入れ替わっている訳ですが、その入れ替わりにかかる時間が、
世界の海に比べるとやはり速いんですね。
MC :へぇー。
ゲスト:小さい海だからということだからだと思いますけれども、ですから、日本海の事、色々調べていくと、
その世界中の海洋ともで、起こっていることと似たようなことが日本海でみえる、
場合によっては日本海が世界の海をこう、先取りをしてこれから世界の海で色々見えてくるようなことを
ですね、こう早く我々に知らせてくれるようなそんな所も日本海は持っている・・・
MC :興味深いですよね。
ゲスト:という重要な海だと思います。
MC :はい、はい。じゃあ例えば、先生研究されてて、最近、日本海でこんな事を発見したから、
やがて世界でこんな事が起きるぞっていう、そういうのはあるんですか?
ゲスト:えー、例えば、えー、最もありふれた物質ですが、酸素ガス、
あのー普通我々は酸素ガスを吸って呼吸をしてますが、
海の中の生物ももちろん酸素ガスで呼吸をしてますが、まあなくてはならない重要な物質なんですが、
その酸素ガス、これがその日本海の深い水の中でですね、だんだん濃度が今、減ってきてるんですね。
過去30年間で大体10%ぐらい・・・減ってきてます。
MC :えっ、大変なことですよ、そしたら・・・
ゲスト:まあ、かなりですね。あのー、もしこのペースでいくと、まあ300年経ったら、
どうなるんだろう・・・という気がしますけども、こう、いや、
そのどうしてかっていう事を色々調べていくと、
日本海の中で起こってるいろんな現象と結びついている・・・
MC :へぇー。
ゲスト:さっき、ちょっとお話しましたが、あの、世界中の海は日本海を含めて表面と一番深い所でこう、
水が入れ替わる・・・
MC :循環して・・・
ゲスト:循環をしているってお話しましたけども、循環することで、
その新鮮な酸素ガスをたくさん含んだ表面の水が深い所へ送り込まれているんですね。
世界中の海というのは・・・そうならないと、どんどん酸素ガスっていうのは無くなってしまう性質を
持ってます。で、日本海の深い所で、そのように酸素ガスが減っているという事は、多分ですね、
そういう日本海の中で起こっている水の循環、表面の水が重くなって沈み込んで、下へ入っていくという、
そういうメカニズムが少し、弱まっているんじゃないかという、そういう事があのー、推測されるわけです。
MC :もう時間ですか?来週は、あとこのお話を続きを伺っていきたいと思います。
ちょっと今、今日恐い話で終わるけれど、これ宿題で、みんなちょっとね、
日本海の事考えようよ、一週間。ね!それで、また来週お会いしましょう。
今日のサイコーは東京大学大気海洋研究所教授の蒲生俊敬先生でした。ありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
8月25日イベントレポート②
2018/10/11 Thu 12:00 カテゴリ:イベント今回の「ネクストサイエンスジャム」でも
文部科学省より指定を受けたスーパーサイエンスハイスクールのみなさんが大活躍!
今回は長崎県立 長崎西高等学校のみなさんが会場の子どもたちにユニークな研究、
『アメンボやカスミカメムシなどの身近な生き物の研究と虫の作る音について』プレゼンしてくれました。

新種のアメンボの発見の話はもちろん、
『ダンゴムシの足音』には会場の子どもたちはもちろん大人達も驚きの表情を見せていました。
『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
科学ジャーナリストの寺門和夫さんが登場。
子どもたちから寄せられた様々な質問の中から
台風の方向を変える方法はあるのか、地球の真ん中は何でできているのか、
そして恐竜が絶滅していなかったらどうなっていたかについて解説してくださいました。
今回はここまで。
現在次の企画が進んでいます。詳細が決まったらこのホームページでお知らせしますので
楽しみにしていてください! -
8月25日イベントレポート①
2018/10/11 Thu 12:00 カテゴリ:イベント子どもたちの「科学する心を育む」プロジェクトとして、
日立ハイテクノロジーズと文化放送、KBC九州朝日放送が協力して、
科学実験とラジオ公開録音が一体になったイベント
「ネクストサイエンスジャム」
4回目となる今回は福岡県にある福岡市科学館のサイエンスホールで開催され、
たくさんの子どもたちが参加してくれました。
ここではそのイベントの様子を少しだけご紹介します!

今回のナビゲーターは、
すっかりおなじみの、俳優でタレントの照英さん!
仕事で世界の様々な場所に行っている照英さんでも行ったことがない場所、宇宙。
今回はその宇宙に関するものがテーマということで
会場の子ども達と同じくらいイベントを楽しんでいました。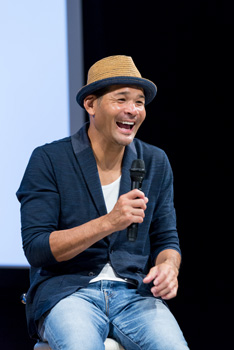
まずはこの公録イベントの目玉のひとつ、ネクストサイエンストークショー。
今回のテーマは「ロケット」。ロケットとは何か、その歴史や仕組み、
現在そしてこれからのロケット開発について、子どもたちにわかりやすく紹介してくださいました。
ゲストは九州大学大学院工学研究院
航空宇宙工学部門教授の麻生茂さん。宇宙飛行士が訓練のときに着るブルースーツで登場した
麻生さんはいきなり子ども達のハートをキャッチ!
そこから『そもそもロケットとは何か?』『どんなタイプのロケットがあるのか』などの
基本的なことをわかりやすく説明してくださいました。
そしてみんなが知りたい『いつ頃一般の人も気軽に宇宙に行けるのか』という疑問に
それを実現するために今、麻生さんが取り組んでいるロケットのアイデアについてお話頂きました。
また子ども達から出た鋭い疑問『ロケットが飛ぶときに分離した部分はどうなるんですか?』や
『ロケットを作るのにかかる時間とお金は?』にも麻生さんは的確に、そしてわかりやすく解説して頂きました。
麻生さんが子ども達に送った「これから求められる人材は自ら新しいものを生み出す人、
チャレンジ出来る人。今日のことを参考にしつつこれからの人生をチャレンジしていって欲しい。」という言葉は、
『これから』を作っていく子ども達にはピッタリですね。
-
「男女の脳の科学 パート2」 ゲスト:黒川伊保子さん
2018/10/01 Mon 12:00 カテゴリ:人体MC :今回のサイエンスコーチャーも先週に続きまして感性アナリストの黒川伊保子さんです。
よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :えー、黒川さんは大学ご卒業後コンピューターメーカーに勤務されて
人工知能の開発に携わったことをきっかけに脳の研究を始められたということですね。
幻冬舎から「鈍感な男理不尽な女」など多くの本を出版されているんですが、
まぁ脳の構造が違うという男女、男の子と女の子によって、違うというお話を聞いて、
いやあ、なるほどなと思ったんですけれど、人間の脳機能が7年周期で変化するっていうお話なんですよね。
ゲスト:そこにきましたか、そこに気づいて下さいましたか。
MC :みんな何歳?だからまあ、14歳だったら2週目だ。
ゲスト:そうですね。
MC :それ以下だったらまだ1周ちょっとっていうことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :7歳未満だったら1周してないってこと?
ゲスト:1周、1周目ってことになりますね。
MC :1周目。なんですかこの、なな、7年周期。
ゲスト:あのー、そうですね、まずね、人の脳の成長もまあ7年ごとって言われてるんですけど、
6歳までの脳とそれから、えーと、7歳から13歳位までの脳、これもうどんどん位相を変えていくんですね。
MC :ほお
ゲスト:で、えー、これを聞いて下さっている例えば中学生の皆さん、
小学校高学年から中学生の皆さんだと一番興味があるのが13歳から14歳の脳の変化なんです。
MC :うーん
ゲスト:大体、えー、人の脳は13歳位で子供脳型から大人脳型のデータベースに変化します。
MC :えっ、子供脳から大人脳に?
ゲスト:脳に。
MC :へー。
ゲスト:これはもうデータベースのタイプが全く変わるので、
MC :ええ
ゲスト:あのコンピューターが分かる人だったらこれ言うと分かるかな、マックからPCに変わるみたいに
MC :へー
ゲスト:もう機構がかわるのですから
MC :ほぉー、ほっほっほ
ゲスト:でなぜ変わるかって言ったら、子どもの時っていうのは何か体験しても、
その体験の感性情報を全部グルッと記憶するんですね。
MC :はい
ゲスト:12歳までは。で12歳までの記憶っていうのは、あの、大人になってからでもふと思い出した時に、
その時口の中に入れてたキャンディーの味とかまで思い出す事が
MC :ほぉ
ゲスト:ありませんか
MC :はいはい
ゲスト:例えば、小学校5年の夏、隣のおじさんがカローラ買って、まあ私の世代だとね
MC :うん
ゲスト:まだ珍しかったから車が
MC :はあ
ゲスト:マイカーが珍しい時、カローラ買って、その車に乗せてもらって海に行ったなあって。
MC :ふうん
ゲスト:あの時、口の中で、食べてたなあのキャンディー、あれだわ、みたいな。
MC :ほぉほぉほぉ
ゲスト:その車のにおいとか、なんかありとあらゆる事を感性情報が、記憶の中についてるんですよ。
でもそうするとね、記憶の容量が大きすぎて、あの一生を使って、使えなくなっちゃうので脳が、
足りなくなっちゃうので脳細胞が。
大人脳っていうのは何か新しい経験をした時に、過去の類似体験を瞬時に引き出してきてその差分だけを、
要領よく言えるっていうデータベースなんですね。
MC :へえー、じゃあ14歳くらい、中学生の2年生くらい
ゲスト:中2です。13歳で変わります。
MC :変わる。
ゲスト:で
MC :へえー
ゲスト:えー、一番その脳が問題なのが13歳から15歳までね、13歳の時に検索のシステムが大人脳型に変わるんだが
MC :はい
ゲスト:データはまだ子供脳型なわけ
MC :うーん
ゲスト:ということはデータと検索の機構が、あのすれ違っているんですよ、この思春期の3年間というのは
MC :はい
ゲスト:なので脳が誤作動するんです。
MC :なるほど
ゲスト:だからこの時期は、大人はとにかく子供達の誤作動に寛大になって頂きたい。
MC :なるほど。逆にこの親の立場からそれは興味深いですよね。
ゲスト:そお、そお、そお。だってこんなに愛してる母親をクソババア、死ねなんて、ほんとにかわいそうに、
この脳っと思ってあげればいいわけじゃない。
MC :あぁー。そういう時期がね
ゲスト:そお
MC :反抗期とか
ゲスト:反抗じゃないんですよ、あれは誤作動していくんですね。
MC :なるほどぉ
ゲスト:だから、この時期自分じゃないみたいって、もし悩んでも、15歳の誕生日直前位に、
自分の脳がしっかりとしてきますから
MC :はい
ゲスト:この不安な時期は、大丈夫。
MC :はあー
ゲスト:永遠に続くわけじゃないよっていうのを、中学生の皆さんに言っときたいんだけど。
まあ、脳っていうのはそうやって7年ごとに大人になっても位相を変えていくんですね。
MC :はい
ゲスト:28歳までの脳は
MC :はい
ゲスト:まあ、もちろんその、その前の脳も含めてだけど28年間は入力装置。
MC :4周、4周分は入力
ゲスト:4周分は入力装置。
MC :へえー
ゲスト:でも脳は入力する為に生まれてきたわけじゃなくて、出力の為に生まれてきてるんだけど
MC :ほー、はい
ゲスト:出力性能が最大になるのは56歳からの28年間ですよ。
MC :え、すごいじゃないですか。じゃまだまだこれから出力
ゲスト:まだまだなんですよ
MC :出来るってこと
ゲスト:まだまだですよ
MC :ですね
ゲスト:うん、ていう事は思春期のお子さんをお持ちの親御さんなんか
MC :ええ
ゲスト:まだまだこれからピークが来ます。
MC :へええー
ゲスト:健康でさえあればね
MC :うーん
ゲスト:だから健康でさえいてくれたら、直感力は実はこの人生第3ブロック、
まあ28年周期でいうと第3ブロックが、あの、最高の脳って事になる訳だから、
まあ中学生くらいで友達に負けたりした事くらい
MC :ええ
ゲスト:なんでもないよ
MC :ああ
ゲスト:なんでもないよ
MC :なるほどね。で、第1ブロックが28歳まで、次の56歳まで、
キッズのお父さんたちの世代なんで僕なんかもそこに入るんですけど
ゲスト:はい
MC :これ第2ブロックっていうのはどういう時代なんでしょう。
ゲスト:第2ブロックはですね、脳が自分の神経回路を宣伝している28年間ですね。
MC :ほおー
ゲスト:あの、脳の中にはそれこそ天文学的な数の沢山の回路が入っているから
MC :はい
ゲスト:あのー若いうちは結局どの回路も反応する。逆に正しい答えが見つからないわけ。
MC :うーん
ゲスト:将棋の米長名人は50代にインタビューに答えてこう言っているんですよ。
えー、20代30代は何百手先まで読めたよって。でも何の手で勝てるか分からない。
考えなきゃ分からない。50代は数手しか読めないけど全部勝ち手なんだ。
MC :へえー
ゲスト:でね、つまり私達の脳が、自分が生きる環境において何が正しくて
何が不必要かっていうのを取捨選別するのが
MC :はい
ゲスト:29歳からの28年間、失敗をしたらその日のまず晩、失敗に使った脳の神経に、
あの電気信号が行きにくくなるんです。成功すれば逆のことが起こる。
これはあの幼い頃からもちろんそうなんですけど、私達は失敗すると頭が良くなるのね。
MC :うーん
ゲスト:そして、ま、この7という数字は私達の脳の中にとっさの、あのー、認知の時に使う、
ま、ちょっとラジオでは難しいけど長短期記憶の場所があるんです。
MC :7?
ゲスト:7個あるんです。それが。私達の脳の中に。
MC :へえー
ゲスト:なにかの世界観をパッとつかむ時に、とっさにその箱の中にポンポンポンッと属性を入れて
7個のなんかビュワーというか、それで世の中を私達は見てるんですね。
MC :へえー
ゲスト:で虹が7色に見える民族が
MC :はい
ゲスト:この地球上のほとんどなんですよ。
MC :はい
ゲスト:虹は光のプリズムだから8色に見ようと思えば見えるし、6色に見ようと思っても見えるのに
MC :うん
ゲスト:自然に地球上のほとんどの民族が7色に見えます。
MC :はい
ゲスト:理由は、私達の脳の中にその超短期記憶の箱が7個あるから
MC :なるほど
ゲスト:光の、あの、色を7個に分類すると脳がしっかり見た感じがするんですよね。
MC :それは納まりがいい数字なんですね。
ゲスト:納まりがいい
MC :脳の中に。7が。
ゲスト:なのでえーっと、ラッキーセブン、七福神。
MC :おー
ゲスト:ね。
MC :おー
ゲスト:それから、そお、えっとー、音階もドレミファソラシ
MC :はい
ゲスト:の7音階に分けると
MC :うーん
ゲスト:私達は情報が伝達しやすいですよね。
MC :うんうん
ゲスト:そして成功の為の7つの法則とか。
MC :うん
ゲスト:私も去年、「目指せ、180センチ!身長を伸ばすための7つの法則」という本を出したんですけど
MC :へえー
ゲスト:まあ、7つっていう言葉は非常に納まりがいい。
でその7つの箱の中に入る属性に時間幅がある時は一巡したって感じがするんですよ。
MC :時間幅がある時は
ゲスト:ある時は一巡したって感覚があるんですね。
MC :うーん
ゲスト:で私達の脳は、20世紀の終わり頃、地球の自転と公転をカウントしてるのが分かってるんですよ、脳が。
MC :へえー
ゲスト:とはつまり生まれて何年目かって脳が知ってるんですね。
MC :はい
ゲスト:何日目かも脳が知ってるんですよ。
MC :へえー
ゲスト:という事は7日と7年の周期が脳の中にある訳
MC :ほおー
ゲスト:さあ7日の宗教を皆さん言わなくても分かる、1週間
MC :はい、1週間
ゲスト:ね。これはキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の神様が7日で暮らせって言ってるから
MC :うーん
ゲスト:でもこの3つの宗教は元を同じ古代宗教だから、揃ってても不思議じゃないが
MC :はい
ゲスト:仏教でも
MC :はい
ゲスト:初七日・二七日って
MC :ほおー
ゲスト:数えていくじゃないですか。
MC :はい
ゲスト:私達の脳の中には7日経つと一巡したっていう感覚が元々、非常に動物的に備わっているんですね。
MC :うーん
ゲスト:もう一つ7年も実はある事が発見できまして
MC :はい
ゲスト:7年経つと一巡して終わった感じがするので
MC :はい
ゲスト:あの、7年で流行が変わったりするんですよ。
MC :ほお、いやあでも56、だって、だってね、56歳からが一番脳が成熟してる時期ってことですよね。
歳を取ることもなんか悪い事じゃない気がしてきて。
ゲスト:そう、そうです、そうです。
MC :ですよね。
ゲスト:もう、60代は
MC :はい
ゲスト:えーっと旅と習い事の好機って言われてますからね。
MC :へえー
ゲスト:あのー、私は今年57になるので
MC :はあ
ゲスト:もうほんとに、アラ還かな
MC :あら
ゲスト:なの、だから
MC :そうですか
ゲスト:60になったら何しようかなっと思って。
MC :今じゃあ絶頂期ですね、脳の。
ゲスト:そう、去年56になって
MC :これから絶頂期を迎えて行くわけですね
ゲスト:そうですよ、すっごい直感働くようになるんです
MC :そうですか、いや、いいですね。いや、素敵な、ねえ、年齢の重ね方で。
年齢聞いてびっくりしましたけど。
ゲスト:あははは
MC :はい、お時間ですね。またぜひ遊びに来て下さい。
えー、今週のサイコ-は感性アナリストの黒川伊保子さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「男女の脳の科学 パート1」 ゲスト:黒川伊保子さん
2018/10/01 Mon 12:00 カテゴリ:人体MC :今回のサイエンスコーチャー、略してサイコーは感性アナリストの黒川伊保子さんです。
ゲスト:こんにちは。
MC :こんにちは。なんですか、感性アナリストって。
ゲスト:ねえ、これ自分で付けた肩書きなんですけど
MC :ほー、初めてです、こういう肩書の方は。
ゲスト:そうですね。
MC :唯一ですね。
ゲスト:というか、私の研究分野も
MC :はい
ゲスト:私の仕事のフィールドも、あのー、非常に珍しくて
MC :ほほお
ゲスト:まあ前人がいなかったっていうか。
MC :はあ
ゲスト:なのでね、まあ新しい仕事の名前になりましたが
MC :うん
ゲスト:あの、私は人工知能のはたけから脳科学を研究して
MC :はい
ゲスト:人の脳の感性の領域、まあ無意識に起こる領域の研究をしている研究者なのです。
MC :すごいですね。人工知能ってAI。
ゲスト:AIですね。
MC :AIの研究からってことですね。
ゲスト:はい。
MC :大学を卒業後コンピューターメーカーに勤務されて、そして脳の研究を始められてる。
幻冬舎から「鈍感な男 理不尽な女」
ゲスト:ふふふ
MC :など、多くの本を出版されてらっしゃる。「鈍感な男 理不尽な女」って駄目駄目じゃないですかこれ。
ゲスト:これね、
MC :えへー
MC :私が付けたタイトルじゃないんですね。
MC :えぇえぇ
ゲスト:な、な、あのー、幻冬舎の、あのー、方が付けてくださったタイトルなんですけど
MC :はい
ゲスト:私が最初に付けたタイトル、まあそのタイトルで本を書いたそのテーマは
MC :はい
ゲスト:女の機嫌の直し方完全マニュアル
MC :おー
ゲスト:なんですね
MC :お父さんに聞いてもらいたいですかね、今日は。
ゲスト:そうですね
MC :ふふふ、ははは
ゲスト:これね小学生でマスターしちゃったら人生自由自在だね。ふふ
MC :えー
ゲスト:これねお母さんにやって使える。
MC :すごいね帯が。なぜ女は適切なアドバイスに逆ギレするのかっていう。
ゲスト:あはは
MC :これみんなもさ、男の子と女の子っているじゃない、
ちょちょっと今、上から目線になっちゃったけど、あのー、男もいけないところあるよ、男の子もね。
ゲスト:ふふ
MC :でもなんとなくこの帯を見ると、なぜ女は親切なアドバイスに逆ギレするのか、
脳科学が解く女の機嫌を直す18の処方箋。
ゲスト:そうですね
MC :バンバンっときますね。
ゲスト:女性はね、とても分かりやすい、あの、言葉で不機嫌を表すんですよ。
MC :ほおー
ゲスト:まあ男子がそんなに分か、分からないと思ってるから
MC :はい
ゲスト:例えば、私なんてどうだっていいと思ってるんでしょ?とか、あなたってどうしてそうなの?とか
MC :はい
ゲスト:だから言ったじゃないの、とか
MC :はい
ゲスト:もうよく聞いたセリフでどの女子も不機嫌を言うんですけど、
あの、男子はね、まあ小学生の男子も分かると思うけど、中学生ならもっと分かると思うけど、
女子のこう不機嫌っていう風に一塊にまとめるけど
MC :はい
ゲスト:その言葉ごとに
MC :ええ
ゲスト:不機嫌さの色合いが違うんですよ。18通りの言葉があり、18通りの色合いがあって、
それごとに言ってあげるべき言葉が違うので、それを完全マニュアルにしたんですね。
MC :ほー
ゲスト:でもこれはR29。
MC :あ、29歳
ゲスト:以上指定ですね。
MC :はい
ゲスト:あのー、まあ、若いうちはその女性の不機嫌に翻弄されて
MC :はい
ゲスト:泣いたり笑ったり恋をしたりしてください。
MC :あ、分かりました。
ゲスト:ふふふ
MC :まとめ入っちゃったけれど
ゲスト:はい
MC :だけど、男の子と女の子で脳の構造が違うという事ですか?
ゲスト:そうですね、その事は知っておいた方がいいですね。
MC :えー
ゲスト:えー、前にあの中学生向けの雑誌で
MC :ええ
ゲスト:えーっと、ま、あの中学生の女子にアンケートを、男子と女子にアンケートを採って
MC :はい
ゲスト:男の子のここが分からない、女の子のここが分からないってアンケートを採ったんですね。
で、えっと、男子の一位が女はなぜ連れ立ってトイレに行くのか?
MC :おー
ゲスト:かな。で女子の一位が男子はなぜ真面目に掃除をしないのでしょうか?っていう
MC :おー
ゲスト:のがあるんですね。
MC :ほおほおほお
ゲスト:これどっちも脳科学で説明が出来るんです。
MC :えっ、えー
ゲスト:ふふ
MC :連れションが?えぇっ
ゲスト:そうですよ
MC :え?脳、脳の機能に影響してるんですか?
ゲスト:もちろん、もちろんそうです。
MC :連れションが?ええええ
ゲスト:連れションが。まずですね、あのーじゃ女子の方から片付けましょうか。
MC :はい
ゲスト:えーっと、掃除の方。
MC :うん
ゲスト:掃除の方から片付けましょうか。
MC :男の子はなんで掃除をしないのか
ゲスト:男の子なんで掃除をしないように女子に見えるのかですね。
MC :はい
ゲスト:まあ、大体あのー、帰りのあのー、反省会では、何々君が、
あのー、ほうきで野球してました、みたいな感じになるじゃないですか。
MC :はい
ゲスト:実はですね、男性と女性ではあのー、こう、目の前の、
直近の目の前の事の観察力が女性の方が3倍あるんですよ。
MC :ふん
ゲスト:ていう事は、掃除とか、あるいはまあ家事ですね、お料理とか買い物とかそういう、
こう、半径まあ大体2メートル以内で起こるような事に関する観察力は女子は3倍あるので
MC :へー
ゲスト:女子は3倍見えてるわけ。
MC :ほー
ゲスト:どういうタスクがあるのかって事が。
MC :ええ、ええ
ゲスト:ね。逆に言うと、これはあの、おうちのお父さんに言いたいんですけど
MC :ええ
ゲスト:僕は家事を半分やってますって言うお父さんで、6分の1しか出来て無いって事ね。
MC :女性の目から見ると。
ゲスト:見ると。
MC :うん
ゲスト:つまり女性は3倍見えてるから
MC :はい
ゲスト:男子は3分の1しか見えていない。そのうちの半分しかやってないから
MC :はい
ゲスト:6分の1になっちゃうわけですよ。
MC :やってる気でいても
ゲスト:そう、これは
MC :まるで評価されてないってことですね
ゲスト:そうです。これは中学校でも小学校でも起こる事なんですね。
MC :うーん
ゲスト:だから女子の皆さんに言いたいのは、もし男子が掃除をしない、文化祭の、あの、
手伝いを真面目にしないと思ったら、それは彼らはやってるつもりなんだけど、6分の1なんだと。
なので残りの6分の2はあなたが命令して足してあげなさい、って事ですね。
MC :なるほど
ゲスト:女性がプロデューサーになって
MC :へえー
ゲスト:はい、鈴木君は、あのー、黒板を掃除して、とか。
MC :はい
ゲスト:ちゃんとなんか、指示をしてあげないと男子は動けないのですね。
MC :へえー
ゲスト:だからもう、あの、家庭のお母さまにも言いたいんだけれども、
えー、家事は6分の1やったところでほんとは良しとしてあげたい。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:逆に言うと、男子に半分やらせると
MC :はい
ゲスト:女子の3倍のストレスって事だからです。
MC :えー、やっぱり、ねえ、男性が家事やるっていうのはストレスになってるってことですか
ゲスト:男性脳にとってはストレスですよね。
MC :はあー
ゲスト:っていう事は半々にやったら
MC :ええ
ゲスト:半々じゃないんですよ。
MC :はい
ゲスト:平等じゃないわけ。
MC :ふーん
ゲスト:3倍苦しいわけ
MC :ふん
ゲスト:だから、そこはもう大目に見てあげてほしいなあって思いますね。
MC :なるほど。
ゲスト:量で半分には出来ないのです。
MC :はい
ゲスト:ま、さあ、その女性はなぜそんな風に観察力があるかというと
MC :はい
ゲスト:とにかく、目の前まわりの出来事がどんどん顕在意識に上がる脳だからなんですね。
MC :うーん
ゲスト:私達は右脳で感じて、ま、もちろん感じるのは小脳とか色んな所が使って、
右脳のイメージの領域を通って、そして顕在意識の左脳に
MC :はい
ゲスト:処理が移って
MC :ふうん
ゲスト:私達は感じた事を顕在意識にあげていくわけ。
MC :はい
ゲスト:で感じた事を顕在意識にあげるのが、脳梁という神経線維の束なんです。
MC :脳梁
ゲスト:右脳、右脳と左脳をつなぐ神経線維の束。
MC :はい
ゲスト:これが右脳の潜在意識の情報、つまり無意識の情報を顕在意識に伝えてくるんですね。
MC :うん
ゲスト:この脳梁という所が男女では生まれつき太さが違ってるんです。
MC :へえー
ゲスト:女性の方が男性より約20%太いんですね。
MC :あ、女の子の方が太いのですか。
ゲスト:太いんです。
MC :へえーー
ゲスト:そして、えー、神経線維っていうのは先がこう枝分かれしてるんですけど
MC :はい
ゲスト:その枝分かれの数も圧倒的に女子の方が多いと言われてまして
MC :ほおー
ゲスト:成人の男女で、成人というかまあ8歳を超えてくると
MC :はい
ゲスト:男女で大体この連携の密度が数十倍違うと言われていますね。
MC :じゃあ女の子の方が脳機能が優れてると考えるわけですか
ゲスト:あ、いや、だから目の前のこと、変化に対する観察力は優れてるということです。
MC :へえー
ゲスト:男性は全体を把握する
MC :ふーん
ゲスト:特に遠く、奥行き感を把握するのにものすごく長けてるので空間認知が良かったり、物の構造を見極めたり
MC :ふーん
ゲスト:する事が、あの、だから複雑な機構を組み立てたり考え出したり
図面を作ったりなんていうのは男性脳がやっぱり得意ですね。
MC :ふんふんふん
ゲスト:ただ、今私が言っている男女の脳の違いっていうのは
MC :うん
ゲスト:これは体のように
MC :うん
ゲスト:真っ二つに分かれているわけじゃなくて
MC :はい
ゲスト:典型的な男性脳型から女性脳型の間にまんべんなく分布してるんですよ。
MC :はい
ゲスト:なので人によっては男性脳40%女性脳60%使えますっていう方もいらっしゃるし
MC :うんうん
ゲスト:それから脳梁太目で生まれてくる男子もいるし
MC :うん
ゲスト:枝分かれの数の少ない女子もいるので
MC :あ、へえー、一概にはじゃあ
ゲスト:一概には言えない。
MC :そうとは言えないという事ですか
ゲスト:うん、ただ群れの差はあります。
MC :へえー
ゲスト:やっぱり百人の男子と百人の女子を
MC :うんうん
ゲスト:グループにするとやっぱり女性の方が
MC :はい
ゲスト:脳梁が太くて、気づくことが沢山ある。そして脳梁が太くて感じる領域とおしゃべりの領域が
MC :うん
ゲスト:あの、とても連携してるんですね。
MC :ふーん
ゲスト:で感じた事がどんどん言葉になって、それを口から出したいって欲求があります。
MC :あ、女の子の場合?
ゲスト:場合。そして
MC :うん
ゲスト:なによりも脳にとって重要なのは
MC :はい
ゲスト:共感
MC :共感
ゲスト:うん
MC :はい
ゲスト:女性脳は共感欲求が男子の、あの、想像をはるかに超えて高いのですね。
MC :へえー
ゲスト:なぜなら
MC :へえ
ゲスト:共感することによって人の体験談を
MC :うん
ゲスト:自分の知恵に変えるからなんです。
MC :ふーん。もっと詳しい話を来週伺おう。もう時間になっちゃいました。あっという間ですよね。
ゲスト:ははは
MC :ぜひまたお話を伺いたいと思います。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :えー、今週のサイコ―は感性アナリストの黒川伊保子さんでした。 -
「キッズの質問特集 パート2」 ゲスト:寺門和夫さん
2018/09/01 Sat 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
前回に続きまして、科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :お願いしまーす。質問きてますよ。国分寺市のつばさ君小学校5年生の男の子です。
キャンディーを燃料にしたロケットが打ち上がったというニュースを見ました。
でも、うまく想像できません。どういう原理なんですか。
キャンディーの他にも意外なものが燃料になるってことってあるんですか。
って、大村さん、知らなかったんですけど、何、キャンディーを燃料にして、
ロケット打ち上げられたんですか?
ゲスト:あ、そうみたいですね。僕も、あの、ニュースでしか知らないんですけども
MC :ええ、ええ。
ゲスト:そういった事が出来たようですね。
MC :そんな、
ゲスト:はい。
MC :何、宇宙まで行くってことですか?
ゲスト:いや、あのー、多分、あのー、少し高いところまで飛んだと
MC :あっ
ゲスト:いうことだと思います、もちろん
MC :いわゆる、ペットボトルロケットみたいな感じ?
ゲスト:まあ、もちろんそれよりは少し、あのー
MC :あっ、
ゲスト:え、高く飛んだと思いますけどね
MC :へえー、
ゲスト:はい。
MC :キャンディーを原料にして?
ゲスト:うん。
MC :キャンディー食べた人間が放り投げたってわけじゃなくて?
ゲスト:あのー、キャンディーを燃やしたんだと思います。
MC :もや、あっ、
ゲスト:はい、はい。
MC :燃焼させた
ゲスト:ええ、そうですね。燃焼させた訳ですね
MC :そうか、
ゲスト:はい。
MC :キャンディーを
ゲスト:はい、はい、ええ、ええ。
MC :燃料にした
ゲスト:はい。
MC :どういうことですか、これは。
ゲスト:そうですね。あのー、ロケットというのはですね、燃料を燃やして、
MC :うん。
ゲスト:飛んでるんですけども、あのー、原理を言うと燃料を燃やした時に
MC :はい。
ゲスト:えっーと、その燃料が、あのー、ガスになる訳ですね。
MC :はい。
ゲスト:うん。で、そのー、発生したガスが沢山、大量に発生して、
それを後ろのノズルという所から、あのー、後ろに噴射してやるわけですね。
MC :はい。
ゲスト:で、そのー、噴射したガスの反動でロケットは、前に飛んでいくと
MC :うん。
ゲスト:これが、あの、ロケットの飛行の原理なんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですから、その原理だけから言うと、燃える物は何でもよくて
MC :うん。
ゲスト:あの、燃焼ガスになって、それが、あのー、大量にガスが発生すれば、
まあ、ロケットの推進の原理としては成り立つわけですね。
MC :はい。
ゲスト:ただ、実際に人工衛星を打ち上げたり、そのー、えー、スペースシャトル打ち上げたりする場合には、
あの、非常に性能のいい燃料使わなければいけないので、
MC :うん。
ゲスト:ま、よく使われるのは、あの、その、ケロシンと言われてるんですけど、これはあの、いわゆる石油ですね。
MC :はい。
ゲスト:ん、それから後は、あのー、スペースシャトルなんかだと、水素、
MC :ふん。
ゲスト:これを燃やしてるわけです。
これは非常に効率が高いので、実際に人工衛星とか打ち上げるのは、そういった物使いますけれども
MC :石油と水素
ゲスト:そうですね。はい。
MC :はい。
ゲスト:あの、ただあのー、まあ、ロケットを飛ばす実験をやる場合には、まあ、いくつか、あのー、
方法があって、まあ、その一つが今回のこのキャンディーのロケットだということだと思いますねぇ。
MC :な、何、じゃあ、その辺で売ってるキャンディーを、燃料タンクに詰めて、も
ゲスト:はい。
MC :火付けた
ゲスト:あ、そうです。あのー、おそらく、その、燃焼させるとこは、ちょっと工夫が必要だと思いますね。
MC :はい。
ゲスト:それからあのー、もちろんそのー、ロケット自体も
MC :はい。
ゲスト:爆発したら大変ですから、
MC :はい。
ゲスト:ちゃんと爆発しないように安全にするとか
MC :はあー。
ゲスト:そういったことは、必要だと思いますけれども、あのー、
キャンディーっていうのは基本的には、お砂糖ですから、
MC :ああ、はい。
ゲスト:お砂糖というのは、成分で言うと、炭素と水素と
MC :ほぉ。
ゲスト:あ、えーっと、それから酸素なんですね。
MC :炭素
ゲスト:うん。
MC :水素
ゲスト:うん。
MC :酸素
ゲスト:ええ。ですから、これは、あのー、いわゆるそのー、えー、ケロシンなんかと同じ、
あのー、基本的には成分なんですよ。
MC :あっ、石油と
ゲスト:うん。
MC :同じ成分なんですか?
ゲスト:同じです。ええ、石油なんかも全部すべてそうですね。
MC :炭素、水素
ゲスト:ええ、そうです。ええ、さん
MC :酸素
ゲスト:そう、そうですね。ですから、原理的には成分は同じなので
MC :へえー。
ゲスト:あの、もちろん、う、あのー、いわゆるケロシンロケットみたいに燃焼がすごい効率的じゃないにしてもね
MC :うん、うん。
ゲスト:あの、ちゃんと燃えて、ガスが発生するから、
MC :うーん。
ゲスト:それをちゃんと後ろから、こう、噴射させるようにすれば、ロケットは飛んでいくという事になりますねぇ。
MC :ここは、科学ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :だって、ケロシンとイコールキャンディーていう
ゲスト:うん。
MC :ま、元を正せば同じっていう
ゲスト:そうです。あのー、
MC :でも、石油とキャンディーっていうと、同じって言われても舐めたくないね、石油は。
ゲスト:そうですね。
MC :だけど、物質は
ゲスト:物質的には同じ物が
MC :ひゃぁー。
ゲスト:入ってるわけですね。ええ。ですから、
MC :紙一重
ゲスト:うん。ですから、まあ、これはですね、あの、要するに、
ま、人工衛星を打ち上げるっていうよりはむしろ、あの、子供たちに
MC :はい。
ゲスト:そういったロケットが飛ぶ原理をね
MC :うん。
ゲスト:あの、実感してもらうということが、あの、一つの大きな目的だと思いますね。
MC :あっ、なるほどね。こういう原理で飛ぶんだよって
ゲスト:そうですね。はい。
MC :うん。糖分でも飛ぶんだよって
ゲスト:うん、まあ、それからそういう、や、話は、こう、未来がありますよね。
MC :うん、うん。千葉県市川市のまりえちゃん。小学校6年生。私は土星が好きです。
それから、あっ、いいねぇ。輪が綺麗だからです。地球にも輪があるといいのになぁとよく思います。
あの輪は、何のためにあるんですか?いつか地球にもあのような輪ができることってありますか?って、
ロマンチックでいいじゃないですか。
ゲスト:そうですねぇ。
MC :いや、いいよ。僕も、水金地火木土天冥、冥海。よく覚えた時に、土星は特別な存在でした。
ゲスト:そうです、やっぱり、あのー、
MC :うん。
ゲスト:特別な存在ですね。
MC :はい。
ゲスト:あの、ほんとに輪っていうのは綺麗ですよねぇ。
MC :はい。
ゲスト:はい。
MC :シャンプーハットなんかすると、必ず土星を思い出しましたもんね。
ゲスト:はい、はい、なるほどね。そうですね。
MC :ああー、はい。
ゲスト:はい、はい、はい、はい。
MC :さあ、その、土星なんだけれど
ゲスト:はい。
MC :えー、地球にも輪があるといいのになって
ゲスト:うーん。
MC :よく思うんだけど
ゲスト:そうですね。うん。
MC :あははは。
ゲスト:まずですね、あのー、土星の輪がどうして出来たかっていう
MC :はい。
ゲスト:ところからお話した方がいいと思うんですね。
MC :あっ、はい。
ゲスト:はい。あのー、土星の輪っていうのはですね、あのー、CDのディスクみたいに見えますよね。
MC :うん。
ゲスト:あの、いっぱい
MC :はい、はい。
ゲスト:輪があって、あのー、何かそのー、ひとつの円盤みたいのが、
MC :はい。
ゲスト:土星の周り、回ってるみたいに見えますけど、
MC :うん。
ゲスト:じ、実際はですね、非常に細かい氷の粒とか
MC :うん。
ゲスト:それから岩石の粒
MC :はい。
ゲスト:そういったものがいっぱい、あの、実はあのー、円盤状に分布してると、そういった状態なんですね。
MC :うん。
ゲスト:で、なんで、そういった輪が出来たかっていうと、昔実はですね、土星の周りを
MC :はい。
ゲスト:あの、お月さまが回っていて、
MC :うん。
ゲスト:えー、ところが、そのお月さまが、実はその、土星に近づきすぎたために、
あのー、土星の重力によってバラバラに壊されてしまったんですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:うん。で、それがあのー、段々、あの、衝突しながら細かい粒になって、出来たのが
MC :はい。
ゲスト:今の土星の輪なんですね。
MC :へえー。
ゲスト:ですから、実はあのー、土星の輪は昔はですね、丸い塊のちゃんとしたあのー、衛星ですね、お月さま
MC :ほぉー。
ゲスト:だったわけですね。それが余りにもちょっと土星が、に近づきすぎたために、
MC :ええ。
ゲスト:あの、壊れて輪になってしまったということなんですね。
MC :も、勘のいいキッズなら、すぐ分かるね。ってことは、土星と衛星、
つまり、に、地球からしたら月ってことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :月が近づきすぎると月が破裂して、地球の輪になるって事ですか?
ゲスト:そうです。
MC :えへへへ。
ゲスト:あの、基本的にはそういうことなんですね。
MC :すごい。
ゲスト:あ、だから実はですね、
MC :ええ。
ゲスト:あの、木星にもね
MC :はい。
ゲスト:それから、あのー、えー、土星の外側の天王星にも
MC :はい。
ゲスト:あの、かすかな輪はあるんですね。
MC :あっ、そうなんですか。
ゲスト:うん。それはやっぱり同じような事が原理で、あの、出来たわけです。
MC :へえー。
ゲスト:ただし、あの、一番問題なのは、重力の強さですね。
MC :はぁー。
ゲスト:で、まあ、あの、木星とか土星って、すごい巨大ですね、
MC :はい。
ゲスト:天王星もそうですけど
MC :おっきい。
ゲスト:だから、重力が強いので、
MC :うん。
ゲスト:あのー、そういう衛星が近づくと、壊してしまう
MC :うん。
ゲスト:まあ、だけどこれ、地球がどうなのかってのは、ちょっと、また、考えなければいけないんですね。
MC :うーん。
ゲスト:で、実はですね、あのー、月は、あのー、今地球から遠ざかってるんです。
MC :そうなんですかぁ。
ゲスト:だからそのー、今のお月さまが地球にどんどん近づいてって、
MC :ええ。
ゲスト:バラバラになって、地球の輪になることはないんですね。
MC :ちょっと、で、ちょっと、月遠くなっちゃうのやだ。それは困るなぁ。
えっ、僕ら素人には分かんないですよ。
ゲスト:ええ、あのー、ただですね、あのー、えっと、遠ざかっていることはちゃんと、
それは、調べられてるので、
MC :えーっ。
ゲスト:間違いないです。で、あの、そもそもの一番昔の事考えるとですね、
実はそのー、地球に輪があったんですね。
MC :えーっ。
ゲスト:うん。それはどうしてかっていうと、えーと、ほんとの昔の、あのー、
生まれたばかりの地球にですね、あの、地球よりももうちょっと小さい天体が衝突して
MC :うん。
ゲスト:えー、そしてあのー、え、それこそほんとにバラバラの、あのー、えー、粒になって、
えー、地球の周りに、えー、そのいわゆる輪が出来ていたんですね
MC :うん。
ゲスト:つ、細かい粒。で、その地球の周りを回ってる輪の中から、
それがいっぱい集まって今のお月さまになってるわけです。
MC :そうなんですか。
ゲスト:うん。そうなんですね。
MC :地球の成り立ちは?
ゲスト:ですから、あのー、ほんとにあのー、最初の頃には、実は地球にも、
輪がそういった意味ではあったんですね。
MC :いや、まりえちゃん。いい質問だったねぇ。いやー、そうなのかぁ。
え、でもこの輪、ま、元に戻すと、地球に元々輪があったけど、
たまたまじゃぁ、月だけが、じゃぁ、残ってるっていうことですね。
ゲスト:そうですね、今は月になって、
MC :うん。
ゲスト:そして、あのー、アポロ計画で、
MC :うん。
ゲスト:えーっと、置いて来た、そのー、あ、反射鏡を使ってですね
MC :うん。
ゲスト:地球からレーザーで、精密に測定すると、
MC :うん。
ゲスト:段々、段々、こう、実は遠ざかっているので、
MC :ええー。
ゲスト:あのー、これからお月さまが近づいて、地球の輪にもう一回なるっていうことは、残念ながらないなぁ
MC :ないのかぁ。
ゲスト:っていうことなんですねぇ。
MC :へえー。前そういえばね、来てくださった「サイコー」が、土星の輪っかの中にタイタンという、
輪っかのこう、中に衛星があって、そこはひょっとしたら、生命体がいるかもしれないという、
そういうお話してくださったんですよね。
だから、土星のあの輪っかには、そういう可能性がある星もあるってことですよね。
ゲスト:ええ、そうです、あのー、今土星の周りを回ってる
MC :うん。
ゲスト:あのー、星としてはですね、実はそのー、タイタンで
MC :うん。
ゲスト:やっぱり生命があるのか
MC :うん。
ゲスト:それから、エンケラドゥスっていうのが、実は回っていて、これが最近
MC :エンケラドゥス
ゲスト:ええ、あのー、話題になってるんですねぇ。
MC :うん。
ゲスト:その、やっぱりそのー、えー、表面は凍ってるんだけれども、内部に
MC :うん。
ゲスト:あのー、解けた海があって
MC :はい。
ゲスト:で、そこで、もしかしたら生命が生まれてるかもしれない。
MC :ほー。
ゲスト:そういった環境があるんじゃないかって言われてるわけですね。
MC :はぁー、いいですねぇー。いやー、やっぱり宇宙の話はロマンがあって面白いですねぇー。
いや寺門さん、また来て下さいね。
ゲスト:はい。
MC :何かゴールデンウィークにはピッタリの夢のあるお話でした。
今週の「サイコー」は、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:どうも失礼しました。 -
「キッズの質問特集 パート1」 ゲスト:寺門和夫さん
2018/09/01 Sat 12:00 カテゴリ:その他MC :さ、今日のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :お願いしまーす。質問きてますよ。結構僕も、興味深くずーっとニュース見てたんですけど、こちらね、
江戸川区のしょうた君小学校6年生からいただきました。
僕も何度か行ったことのある、葛西臨海水族園のマグロが沢山死んで寂しいです。
どういう原因が考えられますか。それから魚って、自然界ではどれくらい生きるものなんでしょうか。
長生きの魚ってどんな魚ですか。まずは、葛西のマグロ。
ゲスト:そうですねぇ。
MC :うーん。
ゲスト:大変だったですね、あれもねぇ。
MC :はーい。
ゲスト:はい。
MC :あれ、な、原因は分かったんですか。
ゲスト:はい。一応調べてですね
MC :はい。
ゲスト:あ、ウィルスだということが、一応分かってるんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:一応ね。ただ、それがあのー、もっと詳しく
MC :はい。
ゲスト:せつ、あのー、調べてですね、原因を、おー、追求して対策とるには、
もっ、もう少し時間かかるかもしれませんね。
MC :だけど、次々に死んでいく様をね、水族館はどうしようもなかった、
そのウィルスってものに対して、ワクチンはなかったんですかね。
ゲスト:あのー、多分なかったんだと思いますねぇ。
MC :ええー。
ゲスト:それから、おそらく、あのー、水族館でね、
MC :ええ。
ゲスト:あの、これだけの規模で、あのー、魚が死んでしまうっていうこともね
MC :はい。
ゲスト:中々今までなかったと思いますねぇ。
MC :はぁー。
ゲスト:ええ。
MC :あのー、マグロというと世界的にねぇ、だんだん数が少なくなっていて、
ただ食しているのは概ね日本人ということで、どっか、こう、日本人とマグロっていうのは、
切っても切れない関係で、
ゲスト:そうですね。
MC :そのマグロがね、ウィルスでなくなっちゃうというのは、何か、
ゲスト:はい、はい。
MC :可愛そうな
ゲスト:はい。
MC :話なんですよね。
ゲスト:そうなんですね、あのー、ま、海ではですね
MC :ええ。
ゲスト:よくあの、海に住んでいる動物がですね、
MC :ええ。
ゲスト:あの、大量に死んでしまうっていう事あるんですね。
MC :ええ。
ゲスト:で、ま、いくつか原因が、こう、考えられるんですけど、1つは、その、ウイルス
MC :うん。
ゲスト:ま、つまり、そのウイルスが感染してですね、あのー、その魚なり、
それから海の生物に、あのー、おー、病気にしてしまう
MC :ええ。
ゲスト:で、そのために、あのー、死んでしまう、例えば、その、内臓がやられたり
MC :うん。
ゲスト:それから、脳の神経がやられたりしてですね、あの、死んでしまうってことが一つありますね。
MC :はい。
ゲスト:それから、ま、ウィルスではないんですが、小さな微生物、
MC :ふん。
ゲスト:うん。特に、あのー、毒を持ったね、あの、微生物が、えー、例えばそのー、体の中に入り込んで、
その毒が悪さをして、やっぱり死んでしまうってことありますね。あの、よく赤潮っていうのを
MC :赤潮。
ゲスト:言いますよね。そうですね。
MC :はい。
ゲスト:ええ。あれやっぱり、毒を持ったそういった微生物が、大量発生したために起こる現象なんですね。
MC :赤潮って、あの、微生物が、帯の様になって、海の上を
ゲスト:そうです。
MC :浮かんでるの
ゲスト:そうです。
MC :たまに、ニュースで映像で
ゲスト:そうですね。
MC :見ますよね。
ゲスト:はい。あれはだから、ほんとに毒を持った微生物が
MC :はあー。
ゲスト:大量に発生してる現場なんですね。
MC :ええ、ええ。
ゲスト:ですから、そういったところにいる魚は、やっぱり、そのー、微生物が体の中に入ったりして、
MC :うん。
ゲスト:その毒素で死んでしまう
MC :はい。
ゲスト:あのー、そういったことが起こりますねぇ。
MC :あの、変な話ね、僕このニュース聞いた時に、さ、最初、あのー、魚、マグロが死んじゃった時に、
海に返してやりゃあいいのにとか、隔離できないのかと思ったんです。
ずーっとあのー、葛西の水、水槽にいたじゃないですか。何か、措置なかったのかなと思うんですよね。
ゲスト:えーっと、おそらくですね、それは、あのー、水族館側もですね
MC :ええ。
ゲスト:あのー、ちゃんと考えていて、多分その、あそこでマグロ、あのー、えー、かっ、飼い始めた時からね
MC :はい。
ゲスト:あの、そういった、例えば、あのー、ま、水の中に変な物質が入らないかとか
MC :うん。
ゲスト:それから、マグロがですね、あの、ストレス受けないかとかですね
MC :はい。
ゲスト:多分、色んな事を考えて、そして大丈夫だからということで、
MC :うん。
ゲスト:あの、その、海の中と同じような環境が保たれてる、な、中でですね
MC :はい。
ゲスト:マグロを飼ってたんだと思うんですね。
MC :うん。
ゲスト:ですから、おそらく今回は、やっぱりそういったあの、これまで考えていて大丈夫だと思ったところが、
何かちょっと抜けてたところがあって、
MC :ほー。
ゲスト:あのー、やっぱり原因不明で、あのー、死に始めたっていうことがあったんじゃないでしょうかねぇ。
MC :ちょっとやっぱり、こう、自然界の生き物を人間が飼う事の難しさみたいなものも垣間見える感じですね。
ゲスト:あ、あの、私もちょっとそんな風に感じましたねぇ。
MC :ふーん。ちなみにね、このしょうた君の質問、魚って自然界でどれくらい生きるんだろうかっていう。
魚の寿命って考えたことないね。
ゲスト:そうですね、あのー、
MC :だって、全然考えたことない。
ゲスト:そうですね、あのー、実はですね、魚の寿命、そのー、図る方法ってのいくつかあります。
MC :はい。
ゲスト:で、一つはですね、あの、鱗なんですね。
MC :へえ。
ゲスト:で、鱗にあのー、よく見ると年輪みたいなものが出来て
MC :ええーっ。
ゲスト:で、木の年輪と同じでですねぇ、あの、一年に一つその、筋ができるんですね。
MC :ええっ。ほんとですか。
ゲスト:ええ、で、それで見る事ができます。それから、もっと正確にはですね、
あの、耳、耳石というのがありますね、我々も
MC :はい。
ゲスト:あの、重力を感ずる、その、耳の中に、
MC :うん。
ゲスト:あの、小っちゃい石みたいのがあるんですけども
MC :はい。
ゲスト:あの、魚にもこれがありましてですね、あの、これの断面を見ると、やっぱりそのー、
えー、なんていうんでしょう、あのー、ま、年輪状のものが見えて、
これの方がはっきりと、よくわかるんですね。
MC :魚の耳?
ゲスト:うん。
MC :の中にある?
ゲスト:小っちゃい石、あ、丸い石があるんです。
MC :それはキッズ達にきびしいんで、鱗でいこう、鱗で
ゲスト:そうですね。ええ。
MC :鱗、じゃあ、鯛。ね、鱗のある魚、鯛。鯛の鱗
ゲスト:ええ、あの、
MC :透明じゃないですか?
ゲスト:よーく見ると、そうですね。
MC :うん。
ゲスト:こう、筋がこう、年輪状に丸くなってるのが、
MC :あっ
ゲスト:多分見えるはずです。
MC :年輪状ね。
ゲスト:うん、うん、うん。そうです。で、その年輪の数を
MC :あー。
ゲスト:数えるんですね。
そうすると、えーと、例えば5年生きた魚は、あの、5つぐらい、
この、線が見えてるはずなんですね。
MC :はぁー。神奈川県のみさとちゃん、小学校4年生からいただきました。
友達の家では猫を飼っています。おばさんが猫に餌をあげるのを見ると、
おいしそうなので一度でいいからキャットフードを食べてみたいなぁと思います。
でも友達は、きっとおいしくないよと言います。人間と動物の味覚は違うんでしょうか。
人間の御馳走も動物にとっては、それほど御馳走ではないんでしょうか。
それから肉食と草食は、どういうきっかけで別れたんですか?
なるほど、まずキャットフード、ドッグフードこういった物があるけれど、
確かに匂い嗅いでみると、香ばしいおいしそうな、こう
ゲスト:そうですね、それからあのー、テレビなんかの
MC :ええ。
ゲスト:コマーシャルでも、すごいおいしそうですよね、あれね。
MC :御馳走ですよね。
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :うん。
ゲスト:はい、はい。
MC :で、これをみさとちゃん、食べたいんだと、一回でいいから食べたいんだと。
でもお友達は、おいしくないから止めとけっていうんだと。これまず、どうですか。
ゲスト:あ、そうですね。まず、あのー、ペットフードは衛生上はね、
MC :はい。
ゲスト:人間が食べても大丈夫だと思います、そういった意味ではね。
MC :おおー。
ゲスト:ただし、あのー、ま、動物が感じてる味と
MC :うん。
ゲスト:人間が感じる味はちょっと違うし、
MC :はい。
ゲスト:我々が、そのー、犬とか猫がどんな味で、お、あのー、食べてるかってのは
MC :はい。
ゲスト:それは分かりませんからね
MC :おー。
ゲスト:なんとも言えないんですが、あの、僕もですね、ちょっとネットで調べてみたら
MC :ええ。
ゲスト:やっぱりちょっと食べてみたっていう人の、あの、
MC :あっ、はー。
ゲスト:意見が結構あるんですよね。うん。
MC :ははは。
ゲスト:でも、やっぱりそれはね、見てみると、あまりおいしいっていう話はないんだけれども
MC :ええ。
ゲスト:色んな味がする、たぶんそれは
MC :へえー。
ゲスト:ペットフードの種類によって
MC :はい。
ゲスト:あのー、味が違うっていうことなんでしょうね。
MC :へえー。
ゲスト:ええ。まあ、ただ、あのー、あまりおいしかったっていう意見は、あ、なかったような気もしますね。
MC :あー。
ゲスト:はい、はい、はい。うん。
MC :あーっ、ははは。でも、結局、ね、みさとちゃん、おいしくないっていうお友達の判断は正しいんだ、ね。
で、あと、人間と動物の味覚は違うんでしょうかっていう部分ですけど、やっぱり味覚は違うん
ゲスト:違うんでしょうね。
MC :ですよね。
ゲスト:だから、ただ、我々にそれは分からないんで、あの、ペットフードを開発してる会社はですね
MC :はい。
ゲスト:結局あのー、そういう動物が何を好んで食べるか
MC :はい。
ゲスト:例えば、あの、鰹節が、あのー、
MC :うん。
ゲスト:よく食べるとかね
MC :はい。
ゲスト:あ、それから、マグロよく食べるとか、まあ、そういったことで、あの、多分判断して
MC :うん。
ゲスト:ま、そういったものに、あの、まあ、犬とか猫の口に
MC :うん。
ゲスト:合ったものを開発するってことやってると思いますが、
MC :うーん。
ゲスト:まあ、むしろやっぱり、あの、味も大事ですけど
MC :うん。
ゲスト:あの、健康の維持ということが
MC :うん、うん。
ゲスト:とても、やっぱりペットフードの場合、大事な事ですよね。
MC :なるほど。肉食と草食はどういうきっかけで分かれたのですか、と最後にありますけども
ゲスト:そうですね、はい。あの、肉食の動物と
MC :うん。
ゲスト:草食の動物って、これ、あのー、昔からありますねぇ、例えば、あの、恐竜なんかでも
MC :はい。
ゲスト:肉食の恐竜とそれから草食の恐竜ありますよね
MC :はい。
ゲスト:ですから、そういった意味では、あのー、肉食なのか草食なのかってのは、
ずーっと昔の生物が生まれて進化してきた過程の中で、
もうずーっと昔にもう決まってしまってるわけですね。
MC :はい。へえー。
ゲスト:だから、あの、草食だった動物が
MC :うん。
ゲスト:ある時進化して、肉食になったってことはあんまりないし、
肉食だった動物が、あのー、進化の過程でどっかで、えー、まあ、
草食になったということもほとんどないと思いますね。
MC :はー。
ゲスト:で、最初はおそらく、あのー、言ってみればその、食べ物、
そのー、一番祖先の動物が、何を食べてたか、つまりその、例えばそのー、えー、
木とか植物がいっぱいある所にいて、あの、葉っぱを食べて、あのー、生きられた動物は、
草食になっていく。それから、もっと条件の厳しい所で、その、言ってみれば、
その、仲間の動物を食べるしかなかったものが、あの、肉食の
MC :うん、うん。
ゲスト:系統になっていく。
MC :いや、もう時間だ。あっという間だな。まだ質問来てますので、来週また伺っていきたいと思います。
今週の「サイコー」は、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:どうも失礼しました。 -
「プラネタリウム パート2」 ゲスト:大平貴之さん
2018/08/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ、今週のサイコーもですね、プラネタリウムクリエーターの大平貴之さんです。
またよろしくお願いします。
ゲスト:はい、お願いします。
MC :大平さん、もうすっかりお馴染みです。日本でプラネタリウムと言えば、大平さんと言われるぐらい、
コマーシャルにもなったぐらいなんですけれど、メガスターというプラネタリウム
ゲスト:はい。
MC :これが大平さんが、開発して今も世界中でこのメガスターっていう名前、知られているんですよね?
ゲスト:まぁ、そうですね。ぼちぼち海外にもね、あの入って来まして、今は何か国ぐらい入ってるかな?
はい、色んな地域に入るようになって来ましたね。
MC :実は、僕が住んでる、今、北海道の札幌にもですね、メガスターがね、
お目見えして早速、僕見て来たんです。
ゲスト:はい、はい、ありがとうございます。あの、藻岩山ですね?
MC :はい。観光地ですからね、ぜひ夏休みにね、家族で北海道来るときは、藻岩山行って下さい、皆さん!はい。
ゲスト:はい、ぜひ。夜景が綺麗で、それでレストランとかもあって、それで星を見ながら楽しめる場所ですから。
MC :そう、そう、そうなんです、もう、ぜひ!さぁ、で、このメガスターなんですけれど、
それまでのプラネタリウムは人間が肉眼で見えるね、
6等級や7等級ぐらいまでのしか見えてなかったんですってね?
ゲスト:はい。
MC :うーん、ところが今、メガスターでは、2千2百万個の星が見ること出来るという
ゲスト:そうですね、最大で。しかも、更にその先のモノがですね、
えー、もう星の数が事実上無制限な物も出来ました。
それはどういう事かというと、星の数を自由に変えられるものですね。
MC :へぇ、いわゆるまぁ、確認されている星は全て出せるよ、ってことですね。見える、見えないじゃなくて。
ゲスト:出そうと思えば出せます。はい。
MC :へーー。さぁ、という事で、大学時代までのお話を先週伺いました。
ゲスト:はい。
MC :今度でも、大学から今度社会に出るわけですよね。
ゲスト:はい
MC :それからどうされたんですか、大平さんは。
ゲスト:あのー、しばらく勤めてまして、でー、正直やはり就職したらプラネタリウムは、
もう続けられないだろうと思ってたんですけども、えー、ただ、結構良い会社で、
あのー、色々やっぱり自由で休みとかもね、こう割と自由、自在に取れたりしたので、
で、プラネタリウム、結局はやっぱり作ってたんですよね、家でね。
それで、会社では仕事して、家でプラネタリウム作って
MC :サラリーマンやりながら、趣味のプラネタリウムを?えぇ。
ゲスト:はい。でそこで生まれたのが、こうメガスターで、でそれを色んな所で発表してるうちに、
だんだんこう、それが活動が大きくなって、まぁだんだん、その会社の仕事と両立できなくなって、
結局独立することになるんですけども、まぁそれから、メガスターは2を開発して、
それから、それ科学未来館に設置して会社を作って、
それで色んな所に設置したりイベントやってるうちに、いつの間にか10年経っちゃったって感じですね。
MC :最初の頃、大学時代に作ったモノが、えー、本来9千個ぐらいしか見えないものが、
えー、普通の学生さんが4万個投影できるマシン作って、で専門家の方にこれはちょっと素人としては、
有り得ないぐらいに言われたんですけれど、それがもう、
もうプロフェッショナルな仕様を作っちゃったわけですね?サラリーマンやりながら。
ゲスト:そうですね。はい。
MC :そして、独立して今に至っているという。
ゲスト:はい、はい。
MC :順風満帆でしたか?
ゲスト:うん、まぁもちろん紆余曲折ありますけど、まぁでも、もう一直線に、一直線ていうかなー?
こう、多直線に色んな方向に向かって突っ走ってたって気がします。世界は広がった気はしますね。
MC :へぇー。はぁー。
ゲスト:あのー1つ、こうプラネタリウムを作って、ただこう高性能な物を作って行くっていう事・・・、
だけじゃなくて、それでこう、出たモノ出たモノをこう、色んなとこに出していくとね、
それが全然今まで想像もつかなかったような世界にこう、繋がる。
例えば、その音楽のコンサートで出すとかあのー、カフェとか、バーとかでね、
星を演出しようなんて最初はそんなこと僕も、考えてなかったんですけどね。
あとは、まさかその自分の作った話が、ドラマになるっていうのも想像もつかなかったし、
そういうね、こうなんて言うのかなぁ。僕が想像もしなかったような、
色んな展開があったのが面白かったですね。
MC :いわゆる、コラボみたいなモノですよね?アイデアとアイデアが、持ち寄ってまた融合して、
新しいものが生まれていくという事ですよねー。
ゲスト:そうですね、はい。そうですね、まさに、まさにその繰り返しだったですね。
MC :んー、でもそこは多分、大平さんの存在がなければ、ここまでこなかったでしょうね。
ゲスト:んー、そうですね。まぁ1つだけ、今までのプラネタリウムと違ったのは、やっぱり個人で作って、
でやっぱり色んな意味で自由だったことでしょうね。やはり、どうしても今までのプラネタリウムだと、
例えばやっぱりね、その業界のしがらみとかもあるでしょうし、
えー、それが個人で作ったのだとそれが無いと。で狭い所で上映ね、作って持ち運ばないといけないので、
こうやって軽量になって、そうするとそれが色んな場所に持って行けると、
それ今までの物になかった特徴ですね。そうすると、今まではプラネタリウムっていう場所、
どこかで大きな場所を作って、そこにお客さんを呼ばなきゃいけなかったのが、
今度は人が集まる所にプラネタリウムやる、みたいなね。なんかそういう形になって、
それがこう思わぬ、なんて言うんだろうな、使い道がね、どんどん広がってくみたいな。
MC :へぇー。
ゲスト:もう僕の手をどんどん、ある意味離れてるし、僕をなんか色んなとこにね、
引っ張りまわしてくれてるような感覚ですね。
MC :確かにそうですね。あのー、やっぱりあの、プラネタリウムのドーム状の施設が無ければ、
プラネタリウムってものは成立しないって思ってたものが、ガラッと変わったわけですもんね。
ゲスト:そうですね、それは僕にとっても予想外でしたね、はい。
MC :うーーん、なるほど。
ゲスト:はい。
MC :あのー、まぁプラネタリウムというのは、いわゆる人工的にね、星を映し出しますけれど、
実際自然の中で大平さんが感動したシーンとかね、ご経験は何かあるんですか?
ゲスト:あのー、最初にオーストラリアで天の川を見た時はやはり、びっくりしましたね。
MC :天の川?
ゲスト:はい。それがそのね、本当の空で、これ高校生の時だったんですけど、
あの天の川の1番キレイな部分が頭の上に見えるわけですね、南半球ですと。
で町灯りもあまり無いので、その時に天の川がこう、立体的に見えたんですよ。
つまりその銀河系っていうね、あのー、大きな円盤状になってるっていうのが
目で見て分かるような感じっていうんですかね?
MC :はい、うん。
ゲスト:それが、こうメガスターを作るための原体験になってますし、やはり宇宙っていうのは本当にこうね、
想像もつかないような広がりがあって、っていうね、やっぱりこう、スケールを感じるんですよね、はい。
MC :うーん、あの天の川をじゃあ今、ラジオの前でね、
子ども達がどれぐらい実際見たことがあるかなって思うと、どうなんでしょうね。
ゲスト:まぁそうですね、あのー、都内ではまず見られないですし、
えー、関東一円だと中々見られる場所が少ないですよね。
MC :ですねー、僕の住んでる北海道のね、山の中行ったり、海沿いの街行くとキレイに見えるんですよ。
まだ見えますよ。
ゲスト:そうですね、はい。北海道はいいですね、はい。
MC :はい。これ、もうぜひね、あのー、夏休みね、来てもらいたいなー、はい。
ゲスト:あ、いいですね、はい。
MC :あ、そっか、天の川がもう立体的に見えるっていうもう、イメージ分かります。
じゃあ、そんな感動を味わえる大平さんのイベントが、近々あるんですって?
ゲスト:はい、まずですね、えー、あの東京のあの現代美述館ですね、
そこで、えー、6月からメガスターと、を、上映するイベントをやります。
MC :はい、8月31日まで?
ゲスト:はい、そうですね。
MC :東京都現代美術館。
ゲスト:はい、あとはえー、千葉県立現代産業科学館、そこでやはりメガスターの上映するイベントを開催します。
MC :それは8月の6日から、8月31日までという事で。
ゲスト:はい、そうですね。ここは最新のメガスターの、今までとはちがう、
全く違う物を上映しますので是非、ご期待下さい。
MC :これ夏休みのお子さんたちには、自由研究にはもってこいですよね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :うーん、いやでも、メガスターもさることながら、やっぱり、やっぱり大平さんの、今ね、
眼を見ながら2週に渡って、お話を伺ったんですけど、やっぱりキラキラ星以上に輝いてますね。
ほんとに40代半ばで、キラキラされていて、好きなことを仕事としてそのまま大人になっちゃったという、
代表的な方ですね。
ゲスト:うーん、あぁ、ありがとうございます。
MC :いやいや褒めてるかどうか、分かんないですけど。
いや、ほんとにあのー、8年掛けてやっとお会いできたサイコーで、
あの七夕の前にふさわしいサイコーだったような気が致します。
あのー、ぜひあのー、この文化放送でイベントなどもやってますので、
大平さんまた、機会があったら是非、ご参加下さいね。
ゲスト:はい、あ、そうですね。はい、お声かけいただければ、メガスター持って参上しますので。
MC :はい、よろしくお願い致します。
今週のサイコーは、プラネタリウムクリエーターの大平貴之さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:はい、ありがとうございました。 -
「プラネタリウム パート1」 ゲスト:大平貴之さん
2018/08/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ、今週のサイコーはプラネタリウムクリエーターの大平貴之さんです。こんにちは。
ゲスト:はい、こんにちは。
MC :あぁ、大平さんは、あのー、プラネタリウムと言えば大平さん、というあの、
コーヒーのコマーシャルでも有名な方で、僕はあの、8年前にこの番組が始まる時に
実はゲストとして大平さんにもう、ぜひ来て頂きたいという
ゲスト:あー、そうですか。
MC :初期の頃から、ずーっと考えていまして、やっと叶いました。
ゲスト:ありがとうございます。いやー、そんな風に仰って頂いて。
MC :いやー、七夕を近くして、やっと織姫と彦星の気分ですね。
ゲスト:えへへへっ。
MC :いや、ほんとにねー、いやー、ようこそいらっしゃいました。
ゲスト:はい。
MC :さぁ、そんな大平さん、プラネタリウム、興味を持たれた。
子どもの頃にじゃあ最初、ご覧になったんですね?
ゲスト:そうですね、小学校
MC :何歳ぐらい?
ゲスト:小学校ね、4年生ぐらいかな?
MC :一般的ですね。
ゲスト:はい、はい。
MC :みんな、その頃ですよね?
ゲスト:まぁ、そうですね、はい。
MC :それ、かん、それ、なん、どれ、何を見て感動されました?
ゲスト:いや、もうとにかく星が綺麗で、えー、その川崎の本当の空だとね、
まばらにしか星が見えないんですけど、プラネタリウムの中って真っ暗になって、
で、富士山のてっぺんで見た星空です。ドーンて見えるじゃないですか。
うわ、キレイだなーと思ってね、とにかくやっぱりそれを本当の空でもちろん、
見てみたいって最初は思ったんですよ。
MC :えー。
ゲスト:でも、中々そのー、ね、小学生が気軽に山奥とか行けないじゃないですか。
で、そうこうしている内に、じゃあそのプラネタリウムって物を作ってみたいな、と思って、
で、とにかくそのー、なんて言うんだろう。なんでも自分で作るのが好きだったんですよね、はい。
MC :すごいですね。それ、すごいですね。
ゲスト:まぁまぁ。
MC :プラネタリウム作っちゃおうって普通思わないですよね。
また行きたいとかあるかもしれないけど、作っちゃおうっていう。
ゲスト:うん、まぁはい。うーん、でもね、なんでも真似して作るっていうのが好きで、
例えばその電池とかモーターとか、もうなんでもそうですけど、その既製品であるものを、
いかにその自分の力で再現するっていうのがね、やっぱりまぁ、こう工作少年ていうか、
理科少年ていうかね、そういうのが凄い好きだったんですよ。
だからそこの所にプラネタリウムもね、こうなんかハマっちゃって。
MC :あー。
ゲスト:それでやっぱり、こうスケールが大きいじゃないですか。
それで自分の部屋をね、ああいうプラネタリウムみたいにして、
こう太陽が昇ったり、月が昇ったり、星の動きとか、そういうのを表現できたら面白いだろうなって、
そんな風に思ったんですね。
MC :僕も子どもの頃ね、レモンで電池作ったり
ゲスト:あー、ありますね。はい。
MC :コイルと磁石でモーターまでは作りましたよ。
ゲスト:はい。
MC :あとね、車まではなんとか作りましたよ。動く車をね。
ゲスト:あー、あの、はい。モーターでね、はい、はい。
MC :プラネタリウムは、でもさすがに思わなかったですけど。
ゲスト:はい、でもね、あのー、原理は簡単ですからね。
MC :えー。
ゲスト:あ、あのー、いやほんとにそのー、あのー、簡単なやつはボール紙に穴開けて、
で中に電球入れて、それでそのね、光を通すだけで、そのピンホール式っていうのはそれですから。
MC :はい。
ゲスト:でもー、まぁ凝り性なんでしょうね。それで飽き足らなくなって、やっぱり最初ピンホールのでね、
星を映してもあんまりキレイじゃなくて、で科学館とか見るとね、はっきり星が映るわけですよ。
あれをなんとかやってみたいなってね、思うようになっちゃって、もう止まんなくなっちゃったんですよね。
MC :へぇー。え、小学校4年生で見て、で、まずピンホール?段ボールに穴開けたのがその直後ぐらいですかね?
ゲスト:はい。
MC :で次の発展したのは、何歳ぐらいでどんなもの作ったんですか?
ゲスト:えー、小学校4年、5年ぐらいでピンホールでいくつか、簡単なのを作って、
でそれで、6年生ぐらいの時ですね、初めてレンズを使った物を作ろうと考えて、
それであのー、レンズをね、レンズ工場とか色々片っ端からあたって、たまたまね、
こうたくさん分けてくれた工場があったんですよ、レンズを。考えられないんですけどね。
MC :へぇー。
ゲスト:それで、途中まで作ったんですけど、まぁどうしてもいくつか越えられない壁があって、
まぁその時は諦めちゃったんですけども、それがやっぱりその当時、プラネタリウム、
まぁピンホールをいくつか作って、レンズ式、でもそれはダメでとりあえず諦めて、
そのーいくつか、いつか、その、作りたいって気持ちだけを残して、みたいなね。
そんな感じだったですね。
MC :はー。え、その後それで、そのレ、レンズはちょっと諦めて?
ゲスト:はい。
MC :で、次はどういうステップになってくるわけですか?
ゲスト:それからは、中学生の時はあまりプラネタリウムはやらなくて、結構ロケット作ったりとか、
そういうのに夢中になっていて、はい。空、飛ぶのが結構、面白くてね、
それで、この固体燃料ロケットをズドーンと打ち上げてね。
MC :え、本格的ですね。
ゲスト:そうですね、かなり大きなものも作りましたね。はい。
MC :へー。それ、多摩川の河川敷辺りでやったわけですか?
ゲスト:そうですね、あ、多摩川はね、あのー、多摩川いったかな?あのー、まぁ、まぁ似たような感じですね。
例えば生田緑地とかね、ほんとはあそこやっちゃいけないらしいですけど。
MC :えぇ、まぁまぁちょっと時効という事で。えぇ、えぇ。
ゲスト:あのー、まぁ近くのね、野球場とか、まぁそういうのでやって、まぁ高校、大学ぐらいになるとね、
かなり山奥まで行って、もう1キロ2キロ飛ぶようになると、あのーいずれはね、
あの友達を乗せて人工衛星を打ち上げたいなんて考えてたんですけど、はい。
MC :すごーい。
ゲスト:まぁ、とてもねぇ、それは無理でしたけどね。
MC :10代でそこまで考えて、えぇ、でまたプラネタリウムに戻ったのは、いくつぐらいですか?
ゲスト:そうですね、高校生の時は両方、並行してやっていて、でー、高校生の文化祭でピンホール式をかなりその、
なんていうかな、性能を上げたものっていいますかね、そういうのを2つ作って、
で、文化祭で公開したんですよ。
MC :えぇ。
ゲスト:で、そのー、それまでは自分の部屋で作って、なんとなく上映していたのが、
その文化祭っていう場でそのー、お客さんに見せるっていうのを初めて経験して、
えー、でー、それがすごく楽しかったですよね。それでますますハマっちゃって、
やー、でもやっぱりレンズ式作りたいなっていう思いだけが残って、
で、大学に進学すると同時にレンズ式プラネタリウムに着手と、もう一度。
MC :それもレンズ式というのが、よくプラネタリウムで見るシステムですよね?
ゲスト:つまり科学館にある、立派なプラネタリウムの仕組みで、
しかしそれは個人で作るのはとても出来ないと。はい、もうドイツとかあのー、そういうね、
せん、元々ドイツ製の物で、それを国内のメーカーが国産化に成功して、
やっとこさで出来てるものをこんな個人で作るなんてとんでもないって言われてた時代ですね、はい。
MC :でもそれをやっちゃったわけですね。
ゲスト:まぁそうですね、はい。大学時代に4年掛けて、やっとこさで完成させました。
MC :ふーーん、それは出来ばえはどうだったんですか?
ゲスト:えーっと、そうですね、まぁ細かい所はね、色々とあるんですけども、
ただ基本的には既成のプラネタリウムに、ほぼ匹敵する能力、
まぁ1部ではそれを上回るような能力の物が出来て、
そういう意味では今までのプラネタリウムとほぼ同等の物を作りたいっていう夢は、
ほぼ実現できたかなって気はしますね。
MC :ほー、それは高校時代のピンホール式を皆さんに見せた時の感動、がまたよみがえってくるわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :それ以上の喜びになってくるわけですね?
ゲスト:そうですね、やっぱりあのー、星が4万個ぐらい映って、で、直径が10メートルぐらいのね、
ドームですから、それなりに規模も大きくて、いわゆるそのー、
普通の公営のプラネタリウムに全く引けを取らないような物だったと思います。
MC :はぁー、4万個。
ゲスト:はい。
MC :通常ね、僕らのいわゆる、まぁあのー、大平さんが作ったものでないプラネタリウムより
既存のプラネタリウムだったら、星っていくつぐらい見えてたんですか?
ゲスト:大体、標準は9千個ぐらいですね。
MC :9千個ぐらい?それで僕ら日本人て、わー、すごいって言ってたわけですよね?
ゲスト:はい。
MC :それが、大平さんは素人で4万個のプラネタリウムを、まず作った?
ゲスト:はい。
MC :それは業界では、どう言われたんですか?
ゲスト:まぁ、やはりビックリされたと思いますね。
MC :うん。
ゲスト:あのー、まぁやはりその個人で出来ないものを、個人でまず、
その、いわゆるその専門のメーカーとのね、いわゆるプロにだけ許されてた世界を
こうアマチュアで作ってしまったっていう事で、うーん、なんて言われたかな。
まぁ、あのー、メーカーはメーカーのメンツが立たないな、みたいな事を言われたかな。
MC :あー、そうですかー、それ大学時代に作ったわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :4万個。で、ちなみに今の大平さんのプラネタリウムは何個、投影できるんでしょうか?
ゲスト:えーっと最大の物で、2千2百万個ですね。
MC :ふっふっふっ。えっと、えー、お父さんたち!お父さんたち子どもの頃は9千個のプラネタリウムで、
僕ら子供たちの頃ね、子どもの頃ね、感動してたの。
今や、2千2百万の星が映し出せるプラネタリウムになってる。
それが大平さんの「メガスター」というプラネタリウムなんですね。
ゲスト:はい。
MC :さぁ、もう時間ですよ、大平さん。さぁ、メガスターという2千2百万個、
投影できるプラネタリウムに関しては、来週お話を伺いたいと思います。
ゲスト:はい。
MC :ワクワクして来ましたね。今週のサイコーは、プラネタリウムクリエーターの大平貴之さんでした。
また来週お願いします。
ゲスト:はい、ありがとうございました。 -
「公開録音 ロボットの科学 パート2」 ゲスト:富山健さん
2018/07/01 Sun 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、続きまして次の写真いきましょうか。はい、これ、
子供 :知ってる。
MC :え、見たことある?
子供 :見たことなーい。
MC :未来館へ行ったことある人。
子供 :はーい。
MC :そう、未来館にこれあります。
ゲスト:あります、明らかにありますね。
MC :ね、なんか、あのよ、よく言えば掃除機みたいなロボットな感じもする。
ゲスト:あはははは。
MC :悪く言ったら、ゴキブリみたいな
ゲスト:ゴキブリじゃーねー
MC :形のロ、ロボット、平べったーいのが出てきてー、これ何ですか、先生。
ゲスト:これはあのー未来の乗り物ということを想定して作ったロボットなんですけども、
MC :はい。
ゲスト:あの4本、傍らに4本ずつついてますよね。これが車輪にもなるし足にもなるし
MC :うん。
ゲスト:動物みたいな歩き方もできるし、昆虫みたいな歩き方もできるし、
MC :うん。
ゲスト:そうするとですね、段差があっても段差気にしないで水平のまま乗り越えたりとか
いろいろ面白い事出来るんですね。
MC :はーい。
ゲスト:だから、行ける、どこでも行けるしー、人間にとって乗り心地もいいしという
ロボットカーのコンセプトモデルですね。しかもガタンとならずに行きますから、
MC :えー、そうですか。
ゲスト:素晴しいですよ。
MC :先生も是非あの国産で、あの日立さんとうまく
ゲスト:ははははは
MC :じゃあ開発してですね、日立のすごい段差をものともしない
ゲスト:はい。
MC :ロボット型掃除機を
ゲスト:作りたいと思います。
MC :えー、今日いる、今日このメンバーでみんなで作りましょうか。
ゲスト:あ、いいですね。
MC :開発して
ゲスト:そしてみんなで儲けようか
MC :儲けよう!
ゲスト・MC :ははははは。
MC :さあさ、続きましてこういう風なね、あのいろんなところ、段差をものともしないロボット、
使い道はねほんと無限大にありますよ。みんなもなにかアイデアがあったらね、
富山先生の方に「こんな使い方したい!」とか、
「こういう掃除だけじゃなくてこういう風なロボットがあったらいいな」と提案すると
先生が具体的に品物にしてくれるかもわかりません。
ゲスト:やりたいね。
MC :ね。
ゲスト:アイデア大切だから
MC :アイデア、そうそう。みんなが不便に思ってること、こういうのは私たちじゃ、
僕たちじゃ無理だからロボットがいたらなぁー、っていう、
そういうのが実はきっかけでロボット開発って生まれる
ゲスト:そういうことですね。
MC :ということなんですねー。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :さ、次です。これおっきいよ。大人の人の身長よりもおおっきいんだけどー、足だけが見えてます。
ゲスト:まだ足しか出来てないんですが、
MC :ね、足だけで2メートル
ゲスト:そうですね。
MC :ぐらいあるロボット。
ゲスト:コアというロボットなんですけれども、
これはもうとにかく200キロぐらいのものを運べちゃうというよりも、
ま、太ったお相撲さんでもこの上に乗っかって行けますよっていう。みんな車椅子って知ってるよね。
MC :うん。
ゲスト:車がついている椅子。あの車椅子ってさー、段差とかめんどくさいじゃん?
だから車じゃなくて足がついている椅子だったらいいと思わない?
子供 :思うー。
ゲスト:うーん。だからこいつはね足椅子っていうんだよ。
子供 :足椅子
MC :うん。足椅子。
ゲスト:だからこの上に座ってこの足が歩いてくれるわけ、代わりに。
だから階段でもなんでも関係なく行けちゃう。
MC :うーん。
ゲスト:でもね、人間って重たいんだよー。
人間はすごく重たいからおっきなロボットちゃんじゃないとなかなか難しいんだよね。
それでこういうでかいの作ってる
子供 :どうやって乗るの?
ゲスト:どうやって乗るの?こいつがひざまずくの、こうやって。
MC :このロボットの足くんがひざまずいて、
ゲスト:うん。
MC :人間乗っけてくれて、で人間はその
ゲスト:うん。
MC :上で操縦するということ。
ゲスト:そういうことです。
MC :いいですねー。あのー思いきり冷たい氷の上裸足じゃ歩けないじゃない
ゲスト:はっはっはっは
MC :思いきり熱い鉄板の上裸足じゃ歩けないじゃない、
こういう時に足椅子があると、どこでも行けるよっていう。
ゲスト:ね、いやー。そう。
MC :これもロボットなんですねー。これは開発もう出来てるんですか?開発途中なんですか?出来上がって
ゲスト:この足まではちゃんと出来上がってますね。
MC :あ、足までは出来てる
ゲスト:この、あのーあそこにいる二人が作ったんですけれど、二人とも私の弟子ですけれども、
これもやっぱりフューロのこのチームが作ってますね。
MC :はーい。ねー、なんかアイデアあったらほんとなんか楽しいよね、こういうの。
いろんな風にロボット作る人って、
ゲスト:そうですね。
MC :それがまた実現しちゃうところがすごいよね。
ゲスト:そうですね。私のいるところの名前が未来ロボット技術研究センター、
フューチャーロボティクスで、フューロ、っていうんです。
MC :フューロってこれ書いてる、これね、FURO、先生の研究機関。
ゲスト:お風呂じゃないよ、お風呂じゃないよ。
MC :フューチャーって未来です。そう、ふ、風呂じゃないよって。
ゲスト:うっふっふ。
子供 :風呂、ふふふ
MC :先生もロボットの事いうのに、面白い事もおっしゃいますねー。風呂じゃないよってそうですねー。
ゲスト:なんてったって、名前がとやまけんなんで。
MC :えー、とやまけんさんです。
ゲスト:とやまけんのお風呂です。
MC :ふふふふ。さあ、次です、これ最後の写真ですか、次が。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:これ。
子供 :おー、おもしれー、
MC :あ、みんな喜んでる。一番最後。
子供 :カブトムシ!
ゲスト:そうです、カブトムシです。でっかいカブトムシです。
MC :あのー、お父さんお母さん世代はタイムボカンのイメージですよね、
ゲスト:あはははは
MC :僕らはね。
ゲスト:なるほど、そうですね。
MC :タイムボカン。
ゲスト:そうですね。
MC :ドクロベエ様とか知ってる?
子供 :あーあーあー。知ってる。
ゲスト:知ってるんだー。
MC :え、ドクロベエ様知ってるのー?ほんとー。
子供 :うん、ヤッターマンのやつ
子供 :ヤッターマンとかそういうの・・
MC :えっ、ヤッターマン知ってるのー?
子供 :知ってるー。
ゲスト:すごーい。
MC :君たち、やっぱりほんとは40代だろ。
子供 :6歳だよ!
MC :6歳か!ヤ、ヤッターマンとかタイムボカンを知ってる。
子供 :見てるよ。
MC :え、そうですか。今これチャンネルも多様化して、昔のアニメも再放送されるから、
良い時代でこれこそほんとにカブトムシ型ロボットですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :うん。
ゲスト:ばーかでかいですよー、上に乗ると、ほんとにもう下がこんなになって怖いぐらい大きいですよ。
MC :で、このロボットはちなみに何の役に立つんですか?
ゲスト:遊びですね。
ゲスト・子供 :あはははは。
MC :ロボットの開発っていうのは、遊びながら人の役に立つってことなんですかね。
ゲスト:ロボットって作るの楽しいんですよ。
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:めっちゃくちゃ楽しいです。だから大学、私が、ま、去年までいたところっていうのは
未来ロボティックス学科っていう学科なんですけれども、
MC :うん。
ゲスト:そこでは一年生からロボット作らせちゃうんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、いったん作った、自分の作ったロボットが動くでしょ。そうしたら面白いと思わない?
も、楽しくなっちゃってね、帰らないんですよ、大学にいて。で、そうするとどうなるかわかります?
MC :え、そしたら家を顧みなくなるとか、
ゲスト:顧みなくなりますよー。
MC :へへへ、家庭を顧みなくなる、ちょっと難しい話ですねー。
ゲスト:はっはっはっは。いやいやもっと簡単な話です。
MC :お父さんが家に帰ってこなくなっちゃう、あー、もっと簡単な話。
ゲスト:はい。学生さんたちがずぅーっと同じ部屋にいてー、まー、お風呂も入んないわけです。
MC :はい。
ゲスト:すごい臭いです。
子供 :ははははは。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:ふふふふ、すごく臭くなっちゃうんです、部屋が。
MC :え、ずぅーともうでもいわゆる没頭しちゃうということですね。
ゲスト:そうです、だからたまには帰りなさいと。
MC :うーん。ねぇー。
ゲスト:1週間に1度は帰れ、と。
MC :あのー、僕なんかこれからね、例えば僕の親なんかは70代ですよ。
ゲスト:はい。
MC :ま、元気にしてるけれどー、
ゲスト:はい。
MC :ただ遠くに住んでるとー、
ゲスト:うん。
MC :ちょっと親大丈夫かなと、
ゲスト:うん。
MC :ま、携帯電話っていうげんり、便利なものがあるけれどー、
じゃあ何かこう親の面倒をロボットがみてくれたら楽だなーと思ったりするんですけれどー、
どうですかねー、介護ロボット。
ゲスト:介護ロボットですか、えーとね、すごくこだわりがありまして、
MC :えー
ゲスト:はい。介護ロボットは作りません。
MC :作らない!
ゲスト:あはははは。
MC :作らない!
ゲスト:実は介護ロボットではなくて私は介護者支援ロボットを作っています。
MC :それ、ちょっと似てるんだけれど、違うんですね。
ゲスト:全然違いますよー。
MC :介護者っていうのは
ゲスト:はい。
MC :僕みたいなあるいはお父さん
ゲスト:そう。
MC :お母さんみたいな
ゲスト:はい。
MC :年上の方、おじいちゃんおばあちゃんを介護する人、を介護者、で、介護者を支援するロボット。
ゲスト:そうなんです。あの介護者の方がすごい大変ですよね、いろんな意味で。はい。
そのあのですのでー、その介護をする方が楽に介護をできるようにするためのロボットを作ってます。
MC :例えばどんなのでしょうか?
ゲスト:例えばー、ロボット、まわかると思うんですけれども、
人間が得意なこととロボットが得意なこととって違うんですね。
MC :はい。
ゲスト:ロボットってさあ、すごく我慢強いと思わない?
MC :うん。
ゲスト:だから、そこにいて何か見てなさいって言ったら、ずぅーと見てるよねー。
子供 :あははは。
ゲスト:でも、君たちそう言われたらー、何分もつ?
子供 :あー、5分ぐらい
ゲスト:5分もつか?
子供 :150分ぐらい。
MC :えへへへへ。
ゲスト:うそだよー、私3分ももたないよ。だからそういう意味であの観察しててもらうとか、
それとかーセンシングっていうんですけども、なんかをね、見つけてくれる能力がすごくあるんですよ。
MC :うん。
ゲスト:だから、たとえばーまあ、あの人間ていうのは、いつ食べる、いつ薬飲む、いつお水を飲む、
いつ排泄をする、そういうことってものすごく大切なんですけども、
そういうのを自動的に検知して教えてくれるっていうそういうロボットさん。
MC :いわゆる、その不具合みたいなものを教えてくれる
ゲスト:そうです、そうですねー。
MC :そうすると、介護者からするとー、100パーセント介護してなくて大丈夫?
ゲスト:そうなんです、そうなんです、だから休めるんですよ、介護してるひとが。
それってものすごく大切でー、ですから、今、私は私の学生さんたちを介護施設に必ず送って、
で、実習をやらせてるんですね。
MC :はい。
ゲスト:それこそ、
MC :実際高齢の方が
ゲスト:そうです。
MC :どういう風な不具合があるかとか、
ゲスト:そうです、そうです。
MC :介護する方がどういう
ゲスト:そうです。
MC :こと考えて介護されているか。
ゲスト:そこでー、どんなロボットが必要ですか?どういう事をして欲しいですか。
子供 :はい!
ゲスト:ということをやってそういうので作ってます。
MC :あっ、もうお時間になりましたねー。
それじゃみんな、拍手でー「有難うございました」って言って、拍手しようか。ね、
それでは今週のサイコーは富山健先生でした。有難うございました。
子供 :有難うございましたー。
MC :はい。先生、有難うございましたー。 -
「公開録音 ロボットの科学 パート1」 ゲスト:富山健さん
2018/07/01 Sun 12:00 カテゴリ:科学MC :それでは、みんな呼びましょう。せーの
子供 :サイコー
MC :はい、お願いいたします。
今日のサイコーは千葉工業大学未来ロボット技術研究センターの富山健先生です。
拍手ー。先生、ようこそー。
ゲスト:はい。
MC :おかけになってください。
ゲスト:とやまけんです。
MC :ふふふふふ、富山健先生です。先生ちなみに
ゲスト:はい。
MC :あのロボット研究の第一人者でー
ゲスト:うっふ、はい、有難うございます。
MC :もう日本にある便利なロボット、
ゲスト:はい。
MC :もう働くロボットたちっていうのは大体先生の手に掛かって誕生したって言われてる。
ゲスト:いや、そうです。いや、うそです。
MC :うはははは。それぐらいですよ。
ドラえもんは猫型ロボットっていうけど、ドラえもんの開発はやっては?
ゲスト:大変ですね、あれは、はい。あれはやってませんね。
MC :あれはちょっとやっぱり考えにくいですか。
ゲスト:ちょっと難しいですね。
MC :そもそもロボットって何ですかね。
ゲスト:そもそもロボットって何でしょう。何だと思いますか?
MC :どういうものをロボットっていうんですか。何までロボットっていうんだろう。
ロボットって何だ、はい、わかる?
子供 :はい!
MC :はい。
子供 :人助け
MC :お!
ゲスト:おー、そうだねー。そういうロボット一生懸命作ってますよー。
子供 :はい!
MC :あとはー、はい。
子供 :動くやつ。
MC :動くやつ
ゲスト:動くやつ。確かだ、動かないとロボットじゃないな。
MC :人助けする、動く、
子供 :はい!
MC :はい。
子供 :えっと操縦が出来る。
MC :操縦が出来る。
ゲスト:操縦が出来る。
子供 :はい!
MC :はい、どうぞ。
子供 :歩いたり、人助けをしたり、いろいろなことができる。
MC :うん。
ゲスト:なるほど。
MC :しっかりしゃべるねー、みんな、ねー。いいよ。はい。
子供 :火災現場に行ける。
ゲスト:火災現場にいける、いいこと言うねー。
MC :あ、人間の入れない所ね
ゲスト:いいこと言うねー。
MC :先生、
ゲスト:はい。
MC :今日のキッズたちは
ゲスト:すごいですねー。
MC :よくわかってますね。
ゲスト:はい、はい。
MC :概ね答えは、これでよろしゅうございますか?
ゲスト:そうですね、ですけどもロボットがどういう風なもので出来てるかって、これ見てわかるかな?
MC :ふん。
子供 :はい!
MC :はい。
子供 :人間が作っても電池だけで動けるすごい
ゲスト:そうだね、電池使ってるよね。それから、
子供 :プラスチックとか鉄を使用している。
ゲスト:プラスチックとか鉄、そうだねー、それから?
子供 :コンピューター
ゲスト:コンピューター、そうなんですよ。コンピューターがね、こいつらロボットの心臓部ですね。
MC :うん。
ゲスト:でもこれ動いてるよねー、何で動いてると思う?
子供 :モーター
ゲスト:モーター、言われちゃったねー、そうだね、そう。
モーターとー電池とーそれからコンピューターとー、から、ボディーがないといけないよな、体。
それと足かこういうタイヤがなきゃいけないですね。
そういうものを組み合わせて、ほんとは自分で動くやつがロボットって言うんだよ。
MC :ほ、自分で動くやつをロボットでいうんですか。
ゲスト:そうなんです。
MC :今、でもコントローラーで動いているじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :これロボットじゃないんですか?
ゲスト:これはー、今こういう、あのモードがいろいろありまして、
MC :はい。
ゲスト:モードっていうのはあのコントローラーで動かすっていうのもありますし、
それからこいつが自分で動くってやつもあるんですね、
MC :はい。
ゲスト:それはプログラムの違いなんですね。
MC :はい。
ゲスト:だから、コンピューターの中に入っているプログラムをどういうのを使うかで、
自分でコントロールしたらいい、だって自分でコントロールするの面白いだろ?
MC :はい。
ゲスト:だから、そういうのもあるわけです。
MC :なるほど。さあ、実際でもこのロボット製作っていうのは
小学校の高学年ぐらいから出来るということなんですけれどー、
ゲスト:はい。
MC :こういうロボットっていうのは男の子も女の子もみんなやろうと思えば出来るわけですよね。
ゲスト:できます、はい。
MC :じゃあ、今日集まってるねー、
ゲスト:出来ますよー
MC :あのー男女はだいたい半分半分ぐらいですけれど、女の子もロボット出来るということですけれど、
先生はロボット作りに興味を持ったのはどういうきっかけですか?
ゲスト:最初はですねーま、大抵の方は鉄腕アトムって言いますよねー。
それとかいろいろあるんですけれど、私の場合は、
MC :先生、多分ね、集まっているキッズは平成生まれだからー、鉄腕アトムまず知らない
ゲスト:知らないかー。
子供 :知ってるー
ゲスト:知ってる?
MC :え?
ゲスト:え、知ってんの?すごい!
MC :え?鉄腕アトム知ってる人。
ゲスト:あっすごい!いるんだ!
MC :8割のキッズが知ってた!
ゲスト:すごい!
MC :君たち平成の皮を、顔をしたほんとは大正生まれじゃないのかい?
子供 :マジンガーZも知ってる
MC :マジンガーZも知ってるの?
ゲスト:あー、すごいなぁー。
子供 :あとガンダムも知ってる
MC :ガンダムも知ってるの?
子供 :だって知ってるよ。
ゲスト:知ってるか。
MC :お父さんお母さんいい教育されましたね。よかったです。
や、同志と呼ばせてください。みんなわかってるんですね。
ゲスト:そうですねー。
MC :はい。
ゲスト:ですけど、私の場合はですね、あのーま、映画だったんですけど、ロビーというものが出てたんですけど、
MC :ロビー、これ。
ゲスト:こいつ、こいつ知ってます?お父さん、お母さん知ってる人います?
MC :え?知ってるの?ロビー。え、キッズも知ってますよ。お父さんお母さんご存じですか?ロビーって。
ゲスト:知らない。
MC :逆に、
ゲスト:逆に、
MC :逆にお子さんの方が知ってるという、このロビーって先生が子供の頃からあったんですか?
ゲスト:そう、私が子供の頃ですね。私がだから6歳か7歳ぐらいの頃にアメリカの映画で出てきた、
MC :はい。
ゲスト:ロボットなんですね。
MC :ほぉー。
ゲスト:のちにあのテレビのシリーズにもなったんですけども、いかにもメカでしょ、これ。
あのー鉄腕アトムってあんまりメカメカしくないじゃないですか。
MC :人間っぽいですね。
ゲスト:そうなんです。ほんとに作られている物って感じしないんですけど、
これはなるほど、これなら、ほんとに機械で作れるかもしれない、
MC :はい。
ゲスト:そこから興味が出たんですね。
MC :へぇー、
ゲスト:えっ、これって作れるんじゃないの?という、鉄腕アトムは作れないかもしんないけど、
こいつって作れそうじゃない?なんか。
子供 :作れそう。
ゲスト:ねー。
MC :実際ね、高校生の女の子でもロボット作っちゃうという時代らしいんですけれど、
ゲスト:そうです、そうです。はい。
MC :この今作ってる写真ってあるみたいなんですけれどね、高校生が、女の子が
ゲスト:出しますか?
MC :この、女の子ってのはどういうあれですか?その作ってる
ゲスト:出しますか?
MC :これ、これの喜んでる、これもロビーみたいなロボット作って
ゲスト:そうですね、あのー手前にありますあのえっあのーま近藤化学のKHR1というキットなんですけど、
それを作ってんですね。
MC :あー
ゲスト:で、この子達はあの高校生なんですけれども、全然その作ったこともなて、
初めてこういうことやったわけですね。でもこのキット1時間ちょっとで彼女たち作っちゃったんです。
MC :はい。だから10代の頃からロボットは作ることできますからね。
ゲスト:作れます、はい。
MC :で、先生ロビーっていうのに興味を持ってそれがじゃあ50年ぐらい前ですか?
ゲスト:そうね、はっはっは、もっと前です。
MC :もっと前、半世紀以上前に
ゲスト:そうですね、はい。
MC :ロビーに興味があり、そのままお仕事にしてしまったということですね。
ゲスト:50年以上前なんですけど、年が、年がばれちゃうじゃないですか。
MC :えーえー。いやいやいや。さあ、他にも写真を見せて下さい。
ゲスト:はい。これですね。これは知ってるかなー。
MC :知ってるー?
子供 :知ってる。見た事あるー。
ゲスト:特に、特に左側のやつは知ってるかなー
MC :ね、この、そ、左側、さっきさー、あの火事の場所にロボットが行くっていったでしょ?
ゲスト:うんうんうん、言ってたよね。
MC :ね、こういう人間の入れない危険な所で活躍しているロボット、どこかわかる?
ゲスト:はっはっはっは。
子供 :それはあの、タンスのすき間とか。
ゲスト:あっはっはっは。しゃんとしてるなー。
MC :タンスのすき間?ちょっと近いけどー。は、はい。知ってる?わかる?はい、どうぞ。
子供 :原子力発電所。
MC・ゲスト:そうです。
MC :ね。
ゲスト:そうです。あの福島の原子力発電所の事故がありましたよね。で、あの建屋っていいますけど、
原子炉が置いてある建物の中、それは放射能がすごいので人間は入れないんですね、
人間が入ったら3分で死んじゃうんです。ほんとすごいとこなんだけど、
そういう所に入っていって中の状況を調べてるのがこのローズマリーさんです。
MC :はい。あのーまだみんながね、えー今から3年ぐらい前になりますけれど、
やっぱり福島の瓦礫の間をね、カメラを持って撮影したロボットです。
ゲスト:そうです。
MC :今、福島の原子力発電所はこうなってますっていう、実は人間が入れなくて
ゲスト:入れないです。
MC :この先生の作られたこのロボット、ローズマリーって可愛い名前ですね。
ゲスト:可愛いですね、はい。
MC :ハーブ系の香り漂うような感じですね。
ゲスト:一応花の名前をつけてたんですね。
MC :なんでローズマリーってつけたんですか?
ゲスト:Rですね、
MC :えっ?
ゲスト:Rですね。ABCでいってRまでいったんでローズマリー
MC :あっ、えーーっ。え、Aは何だったんですか、じゃあ
ゲスト:もう覚えてないですよ。
MC :AからアルファベットでRに開発したのがローズマリー。
ゲスト:そうですね、あのーヒューローという私のいる研究所のこの、
えーまいろいろなグループがあるんですけど、
そのうちのひとつがこのーロボットを作っているグループです。
ゲスト:すごいですねー。はい。
MC :え、O、P、Q、R、その後S、Sはなんと、Sはなんて名前ですか?
ゲスト:桜です。
MC :これですね、じゃあ、だから、Rの次はSです、
ゲスト:はい。
MC :そしてこれ、字読めないでしょう?これ、昔の又、又先生もあのーハイカラな名前つけたり、
あのすごく難しい、これ櫻二号って読むんです。
ゲスト:櫻二号
MC :古い漢字、ですね。
ゲスト:みんなエバンゲリオン知ってるよね。ほらー、こういう字使ってるよね。
MC :知ってるんですね、ちゃんとね。今の子たちもちゃんと。
ゲスト:そうですね。すごいですね。
MC :そうか、で、これ櫻二号、だからこのローズマリーのあとに開発された、新型災害対策ロボット。
ゲスト:そうですね。
MC :これどういう動きをするんですか?
ゲスト:これはー、もっといろんなとこに行かれると。
MC :はい。
ゲスト:例えば水の中も入って行かれますし、
MC :うーん。
ゲスト:そういう事が出来るので、どこでも行かれちゃう。
MC :あのー、広島県でもね、みんな夏休み期間中だったけれど、土砂崩れってのが起きて、ね、
多くの人が亡くなったじゃないですか。
それで救助にあたっていた消防隊員の方も亡くなったりしているので、
ゲスト:そうですね。
MC :こういうところにひょっとしたら、
ゲスト:そうです。
MC :ロボットがね
ゲスト:はい。
MC :活躍してくれたら
ゲスト:はい。
MC :っていう、そういう風な先生のお話なんですね。
ゲスト:はい。
(パート2へ続く) -
「恐竜の科学 パート2」 ゲスト:恐竜くん
2018/06/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ、今週のサイエンスコーチャーは略してサイコーは前回に続きまして恐竜くんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。よろしくお願いします。
MC :よろしくお願いします。恐竜くんはえー、恐竜大好きで、16歳の時にカナダに単身で留学したっていう、
なかなかねーキッズたち何年か後に、「お父さん、お母さん、カナダに行ってきまーす」って
なかなか言えないよね。たいしたもんですね。
ゲスト:なんか、父母が言うにはなんか自分は8歳の時にカナダのアルバータ州に行って
恐竜の学者になるって言ってたらしいので、
MC :小学校2年生で。
ゲスト:なので突然言い出したわけではなかったので、覚悟は特に出来ていたみたいなことは言われました。
MC :きっかけはー
ゲスト:はい。
MC :え、もう小っちゃい頃から恐竜好きだったんですか?
ゲスト:6歳の時に最初に恐竜にはまってもうそこからもう一番好きな物は恐竜というのは変らずで、
であのー自分が8歳の時になんでカナダのアルバータなのかって言うと、
幕張メッセの恐竜博というのがちょうどその時に始まったんですけど、
それが最初の90年の恐竜博が「カナダアルバータ州の恐竜」っていうタイトルで、
ま、その影響ですごくわかりやすく、で、あとはもうほんとにその勢いだけで気が付いたら
アルバータまで行っていたというような経歴です。
MC :なんかすごく恥ずかしいんです。幕張メッセなんて最近出来た建物のイメージなんですけどー、
おじさんからすると。そうかそりゃそりゃ、そうですか。
で、幻冬舎から「知識0からの恐竜入門」という本も出版されてるんですけれど、
実はこの本に様々な恐竜の知識が書いてあるんですが、
実は恐竜くんは絵を描くのも上手?イラスト描くのも上手?
ゲスト:あ、はい。そうですね、この本の
MC :この本のイラストも
ゲスト:えっとこのカラーの表紙だったりとか、
こちらの最初のグラビアのこのあたりのイラストは全部自分で描いています。
MC :あ、これは書店で見たら、一瞬恐竜の写真かと思ったぐらい。
だれがこれ写真撮ったんだ、見たんかいと思って。USJで撮って来たかと思いましたけど、
そうじゃなくて恐竜くんのこれイラストなんですね。
ゲスト:そうです、はい。
MC :すごいですねー。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :プロ級ですね。さ、そんなすごい恐竜くんなんですけど、
もう、今日はこれだ、恐竜くんがすごいと思う恐竜ベスト3いきましょう。
ゲスト:はい。
MC :3つ。いいですか。すごい!って思う恐竜、イメージ出来ました?ワン・ツー・スリーいいですか?
じゃ、第3位なんですか?
ゲスト:第3位は、えっとアルゼンチノサウルスという恐竜を挙げたいと思います。
MC :あっ、大きいやつ。
ゲスト:はい。あのもう図鑑なんかを見るとまあまず確実に最大の恐竜とこう断言されているような恐竜ですね。
MC :恐竜展へ行くとよくね、標本というか骨の標本で、実物大で、ドカーンと大体ありますよね。
ゲスト;はい、多分背骨だと思うんですが。あのー、この恐竜ですね、ま、とにかく最大の恐竜ってんで、
ある意味タイトルが一人歩きしている部分もあって、ま、御覧になったのがやっぱり骨、
一部の骨だけだというところからもそうなんですが、実はですね、ほんとに体のごく一部分、
多分見つかっている骨全部あわせても10個も見つかってないと思うですね。
MC :あ、世界中で?
ゲスト:あの、ま、アルゼンチンのその一か所でいっぱい見つかった骨だけなんですが。
MC :アルゼンチンで見つかったから、アルゼンチノザウルス?
ゲスト:アルゼンチノザウルス。はい。ちなみにあのニッポノサウルスという恐竜もいます。
MC :あ、ニッポノサウルスもいるんですか?
ゲスト:いるんです、はい。だからけっこう国のタイトルがついてる恐竜ってのがやっぱりいるんですが、
ただあのこの恐竜はほんとに一体分のしかも恐竜の骨って全身で250個とかの骨で出来ているんですが、
そのうちのたった10個ぐらいしか見つかってない、要は全体像はほとんどわかってない恐竜なんです。
MC :それで、世界最大の恐竜ってなってるですか?
ゲスト:そうなんです。だからちょっとここ実は恐竜にある意味つきもののちょっとした問題点なんですが、
あのー恐竜ってやっぱり人気があったり、注目度が高いので、
あのーほんとーにこの恐竜ってそこまでいろんな事断言していいのかなっていうものが
情報が先に一人歩きしてしまう傾向があるんですね。
MC :だから人間の妄想によって勝手に大きく膨らんじゃってる感じですかね。
ゲスト:だから図鑑なんかみるとアルゼンチノサウルス全身像あるんですけどー、
ま、ほんとはわかりっこない、ものなんですよ。
だから、全長が何メートル、ましてや体重が何トンというの、ま、ほんとに推測の上に推測の上に推測を
重ねているものなので、ま、そういう意味ではちょっとそんな問題点にも触れて見たくて
取り上げた部分もあるんですが、
MC :でも、アルゼンチン国内で10個しか骨見つかってない、今のところ、でも研究は進められてるんですね。
ゲスト:ま、ただ正直現時点ではこれ以上これ自体から得られる情報ってのはもう限界なので、
新しい発見に期待されるというところですね。
MC :じゃ、どこかの国で、どこかのサウルスで、アルゼンチノサウルスのイメージ出来る骨よりも
もっとおっきい骨が見つかったらアルゼンチノサウルスを抜くかもしれないですね。
ゲスト:はい、その可能性はもう充分あると思います。
MC :なるほど、そういうのなんか夢が膨らんでいいですね。
さあ、続きまして恐竜くんがすごいと思う恐竜の2位はなんですか?
ゲスト:はい。2位はですね、デイノニクスという小型の肉食恐竜です。
MC :デイノニクス?わかんない。
ゲスト:こちらですね、あのージュラシックパークとかの映画御覧になった方は
その中にラプトルという結構怖い恐竜ですね。
サイズは人間くらいなんですが、ま、足が速くて非常に頭が良くて
結構最後までしつこく人間を追ってくるっていう描かれ方をしてた恐竜です。
MC :はい、あの二人の子供達の所を追っかけまわしてたー
ゲスト:はい。台所まできていて
MC :そー、お菓子食べてる時に急に
ゲスト:あの、あれの恐竜の実績なモデルはこのデイノニクスだと言われているようなんです。
MC :あーそうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :それ怖いじゃないですか。あ、で、何がすごいんですか?
ゲスト:えっとですね、実はこの恐竜がすごいというのに挙げたのは、
その、ま、映画とかではなくて、あの、この恐竜自体がというより恐竜の研究史、
研究の歴史においてこの恐竜が果たした役割というのが、
おそらくどんな恐竜よりも重要な役割を果たしたという、
そういう意味でちょっと挙げさせていただきました。
MC :へぇー。具体的には?
ゲスト:鳥が恐竜から進化したというのはもう今では定説になっているんですが、
この鳥が恐竜から進化したというのを、結構決定づける恐竜でもあったんですね。
で、あのーこの恐竜が要はそれまで恐竜というのは今の爬虫類と同じように体温を自分で調節できなくて、
体が大きくなりすぎて時代についていけなくて滅んだ、言ってみれば生き物としては、
あのー、失敗した生き物だったみたいなそんな偏見が非常に強かったんですが、
この恐竜が出てきたことでー、恐竜が全然イメージと違ったじゃないかと、
さらに、鳥が恐竜から進化したっていうことは絶滅した生き物でなくて、
恐竜ってちゃんと生き物として今生きてる鳥を使って研究できるじゃないかとなったら、
もう世界中の主に若手を中心に恐竜研究これからが正に面白くなる時代じゃないかということで、
火付けた、のがこの恐竜だったんですね。
MC :なるほどー。
ゲスト:だから、ほぼこの恐竜の発見以前と以後で恐竜の研究を完全に二分してしまってもいいぐらいに、
もう完全にこの恐竜がターニングポイントなので、おそらく歴史に名前が残り続ける恐竜なんですね。
MC :ある意味これが2位の理由がすごかったですね。なんか、すごい。
デイノニクス、覚えました。さあ、すごい恐竜1位は!
ゲスト:はい。1位はですねー、またしてもなんですが、
MC :ダラララ、うん、うん、うん?
ゲスト:ティラノサウルスです。
MC :好きな恐竜、先週の1位もそうだし、すごい1位もティラノサウルス。
ゲスト:はい。これも迷いませんでした。
MC :あ、はい。
ゲスト:え、あのーこれはですね、僕が好きだからということで贔屓をしているということではなくてですねー、
あのー、実際ティラノサウルスという恐竜はー、ちょっと別格の恐竜なんですよ。
ここまで人気があるっていうのもだからこそなんですがー、
MC :はい。
ゲスト:あのー、いわゆる恐竜の絶滅と言われている、も、ほんとにあのー恐竜が絶滅したと言われている時の
ほんとに間際に登場した恐竜でですね、言ってみれば最後の大型肉食恐竜なんですね。
ま、あのー他の大型肉食恐竜、ティラノサウルスって別に最大の肉食恐竜ってわけではなくて
同じくらいか、中にはもっと大きいと言われている恐竜もいます。
ただあの他の肉食恐竜と比べて見た時にこのティラノサウルスの血筋というのだけは、
ほんとに独自の非常に変わったユニークな進化をとげていて、
ま、ほんとにあらゆる意味で全身どんな部分を比べて見てもちょっとレベルが違う、
かなり特殊な恐竜なんです。
MC :へぇーえー。
ゲスト:とにかく頭の先からしっぼの先まで、何故この恐竜はここまで吐出した進化をしたのだろうかっていうのに、
もう圧倒されるようなそんな特長を持った恐竜ですね。
MC :この間金沢から福井まで行ったら、特急ダイナソー号ってのがありました。恐竜ですよ。
ゲスト:はい。福井はね、恐竜に力入れてますからね。
MC :なるほど、わかりました。もう、時間ですねー。
いや、恐竜くんとはなんかこれが始まりでまたお会いできそうな気がしてきました。
ゲスト:あ、ほんとですか。楽しみにしてます。
MC :是非又番組に遊びに来て下さいね。
ゲスト:是非お願いします。
MC :はい!今週のサイコーは恐竜くんでした、ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「恐竜の科学 パート1」 ゲスト:恐竜くん
2018/06/01 Fri 12:00 カテゴリ:生き物MC :さ、今週のサイエンスコーチャー略してサイコーは恐竜くんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。初めまして。
MC :なんかキョーキョーとか言わないんですか?
ゲスト:あ、いや特にそういう口癖とかは、ないんで、
あのーほんとに普段からこの通りのテンションでやっています。
MC :そうですか、おかげさまでこの番組10年やらせていただいてますけど、
「くん」付けできてるのは、さかなクンと恐竜くんだけなんですよ。
ゲスト:あっそうなんですか?光栄です。
MC :2度目の「くん」です。え、さかなクンとは関係があるんですか?
ゲスト:えーっと、全くその親戚とか全く関係はないんですが、一応ですね、
恐竜くんって名前を名乗る時にあのさかなクンの事務所に伺ってご挨拶はさせていただいたんです。
MC :あっ、一応お伺い立てなくちゃいけないですか?
ゲスト:あっいや、そんなことはなくて、あのーむしろその事務所の方とかも
あのー売り込みに来たんじゃないかって思われて、
あのーほんとにご挨拶だけでって言ったらちょっとあのー君なかなか生真面目だけど、
変わった子だねーって、言われましたね。
MC :さかなクンの事務所に一応見初めて頂いたってことでよろしいんですね。
ゲスト:そうですね。はい。認めて、
MC :生真面目だけど変った子だねって、目の前にその人いるんですけどー、顔がちょっと恐竜っぽいんですよ。
ゲスト:あ、そうなんですか?
MC :あの、草食系の恐竜みたいな顔されてますね。
ゲスト:あ、ほんとですか。
MC :えー、こんなこと言っちゃなんですけど。えー、よろしくお願い致します。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :さあ、この恐竜くんなんですが、子供のころから恐竜が大好きでそのままの勢いで高校時代に
単身カナダに留学、うん、恐竜の研究が盛んなアルバータ大学、そういう大学あるんですか?
ゲスト:はい。そうです、あのカナダのアルバータ州エドモントンっていうところにあります。
MC :はい。で、これは恐竜の研究が盛んなんですか?
ゲスト:あの、恐竜というか厳密には絶滅した生き物全般の研究で、こ、生物学というんですが、
この生物学に関してはもうほんとに世界でもトップと言われている大学です。
MC :へぇー。そして、卒業後アメリカ、カナダなどの様々な博物館や研究施設と交流しながら、
科学の普及活動や体験教育の大切さについて勉強されてきた、と。
ゲスト:はい。
MC :まさに、この番組の為に活動されているような方ですねー。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :はーい。さあ、今日はですね、この恐竜くん、本も出してらっしゃる。
ゲスト:はい。
MC :「知識0からの恐竜入門」親子で楽しめる。恐竜ファン必見!と、ありますねー。幻冬舎から。
ゲスト:はい。これはもうほんとにとてもわかりやすい本にしたいなあと思いまして、
なかなかあのー入門書といっても恐竜の本というのはあの、
子供向けの図鑑かもしくは逆に洋書の専門書なんかを訳したものだったりとか、
ちょっと難しいめのものが多かったので、ま、しっかりと内容はしつつ
どなたにでも気軽に読んでいただけて、で、あとはあのー図鑑とかでデータを覚えるだけではなくて、
もうちょっと先にもう一歩踏み込んでみたいっていうお子さんなんかにもおすすめしている本です。
MC :はい。さあ、そんな恐竜くんなんですけれど、今日は恐竜くんに好きな恐竜ベスト3を
発表してもらってその根拠、ね、ご専門の方から、あのインターネットで調べても
その恐竜わかりますからね。はい。じゃ、まず3位なんですけれど、3番目に好きな恐竜は何ですか?
ゲスト:はい。3位はですねー、迷ったんですが、これはディプロドクスという恐竜です。
MC :何と迷ったんですか?
ゲスト:えっとですねー、いろんな恐竜で、
MC :あ、そうですか。
ゲスト:考えました。なかなかあのー、
MC :ベスト3って言われてー
ゲスト:そうなんです。正直ベスト1と2はもうほぼ即答だったんですけど、3位は候補がいろいろとあったんです。
MC :あっそうですかー。迷ってディプロドクスって。
ゲスト:はい。こちらですね、えっとまず植物を食べる恐竜なんですが、
MC :草食系
ゲスト:はい。とても大きな恐竜です。えっとまあ恐竜っていえば大きいってイメージあると思うんですが、
その中でもほんとに最大級の恐竜の1つとして知られています。
で、あのー実は迷ったとは言ったんですけど、子供のころから結構この恐竜は好きな恐竜で、
あのーま、そういうわけでも選んだんですが、あとですね、自分が2002年にこの恐竜の、
ただでさえ大きいと言われているこの恐竜の中でも一番大きい最大の個体と言われていた
化石のクリーニングといった岩から取り出す作業ですね、ドリルなんかを使って。
あの、それを担当したことがあってまあそん時の思い出なんかもあってすごく思い出のある恐竜です。
MC :ちょっと今、すごい現場感ありましたねー。え、その何、世界最大の、
ゲスト:はい。
MC :ディプロドクスの、
ゲスト:はい。
MC :化石の採掘の場に立ち合って、クリーニングしたということですか?
ゲスト:そうですね、あの研究所に持ち込んでからの作業なんですが、
MC :それを、ちなみに何億年前のものだったんですか?
ゲスト:大体1億5千万年前です。
MC :軽く言いますねー。1億5千万年前ー。
それを、じゃ研究所に持ち込んだものを恐竜くんがクリーニングした。
ゲスト:勿論あのー何人かであの分担してやっていたんですが、ちょっと一時期あのーま、
この恐竜の最大個体っていっても全身が全部出ていたわけではないんですが、
一番重要だった腰の廻りの化石がありまして、そこを自分がほんとに短い期間ではあったんですけど、
任せていただいたことがあって、それで掘り出していたんです。ほんとにおっきな腰の骨です。
MC :今の話聞いたら、めちゃめちゃこれ1位に近いじゃないですか。
十分迷って3位じゃなくて、これ1位に近くありませんか?
もっと上のレベルが、じゃあ好きな恐竜2位は何ですか?
ゲスト:はい。2位はですね、こちらあの角のあるトリケラトプスという恐竜です。
MC :あ、知ってる。
ゲスト:有名どころですね。
MC :犀みたいなやつですね。
ゲスト:はい。
MC :角が2本あって、
ゲスト:はい。ま、あのーちっちゃいのも含めて3本、角があるんですが。
MC :あ、3本ある。鼻にあるんだ。
ゲスト:目の上2本、鼻に、はい。
MC :目の上に2本と、鼻のところに1本
ゲスト:そうですね。あのーこのトリケラトプスっていう名前自体が顔に3本角があるという、
結構そのまんまの名前がついてる恐竜なんですね。
MC :あ、トリケラっていうのはそういうことですね。トリプルの
ゲスト:トリプルとかトリオとかのトリですね。
MC :ほー、
ゲスト:で、あのーま、この恐竜はですね、さっきとは逆に僕、実は子供の頃は、
ま、トリケラトプスってすごく子供に人気ある恐竜なんですが、
逆に僕は子供の頃あんまりこの恐竜好きじゃなかったんですよ。
そんなにー思い入れのある恐竜ではなくて、それが最近になってですね、
何年か前にたまたまちょっとお仕事の関係でこの恐竜について詳しーくリサーチしたことがあったんですね。
で、あのーその時に詳しく調べてみると、あ、なんて面白い恐竜なんだろうということで、
MC :何が面白かったですかー。
ゲスト:えっとですね、まず1つはこの恐竜って化石の発見される数が非常に多いんですね。
で、あの、まあ、アメリカのま、各地で発見されるんですが、
特にこの恐竜が多く見つかる地層なんかですと、見つかる恐竜の80パーセントがこの恐竜って言われてる、
MC :希少性がない感じがして、
ゲスト:実は希少性がそんなに高くない、むしろうじゃうじゃいた、
ま、言ってみれば成功者だったんですね、生き物としては。
MC :あー、なるほど。
ゲスト:で、あの化石の発見数が多いので非常に深く研究されています。
ま、そういう風に詳しく研究されていることで、やっぱり情報量が多くなると
掘り下げれば掘り下げるほど面白くなってくるっていう、そういう意味ですかね。
MC :発見される個体数があるから、研究もいろんなこう多岐にわたって、
こういろんなこうデータが集まるということですね。
ゲスト:そうですね。
MC :トリケラトプス。覚えといてね。恐竜くんが2番目に好きなんだって。さあ、一番好きな恐竜は何ですか。
ゲスト:はい、1位はですね、これはもうほんとに一瞬も迷わずなんですが、やっぱりティラノサウルスですね。
MC :あ、有名どころですね。
ゲスト:はい、一番有名な
MC :結構ベタベタですね。
ゲスト:そうですね、よく言われます。
MC :当たり前すぎるんですけど、いいんですか、それで。
ゲスト:はい、これは、もうほんとに子供のころからもう一度も動いたことがなく、
MC :あ、そうですか。
ゲスト:一番好きな恐竜です。
MC :急になんか子供の話になっちゃったけど、なんか子供ー、
もっとなんかマニアックなところくるかと思ったんですけど。
ゲスト:そうですね、よく期待されるんですけど。
MC :ティラノサウルスでーす、なんて言われたら、普通じゃんと思いましたけど。
ゲスト:ただ、以外とですね、あのー好きな恐竜って、
筋金入りの専門家の方になるほどベタな恐竜が好きっていう傾向があったりします。
MC :なるほど、あーそっか、何かそんな気がしました。はい。
ゲスト:えっとまあ、もちろんですね、軽いところで言えば、
あのージュラシックパークとかああいう映画でも活躍してるのでま、
そういったとこでも影響あるかもしれないんですが、ま、先程のトリケラトプスとか
その前のディプロドクスなんかとも同じでやっぱりよく研究されている恐竜なんです。
なんせあの研究対象としても非常にユニークで面白い恐竜なので、世界中で注目されているので、
もうありとあらゆる様々な角度から深ーく研究されているので、
まああのーもっとも解明が進んでいる恐竜の1つといってもいいくらいなんですね。
MC :でも、2位のトリケラトプスは8割がトリケラトプスですよね。
ティラノサウルスは何割ぐらいなんですか?化石
ゲスト:ティラノサウルスはやっぱり肉食動物ってま全般的に割合は少なくなるので、
あの何体っていうのでもトリケラトプスとは全く比べものにならないぐらいなんですけれど。
MC :少ないけれど。
ゲスト:ただ、あのー非常にいい状態の例えば全身のほとんどの骨が揃っているような化石というのが
複数発見されているので、まそのおかげで詳しく調べることができるんですね。
でさっきお話したような例えば成長段階だったりとか、あのオスとメスの違いがどうだったのかとか、
それから実際に噛みつく力、ま、肉食動物なんで、それがどのくらいだったのか、とかいうのも、
ほんとにけっこう体の隅々まで詳しい研究がされていますね。
MC :へえー、いやー、ちょっとあっという間に終わっちゃいましたね。
あら、もうおしまいですか?ティラノサウルスの話もうちょっと聞きたかったんですけど、
クリーニングの話も気になってしまいました。また、詳しいお話を来週伺いたいと思います。
今週のサイコーは恐竜くんでした。有難うございました。
ゲスト:有難うございました。 -
3月24日イベントレポート②
2018/05/10 Thu 18:00 カテゴリ:イベント
今回の「ネクストサイエンスジャム」でも
文部科学省より指定を受けたスーパーサイエンスハイスクールのみなさんが大活躍!
今回は千葉県立 長生高校のみなさんが会場の子どもたちにユニークな研究、
100人以上の髪の毛を電子顕微鏡で見て発見したことをプレゼンしてくれました。

3人のリケジョのユニークな視点、そして髪の毛の構造を海苔巻きで
表わすなどわかりやすい解説に会場の子どもたちは目を輝かせながら見ていました。
『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
科学ジャーナリストの寺門和夫さんが登場。
子どもたちから寄せられた様々な質問の中から
科学が発達すると無くなってしまうもの、未来の食事、
そして磁石はなぜN極とS極があるのかについて解説してくださいました。
今回はここまで。
現在次の企画が進んでいます。詳細が決まったらこのホームページでお知らせしますので
楽しみにしていてください! -
3月24日イベントレポート①
2018/05/10 Thu 18:00 カテゴリ:イベント子どもたちの「科学する心を育む」プロジェクトとして、
日立ハイテクノロジーズと文化放送が協力して、
科学実験とラジオ公開録音が一体になったベント
「ネクストサイエンスジャム」
3回目となる今回は浜松町の文化放送で開催され、
たくさんの子どもたちが参加してくれました。
ここではそのイベントの様子を少しだけご紹介します!今回のナビゲーターは、前回の京都でも大活躍だった、
俳優でタレントの照英さんをお迎えしました!
「永遠の小学5年生」というだけあって好奇心旺盛な方で、
前回以上に今回も科学のお話に目を輝かせながら楽しんでいました。
まずはこの公録イベントの目玉のひとつ、ネクストサイエンストークショー。
テーマは「おいしいものを科学」。子どもたちには身近な給食の話から
食にまつわる科学について教わりました。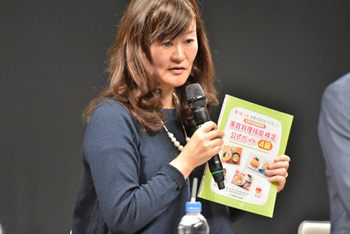
ゲストは女子栄養大学短期大学部准教授の豊満美峰子さん。
最初は給食に関わる様々な変化や、
食器や献立の変遷などを例に説明してくださいました。
また好きな給食・お弁当ランキングの話では
「なぜ好きな人が多いのか」について
科学的視点から解説して頂きました。
そして嫌いな給食・お弁当ランキングの話で豊満さんから出た、
「自然にいずれ食べられるかもしれないし、他のモノでも栄養は代用できるので、
無理に嫌いなものを食べる必要はないのではないか」という言葉は
今の時代にマッチした食育といえるかもしれませんね。
次においしいものの秘密を科学的に、クイズ仕立てで伺いました。
子ども達から飛び出す鋭い答えに豊満さんも感心しきりでした。
-
「イモのスゴイパワー パート2」 ゲスト:鈴木高広さん
2018/05/01 Tue 12:00 カテゴリ:植物MC :さあ、今回のサイエンスコーチャー略してサイコーは、
前回に続きまして近畿大学教授の鈴木高広さんです。こんにちは。
ゲスト:あ、こんにちは。近畿大学の鈴木です。よろしくお願いします。
MC :お願いします。先生からは芋でエネルギー、家庭の電力全部賄えるよ、エネルギー賄えますよ、
車の運転も出来ますよ、ガソリンにもなりますよ、いろいろ伺いました。
芋の可能性、芋、さつまいもとじゃがいもある中で、さつまいもの方がエネルギーになり得ると、
なりやすいというお話も伺いました。
じゃあ、この日本という国で、エネルギーが少ないと言われているじゃないですか、
エネルギーは全部輸入に頼ってる。
ゲスト:はい。
MC :そんな日本がこのさつまいもの力で一億二千万人が賄えるかどうかということです。
最後に先生先週出来るっておっしゃっていましたよね、
ゲスト:えーえー。
MC :疑ってますよ、僕は。
ゲスト:あのね、これはね、あのーだれもが疑いますけど、
MC :あ、そうですか。正しいんですね、じゃあ、疑って。
ゲスト:ただね、これはねあの意外と簡単に出来るんですよ。
MC :えーっ!
ゲスト:まずね、発想を変えないといけません。え。まずね、あのーえー石油石炭天然ガスも元をただせばね、
あの生物ですし、そのまた元をただすと一番大元はね太陽のエネルギーなんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、今日本は国土が狭いといってもあのー日本の国土に一年間に降る太陽のエネルギーを計算すると、
日本が一年間に使うそのーえーと石油石炭天然ガスの100倍分のエネルギーが降り注いでいるんですよ。
MC :あ、太陽の光のエネルギーっていうのは僕ら日本人が全員で使う一年間のエネルギーの100倍?
ゲスト:え、そうです。だからそのうちの1パーセントだけね、芋に変えればいいんですよ。
MC :え、僕らって太陽光発電ってどれぐらい、何パーセントくらいですか?
ゲスト:太陽光発電はね、もう今20パーセントぐらい、にはなりますね。
MC :あ、結構そこそこ太陽の恩恵をエネルギーには変えているわけですね。
ゲスト:そうですね。ただ残念ながら、今のところはその電気を貯めようと思うとコストもかかるし、
それからあのー、ね、太陽光発電の設備なんかを作る時にもやっぱりいろいろこう手間も
コストもかかるんですね。
MC :なるほど。それのなに1パーセントを芋の栽培にかけろってことですか?
ゲスト:あのー、そうですね。で、ていうのはね、例えばあの日本の国土の3分の2は森林なんですよ。
MC :あ、森ですね。はい。
ゲスト:で、森林もまあ植物なんで、じゃあ植、その森林ね、木を使えばいいじゃないのって思うんですが、
普通は、どころがね計算するとねー、あのー森林を全部エネルギーに換算すると
日本が使うエネルギーの2年半分しかないんですね。
MC :あ、いわゆる日本の3分の、国土の3分の2を占めてる木を切ってそれも燃やしてエネルギーにするには
それ全部やっちゃったら2年半でなくなっちゃう。
ゲスト:え、そう、日本の山は全部丸裸、でそこに植
MC :あーはげ山になっちゃう。
ゲスト:え、そこに植林しても今度元通りになるのに50年かかるんです。
MC :そう、言いますよね、うん。
ゲスト:これはね、やっぱり森林はちょっと大きすぎてね、大きすぎる生物っていうのは成長が遅いんですよ。
MC :はーい。
ゲスト:で、あのそのためにあの光合成の変換効率が、先程1パーセントあれば、って言いましたけど、
森林の今の光合成効率はね、0.06パーセントってものすごい低い。
MC :効率悪いんですね。
ゲスト:悪すぎるんですね。ところがね畑で芋を栽培するとね、3パーセントぐらいにまで高められるんですね。
MC :あ、いわゆる芋を栽培すると、光合成のエネルギーが3倍になるってことですね。じゃあ、従来の。
ゲスト:え、えっと従来の、
MC :3パーセントか。
ゲスト:3パーセントですから、森林のね50倍。
MC :50倍。はい。
ゲスト:だから同じその国土の面積の中で50倍大量にエネルギーを作り出せるってことなんですね。
MC :あの、エネルギーにするための野菜を作っている農家さんって今いるんですか?
ゲスト:これはね、残念ながらね、ほとんどいません。
MC :あ、これからの話ですね。はーぁー。
ゲスト:そうです。あのー、というのはね、あのーえーとかつてね、あのー海外でそのーえーと、
とうもろこしやさとうきびからアルコールを作って自動車にこう混ぜて
MC :宮古島とかでもやってますよね、沖縄の。
ゲスト:そうですね。で、これがね一時期ブームになった時に、
あのーそれまで食用で作っていたとうもろこしを原料にしてアルコールにまわしちゃったんですね、燃料に。
そしたらね、食料が足りなくなっちゃったっていう時代があったんですね。
MC :へぇー。
ゲスト:それでーそれ以来、あのー食料として作る農作物はエネルギーに使っちゃだめだよっていう風に、
こうね、世界各国があの、まあ法律で規制するようなところまでしちゃったんですね。
MC :はぁー。
ゲスト:で、日本もその法律があるんですよ。
MC :なるほど。
ゲスト:え。あのはっきりしたこう法律じゃないんですけど、そういうガイドラインっていう
MC :いわゆる農家さんは人の口に入れるためのしょ、食べ物作ってねっていう法律があるっていうことですね。
ゲスト:そうですね。え、だから、食べ物として作る物は燃料作物って言うんですけど、
燃料作物としては使えませんよっていう風にね、あの法律にねこう注意書きで書いてあるんですね。
MC :じゃあ、そもそもこの話2週に渡って伺ったけれど、法律を変えない事には実現がしてこないんですか?
ゲスト:そうです。まずはね、そこのバイオマスエネルギー基本計画っていうね、
その法律の中身をね、まず変える事が大事ですね。
っていうのは、あのー芋をそうやって日本中のエネルギーを賄うだけ作ると
食料っていうのはそのうちのたったの2パーセントで足りるんですよ、日本中の、
そのあのもしそのカロリーを計算するとですね、日本中の人の必要量を。
だから、食料、新たにその燃料作物を作る技術を研究してるんで、
これはもう食料を妨げるわけじゃないですね。
MC :はい。
ゲスト:え、むしろその食料問題も解決できる、併せてもう解決できるような方法なので、
そこはやっぱり新しいこう時代の技術として、あのーまずは法律の方で変えていくことによって、
そうするとね、あの国のその予算とかね、そういうあの各自治体のこう取り組みっていうのも、
非常に取り組みやすくなるんですよね。
MC :はぁー。やぁー、でも近い将来どうですか、あの予感としては国は動いてくれそうですか?
ゲスト:あ、これは必ず動きますね。というのはね、今環境問題、とくに地球温暖化、
それから二酸化炭素の問題はもうますます深刻化してます。
例えば今年も大型台風とかね、その集中豪雨とか、よく起きるようになりましたけど、
これはねあの、鍋の中でね、あのお湯を沸かしている状態なんですよ、要は。
あのこれは温度が上がれば上がるほどどんどん激しくなるでしょ。
MC :うん。今の僕らの暮らしが、
ゲスト:そうです、そうです。で、これを止めるためにはね、将来的にはね、必ず化石燃料も全廃、
あの石油石炭天然ガスは使うのもうやめましょうっていう時代が将来必ず来ます。
MC :そうですか。はぁー。
ゲスト:で、っていうのはね。このまま今あのー石油を使い続けると、
私の計算ではね、あと千年であの二酸化炭素濃度が、今400ppmなんですけど、
これが千年後には2.5パーセントっていうレベルにこう達するんですね。
MC :何倍ぐらいになるんですか?今の。
ゲスト:えっとですね、400ppmってのは、0.00004パーセント。
随分大きなこう規模ですけど、で、それがね、
MC :それが、2.5パーセントになっちゃう。
ゲスト:でも、これはねえっと1700年代の産業革命以降、あの空気中の二酸化炭素濃度ってね、
あのー、ほぼね、38年ぐらい毎に2倍のペースで増えてんですね。
で、倍・倍・倍っていう増え方はねもう加速度的に増えるんで、で、あの今はまだ微量ですけど、
将来的にはどんどんどんどんこう増えていってしまうんですね。
で、今もそのペースで増えてるんで、で、そうするとね、
あのー大変なのは実は二酸化炭素濃度よりも酸素濃度なんですよ。
二酸化炭素濃度が2.5パーセントになるっていうことは、
酸素濃度がまあおよそ3パーセント減るんですね。
今21パーセントある酸素濃度が千年後には18パーセントになってしまう。
で、18パーセントっていうのは人間が酸素欠乏を起こす濃度なんです。
MC :へぇー。千年後、そうなる可能性が。
ゲスト:そうですね。例えば100m走ったらもう呼吸苦しいですよね。
ぜーぜーぜーぜー、それが日常的になっちゃうんですよ。
ね、酸素が足りない状態。これではねやはり人類は将来的にはね、もう、ま、滅亡してしまう。
MC :そういうことですよね。いやー。
ゲスト:で、これを止めるためには化石燃料を使うのをやめて、全て植物で賄う。
で、植物は成長する時にあの酸素をどんどん出してくれるんで、
えー、でも、植物といってもそのー、森林ではスピードが遅すぎて、成長が遅すぎるんでだめなんですね。
MC :いやー、ちょっと今すごい、ね、人類滅亡という惑星が衝突するんじゃないかという、
そんな、そういう問題じゃなくて息が出来なくなるかもしれないという、そういうお話ですね。
ゲスト:そうです、
MC :最終的には、千年後。
ゲスト:これを止めるためには、化石燃料全廃して、日本の場合だったら芋で、全て賄う。
で、これ、実現できるんですね。
MC :いや、すごい貴重なお話でした。また是非遊びに来てください。
ゲスト:あ、はい、どうも有難うございます。
MC :今週のサイコーは近畿大学教授の鈴木高広さんでした。有難うございました。
ゲスト:あ、どうも。有難うございました。 -
「イモのスゴイパワー パート1」 ゲスト:鈴木高広さん
2018/05/01 Tue 12:00 カテゴリ:植物MC :今回のサイエンスコーチャー略してサイコーは近畿大学教授の鈴木高広さんです。こんにちは。
ゲスト:あ、こんにちはー。近畿大学の鈴木です。よろしくお願いします。
MC :近畿ってことは、関西からわざわざ、
ゲスト:あ、そうですよ。えー、あのキャンパスはあのー和歌山県にあるんですけど。
MC :ほぉー。へぇー、えー1959年に愛知県にお生まれになって、現在近畿大学生物理工学部教授、
ゲスト:はい、そうです。
MC :農学博士でらっしゃる。
ゲスト:はい、えー、
MC :農学、農業、
ゲスト:そうですね。え。あのー、ちょっとこう生物理工学部っていうとあまりなじみがないかもしれませんけど、
あのー、ま、生物の機能をま、産業に利用するっていうことで、あの、ま、色んなの工学系のこととか、
そのあの理科学系のね、理科系のこととかいろんなこう技術を持ち寄ってそれで新しい技術を生み出す、
ま、そういう学部ですね。
MC :そして、さつまいも、あるいはじゃがいも、芋から燃料が出来るよ!ってお話なんですよ、今日は。
ゲスト:そうですね。え、あのま、芋というとね、あの非常にこう今も丁度そのね、
さつまいもの美味しい季節なんですけど、
MC :食べる、食べるですよ。もう焼く、揚げる。
ゲスト:そうですね。芋堀りの季節ですよね。ですけど、これが実はあのーすごくいい燃料になるんですね。
MC :へぇー。よくね、サトウキビが燃料になるよ、っていうのは聞きますけど、
芋はおならにしかならないと思ってましたけど。
ゲスト:え、まさにそのおならがいい燃料なんですね。
MC :あ、ガスだから?
ゲスト:え、あのーおならの中にはねメタンガスっていって、あのこれはあの天然ガスと同じ成分で、
しかも都市ガスと同じ成分ですよ。これがあの入ってるんですね。
MC :ちょっと待って待って。え、それよく冗談で言うけど、それほんとなんですか?
ゲスト:ほんとの話ですよ、え。
MC :火が付くんですか?
ゲスト:え、あのーきちんと火は付きますね。
で、あのしかもそれを生成すればまさにあのー家庭で使っているガスと同じガスなんですよ。
MC :ぼくらはそういうものを出してるんですね。
ゲスト:そうです。え、お腹の中にいるそのメタン細菌っていう微生物があのー作ってくれるんですね。
で、芋ってね繊維質が多いでしょ。
MC :はい。
ゲスト:だからね、あの他のそのえっと甘い、あるいは糖分の多いとか、
でんぷんの類のその食べ物より分解がちょっと遅いんですね。
MC :ふーん。お米とかと違うということですね。
ゲスト:そうですね。え、そうするとね、腸のこうまあ奥のね、あの奥の方まで行くんですよね。
で、そうするとそこでメタン菌が待ってるんですね。
だから、その芋の場合は特におならが出やすいんですね。
MC :同じでんぷん質があっても、繊維が少なかったら、すぐ体に吸収されるけれど、
繊維がある分腸の中にとどまる。
ゲスト:そうですね、あのー奥深くまで行って、で、そこは酸素がない状態で嫌気状態というんです。
MC :あー、なるほど。
ゲスト:え、でその嫌気状態になると、そういうメタン菌が元気になってですね、
MC :へぇー、逆に腸に負担かけませんか?
ゲスト:あ、それは大丈夫ですね。あのむしろ繊維質が多いんで、そのね、腸の働きも良くしてくれるんで。
MC :じゃ、万事OK。お芋は体によい。
ゲスト:あ、いいですよ、え、それは間違いないですね。ポリフェノールもありますし、はい、含まれてますし。
MC :えー、それで、ガスも排出するということで、ま、これは人体に関してなんですけれど、
ま、これは科学の力で今、芋からエネルギーが出来る。
ゲスト:そうですね。え、あのーま、そういう風にもともとはすごく芋はそのエネルギーに変換しやすい、
特にメタンガスには変換しやすいんで、これをそのーメタンを作る菌をたくさん培養して、
で、そこにね大量に作った芋をこう投入するんですね。
で、基本的にはね、あっためるだけでね、ガスがどんどん出て来るんですね。
MC :芋と菌を結婚させるんですか?
ゲスト:そうです、そうです。え、タンクの中でですね、ま、水を入れて、で、
芋入れて菌を入れればあとは温めるだけで、それでガスが出て来るんですね。で、
MC :へぇー。その菌っていうのは何ですか?
ゲスト:あの、その菌っていうのはメタン、メタン細菌ですね。
MC :あ、細菌ね。じゃ、本来のお芋と培養した細菌を芋と菌、イモ菌トリオですね。
ゲスト:ははは、そうです。ははは、え、まさに。
MC :で、それで培養するとー
ゲスト:メタンガスがどんどん出てきます。
MC :ほぉー。
ゲスト:で、あのーただまあえっと生物の発酵ではメタンを100パーセント、
100パーセントメタンっていうわけじゃなくて、あの、半分ぐらいは二酸化炭素が含まれています。
で、他にも微量ですけど、あのー他の不純物も入ってるんで、ま、
それを取り除いてあげるともうきれいなメタンになってで、このメタンはあのー、
一般の家庭でガス菅から出てくる、あのコンロで燃やすあのーガスとほとんど一緒ですね。
MC :なるほど。わかりました。いわゆる生成すると家庭でも使える、ガスとして使えるよってことですね、
芋から。今基本的にね、僕らのお世話になってガスっていうのは何から出来てるんですか?
ゲスト:あ、あれはね、だから大昔にね、あのーま、えっと生物がその地下でまさにメタン発酵して
そのガスが溜まってるんですね。
MC :今の、使ってるガスってのは地中から出て来てるガスですよね。
ゲスト:え、そうですね、え。
MC :それを生成して、僕ら家庭で使わしてもらってるけれど、
いわゆるそれは奥深くから掘っているもの、ということですよね。
ゲスト:そうです、そうです。
MC :地球の中から。
ゲスト:そうですね。で、あのー地球の中でそのー長い間かけて、
あのーまさに酸素がないところでゆっくりとこう嫌気発酵が進んだんですね。
で、まあ熟成されて、それでえっとそのガスの濃度が高くなって、で、実際にはあの地中の中でも、
あの二酸化炭素がちょっと含まれてるんで、で、あのー天然ガスを掘っているところはそれを分離して、
で、その生成したガスをそのー日本は輸入してるんですね。
MC :で、家庭で使ってる。
ゲスト:そうです。
MC :あ、ガスは輸入ですか?みんな。
ゲスト:あ、今はそうですよ、え、殆ど日本は、え、
MC :へぇー。じゃ、今のお話だと芋から作るガスっていうのは国内で作ることも可能ってことですか?
ゲスト:そうです、え、これ理論的にはね、今輸入してるガスだけじゃなくて、石油も石炭も、
その天然ガス、これが3つ主なエネルギー源なんですけど、日本はこのえっとエネルギーは、
日本が1年間に使うエネルギーの96パーセントくらい依存してるんですよ。
で、あのところがね、これね、計算上はね、日本の国内で芋を大量に作るとね、全部ね、
あのー作れますね。そのエネルギーの分だけ。
MC :あ、みんなが使っているガス?ま、寒くなったらストーブつける、ファンヒーターつける、
えー、家で料理作る、お母さんカレー作る、いろいろあるけれど、
それは全て芋の力で賄うことも可能なんですか?
ゲスト:あ、可能ですよ。え。
MC :今、芋ってシチューとかカレーに入ってるじゃないですか、で、あとは焼いて食べたりするけれど、
さつまいもとじゃがいもで適しているのはどっちですか?その燃料に。
ゲスト:え、これはね、あのー最初はじゃがいもで実験したんですよ、
ただね、あのーえっと大量に栽培しやすいかどうかっていうのが一番重要で、
で、あのいろいろやってみるとじゃがいもはちょっとあのー連作障害とかね、
それからあのーじゃがいもの方が水分が多いんで、固形分がちょっと少ないんですね。
で、あの固形分を沢山使わないといけない、ってことで最終的にはさつまいもの方が
適しているっていうことがわかりましたね。
MC :北海道と鹿児島が戦って鹿児島が勝ったような感じですかね。
ゲスト:確かにさつまいもの方が、あの暖かい所の方が適してますけど、
ただ北海道でもね、さつまいも作れますよ、ちゃんと作ってますし。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:で、たださつまいものいいところはね、あの蔓を切ってその植えればそこからまたこう芋が出来るんですよ。
MC :へぇー、じゃがいもとは違うんですか?
ゲスト:じゃがいもはね、種芋その、芋がいるんですね。だから、その分もちょっとこうロスがでてしまうんで。
で、やっぱりさつまいものその生命力っていうかね、あの繁殖能力っていうのはすばらしいですね。
MC :じゃ、さつまいもでエネルギー作った方が効率がよいということですね。
ゲスト:そうですね、結果的には今、そういう方針にして、
で、あのーま日本中でさつまいもを大量に栽培できるような、
あのそういう栽培技術を中心に研究してますね。
MC :で、その芋と菌をそれで培養さしてメタンガスを発生させる装置ですよ、今度装置。
これ、どういうものなんですか?
ゲスト:えー、これはね、そのメタンを作る方法とか装置っていうのは、
ヨーロッパではもう当たり前にあるんですね。
ただし、あのヨーロッパでは巨大な装置なんですよ、それが。
で、日本にやっぱりそういうものを普及させようと思うと、これもまたちょっと大変なんで。
MC :そうですよ、はい。
ゲスト:で、今、あの研究で取り組んでいるのはそれを10分の1とかあの20分の1にコンパクトにして、
でー、その地域、でーあのー例えばあの数件の農家が集まっても出来るとかね、
あるいはそのー自治体でこう1つこう管理してあのー運転するとかね、
そういうしくみをあのー開発しようと思って取り組んでますね。
MC :みんなわかったかなー。
すーごい興味深い話で、まみんなの家でエネルギーっていろいろ必要だと思うんだけれど、
料理をしたりね、暖めたり、これからあの寒い季節やってくるからね、ストーブ使ったり、
でもそれをーお芋のエネルギーで全部賄えちゃう。
ね、車の運転もそうだし、それから発電そのものも今石油で火力発電ってやってますけど、
お芋の力で出来ちゃうかもよ、っていう。じゃ、具体的に日本でそれが先生、出来るんですよね。
ゲスト:あ、出来ますね、これは。
MC :このあたりちょっとまた来週詳しくは聞いていきたいと思います。
今週のサイコーは近畿大学教授の鈴木高広さんでした。どうも有り難うございました。
ゲスト:あ、どうも有り難うございました。 -
「お城の科学 パート2」 ゲスト:萩原さちこさん
2018/04/01 Sun 12:00 カテゴリ:その他MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は
前回に続きましてライターで編集者でらっしゃる萩原さちこさんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :萩原さんは「図説・戦う城の科学」という本をサイエンス・アイ新書から出してらっしゃるんですけど、
先週は科学、科学といいながらまったく科学の話出てこなくて、江戸城めぐりになつたけど面白かったです。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :僕も1週間で勉強してきました。
ゲスト:はい。
MC :城巡り、城巡りっていうけど、江戸城を巡る、らないと城語っちゃいけませんね。
ゲスト:いや、そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:もう明日にでもいける
MC :ええ。
ゲスト:近場のお城が東京にありますので、
MC :えー。
ゲスト:ぜひ、キッズももう、江戸城に
MC :すごいですねー。
ゲスト:ねえ、行って欲しいです。
MC :あの、ランニングして汗を流すも良し、
ゲスト:はい。
MC :で、そっからいろんなものを得るも良しで。
ゲスト:はい。
MC :江戸城最高でした。ただ、今回本題です。
ゲスト:はい。
MC :お城から何を科学するか。
ゲスト:はい。
MC :ここですよ。
ゲスト:そうですね。
MC :今回はもう、ケーキのような段積みのお城、
ゲスト:はい。
MC :この科学を語っていただきましょう。
ゲスト:はい。
MC :まず何ですか?科学。
ゲスト:そうですね。やはりこう、お城っていうのはまあ、軍事施設なので、
MC :うん。
ゲスト:そうすると計算されるっていうところに
MC :うん。
ゲスト:なると思うんですね。これがまた面白くてですね、やっぱお城ってなによく利用するかというと、
ま、斜度ですね。角度。
MC :斜度。斜めの角度。
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:とか、ま、縦横、ま、横左右上下からいかに攻撃をくまなく死角なくできるか。
MC :うーん。
ゲスト:これがお城の肝になりますので、
MC :はい。
ゲスト:そういう、まあ、角度に注目するとお城ってすごく科学的で面白いかなあというふうに思います。
MC :そびえ立ってる角度?
ゲスト:そうですね、やっぱり城兵からして
MC :ええ。
ゲスト:守りやすく、えー、敵兵からしたら攻めにくい城っいうてのは、
MC :うーん。
ゲスト:優秀な城と言えるのでそうするとどうするかっていうと、
まあ、隈なく死角なく攻撃を仕掛けられるかっていう所になるんですね。
それを、あの、城の用語で横矢を掛けるというんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:その、いわゆる側面攻撃を如何にかけるか。
MC :はい。
ゲスト:これ肝なんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、その横矢掛りというのはですね、やっぱりその例えば石垣の高さを利用したりとか、
MC :はい。
ゲスト:あとは、えー、狭間というお城によく行くと壁に、ま、四角とか丸とか三角の穴が空いていると
MC :穴が開いてます。
ゲスト:あ、あれは攻撃用の小窓なんですね。
MC :槍とかをね。
ゲスト:そうですね、はい、そうなんです。あそこから弓とか
MC :弓だ、弓。
ゲスト:そうですね。
MC :槍じゃないですね。
ゲスト:槍もあるかもしれない。
MC :弓矢飛ばすんですね。
ゲスト:そうです、そうです。弓だったり、ま、鉄砲撃ったり、
MC :はい。
ゲスト:そういった狭間という穴も覗いてもらうと角度をうまく利用して、
MC :へぇー。
ゲスト:実はあの四角錐のような何というんでしょう城内側が広く、
MC :うん。
ゲスト:城外側が狭くなってるんですよ。で、ちゃんと角度をつけて、えー、そしてよく見てもらうと、
こう、通路に向かってきちんと、えー、向くようになってるんですね。
MC :ふうーん。
ゲスト:そういったものが、あのー、隈なく仕掛けられていて、
で、しかもあの適当にやっぱつけるんじゃないんですね、で、それをつけるようにしてますし、
MC :狭間っていうんですか?
ゲスト:狭間っていうんですよ。
MC :狭間ね。
ゲスト:はい。後は石落としというのもあるので、
MC :うーん。
ゲスト:注目していただきたくて、いわゆる建物の天守なんかも床を見てもらうと、
MC :はい。
ゲスト:出窓のようにちょっと出っ張っていてその下が開いてるんですよ。
MC :うん。
ゲスト:それを、ま、石垣をよじ登ってくる敵に対して、いわゆるま、石を落としたり、
まあ、鉄砲で攻撃したり、そういった、ま、上からの攻撃をできるように工夫してるんですね。
MC :今の話で、そっかここが戦いの場なんだっていうイメージが、
ゲスト:そうですね。
MC :湧きました。
ゲスト:そうなんですよ。
MC :そっか。
ゲスト:見て綺麗なのも大事なんですけれど
MC :うーん。
ゲスト:まあ、実用性があるか
MC :はあ。
ゲスト:そこがお城のポイントなので、
MC :うーん。
ゲスト:えー、壁も注目してもらいたいですし床も注目してもらいたいなと思います。
MC :へえー。
ゲスト:後は、あの綺麗なお堀ですね。
MC :お堀。
ゲスト:水のお堀ですけど、
MC :はーい。
ゲスト:あれもやっぱり軍事施設なんですね。
MC :はい。
ゲスト:ですから、ま、広ければ広いほどよさそうですけれども、
MC :うん。
ゲスト:広くしすぎてしまうと
MC :うん。
ゲスト:場内からの鉄砲が届かなくなってしまうので、
MC :ほお。
ゲスト:適度なやっぱり計算がされてるんですよ。それがあの、例えば長野県の松本城なんかは、
MC :はい。
ゲスト:えー、水堀が当時作られた当時の、ま、鉄砲ですね、が射程を計算して60メートルに計算してあるんですよ。
MC :へえええええ。
ゲスト:そういうところもやっぱ科学的に立証していくと面白いんじゃないかと思います。
MC :なるほどね。60メートルよりも遠いと、
ゲスト:はい。
MC :敵を倒せないということですね。
ゲスト:そうです、そうです。敵も、まあ、えー、天守に近づけなくなりますけど、
MC :ああー。
ゲスト:こっちからのも攻撃もできなくなって、
MC :仕掛けられないってことですね。
ゲスト:そうですね、届かないので、やっぱりその、鉄砲の、
まあ、弾が届く距離っていうのを計算しないといけないという
MC :間合いですね。
ゲスト:ことなんです。間合いです。
MC :いわゆる距離感みたいなね。
ゲスト:そうですね。そういうのやっぱりこう、ま、角度と距離を利用して計算をする、
それがやっぱりお城に隠された科学かなというふうに思うんですけれど
MC :はー。
ゲスト:はーい。やっぱり適当じゃだめなんですね。何事も
MC :ふうーん。
ゲスト:緻密な計算というか
MC :へええ。
ゲスト:そういうところをしていくのが
MC :後は、あとは。ええ。
ゲスト:楽しいと思うんですね。そうですね、やっぱり後はそのまあ、如何に死角を無くすかっていうところ
MC :死角、ううん。
ゲスト:ですので、あのー石垣なんかも見てもらうと
MC :はい。
ゲスト:面白くて有名なのは、えー、ちょっと遠いですけど熊本城ですね、熊本県の
MC :めちゃめちゃ遠いところにいきましたね。
ゲスト:そうですね。でもここは、えー、いつか大人になったら、
MC :はい。
ゲスト:行って欲しい憧れの城として覚えておいていただきたいんですけど
MC :はい。
ゲスト:石垣なんかも
MC :うん。
ゲスト:あのー、やっぱり、こー、壁なんですね。
MC :はい。
ゲスト:えー、まあ、豪壮な壁ですので、そこを利用して、えー、熊本城なんかこう、
MC :うん。
ゲスト:反りが入ってるんですね。
MC :ほー。
ゲスト:それは武者返しなんて言われるんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:あのー、下の方ですね、
MC :はい。
ゲスト:ていうのは、
MC :はい。
ゲスト:ま、斜度が30度ぐらいにしてあって、
MC :はい。
ゲスト:なんかちょっとよじ登れそうな気分になるんですけれども、
それが3分の2ぐらいの位置からちょっとずつこう、斜度を増して60度ぐらいになっていって、
最後は90度垂直になるっていう石垣があるんですよ。
MC :これ、でもどこのお城もそうじゃなくて熊本城は特別やっぱり、その、反り方がすごいんですか?
ゲスト:はい。
MC :へー。
ゲスト:えっと、熊本城だけではないんですけれども、
MC :ええ、ええ。
ゲスト:あの有名な加藤清正という
MC :はい。
ゲスト:武将が作った、ま、石垣の代名詞として知られていて、
MC :ええ。
ゲスト:あの熊本城で加藤清正が造った
MC :はい、はい。
ゲスト:お城なので、その石垣がより顕著ですねぇ。
MC :へえー。
ゲスト:でも、すごく
MC :反りを見るためには熊本城。
ゲスト:熊本城がいいですね。まあ垂直な、あのー、ものもありますので、
MC :今、あのー、「戦う城の科学」で
ゲスト:はい。
MC :熊本城発見したんだけど
ゲスト:はい。
MC :熊本城の石垣半端なくでかい。
ゲスト:でかいんですよ。
MC :なに、何かロングスカートみたいな感じですね。
ゲスト:ああ、そうです、そうです。本当に裾が、こう、広がって
MC :うーん。
ゲスト:で、あのよじ登れそうな気持になるっていうところが一つポイントなので
MC :だけど、上に行けば行くほど角度が、
ゲスト:はい。
MC :垂直になっちゃってるんで、
ゲスト:はい。
MC :敵はなかなか登れないよってことですか?
ゲスト:そうです、そうです。なんで、よじ登ったとしても振り落とされるっていうところから
武者返しなんて言うふうな言われ方も実はしてるんですよね。
MC :へえ。
ゲスト:で、石垣もただ並べるんじゃなくて、
MC :はい。
ゲスト:あのー、石垣って、ま、江戸城なんかもそうですけどあんまりこう真っ直ぐになってるこう、
事ってなくてジグザグジグザグしてるじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:で、それもさっき言った横矢をかける横矢掛りなんですね。
MC :うーん。
ゲスト:やっぱり、フラットに真っ直ぐにしておくと角に60度位のこう、死角ができてしまうので、
MC :はーい。
ゲスト:それを、まあ、左右の石垣をへこませたり出っ張らせたりすることによって
MC :ふううん。
ゲスト:斜めからその死角をカバーできるとそういう科学がそこに隠されているので、
MC :うーん。
ゲスト:お城ってあんまりこう真っ直ぐじゃないんですね。塁腺が。いつもジグザグしていて。
MC :へえええ。
ゲスト:後は、通路もあの、ジグザグしてるんですよ。だからお城行くと結構疲れるんですよね。
MC :ほー。
ゲスト:でー。あのそれはま、横矢を掛けるためにジグザグジグザグして
簡単にやっぱり天守に行けないような計算がされているというのが
MC :へえ。
ゲスト:一つポイントです。あとは角度という意味では、あのー、さっき疲れるって話をしましたけども
MC :はい。
ゲスト:あの、結構ゆるやかな傾斜になってることが多いんですね、お城の中っていうのは。
MC :へええーー。お城の中?
ゲスト:お城ってあの、平地に
MC :へえー。
ゲスト:はい。お城って平地に造られているようでいてあの平地のもあるんですけれども、結構多くが平山城といって
MC :はい。
ゲスト:ちょっと小高い山に築かれていることが多いんですね。
MC :はい。うん。
ゲスト:それはやっぱり上にいれば見下ろせるので
MC :うん。
ゲスト:有利だっていうところを利用していて、だからこう歩いているとなんかこう階段上っているわけじゃなくて
MC :うん。
ゲスト:すごい坂道でもないんですけど
MC :うん。
ゲスト:何となく上ってるんですね。
MC ::はい。
ゲストそれ結構ポイントで
MC :はい。
ゲスト:疲れるんですね。
MC :ああ、そこにアプローチするとだんだん疲れてきちゃう。
ゲスト:疲れていくと、やっぱりこう、なんか緩やかな坂道ってちょっと疲れますし、
MC :うーん。
ゲスト:あと石段なんかも注目してもらうと、
MC :うん。
ゲスト:なんか、歩きにくいんですよ。
MC :へえ。あ、へーえ。
ゲスト:それもやっぱり敵が攻め込んできた時に一気に駆け上がれないように
MC :へええ。
ゲスト:なんか人間て坂道は坂道で道真っ直ぐだとすごいダッシュできるじゃないですか。
MC :はーい。
ゲスト:で、なんですけど、あのー、やっぱりそのジグザグしていたりすると、
MC :はい。
ゲスト:足がどうしても止まっちゃうのでダッシュできないですし、
MC :エスカレーターの登り始めみたいな感じ?
ゲスト:そうです、そうです、そうです。
MC :歩こうとして、ちょっとね。
ゲスト:そうです、一回足を止めさせると。
MC :へー。こう、広くて入りやすいお城に入ったと思ったら実は小窓から狙われてるとかそういう感じ?
ゲスト:そうです。そういう感じですね。
MC :入り易いのには実は罠があるとか。
ゲスト:罠がある。
MC :いやー、もう時間になっちゃった?。いやー今度ちょっと城巡りお供させてください。
ゲスト:ああ、ぜひぜひ。やっぱお城はね行くのが楽しいので、
MC :ええ。
ゲスト:皆さんもこうお城にね、行って妄想力と働かせながら、
ちょっと角度に注目して歩いてもらうと面白いかなと思いまーす。
MC :すばらしいお話でした。でもまた遊びに来て下さいね。
ゲスト:あ、ぜひぜひ、また遊びに来させて下さい。
MC :えー、ライターの萩原さちこさんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「お城の科学 パート1」 ゲスト:萩原さちこさん
2018/04/01 Sun 12:00 カテゴリ:その他MC :今回のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は
ライターで編集者の萩原さちこさんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :萩原さんは、1976年東京都のお生まれで小学校二年生でお城に魅せられて
大学の卒業後出版や制作会社などを経て現在はフリーのライター、城郭ライター、
お城の、お城を専門としたライターさんということなんですね。
ゲスト:はい、そうです。
MC :お名刺をいただきますと、城メグリストってあります。
ゲスト:はい。
MC :かっこいいですね。
ゲスト:城を巡っている人っていうそのままですけれど。
MC :いや、でもオフィス城メグという。
ゲスト:そうですね。ははは。
MC :会社も立ち上げてらっしゃる。
ゲスト:いえいえ。名ばかりですけれども、はい。
MC :すごいじゃないですか、それで実はなんで、あの、お城を巡る専門家の方がこの科学番組、
9年間続く文化放送代表するこの長寿番組の、来ていただいたかと。出版された本がすごいんです。
「図説・戦う城の科学」。
ゲスト:はい。
MC :ゆえにお招きしました。よろしくお願いたします。
ゲスト:よろしくお願いしまーす。
MC :何を持ってお城で科学なんですか。
ゲスト:いえ。なん、どうでしょうね。突っ込まれると、
MC :へえー。
ゲスト:あの、ちゃんと科学的なことが書いてあるか
MC :はい。
ゲスト:心、書いておきながら心配になるんですけども、、
MC :はい。
ゲスト:やはりこうお城って、こう、計算されてるっていうところが一つ魅力なんですね。
MC :はー。
ゲスト:やっぱり、なんでかっていうとお城って、まあ、皆さんもしかしたらイメージでこう、
きれいなものっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、
お城って何のためにあるかっていうと戦うためにやっぱりあるんですね。軍事施設なので、
MC :はい。
ゲスト:そうすると、まあ、いかに敵を倒すか、お城を守るかっていうところで様々なまあ、
工夫計算ていうのがされてますので、
MC :はい。
ゲスト:そこが、まあ、科学的に、えー、ちょっと語れるんじゃないかというところですね。
MC :いやぁ、そうか、あ、すごい基本的なことですけどー、
ゲスト:はい。
MC :だから、殿様っていう人はお城の一番上にいるわけですよね。
ゲスト:いや、それがですね、
MC :ちがうんですか?
ゲスト:天守の、天守にはお殿様はいないんです。
MC :えっ、いないんですか。あれ?
ゲスト:そうなんですよ。
MC :え、よく城を落とすっていうじゃないですか。
ゲスト:ええ。はい、はい。
MC :それじゃ、城のてっぺんには誰がいるんですか?
ゲスト:あのー、えーと、天守ですよね。
MC :ええ。
ゲスト:五重とか三重の天守
MC :はい。
ゲスト:あれ、あそこにはあの人は住まないんですよ。
MC :そうなんですか。
ゲスト:そうなんです、あそこは、
MC :ええ。
ゲスト:あの、いわゆるタワーみたいなもので、
MC :ええ。
ゲスト:えー、ま、象徴なんですね。権力の。
MC :ええー。
ゲスト:ですから、外から見ることに意義があると。
MC :へえーー。
ゲスト:そうなんです。ですから、お殿様じゃ、どこに住んでるかっていうと、
MC :うん、うん。
ゲスト:えぇっと、天守がある麓というか、
MC :はい。
ゲスト:御殿ていう、えー、
MC :ええー。
ゲスト:建物に住んでいて、実はちょっとイメージと違ってガックリくるんですけれどー、
MC :それ、お城のあの、一連のあのー、モコモコしたケーキみたいな状態のあの、お城には住んでなくて
ゲスト:そうなんです。
MC :別に御殿ていうのがあって、
ゲスト:はい。
MC :そこに殿様いるんですか。
ゲスト:はい、そうなんですよ。
MC :でも、その殿様を守るために、
ゲスト:うーん。
MC :お城っていうのは作られて、
ゲスト:はい。
MC :科学的に、
ゲスト:はい。
MC :構築されたわけですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :へぇー。まず一個勉強になりました。
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :すっごい話ですね。で、お城ってちなみにね、
ゲスト:ええ。
MC :何時ごろ造られたものですか、基本的なことですけど。
ゲスト:はい。これはもうあの、遡っていきますとま、諸説あるんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:一般的には弥生時代まで遡ると
MC :ええ!ええ!
ゲスト:実は言われてるんですよ。
MC :弥生時代って紀元前ですよ?
ゲスト:そうですね、ええっと、
MC :紀元前
ゲスト:お城、どこからお城と言うかっていうところになると、
要はその軍事施設としてのまあ、概念が生まれたっていうのを考えると
MC :はい。
ゲスト:弥生時代の環濠集落まで遡るんですよ。
MC :へえ。
ゲスト:いわゆる自分のま、その時は集落ですね村といいますけれども、
ま、その周りを、えー、守るためにその周囲を、の、ま、土を掘ってそれを盛って土の壁を作る
MC :へえー。
ゲスト:こういう概念が生まれたのがま、環濠集落といわれてますので、いわゆる、ま、お堀ですよね。
MC :うん、うん。
ゲスト:水は入ってませんけれども、え、掘って盛って掘ったところが堀のようになりますので、
で、その土を盛ってま、壁を造って防御をすると、そういった概念が生まれたのは、
弥生時代なんですね。であとはまあ、
MC :ほー。
ゲスト:物見台のような高いものを造っていわゆるま、櫓の発祥といいますか、
MC :はい。
ゲスト:そういった物を造って監視をする、両国を守っていうところが、あの、生まれてますので、
ま、遡っていくとま、城という名称ではないんですけれども
そこが始まりという風に言われているんですね。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:そうなんです。あの城っていう字は、ま、土に成ると書きますよね。
MC :うーん。
ゲスト:ですから、こう、まさに、こう、土を掘って盛る土で造るというところで、
MC :へええ。
ゲスト:そこが始まりと言われているんです。
そのあとま、いろんなお城、ま、城と言いますか、えー、お城もいろんな歴史があって、
MC :ええ。
ゲスト:ま、天守が誕生するのって実はものすごい後なんですね。
MC :うん。
ゲスト:そこに至るまでには、ま、様々な、こう、ま、
見た目も違う役割も違うお城っていう長い歴史があって、
実は天守が誕生するのはもう戦国時代の終わりになってからですので、
MC :ほー。
ゲスト:ここ近代建造物というか、
MC :へー、ええ。そうか。
ゲスト:そうなんですね。割とこう戦いの時代も終わって、割と象徴的な役割として、
天守っていうのは誕生しますので、
MC :ほー。
ゲスト:ま、最後に残ってるものがま、今残っているものになり、なるので、
MC :はい。
ゲスト:どうもお城っていうともう、その天守はイメージとしてあるんですけれど、
実は長い歴史と色んなお城があるっていうことなんですね。
MC :じゃ、僕らがイメージするお城は、いわゆる最新のものばかりってことですね。
ゲスト:そういうことになりますね。はい。
MC :新しいものばかり見てるんですね。
ゲスト:新しいものが最後に残るので、
MC :ははははは。
ゲスト:それを私たちは見てるといったことになります。
MC :古ーい、そう、こう、城見に行くイメージだったんだけど、実は、
ゲスト:はい。
MC :最新のお城ばっかりということ。
ゲスト:そうですね。
MC :あらー。そうか、えっ、関ヶ原の戦いで、
ゲスト:はい。
MC :1603年ですよね。
ゲスト:ええ。1600年です。
MC :1600年か。
ゲスト:ええ。はい。
MC :で、それ、それぐらいからもう城って無くなっちゃってるわけですよね。
ゲスト:いえいえ、それがですね、
MC :まだ、あった。
ゲスト:実は、今世の中に残っている、ま、一般的なお城ありますよね、
MC :はい。
ゲスト:姫路城ですとか彦根城とか、
MC :はい。
ゲスト:ま、松江城とか、
MC :ふん。
ゲスト:そういったお城っていうのが、だいたい築かれるのが関ヶ原合戦直後ぐらいなんですね。
MC :おおー。じゃー。
ゲスト:そうなんですよ。
MC :400年位。
ゲスト:そうです。ちょうどその位ですね。
MC :うーん。
ゲスト:で、そういったお城が造られなくなるのが、
MC :うん。
ゲスト:1615年なんですよ。
MC :うーん。
ゲスト:ですから、割とその15年間に
MC :すごい。
ゲスト:全国に一気に今あるお城っていうのは、こう、わーっと築かれて、
MC :へぇー。
ゲスト:ちょっとこう、電光石火のように、築城ブームみたいなところで築かれてると、
MC :そっか。
ゲスト:割とこう、長い間をかけて造られたイメージがあるんですけれども、
実は今残っているお城っていうのはその、15年位で一気にこう、花開いて造られたお城なんですよ。
MC :何か今東京オリンピック前の建設ラッシュの東京と似てますね。
ゲスト:あっ、ほんとにそうですね。はい。
MC :400年前は
ゲスト:はい。
MC :関ヶ原後の
ゲスト:はい。
MC :お城建設ラッシュだったということですね。
ゲスト:建設ラッシュですね。
MC :全国的に?
ゲスト:全国的に。
MC :へえー。鳥肌立っちゃった。何か今歴史感じて。
ゲスト:そうなんですよ。そういうの見ていくと、
MC :ええ。
ゲスト:あの、さっき弥生時代からって言いましたけど
MC :ええ。、
ゲスト:じゃ、それまでの、こう、1600年までのお城ってどうだったんだろって見ていくとまた、
こう、いろんな歴史というか、お城もこう、流行みたいなものがあって、どんどん変わっていくんですよね。
それもまた、一つ面白いところではありまーす。
MC :あの、キッズ達がお城を学ぶにあたって、
ゲスト:はい。
MC :身近なところ?
ゲスト:はい。
MC :ど、どこですか、お城
ゲスト:あの、そうですね、お城っていうとなんか天守をイメージしてしまうので、
MC :はい。
ゲスト:なんかすごく関西の方に多いようなイメージもあるんですけども、
MC :はい。なんか西日本のイメージ強いですね。
ゲスト:まあ、それは、
MC :古墳とか
ゲスト:そう、そうなんです、そうなんです。西の方で石垣の積む技術とか、
MC :うん。
ゲスト:天守が誕生するので、
MC :はー。
ゲスト:なので、やっぱり
MC :へえー。
ゲスト:東京にいるとちょっと違うような感じがしますけれど、実は東京にすごいお城がありまして、
MC :何城ですか?
ゲスト:江戸城です。
MC :江戸城って、
ゲスト:はい。
MC :皇居?
ゲスト:皇居です。そう、今皇居があるところが、
MC :はい。
ゲスト:江戸城で、
MC :はい。
ゲスト:あのー、東京にお城なんかないと思っているキッズも沢山いるかもしれませんけれど
日本一のお城なんです、実は。
MC :あっ、そうか。
ゲスト:はい。
MC :あの、あの皇居のお堀も、
ゲスト:はい。
MC :あれはー、
ゲスト:そうです。あれは
MC :だから、
ゲスト:江戸城。
MC :江戸城時代ということ。
ゲスト:そうです、そうです。
MC :徳川が造ったということですか?
ゲスト:はい。江戸城っていうのは
MC :ふーん。
ゲスト:徳川幕府の
MC :ふーん。
ゲスト:いわゆる本城、居城になるので、
MC :へえー。
ゲスト:ま、幕府のお城ですから、日本一なんですね。
MC :あの、じゃあ、あのお堀の周りのね、
ゲスト:はい。
MC :石垣なんかも綺麗になってるけれど、
ゲスト:はい。
MC :あれもじゃあ、江戸城の
ゲスト:そうです、そうです。
MC :徳川幕府時代のものが、
ゲスト:そうです、そうです。
MC :まだ、残ってるってことですか?
ゲスト:はい。あの、一部もちろん、あの、修復されたりしてますが、
MC :ふーん。
ゲスト:あの、かなり広範囲に渡って残っているんですね。
MC :でも、でも、一周えっと、5キロぐらいあるから、
ゲスト:はい。
MC :相当、じゃあ、大っき城ってことだったんですね。
ゲスト:大っきいですよ、日本一大っきいんです実は。
MC :あっ、そうか。
ゲスト:はい。分かりやすい例だと、
MC :はい。
ゲスト:あの、中央線ありますよね。
MC :はい。
ゲスト:中央線のあのー、飯田橋とか、
MC :はい。
ゲスト:市ヶ谷とか、
MC :はい。
ゲスト:えー、で、線路って何か土手の上に立っていて
MC :ああー、はい。
ゲスト:横に川が流れてるじゃないですか、
MC :はい、川があってボート乗り場あります。
ゲスト:はい。あれ外堀なんですよ。
MC :外堀、はい。
ゲスト:はい。なので、ま、
MC :そっか。
ゲスト:皇居のところから、えー、考えると結構距離があると思うんですが、
もうあそこのぐるっと一体になっているところが、ま、江戸城というんですよ。
MC :ちょっと全然科学から脱線したけど面白い。
ゲスト:脱線しましたけど、そうですね。
MC :面白かったです。
ゲスト:はい、ちょっと、全然科学的ではないですがー、
MC :皆んなこれで、地図を見る。
ゲスト:はい。
MC :飯田橋の駅、そして皇居周辺、江戸城勉強する。そして、宿題だ。来週までの。
ゲスト:はははい。
MC :そしてとりあえずそこで科学的なもの見つけておいでってことですね。
ゲスト:そうですね、そうですよ。はい。
MC :じゃ、来週ちょっとまたお話を伺いましょう。
ゲスト:はい。
MC :いや、あっという間でした。えー、今週の「サイコー」はライターの萩原さちこさんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「天気予報 パート2」 ゲスト:天達武史さん
2018/03/01 Thu 12:00 カテゴリ:自然MC :さ、今週のサイコーも気象予報士の天達武史さんです。こんにちは。
ゲスト:お願いしまーす。
MC :お願いします。えー、何を隠そう僕と天達さんは3年前までフジテレビの特ダネで同僚であったという
ゲスト:いやー、そうですよ。もう先生みたいなものですよ、大村さんは。
MC :ほんとに?そこまで言ってくれるんですか?
ゲスト:いやー、ほんとにそうですよー。
MC :もっと聞かせて。
ゲスト:いやー、ははは。もう僕ほんとに尊敬する方の5人のうちのひとりですよ。
MC :いや、よく聞こえない。
ゲスト:ははははは、
MC :はい?あっそうですか。
ゲスト:いやほんとにそうですよ。
MC :有難うございます。いやー。
ゲスト:大村さんがいたから僕は特ダネでやってこれたんです。
MC :いや僕もそう思います。
ゲスト:ははは。
MC :最初天達さんを見た時は大丈夫かなと思ったんですけど、
ゲスト:ですよねー。えー。
MC :まあ、そんなことはないです。いっしょにね、持ちつ持たれつでやってきました!
さあ、今回もお天気のお話を伺っていきますけれど、
思い出してみると僕がリポーター時代はー埼玉県の熊谷市、
ゲスト:はい。
MC :ね、多分あのー聞いてるキッズたちもいると思うんですけどー、
ゲスト:ふん。
MC :それが40.6度とかね、
ゲスト:あーあー、はいはい。
MC :日本で一番暑い。暑いぞ熊谷。
ゲスト:はい。
MC :よく取材してたんだけど。
ゲスト:はい。
MC :去年いきなり四国の
ゲスト:そうー。
MC :高知県
ゲスト:えー。
MC :むら、これ文化放送聞こえないところ。
ゲスト:はい。
MC :41度。
ゲスト:いやー、ちょっとねー、あのノーマークですよね。
MC :ノーマーク、あははは。
ゲスト:まあ、気温の上がるとこなんですけど、隣にあの四万十川って大きな川があるんで
そんなにね気温が上がるような所でもなかったんですけどー、
MC :はい。
ゲスト:まあ、いろんな条件が重なって猛暑になってしまいましたね。
MC :たまたまですか、それは。
ゲスト:いや、もう全部のあの暑くなる要素が全てあのー加わっちゃったっていうのがあってー。
MC :じゃ、その日去年の夏の1日だけたまたまいろんな条件が四万十市、に集中して41度っていう、
ゲスト:まあ、そうですねー。一つじゃないんですけどねー。
MC :やっぱりでも安定して暑いのは埼玉の熊谷とか
ゲスト:はい。
MC :あのあたりですかねー、
ゲスト:そうですね。熊谷、館林とか
MC :群馬県の
ゲスト:群馬県の
MC :はーい。
ゲスト:えー、あの辺はやっぱりこの先もしかしたらね塗りかえる日が来るかもしれませんね。
MC :あっ、そうですかー。
ゲスト:はい。
MC :まあ、あのーちょっとね熱中症にならないように気を付けながら
ゲスト:いやー、そうですねー。
MC :過して頂きたいけれど、なんであのあたりは
ゲスト:はい。
MC :暑くなるんですかね。
ゲスト:あの辺はですねー、まずあのー都心、東京都心でー、
あったまった熱がー夏の間南風で流されてくんですよね。
MC :ほっほっほ。
ゲスト:それとあともう一つはーちょうど関東の西側にある山の麓にあるんですよ。
熊谷とか館林、はい。そうすると熱風が山を越えてくる時っていうのは気温が上がるんですよね。
MC :フェーン現象
ゲスト:そうです。フェーン現象。このフェーン現象と都市部の熱、
この2つがですねーやってくるところなんですよ。
MC :あ、ダブルパンチ。
ゲスト:そうです。はい。
MC :じゃこのラボのある浜松町の熱もー、
ゲスト:えー、
MC :あのーその熊谷とか群馬の方に流れていく
ゲスト:そうですねー。
MC :わけですか。
ゲスト:はい。午後になると。
MC :あら、そうなんですか。だから暑くなりやすい。
ゲスト:そうですねー。
MC :で、その去年41度記録した、えー、高知県の四万十市はそういう条件にはあてはまらない感じですね。
ゲスト:そうですねー。あの一つはまあフェーン現象っていうのはあちらも山の麓ですからあるんですけれども、
去年の場合はですね、あのよく夏暑くなる時って太平洋高気圧っていう
MC :あ、いいますね。
ゲスト:ね、暑い高気圧がきますよねー。あれが覆ってきたんですけれども、
その上にもう1こチベット高気圧っていう、
MC :ほぉー。
ゲスト:さらに上空の暑い高気圧が2つこう重ね合って要は蒲団の2枚重ねみたいな
MC :ほー。
ゲスト:状態になっちゃてたんですよね。
MC :え。
ゲスト:それが何日も続いたのでー気温が下がらないうちにどんどんどんどん熱が蓄積されてって
昼間気温が上がっていくと、そういう状況が続いたんであそこまでいっちゃったんですよね。
MC :なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :へぇーー。あと僕気になるのがねー。
天達さんがあのテレビで始めるころってね、ゲリラ豪雨って言葉はね、なかったと思うんですよ。
ゲスト:はぁー。
MC :僕もリポートしながらゲリラ豪雨って言葉使ったことなかったんですけどー、
ゲスト:えー。
MC :この何年かじゃないですか、ゲリラ豪雨。うん。
ゲスト:そうですね。
MC :うん。
ゲスト:ま、もともとこれは気象用語ではないんですけれどもー、よくでもこれ名前つけたなーっていう
MC :ゲリラ豪雨
ゲスト:ゲリラ豪雨。まさにそうじゃないですか。
ほんとにあの数十分であの雨の原因となる積乱雲が急発達するんですよね。
で、ゲリラ的にある1ヵ所ピンポイントに降らせるっていう
その雨も激しいそういうのやっぱり増えてますね。はい。
MC :あの、ゲリラってもう一時死語かと思ったけれど、
また今あのねキッズたちも知らなくちゃいけない言葉になってきましたけれど、
このゲリラ豪雨って定義はどういう定義ですか?
ゲスト:はい、これー
MC :何をもってゲリラ豪雨
ゲスト:これはですねー、特に決まって何ミリ以上とか何時間雨が降るとかそういうものはないんですよね。
MC :天達さんが決めるんですか?ゲリラです!って決めたらゲリラ。
ゲスト:あのー、まあただ雨の降り方の雰囲気ですよね。
MC :雰囲気でー?えへへへ、
ゲスト:はははは。
MC :ゲリラか否かは?
ゲスト:えー、
MC :おー、ゲリラだなーって感じ?
ゲスト:いやだから僕なんかはー、まああの気象庁としてはあのー正式な名前にはしてないんで、
ほんとはそんなに使っちゃいけないのかもしれないんですけど、
MC :はい。
ゲスト:ただ、ずうーっと晴れてたところがー急に積乱雲が発生してドバーッと
こう降らせるような兆候がある時にはあえて僕は言って注意を促すっていうのをしてますね。
MC :あー。
ゲスト:えー。
MC :先週話を聞いたね、その新しい衛星のGPM衛星?
ゲスト:はい。
MC :これによると、これがあの運用されるようになるとゲリラ豪雨なんかもピンポイントで、
例えば浜松町、駅前ゲリラ豪雨何時何分来そうだ!とここまでわかるんですか。
ゲスト:え、それはですねー。あのこのGPM衛星ともう一つ今使っているドップラーレーダーっていうですねー、
あの地上から見てるレーダーがあるんですけれど、そういうものを組み合わせることで
より精度アップっていうのが、あのー多分出来ると思いますね。
MC :ドップラー
ゲスト:ドップラーレーダー、
MC :レーダー
ゲスト:はい。これは、
MC :ドップラー効果ってよく聞きますね。
ゲスト:そうですね。
MC :救急車の音が
ゲスト:そうです。
MC :あのー変わるとかー
ゲスト:えー
MC :遮断機の
ゲスト:はい。
MC :ふみきりのキンコンカンコンの
ゲスト:えー。
MC :音が変わるとか
ゲスト:そうです。
MC :それとドップラーレーダー似てるんですか。
ゲスト:そう、まさにそれなんですよね。要はレーダーから電波を出して音が強く聞こえるか、
雨雲に当たってですね、雨粒に当たって、強く聞こえる時は激しい雨だとか、
弱い場合はそこまででもないとか、遠い近いっていうのがわかるレーダーがあるんですよね。
MC :ほっほっほっほ。
ゲスト:そういうものを組み合わせることで、あのGPM衛星、
先週話したGPM衛星っていうのは3時間に1回しか今測れないんです。だからその間を
MC :えーー。
ゲスト:はい。その間をそのドップラーレーダーでフォローしてあげれば
今よりも数段効果は上がってくると思いますね。
MC :あ、そうか。GPM衛星は衛星だから常に日本の上空にいてくれるわけじゃないってこと
ゲスト:そうなんですよ。ぐるぐるぐるぐる地球全体上を回っている衛星なので、
MC :なるほど。
ゲスト:えー、だから、そのGPM衛星で雲の中がどうなっているのか、
どういう特長があるのかっていうのを捉えた上で
ドップラーレーダーなんかを使うと今よりも精度上がってくると思いますね。
MC :なるほどね。そ、ゲリラ豪雨を先読みするよう予測する事もじゃあ可能になってくる
ゲスト:そうですねー。何時何分に降るか、洗濯物何時にしまうかとか、はい。
MC :すごーい。
ゲスト:もしかしたら、あの数日後運動会があるけど、何時頃降るからこの時間は大丈夫かとか、
そういうところももしかしたらわかってくるかもしれないです。
MC :いやー、それがまたそのドヤ顔でさー、ぼんって気象予報士
ゲスト:はい。
MC :天達武史がやったら、また長野美郷ちゃんから1位の座を奪還することできるかもよ。
ゲスト:ほんとですか。
MC :はーい。へへへ。
ゲスト:よーしじゃあ、ちょっとこれ使い方、使う方にもいろいろ
MC :ははははは。
ゲスト:ね。勉強しなけりゃいけないんで、頑張ります。
MC :あー、あと予報士さんも最近PM2.5の動きも注目しなくちゃいけなくなってきたじゃないですか。
ゲスト:そうですねー。
MC :あれは、けっこう慎重にみなさん見てます?
ゲスト:見てますね。あとは結構みなさんあのー大丈夫なんだけれどもー、
大げさに報道しちゃってるところもちょっとあると思うんですよ。
MC :はー。
ゲスト:えー、あのー
MC :どこまで害があるかまだ分からないですもんね。
ゲスト:そうなんですよ、それもありますしー、あともともとPM2.5っていうのは昔からあるものでー、
今、あの中国なんかでーあのー開発が行われてそれがかなりの濃度できてしまうっていうのが、
ま、年に何回かはあるんですけれども、ほんとにね、そのぐらいの頻度なんですよね。
MC :えー、なるほどね。はー、わかりました。
あの、天達さんね、僕うちの子供たちももう大学生になっちゃったんですけどー、
ゲスト:もう大学生ですかー。
MC :会った時まだ小学生だったんだ。
ゲスト:いやー、そうですよー。
MC :それでね、天達さんをテレビで見てね、あのー子供の頃にね天達さんの耳はね、
ねずみにかじられたんだよって教えたの。
ゲスト:えっーー。
MC :天達さんの耳のさ、形がちょっとね、下の方がね
ゲスト:あ、そうですか。
MC :ちょっとそうじゃん、ほんと、テレビ見て。
ゲスト:あーーー。
MC :あのーもしラジオを聞いてるキッズもあのまた月曜日、
天達さんの耳見たら、ねずみにかじられたっていう
ゲスト:あははははは。
MC :ちょっとそういう意識で見よう。
ゲスト:初めて言われました。
MC :僕がかっ、勝手に、今だから告白してるんです。
実はそれをネタにしてね、そんなこと言ってたの。
ゲスト:あ、実は僕の子供もー
MC :うん。
ゲスト:ちょっとね、変わった耳してるんです。
MC :あー、そうですか。
ゲスト:へへへへへ。
MC :はははははは。
ゲスト:あいた、じゃ僕のあれなのかなー。
MC :遺伝ですねー。
ゲスト:あ、そうですかー。
MC :やーまーラジオだからちょっと耳の形はなかなかね、むつかしいけれどー、ま、もしテレビで
ゲスト:はい。
MC :機会があったら、ねずみにかじられた耳
ゲスト:あーそうですかー。
MC :あははははは。
ゲスト:あははははは。そうかなー。ははははは。
MC :いやー、楽しかったなー。えー、もう終わりですかー。えーーー、今度いつ来てくれるんですか?
ゲスト:いやー、もう呼んでいただければいつでも。
MC :じゃあ、二度と呼びません。
ゲスト:あーそんなこと言わずに呼んでくださいよ。
MC :あははははは。
ゲスト:はははは。待ってます。
MC :えーー、はい。やー、二週に渡ってお話伺いました。
あの天達さんも気をつけて、体にね気をつけて、あの頑張ってくださいね。
ゲスト:有難うございます。大村さんも。
MC :応援しています。はい、有難うございます。天達武史さんでした。有難うございましたー。
ゲスト:はい。 -
「天気予報 パート1」 ゲスト:天達武史さん
2018/03/01 Thu 12:00 カテゴリ:自然MC :さ、今日のサイコーは気象予報士の天達武史さんです。こんにちは。
ゲスト:よろしくお願いしまーす。
MC :いやー天達さん、
ゲスト:はい。
MC :え、僕は天達さんとかつてフジテレビの特ダネでお世話になったんですよ!
ゲスト:いやー、もう懐かしいですねー。
MC :ねー。3年振り。
ゲスト:えー。
MC :元気でしたー?
ゲスト:元気です。もー大村さんも全然変わってないですね。
MC :いやーテレビでは見てます、いつも。
ゲスト:有難うございます。
MC :いやー、好きな気象予報士ランキングではね、いつもトップの人気者。
ゲスト:いやーでもね、去年抜かれちゃいました、でも。
MC :えっ、陥落したんですか?
ゲスト:はい。
MC :えっ、誰になったんですか?
ゲスト:あのー、めざましテレビの長野美郷ちゃんが1位になって、
MC :あっ、そうですかー。
ゲスト:はーい。そうなんですよー。
MC :天達さんは育てたようなものなのにねー、彼女のこと。
ゲスト:いえー、いえいえ。
MC :そういうことは言ったほうがいいですよ。
ゲスト:あ、じゃ、そうです。あはははは。
MC :あはははは。抜かれちゃったんですか。でも男性ではナンバーワンじゃないですか。
ゲスト:はー、まー、うれしいことに。はい。
MC :ねー、でも人柄もいいですしねー、
ゲスト:いえいえ。
MC :え、もう何年ですか?
ゲスト:えーと、今度9年目になりますね。
MC :あっ、そうか、9年ぐらい。もっともっと長くずっといるような感じでしたけど。
ゲスト:ねー、
MC :そうですか。
ゲスト:でも半分ぐらいなんですよ、特ダネの歴史のね。
MC :そういうことですね。あーそうですか、じゃ、よろしくお願いしますね。
ゲスト:お願いします。
MC :さあ、今日のテーマは天気予報が変わる、ということなんですけれど。
ゲスト:はい。
MC :ちょっと前にテレビで天達さんもしゃべってましたけれど、
ゲスト:はい。
MC :すごい衛星が打ち上げられたと、
ゲスト:えー、そうなんですよ。
MC :ね、ニュースでやってました。
ゲスト:今回日本のJAXAとアメリカのNASA、これが共同開発して出来た衛星なんですけど、
これ何がすごいってあのみなさん気象衛星のひまわりっていうのは聞いたことあると思うんですけど、
あれはね、宇宙の上から雲の上の部分をこう見てるんですよ。
MC :宇宙から雲の上の部分ね。
ゲスト:はい。雲の上の部分見えますよね。
だけど、今回の衛星っていうのはー、GPM衛星っていうんですけどもー、
MC :GPM衛星?
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:二つの電波をですねー、雲にあてることで、雲の中身までわかっちゃうという、衛星なんです。
MC :熱いですねー、天達さん。
ゲスト:へへへ、そうなんですよ。
MC :いやー、すごいわかりやすい。あっ、雲の中身までわかる?
ゲスト:そうなんですよー。
MC :いわゆる表面上の雲だけじゃないんだ。
ゲスト:そうです。雲の上の部分だけじゃなく、中で例えば雨がどういう風な形で存在しているのかとか、
雪が、雪に代わってるのかとか、そういう事までね、わかってしまうかもしれないっていう。
MC :雪か雨か、雹か霰かとか
ゲスト:それもわかるんですよ。はい。
MC :えーー。あの僕らよくあのブルーベースで白いのがうにゃうにゃってなってて、
で、気象衛星ひまわりの画像ってやってるじゃないですか。
そしたらその白っぽいのが雲だけれど、その中の物質もわかるということ?
ゲスト:そうですね。どういう状況になってるのかっていうのが、
しかもあの世界、地球全体がですねー見えてしまうんですよね。
だから一番のこの衛星を打ち上げた目的っていうのはフィリピンとかマレーシアとかあんまり、
あの気象の観測点がないような場所、そういう所って難しいんですがー、
そういうところの予想もわかることで地球全体のあのー予報の精度のアップにつながるんじゃないか。
水害の予防に特に役立てようっていう。はい。もあるんですねー。
MC :あの、気象に関しての後進国もあるわけですよね、日本はかなり先進国じゃないですか。
ゲスト:はい、そうですね。
MC :だけど、そのー東南アジアの気象予測の後進国からするとすごくじゃあ助かるかもしれない。
ゲスト:えー、そうですね。去年もあのー台風の被害がフィリピンで大きくありましたけれどもー、
ああいうのも前もってどういった台風なのかっていうそういう特長が分かるかもしれないですねー。
MC :へぇー。で、今出てきたひまわりってのはもうずぅーっと多分ね誰もが知ってると思うんですよ。
気象衛星ひまわりの画像。
ゲスト:そうですね。
MC :あれは日本のですか?
ゲスト:そうですね。日本であの打ち上げてるんですけれどもー、
ま、これも何年か一度にこう更新していく
MC :うん。
ゲスト:ものなんですけれどもー。ま、今何号かちょっと忘れちゃいましたけれど、
MC :えー。
ゲスト:えー、あれはあれでまたあのー雲の輪郭とか、あのどういう雲か、
ま、そういうのがわかるんですけど、ま、ちょっとね、
ゆってみればあのー病院に行ってあのーちょっとねー体調悪くなった時に見る
あの聴診器みたいなものだと思うんですよね。
MC :ひまわりは聴診器。
ゲスト:聴診器。で、
MC :お医者さんが耳にあてて、はい、胸出して、背中向けて
ゲスト:そうですね。はい。それでまあ、音をー中の音を感じとってどういうものかっていうのを
ある程度想像していくんだと思うんですけど、今回のこのGPM衛星っていうのは、
まあ、ゆう、ゆうーなればレントゲンとかCTスキャンみたいなもんだと思いますね。
MC :全然違うじゃないですか。
ゲスト:えーぱっとこう中身がこう見えてくるっていう。
MC :これによって、より当たる確率高くなる。
ゲスト:そうですね。あのー急には上がらないと思うんですけれどもー、
ただねもしかすると87パーセントがえー89パーセントぐらいになるかもしれない。
MC :2パーセントぐらいの差ですか。
ゲスト:えー、なかなか90パーセント以上というのは難しいですね。
MC :あ、ある程度上の方までくると、あのー率を上げるの難しいんですか。
ゲスト:そうですね。ただその87から89に変わる2パーセントなんですけども、
その中で例えば局地的なゲリラ豪雨ですとか、
ま、そういった予報は精度がアップする可能性もありますし、
うん、台風の進路予想図なんかもー精度はもっとよくなる可能性ありますね。
MC :いわゆる人命に関わるようなあのー気象に関してはーかなりこう精度が高くなる。
ゲスト:そうですね。そういうーなる可能性あると思いますね。
MC :ふーん。そっかー。でもほんとにあのー僕ら子供の時に比べると、最近ちょっとおかしいですよね。
ゲスト:いやー、そうですよねー。
MC :うーん。
ゲスト:感じます?大村さんも。
MC :思う。で、天達さんも夏になるとーこの人いつ寝てるんだって感じで、
ゲスト:あーははははは。
MC :あちこち行ってるじゃないですか。
ゲスト:いや、そ、僕もほんと実感としてありますね。ここ数年。
えー、夏に限らず冬も大雪になりましたしー、そういう極端な気象っていうのはー、
あのデータ見てもやっぱり増えてるんですよねー。はーい。
MC :それ、あの地球温暖化に、の影響だとかねいろんな風に言われてますけれど、
ゲスト:そうですね。
MC :なんなんですかね。
ゲスト:やっぱりあの、地球温暖化というのが一つ根底にはあると思うんですね。
MC :えー。
ゲスト:でも簡単に言うと、ま、地球の歴史がその46億年、
あのずぅーっとこの美しい地球を守り続けてきたのが、今地球がですね、
自分、地球ってあのすごく頭いいんですよ。自分でこう熱くなり過ぎないように、
寒くなり過ぎないように熱をいろんな所に送ったりして平均化されてきたのがー、
今急激に人間が出す二酸化炭素なんかの影響ですごいスピードでおかしくなって、
気温が上がってきちゃってるんですよねー。
それで地球全体がちょっと今コントロールできなくなってる影響で
極端な気象っていうのが結構いろんな所で出てるっていうのが、
えー、一つあると思いますよね。
MC :ふーん。地球は頭がいいってなかなかいい言葉ですね。
ゲスト:いやー、と、思いますよー。
MC :その頭の回転よりかも僕ら人類が地球をいじくってしまったので、
ゲスト:そういうことですね。
MC :地球がついてこれなくなっちゃったってこと?
ゲスト:はい、今そういう状態だと思います。
ま、だから処方してあげないと僕らが逆に処方してあげないといけない時期に入ってますよね。
MC :どんなことやればいいんですか?
ゲスト:いやー、これはもうほんとに地球温暖化で二酸化炭素を減らすことが大事なんですけれども、
今実際にエコの活動しよう!というふうに思ってても今ほんとの現実のこといってしまうと、
あのーもうその二酸化炭素を減らすにもコストやリスクがものすごくかかってきてしまって、
社会全体を今もう変えなきゃいけない時期になってるんですよね。
だから、ほんとに深刻な問題でそこをもうほんとに世界規模でみんながやっていかないと、
これからどんどんどんどんおかしな感じになってきてもう、
MC :そうですよねー。いや、僕3年北海道に住んだから思うんだけどね、北海道はいいですよ、うーん。
ゲスト:はぁー。どういうところがいいですか。
MC :エアコンもいらないでしょ、クーラーがいらないわけですよ。
で、四季の変化があるから自然に感謝ができるのね、いや、ほんとに。
あのーあの真っ白なシーズンがあったからー、あの今から花がどんどん咲くシーズンで、
そしてもう燃えるような秋の
ゲスト:はい。
MC :こう紅葉のシーズンが来ると
ゲスト:うわぁー。
MC :真っ白になるじゃないですか。
ゲスト:えー。
MC :そうするとやっぱり一年あのー、一緒に生きたなっていう感じがして、
ゲスト:あーーー。
MC :その、さっき言ってた地球の頭の良さというか、自然と向き合えるというか、
ゲスト:うん。
MC :そうするとよりこう、なにかやさしく生きようとかね、考え方もうこう変わってですね、
ゲスト:だからほんとはそういうところにみんな住んで実感された方がいいと思うんですよねー。
そこから比べるとやっぱり関東地方にいるとー、極端にちょっと亜熱帯化してるだとかー、
それすごい人工的な部分て肌で感じてしまうんですよねー。
だからその辺はーちょっとほんとにね考えてみなきゃいけないと思うし、
実行に移さないといけない時期だと思いますね。
MC :でも、東京オリンピックにむけてますます亜熱帯化が進むような気がするんですよね。
ゲスト:ほんとですよね。
MC :うーん。
ゲスト:どうするんだろーってほんとに、この中でーほんとにマラソンとか競技をしたらですね、
ほんとに人命に関わってくると思うんですよ。
だから僕ほんとに会場は東京でもいいと思うんですけれども、
その実際にやる、競技をやる会場は例えば軽井沢とかー、あの車で行けるじゃないですか、
そういう地方にした方がね、ほんとにいいと思うんですけどねー。
MC :ねー。ほんと、や、僕なんかはだから、あのー6年後にねー事前合宿を北海道でどうぞっていう、
こういうの手伝えたらいいなーと思って。
ゲスト:いやー絶対そうすべきだと思いますね。
MC :えー、ね。その時はじゃあ天達さんも手伝ってくださいね。
ゲスト:あ、はい。是非お願いします。
MC :いやー、やっぱり久しぶりにお話するとあっという間ですねー。
ゲスト:あー、そうですねー。
MC :ねー。その他の話はまた来週聞こうかなー。
ゲスト:あはははは。
MC :また来週も来てくださいね。
ゲスト:あ、はい。有難うございます。
MC :今週のサイコーは気象予報士の天達武史さんでした。有難うございました。
ゲスト:有難うございます。 -
「冬季オリンピックの科学 パート2」 ゲスト:柄川昭彦さん
2018/02/01 Thu 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーもライターの柄川昭彦さんです。こんばんはー。
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、柄川さんはスポーツと医療にお詳しくて、
まー、先週のフィギュアースケートの話も面白かったですけど、
今週はスピードスケート、同じスケートでもちょっとね、また見方も観戦方法も違いますけれど、
やっぱり日本はスピードスケートでメダルとってもらいたいですもんね。
ゲスト:そうですね、特にそのー、短い距離、500メートル・・・
MC :はい。
ゲスト:日本はとっても強いですよね。
MC :やっぱりね、長野オリンピックの清水選手ってのは、感動しましたよ。
ゲスト:そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:ちょっと前の話になりますけど・・・
MC :はい。さあ、500メートルをですね、カナダのウォザースプーン選手が出した、
34.03という、これが世界記録になるんですね。
ゲスト:世界記録になるんですね。500メートルの世界記録・・・
MC :はい。もう2007年ですから、えー7年前の記録ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :んー、陸上の短距離と比べると、絶対スピードスケートの方が速いですよね。
ゲスト:そうですね、あのーその先程出た、長野オリンピックで金メダルをとった清水選手ですね・・・
MC :はい。
ゲスト:が、500メールのレースで走っ、あの滑った時の100メートルの通過のタイムがですね、
9秒54ていう数字が残ってるんですね。この9秒54ていうのは、
あのー100メートルの陸上競技の100メートルのウサイン・ボルト選手の世界記録が9秒58ですから・・・
MC :あっ、それよりも100分の4秒速い。
ゲスト:ほんのちょっと速いんですね。
MC :おー、でも結局30秒台で500メートルを走るってことですから、トップスピードにのったら、
スピードスケートってのは相当の速度で走るってことですね、じゃあ。
ゲスト:そうですね。あのー、100メートルの通過する、あのー清水選手の通過と
ウサイン・ボルトの100メートルだったら、ほぼ同じですけれども、
ただスタートダッシュ、あのースタートから20メートルとか30メートルですね、
ここまではあのー、陸上競技で走った選手の方が圧倒的に速いんですね。
MC :あー、そんなイメージですね。なんか最初バーッとね・・・
ゲスト:スケート・・・あのーやっぱりあのー、スケート靴でま、特に真後ろに蹴れませんから、
斜め横にこう蹴っていく感じなり・・・最初のダッシュはとてもかなわないんですけども、
あのー、スケートが滑り始めてからのスピードはもう圧倒的で、
あのー陸上競技を見てるとウサイン・ボルト選手のスピードってのは、とてつもなく速いですけども、
あのウサイン・ボルト選手にどんどんどんどん追いついてって、100メートルの前で直前で、
抜いちゃうってことですから、これは速いですよね。
MC :今イメージわきましたねー。あー。
ゲスト:なおかつ、その後400メートル滑るわけですからねー。
ほんとにスピードスケートの速さってのはホントに速いですね。
MC :えー、何か子供の頃、あのー山手線と京浜東北線で一緒に走った時に、
スタートダッシュで速いのはどっちだなんて話をしてて、京浜東北線じゃないかなって話を今、
そのイメージが・・・えー、思い出しましたね。
ゲスト:そうですね。あのーウォザースプーン選手のあのー500メートル34秒ってのは
すばらしいタイムですけれど、このタイムでもし陸上競技の選手がですね、
陸上のトラックを走ると300メーターちょっとぐらいしか走れない・・・
MC :そうですよね。
ゲスト:そうですね。その間に500メーター滑っちゃいます・・・
MC :走っちゃうんですもんね。
ゲスト:やっぱ、速い・・・
MC :ところが、5000メートル1万メートルとかになると、スケートの方がはるかにスピード速い・・・
ゲスト:そうですね。陸上競技の5000メーターの世界記録は12分台ですけれども、
スピードスケートだったら6分台・・・
MC :あっ、半分。
ゲスト:はい。で、12分台だと1万メーター滑っちゃうんですね。
MC :はい。もう本当に・・・・・・
ゲスト:二倍速いってことですね。本当に速い・・・
MC :へえーーー
ゲスト:はい。
MC :さあ、これスケートというのはあのー、ブレードっていうね、刃がついてますけど・・・
ゲスト:刃がついてますね。
MC :昔固定してたのが、最近はあのー・・・
ゲスト:フラップスケートっていう・・・
MC :フラップスケートっていうね・・・
ゲスト:はい。
MC :これに馴染んだ人がメダルに近いという風にいわれていて・・・
ゲスト:そうですね。変わった時は本当にそうでしたね。
MC :ですよねー。
ゲスト:はい。
MC :日本人の選手でもそれに苦しんだ方もいらっしゃるけど、
今もこのフラップスケートってのが主流になってますよね。
ゲスト:みんな・・・そうですね、あのーその技術が身についてっていうことになりますね。
MC :カチャ、カチャ、カチャ、カチャ、カチャって音がするんですよね。最初ね。
ゲスト:はい。
MC :えーーー、やっぱりあれがいいんですかね?
ゲスト:そうですね。あのー、効率よく、えー氷に力を加えられるっていうことですね、
長い時間、力を加えられるっていうことで、いいんですね。
MC :なるほど・・・あっそうか、じゃあ氷に接、接、接氷している時間が長ければ長いほど、
スピード乗りやすいってことですか?スケートの場合には・・・
ゲスト:そうですね。それだけ、あのー陸上競技みたいに走る時ってのは、瞬間的に地面に力を加えるんですね。
MC :はい。
ゲスト:あのーインパクトある・・・こう力を与え方をするんですけれど、スケートとかですね、
水泳とかってのはこのーじわーっとこう力を発揮・・・
長い時間に渡って発揮し続けるスポーツなんですね。
MC :ほーほーほ。
ゲスト:だから、そのー地球に与えるその、力の与え方がまるで違うんですね。
走るのとそのスピードスケート滑るのでは・・・
MC :走るのは、じゃあ地面を捉えるインパクト勝負で・・・
ゲスト:そうです、その瞬間的に力を加える・・・
MC :スケートでいえば、氷や水を捉える長いスパン・・・
ゲスト:はい、どれだけ長く力を加えられるかなんですね。
一つのそのスピードを上げてくための要素になるんですね。ですから、フラップスケートってのは、
それだけ長い時間そのえー、氷とブレードが接しているので、あのー効率がいいってことですね。
MC :ああー、なるほどねー。
ゲスト:ええ。
MC :それから先週ちらっとお話をしたね、柄川さん一番興味深いのがジャンプ競技だと・・・
ゲスト:はい。
MC :このジャンプに関しては、あの今V字飛行ってのが主流でもうV字になって十数年に経ちますよね?
ゲスト:そうですね。
MC :もうあれが一番究極のジャンプスタイルになるんですかね?捉え方としては・・・
ゲスト:んんー、まあこの先ですね、科学がもっと新しい技術をあのー、
見つけてくるって可能性はありますけれども・・・
MC :あっ、そうですか。
ゲスト:ただあのー、それ以前のですね、あのースキーを揃えて飛んでいた時代から比べると、
えーっとスキーをV字型に開いてその間に自分の体を入れて、自分の体も使って、
えー、空気を受け止めていくという型はやっぱりあのー、効率がいいんでしょうね。
MC :そっかあ・・・そっか、V字型に開くことによって、
自分の体、胸とかお腹でも風を捉えることが出来るというメカニズムなんですね。
ゲスト:そうですね、そうですね、ええ。
MC :そっかあ、昔は板揃えて、2枚の板が風捉えたものが・・・
ゲスト:そうですね。
MC :今は3枚目の板が体ってことなんですね。
ゲスト:ええ、そうですね、そうですね。自分の体を翼の代わりに使われているんですね。
MC :あとー、ボブスレーとかリュージュとかスケルトンてありますよね。
ゲスト:はい、はい、はい、はい。
MC :ボブスレーは、何かこう守られてる感じがしますよね。二人乗り、四人乗りがあって・・・
ゲスト:はい。
MC :で、リュージュはあのー、足が先に出るじゃないですか。スケルトンって頭から行きますよね。
ゲスト:そうですね。あれだけは出来ないだろうなって・・・ハハハ
MC :ハハハ。あれでもああいう風に、競技多様化してますけれど、
興味深いのはボブスレー、リュージュ、スケルトン・・・何が一番科学的に面白いですか?
ゲスト:そうですね、あのー、一つ面白いのはボブスレーはですね、
リュージュとかスケルトンとはちょっと違った要素があって、
えっとーーー、まあ、そりがですね、まあ高い所から低い所に滑っていくわけですけども、
その時にあのー、スピードを生み出す力となるのはまあ、重力です、引力ですね。
地球の引力でまあ下に引っ張られていくと・・・
その時にはあのー、物が、重い物と軽い物は同時に落とすと、空気の抵抗が無ければ、
同じ速さで落ちます。スポンジのボールも鉄の球も1メートルから落とせば、
同時に落ちるわけですけれども、空気抵抗があると、鉄の球の方が速く落ちちゃうわけで・・・
MC :はい、ん、ん、ん。
ゲスト:空気抵抗があるので・・・
MC :はい。
ゲスト:リュージュとかですね、スケルトンは体が大きくなって重くなると、
それだけそのー、面積も大きくなりますから、空気の抵抗も大きくなりますね。
ところが、ボブスレーだけは、このボブスレーの車体というんですかね、
この、そりの大きさが決まって、あのーみんな大体同じですから、空気の抵抗が同じなんです。
MC :ほーーーー。
ゲスト:ですから・・・
MC :そっかあ・・・
ゲスト:ボブスレーは重くすれば重くするほど、速くこう、なるんですね。
MC :重力的にですね。
ゲスト:そうです。
MC :四人のうち一人はパイロットだから、パイロットは・・・
ゲスト:あっ、そうですね。
MC :体重関係ないでね。
ゲスト:うん。
MC :三人の体重ですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :じゃあ力士ですよ、力士。
ゲスト:アハハハ
MC :力士を三人、小兵力士ですね、150キロ前後の・・・
ゲスト:そうですね。
MC :それで、どすこいと・・・
ゲスト:そういうのも・・・
MC :あははは・・・
ゲスト:そうですね、今年も選手選考であのーまあ、パイロットはね非常に技術、
高い技術が必要な世界ですから、まあ決まってるんですけども、押す役はいろんな所から、
あのー公募した方がいいんだろうってことで、で、そこにはですね・・・
MC :へえーー、どんな人がいるんですかね?
ゲスト:アメリカンフットボールの選手ですとか、えー、陸上の砲丸投げの選手とか、
短距離走の選手達が集まってまあいろんなテスト繰り返して、合宿も繰り返して、
最後に選ばれたのは、陸上の短距離の体の大きな選手が何人が入ったみたいですね。
MC :そうなんですか・・・ほーーー。
ゲスト:それとまあ、そりの選手とあの・・・チームみたいですね。
MC :クラウチングスカ・・・スタートの練習してるから・・・
ゲスト:そうですね、はい。
MC :ロケットダッシュってのが・・・
ゲスト:速いんですね。
MC :いやーー、何かますます楽しみになってきましたねー、いやあーよし、今夜も眠れないな。
えーーー、みんなもね、是非オリンピック、エンジョイしてね。
今週のサイコーは、ライターの柄川昭彦さんでした。どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「冬季オリンピックの科学 パート1」 ゲスト:柄川昭彦さん
2018/02/01 Thu 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーはライターの柄川昭彦さんです。こんばんはー。
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、柄川さんは主にスポーツと医療の分野で文章を書かれているんですが、
2年前、ロンドンオリンピックが始まる前に来ていただいて、陸上競技を科学的に解説して頂きました。
ウサイン・ボルト選手の話とかね投擲競技、やり投げの話とか・・・
ゲスト:そうですね。
MC :まあ色々伺いましたけど・・・
ゲスト:はい。
MC :いよいよソチオリンピック、今度は冬の競技が始まりますけれど、
柄川さんが好きな冬のオリンピックの競技は何ですか?
ゲスト:そうですね、一番好きなのは見てて楽しいジャンプですかね。
MC :ジャンプ。
ゲスト:スキージャンプ。
MC :あーーー。
ゲスト:とても考えられないような、自分では体験できないような、見ててすごいなって思いますね。
MC :僕は札幌で今、大倉山のジャンプ競技場のすぐ近くに住んでるんです。
ゲスト:えっ、そうなんですか?
MC :かなり日常的にジャンプ見てますよ。
ゲスト:あっ、そうですか。
MC :練習しに行く姿も見てますし、だから僕もジャンプずーっと見てますけど、
ジャンプの飛び方も変わりましたよね?
ゲスト:変わりましたね。
MC :今のそのV字型飛行になってからは長いですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :やっぱり、あれが一番効率がいいんですかね?
ゲスト:そうですね。札幌で飛んだ時の、選手達の昔の映像を見ると、随分違いますね。フォームが・・・
MC :全然違いますよね。
ゲスト:それだけ、やっぱり科学がスポーツを変えてきたんだと思いますね。
MC :はい、ねーーー。まあそのあたり、スポーツにも科学が含まれているんですけれど、
人気種目というと、やっぱり花形はフィギュアスケートなんじゃないかなと思いまして・・・
ゲスト:そうですね、やっぱりこう、みんなが見てて楽しい・・・
MC :ええ。
ゲスト:のは、フィギュアスケートですよね、何といってもねー。
MC :はい。フィギュアは繊細でもあり、ダイナミックでもあるという・・・
いろんな見せ場があるんですけれど、やっぱり最大の見せ場って、
さっきのオリンピックのジャンプじゃない、スキーのジャンプとは違って、
いわゆる3回転半のジャンプとか、4回転ジャンプとか、こっちのジャンプはすっごく重要ですよね。
ゲスト:はい、フィギュアスケート見てて美しいし、見てて楽しんですけれど、
でもジャンプが成功するかどうかっていう、そこにばっかりこう・・・つい見ちゃいますよね。
MC :はーい。ここがまた加点競技の重要なところですよね。
ゲスト:そうですね。あのー男子でしたら4回転、まあ女子は3回転が中心ですけれども、
まああのー浅田選手のように3回転半まで飛ぶ選手もいますし、
まあその4回転、3回転半成功するかどうかがやっぱり一番あのー、
ポイントにも大きな関係、影響するところだと思いますね。
MC :男子4回転ジャンプやりますかね?
ゲスト:そうですね、もう男子の4回転もちょっと前まではね、あのーほんとにリスクのあるあのー、
技だったと思いますけど、今はもう上位にくる選手はみなどの選手もみんな飛びますね、
4回転を・・・はい。4回転飛べないともうメダルの可能性は全くないという時代ですね。
MC :女子はでもかつてね、安藤美姫選手がね、4回転チャレンジしたりしてましたけれど、
なかなかトリプルアクセル、3回転半以上っていうのは、オリンピックでは見られないですよね。
ゲスト:そうですね。安藤美姫選手の4回転サルコーってのが、1回試合で成功した唯一ですかね。
そう今はなかなか飛べないので、3回転半がまあ勝負の分け目みたいになってますね。
MC :男子は4回転いけるのに、女子は3回転半って、何でなんですか?
ゲスト:はい、これは主にその高く飛べるかどうかで、その滞空時間が決まってきますから、
その滞空時間の中で何回転、何回回れるか、まあ女子のも、男子もその回る回転の速さには
そんなに差はないと思いますけども、飛べる高さが違ってきますから、
空中にいる時間が違ってくるのと、それによってまあ3回転半までしか回れない女子と、
4回転まで回れる男子、ていう違いが出てくるんだと思いますね。
MC :そうなのか・・・いわゆる滞空時間じゃないけれど、高く飛べるか否かという・・・
ゲスト:そうですね、そこはやっぱり一つの大きなわけなんですねー。
MC :じゃあ、安藤美姫さんて若くして相当脚力強かったってことですね。
ゲスト:そうですね・・・ですね。ハハハ・・・女子で4回転を成功してるってのは・・・
MC :ですよね。へえーー。
ゲスト:極めて・・・あれですね。
MC :男子の場合、大体氷の上から何メートルぐらい高く上がるんですか?
ゲスト:えっとー、まあそれ、様々選手によって違うんだと思いますけど、
大体4回転成功する時で、70センチから80センチくらい浮いてるらしいんですね。
MC :へえー。
ゲスト:はい、そのくらい飛ばないと、その滞空時間がないとなかなか回れないってことでしょうね。
MC :あのー、ひねるにはね、縦の力も必要ですけど、ひねるには横の力も必要じゃないですか・・・
ゲスト:そうですね。
MC :あれはポイントは何ですかね?
ゲスト:えーっと、あのー、飛んでる所を見ていると、
空中に飛び上がってからくるくるって回っているように見えるんですけれども、
回転する力っていうのはその、まだ足が氷についている時に体をひねり始めてるんですね。
その、から、氷についた状態でひねっていないと、空中に飛び上がってからだと、
いくら体をひねってもあの、体、回転してくれない・・・
MC :つまりじゃあ、氷の上で力を入れて「よいしょ」って飛ぶ段階でひねりの力も入れてないと・・・
ゲスト:そうですね。
MC :3回転半、4回転いかないってことですか?
ゲスト:はい、同時に高く飛ぼうとする時に、同時に体も強くひねってないと回転できないっていうことですね。
あのー、例えば回転いすに座ってですね、足をついて回ろうとすると、体くるくるって回りますけども、
足を上げちゃってですね、いくら体をひねっても回転いすに座って、と、そのー、
体を例えばひねり、左にひねると足は右側に動いちゃってですね、全然回れないんですね、
それをこう空中にいる状態でいくらひねっても体は回らないっていうのと同じで・・・
MC :わかりやすい話だ、柄川さん。
ゲスト:実際やってみると・・・
MC :ラボの椅子は回転いすですよ。だから、床を蹴ってくるっーとやると・・・
ゲスト:そうですね。
MC :私は今、一回転しました。
ゲスト:見事だ。
MC :床を蹴ってね。それ回転いすだからで・・・
ゲスト:そうですね。
MC :床、かっ蹴って回れますよね、はい。
だけど、両足を挙げて、で、腰振っても手を振っても、回転できない・・・
ゲスト:そうですね。
MC :いやいや、よくわかりましたね。
ゲスト:はい。
MC :あと、くるくる回る、最後になればなるほど、スピンやるじゃないですか。男子も女子も・・・
ゲスト:そうですね。
MC :あれ50回くらい回ってませんか?最後。
ゲスト:なんかね、そんなには回ってないですね。
MC :そんなに回ってないですか。
ゲスト:アハハ、なんか、えーっと・・・たぶん得点の為にはですね、
何回転以上っていう規定があるんですけれども、今大体、十数回から20回くらいの回転数・・・
まあそれでも20回回ったら大変だと思いますよね。
MC :だって、よくすいか割りやる時にね、あのー、バットにおでこつけて
10回回ってすいか割りやるとかやるじゃないですか。
ゲスト:はいはいはいはいはい。
MC :あれみんな転びますよね。運動会でもやりますけどね。
ゲスト:10回回ったらもう、とても歩けないみたいな状態になりますね。
MC :なんで、スケート選手、目が回らないんですか?
ゲスト:それはね、あの、目が回るのはどうしてなのかっていう、
その理由のとこなんですけども耳の奥にですね、三半規管ていう器官があるんですね。
MC :はい、聞いた事あります。
ゲスト:いろんな方向に向いたあのー、管が三つあるんですけども、
半分の形の・・・その管の中にリンパ液という水が入っていて、で、その管の内側にですね、
細かーい毛が生えてるんですね。で、体が動いたり傾いたりするとその水が動くんで、
その水の動きをですね、その管の内側の細かーい毛が察知して体が傾いてるとか
回転してるっていうのを感じるんですね。
MC :へえー、僕らの耳の奥には、液体が入った管があって・・・
ゲスト:はい、そうなんですね。
MC :それが、傾いてるっていうかそれはサインを・・・
ゲスト:そうですね、脳に送るんですね。
MC :送ってる?
ゲスト:はい、で、あのーぐるぐる同じ所で回っていると、その水がこう動き続けちゃって、
止まった後もまだまわ・・水が動いているので、あのーその三半規管はですね、
まだ体が回っているってい風に錯覚しちゃってね、それが目が回った状態ですね。
MC :で、スケート選手はそこがマヒしてるんですか?
ゲスト:はい、スケート選手はですね、どうしてなのかというとですね、
あのー、あんまり技術的には特殊なことはしてないらしいんですよ。
MC :はい。
ゲスト:あの、バレリーナは頭の位置がこう変わらないようにですね、
一点を見て一回転をしたらまた同じ所を見てっていう形であまり頭を回さないようにして、
目が回らないようにするんですけど、でもそのスピンはですね、1秒間に3,4回転するらしくて、
とっても速くてそんなことできない、そういう技術が通用しない世界なんです。
だから、頭もぐるぐるって回っちゃうんですね。
MC :あっ、ついて、じゃあ、頭、頭がついてこないうちにこう回っちゃってるっていうことなんですか?
ゲスト:はい・・・その・・いろんな対処のしようがないぐらい速いんですね。
MC :目が回ってる暇がないってことですか?
ゲスト:それで、あの普通の人だったらとても目が回ってダメなんですけれども、
あの、スケートの選手はですね、ただ単に練習でよくスピンをするので、慣れるってことですね。
MC :えーーーはははーーあまりにも慣れたら目回んなくなりますか?
ゲスト:この回答はですね、非常に科学的でじゃないんで、ハハハ・・・ただ慣れるらしいんですね。
ですから、そのスケートの選手が1ヶ月くらいですね、シーズンオフとかでスピンをしない、
或いは怪我しちゃってスピンをしなかった・・・で、再び練習してくるくるって回るとですね、
目が回るらしいんですね。
MC :あっ、そう、そうちょっとじゃあ練習を怠ると、羽生選手も目回っちゃうんですか?
ゲスト:らしいですよ。
MC :いやーー、面白かった。いやーちょっとまた、また他の競技も来週伺ってよろしいですか?
ゲスト:はい。よろしくお願いします。
MC :え、今週のサイコーはスポーツと医療にお詳しいライターの柄川昭彦さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「北陸新幹線の科学 パート2」 ゲスト:川辺謙一さん
2018/01/01 Mon 12:00 カテゴリ:乗り物MC :今週の「サイコー」も、先週に続きまして鉄道技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :え、前回は北陸新幹線のお話伺いしまたけれど、
ゲスト:はい。
MC :新幹線というと今、キッズ達の間で、
ゲスト:はい。
MC :黄色い新幹線。
ゲスト:はい。
MC :見ると幸せになれると言われてる
ゲスト:はい。
MC :ドクターイエロー
ゲスト:はい。
MC :今、プラレールなんかの
ゲスト:はい。
MC :車両でもドクターイエローっていう車両が出てね、
ゲスト:はい。
MC :子供たちの間で人気だとかいう話
ゲスト:はい。
MC :なんですよねぇ。
ゲスト:はい。
MC :これは、川辺さんは乗ったことあるんですか?
ゲスト:あ、乗ったことはないですけどま、車両基地で見たりとかですね
MC :ええ、ええ。
ゲスト:えー、そういうことはありますけども
MC :あ、見た。
ゲスト:はい。
MC :それで幸せになりました?
ゲスト:いやま、幸せっていうか、やっぱり走ってないと、あれですよね。
MC :あ、車両基地じゃダメですか。
ゲスト:そうですね。
MC :あはは。
ゲスト:ずっと止まってるのは、まあ、あんまり、あれでしょうけど、
MC :ああ。
ゲスト:まあ、車両基地の公開とかですね、
MC :ええ。
ゲスト:浜松工場、あの、JR東海の浜松工場の公開などで
MC :はあー。
ゲスト:あの、見せているので、ま、それを見ることは、ま、可能なんですけども
MC :はい。
ゲスト:実際にその線路の上を走ってるというのは
MC :うん。
ゲスト:なかなか見ることが出来ないので、
MC :これは、JRの時刻表には?
ゲスト:はい。
MC :乗ってないん
ゲスト:これは、乗ってないんですよ。
MC :えっ、じゃいつ何時どこ走ってるかってことは、
ゲスト:はい。
MC :鉄道ファンでも分からないんですか。
ゲスト:分からないですね。
MC :じゃ、ほんとにもうたまたま偶然見つけたって言ったときに
ゲスト:そうです。
MC :幸せかどうかという、それで、もうほんとレアなものですね。
ゲスト:そうですね、ええ、ええ。
MC :それが、カメラ起動してちゃんと写真撮れるかどうかってのも重要ですね。
ゲスト:ええ、だから、もう見つけても、ああっという
MC :あははは。
ゲスト:いっちゃうとかですね、
MC :へえー。
ゲスト:ありますよね。
MC :あれは、ドクターイエローはもともとは何ですかあれは。
ゲスト:あっ、あれはですね、ま、えー、その名前の通りですね
MC :ええ。
ゲスト:線路のお医者さん
MC :ああ、ドクター
ゲスト:ドクターですから
MC :ええ。
ゲスト:あの、せ、医者ですね。
MC :はい。
ゲスト:で、線路を、が異常がないか
MC :はい。
ゲスト:走りながら確認するという車両でして、
MC :うん。
ゲスト:正式名称は新幹線電気軌道総合試験車という名前が
MC :しー、新幹線電気軌道総合試験車。
ゲスト:はい。
MC :あ、そう、昭和な
ゲスト:そう、そう。
MC :何か、名前が
ゲスト:そうですね、漢字ばっかりで
MC :あははは。
ゲスト:んふふふ。
MC :で、えー、ドクターイエローというふうに
ゲスト:はい。
MC :言われてる訳ですね。
ゲスト:はい。
MC :で、これ電気軌道総合試験車っていう
ゲスト:はい。
MC :レールを調べるってことですか?じゃあ
ゲスト:そうですね、レールが
MC :うん。
ゲスト:ゆがんでいないかとかですね、えー、線路の上には架線といわれる電気を送るための、
あのー、電線があるんですけども
MC :はい。
ゲスト:それが痛んでいないか、また信号が、えー、ちゃんとこう列車に伝わるようになってるか
MC :はい。
ゲスト:とかですね、そういうあのー、ことを、えー、確認する、ちゃんと正常になってるかどうか
MC :それは、そうですよ。300キロで走る新幹線で、
ゲスト:ええ。
MC :レールゆがんでたら、命取りですよね。
ゲスト:そうだね、
MC :あ、
ゲスト:だから、どこがゆがんでいるか
MC :ええ。
ゲスト:例えば、東京駅から何キロ地点にそういう、ゆがんでる地点があるかとかですね。
MC :うーん。
ゲスト:そういうのを走りながら確認して、データを取ってると
MC :へえー。
ゲスト:で、それをデータを夜中の、
MC :ええ。
ゲスト:その、夜中に、ま、えー、線路を直す作業するんですけども
MC :はい。
ゲスト:その作業の時に、さっきのそのデータを、えー、反映させるんですね。
MC :はい。
ゲスト:どこの地点にどれだけゆがんでるとこがあるから、どれだけ直さなくちゃいけないとかですね、
そういうのをこう、参考にしながら直すと
MC :ほー。
ゲスト:いうことをやってくことによって、ま、えー、新幹線が安全に
MC :ええ。
ゲスト:列車が走れるようにしてると
MC :へえー。
ゲスト:いうことなんですね。
MC :今、ドクターイエローってね。
ゲスト:はい。
MC :あの、最新の700系みたいな顔
ゲスト:はい。
MC :してるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :新幹線て、東京オリンピックの前に出来た時は
ゲスト:はい。
MC :0系というね、
ゲスト:はい。
MC :だんごっ鼻みたいな付けてる
ゲスト:ありましたね。
MC :もう、今走ってないですけど
ゲスト:走ってないですね。
MC :あの、0系時代から
ゲスト:はい。
MC :黄色い新幹線はあったんですか?
ゲスト:ええ、あの当時から黄色い新幹線
MC :あっ
ゲスト:あったんですよ。
MC :そうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :あ、じゃあ、今の最新型の車両が、黄色になってる訳じゃなくて
ゲスト:なって
MC :昔から黄色い新幹線は
ゲスト:そうなんですよ。
MC :新幹線電気軌道総合試験車という
ゲスト:はい。
MC :名前で、
ゲスト:はい。
MC :ずーっと存在してたんですか。
ゲスト:そうなんですよ、で、なぜ黄色に塗ってるかというと
MC :はい。
ゲスト:実はお客さんを乗せない事業用車両っていうんですけども
MC :はい。
ゲスト:そういう車両は、えー、黄色に塗るという規則があるんですね。
MC :へえー。鉄道のルールで?
ゲスト:ルールで、えー、線路のメンテナンをする
MC :うん。
ゲスト:ま、修理をしたりする車両も全部黄色く塗ってあるんですね。
MC :へえー。あ、日本の鉄道、そうなんですか。
ゲスト:ええ。あのー、東海道山陽新幹線に関しては、この、えー、
そういう試験車両については、黄色く塗っていると、それに従って、
MC :言われてみたら、小田急にしてもね
ゲスト:はい。
MC :ロマンスカーも東武のスペーシアにしても
ゲスト:はい。
MC :京成のスカイライナーにしても、
ゲスト:はい。
MC :黄色い特急はないですよね、JRも含めて
ゲスト:うーん、そうですねぇ。
MC :はぁー。
ゲスト:で、あの、日本の鉄道、先ほどの色の話はですね、
日本の鉄道というふうに決まってるわけじゃなくて、JRの
MC :JR
ゲスト:あの、国鉄時代から続く、ま、話なので、
MC :へえー。
ゲスト:必ずしも、あの、私鉄だとか地下鉄とは別なんですけども
MC :ほぉ、ほぉ、ほぉ。
ゲスト:ええ。
MC :でも、地下鉄でも黄色ないですよね、有楽町線は黄色、西武線だ!
ゲスト:あ、西武線はありますし、
MC :西武線黄色だった。
ゲスト:そうですね、あのー、あとは有楽町線は、
MC :そ、
ゲスト:ま、黄色といえば黄色ですし
MC :そうだ。総武線も黄色だ。
ゲスト:でー、銀座線も昔は実は
MC :そうだ、黄色だ。
ゲスト:黄色だったんです。
MC :あった、黄色。意外にある。
ゲスト:ええ。
MC :はははは。
ゲスト:名古屋の地下鉄も黄色なんですよ。
MC :そうだ。東山線とか
ゲスト:東山線とか
MC :黄色だった。
ゲスト:ええ、ええ。
MC :名城線も黄色でした。
ゲスト:そうです。
MC :なにしろ、ローカルな話ですけど、
ゲスト:ははは。
MC :すいません。子供の頃、名古屋にいたんで
ゲスト:ええ、あ、そうですか。
MC :あはは、そうだ。
ゲスト:ええ。
MC :あ、そ、意外に黄色、優等列車では少ないけれど、
ゲスト:そうですね。
MC :おー、確かにありますね。
ゲスト:ありますね。
MC :あー、
ゲスト:あの、目立つ、夜中に作業することが多いので
MC :はい。
ゲスト:ま、目立つ色にしたというふうに、ま、言われていますけども
MC :へえー。そうか、そうか。
ゲスト:その色が、ま、そのドクターイエローにも使われていると
MC :へえー。あと、年々新幹線てモデルチェンジするたんびにね
ゲスト:はい。
MC :顔が平べったくなっていって
ゲスト:はい。
MC :1号車と16号車っていうか、ま、いわゆる車端部の
ゲスト:ええ、ええ、はい。
MC :先頭車両の乗客の数が減ってくような気がするんですけど、
ゲスト:あ、
MC :あれ、気のせいですかね。
ゲスト:ああ、減ってはいないんですね。
MC :あ、減ってない。
ゲスト:減ってないんですよ。
MC :ええ。
ゲスト:で、ただ、えー、段々するどい顔に
MC :そう、そう、そう。
ゲスト:なってますよね。
MC :段々何か、何かくちばしがとんがってきてるんですよね。
ゲスト:そうです。で、あれも、あれはですね、安全対策というよりは、あのー、
というか空気抵抗減らすという意味もあるんですけど、
MC :ええ。
ゲスト:どちらかというと騒音対策なんですよ。
MC :音!
ゲスト:音。
MC :へえー。
ゲスト:なんですね。
MC :そうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :全然音違うんですか。
ゲスト:あ、音というのはですね、あの、トンネルで発生する音なんですけども
MC :ああー。
ゲスト:列車がですね、あの、在来線ではあまりこういうこと起こらないんですけど、
MC :ええ。
ゲスト:新幹線の場合、列車がすごく速く走るので、
MC :ええ。
ゲスト:えー、勢いよくトンネルに入ると、いきおいよく、トンネルの中にですね空気を押し込んでしまうんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、その時に発生する衝撃派が
MC :はい。
ゲスト:ていわれるものがですね、えー、トンネルの出口に伝わって、そこで急激に圧力が下がった時に
MC :はい。
ゲスト:ドーンという大砲を打ったような音がしてしまう
MC :へえー。
ゲスト:で、これが線路の、ま、周囲に住んでる方々にとっては
MC :うん。
ゲスト:うるさい音になってしまうので、
MC :ふーん。
ゲスト:それを小さくしなければならないと
MC :へえー。
ゲスト:で、小さくするためにはどういうふうにすればいいのかと色々検討された結果ですね、
できるだけ顔を鋭い顔にすると、良いということが分かったんですね。
MC :へえー。
ゲスト:それで、段々鋭くなって、ま、500系という、えー、非常に、あの、シャープな形をした、
ま、新幹線が作られたんですけども
MC :ふーん。
ゲスト:こうするとですね、今度は先ほどおっしゃったように、ひ、人が座るとこがですね
MC :はい。
ゲスト:無くなってしまう
MC :はい。
ゲスト:で、500系の場合は、あの、入口がですね2ヶ所じゃなくて、1ヶ所しかないんです。
MC :あ、お客さんの乗り降りする
ゲスト:お客さんが乗り降りする
MC :そうですよね。
ゲスト:で、
MC :はい。
ゲスト:前に無かったんです。
MC :はい。
ゲスト:それは、やっぱり傾斜させてしまったために、
MC :はい。
ゲスト:一つデッキを無くすしかなかったんです。
MC :はい。
ゲスト:で、これはやはりお客さんにとっては、ちょっと不便なので、
MC :はい。
ゲスト:2つ増や、あの、他の車両と同じように、えー、お客さんが乗るところ、
2つ、1両に2つ必ず確保するためには、顔の形をちょっと変えなければならないと
MC :ほー。
ゲスト:だから、鋭い顔の、と同じような効果を持ちつつも、
えー、ちょっと後ろの客室とかデッキは確実に確保すると
MC :うーん。
ゲスト:その結果ですね、ちょっとカモシャ、ノハシのような顔をしたりとかですね、
MC :うん、うん。
ゲスト:変わった顔になったんですね。
MC :なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :そっかぁ。音対策だとは
ゲスト:そうなんですね。
MC :思わなかったですね。
ゲスト:音対策
MC :空気抵抗の何か、あの、スピードが出るためかと
ゲスト:はい。
MC :思ったら、そうじゃなかったという。トンネルですね。
ゲスト:はい。
MC :じゃ、昔の0系なんかが、
ゲスト:はい。
MC :同じスピード、300キロでトンネル入ったら、
ゲスト:はい。
MC :とんでもない音になってるっていうことなんですかね?
ゲスト:そうですね、で、特にあの、山陽新幹線の長いトンネルで
MC :ええ。
ゲスト:そういう音がよく、えー、けん、あの、見られたのでこういう対策がされるように
MC :うん。
ゲスト:なったんですね。
MC :なるほど。今、何気に500系出てきてて、僕個人的に500系が一番かっこいいと思ってる
ゲスト:ああ、そうですね。かっこいいですね。
MC :かっこいい。
ゲスト:んふふふ。
MC :あのー、これが放送されるかどうかは分からない。
ゲスト:はい。
MC :もう、あ、500系短命でした、かわいそうでしたよ。
ゲスト:ああ、そうでしたねぇ。
MC :ねぇ!
ゲスト:まあ、山陽ではまだ走ってますけどね、んふふ。
MC :もう、飲みに行きましょう今度。
ゲスト:ああ、そう、あははは。
MC :いやー、今週の「サイコー」は、鉄道技術ライターの川辺謙一さんでした。また、遊び来て下さいね。
ゲスト:はい。
MC :ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「北陸新幹線の科学 パート1」 ゲスト:川辺謙一さん
2018/01/01 Mon 12:00 カテゴリ:乗り物MC :さ、今週の「サイコー」は鉄道技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :えー、川辺さんは、あの、私とはとてもね、お話が合うんです、鉄道好きとして
ゲスト:あ、そうですね。
MC :で、えー、いよいよ待望の
ゲスト:はい。
MC :北陸新幹線が
ゲスト:はい。
MC :僕ね、富山の生まれなの
ゲスト:あ、そうなんですか。
MC :だから実は僕の故郷では、
ゲスト:ええ。
MC :メチャメチャ期待してて、
ゲスト:そうでしょうね。
MC :もうね、親戚がいろんなもの送って
ゲスト:あっははは。
MC :くるんだけど
ゲスト:はははは。
MC :全部北陸新幹線のイラスト入ってるんですよ。
ゲスト:ああ、そうでしょうね。
MC :日本酒に
ゲスト:ええ、ええ。
MC :しろ、
ゲスト:ええ、ええ。
MC :お米にしろ、
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :お菓子にしろ
ゲスト:ええ、ええ。
MC :もう北陸新幹線ありきになっていて、
ゲスト:ああ、まあそうでしょうねぇ。
MC :今、沸いてますよ。
ゲスト:ええ、そうでしょうね。
MC :だから、一言いいたいのは
ゲスト:はい。
MC :金沢だけじゃないよ、
ゲスト:えへへ、そうですね。
MC :富山も忘れないでねっていう
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。さあ、
ゲスト:便利になりますね。
MC :そうですよ。で、な、長野までは今まで通っていたんですけど
ゲスト:はい。
MC :なぜか長野行き新幹線という
ゲスト:そうですね。
MC :中途半端なフレーズで
ゲスト:はい。
MC :もう16年ぐらい?
ゲスト:はい。
MC :新幹線通ってたじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :長野行き新幹線。
ゲスト:そうですね。
MC :これがいよいよ北陸新幹線という、
ゲスト:そうですね。
MC :正真正銘の
ゲスト:正式な名称に
MC :なる訳ですね。
ゲスト:はい。
MC :これ、特徴は、これまである新幹線と比べてどう違うんでしょうか。
ゲスト:あ、特徴
MC :はい。
ゲスト:まず、新幹線として
MC :はい。
ゲスト:ある乗り物としては、東京から北陸の、
MC :うん。
ゲスト:ま、富山、先ほどおっしゃった
MC :はい。
ゲスト:富山ですとか金沢の方にですね、乗り換えなしで
MC :うん。
ゲスト:えー、今までの短い時間で行けるようになる
MC :うん。
ゲスト:ということですね。
MC :今までは、越後湯沢で乗り換えなくちゃいけない
ゲスト:そうですね。えー、まず、東京からですと、えー、上越新幹線で越後湯沢まで乗って
MC :はい。
ゲスト:越後湯沢で、えー、在来線の特急に乗って、
MC :はい。
ゲスト:えー、富山、金沢に行ってたと
MC :はい。
ゲスト:だから、全体的に、えー、東京から金沢までですとえー、4時間かかってたんですよ。
MC :うん。
ゲスト:それが2時間半に
MC :うわあー、いいですね。
ゲスト:1時間半短くなると
MC :夢ですよ、夢。
ゲスト:そうですね。
MC :僕ね幼稚園の頃から
ゲスト:はい。
MC :ずっーと
ゲスト:はい。
MC :駅前には
ゲスト:はい。
MC :北陸新幹線を富山へって書いてあって
ゲスト:そう、ありますね。
MC :40数年経ってやっとそれが
ゲスト:そう、そう。
MC :いや、地元悲願ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。
ゲスト:も、めったにあることじゃないんですからね。
MC :2時間半ですか。
ゲスト:はい。
MC :古都金沢に
ゲスト:はい。
MC :へー。
ゲスト:だから、日帰りが、もうしやすくなりますよね。
MC :ええー、えっ、最高速度は何キロなんですか?
ゲスト:あ、最高速度はですね260キロと
MC :えっ、ちょっと遅い、イメージ的にダメだよなあ、
ゲスト:あ、
MC :あれ?
ゲスト:そうですね。
MC :ちょっと待って
ゲスト:ええ。
MC :北陸新幹線
ゲスト:そうですね、今までの新幹線だと、あの、まあ、速いものが多い、あのー、あ、ま、山陽新幹線が、
MC :ええ。
ゲスト:300キロで、
MC :はい。
ゲスト:東北新幹線が320キロっていうものに比べると、まあ、遅いんですけども
MC :どんくさいなぁ、
ゲスト:そう
MC :北陸
ゲスト:えへ、そうですね。
MC :ええっ。
ゲスト:で、これはですね、安く、線路を作るための工夫なんですね。
MC :えっ、安いんですか。
ゲスト:安く作るんです。
MC :ちょっとチープな空気になってきたなぁ。
ゲスト:いや、チープというとあれですけども、
MC :ええ。
ゲスト:やはり、速く走るためには、
MC :はい。
ゲスト:えー、線路をそれだけ頑丈に作る必要があるんですよ
MC :ふん。
ゲスト:レールだけじゃなくて、架線とかもですね、頑丈な構造にしなければいけないので
MC :はい。
ゲスト:お金がかかるんですね。
MC :はい。
ゲスト:あと、坂を緩くしたりカーブを緩くするためには、
ルートが、あの、大回りになってしまう場合があるんですね。
MC :はい。
ゲスト:あの、山ですと
MC :はい。
ゲスト:それを、えー、短くす、するためには、ま、最高速度ある程度下げなければならない場合が
MC :あ、そっか
ゲスト:あるんですね。
MC :地図広げてみると
ゲスト:はい。
MC :あのー、東海道新幹線や
ゲスト:はい。
MC :東北新幹線は、
ゲスト:はい。
MC :まっすぐ、ピューってなるから
ゲスト:そうです。
MC :スピード出せるけれど
ゲスト:はい。
MC :確かに、東京から高崎、
ゲスト:はい。
MC :長野
ゲスト:はい。
MC :富山、けっこうクネクネしてますもんね。
ゲスト:それ、クネクネしてるし、坂がきつい、と、あのー、
非常に標高の高い峠を行かなければならないとかですね、
MC :うん、うん。。
ゲスト:例えば、軽井沢の近辺の
MC :うん。
ゲスト:碓氷峠のように
MC :はい。
ゲスト:標高の高いところに行くために、ま、大回りせずに
MC :はい。
ゲスト:急な坂を登らなきゃいけない部分もあるんですよね。
MC :山を、そっか、超えなくちゃいけない
ゲスト:そうですね。
MC :そうか、だったらしょうがない、もう
ゲスト:そう。
MC :とろくてもいい
ゲスト:そうです。
MC :260キロも
ゲスト:はい。
MC :やむなしと
ゲスト:はい。ただもうやっぱり便利になるってのは大きいですよね。
MC :うーん。そうですね。
ゲスト:で、全国にそういう新幹線のネットワークを作る上で、
やっぱり安く作らなくちゃいけないというのもあるんで
MC :ほー。あ、ある意味非常に難しいところに新幹線を
ゲスト:はい。
MC :敷くってことの
ゲスト:はい。
MC :モデルケースってことですかね。
ゲスト:ま、そういうことですね。
MC :じゃ、安くっていうか、ま、なるべくコストを抑えて
ゲスト:はい。
MC :こういうところも、日本の技術は新幹線敷けるんだよっていうところを
ゲスト:そうですね。
MC :見せるのも大事ってこと
ゲスト:そうですね、東海道新幹線に
MC :うん。
ゲスト:比べればお客さんは少ないかもしれないけども
MC :うん、うん。
ゲスト:そういうとこでも、ちゃんと新幹線を作る事できるんだよっていう
MC :うーん。
ゲスト:事が、ま、今回示されるわけですね。
MC :なるほどね。で、なんていってもやっぱり雪ですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。
ゲスト:北陸地方はやはり、あのー、積雪量が多い、ま、雪が沢山降る、
MC :はい。
ゲスト:また雪が他の地方より重たいという、ま、と
MC :はあー。
ゲスト:というのがありますので、今まで新幹線が通っていた、
えー、東北地方だとか、信越地方とはまた違う雪のトラブルが起こる可能性があるんですね。
MC :雪が重たいってどういうことですか?
ゲスト:あ、湿っていて、
MC :ああー。
ゲスト:雪下ろしをされる方、まあ、すぐ分かると思うんですけれども重たいんです。
MC :そうか、そうだ。僕今北海道在住なんで
ゲスト:はい。
MC :雪は、パウダースノーですよ。
ゲスト:あ、そうですね。
MC :あははは。
ゲスト:ス、スキーに適してるんですね。
MC :だから、外国から色んなお客さんが
ゲスト:そう。
MC :ワンダフルって言って帰っていきますね。
ゲスト:そうですね。
MC :あ、じゃ、北海道の雪みたいなサラサラってやつじゃなくて
ゲスト:はい。
MC :ベチャーっとした
ゲスト:ま、そうです、ま、ベチャ、そうですね。
MC :ええー。
ゲスト:だから、北海道と雪がちょっと質が違うので
MC :重いのか。
ゲスト:そうですね。だから、
MC :うん。
ゲスト:その分ですね、何が、あのー、今までの新幹線では起きなかったことが起こる可能性があるので、
MC :うん。
ゲスト:いろんな対策を、えー、されていますね。
MC :それ、でも東北新幹線にせよ
ゲスト:はい、はい。
MC :新潟に行く上越新幹線にせよ
ゲスト:はい。
MC :あの豪雪地帯を通るじゃないですか。
ゲスト:通りますね。はい。
MC :でも、その雪よりもはるかに重いってことですか?
ゲスト:重た、
MC :北陸の雪というのは
ゲスト:えー、重いと言われてますし、
MC :へえー。
ゲスト:また、量も違いますし、
MC :あ、降る量が。
ゲスト:あと、気温の変化もまた、その地域とはまた違うので
MC :ほー。
ゲスト:あの、寒暖の差も
MC :ええ。
ゲスト:あのー、大きいと、ちい、大きい小さいでまた、あのー、
積もった雪が凍るかどうかというのも変わってきますし、
MC :ほお、ほお。
ゲスト:そういう条件がですね、全然違うエリアに行くので
MC :なるほど。
ゲスト:あの、また違うことが起こる可能性があるので、ま、念入りにチェックを今しているということですね。
MC :ま、春休み多分、北陸新幹線の開通記念で、
ゲスト:はい。
MC :ちょっと乗ろうかという
ゲスト:はい。
MC :キッズも多いかも分からない
ゲスト:あ、そうですね、はい。
MC :車窓から何チェックすると、あ、これ北陸新幹線の雪対策だって分かります?
ゲスト:あ、まずですね
MC :ええ。
ゲスト:あのー、ま、えー、特に雪が多いエリアに行ったらですね、線路が
MC :ええ。
ゲスト:高架橋を走る時に線路が高い位置通ってるという
MC :ええっ。
ゲスト:で、
MC :うん。
ゲスト:それは何故かというとですね、雪を溜めるための
MC :うん。
ゲスト:くぼみが作ってあるんですよね。
MC :はあー、あの、コンクリートの
ゲスト:はい。
MC :あのー、何か、こう、高架みたいな
ゲスト:そうです。高架
MC :あるけれど、線路の方が一段高いところ
ゲスト:そうです。あの、高い、一番高いところ、ま、1メートルぐらい高く
MC :うーん。
ゲスト:なっててですね、
MC :はい。
ゲスト:その両側、左右両側のくぼみに、雪を
MC :ええ。
ゲスト:あの、除雪した時の雪をですね、 溜めておくように
MC :はぁ、はぁ。
ゲスト:溜めれるようにしてあるんですね。
MC :じゃ、つまりこう、土台みたいな地盤が、
ゲスト:はい。
MC :車窓からすごい低いところに見えるということ
ゲスト:そういうことです、そうです。
MC :2階建て新幹線乗ってる感じになるんですかね
ゲスト:うん、まあ、イメージとしてはそうですね。
MC :あっはは。
ゲスト:ちょっと、ちょっと視点が高い所を通ってる
MC :へえー。
ゲスト:ような気になるっていうんですね。
MC :え、それは何、その、じゃ高架の横に雪溜めるための
ゲスト:はい。
MC :溝みたいな、大っきい溝を用意したってこと
ゲスト:まあそういうことですね。
MC :へえー、これ上越新幹線や東北新幹線にはないっていうやつ?
ゲスト:あ、あのー、一部区間にはあるんですけれども
MC :ええ。
ゲスト:それよりも、あのー、ま、そういう採用した区間が長いと
MC :へえー。それどことどこの駅の間で見られるんですか。
ゲスト:あ、という、あの、どことどこというわけではないんですけども、結構長い区間で
MC :へえー、
ゲスト:見ることができますね。
MC :いや、楽しみですねー。えー、じゃ車窓からポッと外みると、おっ、ちょっと高いところ走ってるぞと
ゲスト:はい。
MC :で、この下の底の方には雪溜めるんだぞって
ゲスト:はい。
MC :いうふうなイメージすれば
ゲスト:そういうことですね。
MC :へえー、えっ、あとは何かありますか。
ゲスト:他にはですね、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、ま、ちょっと、あの、車窓からはあんまり確認できないんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:スプリンクラーというですね、
MC :スプリン
ゲスト:水を撒く
MC :うん。
ゲスト:あの、装置が、ま、雪国ではよく
MC :はい。
ゲスト:使われてるんですけども、
MC :はい。
ゲスト:これがあまりないんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:で、ないという、ない代わりに、ま、えー、除雪をするあの、
機関車がですね、夜中に走るんですね。
これも見ることが残念ながら出来ないんですけども、
MC :へ、えっ、普通の新幹線は
ゲスト:はい。
MC :除雪車っていうのはないんですか。
ゲスト:あ、ない代わりにそのー、
MC :うん。
ゲスト:夜中もずっーと、こう、
MC :うん。
ゲスト:水を撒いて
MC :へー。
ゲスト:できるだけ雪が、えー、線路に、えー、積もらないように
MC :ええ。
ゲスト:また、舞い上がらないようにしてるんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、それが、えー、北陸新幹線の場合は、沿線にですね、ま、川があまりなかったので
MC :はい。
ゲスト:水を取ることができなかったんですね。
MC :おー。
ゲスト:そこで、えー、こういう形ですね、雪、先ほど言った雪を溜める高架橋を入れたり
MC :うん。
ゲスト:えっと、夜中に除雪をすることによって、その雪を除去するということをやると
MC :えっ、新幹線のレールを
ゲスト:はい。
MC :除雪車が走るというのは、
ゲスト:はい。
MC :日本の新幹線の50年以上の歴史の中では
ゲスト:あまりないですね。
MC :ええっ、すごい!
ゲスト:ええ。
MC :ええ、いやいやいや、そうそう、そうか。
レアな新幹線というと、じゃそのー、除雪新幹線もさることながらね
ゲスト:はい。
MC :今ドクターイエローっていう
ゲスト:はい。
MC :キッズ達の間で、黄色い新幹線が、話題になってんですよ。
ゲスト:そうですね。
MC :ちょっとこのお話は来週
ゲスト:はい。
MC :伺いたいと思います。
ゲスト:はい。
MC :今週の「サイコー」は、鉄道技術ライターの川辺謙一さんでした。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「プロ野球選手の科学 パート2」 ゲスト:柄川昭彦さん
2017/12/01 Fri 12:00 カテゴリ:人体MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」も、
前回に続きまして、スポーツにお詳しいライターの柄川昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :先週面白かったですねぇ。
ゲスト:あっそう
MC :大谷翔平トーク
ゲスト:はい。
MC :大谷縛りで、伺いしまたけれど、あのー、僕気になるんだけど、最近の野球選手って
ゲスト:うん。
MC :昔に比べると登板間隔も、長いし
ゲスト:はい。
MC :すごく体のケアしてるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :だから、あ、すごくな、長く持つ
ゲスト:うん。
MC :だ、い、今、40代でも、ま、去年引退した、また、ファイターズだけど
ゲスト:はは。
MC :稲葉選手とか
ゲスト:はい。
MC :和田選手なんかもまだ元気じゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :で、あと、50歳の山本昌選手
ゲスト:はい。ついに、50、50代が登場ですよね。
MC :そーですよ。
ゲスト:昔、昔っていうか、私にとっての昔ですけども
MC :はい。
ゲスト:あ、もう、野球選手は30代までで、
MC :そう。
ゲスト:40代も、まあほとんどいなかったですよ
MC :30だったら、ベテランでしたもんね。
ゲスト:あは、そうですね
MC :今、30はまだ中堅どころで
ゲスト:もう全然中堅です。40代の選手、いくらでもいますからね。
MC :はい。選手寿命って確実に延びてるじゃないですか。
ゲスト:延びてますね。
MC :これなんでなんですかね。
ゲスト:はい。一つはあの、先ほど言って、おっしゃったように、その、登板間隔が空いてるとかっての
MC :おお。
ゲスト:ありますけど、もう一つは、こう、きちんとケアをするようになったし、
MC :ほおー。
ゲスト:あのー、練習の後、試合の後にきちんとこう、故障しないようにですね
MC :うん。
ゲスト:ケアしていくと。例えばあの、ピッチャーが投げ終わった後に、一回引っ込んでですね
MC :はい。
ゲスト:インタビュー受けてる時に、こう、肩と肘にこう、グルグル巻きにして、あの、アイシングっていう
MC :おお、はい。
ゲスト:氷で冷やして
MC :はい。
ゲスト:冷やしたまんま、インタビュー答えてたりしますね。あれは、昔は無かったんですね。
MC :うん。
ゲスト:えっと私はその、医療ですとか、スポーツ科学の取材をずっーとしてまして
MC :はい。
ゲスト:長くしてますけれども、1980年代の前半ぐらいにですね
MC :はい。
ゲスト:ある整形外科の、あのー、メジャーリーグに詳しい整形外科の先生からですね
MC :はい。
ゲスト:アメリカのピッチャーは、氷で肩を冷やすんだっての、き、いうのを聞いてですね
MC :それは30年ちょっと前
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:も、ビックリしたことがあるんです。
MC :うん。
ゲスト:その時私も知りませんでしたし、日本で投げ終わった後に、
肩と肘を氷で冷やすピッチャーなんていなかったんですね。
MC :その考え方が、
ゲスト:はい。
MC :いわゆる
ゲスト:考え
MC :ナンセンスだったんですね。日本では。
ゲスト:そう、日本では、ピッチャーが肩を冷やしてはいけないと
MC :あ、言われてた、言われてた。
ゲスト:はい。
MC :布団は、ちゃんと肩まで掛けて寝るっていうね
ゲスト:あ、そう、そう、そう、そう。
MC :ピッチャー。はい。
ゲスト:ええ。
MC :あ、そうだ。
ゲスト:氷を当てるなんてとんでもないっていう
MC :はい。
ゲスト:その時代にあの、メジャーリーグでは、もう、アイシング始まってますね。
MC :はい。
ゲスト:で、あの、例えば投げ終わった後のピッチャーの肩とか肘とかっていうのは、
あのー、こう、炎症を、が起きてるんですね、軽い炎症が起きてて
MC :はい。
ゲスト:こう、内出血が起きてるような血管が拡張して、そっから、えーっと、液体がですね、
滲み出て、うっ血してだから、熱を持って、腫れを持ってひどくなれば赤くなってですね、
その炎症状態をなるべく起こさないようにですね、投げ終わったらすぐ、氷で冷やして
MC :うーん。
ゲスト:血管を収縮させて、
MC :はい。
ゲスト:あと、ちょっと圧迫も加えるんですね、そうすると
MC :はい。
ゲスト:そこが腫れてこないので、
MC :はー。
ゲスト:えーと、炎症が早く治まる、ひどくならないで早く治まるっていうので、
アイシングってのは、で、それをやり始めたのが、多分、えーと、30年、なが、早くても30年
MC :はい。
ゲスト:ぐらい前の選手達ですから、えーと、今山本選手が50歳ですから
MC :はい。
ゲスト:ま、山本選手、選手が20歳ぐらいの頃から
MC :あっ、な
ゲスト:日本でアイシングが始まったのかな?と思いますね。
MC :なるほど、それから
ゲスト:若いころから
MC :ええ。
ゲスト:アイシングをキチンとやってきた第一世代が、山本選手たちで、
MC :なるほどね。
ゲスト:で、その後の選手達はもっときちんとやってますから、
MC :うん。
ゲスト:40代の選手達は、意外と体はまだまだ大丈夫っていう選手は結構いるんだと思いますね。
MC :そうかぁ。
ゲスト:そういうのは、大きいと思います。
MC :そう考えると、400勝の金田さんて、すごいですね。
ゲスト:そう、はははは。
MC :なんにもしてなかった感じで。あと、稲尾さんとか日本シリーズ4連投したっていう、すごい話ですよね。
ゲスト:あ、金田さんは、そうとう年齢がいくまで投げてましたし、
MC :はい。
ゲスト:ただ、あれですよね、肘、や、山本選手もそうですけど、肘が伸びないとか言ってますね。曲がったまま
MC :あー、今ね
ゲスト:になっちゃったんですね。
MC :そうそう、あっ、そう。曲がってるんですよね。
ゲスト:ええ。
MC :金田さんね。
ゲスト:それとあと、いな
MC :巨人の星でも見ました、それ。
ゲスト:あっははは。そうですか。
MC :はい。ははは。
ゲスト:稲尾投手は、やっぱ故障で
MC :ああ
ゲスト:選手寿命は短かかったん
MC :やっぱりそう
ゲスト:だと思います。
MC :そうですよね。
ゲスト:はい。
MC :そうか、そうか。なぁるほど。
ゲスト:うーん。
MC :よ、よく、高校の時に無理しすぎたら
ゲスト:ええ。
MC :プロになって、て、ダメだって言うけど、
ゲスト:ええ。
MC :それもやっぱりあるんですかね。
ゲスト:それも、あると思いますね。
MC :あー。
ゲスト:あのー、高校野球はね、連投連投のかなり
MC :うーん。
ゲスト:過酷な、あれですから、あの、そこで、ま、肩を酷使してしまう
MC :うん。
ゲスト:肘を酷使してしまうって選手はいると思いますね。
MC :はー。みんな無理しないでね、キッズ達もね
ゲスト:そうですね。
MC :あー、そうかぁ。いや、あと、あれ、選手ってま、体大きけりゃいいやっていうのも
ゲスト:うん。
MC :あるけれど、ヤクルトの石川投手っていうベテラン
ゲスト:うん。
MC :何か167センチで
ゲスト:はい。
MC :実は、僕とあんまり変わんなかったりとかね
ゲスト:あっはは。
MC :結構、こ、小柄な選手が最近頑張ってるじゃないですか
ゲスト:あー、な
MC :えーと、広島のセカンドの菊池選手とかね
ゲスト:はい。そうですね。
MC :たぶん、日本代表に選ばれて
ゲスト:えー。
MC :多分これからねぇ、また、名をはせてくると思うんですけど
ゲスト:そうですよ、菊池選手の守備は、あの、アメリカのね、大リーグの選手達も結構注目したっていう話が
MC :あっ、そうなんですか。
ゲスト:去年ありましたよねぇ。
MC :あー。
ゲスト:あのー、守備範囲が広くて
MC :ええ。
ゲスト:こう、外野に抜けたというような球にも追いついて、ま、処理出来ちゃうと
MC :はい。
ゲスト:あのー、菊池選手の守備は、なんか最近すごく注目されてますけども
MC :うん、うん。
ゲスト:あのー、そうやって守備範囲が広くて追いついちゃうっていうと、まず、あ、反射神経がいいんだなって
MC :はい。
ゲスト:普通に考えちゃいますね。
MC :はい。
ゲスト:でも、人間の反射神経って実はそんなに差はなくてですね
MC :はい。
ゲスト:もちろん、一流選手となんでもない人では、ちょっと違うかもしれませんけれども
MC :はい。
ゲスト:大体プロ野球にいるような、えー、選手たちの反射神経って、そんなに変わらないと思います。
MC :ええ。
ゲスト:て言うのはですね、陸上競技では、ヨーイドンとなってから、
スターティングブロックていうブロックを蹴るまでのですね、反応時間ていうのを計ってて、
それが短すぎるとフライング
MC :うん。
ゲスト:とられちゃうんですけれども、でそのー、すう、反応時間を見るとですね、
ま、早い選手、遅い選手いるんですけれども、そのいつも早い選手とかですね、
いつも遅い選手っていなくて
MC :はい。
ゲスト:まあ、ほとんど差はなく、たまたま早い選手と遅い選手がいるという程度でですね、
あのー、一流のアスリートの中では、ほとんど差はつかないんですね。
MC :へえー。
ゲスト:反応時間は。あの、ウサインボルトがすごい記録で走ったときも、
MC :はい。
ゲスト:8人中5番目ぐらいの反応時間で、決して早くなかったんですね。
MC :おー。
ゲスト:だから、そのウサインボルトも反射神経って意味では、他の選手と変わんないんですね。
MC :はい。
ゲスト:だから、菊池選手もですね、多分、反射神経がどうっていうよりも、
むしろですね、その、えー、打者が打ってからですね、そのー、最初の二・三歩、三・四歩かな
MC :はい。
ゲスト:その最初の数歩がですね、メチャクチャ早いんだと思うんですね。
MC :スタートダッシュが早いん
ゲスト:早い
MC :ですか?
ゲスト:はい。で、
MC :それは体格にも影響しているんですか?
ゲスト:そうですね、それ、あのー、菊池選手のですね、数値を見ますと、
えーと、身長171センチ、体重69キロっていうふうに
MC :はい。
ゲスト:発表されてるんですけれども、えーっとその、プロ野球で60キロ台の選手ってのは、そんな
MC :ほぉー、はあー。
ゲスト:いないですよね。う、すくな、あのー、
MC :確かに
ゲスト:80キロ、90キロあるいは、100キロ超える人ザラにいますから、60キロてのはかなり軽い
MC :はい。
ゲスト:で、その、人間の、その、大きさとですね、筋力ってのを考えてみると、
例えば、話を単純にするためにですね、身長が2倍になるってこと考える、
ありえないですけども、身長2倍になるとですね、
MC :はい。
ゲスト:えーと、体の体積ってのは、え、縦×横×高さですから、え、2×2×2で8倍になっちゃうんですね
MC :はい。
ゲスト:体積8倍だから
MC :うん、うん。
ゲスト:体重も8倍になる
MC :はい。
ゲスト:で、筋肉の断面積っていうのはですね
MC :はい。
ゲスト:面積ですから、縦×横でいいですから
MC :はい。
ゲスト:2×2で4倍になりますね。
MC :はい。
ゲスト:ん、そうすると、あの、筋肉の強さってのは、えー、筋力ってのは、その太さに比例しますから、
えーと、体の大きさが、に、身長が2倍になると、筋力は4倍になるんですけれども、
その、4倍になった筋力で、8倍になった体重を動かさなくちゃいけないんです。
MC :ふーん。
ゲスト:すると、体が大きくなると
MC :うん。
ゲスト:自分の体の重さのために
MC :うん。
ゲスト:動かすのに、大変なんですね、ですから、そこ、例えばダンプカーとか
MC :はい。
ゲスト:と軽自動車がですね
MC :はい。
ゲスト:同しところで、スタートするとですね、多分最初はですね、数メーター、数十メーターは、
軽自動車の方が速いんですね。
MC :はい。
ゲスト:それと同じように、体の軽い菊池選手はですね、その、体の割に筋力が強いってことになりますから、
MC :うん。
ゲスト:最初のスタートは、だんぜん有利で
MC :なるほどね。
ゲスト:ええ。
MC :身長の高いウサインボルトもスタートが遅いの
ゲスト:遅いですね。
MC :なんかうなづけますよね。
ゲスト:そうですね。
MC :で、50メートルから
ゲスト:はい。
MC :一気に来るから、
ゲスト:そうなんです。
MC :そうか、そうか。で、でも、そ、
ゲスト:スピードに乗っちゃえば、もうあれなんですけども、
でも野球の守備に必要になるのは、最初の数歩ですから
MC :はい。
ゲスト:多分、ウサインボルトよりもですね、菊池選手の方がはるかに速いスタートを切ってるんですね
MC :え、二塁手とかショートの選手ってのは
ゲスト:うん。
MC :小柄な選手の方が、ん、適してるのかもしれないですね。
ゲスト:そうですね。ちょっと高めのライナーとか来ると、つらいかもしれませんけど。
MC :あ、そうか
ゲスト:ははは。
MC :えー、いやー、中々一長一短で難しいですね。なるほど。
ゲスト:でも、菊池選手の魅力ってのは、やっぱりそこですね。
MC :はい。
ゲスト:最初の数歩の
MC :うーん。
ゲスト:メチャクチャ早いところ、そこが、あのー、守備を可能にしてるんだと思いますね。
MC :なるほどねぇ。さあ、お時間になりました。
今週の「サイコー」は、ライターの柄川昭彦さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「プロ野球選手の科学 パート1」 ゲスト:柄川昭彦さん
2017/12/01 Fri 12:00 カテゴリ:人体MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
スポーツにお詳しいライターの柄川昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :去年
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :ワールドカップの時に、来ていただいてね
ゲスト:そうですね。
MC :サッカーに関して科学的にお話伺いましたけれど
ゲスト:そうですね、サッカー
MC :はい。
ゲスト:はい。
MC :今日は、野球ということなんですけれど
ゲスト:はい。
MC :ね、野球。今ね、やってますけれど、柄川さん、ちなみにどこが、ご贔屓ですか?
ゲスト:一番今、関心があるのは
MC :ええ。
ゲスト:大谷
MC :ああ、そうですか。
ゲスト:選手ですね。あのー、ファイターズの
MC :でも、文化放送昔からはっきり言って、ライオンズ贔屓ですってずーっとやってたんですよ。
ゲスト:あははは。
MC :大丈夫ですか?
ゲスト:でも、あの、魅力を感じるのはやっぱり、何度も言いますけど
MC :ええ。
ゲスト:大谷選手ですね。
MC :ありがとうございます。僕はファイターズファンです。
ゲスト:ははは。
MC :ええ。僕はファイターズファンです。ええ、いいんです、いいんですよ。
いやいや、ありがとうございます。うちの翔平をありがとうございます。
ゲスト:あっはは。そうですね。
MC :何がすごいですか?
ゲスト:えーと、あのー、やっぱり球の速さ
MC :ええ。
ゲスト:160キロを超える球を
MC :ええ。
ゲスト:普通に投げてくるっていうところは、今までなかった
MC :はい。
ゲスト:次元ですよね。
MC :はい。なんか、今シーズンはねぇ
ゲスト:はい。
MC :去年にくらべると
ゲスト:うん。
MC :ちょっと抑えてる気がするんですよ。
ゲスト:あっ、どんどん投げてこないと
MC :はい。
ゲスト:160キロ
MC :そう。
ゲスト:こないだもそうですね。
MC :そう。
ゲスト:150キロ台で止まってましたからね。
MC :そうなんで、もう、今はちょっとスピードではなくて
ゲスト:うん。
MC :ちょっと戦術的に投球戦術を、
ゲスト:はい。
MC :こう、自分なりにやってるのかななんて思ったんですけれど、本人は162キロという今、プロ野球で
ゲスト:うん。
MC :最速を持ってますよね。
ゲスト:そうですねぇ、はい。去年投げました。
MC :はい。
ゲスト:はい。
MC :一番早い球って、あれですよね、167キロ?
ゲスト:うん。
MC :が、外国で
ゲスト:なんかあるみたいですね、なんか色々調べたら171キロって数字も出てきましてですね
MC :ああ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :キューバのね、チャプマンていうピッチャーが
ゲスト:あっ、あ、そうです。
MC :すごく球速くて
ゲスト:そのチャプマンという数字ですね。
MC :171があるんですか?
ゲスト:171というふうに出てましたね。
MC :へえー。
ゲスト:106マイル?
MC :はあー。
ゲスト:ええ。
MC :大谷さんはね
ゲスト:ええ。
MC :今年、成人だったんですけど
ゲスト:うん。
MC :その時に、本人は
ゲスト:うん。
MC :170キロ出せるって
ゲスト:ええ、ええ。
MC :そうおっしゃったんですけど
ゲスト:あれですよね、野球の試合の中で投げるのと、
MC :はい。
ゲスト:どれだけ投げられるかって、思いっきり投げるのは、また別でしょうね。
MC :あっ、そっ、あ
ゲスト:きっと。
MC :コントロール抜きにしてね
ゲスト:抜きにして
MC :バッターいるから、当たったら危ないし、
ゲスト:あっはは、そうですね。
MC :色んな事考えると
ゲスト:ええ、ええ。
MC :いわゆる、フリーで投げたら
ゲスト:もっと速いでしょうね
MC :ああー、いく、嬉しいじゃないですか。
ゲスト:んふふ。きっとね。ははは。
MC :えーっ。だけどちょっと心配なのが、
ゲスト:はい。
MC :いわゆる、ビュンビュンいったピッチャーてね、
ゲスト:うーん。
MC :例えば大谷投手の先輩のダルビッシュ
ゲスト:ええ。
MC :さんですとか、手術したじゃないですか
ゲスト:そうですね。
MC :あと、田中マー君もね
ゲスト:去年ですね。
MC :うーん。
ゲスト:休みました。
MC :そう。で、松坂
ゲスト:も、手術しました。
MC :そうですよねぇ。
ゲスト:はい。
MC :だから、ちょっと
ゲスト:ええ。
MC :酷使しすぎちゃうのが心配なんですけど
ゲスト:そうですね。
MC :あれ、なんでみんな、
ゲスト:はい。
MC :同じところやられちゃうんですか
ゲスト:ええと、痛めてるのは、その肘の内側にある
MC :はい。
ゲスト:小さい靭帯があるんですね
MC :どこですか、それ。
ゲスト:あの、
MC :肘の内側
ゲスト:机なんかにぶつけると、ビィーンとこう響いちゃう
MC :おぉ、おぉ、おぉ、おぉ。
ゲスト:出っ張りありますね。
MC :ええ。
ゲスト:あそこから、この手首側にですね付いてる3~4センチの小さい靭帯なんですね。
MC :あの、痺れるところを痛めるんですか?
ゲスト:そうですね、そこから
MC :へえ。
ゲスト:手首側にこういってる靭帯があって
MC :はい。
ゲスト:そこが、ええっと、ボール投げる時にですね、強い力で引っ張られるんですね
MC :あ、今押してみると、いた気持ちいい
ゲスト:はい。
MC :気持ちいい
ゲスト:ほんとに小さいんですけれども
MC :うん。
ゲスト:あのー、投げる時にそこに一番力が加わっちゃう
MC :あ、ピッチャーはそこに負荷かかる。みんなそこ痛めてるんですか
ゲスト:あ、みんな同じなんです。
MC :おなじ?へえー。
ゲスト:松坂も、ダルビッシュも、田中マー君もですね
MC :へえー。
ゲスト:みんな同じなんですね
MC :はい。
ゲスト:で、あのー、ピッチャーが肘を痛める時は、必ずそこで、やっぱりこう投げすぎとか、
MC :はい。
ゲスト:特に速い球を投げる選手たちですから
MC :はい。
ゲスト:ものすごく大きい力が加わるんだと思いますね
MC :はい。
ゲスト:で、あのー、なんでそこが、その、痛めちゃうのかっていうとですね、
例えば人間が、歩くっていうのは、人間がこう、立ち上がったのが400万年前とか言われてる、
400万年人間は歩いてますから
MC :はい。
ゲスト:歩くっていう動作は、ま、人間の体にとって非常に普通の
MC :ああー。
ゲスト:動作なんですね。
MC :進化の過程で
ゲスト:はい。
MC :歩くことに関しては
ゲスト:ええ。
MC :そんな負荷かかってないんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:で、人間がいつからその、例えば石ころをですね、
ビュッと上から投げられたかどうかは、分かってないんですけども
MC :ほぉー。
ゲスト:多分、2~3万年前
MC :狩りをしてた頃ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:それで、あのー、投げたんだろうと
MC :はい。
ゲスト:でもそれはもう、時間にするとですね、すごく新しい動作なんですよね
MC :はい。
ゲスト:で、例えば、赤ちゃんがですね
MC :はい。
ゲスト:気に入らない、ぼ、あの、おもちゃを投げたりしますけれども
MC :はい。
ゲスト:それは、野球のピッチャーが投げるようなフォームで投げるんじゃないんですね
MC :はい。
ゲスト:で、投げるっていうのは、習わないと出来ない、人間にとっては自然の動作じゃないんですよ。
MC :はい。フォームってものがあるぐらいですからね。
ゲスト:そうですね。だから野球をやらない、あのー、例えば女の子で、
MC :はい。
ゲスト:ボールを上手に投げられない子っていくらでもいますけれども、
上手に歩けない、上手に走れないって子は、まあ、基本的にいないわけですね。
MC :うん。
ゲスト:そのくらい、あの、投げるという動作は、人間の体にとっては、ちょっと特殊な動作なんですね
MC :はい。
ゲスト:なので、あのー、ある一か所にですね、力が加わりすぎて体の方が負けちゃうと
MC :なるほどねぇー。
ゲスト:いうことみたいなんですよね。
MC :そうか、そうか。日常じゃない動作をすると
ゲスト:うん。
MC :どっか、こう、負荷かかりすぎて
ゲスト:そうですね。
MC :痛めちゃうってことですね。
ゲスト:どっかにかかっちゃうんですね。
MC :僕らってなんだろうなぁ。しゃべる。
ゲスト:あっははは。そうですね。
MC :喉に負荷かかって
ゲスト:喉に負荷かかって、でも、ま、これはちょっとね
MC :みんなやってる
ゲスト:人類生まれた時からやってることですから
MC :はぁー、やっぱ、スポーツ選手ってのはやっぱり、特異な
ゲスト:そうですね、体の動かし方を
MC :部分を使うわけですよね。
ゲスト:してるんでしょうね。
MC :そっか、大谷さんには、ちょっと大事にしてもらいたいですね。
ゲスト:そうですね。
MC :じゃあねー。
ゲスト:でも、大谷選手は、こう、二刀流ですから
MC :はい。
ゲスト:去年のちょっと数字を調べてみると
MC :はい。
ゲスト:えっと、去年は一年間、ピッチャーとしてもフル稼働しましたけども
MC :はい。
ゲスト:えっと、155イニング投げてますね。
MC :はい。
ゲスト:それに比べると、例えばあの、前田健太投手とかですね
MC :はい、ええ。
ゲスト:田中投手とか
MC :はい。
ゲスト:こう、一流の、えーと、エースピッチャーは、ま、多くなると200回以上投げるんですね
MC :はい、そうですね
ゲスト:一年間にですね。
MC :はい。
ゲスト:それに比べるとまあ、バッターと、に、二刀流にすることで、この、肘のですね、
MC :はい。
ゲスト:弱いところに、この、負担が集中しなくて済むっていう
MC :なあるほど
ゲスト:意味では
MC :ほ、ほ、ほぉ。
ゲスト:もっと大谷投手は、その、怪我しないで長持ちしてく可能性はありえますよね。
MC :ええ。一部のねぇ
ゲスト:はい。
MC :プロ野球の専門家からは、どっちかに絞れよって
ゲスト:そうですね。
MC :話もありますけれど
ゲスト:専門家ほどそういう意見みたいですけど
MC :そう、そう。実は二刀流やってるから
ゲスト:ええ。
MC :バランスが取れてるってことも
ゲスト:そうだ
MC :あるんですね。
ゲスト:ええ、そうだと、私は思いますねぇ。
MC :あ、いいお話ですね。
ゲスト:はい。
MC :あ、それはいい、すごくね、あのー、ラジオ聞いてるキッズも、納得出来たんじゃないかなぁ。
ゲスト:そうですね。
MC :うーん。
ゲスト:野球の少年達も肘を
MC :はい。
ゲスト:痛めます。
MC :はい。
ゲスト:ま、ちょっと靭帯じゃなくて、靭帯よりも骨が弱いので、子供達は
MC :はい。
ゲスト:子供達は、骨痛めちゃうんですよ。やっぱり投げすぎとかは
MC :うん。
ゲスト:良くないですね。
MC :なるほどね。
ゲスト:ええ。
MC :バランスよくということですね。
ゲスト:そうですね。
MC :だからもう、最近もあれですね、高野連なんかもピッチャーはね、
ゲスト:そうですね。
MC :エースが一人じゃなくて、二人っていうふうに
ゲスト:ええ。
MC :ねえ。
ゲスト:進めます。
MC :進めてますからね
ゲスト:はい。
MC :さあ、その大谷投手なんですけれど
ゲスト:はい。
MC :どこまで出るかっていう話で170キロ
ゲスト:はい。
MC :でね、162キロが本人の
ゲスト:うん。
MC :最速なんですけれど
ゲスト:最速ですね。
MC :えー、去年オールスターで出して、
ゲスト:うん。
MC :その後シーズン中に終盤にもう一回、出してるんですけどね
ゲスト:はい。
MC :これ162キロというものは、みんなのイメージでは、何をもってどこが162キロって
ゲスト:うん。
MC :ところなんですけど
ゲスト:はい。ま、162キロの
MC :うん。
ゲスト:ボールを投げるってことは
MC :はい。
ゲスト:その、指先がですね、162キロで動いたっていうことですよね。
MC :指先が162キロで・・・動いてるってこと?
ゲスト:動いてるってことですね。
MC :指先の
ゲスト:はい。
MC :爪の先が
ゲスト:投げ出したボールは、速くはなりませんから
MC :ほー。
ゲスト:投げ出した瞬間が一番速いんですね。
MC :ほ、ほ、ほ。
ゲスト:ですから、まあ、えーと、どこ計ってるんだろうあれ、
だから162キロ以上では指は動いてたっていうことです
MC :あれ、これ、ゴルフやる人なら分かると思うんだけど
ゲスト:うん。
MC :ゴルフのヘッドスピードってのが
ゲスト:ええ。
MC :速くても大体、50キロ
ゲスト:ああー。
MC :だから、思いっきり、だからお父さん振っても
ゲスト:振っても
MC :50キロしかいかないわけですよ。
ゲスト:あっ、それに比べると大谷投手の指先は、162キロで動いてたわけですから
MC :ほ、すごいことですね。
ゲスト:すごいですね。で、この、162キロっていう数字は、筋肉の収縮する速さだけではですね
MC :はい。
ゲスト:どんなに頑張っても出ないんですね。
MC :はい。
ゲスト:やっぱり、体を上手に使って、えー、指先を162キロで動かすと
MC :はい。
ゲスト:その、動かすための技術っていうのが、えー、体全体をですね、
ま、よく言われてるのがムチのように使うと
MC :はぁー。
ゲスト:いうことで、
MC :ああー。
ゲスト:先っぽだけが、ピュッと速くなるんですね。
MC :ああー、
ゲスト:はい。
MC :釣竿みたいな感じ?
ゲスト:そうですね、柔らかいしなやかな
MC :な、なんか
ゲスト:釣竿の先端が、ピュッと最後に動くと
MC :そうか、そ、そうすると
ゲスト:はい。
MC :人間のしなりと
ゲスト:ええ。
MC :お、も、お、ま、大谷投手の指先なんだけど
ゲスト:ええ。
MC :手を釣竿の先端みたいなイメージで、ピシャッて
ゲスト:そうなんですね。
MC :ムチみたいな感じで、ピシャッて感じ?
ゲスト:そうですね。
MC :はあー。
ゲスト:そういう使い方をすると
MC :ええ。
ゲスト:一番速くなるんですね。で、そういう使い方をしなければ、
とてもこういう、スピードが出ないんですね。
MC :おおー。
ゲスト:だから、体の軸、体の、えーと、胴体の部分ですねぇ
MC :はい。
ゲスト:胴体の部分をこう、回転させる、ひね、ひねる動作から始まって
MC :はい。
ゲスト:それに少し遅れて腕が付いて来るんですね。
MC :うん。
ゲスト:で、胴体が回り終わったあたりで、い、腕が出てきてその腕の中でも、その肘までの部分ですね
MC :あ、はい。
ゲスト:先に出て、で、肘が前に出た後に、肘から先の部分がピュッと出てくると
MC :なんか、すごく科学的な話を聞きました。ヤバイな、はっきり言ってライオンズ贔屓だけれど、
ちょっと今日は、すいませんでした。えー、我がファイターズのお話だけをしてしまいました。
また来週違う球団のお話をしたいと思います。多分、ライオンズだと思います。
え、今週の「サイコー」は、スポーツにお詳しいライターの柄川昭彦さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「彗星 パート2」 ゲスト:縣秀彦さん
2017/11/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さあ、今週のサイコーもですね、前回に続きまして星の専門家、
国立天文台天文情報センターの縣秀彦さんです。こんばんは。
ゲスト:こんばんは。
MC :縣さんは、星に詳しいサイコー、幻冬舎エデュケーションからですね、
「一番わかりやすい彗星の秘密」という本も出版されてるんですが、前回途中で終わっちゃったの。
えー、2061年・・・だからこれから47年後?ハレー彗星がやって来ると・・・で、
これは今のキッズ達がおじさんになった時に、ハレー彗星見る為の47年後の準備の放送ですね。
ゲスト:そうですね。まああのー、彗星っていうのは突然発見されることが多いんですねー。
MC :はい。
ゲスト:大体あのー、彗星、太陽に近づくのが、年間100個以上はあるんですが・・・
MC :特に去年はね、彗星、彗星って言われてました。
ゲスト:はい。去年のあの騒ぎになったような、あのーパンスターズ彗星が3月にあって、
11月にアイソン彗星、それから12月にラブジョイ彗星っていうのが話題になりましたけど、
ああいう一般の方でも、こう注目してもらえるような彗星らしい、尾がこうある彗星っていうのはその、
ほんのわずかなんですね。
MC :はい。
ゲスト:ほとんどは、んーまあ、太陽系の果てにある小さな氷の塊なので、ほんとに太陽に近づいた時じゃないと、
おー、尾が発達しないのとあのー、ハレー彗星みたいに何回も何回も回ってる彗星の場合には、
表面に段々こう殻が出来ましてね・・・
MC :はい。
ゲスト:んー、だから、塵がこう積もれば山となる・・・じゃないですけど、
塵のこう・・・あのこうなんていうかな・・・覆いができちゃうもんですから、
まああのー僕ら「ダストマントル」って呼んでる・・・ダストのダスト、ダスト達です・・・
MC :ゴミ?塵?
ゲスト:うん、塵・・・こういう囲いができちゃって、で、段々こう・・・えー、
尾が作れなくなりますので、えーまあそんなに・・・
えー、毎年毎年その彗星が見えるわけではないのですが、えーもしかしたらまあ、あのー、
突然現れますから、あのーこの放送が・・・んー、された直後に例えば、
彗星また見えるっていう話もないわけじゃないんだけど・・・
MC :まあ、宇宙は気まぐれで・・・
ゲスト:そうそうそうそう。
MC :人類はコントロールできないですものね。
ゲスト:そうそう、大体10年にいっぺんは、あー肉眼で皆さんがこう楽しめるような彗星ってやって来る頻度、
その位の確率ではやって来てるんですが、まあ間違いないのはとにかく、2061年・・・
MC :このハレー彗星。
ゲスト:はい。
MC :ありがたい、ハレー彗星は必ず帰って来てくれると・・・でもね。
ゲスト:はい。
MC :これがまた、多分・・・僕なんか思ったのは、
「ハレー彗星間違いなく・・・」って今おっしゃったけれど・・・
ゲスト:はい。
MC :この間のアイソン彗星みたいに太陽にね、
溶かされてなくなっちゃうんじゃないの?って疑ってる訳ですよ、こっちは。
ゲスト:そうですよねー。
MC :なんで、ハレー彗星は47年後、来るって言い、言いきれるんですか?
ゲスト:そうなんですよねー。これ多分、皆さん心配されてハレー彗星、
みんなおんなじことになっちゃったらどうしようって思われる方多いと思うんですけど、
実はですね、彗星の中にはいろんな種類、いろんなのがありまして、
この昨年11月に話題、話題になったアイソン彗星の最大の特徴は、
なんであんなに騒ぎになったかというと、太陽のすぐ近くを通り過ぎるという・・・
MC :んーーーーそう、あっつい所を通っちゃう・・・
ゲスト:太陽の直径っていうのは、ひゃくさー139万キロっていうサイズです。
MC :はい。
ゲスト:地球のサイズでいうと、地球をですね、100個以上、100個、
大体100個こう並べると139万キロっていう計算ですね。
その直径、その表面から・・・んー、100キロぐらいの所・・・
MC :はい。
ゲスト:だから、太陽の直径分よりも内側をこのアイソン彗星は通り過ぎた・・・
MC :わー、いわゆるもう一番ちんちんに熱い所を通ってると・・・
ゲスト:そう、大体ねーあの・・・2000度から3000度近くまで温度がある所の領域を通り過ぎたので、
まあ大きさがアイソン彗星、最初は5キロメートルくらいの直径、で、
そのうち小っちゃいから2キロメートルぐらいっていうふうに修正されましたけど、
もうちょっと小っちゃかった可能性も今指摘されてますが、とにかく溶けっちゃったんですねー。
MC :飛んで火にいる夏の虫みたいな感じですね。
ゲスト:いやほんとにね、あのー、その時の熱さは大変な熱さですよねー。
MC :はーい。
ゲスト:だから、塵粒・・・うー、つまり、そこに入ってる塵の粒々ももう一旦溶けちゃうぐらいのこと・・・
だからあのーもう、完全に何にも見えなくなっちゃった訳ですが、ハレー彗星とかね、
ほとんどの彗星、そんなに近くまで行かないんですよ。
MC :えー、セーフティーゾーンを回ってるんですね?
ゲスト:そうです、そうです。
MC :安全な所を・・・えー。
ゲスト:そうです。ハレー彗星があのー、76年周期でもう出現がですね、
えーもうその100回以上数えられるぐらいね来てるっていうのは、なぜかって言うと、
太陽から割と離れたところを通るんですよ。
でも、太陽から離れたところを通ってるのに何で大彗星かって言うと・・・
元々ハレー彗星って多分あのー、ちょっと大きなんね、直径が15キロぐらいあります。
それから、ハレー彗星の場合はですね、んーと地球との位置関係で、
地球のすぐ近くに来るとやっぱりすごい大彗星に見える・・・
MC :76年に1回・・・
ゲスト:そう。
MC :地球の近く来る。
ゲスト:そう。あのね、1910年の時のが地球にすごい近づきましてね、
このハレー彗星の尾の中を地球が1910年にハレー彗星が接近したというか、通り過ぎてるんですね。
ていうことは、夜空を見上げるとその当時は、ハレー彗星がこう東の空にあったとすると、
ずーっと、尾がもう真上を通って反対側まで・・・
MC :えー。
ゲスト:180度近く尾が見えるということですね。その尾の中を僕ら通ったわけだから・・・
MC :はーい。
ゲスト:だから太陽のすぐ近くを通り過ぎるか、地球のすぐ近くを通り過ぎるか、
彗星そのものがとても大きいかって、この3つでこの彗星がどれだけ明るく見えるかっていうのが
決まってくると・・・
MC :へぇー。じゃあ、ハレー彗星はじゃあ、47年後やって来る、76年に1回やって来る・・・で、
これは、えーまあ条件がいいから、滅びることなく確実にやって来ると言えるわけなんですね。
ゲスト:そう、近過ぎない。近過ぎるのはサングレーザーって呼ばれる仲間なんだけど、
このサングレーザーっていうのは、中には溶けっちゃったり、3つ4つに分裂しちゃうとかね・・・
MC :あっ、「サン」っていうのは太陽のサンですか?サングレーザー・・・
ゲスト:はい、サンにサンにすごい近づくの。これらは危険ですね。だから、帰ってこれない場合もあるし、
中には太陽にもう飲み込まれっちゃうのも結構多いんですねー。
MC :んーーーー。
ゲスト:んーでも、ハレー彗星ってこう帰って来るのがもう計算できるので、
前もって色々準備できるじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:あのー1986年の時にはね、探査機がね6つも飛んでったんですよ。
MC :へぇーーーー。
ゲスト:NALからも2台。えー当時のまあ、今のロシア・・・当時ソ連って言いましたけど、2台。
アメリカが1台、それからヨーロッパの人達が1台飛ばしたんですよ。
MC :へぇーーーー。
ゲスト:で、その、この時にハレー彗星にものすごい近づいた、えー、
ヨーロッパの「ジオット」という探査機がそのー今まで誰も見たことがないこのー、本体、
彗星本体ってほら、小っちゃくってまわり全部ほら、コマっていうんで、こうねガスで囲まれてるから、
見えないんですよね。地球からどうやっても、どんな大きな望遠鏡でも、
探査機が近づいてようやくハレー彗星が撮影されました。
MC :へぇーーーー。
ゲスト:でね、ピーナッツのような形してましてね・・・
MC :ハレー彗星が?
ゲスト:そうなんですよ。
MC :え?あの・・・・
ゲスト:細長いんですよ。
MC :落花生みたいな?あの?
ゲスト:そうです、そうです。
MC :2つ、じゃあ双子みたいな感じですか?
ゲスト:そうです、そうです。それでね・・・
MC :えーーーー。
ゲスト:あのー、一番長い所で15キロメートルぐらいで、
えーその幅が5キロくらいとか・・・ちょっと細長い形・・・
MC :結構小っちゃいんですね、小ぶりで・・・
ゲスト:それでもね、結構大きいほうなんですけど、それでね・・・・
MC :ホーーーーー
ゲスト:このー割と僕ら、僕も見てびっくりしたんですけどね・・・割と真っ黒なんですよ。
黒ずんでましてね、で、途中土地どっかあのー、んー、適当な場所から何か所かからこう、
びゅっとジェット、ガスが噴出してる・・・表面全体から噴き出してる訳じゃなかったんですね。
MC :えーーー。
ゲスト:それは衝撃的でした。で、でそのもうあのー・・・
MC :見た、見た感じになってきた・・・
ゲスト:ええ、探査機があのー、あっちこっちの彗星に行って、
今まで、えっとーえー1、2、3、4・・・5・・・うん、5つの彗星のその本体まであのー、
近づいた探査機がいます。で、いよいよですね、あの・・・今年の一番注目してるのはですね、
やっぱりヨーロッパの「ロゼッタ」という探査機がある彗星に着陸する予定です。
MC :えっ、だって彗星小っちゃいんですよね?
ゲスト:ええ。
MC :小っちゃいけれど着陸できるんですか?
ゲスト:ええ、ええ、あのー例えばねー、あのー、イトカ・・・
あー「はやぶさ」が飛んでった「イトカワ」っていう小惑星は直径がね500メートルしか・・・
500メートルってすごい・・・
MC :そうですね、学校の校庭よりもちっちゃいんですよね・・・
ゲスト:そうそう、それぐらいのサイズでしょ?ほいで、それよりは今度近づく彗星は大きいのです。
それで、とにかく彗星に着陸したことが今までもないので・・・
MC :はい。
ゲスト:今年中にそういう、とっても貴重なニュース?大発見が伝えられるかもしれませんね。
これヨーロッパの打ち上げた「ロゼッタ」という探査機です。
MC :はい。いやあーーーもう終わっちゃった。どうしよー。ハハハハ・・・短かったですねー。
縣さん、また今度いつか来てくださいね。
ゲスト:はい。はい、またお邪魔しまーす。
MC :47年後、またお待ちしてますんで・・・
ゲスト:ハハハハ・・・
MC :いやー、楽しかった二週に渡って伺いました。
今週のサイコーは国立天文台天文情報センターの縣秀彦さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「彗星 パート1」 ゲスト:縣秀彦さん
2017/11/01 Wed 12:00 カテゴリ:宇宙MC :今週のサイコーは、国立天文台天文情報センターの縣秀彦さんです。こんばんは。
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、縣さんは、とても星に詳しいサイコーで、
幻冬舎エデュケーション発行「一番わかりやすい彗星の秘密」という本も出版されてるんですね?
で、あのー、彗星ってよく「ほうき星」なんてて言われてます。
ゲスト:はい。
MC :あのー、絵にすると大体みんな五角形の星描いて、
それにちょっちょっちょっと3本ぐらい髭描いて、彗星っていうイメージ・・・
ゲスト:あー、はい、そうですね。そんな感じですかね・・・ええ。
MC :一番わかりやすい彗星の秘密ということで、そもそも彗星って何ですか?
ゲスト:そうですね。あのー、星形に星って描きたくなりますけど、
確かに普通の星はキラキラ瞬いてて、そんなイメージですよね。
彗星はですね、ご覧になった方は多分少ないんだろうなあと思うんだけども、
星と違ってね、少しぼやーっとしてるんですねー、見かけがね。
MC :でも去年の年末?彗星ってやたら話題になったじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :すごく今、日本人にとって「彗星」、いや世界的に今「彗星」って大注目だと思うんですけれどね・・・
ゲスト:「彗星見たいなー。」と思っているね、あのー、リスナーの方たくさんいらっしゃるでしょうね。
MC :はい。
ゲスト:彗星っていうのはですね、まあ氷の塊なんですね。よく、一言でいうと・・・
MC :氷の塊・・・
ゲスト:汚れた雪玉とか雪だるまって言うんですけど、要はほとんどは氷の塊で、
まあ直径が数キロメートル、10キロとかね、せいぜいそんなもんなんですね。
MC :直径10キロって結構デカいですけど・・・
ゲスト:そうですね。
MC :で、それ氷なんですか?
ゲスト:うん、でねー、汚れたっていう意味は、そこに、んー砂粒とか炭素の粒が混じっている・・・ですね。
だからちょっとあのー、泥だらけの、んー所、あのーで、雪だるま作ると、
乾くとほら段々段々こう土、土の部分がね、泥とか染み出てきて黒っぽくなってきちゃう、
きれいな白い雪だるま、あんな感じで太陽の光を受けて段々ちょっと黒ずんでくるってことがありますけど、
実は太陽系の果てからやって来る「太陽系の化石」とも呼べる天体なんですよ、この彗星は。
MC :ちょっ、古いものは古いということですね。
ゲスト:古いですねー。大体46億年位前に、できら・・・あのー、
まあ僕らも太陽や地球も同じ頃創られたんですが、その当時の状況ってほら、
地球の表面も太陽の表面も、どんどんどんどん変わっていっちゃうから、
昔の記憶ってとどめてないですよね。
MC :はい。
ゲスト:でもこの彗星ってのは、太陽系の果て、太陽地球間の距離の大体1万倍、
んー、とっても離れた寒い所にずっといて、太陽に近づいて来るもんですから、
ずっと昔の状態が冷トン保存、冷凍保存された状態と思ったんでいいんですねー。
MC :ほほほーじゃあ、北極辺りの氷が赤道近くにやって来るイメージですか?
ゲスト:あああー、いい例えですね。そうですね。
MC :おー、本来凍っているべき所から突然、あったかい所にやって来るいう?
ゲスト:あったかい所にやって来た。・・・うん、うん。
MC :だから消えちゃったりするんですか?
ゲスト:そう、それでびっくりして、あのー、びっくりするって変ですけど・・・
MC :ええ。
ゲスト:太陽のエネルギーでですね、どんどんどんどん溶けちゃうんですよね。
それで、いわゆる水?あのH2Oっていうふうに書くね、水ね。
水っていうのが大体8割、9割位だと思われています。
まあ個性的で、それぞれちょっとずつ違うんですけど、で、そこに一酸化炭素、二酸化炭素、
あとメタン、アンモニアなど・・・こういったものも固体になってる・・・だから、
そういうのって、気体じゃないですか、僕らの常識だとねー、
でも二酸化炭素も冷やすとドライアイスになるように、寒い所に来るとそれも全部冷凍になって、
氷になってて、混ざってる状態のものがやって来て順番に溶けてくような・・・
MC :ほほほー、それで溶けていく過程で光って見えたり・・・
ゲスト:そうですねー。
MC :あの、尾ひれが見えるという事ですか?
ゲスト:そうなんですよ。太陽からね、太陽風ってのがやって来て、
この・・・んーまあ、頭の部分、その本体、氷の本体の周りは今、溶けたものが雲を作って、
「コマ」って呼ぶんですけどね・・・コマ。コマってあの、髪の毛とか頭を意味するんですけどね、
コマ、コマから、んー太陽風によって、吹き流されましてね、尾がビューっと伸びたり太陽の光って実は、
ものすごい圧力がありましてね、こう押してるんですよ。プレッシャーこうやって、
押してるので、それによってこう、尾が出来たりする・・・ですねー。
MC :おーあのー彗星と流れ星は違うんですか?
ゲスト:あっ、そこは大事なとこですね。
MC :そこ、すごい興味があるんですけど・・・
ゲスト:実はあのー、流れ星とこの彗星、ほうき星ってごっちゃになってる方、とっても多いですね。
MC :多いです。絶対ごっちゃです。
ゲスト:何かこう、線のような形に見えるから。んで、流れ星っていうのは実は彗星が通り過ぎた後に、
さっき言った砂粒とか炭素の粒みたいな物が、んー彗星が通ちゃった後に残ってましてね、
そこをたまたま地球が通ると、本当に地球の中にこう大気で光るわけですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、流れ星ってのは、分かりやすく言うと、おーほんとに1秒も光らない。0.2秒とか・・・
MC :一瞬ですよ。
ゲスト:そうそうそう。
MC :願い事なんか3つ言えない。
ゲスト:3つ言えないよね。
MC :ていう感じですよね。
ゲスト:それに対して、彗星っていうのは、こう尾を引いていて、まあそうですね・・・えー、
一週間、一か月位は見える・・・つまりあのーまあー、星の間を少しずつは動いていくんですけども、
あのーまあ、毎晩晴れてれば、「あっ」って見えるんですね。で、流れ星は一瞬。んー・・・で、
彗星は直径10キロとか数キロの氷の塊。えー流れ星は、んーと、ほんとにちっちゃい、
そうですね、皆さん指のこの爪の先ぐらいのサイズ。5ミリとかね1センチもないような、
そういう塵の塊が地球の大気中で光ってる・・・
MC :あの彗星って大体こう、直径10キロぐらいだとおっしゃってましたよね?最初に。
流れ星ってのはもっとちっちゃいものですか?
ゲスト:流れ星はね、そっからこうどんどんとこう吹き出してったほんとにあの数ミリ・・・
MC :のものの集合体?
ゲスト:そう、そう数ミリぐらいのサイズの物が見えないで、この太陽系の中に漂ってましてね・・・
MC :はい。
ゲスト:そこをまあ、地球が通りす、通って来る時にそこに入ってくるわけですよ。ぽんぽんと。
MC :はい。
ゲスト:それが地球の大気を発光させるんですよねー。
MC :で、流れ星ってのは塊じゃないんですか、
元々・・・星の塊が何か砕け散る瞬間流れるとか、そういう風に・・・
ゲスト:あーーー
MC :伝説に言われていること・・・
ゲスト:そういうイメージもありますよね。
MC :そうじゃない。
ゲスト:ええ。普通の流れ星、例えばペルセウス座流星群とか、あーしし座流星群とかよくね聞く・・・
ああいうのは、あーその、お母さんが彗星、ほうき星。
もっと明るくて隕石になったりするのはお父さんが小惑星。
まあ、こんな感じでとらえるといいんじゃないでしょうかね。
MC :ほー。流れ・・・あっ、じゃあ、しし座流星群なんかは流れ星の仲間と考えてよろしいんですよね?
ゲスト:流れ星ですね。
MC :だーそうか・・・。あのーなんか擬音でいうと、あのー、
流れ星って「シュッ」っていう感じじゃないですか。「シュッ」
ゲスト:あっ、うんうんうん。
MC :彗星は実際じゃあ、どんな感じですか?擬音でいうと・・・
ゲスト:あっ、僕のイメージだと「ボーーーーーー、ボーーーー」
MC :はい。それでしばらくずっと見えてるわけですね。
ゲスト:そうですね。太陽に近づいた時だけに氷が解けて、周りにコマと尾を作るのです。
ですから、太陽の近づいている時だけ見えましてね・・・
MC :はーー
ゲスト:今までで一番長く見えたのでも、えー1997年のヘール・ボップ彗星というのが、
1年半見えたんですが・・・
MC :おっ、ずっと見え続けてたんですか?
ゲスト:これが最大の記録ですね。1年半見えましたよと、肉眼で・・・
MC :「ボーーー」っと。
ゲスト:世界のどこかでは「ボーーー」っとしてましたよ。で、普通の彗星っていうのは、
この間のアイソン彗星っていうのも、あのー普通の人が肉眼で見える明るさだったのは、
えー、一週間もなかったですね。あのーちょうど太陽に近づいてこれから明るくなるって時に、
全部溶けちゃったので・・・
MC :はい。
ゲスト:残念だったんですけどねー。また戻ってればね、あのー、昨年の12月、
もしかしたら1月も見えた人もいたかもしれないぐらい大彗星になる可能性もあったんですけど、
残念ながら全部、太陽に近づいた時に溶けちゃったんですねー。
MC :んー。なんかアイソン彗星の時ってね、ニュースになって突然消えちゃったってなったじゃないですか。
ゲスト:はい。はい。
MC :でも僕らは、「あー残念だな。」と思いましたけど、
縣さんみたいなご専門の方からすると心から悔しいと・・・
ゲスト:はー、悔しい。悲しい。
MC :あっ、やっぱり、もうそういう世界なんですね。
ゲスト:残念、本当に残念。まあ・・・はい。
MC :えー、あのー、このあのだから、アイソン彗星はじゃあ、10年に1回、
何十年に1回と言われてますけど、この2014年以降、僕らが見ることが出来る彗星ってのはないんですか?
ゲスト:確実なのは、あのー、有名なハレー彗星ですよね。
MC :えー。
ゲスト:ハレー彗星は実は今年来ません。2061年に戻ってきます。76年周期なんですよ。
MC :いやーー。
ゲスト:ただ、1985年6年によく見えたんですけど、次は2061年。
MC :よし、じゃあその・・・キッズ達がおじさんになった時にやって来るハレー彗星については、
来週また伺うことにしてよろしいですね。もう時間なってしまいました。
はい。えー、今週のサイコーは国立天文台天文情報センターの縣秀彦さんでした。
また来週よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いしまーす。 -
「小笠原諸島に現れた新しい島はなぜできたの? パート2」 ゲスト:野上健治さん
2017/10/01 Sun 12:00 カテゴリ:環境MC :さ、今週のサイコーも火山にお詳しい東京工業大学教授の野上健治先生です。こんにちはー。
ゲスト:どうも、こんにちは。
MC :えー、先週のー衝撃のー47都道府県の中で東京都が一番火山が多いという
ゲスト:そうですね、一番火山が多い
MC :これ、よくわからなかったけど言われてみたら、伊豆大島は火山ですか?
ゲスト:もちろんそうですね。1986年に大きな噴火がありました。
全、全島避難を余儀なくされたという噴火がありましたね。
MC :ふん。記憶に新しいところで三宅島
ゲスト:そうですね。2000年にえー非常にあれも珍しい噴火だったんですけど、
大量の火山がそうだして、あれは住民の方々5年間も避難を余儀なくされましたね。
MC :そうですよー。そして、この間の西之島という。それ以外は、あとはどこがあるんですか?
ゲスト:そうですね、もっとずっと南へ行くと硫黄島って島がありますね。
MC :おーっ。いやー、
ゲスト:硫黄島
MC :激戦地
ゲスト:まあ、そうですね。あそこはあの昔から火山島なんですね。
MC :だってあそこまだガスが出てるって言うじゃないですか。
ゲスト:えーえー、そうです、そうです。
MC :洞窟に行ったら危険だって話も聞きましたけど。
ゲスト:はい。
MC :あ、あ、か、活火山と考えていいんですか。
ゲスト:もちろん活火山、もちろん活火山です。活火山には実は定義がありましてー、
一つはですね、一万年以内にもう噴火した事があの証明されてるってことがひとつ
MC :一万年
ゲスト:一万年です。
MC :けっこう長いですね。
ゲスト:長いんですね。で、に、ついこの間まで2000年、ま、10年ぐらい前ですけど、
2000年間に噴火したことだったやつが、ま、定義を変えて一万年に伸びたんですね。
一万年以内に噴火をしてるってことが一つの火山
MC :5倍になったんですね。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :富士山は、じゃあ活火山ってことですか。
ゲスト:あ、りっぱな活火山です。
MC :あらー。
ゲスト:なぜかと言うと、あれ、江戸時代にもう噴火して、あの詳細な記載が残ってますよね。
MC :はーい。
ゲスト:あの、もちろん絵にも沢山出てますし
MC :はーい。
ゲスト:残ってますし
MC :はーい。
ゲスト:後あのー、江戸時代、江戸市中にですね火山灰が降ったってことも、
あのー記録にありますから、で、実際にそれ採取されてるんですね。
MC :えー。
ゲスト:で、それが実は蔵に、蔵を壊した時に出てきたっていう
非常にフレッシュな火山灰が出てきた例も実はあるんですね。
ま、富士山なんかは立派な活火山ですね。
MC :あー、
ゲスト:でー、あともう一つはですね、あの火山ガスを出しているところ、
噴気活動があるところですね。
MC :例えば?
ゲスト:例えば、東京の近くだと箱根がそうですね。
MC :あーーー。あ、あれも、そっか地獄谷とかいってもくもくなって温泉卵を食べてるけどー、
あれも立派な火山ってことですか。
ゲスト:そうです、そうです。大涌谷ですね。
MC :大涌谷
ゲスト:えー、あそこは立派な火山ですね。
MC :うわー、え、あとは?
ゲスト:あとはですね、群馬県と長野県の境界の、にある浅間山がそうですね。
MC :浅間山、はい。
ゲスト:そうですね。で、今僕らがいる草津白根山にもま、その噴気活動がありますね。
MC :草津温泉
ゲスト:あそこは噴火が、噴火活動もありましたから、ま、活火山なわけですね。
MC :日本って、昔からその火山っていうかー、
そういうものでこの日本列島だって生まれてきたようなものじゃないですか。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :サンゴ礁の隆起とかー、南の方は。だけど僕らの暮らしってやっぱり火山とどうしても
ゲスト:そうですね。
MC :関係がある
ゲスト:えー、日本列島はもう、その、に住んでいる以上はですね、
火山活動と無縁では生きていけないですね。
で、家の近所に火山ないよっていう方もいらっしゃると思うんですが、
火山灰ってすごく遠くから飛んできますんで、大正、今から百年前に、大正時代ですね、
桜島ですごく大きな噴火がありました。そん時に桜島が初めてくっついて島じゃなくなって
陸続きになった噴火ありましたね。
MC :そうなんですかー。
ゲスト:大量の溶岩出しましたよね。
MC :東側で、はい。
ゲスト:あの噴火の火山灰はえー、遥か仙台を越えてるんですね。
MC :えっ、東北の仙台?えーーっ。
ゲスト:だから、ものすごいとこまで飛んでるので、まあ、今もしそういう事が起こってしまうと、
えー航空とかですね、こ、あのーいわゆるそのー鉄道とかですね、
そういうとこにも影響出てしまうんですね。だから無縁ではない
MC :僕らの暮らし、普通に土の上で生きてますけど、そこにはーいろんな火山灰の層ってあるー
ゲスト:そうですね。
MC :わけですよねー。関東ローム層って赤土って習ったけれどー、それ以外にも火山灰の層があったり、
ゲスト:そうです。
MC :富士山の噴火による層があったりー、
ゲスト:あるわけですね。
MC :競争してるわけですねー。
ゲスト:そうです。だからあのー無縁では絶対生きていけないですね。
MC :へぇーー。
ゲスト:例えば、あの2000年の三宅島の噴火の時に
MC :はい。
ゲスト:大量の火山、あの火山ガスSO2ですねー、二酸化硫黄のガスが出ましたけど、
あれはたまたまですね、だし、あのーそん時に台風が近くを通ってですね、
MC :え、
ゲスト:えー、火山ガスをですねー、全国に巻き散らかしたことがあるんですね。
MC :ふーーん。ガス
ゲスト:ガスを。で、そのーどうしてそれがわかったかって言うと、
道路にその環境測定のポイントがたっくさんあるんですね。
で、いわゆる環境状況測ってるわけですね、で、そこに全部異常値が出てきたわけですね。
MC :そうですね、全島避難になったのもー、ガスがあるからってことですよね。
ゲスト:そうです、そうです。
MC :いわゆる
ゲスト:溶岩を出したわけでもなくて
MC :そうですよねー。火山性有毒ガスがあるからってことでみなさん避難されたんですよねー。
ゲスト:そういうことです。で、それがたまたま通った台風のおかげでですね、
全国に巻き散らかされて、すごい事になったことがあるんです。
だから決して無縁ではないですね。
MC :先生、一万年以上前に噴火の実績があるものを活火山と言うと。
ゲスト:一万年以下ですね。
MC :以下、だから最近、一万年よりも
ゲスト:新しい方ですね。
MC :じゃあ、日本に活火山いくつあるんですか
ゲスト:全部でですね、今110あります。
MC :けっこうあるんですねー。
ゲスト:けっこう多いですよ、110あります。
MC :え、東京都はそしたらいくつですか、だいたい。
ゲスト:東京都はですね、えー20いくつあるんですね、ちょっと今細かい数字
MC :僕、今、住んでる北海道は、
ゲスト:え、
MC :十勝岳とか有珠山とか
ゲスト:そうです。
MC :あのーけっこうあるみたいですよ。
ゲスト:ありますねー。あのー雌阿寒岳もありますし、北海道駒ヶ岳もありますし、
MC :あるある。それでだって九州に行ってもね、
ゲスト:ありますね。
MC :鹿児島に行ったら桜島ってあるじゃないですか。
ゲスト:そうですね。
MC :だから何げに太平洋の沿岸部っていうか円弧状にやっぱり日本列島って
火山といっしょにこう共存している感じの島ですよね。
ゲスト:そうですね。あの北海道から東北通って伊豆マリアナまでずっとつながってますよね。
MC :はい。
ゲスト:で、そこは一つのラインですね。で、もう一つがあのーま、
九州からあのー台湾に向けてのラインがあります。それは琉球弧っていう弧なんですけども。
MC :けっこう長い。
ゲスト:長いですね。
MC :へぇー。何キロぐらいですか。
ゲスト:えーと、あっちはせん、千キロはないと思いますけど、あの台湾までつながってますので、
けっこう長い距離ですよね。
MC :延べでいくとじゃ北海道から台湾まで数千キロですよね。
ゲスト:まあ、そうですけど、ま、チェーンが二つ、鎖が二つありまして別々のチェーンですけどね、
で、まあ、あのそういう風にあのーたくさん火山が実はあるんですね。
でー、3割ぐらいは海に、海域にあるんですが、6割、あと7割ぐらいが、
ま、陸域にあるということですね。
MC :で、先週おっしゃってたその3割、海にある火山っていうのが非常に研究難しいということですよねー。
ゲスト:そうです、え。
MC :今、ちょっと火山の話聞いて僕なんかいろいろと、「あー、大丈夫かなー」なんて思いますけど、
なんか地球からすると吹出物がこう吹き出すような感じになるんですかねー。
ゲスト:まあ、あのー、いろんなタイプの噴火があってー、
ま、マグマの出方もいろいろあるんですけども、あの、ま、例えばハワイなんかはまさにま、
そういういつも常時出ているところにこう島があっ、出来てですね、
それがまるでベルトコンベアーに乗ってるように、ま、ハワイ島を移動してだんだん火山が出来、
あの島が出来てくわけですよね、で、日本の場合はちょっと違って沈み込みという現象で
マグマが出来るので、ま、同じ場所からだいだいまあ噴火をするのが常なんですよ。
MC :はぁー。
ゲスト:だからあの突然、あ、突然噴火した場所もありますよ。
例えば1989年の伊東沖の、あのー、海底火山噴火。あれは新しく火山が出来た噴火だったんですね。
なんもなかったところに火山が出来た噴火ですね、あれは。
MC :でもそれはレアケースだけれど、大体日本の110は吹き出し口は大体決まってるということ
ゲスト:まあ、大体そうです。
MC :そうかー。じゃ、富士山に関しては、ど、どうですか、ずばり、
もういろんな新聞にもよく出てるじゃないですか。
ゲスト:それはですねー、あのー、ま、火山ってなんか何もなく突然噴火するってことはまあ、
なくてですねー。例えば、地震が起こるとか、ま、それはオーソドックスな話ですよね。
で、例えば火山っていうのはあのー現象としては、エネルギーとま、
物質の移動って僕はよく言うんですがー、つまり熱を出さないといけないわけですね。
となると、富士山、富士山でもどこでもいいんですけど、
なんか起こる時には必ず熱の兆候がでるはずだろう、と僕は思っているんですね。
で、何故かというとガスが一番移動する速度が速いから。
MC :はい。
ゲスト:で、その火山帯のどっかに温度が上がってきたよ、とか、噴気が出始めたよーとか、
だんだん植物が枯れてきたよーとかってそういう現象がでるはずなんです。
MC :そうですか。
ゲスト:で、そうなると、これはいよいよってことが起こるかもしれません。
でも今の所その現象起ってませんし、で富士山っていうのはもう日本でも
その観測の密度がすごく高いんですね。
いろんな機関がいろんな装置をおいてずっと見てるので抜き打ちで噴火して
「あれっ」っていうことはまずないだろうと。
MC :なんかあのー、この間やってたオリンピックの有名競技と
マイナー競技の国のお金のかけ方と似てますね。
ゲスト:ひっひっひ、まあ、ひっひっひ、まあ言い方いいにくいんですが、はっはっは。
MC :やっと、よくわかった!もうだから地震学者10に対して火山学者1
ゲスト:そうですね、予算規模でいうと実はもっと開きがあるんです。
MC :そうですかー。いやー、今度お酒でも飲みながらその話、しませんか。
はっはっは、有難うございました。はっは。やー、興味深かったなぁー。
今週のサイコーは東京工業大学の野上健治先生でした。有難うございました。
ゲスト:どうも、有難うございました。 -
「小笠原諸島に現れた新しい島はなぜできたの? パート1」 ゲスト:野上健治さん
2017/10/01 Sun 12:00 カテゴリ:環境MC :さ、今週のサイコーは群馬県の草津からお見えです。
東京工業大学教授の野上健治先生です。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :群馬が拠点なんですか?
ゲスト:そうです、我々は群馬県の草津白根山を研究対象にしております。
MC :あ、火山だからですねー。
ゲスト:そうです。
MC :えー、野上さんの研究は火山科学や火山熱学。で、記憶に新しいところで去年の暮れですねー、
小笠原諸島に新しい島が出来たと。これ、テレビでもよく見ましたし、新聞でも載りましたよね。
で、野上先生は早くからこの島に臨場してたってことですね。
ゲスト:まあ、あの実はこの噴火の前からですねー、
MC :え、
ゲスト:海上保安庁の飛行機に同乗許されまして、
MC :え、
ゲスト:ずぅーと10年以上を観測してきました。
MC :ちょっと待ってください。え、10年前から怪しいぞって空気があったんですか?
ゲスト:いえいえ、あの西之島っていうのは実は40年前に大きな噴火をしてます。
で、その40年前の噴火の時にその観測を携わったのが僕の指導教官の先生だったんです。
MC :あ、すごい。
ゲスト:で、東京工業大学のその研究者がずぅーっと海底火山の噴火の、ま、火山活動のね研究を、
ま、してきたんですね。で、僕が、ま、それを引き継いでもう10年以上前から海上保安庁と一緒に研究を、
まあしてきたんですね。ですから噴火の前の状態も僕は見てるんですね。
MC :じゃ、この西之島、今くっついちゃいましたけど、古い西之島は40年前に噴火してできて、
それを東京工業大学の方で研究の、材料として使っていて、先生それ引き継いでて10年前から、
研究してたってことですか。
ゲスト:そうです。
MC :でも、かと言って100パーセントでもその西之島がね、
10年ずぅーっと見続けていて噴火するとは限らないわけじゃないですか。
ゲスト:えー。
MC :たまたま来たってことですよね。
ゲスト:まあ、そうなんですけどー、あのー西之島だけ特化して見たわけではなくてー、
日本列島まあ、いわゆる火山列島ってのがありますね、
MC :えーえー。
ゲスト:で、非常に長いですね。あのー硫黄島よりまださらに南まで海底火山が続いてます。
で、それを全部一応そのモニターしてるんですね。
MC :へぇー。
ゲスト:で、研究対象にして、ま、ずっと一緒に、ま、やってきたわけですね。
MC :あ、先生が取り扱ってる島は西之島だけじゃなくて
ゲスト:んー、違います。
MC :もっといっぱいあって
ゲスト:いっぱいあります。
MC :そのうちの一つが噴いたってことですね。
ゲスト:そうです。そういうことです。
MC :あの西之島ってもともとは無人島ー
ゲスト:そうですね。
MC :ってことでよろしいんですよね。
ゲスト:え、無人島です、はい。
MC :で、去年の11月の下旬でしたっけ?
ゲスト:そうです。
MC :噴火した。
ゲスト:そうです。
MC :これ、テレビでも見ましたけれど、先生はその日どこにいらっしゃったんですか?
ゲスト:僕はですね、たまたま20日の日はあの観測所の方におりまして、
えー、海上保安庁の方から一報受けたんですね。
それで、あのーまあどういう状態なのかよくわからなかったんですが、
写真が送られてきて、もう確実に100パーセント噴火してると、
しかもそん時にはもう島が出来てたんですね。
MC :はい。
ゲスト:それで、これはあの大きなことになると思って、僕翌日の21日から同乗させてもらって、
えー、観測に、ま、行ってたんです。
MC :去年11月20日にそれを知り、11月21日に現場に行ってる?どうやって行くんですか?
ゲスト:えーとですね、まあ海上保安庁には特別な航空機がありましてー、
その航空機をま、使ってですね、えー写真を撮ったりですね、熱計測をしたりですね、
いろんな事が出来る飛行機なんですけども、その飛行機に乗って上空から観察をするんですね。
写真を撮ったりして。
MC :テレビで流れている映像や、あのー新聞で出てきた写真も
先生と一緒に行った飛行機から撮ったものですか?
ゲスト:えっと、そうですね。あん時は多分僕ー、達の撮った写真が使われたと思います。
MC :あー、そうですか。で、日に日に大きくなってー、
最後年末にはくっついちゃったじゃないですか、隣の島と。
ゲスト:えー、えー、えー。
MC :あれをじゃ日々観察をされていたわけですか?
ゲスト:まあ、そうですね。10日に一回ぐらいは乗って見てましたのでー、
えっともう21日の翌日22日にも飛んでますし、
そん時にはどういう風に変化してきたかっていうのはもう、
それを、最初の頃ってすごく変化が激しいのでー
MC :はい。
ゲスト:えー日々追っかける必要があるんですね。
MC :はい。
ゲスト:で、安定してくるとま、一週間に一回くらいでいいかなと思ってたんですけれども、
非常に変化が激しいので、ま、今に至るまでずっとこう観測を続けているわけですね。
MC :あーー。僕ら最近ちょっとニュースで見なくなりましたけれど、
まだちゃんと日々観測をしているわけですね。
ゲスト:そうです、そうです。
MC :島は大きくなってます?
ゲスト:非常に大きくなってますね。
MC :大きくなってる?
ゲスト:非常に大きくなってますね。
MC :僕らは記憶に新しいのは、モクモクと煙が出てるのと真っ赤なマグマ、
これが海とのアンバランスな映像が記憶に残ってますけど。
ゲスト:そうですねー、えー。
MC :あれ、何が起きたんですか?
ゲスト:結局ですね、まああの、この辺が非常によくわかってないところで、
西之島のその火山帯ってのは海の中にありますね。
MC :はい。
ゲスト:ですから、そのーいろんな観測機器を置くのを非常に難しいんですね。
例えば陸上の火山の場合は地震計を置いたり、GPSを置いたり、
えー傾斜計を置いたりですね、ま、いろんなことが出来るんですね。
ところが海の場合はですね、その装置を置く事がなかなか難しい、
じたい置くのが難しい、電源が取れない、で、データを取って送れないんですね。
非常に難しい事がたくさんあって、よくわかってない火山なんですね。
MC :今もですか。
ゲスト:海域火山ってのはよくわかってないんですね。
MC :かいき火山?
ゲスト:海のエリアにある火山の事を海域火山っていうんです。
MC :海域火山
ゲスト:で、そういうところにはデータが今でも欠測してるんです、少ないんです。
MC :そっか、あの群馬の白根山とかー、鹿児島県の桜島とかー、
そこは陸上にもうありますから、機械は設置できるんですね。海の火山ってのは観測難しい。
ゲスト:極めて難しいんです。
MC :どうやってやってるんですか。
ゲスト:ですから、我々は実はその飛行機の上から写真を撮るんですが、
ま、撮ったり目で見たりするんですけど、そん時にですね、海面にあのよく変色海水っていう、
よく言い方をしますね、海面が濁ったりするんですね、
色が変わって茶色くなったり白くなったりするんですけど。
そういう現象があります、で、その現象の、が、どれぐらいの大きさになってるかとか、
どういう色なのかっていうのを見るとですね、
MC :はい。
ゲスト:あの、活動度とかをほぼ推定できるんですね。
MC :じゃあ、結構そのアナログ的な目視によって、
ゲスト:まあ、アナログっていえば、アナログなんですけど。
MC :この、ちゃ、茶色いぞとか、マグマ出てるぞーとか、水蒸気出てるぞーとか、
ゲスト:まあ、あのマグマは出てきたりするともっといろんな事が起こるんですけど、
ま、初期段階としてはその海の色が濁る、で、色がどういう風に変わっていくか、
面積がどういう風に変わっていくかってことをちゃんとこう見ていかないと、
ま、わからないんですね。
MC :へぇー。あのー、今回この海底噴火っていうものが起きて新しく島が出来たっていう、
これとても珍しいことと考えてよろしいわけですか?
ゲスト:はい。極め、極めて珍しいことですね。
MC :あ、極めて珍しい?
ゲスト:極めて珍しい。で、わが国で3回目の事例なんですけど、
MC :えっ!3回しかないんですかー。
ゲスト:3回しかないですね。で、非常に、ま、戦前の話になりますけど、
えっと鹿児島県の沖に薩摩硫黄島って島があります。で、その東側の沖にですね、
えー、昭和硫黄島っていう島が、ま、小さい島なんですが。
MC :鹿児島県の沖ですねー。
ゲスト:え、
MC :地図で調べてねー、みんなー。
ゲスト:そういうところがあるんですが、そこに非常に小さい島があります。
MC :昭和硫黄島。
ゲスト:昭和硫黄島っていう島があります。で、そこはですね、
えー戦前にまあ噴火があってですねー、1934年から35年にかけてま、噴火があって、
MC :80年前だ。
ゲスト:そうですね。
MC :はい。
ゲスト:80年前ですね。
MC :はい。
ゲスト:で、そこでこう島ができたわけですね。で、そん時の、活動記録も実は残ってて、
非常に詳細なスケッチが残っていますね。昔の先生はすごかったですね。
で、その40年後にですね、今度は西之島
MC :あ、
ゲスト:が、噴火をしまして、今から40年前に西之島が噴火をして、で、
それは40年前の西之島の噴火っていうのは、有史以来初めての噴火で、
MC :はい。
ゲスト:で、そん時にはこういろんな事がまあ実は起こって、あのー、例えばですね、
噴火の場所がですね、点々と変わったとかですね、で、あのどんどん溶岩を出していくんですけど、
あの今回の噴火とはちょっと違うタイプのような噴火が起こって、
でまあ噴火が止まった後にですね、島がくっついたんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:で、約20年かけて島の形が変わっていって現在の形になったんです。
MC :へぇー。
ゲスト:で、その後、それから40年経って、ま、突然また噴火を始めて
MC :はい。
ゲスト:で、現在に至る。
MC :すごい、すごいけれど、東京都の西之島っていうところ、集中してませんか。
ゲスト:実は、日本で一番火山が多いのは東京都
MC :えーーっ、えーーっ!
ゲスト:これ以外なんですけど、東京都なんですね。で、なぜかというと小笠原まで全部東京都ですから、
MC :47都道府県で一番火山が多いのは東京都。
ゲスト:東京都です。
MC :ちょっと待ってください。時間になりましたねー。このお話また来週聞かせて下さい。
今週のサイコーは東京工業大学教授の野上健治先生でした。有難うございました。 -
8月19日イベントレポート②
2017/09/26 Tue 10:00 カテゴリ:イベント
今回の「ネクストサイエンスジャム」でも
文部科学省より指定を受けたスーパーサイエンスハイスクールのみなさんが大活躍!
今回は京都市立堀川高等学校のみなさんが会場の子どもたちに
「生物の進化」というテーマの発表を行いました。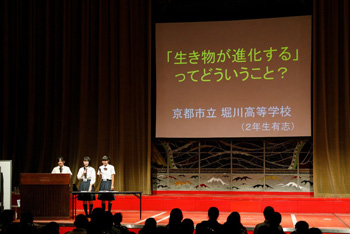
3人のリケジョが高校生とは思えないくらい深く、
そしてユニークな視点でのプレゼンに会場の子どもたちは
目を輝かせながら見ていました。
『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
子どもたちから寄せられた質問に科学ジャーナリストの寺門和夫さんが
回答してくれました。子どもたちから寄せられた、
宇宙における永遠の謎、ブラックホールに関する質問では
難しいブラックホールの仕組みを角砂糖を例に解説してくださいました。
今回はここまで。
現在次の企画が進んでいます。詳細が決まったらこのホームページでお知らせしますので
楽しみにしていてください! -
8月19日イベントレポート①
2017/09/26 Tue 10:00 カテゴリ:イベント子どもたちの「科学する心を育む」プロジェクトとして、
日立ハイテクノロジーズと文化放送、KBS京都が協力して、
科学実験とラジオ公開録音が一体になったベント
「ネクストサイエンスジャム」
3月の東京に続いて、2回目となる今回は京都のKBSホールで開催されました。
ここではそのイベントの様子を少しだけご紹介します!今回はイベントゲストとして俳優でタレントの照英さんをゲストにお迎えしました!
照英さんが登場した時に言ったサイエンスな?挨拶に会場も大盛り上がりでした。
続いてイベント目玉の一つ。ネクストサイエンストークショー。
テーマはDNA。今回はその中でも今後の医療に大きな変化をもたらすかもしれない、
『iPS細胞』について教えてもらいました。
ゲストは京都大学iPS細胞研究所の副所長で
教授の江藤浩之さん。最初はDNAとは何なのかについて家やビルなどの設計図を例に解説してくださいました。
「一般的に10~14歳の時に細胞が活動的に増えていく」という話の時には
会場の子どもたちは大喜び!一方大人達はなんとも言えないリアクションでした。
次にiPS細胞とは何か?について。
百科事典を例にiPS細胞について解説して頂いたり、
江藤さんが今研究されていることについてもお話しくださいました。会場の子どもたちから出た、「動物の遺伝子組み換えをしたら、空を飛べる馬ができるのか?」などの
ユニークな質問にも丁寧に答えてくださいました。最後に江藤さんから出た「自分で好きなことを見付けて、それを邁進してください。
そして失敗しても諦めないことです。」という言葉が印象的でした。
-
「2014FIFAワールドカップの科学 パート2」 ゲスト:柄川昭彦さん
2017/09/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他MC :さぁ今週のサイコーもですね、前回に続きましてライターの柄川昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。よろしくお願いします。
MC :えー、ブラジル明日ですよ。ワールドカップ。
ゲスト:そうですね、いよいよですね。
MC :コートジボワール戦。どうしますか?
ゲスト:あれですよね、他のギリシャとコロンビアがとっても、なんか世界ランクなんかでも上の方ですから
MC :ギリシャが10位?コロンビアが5位?コートジボワール21位です。
ゲスト:21位です?と、ここで勝っておきたいってのは
MC :もちろんですよ。
ゲスト:ですよね。
MC :4年前は初戦、カメルーンに勝ってるんですよ。
ゲスト:勝ってますね。
MC :アフリカにはね、分が良いんですよ、日本は。
ゲスト:その時と同じですね。アフリカ勢と初戦だから。
MC :そうです。
ゲスト:ここで勝ちたい。
MC :はい。
ゲスト:勝ってほしいですね。
MC :そうなんですよね。であとは、現地のやっぱり気温なども含めて、
まぁ日本の選手からするとどうかという事なんですけどね。
ゲスト:えぇ、えぇ。
MC :初戦、さぁブラジルなんですけど赤道の通る国であり、えー、
初戦の海沿いのレシフェという町で戦いますけども。
ゲスト:はい、レシフェですね。ちょっと調べてみたら、あのー、あれですね、
気温が最高気温でもう30度前後になりますし、あのー、最低気温も高いんですね。
ですから、涼しい時間帯を狙ってもかなり気温は高いと。
あと、レシフェの6月は1年間で1番雨が多い季節で、てことは湿度がかなり高いんですね。
MC :ほぉほぉほぉ。日本とじゃあ、似たような状況?
ゲスト:そうですね、高温多湿の日本の夏に近いような状態と考えればいんじゃないでしょうかね。
ただ赤道直下ですから、まぁどのくらいの暑さなのかは、あれですよね。
MC :うーん、どうだろう。コートジボワールも暑さに強いと思いますけどね。アフリカなので。
ゲスト:そうですね、でもあちらはちょっと空気乾燥してそうですね。
MC :あー、そっか。そうだ。向こうはね、アフリカはカラッとしてますからね。
ゲスト:高い湿度ってのは、なんか日本人の方が対応能力ありそうな感じがしますね。
MC :そうですねー。そっか、湿気が多いとね、よくあの選手なんか、
ボールがスパイク?フリーキックなんかの時に馴染みやすいとか、
カーブかかりやすいとかよくそう言いますけれど、湿度高いとその辺有利じゃないですか?
ゲスト:どうなんでしょうね。あのー、細かく言うとそうかもしれませんけども、
ただボールというのもですね、以前は、えー、革だったんですけれども、今は合成皮革を使っててですね、
水分を吸わないんですね。だから雨が降っても、あのなんか濡れても重さが変わらない様に
そうしてあるわけですけども、ですからあのー、革の時代はね、湿度なんかでずいぶん違ったと
思いますけども、今はそんなには変わらない。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :確かに今のボールね、つるんとしてますから、そっか、あれは合成皮革なんですね?
ゲスト:そうなんですね。ですから
MC :どんな条件でも、まぁ同じという
ゲスト:同じ、大体同じになると。あのー、水を吸って重くなったりはしないそうですね。
MC :へー、そっか。まぁ日本はセットプレーからの得点というのがですね、武器だと思うんですけれど、
思い起こしてみると、去年、4年前か6月の第3戦?
ゲスト:はい、第3戦ですね。
MC :デンマーク戦、本田選手のフリーキック、あれが印象に残ってますよ。
ゲスト:そうですね、すごく変化しましたしね。
MC :無回転ボールと言われて、こうブレるようにしてストンとゴールに吸い込まれていく。
あれはどういうボールなんですか?
ゲスト:はい、あのー、普通のインステップキックという蹴り方で普通にシュートを打つと、
あのー、ボールにはバックスピンが掛かるんですね。バックスピンが掛かって、飛んでいくと。
そうすると少しボールがですね、こう浮き上がるような、伸びてくるような感じの飛び方をするんです。
MC :バックスピンね。ゴルフと同じですね。
ゲスト:ゴルフと同じですね。そうすると、あの、シュートの蹴ったボールは、
そういう軌道を描くものだという風にみんな認識しているわけですね。ゴールキーパーも。
ところが無回転で蹴りますと、そのスピンが無いので、あのー、
そのスピンをかけた普通のシュートに比べると落ちて見えるんですね。
それが、あの野球のですね、まぁフォークボールですが、最近はスピードフィンガーボールって
言いますけれど。は、回転、スピンがですね、バックスピンがちょっと緩やかなんですね。
ですからやっぱり落ちると。ナックルなんかは、野球のナックルは、ほとんど回転しないので
もっと落ちるというような感じの無回転系の変化球なんですね。
MC :はい。
ゲスト:それがサッカーでも行われている。サッカーの場合もっとすごいのは、速いってことですよね。
MC :はい。
ゲスト:はい、野球の変化球はどうしてもスピードが落ちちゃいますけども、サッカーのは速くて、
無回転で飛んでくるので、えー、中々取れないと。それに加えて、その4年前の、あのー、
ワールドカップで使われたボールにも影響、あの関係してるんですね。
MC :あ、今回とボール違いますよね?前回ジャブラニというボール。
ゲスト:ジャブラニという。昔のサッカーボールというのは、そのー、5角形が12枚と6角形が20枚。
こう32枚のパネルを組み合わせた、まぁいわゆるサッカーボールのあの形になってるんですけども、
えーっと2002年からあのー、正確な球にするためにもうちょっと考えられたあのー、曲線を活かした、
あー、パネルを組み合わせるボールになってるんですね。
MC :あ、そうなんですか。あー。
ゲスト:で、前回のジャブラニはえっと、8枚のパネルを、あのー、組み合わせて
まぁボールの球にしてあるんですけども
MC :はい、瓢箪みたいな形のね?
ゲスト:あのー、そうですね。
MC :あのあれが、あれ8枚?
ゲスト:8枚だけ
MC :8枚だけで出来てたんですか?
ゲスト:そうですね。
MC :へー。
ゲスト:で、今度の、えー、ブラズーカっていうボールは6枚なんですね。
MC :あ、ブラズーカ?今回使われるボールは6枚で丸、つくってるんですか?
ゲスト:6枚も。あのー、野球なんかは2枚ですよね。
MC :あ、たしかに。あ、そうだ。野球のプロ野球の公式ボールは瓢箪みたいな形2枚で。
そっかー、丸を作ってる。
ゲスト:そうやって、なんかいろんな形を組み合わせて、まぁ球の形にするわけですけども、あのー、
その4年前のボールはですね、えっと縫い目が、あのー、縫い目の溝がですね、あのーなんていうのかな、
正面から見た時に、どちらか片側に偏りがちだったんですね。
MC :へー。
ゲスト:あの、32枚のパネルで作ったボールというのは、正面から見るとその縫い目がまぁ、
右にも左にも上にも下にも全体的に均等に散らばりますね。ところがあのー、
パネルの数が少なくなっちゃったんで、その縫い目がですね、例えば右側にこう寄っちゃったり、
左側に寄ったりすることによって、えーっと右に曲がったり左に曲がったり、あるいは上に浮いたり、
沈んだりっていうあのー、予測できない予測不能の変化をするようになっちゃったんですね。
4年前のボールは。
MC :変な話、いびつな形だったんですか?
ゲスト:いびつというか、その例えば野球のボールもですね、あのー、
たった2枚ですからこう正面から見た時にですね、白い部分ですね、
縫い目のない白い部分が多い方と、縫い目がこう重なって見える部分てのがあります、
出来ちゃいますよね?
MC :はい、はい。
ゲスト:均等には中々ならない。それと同じように、枚数が少ないので中々均等にならないんですね。
ですから、あのー、4年前のジャブラニは、こう揺れる、あの不規則に揺れるシュートってのが
たくさん出て、それがまぁ、本田選手が蹴ったのもそうだったわけですよね。
すごい、もうほんとに考えられないような変化をして、シュート決まってしまうと。
MC :今回はでも6枚になったってことは、よりそうなるってことですか?
ゲスト:ところがですね、やっぱり4年前にあれだけ変化しちゃったので、
やっぱりちょっとまずいと思ったんじゃないかと思いますけれどもあのー、
枚数は6枚という風に減ってるんですけども、1枚1枚がですね、非常にこう複雑な形の1枚なんですね。
MC :へー。
ゲスト:ですから、それを6枚組み合わせたその縫い目の長さはですね、4年前のジャブラニよりも、
測ったわけではないですけども、ひと目だけでもそうとう長いなって感じがするんですよ。
MC :おー。
ゲスト:で、ボールを正面から見た時に、まぁどっち向きにしてもですね、大体こう縫い目が多いですから、
縫い目がバラバラと均等に散らばると。ですから、あのー、4年前のようなですね、
あの大きく揺れるようなシュートってのは今回は出ないんじゃないかって言われてるんですね。
MC :いやー。しかしみんな世の中お祭りで明日行くぞーっていってんのに、
こんな科学的に語り合ってる番組って僕らだけでしょうね。
ゲスト:そうですね。
MC :はいー
ゲスト:どうもありがとうございます。
MC :いやー、いやいや。よっし、後はもう明日を待つだけですね。いやー、もう時間ですね。
ありがとうございました。えー、今週のサイコーはライターの柄川昭彦さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「2014FIFAワールドカップの科学 パート1」 ゲスト:柄川昭彦さん
2017/09/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他MC :さぁ今週のサイコーは、ライターの柄川昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :柄川さんは主にスポーツと医療の分野で、文章を書かれてらっしゃる、
いわゆるライターの方なんですけれど、えー、今年のソチでの冬季オリンピックが始まる前にも
来ていただきました。あとロンドンオリンピックの際もですね、お世話になったんですけれど、
やっぱり4年に1度のオリンピックと双璧、それ以上と言われているのが来ましたねー。
ゲスト:サッカーの。
MC :サッカー、ワールドカップ。
ゲスト:はい。
MC :4年に1度。
ゲスト:いよいよですね。
MC :はい。柄川さんはオリンピックとワールドカップはどちらが?
ゲスト:まぁどちらが?ってこともない、どちらも楽しんでますね。
MC :あー、そうですか。僕はワールドカップ派なんですよ。
ゲスト:はははっ、ワールドカップなんですか?
MC :僕は4年前、南アフリカに臨場したんですけれど
ゲスト:は、すごいですねー。
MC :今回は、行けない。もー、切ない。でも携わりたいっ。という事で、語りましょう、一緒に。
ゲスト:そうですよね、今回は遠いですよね?地球の裏側ですから。
MC :そうです。みんな、地球儀用意して見てー。ブラジル、日本の真裏ですね。
南アメリカで、えー、ブラジルの地図、一番北側は赤道が走っていますね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :赤道のそれからずっと南側にひろーい国土があって、日本の20数倍だって。相当広いんですね。
ゲスト:広いですねー。あのー、南アメリカ大陸のね、かなりの部分を占めてます。
MC :ですよねー。子どもの頃ね、庭を掘ってくとアルゼンチンかブラジルにたどり着くなんて言われたけれど、
それぐらい日本の真裏ですよね?
ゲスト:えぇ、そうですね。真裏ですね。ちょうど、南半球になりますから、
北半球にある日本のちょうど真裏って感じですね。
MC :さぁ、そこでわれらが日本代表は、ワールドカップを戦うんですよ、日の丸背負って。
ゲスト:そうですね。
MC :あのね、僕、いつも思うんですけど、まぁヨーロッパでプレイしている選手も大勢いますし、
Jリーグでプレイしている選手もいますけれど、いずれにしても南アメリカでプレイしている選手って
一人もいないんですよ。
ゲスト:あー、そうですね。日本人の人、今、いないですね。
MC :そう。となると、時差の調整とか、いわゆる彼らの日常習慣とは違う時間帯に
最高のパフォーマンスをしなくちゃいけないんですよね。
ゲスト:そうですね。一番、何もしてない時に一番の最高のプレイをしなくちゃいけないと。
MC :来週のコートジボアール戦は、夜の10時?向こうで。ということは日本の朝の10時ということは、
その日本の朝の10時にフル回転で身体を動かすっていう事をしなくちゃいけない。
ゲスト:そうですね、はい。それに合わせて体調をつくっていかなくちゃいけないという事ですね。
MC :時差調整っていうのは、どういうメカニズムなんですか?
ゲスト:はい、あのー、丁度地球の裏側になりますから、どちらを周っていくかっていうのは
2通り考えられると思うんですね。
MC :西と東?
ゲスト:西周りにいくか、東周りでいくかっていう。
MC :え、どっちでもいいんじゃないですか?
ゲスト:なんか大航海時代みたいな話ですけどもね。で、東周りで行きますと、
地球は、えーっと東から西へまわってますから、えっと地球と反対向きに飛ぶことになるので、
短い夜を過ぎて、朝になっちゃうんですね。
MC :あ、確かに。
ゲスト:はい。で、えーっと、西周りで行きますと、地球と同じ方向に飛行機が飛ぶことになりますから
夜が中々終わらないと。目が覚めちゃったんだけど、まだ夜っていう状態が続いて、朝になる、
到着という感じですね。ですからあのー、東周りで行くと、えーっと、丁度昼間が眠く、
まだ本来だったら夜が続いてるはずなのに朝になっちゃうので、まだ眠いなっていう感じがしますし、
夜になってさぁ寝ようと思ってもちょうど眠れないっていう時間帯になっちゃって
MC :東周りで行くと?
ゲスト:そう、そうですね。これ中々、体調を整えるのが難しいんですけど、
あのー、西周りで行くとちょっと眠いのを我慢して活動してる、えーっと、
日本に居て夜更かししてるのと同じような事ですね。
MC :なるほどね。
ゲスト:すると、また時間が合ってくると言われてます。
MC :調べてないけど、なんか東周りな気がするな。
ゲスト:そうですね。
MC :ヨーロッパ経由で行けば
ゲスト:まず、アメリカに行きますよね、きっと。
MC :そうですよね。さぁさぁ、そうなってくると、あのー、選手たちのやっぱり、
運動能力というかパフォーマンスにも影響されると思うんですけれど、やっぱりサッカー選手、
まぁ、ゴールキーパーしかり、フォワードの選手しかり、パスを送り出す選手しかり、
瞬時の対応っていうのは、もーのすごく大事になってきますよね?
ゲスト:そうですね、サッカーのプレイを見てると、こう、最高のプレイっていうのは結構、
何にも考えずにやってる様なパスとかですね、あのー、ダイレクトでパスを送ったのがすごくいいところに
行くとか、ど、ど、何を元に判断したのか分からないけども、えっとパスをスルーしたら丁度そこに選手が
走り込んでるとかですね、なんかもう信じられないようなプレイが続出しますよね。
それが、まぁサッカー見ている楽しみでもありますけども。
MC :素人的には、なんかこのー、偶然が重なってと思われがちだけれど、
選手たちはしっかり考えて瞬時に判断してるわけですね。
ゲスト:えぇ、そうですね。でも、その考えてるていうのはですね、えーっと、
そのサッカーのグラウンドを上から見て、ここに香川選手がいるからこっちにパスを送ろうとか、
あー、内田選手が上がってきたからあそこにパスを送ろうとかっていう考えとは、だいぶ違っててですね、
そういうえっと、状況を判断して、えー、考えるという判断ですね、
これはえっと、大脳の新皮質という所で行っているんですね。
MC :大脳の中の、新皮質?
ゲスト:新皮質、一番外側の部分ですね。
MC :外側?
ゲスト:はい。
MC :頭蓋骨のちょっと内側ですか?
ゲスト:そういう事です、そういう事です。
MC :そこに新皮質って所があるんですか?
ゲスト:はい。
MC :どういう字を書くんですか?
ゲスト:新しい、皮の、質、ですね、質。
MC :新しい、皮、質、はい。
ゲスト:で、脳っていうのは、あのー、元々ですね、あのー、下等動物にもあるのは一番内側にある、
下にある脳幹ていう部分ですね。
MC :中枢ですね、脳幹。
ゲスト:はい。これがもう生きていくのに必要な脳で、あのー、それにちょっとこう進化してですね、
爬虫類ぐらいまでなると、えーっと大脳基底核って部分がそのちょっと上にできるんですね。
ここに、あのね、線条体っていう部分があって、あのー、ですからかなり、えーっと、
本能的な行動を司ってるんですね。その、奥の方にあるのは。
MC :脳のイメージね。真ん中の脳幹、他に線条体?大脳
ゲスト:脳幹、それから大脳基底核っていう部分があって、その上に大脳辺縁系ていうのが乗ってきてですね、
これが鳥類とか下等な哺乳類、モグラとかですね、その上に大脳新皮質っていうのが
MC :人間は、大脳新皮質まであるんですね?
ゲスト:いわゆる物を考えるっていうのは、その一番外側でやってるんですね。でもその線条体っていうのは、
ずいぶん下の方、奥の方にあってですね、あのー、ですからトカゲとか亀とかワニとかも、
持ってるんですね。ですから、かなり本能的にこれはこういう行動した方が、
自分にとって良いっていうのを、あのー、考えているんじゃなくてその脳の、
えー、線条体って部分がですね、判断して行動させてるんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:えぇ、ですから元々は自分の命を守るためとかですね、獲物を捕るための、こうすれば良いっていう、
考えずに反応する行動を司ってるわけですね。
MC :はい。
ゲスト:でもあのー、それがそのサッカーのですね、ゴール前の、あの際どいとこで自分の体を
どう動かせばいいのかっていうのを、とっさに頭で考えてるんじゃなくて、
その線条体って部分が反応して、えー、シュートを打ったりパスを送ったり、っていう事が出来ると。
で、それが凄く速いんですね。
MC :大脳の内側の、速いんですね?
ゲスト:線条体っていう部分が
MC :野性的なものですね?
ゲスト:そうですね、すごく速いんですね。あのー、大脳新皮質を使うと、やっぱり色々考えるわけですね。
あそこから香川が来て、あそこにスペースが空いていて、あそこに行くだろうから、ここに送ろうとか。
それは考えているととても間に合わないんで、その線条体という部分を使って身体がどんどん動いていくと。
MC :へぇー。今のなんか、人体標本図でね、大脳っていうとざっくりと、ウネウネしたあの脳みそありますけど、
あの中でも内側と外側では機能が違うんですね。
ゲスト:だいぶ違う、違うんですね。はい。
MC :サッカー選手は、内側のどちらかというと動物的な、トカゲとか蛇とか、
そういう所の線条体みたいなものの働きで、瞬時の判断していると。
ゲスト:そうですね。ですから、サッカーですとかラグビーとか、そういう止まらないスポーツっていうのは、
線条体の部分が必要なんですね。
MC :ふーん。
ゲスト:その点、野球ですとかアメリカンフットみたいに1回1回止まって、監督がこうサインを出したりする。
これは大脳新皮質でやってるわけね。
MC :あ、外側の?
ゲスト:だから、アメリカ人が好きなスポーツは、意外と大脳新皮質系で、
イギリス人が好きなスポーツは、あれですね、線条体っていう感じがする。
MC :なるほどー。いや、えっ、もうおしまいですか?やっぱり、ちょっとサッカーの話、ダメですね。
すぐ終わっちゃいますね。ちょっと柄川さんには、来週、またもっとブラジル、
あっ、来週もうちょっとコートジボアール戦の前日だー。また来週よろしくお願いします。
ゲスト:はい、こちらこそよろしくお願いします。
MC :今週のサイコーは、ライターの江川昭彦さんでした。 -
「すき間の植物 パート2」 ゲスト:塚谷裕一さん
2017/08/01 Tue 12:00 カテゴリ:植物MC :さあ、今週の「サイコー」も前回に続きまして、東京大学大学院教授の塚谷裕一先生です。
こんばんは。お願いしまーす。
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、スキマの植物というお話で、先週とても興味深いお話を伺ったんですけれど、
えー、節分を過ぎて、暦の上では春ということですね。
ゲスト:はい。
MC :この春、この時期に是非とも、スキマ植物、も、
キッズ達にチェックしといてもらいたいというのがありましたら、是非、お願いいたします。
ゲスト:あ、そうですね、えっと、今、ちょうど冬から春になろうというところなので、
MC :はい。
ゲスト:続けて観察してたら楽しいだろうなっていうのが、ロゼットを作る植物っていうのがあるんですね。
MC :ロ、ロゼットじいさんですか?
ゲスト:いや、違います。
MC :えっ。
ゲスト:それ、別の、あれですね。
MC :ロゼット。
ゲスト:はい。
MC :ロゼット。
ゲスト:ロゼットというのはね、あれなんです、あの、タンポポを想像してもらうといいんですけれども、
MC :タンポポ。
ゲスト:えーと、地面に葉っぱをペターって並べてる植物で、
MC :はい。
ゲスト:葉っぱがしかもこう、なんていうんですかね、あの、周りに丸、円を描くように葉っぱを並べてるやつ。
MC :はい。
ゲスト:で、葉っぱが上に立ってなくって、ほとんど地面にペッタンコ。
MC :平べったい。
ゲスト:はい。
MC :踏んづけても、タフな感じがしますよね。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :はい。
ゲスト:はい。
MC :それをロゼット。
ゲスト:そういうのをロゼット、そういうのをロゼットっていうんです。
MC :ロゼット。
ゲスト:そういうのを作る植物が、
MC :ロケットでもなくてロゼット。
ゲスト:そうです。
MC :覚えました。
ゲスト:はい。
MC :横に広がってるロゼット。
ゲスト:打ち上げないです。
MC :はい。
ゲスト:えっと、ロゼット型の植物は、あの、なんでそんな恰好してるかっていうと、
ま、冬の間寒いじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:で、寒いのにあの、茎立ててたりしたらもう、ね、風が吹いて寒いので
MC :そうだ。
ゲスト:ま、冬の間地面スレスレでペッタンコにして、
MC :はい。
ゲスト:日を浴びて、まあ、まあ、とにかくちょっと暖かくして、待ってると、
MC :ええ。
ゲスト:いう状態なんです。で、そういった植物、今ちょうど見ごろなんですが、
MC :その代表格は?
ゲスト:タンポポもそうだし、
MC :あ、も、タンポポ、
ゲスト:はい。ノゲシの、ノゲシの仲間もそうだし
MC :ノゲシの、ノゲシ
ゲスト:はい。
MC :ほー。
ゲスト:あのー
MC :タンポポ、ノゲシ。
ゲスト:はい。そういったやつはですね、もうちょっとすると、
そのロゼットを作ってる丸く葉っぱが並んでる真ん中から、なんかモゾモゾし始めてですね、
MC :おー。
ゲスト:茎が立ったり、まあ、つぼみがあったりしてくる。で、葉っぱだけだと、
な、やっぱり、なかなか何の種類だか、慣れないと分かりにくいんですよ。
MC :あ、はい。
ゲスト:だから、なんかいるな、と思うんですけども
MC :はい。
ゲスト:えー、まあ、その時の葉っぱの特徴覚えといてもらって
MC :うん。
ゲスト:で、それから、もうちょっと待ってもらうと、花が咲きだすと図鑑で何だかわかると思うので、
MC :ロゼットは冬の間、
ゲスト:うーん。
MC :花が咲かない段階では、
ゲスト:葉っぱばっかりしかないと
MC :分からないんですね。
ゲスト:分かりにくいですね。
MC :何が生まれるか分からない。
ゲスト:うん。それをだから、覚えといて、
MC :ええ。
ゲスト:まあ、日が経ってですね、段々暖かくなるにつれて、何か出て来るはずなんで、
それを見てもらうと、例えば、
MC :すごーい。
ゲスト:えーっと、タンポポだったら、
MC :うーん。
ゲスト:みなさんよく知ってる、黄色い花が咲きますし、
MC :はい。
ゲスト:花が直接こう、出てきますし、ノゲシだと一旦茎がヒューって伸びてくると思うんですね。
MC :はい。
ゲスト:それから、例えばナズナなんかもロゼット作りますけども、ナズナだったら、
その真ん中からやっぱ、茎が伸びてくんだけど、そっから白い小っちゃい花が咲いて、
MC :ほー。
ゲスト:で、その花が、実になる時、実が三角形してる。ので、もうナズナだって分かるって感じで、
ま、花が咲くまではですね、何かまあ、似たような葉っぱが、こう、丸く並んでるだけで
MC :へー。
ゲスト:よく似てますけど、それなりに特徴はある。だからそれを
MC :タンポポ、ノゲシ、
ゲスト:見ておいて、
MC :ナズナ、
ゲスト:はい。
MC :でもこれは、葉っぱの形はほぼ同じ。
ゲスト:まあ、同じとは言わないけど
MC :うん。
ゲスト:見慣れてないと、見分けがつかない。
MC :見分けつかない。
ゲスト:うん。
MC :で、これからのシーズン、
ゲスト:そう、そう。
MC :何が咲くかによって
ゲスト:うん。
MC :答え合わせができる
ゲスト:そう、そう。
MC :ということですね。
ゲスト:そう、葉っぱで、たぶんこれかなってアタリつけといて、
MC :ええ。
ゲスト:ま、花が咲いたら、
MC :えー。
ゲスト:答えが分かると。
MC :なんか、タンポポは
ゲスト:はい。
MC :その辺にありそうですけど
ゲスト:はい。
MC :ノゲシ、ナズナも結構
ゲスト:あります、あります。
MC :あちこちに?
ゲスト:はい。
MC :大丈夫ですか。
ゲスト:はい。例えば
MC :ああー。
ゲスト:もう、都心のほんと真ん中のビル街なんかでも
MC :ええ。
ゲスト:結構あります。
MC :あ、そうですか。
ゲスト:はい。
MC :いや、ちょっと早速じゃあ、平べったい、まだ花の咲いてないロゼット型の植物、
みなさん是非チェックしてみて下さいね。いやー、その他このシーズンに見とくべき、
植物、スキマ植物は何かあります?
ゲスト:ま、冬の間ですので、まあ、冬らしいものとしてですね、変わった物としては、
MC :はい。
ゲスト:えっと、草ばっかりが隙間に入るわけじゃなくって
MC :はい。
ゲスト:木が生えてくることもあって、
MC :はあー。
ゲスト:で、冬、あの、鳥が好きな赤い実つけるような植物も、時々、そ、見られるんですよ。
例えば南天みたいなやつ
MC :南天
ゲスト:はい。
MC :はい。赤い
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:あれ、鳥が赤い実好きなもんだから
MC :はい。
ゲスト:食べるんですよね。
MC :あっ、へ、鳥、鳥が、何、ま、南天て
ゲスト:はい。
MC :あのー、赤い実のつく
ゲスト:はい。
MC :花?
ゲスト:はい、はい、実ですね。
MC :実、
ゲスト:うん、うん。
MC :なんか、ナナカマドみたいな感じの
ゲスト:ああ、ナナカマド
MC :はい。
ゲスト:を立てたみたいな
MC :はい。
ゲスト:感じですね。
MC :で、この
ゲスト:うん、うん。
MC :鳥は、赤いから
ゲスト:うん。
MC :目立つから、それを狙って
ゲスト:食べる。
MC :食べるんですかね。
ゲスト:はい。
MC :南天のもし、
ゲスト:うん。
MC :実がね、あの、緑だったら鳥は狙わないんですかね。
ゲスト:狙わないですね。
MC :あ、赤いから?
ゲスト:はい、はい。鳥ね赤いのが好きなんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、実も、実も赤いのが好きだし
MC :ふーん。
ゲスト:あの、今からちょっ、もうちょっとすると椿が花のシーズン迎えますけど
MC :ええ。
ゲスト:あれ、赤いじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:であれ、鳥がよく蜜吸いに来るんですけど
MC :ほー。
ゲスト:あれも赤いから好きで、来るんですよね。
MC :へー。目立つから、
ゲスト:うん。
MC :鳥の目にも
ゲスト:うん。
MC :止まりやすいってことですか?
ゲスト:うん。鳥赤いのすごく好きなんですね。
MC :へー。で、南天からしても、
ゲスト:はい。
MC :その赤いまんま維持してるから、
ゲスト:うん。
MC :先週の話じゃないけれど
ゲスト:うん。
MC :南天が別の所で、スキマ植物として生き残るためには、
ゲスト:うん。
MC :鳥によってね
ゲスト:うん。
MC :種運んでもらいたいとかあるんですかね。
ゲスト:それはそうですね、あの、隙間とは限らないけど
MC :うん。
ゲスト:どっか遠くに行きたいっていうわけですよね。
MC :あ、じゃもう、その植物が赤いのは訳があって
ゲスト:うん。
MC :どうぞ鳥さん、僕を食べてねって言って、
ゲスト:うん。
MC :その代り遠くに運んで、遠くで子孫の繁栄したいよってメッセージがあるってことですか。
ゲスト:そうです。で、鳥は食べた後、ま、糞の形で、種あちこちに
MC :はい。
ゲスト:ばら撒きますから、
MC :へー。
ゲスト:その糞が落ちた場所が、たまたま隙間だったら、そこで、ま、生えてくると。
MC :いやー、南天ありがとう。鳥の胃も満たされて、南天も全国各地に子孫の繁栄ができるということですね。
ゲスト:そうです。はい。
MC :お互いWin-Winな関係で、
ゲスト:そう、そう、そう、そう。
MC :へ、えっ、この南天は、木なんだけれど、先生のね、「スキマの植物図鑑」を見ると、
コンクリートの割れ目から、木がニョキニョキニョキって生えてる写真がある。
ゲスト:はい。
MC :これは、ちなみに何処で撮影されたんですか?
ゲスト:これはね、愛知県ですね。
MC :愛知県で?
ゲスト:はい。
MC :東京にもそういう
ゲスト:あります、あります。
MC :ある。
ゲスト:はい。
MC :いやー、この木が生えるというのは、もう、非常にタフな感じがしますけれど、
ゲスト:はい。
MC :長い年月かけて、
ゲスト:うん。
MC :コンクリートを
ゲスト:うん。隙間をうまく
MC :うほほ。
ゲスト:そうですね。
MC :いやー、すご、これコンクリートはすごいですね。だって、アスファルトより硬いものですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :う、でも、そのコンクリートも、破ってしまうぐらいの
ゲスト:はい。
MC :南天のパワー。
ゲスト:うん。
MC :ふーん。
ゲスト:根の力ですよね。
MC :根っこの力。
ゲスト:うん。
MC :へえー、え、これも、じゃ探せばあるんですね。
ゲスト:はい。
MC :植物だけじゃなくて、木もスキマ植物、あるよっていう
ゲスト:はい。そうですね。
MC :葉っぱじゃなくて、木もあるってことですね。
ゲスト:木もありますね。
MC :へえー、今ラジオ聞いた後、表に出て、探したい、くなる子いっぱいいると思うんですよね。
ゲスト:はい、はい。
MC :先生、でも、これ研究ずっとされて、東大で教えてらっしゃる訳ですよね。
ゲスト:いや、これはあの、えっと仕事とは違って
MC :あ、
ゲスト:やっぱり趣味なので
MC :これ、趣味。
ゲスト:はい。
MC :東大の学生さんが、隙間の話を聞いてるんじゃなくて、
ゲスト:そうですね。
MC :これは、これは先生のライフワークみたいなものなんですね。
ゲスト:まあ、遊びですね。
MC :えっ、
ゲスト:はい。
MC :先生のこの、遊びの、とう、到達地点てのは、最終的にはどこが目標なんですか。
ゲスト:いや、まあ、特別目標はないんですけども
MC :はい。
ゲスト:やっぱり、歩けば歩くほど、
MC :はい。
ゲスト:変なもん、というか新しいもん、やっぱり出てくるんですね。
MC :はい。
ゲスト:まあ、今回この「スキマの植物図鑑」て一旦まとめましたけども
MC :はい。
ゲスト:実は今、続編を作ってるくらいで、
MC :はい。
ゲスト:あの、まだまだいっぱい種類が見つかるんですよ。
MC :だって、無限だと思いますよ。これは、
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:はい。
MC :だって多分、植物の種類は一通り、ご紹介するかもしれませんけど、今度そのシチュエーションですね。
ゲスト:シチュエーションです、はい。
MC :そう。だから生えてる、その
ゲスト:そう。
MC :こんなところで生えてるっていったら
ゲスト:はい。
MC :最高ですよね。
ゲスト:そうです。こんな変なとこにまで、これるのかって
MC :ええ。
ゲスト:いうところですよね。
MC :えっ、今までの中で、先生の、も、ビックリポイントってどういう所から生えてるものがありました。
ゲスト:やっぱり、あの、普通は隙間って乾いてる感じがするので、
MC :はい。
ゲスト:あんまり地面から離れると生えられないイメージがあるじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:でも、意外に何かの条件、たまたまうまく偶然あって
MC :うん。
ゲスト:あー、こんな高いとこまでいるとか、こんな変な隙間に生えてるとかですね、
MC :うん。
ゲスト:そんなんいますよね。
MC :いやー、でも僕も何か、すごく町歩きが楽しくな、楽しみになりましたこれで。
ゲスト:はい。是非色々探してみて下さい。
MC :うーん、そうか。えー、東京大学大学院教授の塚谷裕一先生でした。どうもありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございました。 -
「すき間の植物 パート1」 ゲスト:塚谷裕一さん
2017/08/01 Tue 12:00 カテゴリ:植物MC :今週の「サイコー」は、東京大学大学院教授の塚谷裕一さんです。こんばんは。
ゲスト:こんばんは。
MC :えー、塚谷さんは、えー、1964年神奈川県のお生まれで、専門は、葉っぱの発生・分子遺伝学。
葉っぱ、葉っぱに詳しいんですね。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :はい。
ゲスト:はい。葉っぱなどですね。
MC :はい。中公新書から「スキマの植物図鑑」といった本を出版されてるんですが、
この本は、今僕の手元にあるんですが、いわゆる、あの、掃除当番の人がですね、
この、校舎の下あたりから生えてるね、草、摘み取っちゃいそうな、ま、
そういう草花を写真に収めて本にしてるっていう、こういう感じですかね。
ゲスト:まあ、そういうのも。
MC :あははは。
ゲスト:含まれてますね。はい。
MC :スキマの植物、だから、皆の周りにも隙間の植物って、いっぱいあると思うんだよね。
あの、マンションの玄関の脇、の隙間とか、コンクリートの割れ目から、草花が出ていたり、
それこそほんとに校舎のね、下の方から出てたり、ま、いろんな形で僕らの日常に隙間から
植物ってありますよね。先生そういうものに、関心を持たれてると。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :あー。
ゲスト:はい。
MC :その、隙間の植物の関心はいつぐらいからですか?
ゲスト:ああ、そうですね、それは、まあ、道歩いてても隙間に限らず、
MC :ええ。
ゲスト:植物を、まあ、なんとなぁく見ているので、
MC :ええ。
ゲスト:ま、変わり者がいれば、目が止まる。
MC :あ、変わった
ゲスト:はい。
MC :植物見ると、おっ、て思ってしまう。
ゲスト:そうですね。はい。で、変わった物っていうと、まあ、時には変なとこに生えてる、
それはまあ、隙間ですけど
MC :はい。
ゲスト:あるいは、あの、普段、普段見てるのとは形が違うとか
MC :はい。
ゲスト:ま、斑が入ってるとか、変わり者、そういうのが目に入る。
MC :斑が入ってるって何ですか?
ゲスト:あ、えっとね、葉っぱに白とか黄色とか模様が入るやつが、時々出るんですよ。
MC :葉っぱに白とか黄色の模様ね。はい、はい。
ゲスト:はい、はい。
MC :はい。
ゲスト:そういうのを斑入りって言うんですね。
MC :ま、ま、マダラ模様みたいなやつ。
ゲスト:そうです、そうです。はい。
MC :うん。ホルスタインみたいな感じですね、牛で言うと。
ゲスト:まあ、そうですね。
MC :ええ。
ゲスト:はい。ああいうの変わり者、時々なんかの拍子に出てくるんですよ。
MC :ええ。
ゲスト:割と、はい。
MC :へえー。そういうの見ると思わず立ち止まって、
ゲスト:そうですね。
MC :写真に収めてしまうんですね、カメラに。
ゲスト:ま、昔はカメラ大変だったですけど、今、デジカメで、
MC :はい。
ゲスト:気楽に撮れますからね。
MC :いつもじゃあ、あの、接写ができるデジカメをお持ちで?
ゲスト:ああ、そうですね。小っちゃいやつですけどね。
MC :あ、そうですか。さあ、えー、もともとじゃあ、こういうものがお好きで、植物?で、
海外も行ってしまうという。
ゲスト:ああ、そうですね。はい。
MC :例えば、どういうとこ行かれるんですか?
ゲスト:まあ、最近好きなのは、東南アジアですね、
MC :ええ。
ゲスト:ボルネオとか
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :インドネシアですか?それは
ゲスト:そうですね。
MC :はい。それは、この、植物撮りに行くためにですか?
ゲスト:あ、それは色々な植物、あそこはやっぱり豊富ですので、
MC :ええ。
ゲスト:はい。
MC :ええ。例えばどんな植物が、例えばインターネットで今調べると、
こういう珍しいのがあったよってあります?
ゲスト:ああ、はい。えっとボルネオはほんとにあの、非常に植物の種類が多くって
MC :うん。
ゲスト:日本では全然見られない物が沢山いるんですけれども
MC :はい。
ゲスト:まあ、一番うれしいのは、誰もまだ名前を付けてない、新種がいっぱいいるってことですね。
MC :あ、じゃ今、ラジオの前で言葉にはできないってことですね。
ゲスト:ま、は、はい。ありますけども、名前、
MC :インターネットでも調べられないってことですね。
ゲスト:あ、調べられますよ。
MC :おっ。
ゲスト:それはただ、でも、あの、横文字になっちゃうんで
MC :あ、へえー。
ゲスト:はい。
MC :日本名がないような植物が、
ゲスト:はい。
MC :ボルネオに行ったら、いっぱいあるっていうことですね。
ゲスト:そうですね、はい。
MC :え、言葉で形容すると、ど、どんな珍しい植物がありますか。
ゲスト:えーっと、例えば、ま、僕は、さっきもご紹介いただいたように、
葉っぱを一応専門にしているんですけども、
MC :はい。
ゲスト:葉っぱを作らないですとか
MC :葉っぱを作らない
ゲスト:はい。
MC :花だけの植物?
ゲスト:はい。
MC :はい。
ゲスト:で、根っこのところで、ま、カビとかキノコを食べてる植物とかですね、ま、色んなのがいます。
MC :カビとかキノコを
ゲスト:はい。
MC :栄養素にして、
ゲスト:はい。
MC :成長してる植物?
ゲスト:はい。
MC :それ、日本にはないんですね。
ゲスト:あ、日本にもありますけども
MC :ええ。
ゲスト:熱帯の、そういったインドネシアとかボルネオの方が、
MC :はい。
ゲスト:はるかに色んな種類があります。
MC :へえー。変わった植物の宝庫という
ゲスト:はい。
MC :ことですね。
ゲスト:はい。
MC :そもそも、先生の定義する、スキマの植物というのは、
ゲスト:はい。
MC :どういう定義になりますか?
ゲスト:あ、それはですね、えっと、いわゆる隙間、ええっと
MC :はい。
ゲスト:何かの隙間に生えてる植物ってことで、
MC :はい。
ゲスト:何かって一番多いのは、まあ、アスファルトが割れてる所ですとか、
MC :はい。
ゲスト:ま、レンガ塀だったりすると、塀の隙間だとか、
MC :はい。
ゲスト:まあ、コンクリートブロックだったらコンクリートブロックの、この、ちょっと、
作り悪くて隙間が出来てるとことか
MC :はい。
ゲスト:そういうとこから、 顔出している植物です。
MC :うん。いっぱいありますよね。
ゲスト:はい。
MC :いや、すごくいっぱいある。えっ、例えば、なんだろう。いや、ほんと町歩けばいっぱいありますよね。
ゲスト:はい。
MC :その辺にありますもんね。
ゲスト:そうですね、あの、ま、今回のこの図鑑として本を出してから、
MC :はい。
ゲスト:あの読者の方から多かった反響は、
MC :はい。
ゲスト:あの、朝の散歩の時に、確かに言わたように沢山あるとか
MC :はい。
ゲスト:あの、犬の散歩の時に、あの犬の目線で見てるとやっぱり
MC :はい。
ゲスト:沢山いるのに気付いたとか、そういうのが多いですね。
MC :よく、例えば、じゃ、ほんとに道歩きながらだったら、アスファルトの下から、
ゲスト:うん。
MC :植物出てくるじゃないですか。
ゲスト:はい。
MC :あれを見るとね、アスファルトがモロいのか、植物の生命力が強いのかってったら、どちらなんですかね。
ゲスト:あ、両方です。
MC :両方?
ゲスト:はい。
MC :へえー。
ゲスト:ていうのは、アスファルトって硬いじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:で、車、おっきい車が上通っても全然、まあ、ビクともしないですよね。
MC :ええ。
ゲスト:で、強い力が、ガッてかかる時には平気なんですけども、
MC :うん。
ゲスト:えーっと、アスファルトって実はモロいところがあって、ゆっくり、ジワジワ力掛けるのに弱いんです。
MC :ほー。
ゲスト:いきなり
MC :あー。
ゲスト:いきなりガンてかけるのには、強いんですけれども
MC :うん。
ゲスト:ジワジワとするものには、弱いんですね。
MC :いわゆる、ピッチャーの投げるデッドボールには強いけれど、
グリグリグリグリってボールを押し付けられたら弱いってことですか。
ゲスト:そんなもんですね。
MC :はあー。
ゲスト:で、一方、動物は、
MC :ふん。
ゲスト:力をかける時に、まあ、何か蹴ったりとか、いきなり力かける方が得意ですけども
MC :はい。
ゲスト:植物はそうあの、出来ないじゃないですか。
MC :ええ。
ゲスト:パッて動けない。
MC :はい。
ゲスト:その代り、ジワジワおっきくなりますよね。
MC :なるほど。
ゲスト:段々、木でも何でも、ジワジワとした動きでおっきくなってくじゃないですか。
MC :はい。
ゲスト:だから、両方がうまくあってるので、
MC :ええ。
ゲスト:植物が、まあ、大きくなりたいなと思うぐらいの、力をかけるとアスファルトは弱いので
MC :なぁるほど。
ゲスト:はい。
MC :だから、アスファルト破れるのは、
ゲスト:はい。
MC :植物だから故の特技ということですかねぇ。
ゲスト:そうですね。人間だったらそんな辛抱しきれないですからね。
MC :うーん。どんなに空手の達人だってね、
ゲスト:はい。
MC :パンチでアスファルト割れるかって、レンガみたいなものは割れるかもしれないけれど
ゲスト:はい。
MC :アスファルトはやっぱり確かに割れませんもんね。
ゲスト:あれ、粘っこいんですよね。
MC :粘っこいから。
ゲスト:はい。
MC :と、植物だったら粘っこいが故に、
ゲスト:うん。
MC :ジワジワジワって出来る。
ゲスト:そうですね。
MC :なるほど。それがスキマ植物と
ゲスト:はい。
MC :いうことなんですけれど。さあ、例えば今回、特筆すべきスキマ植物は、例えばどんなものがありますか?
ゲスト:まあ、一つはですね、ま、まい、これの、えっと本の中にも入れましたけども、
ブロック塀の結構、えーっとね、膝ぐらいの辺りの高さの、
MC :ふん。
ゲスト:所から生えてる、えー、ビオラを見つけたことがあって、
一体こんな高さにどうやって飛んできたんだろうって、そんなのもありますね。
MC :ブロック塀の膝ぐらいの高さにある、
ゲスト:割れ目のところから
MC :はい。
ゲスト:花を咲かせてる
MC :ビオラ?
ゲスト:はい。ビオラ
MC :ビオラ
ゲスト:っていうのはね
MC :はい。
ゲスト:あの、パンジーの仲間です。
MC :パンジー。
ゲスト:パンジーの小っちゃいのをビオラっていうんですね。
MC :これは、東京に住む子供たちの
ゲスト:うん。
MC :キッズ達の暮らしの中にもあるわけですね。
ゲスト:あります、あります。
MC :おおー。パンジーみたいな
ゲスト:うん。
MC :紫っぽいお花。
ゲスト:ま、紫と黄色とか
MC :黄色。
ゲスト:ですね、うん。
MC :いわゆる、スミレ系ですね。
ゲスト:スミレ系です。
MC :うん。パンジーですとかはね、
ゲスト:はい。
MC :学校の
ゲスト:ふん。
MC :花壇に植える花じゃないですか。
ゲスト:植えますよね、うん。
MC :でも、それも
ゲスト:はい。
MC :そういう、隙間に生えることもあるってことですか。
ゲスト:そうです。あれ、パンジーずっとそのまま花壇で育ててると
MC :ええ。
ゲスト:実がなるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、スミレの仲間、パンジーに限らないんですけども
MC :はい。
ゲスト:みんな、特殊な能力があって
MC :はい。
ゲスト:実が熟すとですね、
MC :はい。
ゲスト:3つに割れるんですよ。
MC :ふん。
ゲスト:で、3つに割れる時に、実を作ってる皮が、キュッて縮むんですね。
MC :実を作ってる皮が
ゲスト:はい。
MC :キュッと縮む。はい。
ゲスト:そうすると、た、実の中に含まれてる種が、その縮んだので、狭くて、
おしくらまんじゅうするもんだから、その勢いでピンてはじけて、
MC :ほお。
ゲスト:種が遠くに飛ぶんですよ。
MC :うん。
ゲスト:で、その種が遠くに飛んで、もともと花壇から、いたやつが外に出られるのと、
もう一つはですね、パンジーとかスミレの仲間の種には、特別な器官がついていて、
MC :はい。
ゲスト:蟻が好きなものが、お弁当がついてるんですよ。
MC :はい。
ゲスト:だから、蟻は、その種を見つけると、その、種本体じゃなくて種にくっついてる
お弁当の方が欲しいもんだから、
MC :はい。
ゲスト:拾って、自分の巣の方に持ってっちゃう。
MC :はあ。
ゲスト:ので、さらに遠くに行ける。
MC :すごい、面白い。先生、もうお時間になってしまいました。
ゲスト:はい。
MC :イメージ膨らみますねぇ。
ゲスト:そうですね。
MC :いや、もう、あのー、来週はもう節分過ぎてますから、
ゲスト:はい。
MC :春ですよ。いよいよその、シーズンがやってくると、
ゲスト:はい。
MC :いうことで、また、来週もお話を伺いたいと思います。
ゲスト:はい。
MC :今週の「サイコー」は、東京大学大学院教授の塚谷裕一先生でした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:どうもありがとうございます。 -
「イモムシのふしぎ パート2」 ゲスト:森昭彦さん
2017/07/01 Sat 12:00 カテゴリ:生き物MC :さ、今週の「サイコー」は、先週に続いてですね、えー、
サイエンスジャーナリストの森昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:みなさんよろしくお願いしまーす。
MC :お願いしまーす。えー、先週ね、アカボシゴマダラで、大村さんは絶句して最後終わっちゃってですね、
ゲスト:んふふふ。
MC :なんだか分かんなかったんだけど、とにかくイモムシは可愛いってことですよ。
ゲスト:そうです。
MC :で、これ僕ら飼ってもいいんですよね。キッズ達も
ゲスト:そ、もちろんそうです。
MC :で、この飼い方のコツというのは、あのー、森さんは、普通の、あのー、虫の飼育ケース?、
あの、カブトムシやクワガタ飼うのと同じ物に入れてラボに連れてきてくれたんですけれど
ゲスト:はい。
MC :飼い方のポイントなんですか。
ゲスト:そうですね、まずは、餌を切らさないことがまず、一つですね。
MC :え、餌は葉っぱですよね。
ゲスト:そうです。
MC :好き嫌いがあるんですか?
ゲスト:好き嫌いあります。
MC :えっ、なんだろ。
ゲスト:えーっと、同じ葉っぱしか
MC :あー、ああ、ああ。
ゲスト:種類を、えー、あんまり多くの種類を食べないので
MC :ほー。
ゲスト:ええ、例えば、えー、今アカボシゴマダラが、え、食べてるのは、榎という木なんですけど
MC :はい。
ゲスト:この子は、榎しか食べないので
MC :ほぉほぉほぉ。
ゲスト:それを沢山持ってきておいてあげると
MC :じゃあ、えー、採集したところの
ゲスト:はい。
MC :住んでたところの
ゲスト:はい。
MC :環境そのまま持って来ればいいんですね
ゲスト:そうですね。
MC :はい、はい。
ゲスト:で、お食事がなくなってしまうと
MC :はい。
ゲスト:途端に、あのー、お食事を探してウロウロ、ウロウロして、
MC :うん。
ゲスト:いつもでも、ウロウロして、で、体力を消耗して、えー、コテっと倒れてしまいますので
MC :ひたすら食べてるんですか?
ゲスト:素晴らしいことにですね
MC :ええ。
ゲスト:この子たちは食べて寝て、食べて寝て、食べて寝てを
MC :ほおー。
ゲスト:ずーっと繰り返します。
MC :へえー。あ、さっきまで食べてたんだけど
ゲスト:はい。
MC :今度寝ちゃった。
ゲスト:ははは。すいません。
MC :勝手ですね。
ゲスト:勝手です。
MC :いやー。
ゲスト:でー、注意しなければいけないのは、あの、夜中にも、え、この子達は起きて食べますので
MC :はい。
ゲスト:えー、夜中寝る前とかにも、少しちょっと餌を足してあげると
MC :あっ、おお、大目にじゃぁ、
ゲスト:はい。
MC :えっ、すいません。
ゲスト:元気に育ちます。
MC :この子達がね、基本イモムシ達が青いのは
ゲスト:はい。
MC :葉っぱ食べてるから、青いんですか?
ゲスト:あ、それはですね、体液が実は透明もしくはあの、ちょっと薄い黄色みたいな感じなんですね。
MC :へえー。
ゲスト:で、表面の色っていうのは、あのー、虫によって、全然、イモムシに毛虫によって全然違っていて
MC :はい。
ゲスト:それは、あの、食べ物の中から出てくる、えー、栄養成分によって変わってくるというのが、
あのー、ちょっと難しい話なんですけども
MC :うん。なるほど。
ゲスト:ありまして、色んな色があります。
MC :別に食料で、体の色が付くってわけじゃないんですね。餌で
ゲスト:はい。
MC :ふーん、なるほど。餌を切らさないこと。それから、普通に環境としては、家の中とかベランダでも大丈夫
ゲスト:そうですね、できれば、日の当たらないところに置いてあげるといいです。
MC :あっ、ほー、あんまり暑くなっちゃうと良くないんですね。
ゲスト:はい。
MC :うーん。いやー。
ゲスト:そして、あのー、まあ、あの、面倒な人は、えー、3日に一度でいいですけども
MC :はい。
ゲスト:できれば、2日に一度ぐらいは、えーっと、飼育ケースの中の掃除をしてあげると
MC :うん。
ゲスト:はい。
MC :清潔にするんですか。
ゲスト:はい。
MC :うーん。
ゲスト:例えば、今回もお持ちしたケースの中には、あの、ティッシュペーパーが、し、下に
MC :はい。
ゲスト:敷いてあるんですけども、えー、これ、いし、一つ敷いとくだけで、あのー、取り換える時に
MC :はい。
ゲスト:あのー、クルッと丸めてポイして、また新しいシートを、えー、敷いてあげればいいだけなんで
MC :うーん。
ゲスト:非常に便利です。
MC :なぁるほど。
ゲスト:はい。
MC :いや、ほんとに、いやペットとしてもありですね。行動見てるだけで、た、癒されますもの。
ゲスト:ありがとうございます。
MC :ね。
ゲスト:はい。
MC :しかも、お金かかんないでしょ?
ゲスト:はい。
MC :あ、だって、連れて来ればいいんだもんね。
ゲスト:はい。
MC :で、後は蝶々になって放せばいいってことで
ゲスト:その通りです。
MC :ね。
ゲスト:はい。
MC :すばらしいキャッチアンドリリースですねぇ。
ゲスト:あっはははは。はい。
MC :いやー、いいわぁ。
ゲスト:はい。
MC :さあさあ、そのイモムシの生態なんですけれど
ゲスト:はい。
MC :森さんがね、イモムシずーっと研究されてて
ゲスト:はい。
MC :すごいと思うのはどんなところですか。
ゲスト:えーっと、やっぱり、ま、イモムシなんてこんな無力で非力な生き物だと思うんですけども
MC :うん。
ゲスト:なぜか脈々と
MC :うん。
ゲスト:えー、大体3000万年といわれてるんですけども
MC :えー。
ゲスト:3000万年間生き残ってきたと
MC :へえー
ゲスト:はい。これがどこに隠されてるのかっていうのを自分で、こう、観察しながら、
MC :はい。
ゲスト:ちょっと、そ、その秘密のベールをちょっと覗いてみたいなという
MC :へえー。進化はあまりしてないんですか。
ゲスト:えーと、結構してるんですよね。
MC :へえー。
ゲスト:例えば、あのー、よく見るアオムシなんかは
MC :はい。
ゲスト:あのー、キャベツとかで育ってますよね
MC :はい。
ゲスト:えー、で、ああいう植物を、食べる植物を段々少しずつ増えてったり
MC :はい。
ゲスト:する、えー、ケースもありまして、それから、ですとか、あと、こんな角が生えてる種族もいれば
MC :はい。
ゲスト:坊主頭の種族もいて
MC :はい。
ゲスト:あとは、変な話シジミチョウなんていう小っちゃい蝶々の子供たちは、なんと蟻の巣に潜り込んで、
MC :はい。
ゲスト:えー、蟻に餌をもらいながら、あの、育っていくという
MC :へえー、へえー。
ゲスト:はい。
MC :あ、蟻が餌を与えてくれて、
ゲスト:はい。
MC :育っていくイモムシもいるんですか?
ゲスト:そうです、清潔に体撫でてあげたりですとか、
MC :へえー。
ゲスト:はい。してるイモムシもいます。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :え、あとはイモムシの生態で変わってる生き方あります?
ゲスト:そうですね
MC :うん。
ゲスト:あとは、えー、ちょっと面白い物に、あのー、ウスタビガというのがありまして、
MC :ウスタビガ。これ、これ、蛾ですか
ゲスト:蛾なんですけれども
MC :ええ。
ゲスト:非常に美しい
MC :ええ。
ゲスト:えー、フォルムをしてて、
MC :はい。
ゲスト:あの、西洋の鎧兜のような形なんですけども
MC :はい。
ゲスト:えー、色味は、えー、明るいグリーン
MC :はい。え、ウスタビガ。
ゲスト:はい。
MC :えー、著書から発見いたしました。えー、森さんは、サイエンス・アイ新書から
「イモムシのふしぎ」という本も出版されているんですが、そこにウスタビガ。
ありますね。これぞイモムシっていう感じのイモムシですよ。
ゲスト:そうですね。
MC :ぼ、あの、多分イモムシの絵描いてって言ったら、大概これを描くでしょうね。
ゲスト:あ、なるほどー。
MC :うん。あのー、先週お話伺ったオオムラサキの絵は、多分描かないと思うんですよ。
ゲスト:ああ、そうですね。
MC :オオムラサキのイモムシよりも、やっぱりイモムシ、ザ・イモムシみたいなのが、
でも、これ蛾なんですね。
ゲスト:蛾です。
MC :へえー、どんな特徴があるんですか。
ゲスト:はい。えーと、この子はあのー、鳴きます。
MC :えっ、イモムシが?
ゲスト:はい。
MC :どんなふうにですか。
ゲスト:キュゥ。という感じです。
MC :えへへへ、ほほほほ、ははは。
ゲスト:いやいや、ほんとなんですよ。
MC :はははは。
ゲスト:ほんとなんですって。ほんとなんです。え、特にですねぇ、あのー、ここにも絵にあの、写真載ってますが
MC :はい。
ゲスト:あのー、えー、ヤマカマスという形の変わった繭を作るんですけれども
MC :はい。
ゲスト:ちょうど、柄杓を、の、上をすぼめたような形をしてる繭なんですけども、
MC :はい。
ゲスト:これを作る時は3日3晩、キュゥキュゥ、キュゥキュゥ
MC :え、
ゲスト:鳴きながら
MC :き、聞こえるんですか、僕ら人間
ゲスト:聞こえます。
MC :へえー。
ゲスト:僕だけかの幻聴かと思って
MC :ええ。
ゲスト:色んな人に聞かせたら
MC :ええ。
ゲスト:やっぱり聞こえるって言ってますね。
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:多分、みなさんに聞こえると思います。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :で、どの辺に生息してるんですか
ゲスト:これも近くの森ですね
MC :へえー。
ゲスト:コナラですとか、
MC :ええ。
ゲスト:普通に生えてる樹木に
MC :ええ。
ゲスト:桜に付くこともあるらしいんですけども
MC :ええ。
ゲスト:はい。そういったものに付いてるので、見つかる機会はあるかと思います。
MC :へえー。ウスタビガ。
ゲスト:はい。
MC :鳴く。
ゲスト:鳴く。
MC :へえー。いや、いいですね。え、でも、でもねぇ
ゲスト:はい。
MC :いやすっごい、ほろ苦い思い出があってね
ゲスト:はい。
MC :普通にやっぱり、イモムシを学校で飼ってたわけですよ
ゲスト:あぁ。
MC :それ、蛾になったんですよね。子供の頃。
ゲスト:はい。
MC :今、それを思い出してですね、いやぁ、がっかりですよね。
ゲスト:あはははは。
MC :でも、でも、な、蝶々と蛾の違いってなんですかねぇ。なんで、蛾って
ゲスト:はい。
MC :あんな、嫌われるんだろう。気持ち悪いからですかね、色合いが。美しさなんですかねぇ。
でも、蛾を美しいっていう人もいますよね。
ゲスト:ああ、美しいと思います。
MC :えっ、え、蛾と蝶の違いって、森さんから言わせたらなんですか。
ゲスト:えーと、実は蛾と蝶は違いがないんですね。
MC :僕の中では
ゲスト:はい。
MC :羽根を縦に、あの、立ったまんまパチッと閉じるのが蝶々
ゲスト:はい。
MC :止まる時。羽根を広げて止まってんのが、蛾っていう認識なんですけどそれ違うんですか。
ゲスト:あっ、色々例外が多すぎて
MC :へえー。あっ
ゲスト:あまりにも例外が多すぎてそれは無くなってしまいましたね。
MC :あっ、違うのか。
ゲスト:はい。
MC :多分、キッズ達のお父さんお母さんは大概、そう思ってると思いますよ。
ゲスト:そうか、そうか。
MC :はい。
ゲスト:そうですねぇ。
MC :そうじゃないんですね。
ゲスト:そうです。
MC :蛾と蝶の違い?
ゲスト:はい。
MC :誰が決めてるんですか?蝶と蛾の区別は。
ゲスト:あっ、いや、実はあのー、蝶々とか蛾を研究してる学会の方では、区別はしてません。
MC :あっ、そうなんですか。
ゲスト:はい。
MC :人間が勝手に決めてるだけですか
ゲスト:なんとなーく決めてるっていう
MC :えっ。
ゲスト:感じです。
MC :全然違うじゃないですか
ゲスト:ははは、はい。
MC :いや、ほんと可哀想ですよね、蛾。あははは。
ゲスト:そうなんですよ。
MC :ええっ。
ゲスト:日本で5700種ぐらい、あの、蝶と蛾って見つかってるんですけども
MC :はい。
ゲスト:その内、蝶々がいるのが250から60種類ぐらいで
MC :えっ。
ゲスト:あと残り全部、蛾なんです。
MC :じゃ、5%しか蝶々いなくて
ゲスト:はい。
MC :95%が蛾みたいな計算ですか。
ゲスト:そうです。身の回り蛾だけが、蛾、蛾だらけです。
MC :あっははは。だけど
ゲスト:はい。
MC :あの、イモムシでいる分には、両方とも可愛いですよね?
ゲスト:可愛いですよ。
MC :うん。だからあとは、成長したら、だから、リリースすればよろしいっていう
ゲスト:あははは。そうですね。
MC :来年ぐらいにちょっと僕も、育ててみたいなと思いましたねぇ。
ゲスト:あ、そうですか。
MC :いや、あははは。
ゲスト:特に今時期はもう
MC :はい。
ゲスト:最高の時期なので、見つけやすい
MC :あ、そう、そうですね。
ゲスト:いっぱいいる時期なんで
MC :でも、数か月で、
ゲスト:はい。
MC :あの、リリースすればいいですから
ゲスト:そうですね。
MC :ね?蛾になるのか、
ゲスト:はい。
MC :蝶になるのか
ゲスト:はい。
MC :あるいは、この「イモムシのふしぎ」という本から
ゲスト:はい。
MC :調べてもらって
ゲスト:あは。
MC :蝶か蛾か調べて
ゲスト:はい。
MC :育てるもよし、と。
ゲスト:はい。
MC :とにかく見てるだけでいいですね。楽しいねこれは。
ゲスト:ありがとうございますー。
MC :いやー、お時間です。ますます、じゃぁ、活躍して下さいねぇ。
ゲスト:あっ、はい、ほんとにありがとうございました。
MC :はい。今週の「サイコー」は、サイエンスジャーナリストの森昭彦さんでした。 -
「イモムシのふしぎ パート1」 ゲスト:森昭彦さん
2017/07/01 Sat 12:00 カテゴリ:生き物MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
サイエンスジャーナリストの森昭彦さんです。こんにちは。
ゲスト:みなさん、よろしくお願いします。
MC :お願いしまーす。森さんは、関東を拠点に植物や動物、
これの関係について調査研究をされてるんですけれど、
サイエンス・アイ新書から「イモムシのふしぎ」という本も出版されてます。
それにちなんで今日は、お越しいただきましたけれど、たぶんね、キッズ達は、
イモムシよりかも「はらぺこあおむし」とかの絵本でね、
アオムシっていうイメージはあるんだけど、
ゲスト:うふ。
MC :アオムシとイモムシの違いって何とかね、でも毛虫とイモムシとアオムシって何とか、
な、なんかちょっと、そっからちょっと、お話いただいてよろしいですか。
ゲスト:わかりました。
MC :はい。
ゲスト:えっと、ほんとは、あの厳密に言うとですね、えー、イモムシというのは、
えー、植物のえー、じゃがいもですとか、
MC :ええ。
ゲスト:里芋とか
MC :はい。
ゲスト:えー、芋に付く虫のことをイモムシと言いまして、
MC :うん。
ゲスト:えー、他にもえー、アオムシですとか、先ほどおっしゃられたアオムシですとか
MC :はい。
ゲスト:イネツトムシですとか、ヨトウムシとか、他の名前が付いてる虫が多いです。
MC :えっ、イモムシってのは、
ゲスト:はい。
MC :えっ、い、芋に寄生する虫のことですか?
ゲスト:う、そうです、そうです。
MC :えっ。
ゲスト:大きい虫があのー、イモムシに、あ、芋に付くんですけど、スズメガの幼虫というんですけれども
MC :ええ。
ゲスト:普通、イモムシというと、えー、そのスズメガという大きなイモムシのことをイモムシと言いまして、
毛のない、えー、ぽ、ちょっとぽっちゃりしたツルッとしたものをイモムシというわけでは、
ほんとはなかったんです。
MC :でも今は
ゲスト:はい。
MC :全般的に
ゲスト:はい。
MC :毛虫かイモムシかアオムシ
ゲスト:あははは。そうですね。
MC :に分かれちゃってますけど
ゲスト:はい。
MC :け、毛がない
ゲスト:はい。
MC :毛虫をイモムシ、
ゲスト:と、今は普通に言ってますけども
MC :はい。
ゲスト:ま、それでいいと思います。
MC :だいたいそれでいいですか。
ゲスト:それでいいです。
MC :誰も知らないと思いますよ。
ゲスト:あは、そうですね。
MC :みんな、なんか青いさぁ、
ゲスト:はい。
MC :イボイボした虫みたら、イモムシだっ。あるいは、アオムシだって言うけど
ゲスト:はい。
MC :でも、それは、正確には
ゲスト:はい。
MC :芋に寄生してなければイモムシと呼んじゃいけないんですね、ほんとは。
ゲスト:ああー、ていうか元々そういう、あのー、芋にいっぱい付くんで
MC :ええ。
ゲスト:これは、イモムシだ、イモムシだと
MC :へえー。
ゲスト:ですから、ゴマに付く虫は、農家の方はゴマムシと言ったりします
MC :へえー。
ゲスト:やっぱり。
MC :蝶々の幼虫を
ゲスト:はい。
MC :総じてイモムシって言うじゃないですか。
ゲスト:あー、言いますねぇー。
MC :うん。あれ、それは芋には寄生してないんですよね、ほんとは。
ゲスト:してません。
MC :でも、イモムシって呼んでいいんですか?
ゲスト:イモムシって呼んでいい、結構です。
MC :あ、分かった。
ゲスト:あはは。はい。
MC :毛のない、だから、
ゲスト:はい。
MC :虫をじゃもうイモムシにしちゃいましょう。
ゲスト:はい。そうですね。
MC :いいですか?
ゲスト:はい。
MC :分かりました。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :あははは。えっ、イモムシはじゃあ、大人なるとなんになるんですか?
ゲスト:イモムシは、えーと、蝶と蛾に両方ともなります。
MC :紙一重ですねぇ。
ゲスト:かみ、そうです。
MC :何それ。
ゲスト:はい。
MC :だ、いや、可愛そう。
ゲスト:あははは。
MC :ええっ、蝶か蛾ですか?
ゲスト:蝶か蛾です。
MC :意外。悲惨ですね、ある意味。
ゲスト:はい。でも中には、えー、は、えーっと、蜂になる子もいます。
MC :えっ、ええっ。蜂?
ゲスト:はい。
MC :えっ、だって蜂は
ゲスト:はい。
MC :そうだ、イモムシだ。
ゲスト:そうなんです。
MC :なんか、白いですよね。
ゲスト:あ、白いんですけど
MC :うん。
ゲスト:ほんとにあの、ハバチという仲間の蜂は、あのー、女性たちがよく、
子供たちがこんなイモムシ連れてきたんですけど何ですか?って
MC :ええ。
ゲスト:あの、持ってくるんですけども、えー、そん中には、えー、蝶になると思って育てたら、
蛾に、蛾が出て来たとか、
MC :いやー。
ゲスト:蜂になったとか、
MC :へえー。
ゲスト:そういうケースもよくありまして、
MC :へえー。
ゲスト:意外と難しいんですよ、この辺の見極めが
MC :そうかぁ。
ゲスト:はい。
MC :いやー、さあそんな著書の中にですね、多くのイモムシが登場してくるんですけれど、
ゲスト:ええ。
MC :森さんは、特に好きなイモムシってのはなんですか?
ゲスト:ちょっとイモムシのイメージをちょっと、まるっと覆す
MC :はい。
ゲスト:えー、可愛らしいイモムシを紹介したいと思います。
MC :はい。
ゲスト:えー、まずはちょっと、名前は聞いたことあると思いますが
MC :はい。
ゲスト:オオムラサキという、蝶々をご存じでしょうか。
MC :私、大村正樹です。
ゲスト:あはは。
MC :ええ。
ゲスト:そうでした。よろしく
MC :ええ。あっ、オオムラサキね。
ゲスト:はい。オオムラサキ
MC :あのー、日本を代表する蝶々ですね。
ゲスト:あ、その通りですねぇ。
MC :ええ。
ゲスト:はい。
MC :で、それの
ゲスト:ええ
MC :幼虫
ゲスト:はい。
MC :がイモム、可愛い
ゲスト:可愛いんです、これが
MC :可愛い。ちょっと待って下さい。
ゲスト:はい。
MC :あ、ありました。えー、オオムラサキ。えー、角が二本生えていて、緑色をしていて、
えー、あんま、可愛くないんだけど
ゲスト:あっはははは。
MC :森さんから
ゲスト:そうですか。
MC :言わせりゃ、可愛いんですね。
ゲスト:すごく可愛いです。
MC :何が可愛いんですか。
ゲスト:もう、とにかくえー、正面から見るとですねぇ
MC :ええ。
ゲスト:えー、ちょっとミッフィーを思わせるような、
MC :ミッフィー?
ゲスト:そうです、愛らしいこのマスクがもうたまりません、ほんとに。
MC :ちょっと待って下さいよ
ゲスト:うん。
MC :ちょっとみんなさぁ、あー、あのー、パソコンあったりしたら、あの、オオムラサキ調べて、
え、それとミッフィーがどう結び付くのか、僕にはよく分かんないけれど、
専門家から言わせりゃ、ミッフィーなんだ。
ゲスト:ミッフィーです。
MC :分かりました。
ゲスト:はい。
MC :で、このオオムラサキは、ミッフィーの顔?まあ、
ゲスト:はい。
MC :あとは、角が二本?
ゲスト:はい。
MC :あとは何ですか?背中に四対の襟って書いてある。
ゲスト:ああ、ありますねぇ。可愛らしい、あの、ちょっとした、あの、ワイシャツの襟みたいのがですね、
ちょんちょんちょんと付いてるんです。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :へえー、あっ、それはオオムラサキの独特のものですか?
ゲスト:特徴ですね。
MC :へえー。
ゲスト:特徴の一つです。
MC :で、そのイモムシは何処に行ったら、会えるんだろう、関東では
ゲスト:関東では普通の雑木林に実はいたりします。
MC :ええっ。
ゲスト:あの、貴重で貴重で
MC :はい。
ゲスト:よく保護区なんかー作られてますけれども
MC :はい。
ゲスト:実は、私も、あのー、全然生息地だって言われてない場所で、
MC :はい。
ゲスト:たくさん見つけてます。
MC :へえ、じゃ、もうキッズ達のちょっと、家の周辺で、森の中入ったりとか
ゲスト:はい。
MC :畑の周辺行ったりとか
ゲスト:はい。
MC :キャベツ畑の傍らにオオムラサキがいたりするわけですか?
ゲスト:キャベツ畑は知りませんが
MC :ええ。
ゲスト:ゴルフ場の
MC :ゴルフ場かぁ
ゲスト:あはは、裏口とかに
MC :へえー。
ゲスト:の雑木林にいたりしました、やっぱり。
MC :だいたいこの時期ですか?イモムシ
ゲスト:まさに、今なんです。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :それで夏になると、
ゲスト:はい。
MC :大人になって、羽ばたいてくんですか?
ゲスト:美しい、それは美しい蝶になりますねぇ。
MC :へえー。
ゲスト:日本の国蝶と呼ばれるぐらいの
MC :うん、うん。
ゲスト:誉れ高い、紫色が
MC :へえー。
ゲスト:輝いてる
MC :そうかぁ
ゲスト:はい。
MC :角を持っていて、顔がミッフィー、
ゲスト:はい。
MC :そして背中に、襟が付いていると
ゲスト:はい。
MC :いうことですねぇ。
ゲスト:はい。
MC :え、あとは?なんかお勧めのイモムシはありますか?今の時期
ゲスト:はい。
MC :子供たちがポッとこう、外に行った時にですね、
ハッと思ってその辺にいっぱいいるイモムシは何でしょうか。
ゲスト:はい。えーと、実は今日も連れて来たんですけども
MC :あ、ラボリンイモムシを
ゲスト:はい。
MC :わぁお。
ゲスト:えー、実はこのイモムシの方が、多分みなさんにはよく見つかると思うんですけども、
これ実はあのー、最近になって増えてきた種族で、
姿形はオオムラサキとゴマダラチョウとそっくり、なんですね。
MC :も、森さんね、今僕の前に、
ゲスト:はい。
MC :飼育ケースがあるんですけど、イモムシの姿見えないんですけど、
ゲスト:はい。
MC :僕の目が悪いのか、保護色でよく見えないのか、どっちだろうか。
ゲスト:その通りです、今の時期このー、えー、アカボシゴマダラという蝶がいるんですけども
MC :アカボシゴマダラ
ゲスト:はい。
MC :を連れて来てくれたけれど
ゲスト:はい。
MC :今、僕の目には見えない。
ゲスト:はい。あのー
MC :ちょっと待って。
ゲスト:実によくできた保護色なんです。
MC :えっ、ほんとに?
ゲスト:この小さなケースん中に小枝がチョンとか入ってるだけなんですけど、中々見つからないですよねぇ。
MC :ちょっと今、アカボシゴマダラ、みんな調べてみてぇ。
ゲスト:あっはは。
MC :うん。さあ、教えて下さい。
ゲスト:はい。
MC :あ、今、えー、森さんの著書でアカボシゴマダラを確認しました。
それによると緑色をしてるんですけれど、僕は全然分かんなかった。
で、今、うわぁーお。参ったなぁ。これは参ったな。衝撃すぎる。
ゲスト:衝撃ですか。
MC :あー。
ゲスト:どの辺が衝撃的でしょうか。
MC :分かんないですよ。これー。
ゲスト:あはは。分かんないですか。
MC :これさあー、いやー、これ、これ、ちょっと何処で採取できますか?首都圏だったら。
ゲスト:これも、ほんとに、えー、例えばその、榎という木に、やはり同じ木に付くんですね。
MC :榎が、きか、近くにあればいいけどみんなの家の近くにありますか?
ゲスト:榎というのは、非常に農家から嫌われる雑木でして
MC :ええ。
ゲスト:何処にでも、生えてる
MC :え、何処にでもある?
ゲスト:生えてるんです。
MC :えーっ、ちょっとじゃあ、じゃ榎の、これ今葉っぱは、これ榎の葉っぱですか?
ゲスト:はい。
MC :動きやがったよ。
ゲスト:あはは。
MC :あははは。
ゲスト:可愛らしいですねぇー。
MC :今、動きました。いやー、
ゲスト:いやー、実に可愛らしい。
MC :ア、アカボシゴマダラ
ゲスト:はい。
MC :ちょっと衝撃でした。あー。
ゲスト:大村さんにご挨拶しに
MC :いや、
ゲスト:わざわざ顔出してますね。
MC :ほんとこっち見てくれた。
ゲスト:はい。
MC :角が二本あって、
ゲスト:はい。
MC :今、起きたみたいです。ほんとに葉っぱと同化してですね、
ゲスト:はい。
MC :ただ、今、むしゃむしゃと榎の葉っぱを食べだしてます。
ゲスト:すいません、ちょっと躾がまだ甘いもんですから
MC :可愛いー。
ゲスト:食事まで始めてしまいました。
MC :いや、僕これ見ながら、今日お別れします。もう時間になりました、癒されました。
ちょっと、また来週、詳しい話伺いますね。いやー、はっはっはっは。
今週の「サイコー」は、サイエンスジャーナリストの森昭彦さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「自然エネルギーの科学 パート2」 ゲスト:高橋真樹さん
2017/06/01 Thu 12:00 カテゴリ:自然MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、前回に続きまして、
ノンフィクションライターの高橋真樹さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :高橋さんは、全国各地を回って自然エネルギーの取材をされているんですが、
ゲスト:はい。
MC :岩波書店から「ご当地電力始めました」という本も出版されています。
前回は日本国内の自然エネルギーのありよう、だから、
電力会社から供給される発電エネルギーだけじゃなくて、実は僕らの暮らしの周りには、
自然エネルギーて結構あるよねぇって話。それからそれに関して、考える事もですね、
とても重要だというお話伺いましたけれど、実は高橋さんは世界を股にかける男、
ゲスト:えへへ。
MC :70ヶ国を取材されて、ご当地電力を、こう、研究されてらっしゃる。
ゲスト:そうですね、まあ、あのー、エネルギーだけではないんですけども
MC :ええ。
ゲスト:でも、結構、回ってますね。
MC :え、世界、え、じゃあ、世界でご当地電力の先進国は、ズバリどこだったでしょうか。
ゲスト:ま、一番すごいのはデンマーク。
MC :デンマーク。
ゲスト:はい。
MC :そんなにおっきい国じゃないですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :ヨーロッパ。
ゲスト:北欧の方ですね。
MC :ほー。日本よりも寒いですか?
ゲスト:も、めちゃくちゃ寒いですね。
MC :てことは、エネルギー必要ですね。
ゲスト:そうですね、暖房とかね。
MC :はーい。
ゲスト:電気とかはやっぱり使いますよね。
MC :エアコンは夏場はクーラーは?
ゲスト:クーラーは、でも夏場はわりと涼しいので、
MC :涼しい。
ゲスト:あんまりエアコンて、
MC :ほーほーほー。
ゲスト:使わないですね。
MC :僕の住んでる北海道みたいな感じですかね。
ゲスト:そうだと思います。
MC :へえ、で、
ゲスト:ええ。
MC :自然エネルギーは先進国?
ゲスト:そうですね。
MC :具体的に何ですかそれは。
ゲスト:まあ、あのー、一番多いのは風車
MC :あー。
ゲスト:ですね。
MC :風力発電。
ゲスト:はい。
MC :あっ、風車ね。
ゲスト:ええ。
MC :よくヨーロッパの絵画で風車出てきますけど、
ゲスト:そうですね。
MC :あのイメージですか。
ゲスト:まあ、あのー、まあ、新しい鉄の
MC :あっ、もっといいやつ
ゲスト:物なんですけども
MC :もっといいやつ
ゲスト:ええ。
MC :ゴッホとか描かないですね。
ゲスト:そうです、でも、元々ヨーロッパの風景にね、
MC :ええ。
ゲスト:マッチしてるというか、伝統的に使われてきたので、
そんなに抵抗感、向こうではないんだと思うんですけど、
MC :質問なんですけど、
ゲスト:はい。
MC :何かヨーロッパの風車ってね
ゲスト:ええ。
MC :発電じゃなくて
ゲスト:ええ。
MC :穀物を
ゲスト:ええ。
MC :何か、こう、突いたりするためにあるっていうイメージだったんですが
ゲスト:昔はそうですよね。
MC :ですよね。
ゲスト:ええ。だから、発電に使われるようになったのは、割と最近
MC :あっ。
ゲスト:のことなんです。
MC :じゃ、やっぱり昔は、
ゲスト:ええ。
MC :あのー、農産物を、
ゲスト:はい。
MC :こう、何か、こう、脱穀したとか
ゲスト:そうです、そうです。
MC :するためにあったけれど、
ゲスト:ええ。
MC :それが、エネルギーを生み出すためにシフトしてるってことですか?
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。何年ぐらい前からですか。
ゲスト:まあ、あのー、デンマークでも実は80年代の、
MC :ええ。
ゲスト:に、オイルショックっていうのが、日本でもあったんですけども、
MC :うん。
ゲスト:それで、まあ、とにかくどんどん燃料代が上がってってやばいと
MC :はい。
ゲスト:いう時に、あの、デンマークなんかは、国民でいろんな議論をして、
これからはやっぱり自然エネルギーを生かして、自分達でエネルギー作ったら、
外から買う必要がないじゃんと
MC :はい。
ゲスト:ということになったんですね。
MC :はい。
ゲスト:だから、積極的に自然エネルギー入れてこうっていう話になって、それから風車
MC :日本とは違うんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :キッズのお父さんお母さん達が、ぼ、僕らも子供の頃
ゲスト:はい。
MC :あ、ありましたよ。
ゲスト:ああ、ええ、ええ。
MC :だけど、デンマークは、自然エネルギーに
ゲスト:日本は、はい。
MC :シフトしようっていうふうに
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。
ゲスト:日本は当時慌ててね、トイレットペーパーを買い占めたりして、
MC :はい。
ゲスト:してましたけど
MC :はい。
ゲスト:ええ。
MC :そうか。
ゲスト:はい。
MC :じゃあ、それで、本来ある風車を発電用にっていうふうに変えたのが、30年ほど前。
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。
ゲスト:で、しかも面白いのが、そのー、ま、前回ちょっとお話しましたけど、
MC :ええ。
ゲスト:すごくそのー、大企業がドカンと風車作って
MC :はい。
ゲスト:地元の人関係ないよっていうのではなくて、えー、デンマークにある風車の7割から8割が今、
地域の人が所有する市民風車ってなってますね。
MC :へえー。あっ、へえー。
ゲスト:ええ。
MC :えっ、ちょっとイメージするとじゃあ、今日本だったら、火力発電がメインなってますから
ゲスト:はい。
MC :日本の火力発電所の7割から8割が
ゲスト:はい。
MC :市民所有みたいなイメージですか?
ゲスト:そうですね。ちょっと
MC :すごい。
ゲスト:イメージしづらいですけどね。
MC :あははは。出来ない。
ゲスト:ええ。
MC :でも、風車は
ゲスト:ええ。
MC :そういう形で、ふ、市民が所有してる?
ゲスト:そうですね、自分たちがお金を出して
MC :へえー。
ゲスト:うまく運営できると、
MC :うん。
ゲスト:ま、自分たちにお金が返ってくるという形になってますね。
MC :その、ふう、風車から、え、得られた電力は
ゲスト:ええ。
MC :一旦どこに売るんですか、じゃあ。
ゲスト:まあ、あのー、電力市場というのがあって
MC :はい。
ゲスト:流通してるんですけども、
MC :はい。
ゲスト:あの、国の中で足りない必要なとこに送られるというシステムになってますね。
MC :へえー。
ゲスト:はい。
MC :そして、国民に供給される。
ゲスト:そうです。
MC :で、えー、デンマークの電力不足というのは、基本的にないんで
ゲスト:ないんです。
MC :ない。もう、十分てこと
ゲスト:ええ。
MC :すごーい。出来るんじゃないですか。
ゲスト:出来ます。
MC :やりゃぁ。
ゲスト:だから、もう、デンマークは、今30%以上年間で
MC :ええ。
ゲスト:風力発電だけの電気で賄ってますから、で、しかも、まあ、
2000何十年に100%にするってのは、近々目標立ててるんですね。
MC :なるほど、あと、じゃ他の世界で、
ゲスト:はい。
MC :風力以外でおっ、っていう自然エネルギーは?
ゲスト:うーーん。ま、風力以外ですと
MC :うん。
ゲスト:ま、太陽光なんかで有名なのは、ドイツですよね。
MC :ああ。
ゲスト:ええ、ドイツでは結構盛んで、ま、ノルウェーなんか水力が
MC :、水力。
ゲスト:盛んにやってますよね。ま、水力はでも、出来るとこと出来ないとこがすごいね。
MC :はい。
ゲスト:あるので、えー、例えば、ま、ちょっと、日本なんですけど、
MC :はい。
ゲスト:日本の屋久島って
MC :おー、せ、
ゲスト:あるじゃないですか。
MC :世界遺産。
ゲスト:はい。
MC :鹿児島県。
ゲスト:あそこ実は、自然エネルギー100%の島なんですよ。
MC :えっ。そうなんですか?
ゲスト:そうなんです。
MC :な、な、何のエネルギーで?
ゲスト:あそこ水力ですね。
MC :あ、あ、あのね、一年間で
ゲスト:ええ。
MC :さ、えっとね、365日のうち
ゲスト:ええ。
MC :370日雨が降るって言われてます。
ゲスト:そう、そう。
MC :雨ばっかりなんですよ。あそこ。
ゲスト:だから、雨が多くて
MC :あー。
ゲスト:山が多いじゃないですか。
MC :そう。
ゲスト:滝が多くて
MC :宮之浦岳っていう山があって
ゲスト:はい、はい。
MC :なんと関西から西の中では
ゲスト:はい。
MC :日本で、あ、西日本で一番高い山っていう
ゲスト:そうですね。
MC :1997メートルなんですよ。
ゲスト:はい、はい、はい。
MC :だから、その屋久島って
ゲスト:ええ。
MC :海の上に浮かぶんだけれど、
ゲスト:ええ。
MC :なぜか、2000メートル級の山がボコッてあるっていう
ゲスト:はい。
MC :不思議な島ですよね。
ゲスト:そうですね。だからあそこは、もう
MC :はー。
ゲスト:水量豊富なんで、
MC :ええ。
ゲスト:自然エネルギー100%で電力賄って
MC :ええ。
ゲスト:まだまだ、ま、開発っていうかポテンシャルあるんだけど、
MC :ええ、ええ。
ゲスト:もう、島で使いきれないから、いらないぐらい
MC :へえー。
ゲスト:あ、あるんですよ。
MC :へえー。すごい。
ゲスト:意外と知らないでしょ。
MC :知らない、知らないです。僕、屋久島、今語るぐらいに、
ゲスト:ええ。
MC :実は、あのー、屋久島マニアなんですよ。
ゲスト:あははは。そうなんですか。
MC :あの、自然遺産に、世界遺産になる前から
ゲスト:ええ。
MC :屋久島の四季を訪ねて回ってて
ゲスト:はい。
MC :屋久島トレッキング大好きだったんですね。
ゲスト:ええ。ええ、ええ、ええ。
MC :だから、今、あの、高橋さんが屋久島の話してくれて嬉しかったんですけど
ゲスト:はい。
MC :そんな、電力供給率が、あは
ゲスト:はい。
MC :100%なんて知らなかった。
ゲスト:そうですね、だから日本でももっと、その、い、あん、あのー、
知られてないところもいっぱいありますし、
MC :そうかぁ。
ゲスト:ポテンシャル活かせば、色んなことが、まだまだ、これから出来る、ま、島もそうですし、
MC :ああ。
ゲスト:地域もあるんですよね。
MC :そっか、その、電力供給、そのね、自給率っていうものって
ゲスト:ええ。
MC :日本てすごく乏しい国だって言われてましたけれど
ゲスト:はい。
MC :そういう考え方で、やりぁ出来るんですね。
ゲスト:そうですね。
MC :節約したり、あと生み出したり、
ゲスト:はい。
MC :水力それから火力、風力、
ゲスト:ま、太陽光
MC :太陽光、太陽光ってでもなんか
ゲスト:はい。
MC :あの、不安定だなと思って
ゲスト:ええ。
MC :面積食う割にはね
ゲスト:ええ。
MC :あの、梅雨時になると発電出来ないとか、不安定じゃないですか。
ゲスト:いや、あの、仕組みによって、あの、それもねアイデア次第で
MC :えっ、ほんとですか。
ゲスト:僕もよく、その、福島県と会津地方で今やってるプロジェクト見にいくんですけども
MC :ええ、ええ。
ゲスト:そこはあの、すごい雪が降るんですよ。
MC :はい。
ゲスト:で、雪の間発電できないってのは従来の、太陽光発電の常識だったんですけど、
MC :ええ、ええ。
ゲスト:雪が滑り落ちるようにちょっと傾斜を大きくしたら
MC :うん。
ゲスト:冬でも普通に発電出来るんですね。
MC :あ、ああ、分かった。
ゲスト:はい。
MC :パ、パネルに雪が
ゲスト:はい。
MC :あ、なに、積もんないように
ゲスト:滑り落ちる
MC :滑るようになる
ゲスト:はい。
MC :そしたら、太陽光当たるってことですか?
ゲスト:そうですね。
MC :なるほど。
ゲスト:はい。
MC :ゆ、雪に埋没しないってことですね。
ゲスト:はい。
MC :へえー。
ゲスト:それから、昨日、ちょうど、ちゅ、取材行ってきたんですけども、農地の上に
MC :ええ。
ゲスト:太陽光パネルを、まあ、隙間を空けて設置して
MC :はい。
ゲスト:作物の栽培もしながら、
MC :ほー。
ゲスト:発電、おー、の出来るっていう
MC :ほー。
ゲスト:ソーラーシェアリングっていうのは、最近出て来てますけど
MC :おー。
ゲスト:それなんかは、逆にその、土地を無駄にしないわけですよね。
MC :おー。
ゲスト:下で作物も栽培できるので
MC :確かに。
ゲスト:うん。
MC :米やってない時期は
ゲスト:はい。
MC :安定した
ゲスト:はい。
MC :冬の、太陽光を得ることも出来るし
ゲスト:そうですね。作物によっては、その、光が、あの、強すぎると
MC :うん。
ゲスト:成長が止まっちゃう作物もあるんで
MC :なるほど。
ゲスト:逆にちょうどいいんですよね。
MC :いやー、お、もう時間?いやー、いや、面白かったなぁー。
ゲスト:ええ。
MC :ちょっと日立ハイテクさんにちょっと、あれだ、ちょっと相談してみます。
ゲスト:あはは。
MC :あははは。えー、今週の「サイコー」はノンフィクションライターの高橋真樹さんでした。
また来て下さいね。ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
「自然エネルギーの科学 パート1」 ゲスト:高橋真樹さん
2017/06/01 Thu 12:00 カテゴリ:自然MC :さあ、今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
ノンフィクションライターの高橋真樹さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :真樹さんですねぇ、
ゲスト:そうです。
MC :いい名前ですね。真樹という名前をいただいて、何か得したありますか?
ゲスト:あんまりないんですけど、ははは。
MC :ですよね。
ゲスト:あははは。
MC :いや、僕もなんですけど、ただ同じ名前の人と出会うとちょっと嬉しい。
ゲスト:ああ、嬉しいですね。
MC :あは。はい。
ゲスト:あは。
MC :大村正樹です。よろしくお願いします。
ゲスト:よろしくお願いします。
MC :さあ、えー、高橋さんは、全国各地を回って、自然エネルギーを取材されていて、
岩波書店から「ご当地電力始めました」という本も出版されています。
ゲスト:はい。
MC :ご当地電力。ご当地ビールとかね、
ゲスト:ええ。
MC :何かそういうのってあるんですけど、
ゲスト:ご当地グルメとか
MC :グルメ
ゲスト:はい。
MC :あー、ご当地電力
ゲスト:ええ。
MC :え、なん、なんだろ。僕、北海道ですけど
ゲスト:ええ。
MC :北海道では太陽光パネルとか
ゲスト:はい。
MC :風力発電が結構、ま、ニュースとか新聞には出てきます。
ゲスト:はい。
MC :あれもご当地電力ですか?
ゲスト:いえ、
MC :ちがう。
ゲスト:あのー、ここで言うご当地電力
MC :ええ。
ゲスト:って言うのは、まあ、うん、まあ、要は電力会社って、今日本で、
MC :はい。
ゲスト:10個、でその
MC :各地域
ゲスト:だいたい地域で
MC :はい。
ゲスト:東京、東京ちい、地域っていうか、首都圏は、もう
MC :はい。
ゲスト:東京電力が全部やるってなってるんですけども
MC :ええ。
ゲスト:ただ、今、あー、起きてる動きっていうのは、あー、ま、それぞれ地域に、
ま、地域の人達が立ち上げた、ちっちゃな、まあ、電力会社というかね
MC :へえー。
ゲスト:あの、エネルギープロジェクトは、各地に立ち上がって
MC :うーん。
ゲスト:ますよって、それがすごく地域地域の特色を生かして、ユニークな活動をしてるので、
それをご当地電力と私が呼んでるというような形になってますね。
MC :僕らの知る、はつ、な、電力会社の発電形式とは違うということですか?
ゲスト:そうですね。
MC :例えばどんな
ゲスト:はい。あのー、ま、従来の今までの、げ、電力会社とか、ま、あの、発電方法ってのは、
MC :うん。
ゲスト:まあ、火力発電とか原子力発電とか、まあ、すごく大きな
MC :はい。
ゲスト:あー、発電の、おー、仕組みで、それを長い送電線を使って電気を家庭に届けるっていうのを
MC :はい。
ゲスト:やって来てるんですね。で、それはそれでまあ、いいんですけども、
でも、おー、もっと火力発電とかを、じゃあ、自分の地域で作ろう、
自分の町で作ろうつっても、なかなか難しいですよね。何十億円もかけて
MC :はい。
ゲスト:作るものですから、でも、もっと、地域地域で自分達でエネルギーのこと
考えていこうっていう人達が、自然エネルギーを使って、
MC :はい。
ゲスト:太陽光発電とか、風力発電とかを
MC :うん。
ゲスト:おー、自分たちの地域に自分たちのお金で作って、
その、おー、運営も自分達で賄って、
MC :ああー、おおー。
ゲスト:という仕組みを作ってるんですね。
MC :は、は、おっきい企業から電気を供給してもらうんではなくて、
ゲスト:はい。
MC :自分たちで
ゲスト:ええ。
MC :組織を作って
ゲスト:ええ。
MC :で、そのライフラインを確保するっていう
ゲスト:そうですね。
MC :考え方ですか。
ゲスト:はい。
MC :今、あの、全国ご当地電力マップっていうものをいただいたんですけど、
ゲスト:はい。
MC :え、北は北海道から、沖縄はないけど、南は鹿児島まで
ゲスト:ええ。
MC :北海道グリーンファンドからずっーと日本列島を縦断する形で、
ゲスト:はい。
MC :薩摩自然エネルギー
ゲスト:はい。
MC :鹿児島県。で、えー、ウィンドパワーとか、
ゲスト:はい。
MC :えー、お日様コーポレーション
ゲスト:ええ。
MC :あの、想像すると、ま、風の力とか太陽の力とか、
それからグリーンエネルギーっていう文字も随分見えますけど、
ゲスト:ええ。
MC :なんだろ、グリーンエネルギーってどういうエネルギーですかね。ええ。
ゲスト:ま、あのー、グリーンエネルギー色んな、あのー、取り組みがあるんですけど
MC :はい。
ゲスト:一つは、その、バイオマスっていう、その山のね
MC :バイオマス。
ゲスト:ええ。
MC :うん。
ゲスト:木を切って
MC :はい。
ゲスト:それを燃やして、ま、薪ストーブとかっての昔からありますけども
MC :はい。
ゲスト:あの、今、ペレットといってもっと細かくして、あの、薪のようにこう、自分が入れなくて、
MC :はい。
ゲスト:いい、いいっていうか自動でね、やってくれるストーブなんかも出たりとか、
MC :ほー。
ゲスト:それで、発電をしようという取り組みなんかもあるので、
MC :バイオマスエネルギーって
ゲスト:はい。
MC :そういうことなんですか?
ゲスト:そうですね、まあ、幅広く、こう、何ていうんですかね、生物とか
MC :はい。
ゲスト:植物とか、あ、を燃やすゴミ発電なんかもその一種なんですけども
MC :ええ。
ゲスト:でも、おー、日本で一番可能性があるって言われてるのが、そのー、里山を利用して、
MC :はい。
ゲスト:間伐材なんかを燃やすっていう
MC :ほー。いわゆる、その、薪とはまた違うんですか。
ゲスト:そうですね、薪もそうですね。
MC :へえー。
ゲスト:薪もバイオマスエネルギーですね。
MC :でも、そうするとCO2がいっぱい出ちゃったりしないんですか。
ゲスト:薪はもともとそのー、空気中に出てるCO2を吸収したものなので、
MC :ははあ。
ゲスト:余分に出てるわけではないですし、いずれは、そのー、まあ、今の従来の山もね、
MC :ふん。
ゲスト:あのー、木が倒れたりすると自然にCO2出ちゃうので
MC :ええ。
ゲスト:ま、おんなじことですよね。
MC :あ、プラスマイナス
ゲスト:プラス
MC :0という考え方。
ゲスト:そうです、そうです。ええ。
MC :なるほどね。え、僕今、北海道に住んでるんですけど、
ゲスト:ええ。
MC :北海道には、ご当地電力、
ゲスト:ええ。
MC :北海道グリーンファンドって書いてあります。
ゲスト:はい。
MC :これ何ですか。
ゲスト:はい。北海道では、まあ、日本で一番風力発電のポテンシャルが高いところで
MC :ああ。
ゲスト:実は北海道の風力をちゃんと生かせれば、それだけで日本中の電力が賄えるぐらいの
ポテンシャルあるんですよ。
MC :え、北海道の風のエネルギーで、
ゲスト:そうです。
MC :日本中、全員?
ゲスト:ええ。
MC :賄えちゃう?
ゲスト:そうです。
MC :1億2000万人分?
ゲスト:賄えちゃうんです。
MC :すごい!
ゲスト:ええ。でも、まぁ、いろんな送電線の問題とかで、
MC :ええ。
ゲスト:実際には、そこまで風車はまだ作れてないし、
MC :はい。
ゲスト:それが活かせない状態にはあるんですけど、
MC :はい。
ゲスト:それをもっと活かして行こうっていう、まあ、
地域のグループが立ち上がってですね、えー、
まあ、風車っつっても一基5億円とかするんで、
MC :ああーー。
ゲスト:なかなか、一般の人作れないじゃないですか。
MC :これ、テレビなんかでよくね
ゲスト:はい。
MC :白ーい
ゲスト:ええ。
MC :のっぺりした風車が
ゲスト:ええ。
MC :回ってるのって、放映されるけど、
ゲスト:はい。
MC :僕あそこの下、よく行くんですよ。
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :結構、ごっついですよ。
ゲスト:えへへへへ。
MC :すーごいでかい。5億円もするんですか、あれ。
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :へえー。
ゲスト:で、まあ、従来はそうやって、大企業とか
MC :ええ。
ゲスト:あのー、国とかで、まあ、大手の電力会社じゃないと、
手が出せないものだったんですけど
MC :ええ。
ゲスト:この北海道グリーンファンドは、日本で初めて市民で、
ほんとに自分たちのための風車を作ろうって
MC :へえー。じゃ、みんなで
ゲスト:取り組んだ
MC :お金集めて、
ゲスト:はい。
MC :5億円の風車
ゲスト:そうですね。
MC :何本か作って
ゲスト:そうですね。
MC :で、それで、ええっと、生産された電気は、
ゲスト:ええ。
MC :自分たちの元に還元されるんですか?
ゲスト:電気は一応その、今の仕組みで言うと、電力、北海道電力に売電をして
MC :はあー、
ゲスト:収入を得てるんですけど、
MC :なるほど。
ゲスト:そのー、収入を、ま、地域貢献に役立てたりとか、
MC :おー。
ゲスト:ええ。あのー、ま、あのー、市民出資と言ってね、あの、
お金を集める一つの仕組みで、一般の方に公募をして
MC :ええ。
ゲスト:北海道の人もそうですけども、東京の人なんかも一口10万円とか50万円とかで、
えー、応募をして、えー、まあ、事業が順調にいったら、10年間で、
ちょっと利子というか配当がついて返りますよっていう、
MC :ほー。
ゲスト:仕組みを、は、初めてやったんですね。
MC :へえー。
ゲスト:それで何億円か集まって、
MC :ええ。
ゲスト:運営しているので、だ、みんなの、お金の話をしたら、みんなの風車に
MC :ええ。
ゲスト:なってるので、すごく大事にされていると
MC :いわゆる風車を共同出資して
ゲスト:ええ。
MC :え、そこで電力を生み出して、
ゲスト:はい。
MC :電力会社に売電して、
ゲスト:はい。
MC :利益を得て、
ゲスト:ええ。
MC :出資した人の元に、
ゲスト:ええ。
MC :また、お金が戻るっていう。
ゲスト:そうですね。
MC :へえー。
ゲスト:ええ。ただ、どうしても日本では自然エネルギーっていうと太陽光発電だし、
MC :うーん。
ゲスト:エネルギーの話をすると、は、いかに、はつ、
沢山発電するかみたいな話になっちゃうんですけど、
MC :はい。
ゲスト:でも、もっとトータルで考えたら、そもそもエアコン要らないじゃんとかね
MC :はい。
ゲスト:エネルギーいらないじゃんていう、こう、アイデアっていっぱい出せると
MC :ほー。
ゲスト:思うんですよね。それを色々アイデアを出し合っていくっていうのが
大事なんのかなと思ってますね。
MC :なるほどね。
ゲスト:はい。
MC :いや、そうだよな。供給されるものがエネルギーと思ってるけれど、
ゲスト:はい。
MC :その事について、ちょっと今一度考えるっていうのも、
次、僕らも考えなくちゃいけないことなのかなっていう感じもしますね。
ゲスト:そうですね。
MC :さあ、さあ。えー、来週はまたこの、海外のご当地エネルギーに関して
話を伺っていきたいと思います。
今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は、
ノンフィクションライターの高橋真樹さんでした。
どうもありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。 -
3月25日イベントレポート②
2017/05/13 Sat 09:00 カテゴリ:イベント今回の「ネクストサイエンスジャム」Vol.1では
文部科学省より指定を受けたスーパーサイエンスハイスクール、
東京都立科学技術高校のみなさんによる実験教室も開催されました。
 高校生とは思えないくらいユーモアのあるトークを駆使して
高校生とは思えないくらいユーモアのあるトークを駆使して
難しい科学の知識をわかりやすく説明しながら科学ショーを繰り広げてくれました。
会場の子どもたちは食い入るように見つめていました。

 『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
『ネクストサイエンスしつもんショー』では、
子どもたちから寄せられた質問に科学ジャーナリストの寺門和夫さんが
回答してくれました。
 寺門さんが最も良かった質問に選んだのは、『科学者になるにはどうしたらなれますか?』。
寺門さんが最も良かった質問に選んだのは、『科学者になるにはどうしたらなれますか?』。
その質問に対して、『いろいろな方法がありますが、何にでも興味を持つこと、
疑問に思ったことを探求することが、将来の役に立つ』との話でした。今回はここまで。
現在次の企画が進んでいます。詳細が決まったらこのホームページでお知らせしますので
楽しみにしていてください!
-
3月25日イベントレポート①
2017/05/13 Sat 09:00 カテゴリ:イベント子どもたちの「科学する心を育む」プロジェクトとして、
日立ハイテクノロジーズと文化放送が協力して、
科学実験とラジオ公開録音が一体になったベント
「ネクストサイエンスジャム」
その第一回目のイベントが、浜松町の文化放送で開催され
たくさんの子どもたちが参加してくれました。
ここではそのイベントの様子を少しだけご紹介します!
 イベントスタートは宇宙海賊・ゴージャスさんの登場から!
イベントスタートは宇宙海賊・ゴージャスさんの登場から!
最初はキョトンとしていた子ども達でしたが・・・
ゴージャスさんのギャグをきっかけに徐々に笑顔に。続いてイベント目玉の一つ。ネクストサイエンストークショー。
テーマは防災。今回はその中でもこの日本には常に起こっており、
生活に大きな影響を与える『地震』について教わりました。
 ゲストは災害情報論の研究者、東京経済大学名誉教授の吉井博明さん。
ゲストは災害情報論の研究者、東京経済大学名誉教授の吉井博明さん。
高校生の時に伊勢湾台風に遭遇したことをきっかけに防災研究の道へ進んだそうです。最初は地震の仕組みや種類について解説してくださいました。
地震の種類が多いことに参加した子ども達はビックリしていました。次にいつか起きると言われている首都直下型地震、南海トラフ巨大地震について。
被害がどのくらいになるのか?また被害を少なくするための対策を紹介。そして東日本大震災後に取ったアンケート結果からわかった
『ほとんどの人が避難までに意外に時間がかかっていた』ということと、
早く避難するための心構えを表した言葉、『てんでんこ』の意味を
解説してくださいました。
 子ども達から寄せられた、『地震の予知が出来るのか?』
子ども達から寄せられた、『地震の予知が出来るのか?』
『地震対策の備えはどうすればいいですか?』という質問に
吉井さんが丁寧に回答。最後に吉井さんから
『災害は意地悪。備えていないところにくる』という言葉があり
会場のみなさんも色々考え、感じたようです。 -
「人工知能 パート2」 ゲスト:松尾豊さん
2017/05/01 Mon 12:00 カテゴリ:サイエンスコラム 科学MC :さ、今週の「サイコー」も東京大学准教授の松尾豊さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :よろしくお願いします。
さあ、えー、松尾さんは人工知能の研究の第一人者でらっしゃるんですけれど、
僕らの暮らしの中で人工知能って色々ある中で、意外に気付いてないけど、
これ、人工知能だよっていうのあります?
ゲスト:そうですね、あの、例えば、あの、スマホの、
えー、日本語文字を入力するときに、あのー、
ひらがなを漢字に変換しますよね。
MC :はい。
ゲスト:で、かな漢字変換っていうんですけれども、
MC :はい。
ゲスト:あれも、もともとは人工知能の技術なんですね。
MC :ええ。あっ、そうなんですか。
ゲスト:ええ。
MC :あっ、すごく親近感。
ゲスト:ええ。
MC :あっははは。
ゲスト:それ意外にも例えば、検索エンジンは、
MC :ええ。
ゲスト:えー、かなり人工知能の技術が色んなとこに、使われていますし
MC :あ、そうなんですか。
ゲスト:ええ。
MC :あれ、パソコンの学習機能とかじゃなくて、
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :人工知能なんですか。
ゲスト:ええ、そうですね。中でその、
MC :はい。
ゲスト:機械学習っていう技術を沢山使ってますね。
MC :そうですか。
ゲスト:ええ。
MC :あ、じゃ、ほんとに身近なところで
ゲスト:ええ。
MC :僕らは日常的に、じゃ、人工知能と普段触れてるわけですね。
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :へえー。これ、ラジオ局の中には、人工知能はあるんですか。
ゲスト:いやー、あるんじゃないですかねぇ。
MC :ええ。
ゲスト:あのー、えー、そうですね。例えば、あのー、ま、番組制作する時に、
MC :はい。
ゲスト:ま、色々その編集したりすると思うんですけども、
MC :ええ。
ゲスト:そん時にたぶん、あの人間が操作する部分と
MC :はい。
ゲスト:結構自動でやってくれる部分、自動で調整したりとか
MC :ええ。
ゲスト:いう部分てあると思うんですけども、
MC :あ、そうなん、あるの?みんな?おっ、あるんだ、へえー。
なんかアナログチックな顔して奴らが
ゲスト:あははは。
MC :あるよ、みたいな、あっ、そうなんだ。
ゲスト:ははは。
MC :あ、たいしたもんだね、ラジオ局も。あは、そうですか。
へえー。な、なんかそうなのか。いや、意外にあるんですね。
へえー。あと、なん、何か活字の世界もこれから人工知能が凌駕してくるんじゃないかという、
ゲスト:うん。
MC :例えば、SFの短編でショートショートってあって、星真一さんなんか
ゲスト:うん。
MC :で、僕、子どもの頃よーく読ましていただいたんですけど、星新一さんの
ゲスト:うん。
MC :ショートショート
ゲスト:ええ。
MC :みたいなものも人工知能によって、より面白いストーリーになっちゃうって、ほんとですか。
ゲスト:ええ、あのー、星新一さんの、えー、まあ、あの、
ショートショートを人工知能で作ろうってプロジェクトが
MC :ええ。
ゲスト:あの、始まってまして、
MC :それ、星真一さんの立場はないじゃないですか。
ゲスト:あっははは。
MC :作家さんの立場は。
ゲスト:いえいえ、それは、あの、目標なんで、
MC :ええ。
ゲスト:ただ、やっぱりすごく難しいんですね。
MC :へえ。
ゲスト:で、あのー、ま、それに向けて、えー、少しずつ研究して行こうっていうことで、
MC :へえー。
ゲスト:例えば、星真一さんがよく使っている、その、単語とかですね。
MC :ええ。
ゲスト:言葉の使い方っていうのをコンピューターがある程度まねすることはできるんですけども、
MC :うーん。
ゲスト:やっぱりその、ストーリーを、えー、ちゃんと組み立てて、
ま、最後オチまでつけてっていうのは、やっぱりすごく難しいとこですね。
MC :あ、え、じゃ、星真一さん、例えば奇妙なとか
ゲスト:ええ、ええ。
MC :不思議なとか
ゲスト:ええ。
MC :謎のとか
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :宇宙からとか
ゲスト:ええ。
MC :UFOがとか
ゲスト:はい。
MC :色々あるじゃないですか。
ゲスト:ええ。
MC :ああいう、キーワードを使いながら、
ゲスト:そうです。
MC :ストーリーを構成して、
ゲスト:ええ。
MC :一編の物語
ゲスト:ええ。
MC :ショートストーリーはできるわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :ただ、オチを付けるのは難しい。
ゲスト:そうです、そうです。は、お話にするのは難しくて
MC :はあー。
ゲスト:ま、それより簡単なのは、あのー、えー、作詞
MC :はい。
ゲスト:いー、の方が簡単で、
MC :あっ、
ゲスト:歌の歌詞ってあの、あんまり意味通じてなくてもいいので、
MC :ええ。
ゲスト:そうすると、こ、この作詞家が、えー、よく、あの、使いそうな、
え、フレーズなんかを、こう、つなぎ合わせていくと
MC :ええ。
ゲスト:かなり、それっぽいのが出来るんですね。そういう研究もあります。
MC :ほー。僕の崇拝する、じゃ、尾崎豊だったら、自由とか
ゲスト:あは、そう、そう、そう。
MC :あははは。
ゲスト:そう、そう。
MC :野良猫とか、あはは。
ゲスト:あはは。
MC :俺とか、彼女とか、そういうことですね。
ゲスト:ええ、そういうことです、そういうことです。
MC :ああ、そういうフレーズで場合によっては、尾崎豊の
ゲスト:ええ。
MC :歌詞を超える
ゲスト:ええ。
MC :ストーリーっていうかフレーズが
ゲスト:ええ。
MC :生まれてきちゃうかもしれない。
ゲスト:ええ。
MC :くやしいぞ、尾崎。
ゲスト:あはははは。
MC :いやぁ、悔しいな。そうなんですか。
ゲスト:はい。んはは。
MC :じゃあ、秋元康先生も、うかうかしてらんないかもしれない
ゲスト:あははは。
MC :ですね。
ゲスト:そうですね。
MC :おおー、アイドルグルーブだって、大体こう、色んなフレーズありますけれど、
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :それによっては、既存の歌詞よりも
ゲスト:ええ。
MC :もっとこう、
ゲスト:ええ。
MC :レベルアップしたものが
ゲスト:ええ。
MC :生まれちゃうかもしれない。
ゲスト:そうですね。で、売れる曲、売れない曲で、その、そういう、
どういうフレーズがあるかっていうのを分析してですね
MC :ええ。
ゲスト:えー、そうすると、その、うれ、うれ、売れる曲に共通するような、
言い回しを沢山使うとかいうのも、出来るかもしれないですね。
MC :でも、それはアーティストからすると
ゲスト:あははは。
MC :屈辱ですね。こ、こんなね、東大の准教授がね、ピコピコピコって打ったのはね
ゲスト:あははは。
MC :これが人工知能で作った歌詞ですよみたいな
ゲスト:あははは。
MC :それで、人の心打ったら、ふざけるなってアーティスト怒ったりしないですか?
ゲスト:あははは。
MC :え、いいんですか。
ゲスト:いや、あの、そういうデータで
MC :うん。
ゲスト:あのー、なんて言うか、いいものを作っていくっていうのは、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、今、ずーっと、こう、流れとしてあるところで、
MC :ええ。
ゲスト:例えば、そのー、えー、プロ野球選手の能力を
MC :はい。
ゲスト:測るっていうのも
MC :うん。
ゲスト:実は昔は、スカウトの人が一所懸命、あの、その選手を見てですね、
やってたのが、それが、その、ま、マネーボールっていう、有名な本がありますけども
MC :はい。
ゲスト:それをデータで分析することによって、えー、実はどのぐらい活躍するかっていうのが、
MC :あ、
ゲスト:数字で分かる。
MC :うん、うん、うん。
ゲスト:そうすると、今まで目で見てた人達は、えー、怒っちゃって
MC :はい。
ゲスト:あんなんで分かる訳ないと言うんだけども
MC :ええ。
ゲスト:結局、やっぱり、分析した方が強いって
MC :はい。
ゲスト:いうことになって来てるので、
ま、そういうことは色んな世界で起こっていくんじゃないかなと思いますね。
MC :それはね、あると思います。
ゲスト:えへへへ。
MC :だって、あの、あるプロ野球の球団は、全部コンピューターに、全部数字入れ込んで
ゲスト:ええ。
MC :年俸の査定出すっていいますもんね。
ゲスト:ええ、ええ、ええ。そう、そう、そうなんですよね。
MC :そうすると、選手もグウの音も出ないっていいますもんね。
ゲスト:うふふふ。そうですね。
MC :越年交渉なんて昔よく
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :聞いたけど、最近聞かないのは、
ゲスト:ええ。
MC :コンピューターが全部選手の
ゲスト:ええ。
MC :こういう活躍したから、
ゲスト:ええ。
MC :あなた、来季こうですよって
ゲスト:ええ。
MC :答え一発だって
ゲスト:ええ。
MC :言いますもんね。
ゲスト:ええ、そうですね。でも、そうすると、あの、結構面白いのが、
やっぱりヒットを打つよりも、実はフォアボールを選ぶ方が、重要だとかですね
MC :ほおー。
ゲスト:そういうのもやっぱり分かってくるんですよね。
MC :なるほど。いわゆるヒットを打つ価値よりも、フォアボールで歩く方が、
ま、ヒット1本の価値と、ま、同等か
ゲスト:ええ、ええ。
MC :それ以上っていう評価もされちゃうということですね。
ゲスト:ええ、そうです、あの、ピッチャーに投げさせますし、
MC :ええ、ええ。
ゲスト:ええ、あの、出塁率で見た方が、
MC :はい。
ゲスト:あの、打率で見るよりも、いいっていうことですね。
MC :いや、すごーい、すごーい。いやぁ、すごい、先週のお掃除ロボットに、
はっ、端を発して、将棋だとか、えー、それから、アーティストを凌駕し、
さらにはプロ野球の世界まで、人工知能は入ってくるわけですね。
ゲスト:そうですね。
MC :えーっ。
ゲスト:人間のように学習したり、判断する能力っていうのは、
MC :うん。
ゲスト:どんどん、どんどん研究されて、えーっと、高くなってますし、
MC :はい。
ゲスト:それをその、ま、社会の色んなところに役立てて行くことで
MC :はい。
ゲスト:人間が、あのー、いままでやってたことがもっと楽にできるようになったり、
正確にできるようになったり
MC :ほー。
ゲスト:ということが、沢山あると思うんですよね。
MC :あのー、今年の初めにね、あの、イギリスのホーキング博士が、人工知能が、
ゲスト:うん。
MC :人間を凌駕しちゃうと、に
ゲスト:うん。
MC :人類ダメになっちゃうよみたいな
ゲスト:うん、うん。
MC :ことをおっしゃってましたけど、
ゲスト:うん、うん。
MC :それを研究されてる立場からするとどうですか。
ゲスト:ええ。ええ。あのー、えっと、人工知能に対してそういう、
その、不安を、え、抱くような、あの、意見もあるんですけども
MC :ふん。
ゲスト:あのー、僕は、あの、あんまり心配する必要はないと
MC :はあ。
ゲスト:思ってまして、
MC :そうですか。
ゲスト:えーと、なぜかっていうと、その、えー、みんな恐れてるのは、
あの、人工知能が、えー、ま、暴走するとかですね
MC :うん。
ゲスト:あの、人間の制御できなくなるっていうような、あの、
ことを恐れてるんですけども、あの、人間ていうのは、知能プラス生命なんですよね。
MC :うん。
ゲスト:で、あの、生命の部分ていうのは、作るの非常に難しくて
MC :うん。
ゲスト:で、知能はできると思うんですけども、あの、生命ができないんで結局それが、
あの、複合した、あの、ものが勝手に動き出すっていうことは、
ま、起こんないというふうに、ま、僕は思いますね。
MC :なるほど。そうか。あー。やっぱり血が通ってるってことですね。
ゲスト:ええ。
MC :僕ら
ゲスト:なんで、あの、すごく、あの、賢いのは出来ますし、
MC :うーん。
ゲスト:それは、やっぱり人間の道具として、
MC :うーん。
ゲスト:人間の社会、生活をよくしていくために
MC :うん。
ゲスト:使っていくっていうことだと思います。
MC :そうですか、いやー、でも楽しみになってきましたね。
やっぱり、あの、オリンピックですかね、
5年後のオリンピックぐらいに、日本の人工知能の
ゲスト:ええ。
MC :の、研究が、世界に、ど、どこまで、こう、出せるかとか
ゲスト:うん。
MC :それ、楽しみですね。
ゲスト:楽しみですね。
MC :えー、ますますのご活躍を、え、お祈りして
ゲスト:はい。
MC :あの、私も応援しとりますので
ゲスト:ありがとうございます。
MC :遊びに来て下さい。
ゲスト:はい。ありがとうございます。
MC :今週の「サイコー」は、東京大学准教授の松尾豊さんでした。
-
「人工知能 パート1」 ゲスト:松尾豊さん
2017/05/01 Mon 12:00 カテゴリ:科学MC :今週の「サイコー」は東京大学准教授の松尾豊さんです。こんにちは。
ゲスト:こんにちは。
MC :松尾さんの専門分野は人工知能。聞いたことありますけれどね、人工知能。
ただ、イメージとすると、コンピューターなのか、
何か人の脳の内部を絵に描いたものなのかよく分かんないんですけれど、人工知能。
ズバリこれはどういうことですか?
ゲスト:人工知能っていうのは、あのー、コンピューターに人間のように、
MC :うん、うん。
ゲスト:えー、賢い動きをさせるっていうことを、ま、目標にして、え、研究している、ま、研究ですね。
MC :イメージは、じゃ、パソコンですか。
ゲスト:そうですね、パソコンを、あの、もっともっと賢くして行こうと
MC :うん。
ゲスト:人間のように賢くして行こうということですね。
MC :うん。具体的には、さらにどんなことやってくんですか?
ゲスト:そんために、まあ、どういうことしないといけないかって
MC :はい。
ゲスト:いうとですね、あのー、データを処理する、
プログラムで処理をするっていうことをやっていくんですけども、
MC :はい。
ゲスト:ま、どういうデータを取って来たらいいか、
MC :うん。
ゲスト:えー、それをどういうふうに処理したらいいか、
えー、さらにそれを使って、ま、どういうふうなその、動き、
いー、出力に変えていったらいいかっていうことを、あの、研究しています。
MC :うん。あの、人工知能というのは、じゃ、コンピューターにいろんなこう、
データを、おー、インプットして、そこからそのコンピューターが何かを考えたり生み出したり
ゲスト:ええ。
MC :動いたりという
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :おー。
ゲスト:で、それは、あの、人間も同じことで、
MC :はい。
ゲスト:人間もその目とか耳とか、ま、体から外の世界の情報を受け取って、
えー、脳の中で、えー、処理をして、
MC :はい。
ゲスト:それで、それが行動に繋がってるわけですよね。
だから、それと同じことをコンピューターでやろうということです。
MC :そうか、その人間の脳の部分が、コンピューターって事ですね。
ゲスト:はい、そうです。人間の脳を、えー、プログラムで、えー、作るっていうのが、まあ、人工知能ですね。
MC :はい。さあ、具体的に2つの流派があるということなんですけれどね、
ゲスト:はい、あのー、昔から、あのー、強いAI、弱いAI、
えー、えー、というあのー、ま、言葉がありまして、
MC :はい。
ゲスト:えー、割と哲学的な話なんですけれども
MC :ふん。
ゲスト:えー、強いAIっていうのは、その人工知能のプログラムを突き詰めていくと、
最後そこに心が宿るだろうと
MC :ええっ。
ゲスト:ええ、いう、あのー、ま、あのー、考えの、まあ、あのー、流派でして、
MC :ええ。
ゲスト:もう一つの弱いAIっていうのは、えー、そうでなくても、
その人間の知能の、えー、知的な一面っていうのを、ま、実現していけばいいではないかと
MC :ふん。
ゲスト:だからその心を持つまで行かなくても、え、計算が速いとか
MC :うん。
ゲスト:えー、パズルが解けるとか、えー、そういう、
そういうことを突き詰めていきましょうというのが弱いAIですね。
MC :うん。強いAIってことは、
ゲスト:うん。
MC :じゃあ、例えば今スマホの中でね、いろんなこう、
見た目のかわいい女の子が出てきて、その女の子から好きだとかね
ゲスト:うん。
MC :お帰りとか言われたら、
ゲスト:うん。
MC :それにちょっと恋しちゃったりとか、
そういうレベルに行っちゃうと強いAIになっていくんですかね。
ゲスト:え、あのー、そうなんですけど、その、それが見せかけの
MC :ええ。
ゲスト:えー、まあ、心ではなくて、
MC :ええ。
ゲスト:あの、プログラムを追求していく上で、
ほ、ほ、本質的に出てくるはずだっていうのが強いAIなんですね。
MC :ええっ、コンピューターから?
ゲスト:あはははは。
MC :怖い。それ、怖い、強いAIよりも怖いAIだ、それ。
コンピューターから本質的に、心を宿した、ものが出てきちゃうってことですか?
ゲスト:え、出てくるんじゃないかっていう、まあ、立場の、えー、考え方ですね。
MC :へえー、弱いAIっていうのは、じゃあ、将棋の人間対コンピューターとか?
ゲスト:ええ、ええ、そうですね。
MC :それ、弱いAI。
ゲスト:そうです、そういうことです。
MC :その程度で私はいいと思いますけどね。
ゲスト:あはははは。そうですね。
MC :うーん。
ゲスト:ただ、これもそのー、ま、あの、哲学的な論争で、
えっと、つまり人間の知能っていうかどんどんどんどん突き詰めていった時に、
MC :はい。
ゲスト:心が出てくるのかどうなのかっていうのは、こう、昔から
MC :はい。
ゲスト:あの、みんな興味があって、議論してるとこなんですね。
MC :それも興味あります。
ゲスト:ええ。
MC :え、だって、いや、だって、例えば、家の中でね、
ゲスト:うん。
MC :お父さんお母さんに感謝の気持ちを出す時に、人間てどっか照れ屋さんだから、
ゲスト:うん。
MC :本当は思ってても
ゲスト:うん。
MC :言えなくて
ゲスト:うん。
MC :相手に伝えられない言葉って
ゲスト:うん。
MC :あるじゃないですか。
ゲスト:うん。そうですね。
MC :じゃ、人工知能の方が、お母さんにね
ゲスト:うん。
MC :いつもありがとうとか、
ゲスト:うん、うん、うん。
MC :いつもおいしご飯とかね、
ゲスト:うん、うん、うん。
MC :その感情を超えちゃったらね
ゲスト:うん。
MC :人間どうすんのよって
ゲスト:ははは。
MC :感じなんだけど、
ゲスト:そうですね、あの、その感謝の心を持つとかですね、
MC :ええ。
ゲスト:そういうのの、えー、前に難しいのが、
えっと、自分自身をどうやって認識するかっていうことで、
MC :うん。
ゲスト:あのー、人間って自分がこうやっていて、あのー、世界の中にいて、
自分が考えていてっていうの認識してますよね。
MC :はい。
ゲスト:だけど、そのコンピューターに、その、つまり、ま、自我っていうか
MC :はい。
ゲスト:自分自身が、えー、こうやって動いてるんだっていうこと自体が、
理解できるかっていうところがまず難しいとこだと思うんですよね。
MC :そりゃそうだ。お母さんからしてみると、我が子は可愛いのよ。
でもコンピューターからご飯おいしいとか、
ゲスト:ええ、ええ。
MC :お礼言われても、
ゲスト:えっへへ。
MC :コンピューターはコンピューターだから
ゲスト:え、ええ。
MC :そういうことですね。
ゲスト:そうですね。
MC :その、コンピューターが自分の立ち位置
ゲスト:ええ。
MC :人工知能が、
ゲスト:ええ。
MC :自分のポジションを分かってなければ
ゲスト:ええ、ええ、そうです。
MC :ああ、そうか、そうか。
ゲスト:そう。
MC :分かりやすいお話ですね。
ゲスト:はははは。
MC :えっ、じゃ、ちょっとお母さんつながりで、
お母さんにとって身近な人工知能ってなんですかね。
ゲスト:やっぱり、今だと一番わかりやすいのが、こ、お掃除ロボットだと思います。
MC :はい。そう、うちも。
ゲスト:うふふふ。
MC :妻がそっちに恋してますよ。
ゲスト:あはは。
MC :お掃除ロボット。
ゲスト:ええ、ええ。
MC :勝手にやってくれますもんね。
ゲスト:ええ、そうですね。で、あのー、やっぱり、使ってる人、あの、色々話聞くと、
MC :ええ。
ゲスト:あのー、まあ、愛着が湧いてきて、
MC :はい。
ゲスト:あの、どっかで止まってるとなんか、あ、可愛そうだなと
MC :はい。
ゲスト:思ったり、
MC :はい、はい。
ゲスト:なんか、そういうこと多いらしいですよ。
MC :だってさあ、20年ぐらい前は、ペット型ロボットっていたじゃないですか。
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :でも、それは、掃除してくんないじゃないですか。
ゲスト:あははは。
MC :だけど、別に、お掃除ロボットは可愛くはないけれど
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :健気ですよね。
ゲスト:そうですね。
MC :凹凸を乗り越えたり、
ゲスト:そうですね。
MC :絨毯で苦戦したり、
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :玄関にはまっちゃったり。
ゲスト:ええ。でも、やっぱりお掃除ロボットが動けるように、
えー、掃除してあげないといけないっていうのが、割と
MC :ああ。
ゲスト:あの、大変なとこ、えー、らしいですよ。
床が、あの、ちゃんと出るようにしないといけない
MC :なるほどね。そっか、お掃除ロボットが活動するために、
人間がその前に露払いしてあげるって
ゲスト:えぇ、ははは。
MC :お膳立てってことですね。
ゲスト:そうです、そうです。
MC :人工知能を上回る人間の愛というのも
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :あるわけですね。
ゲスト:そういう意味では、もう、あのー、そういうその、
ま、あのー、人工知能を、あのー、搭載した機械と
MC :ええ。
ゲスト:人間が、まあ、何らかの、こう、協調的に仕事をやってるっていうのが、
もう、既に、おこ、起こっているんだなっていう感じですね。
MC :そっかぁ。え、あとは、じゃあそれが身近な家庭での人工知能ってよく分かりました。
てことは、例えば、最近エアコンで、人を感知する
ゲスト:うん、うん。
MC :センサーがついていたり、
ゲスト:うん。
MC :あるじゃないですか。
ゲスト:ええ、ええ、ええ。
MC :あれもやっぱり、人工知能。
ゲスト:ええ、そうですね。そのー、えー、センサーで、えー、ま、取ってきた情報から
MC :はい。
ゲスト:あー、ま、自分の振る舞いを最適化していくっていうのは、ま、人工知能なんで、
MC :おー。
ゲスト:あのー、ま、どこに人がいるかとかですね、
MC :はい。
ゲスト:今の温度の状況とかを見ながら、
まあ、あの、えー、動かしていくっていうのは、あのー、
ま、人工知能といってもいいかなと、でも、従来は、その、制御工学とかですね、
MC :ええ。
ゲスト:もうちょっと違う言い方で言われてたのが、
ま、割と今人工知能っていわれることが多くなってきてますね。
MC :ま、確かに制御工学って
ゲスト:ええ。
MC :わかるけれど
ゲスト:ええ。
MC :ちょっと硬いですもんね。
ゲスト:そうですね。
MC :これ、人工知能っていわれると
ゲスト:ええ、ええ。
MC :何かお茶の間も、ああ、これ人工知能なんだっていう
ゲスト:えへへ。
MC :いい言葉ですね。
ゲスト:ええ、そうですね。
MC :へえ。あの、あと、将棋
ゲスト:ええ。
MC :とか、チェスとか
ゲスト:ええ、ええ。
MC :囲碁とか
ゲスト:ええ。
MC :ああいう、こう、本来のゲーム
ゲスト:ええ。
MC :で、人間対
ゲスト:ええ。
MC :コンピューターってあるじゃないですか。
ゲスト:ええ。
MC :あれも人工知能ですか?
ゲスト:ええ、そうですね。あれは、あの非常にわかりやすい人工知能の例で
MC :ええ。
ゲスト:えー、あのー、それも相手の打った、あのー、ま、手に応じてですね、
MC :はい。
ゲスト:自分が、あー、どういうふうに、 あの、次の手を打つのかっていうのを、
ま、考えていかないといけないので
MC :ふん。
ゲスト:えー、そういう意味では、その、えー、
まあ、中で考えてるわけなんで、えー、人工知能ですね。
MC :ふーん。いや、僕、すごい基本的なことですけど
ゲスト:はい。
MC :松尾さん、たぶん全部その辺研究されてると思うんですけど、
日本には先手必勝て言葉があってね、
ゲスト:ええ、えへへ。
MC :基本的には、将棋とか
ゲスト:ええ。
MC :オセロとか、
ゲスト:ええ。
MC :先に
ゲスト:ええ。
MC :駒進めた人が勝つんじゃないんですか。
ゲスト:えーとですね、あのー、それはいい質問で
MC :ええ。
ゲスト:あのー、えっと、ゲームによっては確かにそうなんですね。
MC :へえ。
ゲスト:で、あのー、先手必勝のゲームもあれば
MC :ふん。
ゲスト:後手必勝のゲームもあって
MC :えーっ。
ゲスト:それは、あのー、相手が、あ、ま、自分が、あのすごくミスなく完璧に打てば、
絶対に、その先手もしくは後手の場合に勝つっていう、
MC :ふーん。
ゲスト:それはゲームの性質としてあると。
ところがえっと、将棋とか囲碁の場合は、
えー、基本的にはそれ分かってない。
MC :へー。
ゲスト:えへへ。
MC :そうなんですか?
ゲスト:必勝法は、あの、分かってないので、えー、結局先手が勝つのか、
後手が勝つのかっていうのは、あの、分かってないですね。
MC :お時間です。また、来週もよろしくお願いします。
今週の「サイコー」は東京大学准教授の松尾豊さんでした。
ありがとうございました。
ゲスト:ありがとうございました。