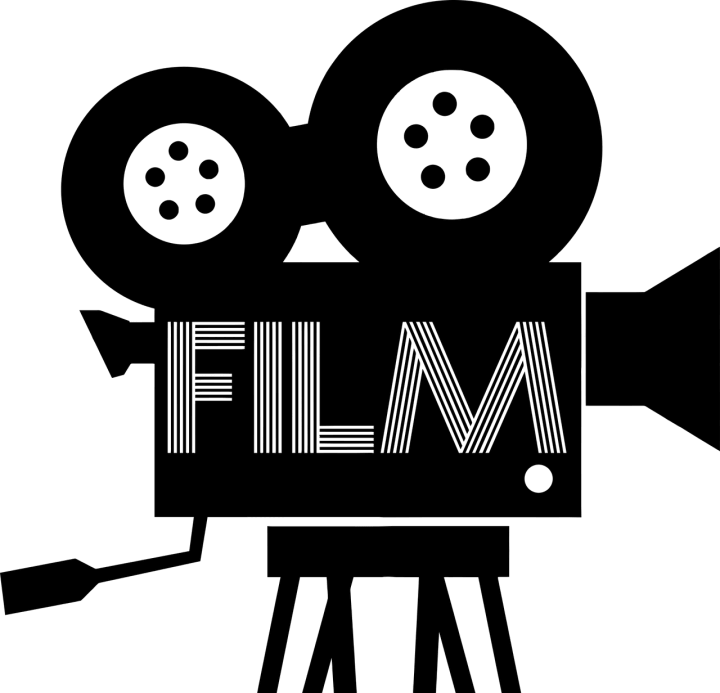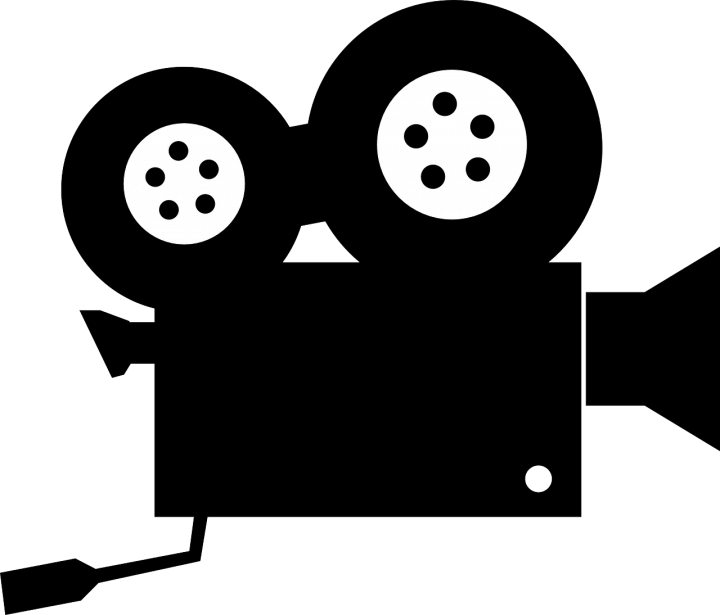第5スタジオは礼拝堂 第23章「終戦」
「プロローグ」はこちら
第1章:「それはチマッティ神父の買い物から始まった」はこちら
第2章:「マルチェリーノ、憧れの日本へ」はこちら
第3章:「コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ」はこちら
第4章:「暴風雨の中を上海、そして日本へ」はこちら
第5章:「ひと月の旅の末、ついに神戸に着く」
第6章:「帝都の玄関口、東京駅に救世主が現れた」
第7章:「東京・三河島で迎えた夜」
第8章:「今すぐイタリアに帰りなさい」
第9章:「今すぐ教会を出ていきなさい」
第10章:「大森での新生活がスタートした」
第11章:「初めての信徒」
第12章:「紙の町で、神の教えを広めることに」
第13章:「戦争の足音が近づいてきた」
第14章:「ベロテロ、ニューヨークに向かう」
第15章:「印刷の責任者に」
第16章:「イタリアの政変で苦境に」
第17章:「警察官と一緒にNHKに出勤」
第18章:「裏口から入ってきた警察署長」
第19章:「王子から四谷へ〜マルチェリーノの逮捕」
第20回:「本格的な空襲が始まる」
第21回:「東京大空襲」
第22章:「修道院も印刷所も出版社も」
第23章:「終戦」
あの日の光景はイメージで記憶している人が多い。玉音放送を生で聴いた人も、そうでない我々の世代も、「ギラギラと太陽が照りつける暑い日だった。」そんな刷り込みがある。東京都心でも「真夏日だった」「暑く無かった」など人によってずいぶん違う。気象情報は当時の国家最高機密の一つ。天気状況の次第で米軍も攻撃の可否を決める。都心の当日の気温は28度程度だったというのがもっとも確度が高そうなのだが、それも確たる証拠はない。人の記憶は様々。そしてあの日あの時、それぞれが取った行動も様々だ。320万人もの日本人の命が奪われ、他国にも攻め入り多くの命を奪った悲惨な戦争は、玉音放送を聴いて泣いて立ち尽くす人々のイメージも強いが、この玉音放送経験も人によって違う。
それぞれの玉音放送
戦後70年の年に、戦争体験者47人の方に話を聞いたのだが、その中には先日亡くなられた落語家の三遊亭金翁師匠、4代目金馬さんもいた。当時の思い出を滑稽話のように楽しく聞いたが、その中にも戦争の不条理さや愚かさという鋭いメッセージが随所にこめられていて、印象に残る話だった。もちろん玉音放送で敗戦を知り大泣きした方もいた。特に、当時まだ少年少女だった人たちは、神国日本の教育で育ってきたので大きなショックを受けた人が多かったように思う。一方、戦場に赴いた人たちは現実を目の当たりにしているので、現場を知らないエリート士官たちの戦術の無さを嘆いた人が多かった。そういえば電車に乗っていて玉音放送のことを知らなかった人や、終戦祝いの酒を飲んで万歳を叫び続ける父親を、兄と一緒に押し入れに閉じ込めた人もいた。サハリンでソ連兵に整列を命じられたが、列からそっと抜けて逃げ延びた人もいた。あるベテラン有名女優の方には、敗戦を知って青酸カリを手に皇居に向かったという経験を、電話で2時間以上伺ったのだが、放送では話したくないと言われた。広島原爆で被爆した方は、一面瓦礫の山で電気も通っておらずラジオも聴けない状況だったので、玉音放送のことを知ったのは終戦から1週間後だったそうだ(当時、乾電池で聴けるトランジスタラジオは無い)。

作家の近藤富枝さんの経験も面白かった。当時NHKのアナウンサーだった近藤さんは、玉音放送の中身の記憶は薄いが、前振りアナウンスを務めた先輩の和田信賢アナの喋りは鮮やかに記憶していた。ちなみに近藤さんは局舎を出て新橋駅に向かう途中、官庁街で、ひたすら重要書類を火にくべる職員たちの姿を目撃している。最近どこかで聞いたような話だ。歴史は繰り返される。とにかく、皆それぞれの終戦があった。そう言えば、近藤さんが勤務していたのは港区の愛宕山にあったNHKの局舎で、同時期にマルチェリーノたちもこの愛宕山局舎に勤務している。現在の渋谷・放送センターのような広大な局舎では無い。日常的に廊下ですれ違っていた可能性は高いし、ひょっとしたらマルチェリーノと近藤さんは顔見知りだったかもしれない。そのような話もぜひ聞いてみたかったが、近藤さんも2016年に鬼籍に入られたので、今となっては確かめようもない。
マルチェリーノの終戦は
長々と書いてきたが、肝心のマルチェリーノたちの終戦はどのようなものだったのだろう。実はそのことに触れた記述がない。四谷の修道院も焼かれ、信徒も神父も皆ばらばらになり、戦地から2度と戻らなかった信徒もいた。イタリアと日本の関係もまた、同盟国から敵国に変わり、さらに再び「形だけの味方」に戻ったが、愛憎まみえたまま敗戦を迎える。そのような中でも、マルチェリーノたちが日本を離れなかったのは、信仰のためだが、そうは言っても、面立ちの違う外国人たちが、戦争中の異国に身を置くのは不安がいっぱいだったと思う。
太平洋戦争が始まった当初、抑留の対象は敵国の成年男子だけだったが、そのうち女性にも拡大され、バドリオによるイタリアの降伏によって同盟国だったイタリア人も抑留の対象になった。さらに1945年になると、「ナチスではない」ドイツ人にも抑留の対象は拡大されている。その多くは、ナチスが弾圧を加えていたユダヤ系ドイツ人だ。リトアニアの領事だった杉原千畝が、ナチスドイツやソ連の弾圧に逃れようとする多くのユダヤ人のために「命のビザ」を発給したのは1940年の事だが、1941年にはゲシュタポが来日し、特高警察と協力してユダヤ系を中心とするドイツ人の監視も行っていた。日本にはユダヤ人に対する同情論が強かったので、ドイツによる「ユダヤ人に同情的な日本を見張る」という意味合いもあったのではないだろうか。この外国人抑留の歴史については、POW研究会(戦争捕虜研究会)のメンバーである小宮まゆみさん著の「敵国人抑留―戦時下の外国民間人 (歴史文化ライブラリー、吉川弘文館)」に詳しく書かれている。その小宮さんが「大正昭和カトリック教会史3」という書物の180ページから183ページにある、抑留扱いを受けたカトリック宣教師たちの一覧表を見つけて下さった。パリ外国宣教会の14人から始まって、聖ドミニコ会、サレジオ会と記載は続く。3番目のサレジオ会の名簿には、チマッティ神父の名前は無かった。サレジオ会のメンバーは、終戦間近の1945年7月に熊本県の栃ノ木というところに抑留されているのだが、全員が大分や宮崎の修道院にいた神父や修道士たちだ。当時、九州から遠く離れた東京・練馬の神学校に移っていたチマッティ神父は抑留を逃れることができた。サレジオ会の次は、コンベンツアル聖フランシスコ会。そして5番目に聖パウロ会があった。パウロ・マルチェリーノ42歳、ポアノ・カルロ36歳、グイド・パガニーニ34歳、キエザ・ジョヴァンニ32歳、ミケレ・トラポリーニ30歳と5人の名前が並んでいた。いずれも王子教会で昭和19年の9月9日から10月10日に抑留されたとある。多くのカトリック関係者は抑留所に送られ、それは、サンモール会、幼きイエズス会といった女子修道会も例外ではなかったが、聖パウロ会は修道会内での抑留、いわば軟禁状態。しかもこの年の5月、聖パウロ修道会は本拠を四谷に移転している。マルチェリーノは王子に留まっていたが、すでに本拠ではない王子教会への抑留(実質は軟禁)、しかも1ヵ月の期間限定の措置だった。王子警察署長の計らいがあったのか、マルチェリーノにより動きがあったのか、もう少し調べる必要があるだろうが、王子が米軍の空襲対象になっていたことを考えると、決して特別扱いだったとも言えないだろう。外国人抑留に関しては、先述の「敵国人抑留―戦時下の外国民間人 」が非常に詳しいので、機会があればお読み頂ければと思う。
この本の中で引用されているオランダ人抑留者アニー・レルスの手記「アニーの日本抑留日記」にこのような記述があった。「15日午後、愛知抑留所ではイタリア人が「戦争は終わった、戦争は終わった!」と叫んでいた。16日夕方にはイタリア人とオランダ人合同でささやかなパーティーを開いた。(中略) 翌朝イタリア人の神父は、戦争で亡くなった人びとすべてのために、ミサを行った。修道士コレッシとベンチヴェンニの歌声が気持ち良く響いた」
終戦の時点で、マルチェリーノたちは抑留はされていなかったものの、修道院も焼け落ちて、カトリック関係者に身を寄せていた。戦争が終わっても帰る家は無い。途方に暮れたままだったろう。しかし戦争が終わったことで、再び布教や使徒職活動に身を捧げることができると、マルチェリーノは考えたのではないか。ピンチをチャンスに変える名人だから。さて、これからどうやって聖パウロ修道会を立て直すのか、マルチェリーノの関心はその一点だけにあったに違いない。
次回に続く
-
Profile
-
1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか