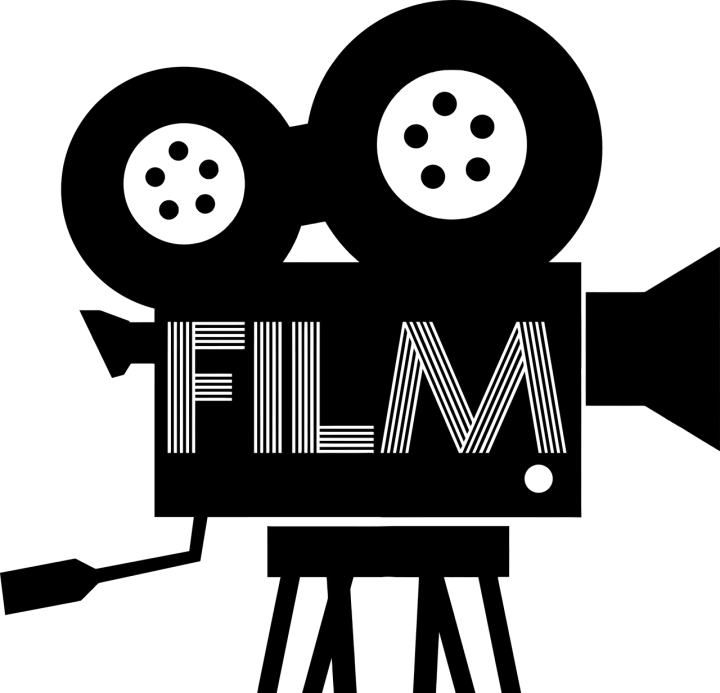第5スタジオは礼拝堂 第16章「イタリアの政変で苦境に」
「プロローグ」はこちら
第1章:「それはチマッティ神父の買い物から始まった」はこちら
第2章:「マルチェリーノ、憧れの日本へ」はこちら
第3章:「コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ」はこちら
第4章:「暴風雨の中を上海、そして日本へ」はこちら
第5章:「ひと月の旅の末、ついに神戸に着く」
第6章:「帝都の玄関口、東京駅に救世主が現れた」
第7章:「東京・三河島で迎えた夜」
第8章:「今すぐイタリアに帰りなさい」
第9章:「今すぐ教会を出ていきなさい」
第10章:「大森での新生活がスタートした」
第11章:「初めての信徒」
第12章:「紙の町で、神の教えを広めることに」
第13章:「戦争の足音が近づいてきた」
第14章:「ベロテロ、ニューヨークに向かう」
第15章:「印刷の責任者に」
第16章:イタリアの政変で苦境に
聖パウロ修道会のメンバーのうち、ベルテロだけが渡米。ニューヨークのスタテン島にあるアメリカ本部に腰を落ち着けて、宣教活動とともに、日本支部を立て直すための寄付集めに奔走していた。ベルテロも、渡米した当初は「真珠湾攻撃を仕掛けた日本の仲間」であるイタリア人ということで、偏見に悩まされることも多かったが、しばらくするとそうした見方も薄れてきた。それには、ベルテロの真面目な人間性も大きく寄与したが、ニューヨークのイタリア人社会がバックアップしてくれた部分も大きかった。同じ西洋社会という大きな土壌の中にあって、ましてや聖職者のベルテロが逆風を受ける理由はほぼ無かったのだ。少しずつ寄付集めも軌道に乗り、ベルテロはアメリカにおける新生活をまずまず順調に送ることができたと言える。一方、マルチェリーノやパガニーニら日本に残ったメンバーは違った。信徒の激減や食糧不足など極めて厳しい状況に置かれることとなった。日独伊三国同盟を結んでいる以上、日本とイタリアはもちろん敵ではない。しかし、互いに「仲間」と呼び合えるほどの連帯意識を持ってはいないのも事実であった。
ドイツと日本の間においても同様であった。「どこよりも優れたドイツ」と言うスローガンの下、ヨーロッパにおいても、アーリア人としての人種的優越心を隠さなかった当時のドイツ人が、極東の日本人を好きになる道理がない。1936年には現地で日本人の少女がドイツ人の少年に殴られると言うような事件も起きた。ヒットラーの「我が闘争」においても、明らかに日本人を侮蔑する表記が見られる。一方、日本においてもヒットラーを好きであったわけがない。訪独した高官が、ヒットラーと撮った記念写真を皆で眺めて話題にすると言うようなことはあったが、それは珍しいものを眺めるようなことであって、好きと言う感情値とは全く違う。当時の日本人は、同じちょび髭をつけていてもチャップリンの方をずっと愛していた。
 WikimediaImagesによるPixabayからの画像
WikimediaImagesによるPixabayからの画像
日独の連携はあくまでも国際情勢を鑑みた妥協の産物だった。大きな節目となったのが、1936年11月の日独防共協定の締結で、それに合わせる形で無理にでも日独が接近するため、双方の国民の親近感を高めねばならない。そこで着目されたのが「映画」であった。正確に言えば、合作映画の企画はすでに有り、それを知ったドイツの当局が、その企画に乗って支援したと言うのが実情のようだ。そうして防共協定締結の4ヶ月後に、1937年に日独合作映画「新しき土」が公開される。監督は山岳映画の名手、アーノルト・ファンク。主役のドイツ帰りの青年役には小杉勇。名優の早川雪洲も脇役で登場している。スタッフも山田耕作や北原白秋が音楽を担当し、円谷英二が撮影を担当するなど豪華な布陣だった。しかし、この映画において圧倒的な話題を集めたのはヒロインを演じた原節子だ。1937年3月10日、ドイツにおけるプレミアに出席するため原は東京駅からドイツに向けて出発する。チャップリンが来日した時と同様、東京駅は新進気鋭の若き女優が旅立つのを見送るため詰めかけた大観衆で膨れ上がった。王子教会における活動を軌道に乗せていたマルチェリーノたちもこのニュースのことを知っていたに違いない。日本中の話題だったからだ。そもそも日本人は映画が好きだ。戦前から溝口健二や黒澤明、内田吐夢、山中貞雄らが活躍して、映画スターも多かった。映画のレベルも高かったので、観客の目も肥えていた。
この「新しき土」は公開後、酷評が多く寄せられたと言う。しかし映画は大ヒットする。まずは国際映画という言葉の甘美さだ。日本はすごい国なのだという自信に当時の国民が酔いしれていたので、ドイツとの合作と言う表現には弱かった。阿蘇などを舞台にした映画をドイツ人監督がどのように撮影したのかと言う興味もあった。共同監督だった伊丹万作とファンクが方向性の違いで決裂し、ファンク版と伊丹版双方が作られたのも結果的に話題を呼んだ(ちなみにファンク版のタイトルは「サムライの娘」とされた)。プレミア出席のため原節子ら一行は下関から船に乗り、大連港に到着。満州鉄道、シベリア鉄道と乗り継いで一路ベルリンを目指した。欧州と日本を結ぶ最短ルートだが、それでも2週間かかったと言う。映画は日本の満州支配のプロパガンダの色彩も帯びているが、興味深いことに公開の時点ではドイツは満州国を承認していない。原節子はドイツ各地で大歓迎を受け、日本の印象を大いに高めて帰国した。原が戦後も小津安二郎の映画などでさらに才能を開花させたことは説明するまでもないが、一方、メガフォンをとったファンクや伊丹は、国策映画を製作したことで、戦後批判を受けることになる。
日本とイタリアの関係は
様々な思惑が混じり合い、時間も前後しながら「日独」と後に「伊」も加わる枢軸国の形が作られていったわけだが、日本とイタリアとの関係は、ドイツとほどには深く進んではいなかった。「ー億総火の玉」の日本にいては見えない事態がイタリアには存在した。それは国内における「反ファシズム」「反ムッソリーニ」の動きだ。そもそもイタリアは19世紀に多くの小国が統一されて生まれた国。地域によって顔立ちも違えば、気質も随分と違う。イタリア軍の内部でも、参戦には懐疑的な声も多かった。1943年春になると、枢軸国側が目に見えて劣勢になるにつれ、ムッソリーニの求心力は著しく低下していった。北アフリカ戦線においてイタリア軍が惨敗を喫し、連合国軍によるシチリア島への上陸が始まるとイタリアの敗北が決定的になる。国内ではムッソリーニのファシズム体制に批判が吹き荒れ始めた。
 そしてついに1943年の7月25日、ヴェネチアで5年ぶりに開かれた「ファシズム大評議会」において、ムッソリーニは失脚する。首相にはイタリアで尊敬を集めていた72歳の軍人バドリオが任命された。すぐさまバドリオ政権はイタリア全土に戒厳令を敷く。このバドリオ将軍に関しては、現在でも毀誉褒貶がある。というのも、「彼は、第二次大戦への参戦に賛成だった」と証言するものと、「最初から反対だった」と証言するものがいて、今も歴史的な結論は出ていないのだ。ただ、実際に戦争の現場を知るバドリオとしては、軍人出身ではないムッソリーニの稚拙な戦略は我慢できないものだったことは間違いない。1943年の時点で、このまま戦争を続ければ国土は荒廃するという確信にも至っていた。そのような気運の中、ついに政変が起き、ムッソリーニは身柄を拘束されてしまう。
そしてついに1943年の7月25日、ヴェネチアで5年ぶりに開かれた「ファシズム大評議会」において、ムッソリーニは失脚する。首相にはイタリアで尊敬を集めていた72歳の軍人バドリオが任命された。すぐさまバドリオ政権はイタリア全土に戒厳令を敷く。このバドリオ将軍に関しては、現在でも毀誉褒貶がある。というのも、「彼は、第二次大戦への参戦に賛成だった」と証言するものと、「最初から反対だった」と証言するものがいて、今も歴史的な結論は出ていないのだ。ただ、実際に戦争の現場を知るバドリオとしては、軍人出身ではないムッソリーニの稚拙な戦略は我慢できないものだったことは間違いない。1943年の時点で、このまま戦争を続ければ国土は荒廃するという確信にも至っていた。そのような気運の中、ついに政変が起き、ムッソリーニは身柄を拘束されてしまう。
代わって首相に任命されたバドリオは、表面的には戦争の継続を標榜していたものの、実は密かに国王と意思の疎通をはかりながら、連合国側と水面下で交渉を開始していた。一方、ヒットラーも当初からバドリオの寝返りを警戒し、すぐにイタリアに向けて進駐する準備を進めていた。そしてドイツの予感は的中する。9月3日、秘密裏にイタリアと連合国の休戦協定が結ばれたのだ。これによりイタリアは終戦にあと一歩まで近づいたが、ここで予想していなかった事態が起きてしまう。9月8日、連合軍総司令官(のちのアメリカ大統領)、ドワイト・アイゼンハワー将軍が、イタリア側の承諾なしに突然、イタリアの無条件降伏を発表してしまったのだ。「やはり、寝返ったか」ヒトラーは、激怒し、すぐさまドイツ軍をローマに進撃させる。それを知った国王エマヌエーレ3世と首相のバドリオらは慌てて避難することになった。彼らが逃走した先は、マルチェリーノたちが1934年、日本を目指して「コンテ・ヴェルデ号」に乗り込んだイタリア南東部のブリンディジだ。マルチェリーノたちが、期待と不安に胸を膨らませ海を眺めた美しい港町は、その9年後、ナチスドイツに追われたイタリア国王と新首相が逃げ延びる場所という予想もしていなかった形で歴史の舞台になった。そしてその瞬間、イタリアは日本の「敵国」になった。
警察が修道院に突然姿を見せる
アイゼンハワーが口を滑らせた日から2日後。1943年9月10日の朝8時半ごろ、王子警察署の警察官が北区・王子の修道院に突然姿を見せた。ベルテロの手記「日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち」から抜粋する。
「九月十日の朝八時半ごろだった。私はヒゲを剃るための準備をしていた。何気なく窓から外を見ると、見知らぬ男が家と印刷所の間の狭い隙間を通り抜けて、中庭に入り込もうとしているのが見えた。その見知らぬ男は私に気づくと立ち止まり、ジロジロと無遠慮に私を見た。私も彼を見つめた。そして彼に「何か用か」と尋ねようとしたその時、私は誰かに応接室に呼ばれた。かみそりとタオルを置いて私は応接間に向かった。応接室はパウロ神父(マルチェリーノ)の事務室にも使われていたのである。そこにはすでに、パガニーニ神父とキエザ神父、そしてミケーレ修道士が来ていた。パウロ神父は、朝早く「カトリック・プレスセンター」に出かけていて留守であった。」
「パウロ神父は緊急の電話で修道院に呼び戻された。応接室には見たことのない男たちがいた。私はすぐに彼らが王子警察署の署長と二人の警官だと分かった。私が部屋に入った時、署長はもう話し始めていた。パガニーニ神父が私に、事態をかいつまんで説明した。すなわち、イタリアが戦闘を中止し分離休戦を願い出た。こうしてイタリアは、日本とドイツとの同盟関係を裏切ったのだと。署長は続けて、日本政府はイタリア人を裏切り者と見なし、決定的な措置が取られるまで、お前たちは自分たちの管轄下に置かれる。すなわち、お前たちは警官の同伴がなければ外出することができず、他人の訪問を受けることも電話をかけることもできなくなる。幼稚園と教会は新たに命令が出るまで閉鎖される。この命令が厳格に守られるよう警官が一人、常時、修道院の門に見張りとして残ることになる、と。パウロ神父が戻った時、彼も署長の説明をじっと我慢して聞いていなければならなかった。それは私たちの共同体の責任者にとって、極めて厳しい通達であった。」
「味方だった日本が、敵国に変わる」と言う思いもよらぬ災難が、日本のイタリア人社会全体に降り注いだ。もっとも厳しい監視下に置かれたのは、言うまでもなく公的な機関だ。日本政府は、大使館などイタリア公館の外部からの監視を行うとともに、徹底的な職員の外出制限を科した。逃げることができないように、イタリア人職員たちは、自家用車を使うことを禁じられ、本国との連絡路を断つため電話も切断された。さらには郵便や電信の配達も止められてしまう。治外法権が認められているはずの公館に対するこういった非常識なやり方は国際法上許されるはずがないが、当時の日本が、戦況悪化の中、正常な判断力を無くしていたことの証左であろう。そして一般のイタリア人に対しても、公館員に準じる形で厳しい措置が取られることになった。その被害者がまさに、マルチェリーノたちであったのだ。
-
Profile
-
1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか