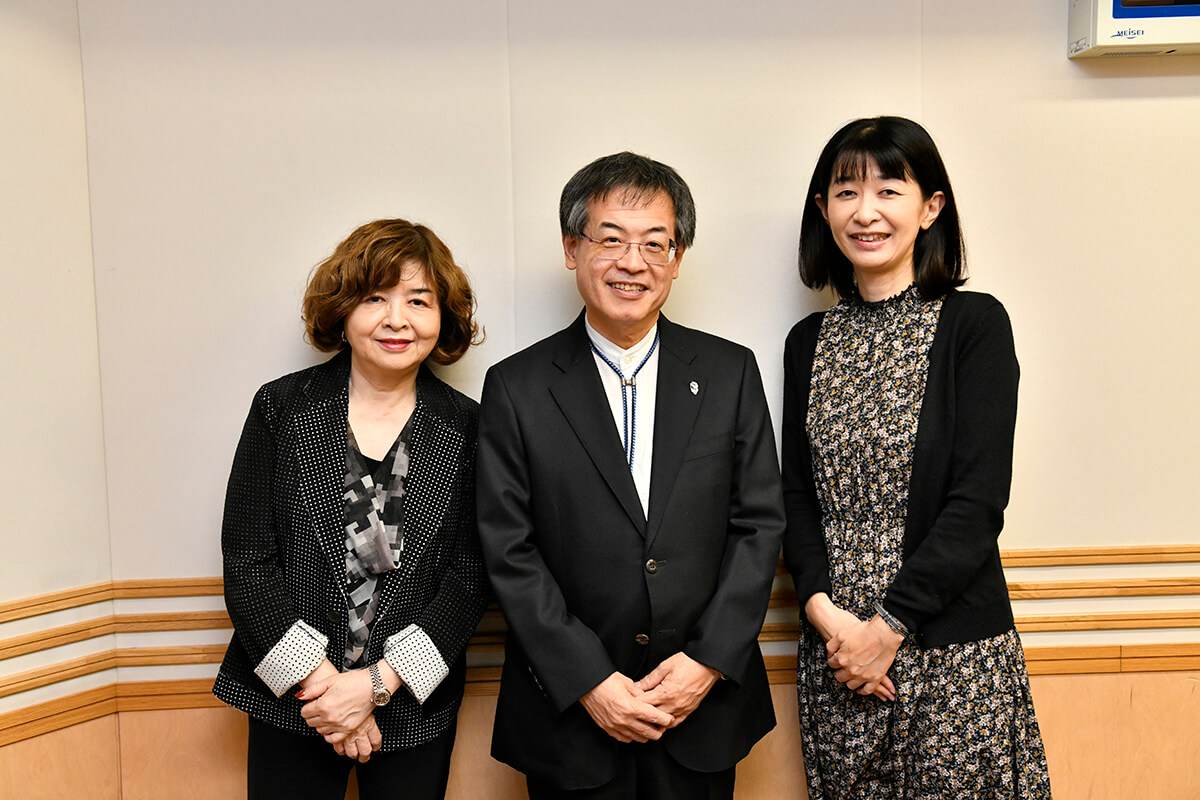『大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ』 庵功雄さんを迎えて
情報番組「大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ」では、残間里江子さん(フリープロデューサー)と、大垣尚司さん(青山学院大学教授、移住・住みかえ支援機構代表理事)が、お金や住まいの話を中心に、大人世代のあれこれを語ります。
この連載は、番組内の人気コーナー「おとなライフ・アカデミー2025」の内容をもとに大垣さんが執筆した、WEB限定コラム。ラジオと合わせて、読んで得する家とお金の豆知識をお楽しみください。
今回は特別編。「やさしい日本語」の提唱者で一橋大学国際教育交流センター教授の、庵功雄さんをゲストにお迎えした、2025年2月8日放送のダイジェストをご紹介します!
<庵功雄さん プロフィール>
・大阪大学大学院博士課程修了後、大阪大学助手、一橋大学講師、准教授を経て現在は一橋大学国際教育交流センター教授。専門は日本語教育、日本語学。「やさしい日本語」研究グループ代表。著書に「やさしい日本語 多文化共生社会へ」など。
そもそも「やさしい日本語」とは
鈴木 そもそも「やさしい日本語」というのは、どういうことなんでしょう。
庵 外国人にはいろいろな人がいますけども、日本語の能力もいろいろです。まだ、あんまり日本語に慣れていない人とコミュニケーションするときに、相手の母語はいろいろなので、日本語でやった方がいいということです。そのときに我々がふだん話している日本語でそのまま話しても相手には難しいので、両方が折り合いをつけて話せる言葉として「やさしい日本語」というのを考える ということです。
残間 「やさしい」というのは、「心優しい」の「優しい」と、簡単な、という意味の「易しい」とありますが、両方の意味ですか?
庵 そうですね。日本語は、ひらがなだと両方の意味にとれるので、ひらがなで書くようにしています。
鈴木 ダブル・ミーニングなんですね。ここ数年、外国人の労働者の方が増えてきましたが、「やさしい日本語」の取り組みは、成果が上がってきていますか?
庵 だいたい私たちのグループが始めたのが20年近く前です。最初のきっかけは、私たちの前の世代の方がやられたのですが、阪神淡路大震災のときですね。そのとき、私も大阪だったので、地震のことはけっこう知っていますが、やはりあの時、復興過程でいろんな情報が出たとき基本的には日本語と英語でしか出ませんでした。そのほか中国語や韓国語は地域で回るとしても、それ以外の言葉はよくわからない状態になってしまったわけです。その時にこれはまずい、ということで、大きな災害のときなどに簡単な言葉でやる、それを「やさしい日本語」と名付けたわけです。それが、私たちの先生の世代がやられたことなんですけど。それを受けて、じゃあ一般の普通のときにもやっていこう、ということで始まりました。
大垣 残間さん、これ知ってた? 「やさしい日本語」ということば自体。知らなかったでしょう? こんな大事なことなのに、私も恥ずかしながら今回、たまたまこの本を読んで。でも「やさしい日本」というカギカッコつきのは、スローガンというのか…。
残間 概念としては、なかなかね。
大垣 でも、いま、ヘタしたらインバウンドに頼って日本経済を立てていかないとどうしようもない、ぐらいのことを言われてますからね。
残間 鈴木さんも私も、アナウンサー出身だとなるべくわかりやすく音で示すには、漢字とか熟語とか使わないで、かなで話しましょうと…。
「けさ」は×、「今日の朝」が〇
大垣 「やさしい」がいい例ですよね。漢字を充てないと意味が分からないような言葉は使わない、というか、わかりやすくしゃべってあげないといけない、ということですよね。だから「かんたんな」と言い換えたほうがいいわけですね、おそらく…。
庵 そこはむしろ、逆で、中国語みたいに漢字をベースで使うところと、そうでないところでだいぶ違うんですね。
大垣 漢語でしゃべる、和語でしゃべるというと、和語のほうが簡単だと、日本人的には思いますけれども、外国人の方もうそうなんですか?
庵 それは中国語系とそうでないところでだいぶ違います。中国語系はやはり漢語のほうがいいんですけど、ただ漢語も発音がずれているので、耳で聞いたときにわかるかどうか。目で見るのはいいんですけど。
鈴木 庵さんのご本を読んで「けさ」と言われてもわからない、「きょうの朝」と言われるとわかると。こういう一言からして違うんだなと思いました。
大垣 僕ら「かんたんに」といわれるとゆっくりはしゃべれるけど、どう翻訳すればわかりやすいかというのは、わからないですね。
庵 そのあたりは、多少マニュアルはあるんですが、大事なのは結局「相手を見て話す」というか…。要するに、書くときは別ですが、話すときは相手がわかってるかどうかを確認しながら話すとかですね。「どうやったらやさしい日本語になりますか」とよく聞かれます。たとえば耳が遠いお年寄りと話すときは「大きな声でゆっくり」。子どもと話すときは「子どもがわかるような言い方に言い換える」ということをしますけど。それは「どうしたらできますか」とは聞かないですよね。お年寄りと話すときはどうするか、とか。でもそれが「やさしい日本語」なわけです。それを外国人相手でも…日本語が十分じゃないときでも、伝わるためにはどうするか、ということを考えてやるかどうか。だからアクションを…なぜそういう調整をするかといえば、自分のことを知ってほしいとか、相手のことを知りたいと思うからでしょう。ですから外国人相手でもそういう風に考えられれば、たぶん…この人と何かいま話したいとか、この人が困ってるみたいだから助けてあげたいとか、そういう気持ちだったら言葉を選んで話すということがあるので。まずそういう気持ちになるかどうかってことが、より重要なのではないかと思います。
日本人は英語で話そうとする
大垣 面白いなと思うのは、アメリカに行きますでしょう。アメリカ人って絶対「やさしい英語」をしゃべろうとはしませんよね。「人間は英語をしゃべれ」みたいな感じで、ナチュラル・スピードで話しかけてきます。日本人は逆でね、とくにアメリカ人、白人の方とか見るとなんとか英語でしゃべろうとするか、もうしゃべらないかで。急に日本語でしゃべりかけられるとかえって「違うだろう」みたいな雰囲気になってて。でもみんな当然に日本語をやさしくしゃべってあげるというのが、外国人が目の前に来たときの、第一行動だと思ってないですよね。
庵 そうですね。そういうところはあると思います。
大垣 英語をしゃべらないといけないんじゃないかとプレッシャーがかかって、助けてあげたいけど、ちょっと引いて誰か出るのを待とう、みたいな。だから素直に入ってって、ただ当然日本にいるんだから俺が日本語をしゃべるけど、わかりにくいだろうからゆっくりしゃべってあげるよ、という風に思わないですよね。
残間 英語に対するコンプレックスがあるんじゃないの?
庵 そこが、まずは関門ではあるんですね。
大垣 そのあと、初めて「やさしく」ね。すごく短い時間なんですけど、いろいろ教えてらっしゃるということなんで、リスナーの方にちょっとしたコツというか…こういう風にやると、外国人の方にわかりやすい言葉になるというのはありますか?
庵 尊敬語とか謙譲語を一切抜く、ということですね。です、ますだけにする。
大垣 「食べますか?」はいいけど、「召し上がりますか?」はいけない。
庵 そうですね。食べるは知ってるんですけど、召し上がるは知らないから…。
大垣 でもやっぱり「召し上がりますか?」って言いますよね。
残間 乱暴な気がするからね。
鈴木 外国からいらした方だし。
大垣 でも丁寧語をしゃべるとわからなくなる。
庵 そうですね。全然違う言葉ですよね。「食べる」と「召し上がる」、客観的に見たら似てないですから。それをまずやめるとか、カタカナ語もできたらやめた方がいいですね。
残間 カタカナ語を英語だと思ってる人がいるからね。
大垣 和製英語はわけがわからない。
センテンスはとにかく「短く」
大垣 あとは何かありますか?
庵 文をとにかく短くするということですね。日本語の話し言葉は、ほっとくと、どんどんどんどんつながっていくので。ここで終わり、っていうことをとにかくはっきりさせて。「…です」「…ます」で言い切って次の話にする。聞く方からすると「ここで終わり」というのがわかる。そういうのもとても大事だと思います。
大垣 あとは外国人の方が、日本語をどう教わっているかを知らないから。何が「基礎日本語」かを知らないので、基礎日本語で喋ろうと思っても知識がないですよね。一般的にはどういう風に習うものなんですか?
庵 日本語は日本語で教えます。英語で教えたりはしないので。それこそ、「あいうえお」から、「私は何々です」というところから始めて。要するに教室で習う言葉だけで説明を進めていくという形でやっていくんですね。日本の子どもが身に着けるのと一番大きな違いは、日本の2,3歳の子どもは「ですます」から始めない。「好きです」とは言わないで「好き」だけですよね。外国人が習う日本語は必ず「です」「ます」から始めます。それである程度、初級が終わったぐらいで、いわゆる「タメ口」にあたる「です」「ます」がない形の話し方に入るっていう。そこも大きな違いですね。
残間 単語だけでも通じるもんね。英語だと。でも日本語教えるときに「寿司」とか言うけど、寿司のどれが好きとかいうのを聞くときにみんなためらうよね。それこそ「召し上がりますか」って言いかねない。
大垣 絶対言いますよね。でも「なに食べますか」って言わないとわからない。
庵 そうですね。
大垣 こういうのは国民常識みたいにしていかないと行けないような気がするんですが。どこか見るとアンチョコがあるとか、そういうのはあるんですか?
庵 けっこう今は、いろんな自治体が「やさしい日本語」でお知らせを出したりしていて、そういうのは作られてきています。ただ国としてやっているということではないので。国としてやってるというのは、ガイドラインを作っているのはあります。ただそれでも、日本語教育を国とか自治体とか企業が責任をもってやるべきだ、という法律はできたんです。それをどう活かしていくかなんですけど。やはりそこは住民もこういうことが必要だっていうふうに言ってもらうことすごくが大事ですね。
大垣 場所によっては、外国からいらした方がずいぶんの人口になってますよね。最近は地方のほうでもあるわけですから。こういうことを知ってるのと、知らないのとでは、ずいぶん違いますよね。
大切なのは相手を思う気持ち
残間 庵さんはどうしてこういうことを研究しようと思ったんですか?
庵 もともと、高校のころに新聞記事で、インドかどこかだったと思うんですが、女の子が女の子だから勉強ができないという話があって。それがどうして日本語教育につながったのかよくわからないのですが…。そういう人をなんとか助けたいっていうようなことを思って。そのとき、自分にできることってなんだろうと思って、「日本語を教える」ということをやりたいと思いました。当時はあまり各地の大学にそういう講座があるわけではなかったので、大阪大学に行った…っていう感じですね。
大垣 ものすごく大事な話だと思うんですけど。私は岩波新書の「やさしい日本語」を読んだんですけど。先生がいろいろお書きになってる中で、リスナーに「これ読んどけよ」というのはありますか(笑)。
庵 (笑)とりあえず、この岩波の本を読んでいただくと概略はわかります。「やさしい日本語は、基本的には外国人のための行動でもあるんですけど、もう一つ日本人の問題としても…日本語の表現の問題としてもあるんです。たとえばお医者さんが患者に説明するときの言葉がわかりにくいのは、やっぱりそれは外国人だからわからないんじゃなくて、日本人でもわからないということがあります。やっぱりそういうのは、日本人側にも、なんとなく難し気な言葉を使っている方が、頭がよく見える…というようなことがあるんだと思うんです。だからそういうのをとりあえず取っ払って、日本語として大事なのは「とにかくわかりやすい」とか、「論理だてて、筋道立ててって」ということを評価の基準にする…。
残間 一番大事なのは政治家ですね。
庵 そうですね(笑)。
大垣 官僚もだよ。先生、これ「やさしい日本語検定」とかやられてはどうですか?
庵 そういう風にするのもあると思います。でも、やっぱりさっきも申し上げましたように、少なくとも外国人向けの「やさしい日本語」っていうのは、気持ちがまず大事なので。そこを…
大垣 そう思ってない人多いよね。親切な人はとにかく親切だから、自然とそうなるかもしれないけど。
鈴木 そういう気持ちを広げていきたいですね。
庵 そうですね。
残間 いまおっしゃったことが広がると、もっと柔らかな感じの人間関係になりますよね。
大垣 これ、もっともっと広がっていないといけない話だと思いました。
残間 大学の先生も偉そうな人多いよ。
大垣 私なんか難しくしゃべらないと、そんなもん、権威が…(笑)。
鈴木 それじゃダメっていうお話ですよね。
庵 そうですね(笑)。
大垣尚司 プロフィール
青山学院大学 法学部教授、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構代表理事。
第一線で培った金融知識をもとに、住宅資産の有効活用を研究・探究する、家とお金のエキスパート。
東京大学卒業後、日本興業銀行、アクサ生命保険専務執行役員、日本住宅ローン社長、立命館大学大学院教授などを経て、現在、青山学院大学法学部教授。
2006年に「有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構」(現、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構)の代表理事に就任。
日本モーゲージバンカー協議会代表理事を兼務。著書に『ストラクチャードファイナンス入門』『金融と法』『49歳からのお金ー住宅・保険をキャッシュに換える』『建築女子が聞く 住まいの金融と税制』『生きづらい時代のキャリアデザインの教科書』など。
家とお金に関するご質問、お待ちしてます
番組では、家とお金にまつわるメールやご質問をお待ちしています。
宛先は、otona@joqr.netまで。
※この記事で掲載されている情報は全て、執筆時における情報を元にご紹介しています。必ず最新の情報をご確認ください
お知らせ
パーソナリティの一人である大垣尚司さんが代表理事を務める一般社団法人「移住・住みかえ支援機構」(JTI)では、賃貸制度「マイホーム借上げ制度」を運用しています。
住まなくなった皆さまの家をJTIが借り上げて、賃貸として運用。
入居者がいない空室時でも、毎月賃料を受け取ることができます。
JTIは非営利の公的機関であり、運営には国の基金が設定されています。
賃料の査定や、ご相談は無料。資格を持ったスタッフが対応いたします。
制度についての詳しい情報は、移住・住みかえ支援機構のサイトをご覧ください。
関連記事
この記事の番組情報

大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ
土 6:25~6:50
楽しいセカンドライフを送るためのご提案などがたっぷり! 金融・住宅のプロフェッショナル大垣尚司と、フリープロデューサー残間里江子が 大人の目線でお届けします。…