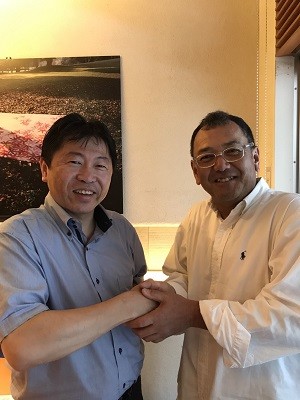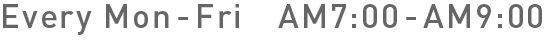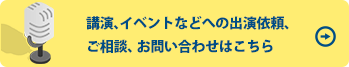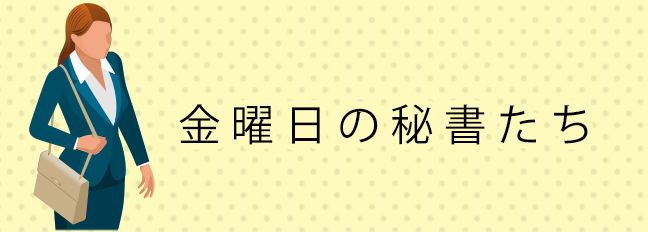文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビューで今回お話を伺うのは山形県鶴岡市のイタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ・奥田政行さん。地元・庄内産の食材を使って自由自在においしい料理に仕立てる奥田マジックは国内だけでなく世界からも注目を集めています。番組パーソナリティでもあり、スポーツマネジメントを学んだゴルフ解説者のタケ小山が奥田シェフの果てることのないパワーと魅力の根底にある”想い”を探ります。
◆「30秒」で決めた未来

山形の海の近くでドライブインを経営する両親のもとに育った奥田シェフは、子どもの頃から親の働く姿を間近で見つめてきた。「24時間営業のレストランだったから、忙しくなると『おい、手伝ってくれ』と、駆り出されるんです。小学校4年生の頃から、調理場に立ってカツ丼やラーメンなどを作っていましたね」。そのおかげもあって、高校の文化祭の屋台では同級生が調理に四苦八苦する中、いとも簡単にひょいひょいっと軽快にメニューにある品を作って賞賛をあびたという。
「じゃあ、将来の夢はやはり料理人だったんですか?」
そう問うタケに、ニッコリ笑って「いや。絶対に料理人にはなりたくないと思っていたんです。年中忙しい親の手伝いばかりさせられていたから、こんな仕事はいやだなって思ってました」と答える奥田シェフ。「だから、高校三年生になって進路希望を記入するときには、得意だったコンピューターの分野に進むつもりだったんです」。なんと、当時の奥田少年はプログラムを自分で組めるほど、コンピューターに精通していたのだ。
「えっ?じゃあ、どうして今シェフに…?」と驚くタケだったが、実はこの話には最後の30秒のどんでん返しが待っていた。
「あと30秒で提出、という時になって自分の中に流れる『血』にスイッチが入ったんでしょうか、ぎりぎりになって書いたのは東京のフランス料理店の名前でした」。フランス料理を選んだのは、その頃全盛を極めていたこともあるが「親父が和食をやっていたから、同じ道だと一生あれこれ説教されそうでしょ。それがイヤだったから」と軽やかに笑う。
そして、上京。東京の渋谷にあったレストランでの修業が始まる。「フランス料理を希望していたのに、配属されたのはイタリアンでした」。当時はイタリアンというのはまだまだヨーロッパの郷土料理の一つという程度の位置づけで、家庭料理に近いものだった。「マヨネーズやバジルのペーストを作るのに、ミキサーじゃなくてすり鉢とすりこぎを使って手作業で作ってましたからね」。
ところが、その後、日本ではイタリアン大ブームが起こる。「あれよあれよという間にイタリアンが注目され、カッコいい!と人気を集めて流行り出したんです」。奥田シェフと日本におけるイタリア料理は、ともに成長してきたというわけだ。
◆「あと一点」ですべてが変わる

奥田シェフには、今も忘れることのない学生時代のあるシーンの記憶がある。
「高校生の頃、バドミントンに夢中で必死で練習もしたのでかなり上手になって、1年生の後半からはレギュラーになって試合に出してもらっていたんです」。どんなことでも夢中になると、寝食も忘れて取り組む性格なのだ。「2年生の終りのインターハイ予選では、インターハイ選手との試合で『あと一点』で勝つ、というところまでいったんです」。だが、相手の選手を応援する人たちに囲まれて完全にアウェイの環境の中であと一点が取れずに、ついにひっくり返されて負けてしまった。話を聞きながら「ああっ」と残念がるタケ。
「だけど、その後も大人に混じって練習を続けて自信もあったから先生に『国体予選に出してください』とお願いしたんです」という奥田シェフに、「おっ、いいですねぇ」とすっかり応援モード。
「でも、出られなかったんですよ」。
なんと、国体予選の日程は修学旅行と重なっていたのだ。国体予選の方にどうしても出たいと懇願した奥田シェフだったが、先生からはいともあっさりと「何を言ってるんだ、国体予選に出たって勝てるわけない。無理に決まってる」と言われてしまった。
結果、修学旅行先の台湾で友人たちとのふざけが過ぎて、あわや退学?の危機に瀕することになってしまった奥田シェフは、「その時に学習したんです」とこう続けた。「あの時、一点を取れなかったから試合に負けて、一気に転がり落ちた。チャンスは絶対に取らないといけない。男は結果を出さないと、引き上げてもらえない」
この時に見つけた”真実”は、この後もずっと奥田シェフの人生を支えることになった。
◆1億3000万円の負債を抱えて

東京のレストラン万葉会館のイタリアン部門で働きだした奥田シェフだったが、ある日友人と食事をしたフランス料理店のジャガイモ料理の美しさとおいしさに出会ったことで、やはりフレンチをやりたいという想いが再燃した。「すぐにそのお店で働かせてくださいってお願いしたんですが、断られたんです」。そこで、こう考えた。「フランス菓子の勉強をしよう。デザートが作れれば、きっと雇ってもらえる」。
思い立ったら行動の人である奥田シェフは、そのあとすぐにフランス菓子のお店で修行を始めた。イタリアンで働きながらの二足目のわらじ、しかも「ただ働きで勉強させてもらったんです」。
忙しくも夢に向かって順調に進んでいた奥田シェフに、ある日、一本の電話がかかった。父親が経営コンサルティングを名乗る人物にだまされて小切手を悪用されたために、1億3000万円の負債を抱えてしまったという連絡だった。驚いて帰省すると、それまでは「困っている人がいたら助けるんだよ」と言っていた父が、すっかり人間不信になっていた。二十数人いた従業員のほとんどが店を去って、残ってくれたのはたった一人という状況だった。父親と一緒に借金の後始末で駆けずり回りながら、奥田シェフは父親にこう宣言したという。「店は、今はいったんあきらめよう。でもいつか俺が必ず再興するから」。
そのとき、”魂”のスイッチが入った。「奥田家を再び復活させるために、俺がやっていかないといけない」
1億3000万円もの借金、どうすれば返せるのか?考え抜いて出して結論は「人に使われていては、一生かかっても無理だ」ということだった。と同時に、お世話になってきた鶴岡に恩返しもしたかった。「いつか鶴岡に帰って自分がオーナーになろうと決めました。逆算すると、そのタイムリミットは25歳。残り3年半でした」。
◆「どんなときも」を聴きながら
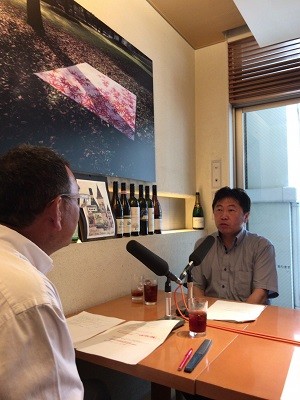
小学生の頃から調理をしていた奥田シェフは、東京での修業中も同僚たちに比べて格段に器用で「みんなが30分かかるところを10分くらいで終えられて、楽勝って感じだったんです」と笑う。右手と左手を両方同じように使えるというのも、大きな武器となった。
だが、25歳までに鶴岡に帰り、いずれはオーナーになるという新しい目標を持ったことで「もっと厳しいところでの修業が必要だ」と考えるようになった。
そして選んだのが、VIPを顧客に持つ超高級レストラン。その料理を任されていた30代の気鋭のシェフは、優秀な人であったが相当なプレッシャーを抱えていることもあって、弟子に対して非常に厳しい人物であった。「シェフを怒らせないように、機嫌を損ねないように、毎日意識を集中させていました」。
調理場に入ってくるときのドアのノブのまわり方でその日の機嫌を読み取り、足音や姿勢から感情を察したという。「朝一番に出す飲み物を何にするかも、様子を見ながら必死で考えるんです。毎日が真剣勝負でした」。厳しく叱責されてもシェフのことを嫌いになってはいけないと写真を常に持ち歩き、自らの気持ちを盛り上げるために出勤時にはロッキーやトップガンのテーマを聞いていた。
「今振り返ると、他の一切合財を捨てて料理道に突き進んでいたなぁと思います」。
当時のヒット曲「どんなときも」の歌詞をマネして鏡の前で笑顔の練習も繰り返した。
「どんな時も満面の笑みで挨拶するようにしていたんです。最初は偽りの笑顔でしたが、気がつけば本当の自分の笑顔になりました」。
「確かに、奥田さんのニコニコ顔は本当に素晴らしい」とタケも釣られて満面の笑みに。
◆「目の前のことを一生懸命やっただけ」

修行の場で「奥田、これできるか?」と問われたときには、必ずすぐに「はい」と答えた。
「本当はできないんだけど『できます!』と答えて、次の日までにできるように猛勉強していく。そんなことをくり返していました」。その努力もあって、皿洗いから始まった修行の日々は、野菜の下処理、野菜の切り出し、火を使えるようになって魚や肉も扱えるようになり、フレンチの花形ともいえるソースづくりまで担当できるようになっていった。
その後、計画通り25歳で鶴岡に戻った奥田シェフは鶴岡駅周辺が自分の学生時代に比べて閑散としていることにショックを受けた。「誰も歩いていなくて、寂しくなってしまった」。だから、その時、「この町を食で元気にする!」と宣言したのだ。「誰に?」と突っ込むタケに「駅前の通りに向かって、です」とひょうひょうと答える奥田シェフ、その足で駅前のホテルのレストランに入り、そこで働くことを決めた。「席数が11テーブルで36と、ちょうどよかったんです」。この数字は奥田シェフいわく「黄金法則」にのっとっているという。「流行っている店は、たいてい同じですよ」。
だが、自ら選んで入ったこの店で奥田シェフはイジメにあった。「仕事が出来過ぎて、しかも真面目に働き過ぎるからけむたがられたんでしょうね」。
例えばこんなことがあった。
休憩も取らずに働いていると、バチンと電気を消されてしまう。暗い中では調理の下ごしらえなどはできないから、「仕方ないから、牛乳パックを切り開いてスーパーの回収ボックスに持っていくことを続けていたんです」。毎日飽きもせずに続けていたら、洗い場のパートの女性たちが「あんた、えらいね」と手伝ってくれることになり、「気がつけば、パートの女性に囲まれて大牛乳パック切り開き大会ですよ」と、本当に奥田シェフの話にはいつも明るい笑いがつきまとう。さらに、そんな様子を見ていた若いスタッフの信頼も得て、一年半後には調理長に命じられることになった。素晴らしい大出世! だが、「みんなにチヤホヤされて、かえって居心地がよくなくて辞めちゃったんですよ」。
「もったいない…」とつぶやきつつも、タケは次の行動が気になる様子。「で、どうしたんです?」
次に奥田シェフが選んだのは農家レストラン。これが、まさにアル・ケッチァーノに続く道だった。
◆どんなに八方ふさがりでも、必ず小さな光はある

農家レストランで、地元の野菜や山菜などについての知識を深めた奥田シェフは、ついに鶴岡に自分の店「アル・ケッチァーノ」を開業する。「資金はたった150万円。今の店がある場所のもっと脇の方、家賃10万円の元喫茶店だった店舗でスタートしました。とにかくお金がないから、お皿もワイングラスも100円ショップで揃えました。ただしウェルカムプレートだけは5000円のものにしたんです。そうするとね、みんな後に出てくる100円のお皿までいいものに思ってくれるんですよ」。工夫は、さらに続く。「壁に飾る絵は、額だけはいいものを買ってきて中の絵は画集から切り抜いていて入れました。メニューを作るお金もなくて、毎日黒板にその日のメニューを書いていたら、その頃アラカルトで100種類くらい用意していたから『すごい!』って評判になったりもして」と笑う。また、料理に使うハーブを買うお金がなくて、その代わりになるものを山から探してきて使っていたら、アウトドア雑誌に「日本の野草を使いこなす天才的なシェフがいる」と取り上げられたこともあった。
「どんなに八方ふさがりの状況でも、必ず小さな光はある」と奥田シェフ。「その光に向かってまっすぐに走っていれば、ある時突然、オセロの黒の駒が白にパッと変わる瞬間がやってくる」。
あきらめてしまったら、完全に暗闇に入ってしまう。光が見えないな、と思っても必ずどこかに打開策はあるんだと力強く語るのには確かな理由がある。「だって、これまで、いつでもそうだったから」。
奥田シェフだって、決して順風満帆の道を歩んできたわけではない。「まっ暗闇に入ったとことが、これまでに4回あります」。でも、そのたびに目の前のことに最大限の力を注ぎ、小さな光を探して、見つけて、まっすぐに歩んできた。高校生時代のバドミントンの試合での「あと一点」の悔しさを忘れずに、チャンスをつかむための努力を重ねてきたのだ。
◆頼まれごとは「120点で返す」という心意気

アル・ケッチァーノには連日全国から客が押し寄せるようになり、いつのまにか押しも押されもせぬ有名シェフとなった奥田シェフ。気がつけば、海外からのオファーも多く入るようになっていた。「お前の料理は面白い、という評価を海外からももらえるようになったんです」。その代表となる料理は日本のお米を使ったリゾットだ。一般的にはリゾットには日本の水分の多いお米は向かないとされているが、「日本のお米は世界一おいしいんだから、それで作ったリゾットも世界一おいしいはずなんです。ただ、べチャッとならないように、いろいろな工夫はしています」。
頼まれたことに対して「必ず120点で返す」という奥田シェフ。「誰かに何かを頼むときというのは、だいたい成功したらこれくらいで失敗するとしたらこれくらい、というふうにラインを引いているものなんです。その期待値を超える120点をマークすると、また声がかかります。みんなが想像する以上の飛びぬけた結果を出せるからこそ、将棋の藤井くんもスケートの真央ちゃんも卓球の愛ちゃんもスーパースターになれたんですよ」。
そして、と続ける。「頼み事やツキは、必ず上の人が持ってきてくれます。だから、上の人に可愛がられる存在でいないといけない」。そのためには、年上の人を尊敬し、年下の人を尊重することが大切だという。「一緒にいて居心地がよくてそばに置いておきたくなる存在になると、チャンスが広がります」。店のスタッフたちにもいつも「可愛がられる人になりなさい」と教えている。
チャンスを得た後は「一所懸命」つまり「やりきろうと決めたひとつの場所をしっかり守ることが大切です」。守りきれたら、次は360度の視野をもって真剣勝負に挑む。戦えるようになると信頼されて評価されるから、お金もついてくる。給料も上がる。「そして、採取的には”夢中”というステージに入っていく。そうなると、もう、こわいものはありません」。
いろんなレストランでの修行経験のある奥田シェフに、タケは、一つ聞いてみたいことがあった。「ビジネスパーソンの中には、今の場所じゃない別の場所で力を試してみたいという転職へのあこがれがあると思うんですが、奥田さんならそんな方にどんなアドバイスをしますか?」奥田シェフの答えは明快だった。「これまでの経験は財産だから、それは活かすべき。今までやってきたことを活かせる、でも全く別の世界に行くといいと思う」。
そのあと「僕もね」と、こう続けたから驚きだ。「包丁をバドミントンラケットだと思って使うと、リズムよくダダダダっと切れるんですよ。あの時、一点が決められていたら、今頃はバドミントンのナショナルチームの強化部長だったかもしれないなぁ」。爆笑するタケ。「奥田さんのこと、大好きになっちゃいました」
◆成功の秘訣は「時間」
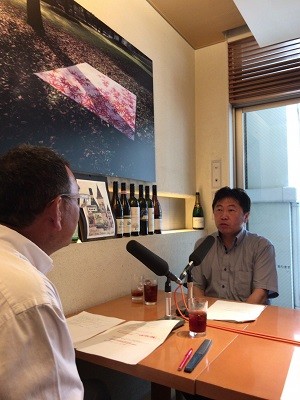
JR東日本の豪華寝台列車「トランスィート四季島」の朝ごはんの監修を担当したことでも話題を呼んだ奥田シェフだが、「そういうお誘いはどんなふうに入ってくるんですか?」と聞くタケに「鶴岡に列車を停めてくれるなら引き受けますって返事したんですよ」と笑う。そして、停めてくれるなら鶴岡ではこんなサービスが用意できます、と逆提案もしたおかげで、その場で即決。「その時点では実現できるかどうかわからなかったんですけど、ここが勝負時だと思ったから。そういうときはまず決めちゃって、あとで関係者を説得すればいいんですよ」。
いつでも「時間」がとても重要だという。
「ドラえもんみたいな存在でいたい」という奥田シェフは、困っている人がいたらなるべく3秒以内で答えを出してあげるそうだ。「はい、タケコプター」という感じで素早く、ニッコリ、相手が負担にならないような気軽さで、もちろん見返りなんて期待しないで。
時間に関する感覚を磨くために、お風呂に60秒間潜ることを日課にしている。「60秒くらいなら息を止めていられます。その時間感覚を身に沁みこませるんです」
それがどんな時に役立つのか?たとえば店でカップルがデザートを待ちながら楽しそうに「いちご」の話をしているのが耳に入ったとする。予定していたのはチョコレートを使ったデザート。でも、このタイミングでイチゴのデザートを出せば二人の気持ちはきっと盛り上がる。さあ、間に合うか?「そのタイムリミットは25秒くらいなんですよ。それを過ぎたら、きっといちごの会話は流れて行ってしまうから。でもうまく間に合えば二人に未来への翼をプレゼントできる」。奥田シェフにとっては、時間まで含めての料理なのである。
人生の中で起こったさまざまな出来事を、すべて自身の糧として今につなげている奥田シェフ。その優しい温かな眼差しの向こうにはどんな未来が映っているのだろうか。
「飲食業という枠にはまらず、よりよい未来に向かってバトンを渡したい。ずっと先の日本の農林水産業のことまで考えられる料理人を育成することに、力を注いでいきます」。
初対面で、たった一時間の対談。それでも互いに感じあうところがあった二人は最後にがっちり握手をして、再会を誓った。「お互い、未来のためにがんばりましょう!」