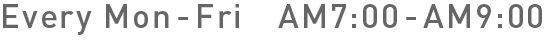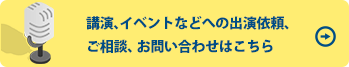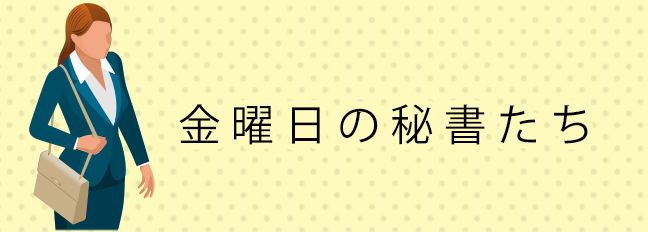文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビュー。パーソナリティのタケ小山が今回お迎えするのは、ビジネスマンだけでなく組織に属するあらゆる層からの支持を受けて16万部超えのベストセラーとなっている『不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか』(講談社現代新書)の著者でもあり、劇作家・演出家として長く活躍を続けている鴻上尚史さん。最良の結果を出すチームとは?そして、それを率いるリーダーの在り方とは?自由闊達な二人の会話の中に、様々なヒントがきっと見つかるはずです。
●僕が『不死身の特攻兵』・佐々木友次さんに強く惹かれる理由

9回特攻に出て、9回無事に帰ってきた佐々木友次さんという人がいた――。「これってすごい驚きじゃないですか?」と語り始める鴻上さん。「当時のことを調べれば調べるほど、軍隊という環境の組織としてのハードさがわかる」。その中で、たった21歳の若者が特攻を命じる50代や60代の上官に向かって「体当たりして死ななくても、爆弾を命中させて帰ってくればいいじゃないですか」と言い続けて、それを実行し続けた。当時の資料を紐解くと、佐々木さんが特攻から戻ってきて上官から「なぜ、体当たりしないのか?」とののしられていた場面を目撃したという証言がたくさんある。何度目かには「とにかく死んで来い」と言われて「爆弾を落として船を沈めるのが私の仕事で、無理に死ななくてもいいと思います」と佐々木さんは答えている。そんなことを軍隊という徹底した上意下達の組織の中で行うことができる日本人が存在した。「想像を超える事実でした」と、鴻上さんは言う。
その佐々木友次さんが、(数年前の取材時には)まだご存命であった。「そのことを知ったとき、思わず叫びました」。すっかり歴史上の人物だと思い込んでいたからだ。すぐにでもインタビューに飛んでいきたかったが、場所は北海道。ちょうどその時期は芝居の本番を控えていて稽古に追われていたので、どうしても動けなかった。「その後、公演を終えてお会いできたのが亡くなる数カ月前でした。合計で5回のインタビューを行うことができた。まるで奇跡のようなタイミングで、これもめぐりあわせだったのかな」と振り返る。
「鴻上さんがそんなにも惹かれて、インタビューをしたり当時の資料を読み込んだりして書き上げたこの本、どんな人たちに読んでもらいたいと思っていたんですか?」とタケが聞くと、「日本型組織に苦しんでいる人ですね」と答えた後で、「これは、実はこの本の編集者が教えてくれたんです」と笑う。担当編集者が考えたという本の帯には確かにこう書かれている。「命を消費する日本型組織に立ち向かうには」—-これを見た時、なぜ佐々木友次さんに強く惹かれたのかが腑に落ちた、という。
現代はブラック企業、ブラックバイト、ブラック校則のように構成員の命を消費しながら伸びていく組織の中で、それに立ち向かいたいと思いながらもそうできなくて苦しんでいる個人が非常に多い。たとえば、会社員の残業。仕事がたくさんあるから残業してそれをこなすということだったはずなのに、いつの間にか上司が残っているから残業する、みんなが残業するから残業する…というように、残業そのものが目的になっている。これは、特攻という戦術が、「体当たりをしたら船を沈められる」ということで始めたのに、それに対してアメリカ軍がすぐに防衛方法を編み出して効果が少なくなってしまったにもかかわらず「体当たりする」ことそのものが目的になっていった状況とよく似ている。「会社員だけじゃなく、PTAやママ友といった組織の中でも同様のことが起こっていると思います」。
「そういう状況を変えていくためにはどうすればいい?」と問うタケに、「佐々木友次さんという人がいたことを知るだけでも勇気になる」とキッパリと語る鴻上さん。「本の中では、なぜ特攻という効果のない戦略が続けられたのか?についても、僕なりに分析を行っています。日本人の精神性と密接な関係にある。何らかのヒントを得てはもらえるんじゃないでしょうか」。
●ろくでもないリーダーほど精神論しか語らない

「命を賭けろ!」とか「気合いだ!」「ガッツだ!」なんてことしか言わないリーダーは「ろくでもない」とばっさり切り捨てる鴻上さん。「リアリズムを語るのが優れたリーダーです」。
『不死身の特攻兵』の中にも印象的に描かれているが「美濃部正さんという少佐は非常に優れたリーダーでした」という。特攻の末期、ほとんどヒステリー状態のようになっていた軍隊では、時速200㌔しか出ない布張りの練習機(赤とんぼ)で特攻に出ろ!という命令が年配の参謀たちから出された。そのとき、最も年少の少佐であった29歳の美濃部さんはこう言った。「赤とんぼでの特攻が有効だとお思いでしたら、箱根の上空で私はゼロ戦一機で待ってますから、みなさんは50機でやってきてください。私が全部撃ち落として見せます」。
そして、美濃部少佐が部下に対して行ったのは厳しい飛行訓練だった。目視出来ない夜間の飛行訓練は、着陸と離陸だけでも通常は500時間から1000時間の練習を必要とするが、それを100~200時間で習得させるような非常に厳しい訓練を行った。その際の美濃部少佐の口ぐせは「お前たち、この訓練に音を上げるなら特攻に出すぞ」だったという。
「今、何が必要で、そのためには何をすべきかを分析できるリーダーであった」「すごい勇気、そして非常に合理的だ」と鴻上さんは称賛する。
戦争だから死ぬことは構わない。ただ、死に甲斐を求めている。赤とんぼでの特攻を拒むのは臆病だからではなく、部下を戦に出すからには効率的な戦いをしたいんだと言い続けた美濃部少佐。ただ、残念なことに美濃部少佐の発言を参謀たちは悠然とタバコをくゆらしながら無視した、と記録には残されている。組織は変わらなかった。赤とんぼの特攻は送り出された。
この話にショックを受けて「何も変わらなかったんですか?」と問いかけるタケ。鴻上さんは「全体は変わらなかったが、少しは変わったこともあった。美濃部さんは、やはり希望だったと思う」と教えてくれた。特攻を推進した大西滝次郎も、美濃部さんにだけは特攻を命じなかった。一時期は命じられたが、最終的には「お前はいかなくていい」と。
現場においても変化があった。
佐々木友次さんの属する陸軍の特攻機は、爆弾だけを落とすことができないように機体に800キロ爆弾が縛り付けられていた。敵機を爆破するためには機体ごと突っ込むしかなかったのだ。敵機を見つけられなかったり機体の不備で不時着することになったりしても爆弾を外すことができなくて無駄死にするしかなかったという。佐々木さんは第一回目の特攻のメンバーで、その時の隊長の岩本さんはその状況を憂慮して、機体から爆弾を外して落とすことができるような細工を整備兵に頼んでくれた。この岩本隊長もリアリズムを大切にできる優れたリーダーだが、残念ながらくだらない上官のくだらない命令のせいで、命を落とすことになった。「調べれば調べるほど、怒髪天を衝いて情けなくなるエピソードがごろごろしています」と嘆く鴻上さん。「でも、岩本隊長が亡くなった後も、整備兵は佐々木さんの機体から爆弾が落とせるようにし続けてくれたんです」。これが、現場の力学だ。
現場の人は、みんな、特攻という戦法には意味がないと感じていた。800㌔爆弾をくくりつけていたら、優秀なパイロットがみんな死んでしまうじゃないかと怒っていた。特攻の初期はベテランのパイロットに出撃が命じられることが多かった。飛行士としてプライドを持って急降下などの練習をしていたのに、突然「急降下しなくてもいい、ぶつかれ」と言われて、パイロットたちはものすごく怒ったのだ。そのことを現場は知っていて、力学が働いた。整備兵たちは毎回ちゃんと爆弾を落とせるように調整をして送り出してくれたという。
「企業でもありそうですね。トップはだめだけど、現場はちゃんと機能している」とちょっぴり苦笑するタケであった。
●「情報は流通させないといけない」~鴻上さんのリーダー論

「鴻上さんご自身の話も聞かせてください」と、リーダーとしての鴻上尚史像に迫るタケ。
「そもそも何がやりたくて劇団の旗揚げを?」という質問に「表現がしたかった」と答える鴻上さん。「表現したいことがあって、劇団でワイワイしゃべりながらやるのが好きだったんでしょうね」。最初は役者として参加したが、自身の劇団を作るときに演出家を選んだのは、「客席に座って、幕が上がってから下りるまで作品を観ている者が必要だと思ったから」だ。
演出家になって、その責任範囲の広さを実感したという。「俳優が喉を嗄らして声が出なくなっても、お客さんはなんだかつまらない作品だったね、と言うわけです。いやいや、それは作品のせいじゃなくて声を嗄らした俳優の責任だ!と内心では思うわけですが、演出家は全体の責任を取らないといけないんです」と笑う。
22歳で劇団を作って、「最初の数年は人間関係の調整で90%くらいの力を使っていましたね」と振り返る鴻上さん。海のものとも山のものとも知れぬ旗揚げしたばかりの劇団で、売れるのかどうかもわからない状況。試行錯誤の連続だった。「劇団員の誰と誰がくっついただの、仲が悪いだの…。あとは、せっかく早稲田まで行かせたのに子どもが大学行かずに芝居にのめり込んでしまったと嘆くご両親との攻防も。核戦争後の廃墟の芝居なのに、初日に主役の俳優がリクルートカットでやってきたなんてこともありましたよ」と振り返る。
そんなドタバタのスタートからはや36年。鴻上さんが劇団を率いるリーダーとして最も大事にしていることは「楽しくやることですね」と、ニッコリしながらキッパリと答える。「どんな状況になっても楽しくやろうと、いつも思ってきました」。
「だけど、言うこと聞かない生意気な役者もいるでしょ?」というタケの質問に、「いますよ!」と答えた鴻上さん。そんなときには「じゃあ初日は俺の言うとおりにしてよ、二日目はお前の思うようにしていいから。それで、どっちがお客さんの反応がいいか見て決めようぜ」なんてこともあったという。「結局、指導力というのは情報の流通。自分には指導力がないと思い込んでいる人は、情報を抱え込んでしまっている」。今、この部署がどれくらい大変なのか、どれほどひどい状況なのか?自分の中だけで処理しようとしてしまっている。「そうじゃなくて、情報を共有することでチーム全体の意識も高まっていくはずです」。
情報を流通させることで「人のアタマが使える」ようになる。「ダメなリーダーは人のアタマを使っていないんですよ」と鴻上さんは言う。
たとえば戦時中、優れた見識を持つ多くの人が「特攻には効果がない」とデータを用いて教えていたのに、それを一切はねつけて自分の頭の中の観念だけで推し進めようとしたリーダーがいた。現代においても、大人たち、特に男性はある年齢以上になるとプライドがあって他人の言葉が聞けなくなってしまう。「現場の若造から、部長、そんなの意味ないですよ!なんて言われてカッとなって怒鳴りつけたりするんです」。
でも、と鴻上さんは続ける。「何が大事で何が大事じゃないか。現場のものがいちばんよくわかっている。聞くことが大事なんです」。一方、部下の方へのアドバイスとしては「情報のシェアをお願いする態度が効果的だ」と教えてくれた。「こうしたらどうですか?」と言われるとムカッとする上司も「今どうなっているのか教えてください」と言われて怒ることはないはず。「どんなに忙しくても、情報の流通が大事だということをいつも思い返してほしい」。
●チームをデザインする際に大切なこととは?

「チーム作りの話に関連して、先日、サッカー日本代表のハリルホジッチ監督が選手とのコミュニケーション不足を理由に突然解任されるということがありましたが、演劇界でもそういうことってあるんでしょうか?」と、タケ。
僕は幸い今まではなかったけれど、と前置きしながら「そんな例は山ほどあるみたいですよ」と鴻上さん。役者側の座長が、あの演出家ではダメだと言い出してプロデューサーに「僕を取るか演出家を取るか」と迫ると、たいていの場合プロデューサーは俳優を取るらしい。
そんなことにならないためには何が必要なのか?
「コミュニケーション力だけでもダメでしょうね。少なくとも僕は、コミュニケーションも大事にしながら、時には耳に痛いことも言う演出家でありたい」。
劇団の公演は毎回参加メンバーが変わる。そのたびに新たなチームとして動くことになるが「結構な確率でベストチームになる」という。その理由として「事前に必ず評判をチェックする。つまり、性格がいいかどうかを確認するんです」。ここで言う「性格の良さ」というのは、「無駄かもしれないトライアルをやってくれるかどうか」だ。表現というのは最短距離でゴールにたどり着けるものではない。三日間稽古をしたけれど、全部無駄でしたなんてことも起こるのが芝居の世界なのだ。「それを面白いトライアルだと思ってくれる人か、三日間を返せ!と感じる人か」を見極めることが大切になる。
「試行錯誤やトライアルを楽しめない人は、仕事がなくなっていくでしょうね。だって、それじゃあいいものは作れないから」。パターンで作ってもつまらない。「今まで観たことのないものがここにはある」と観客に思ってもらうためには試行錯誤が必要で、それが表現を追求するということだ。
「チーム作りには作戦が必要」という鴻上さん。チーム力は総力戦だから、個人の資質だけではなくチーム内でのバランスや力関係も大事な要素になる。「ものすごく性格は悪いんだけど切れ者のやつと、すごく性格がいいんだけどあまり賢くない人。仕事はできないんだけど宴会部長としては最適なムードメーカー的存在や仕事はともかく若い者の面倒見が良いやつ。総合戦力を考えつつ、地盤沈下しないようなチームをデザインしていくのがチーム作りです」。そして、大事なのは、一人一人を「知る」こと。そのために、一人ずつとじっくり飲んで話をする時間を必ず作るようにしている。
「試行錯誤ができる組織」がいいという鴻上さん。「全く働いてないけど、あの人はいったい何をしてるの?という組織はいい組織です。どうしようもない人間も抱擁できる組織は余裕のあるいい組織です」。
●クリエイティブな仕事に必要なのは「寝ること」だ!!
鴻上さんが、仕事の上で最も大事にしているのは「寝ること」だ。7時間から7時間半は寝るようにしている。「クリエイティブなことをしようと思ったら、それくらい寝ないと頭は回らないと僕は思っています」。5時間の睡眠でも、仕事を進めることはできる。「でも、本当の意味で深く考えていない気がしますね」。ルーティーンで単にこなしているだけになってしまうのだ。「待てよ、もっと本当にベストなアンサーはないか?ベターなアイデアは浮かんだけど、ベストがあるんじゃないか?と考えるには、十分に寝ておかないと思考が働かない」。
鴻上さんの芝居には、いわゆる「名セリフ」と呼ばれるものが多い。鴻上ファンの中にはそれらの言葉を大切にしている人がたくさんいる。だが、「芝居の名言みたいなものも、相当頭を絞るんですか?」と聞くタケに対する鴻上さんの答えは「セリフはあくまでもキャラクターの言葉なので、名言を書こうとは思っていないんですよ」というものだった。ふと思い浮かんで書き留めるようなこともあるが、ほとんどの場合は役者とのキャッチボールの中でいい言葉がパッと浮かぶのだという。以前書いた芝居の脚本で、アルバイトをしながら小説家を目指していた若者が、しばらくしてそれを諦めた時に年上の姉御が「あのね、才能っていうのは夢を見続ける力のことなんだよ」という場面があって、「我ながらいいこと書いたねってホロっとしました」と笑う。「キャラクターが生きていると、ポロっといいセリフが出てくるんですよ」。
脚本を書く際には、テーマに関することについては徹底的に調べて勉強するようにしている。専門家や業界の人が観に来た時に「なまぬるい」「間違っている」と思われたくないからだ。はじまりの場面から順に書いていくこともあれば、最後の場面のイメージが浮かんで、そこに向かうためには?と遡って書くこともあるという。70歳になっても80歳になっても書いていられたらいいな、と考えている。「脚本家の仕事には、これで終わりという意識がないですね。それがいいのかどうかわからないけど」。
最後に、タケはこっそり鴻上さんにこんな相談をしてみた。「ラジオ番組がもっと広く受けるようにするにはどうしたらいいですか?」
「あはは」と気持ちよさそうに笑った後で、鴻上さんはこう言った。「結局大事なのは、コンテンツ。内容が面白ければ、とても可能性のあるメディアだと思う」。嬉しそうに大きくうなづいて目を輝かせたタケ。何か大きなヒントを見つけられたのかもしれない。

文化放送『The News Masters TOKYO』のタケ小山がインタビュアーとなり、社長・経営者・リーダー・マネージャー・監督など、いわゆる「リーダー」や「キーマン」を紹介するマスターズインタビュー。音声で聞くにはpodcast で。The News Masters TOKYO Podcast
文化放送「The News Masters TOKYO」http://www.joqr.co.jp/nmt/ (月~金AM7:00~9:00 生放送)
こちらから聴けます!→http://radiko.jp/#QRR
パーソナリティ:タケ小山 アシスタント:西川文野、長麻未(文化放送アナウンサー)
「マスターズインタビュー」コーナー(月~金8:40 頃~)