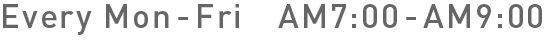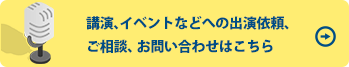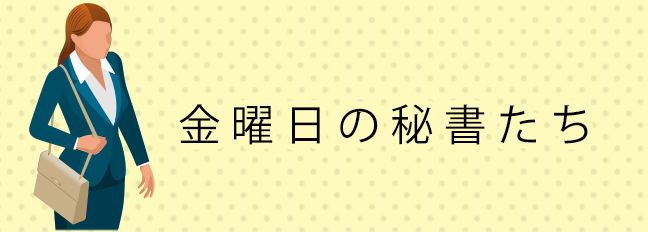文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビュー。パーソナリティのタケ小山が今回「この社長にぜひ会いたい!」と訪れたのは「築地銀だこ」の創業者、株式会社ホットランド代表取締役の佐瀬守男さん。
外食産業は「人ビジネス」で、「人の喜びを自分の喜びにできる仕事だ」と語る佐瀬さんのこれまでの挑戦の軌跡を追いかけながら、夢を追い続けることのできる情熱の”源”を探ります。
●始まりは、焼きそばから

「初日の売り上げは、350円でした」そんなびっくりの告白から始まった、ホットランド佐瀬守男社長のインタビュー。「築地銀だこ」という、今や知らない人のいないほどの食のブランドを一代にして作り上げて育ててきた佐瀬さんからのまさかの創業秘話に、思わずタケも「あはは」と大笑い。「え?そのあたりのこと、もっと詳しく教えてください」
佐瀬さんが生まれ育った群馬県の桐生市で初めて店を構えたのは25歳の時だった。ラーメン屋の居抜き物件で、二階は住居。家賃4万円の物件を借りて「おふくろと二人で、焼きそば屋でもやろうかって」という気軽なスタート。
「他にやることもなかったから」という佐瀬さんだが、そこで飲食、しかも焼きそば屋に決めたのは、高校生時代に抱いた夢がずっと心の中にあったからだ。「街にマクドナルドなどのファストフードの店ができて、そこに通うのが本当に大好きだったんです」
こんなに楽しい場所を、自分も作りたい。いつしか「和のファストフードを自分でやってみたい」と思うようになっていた。「とはいえ、お金がありませんから。中古車を友達に40万円で買ってもらって、それを元手に始めたのが『ホットランド焼きそば』という店です」そう、今に続くホットランドが生まれた瞬間だった。
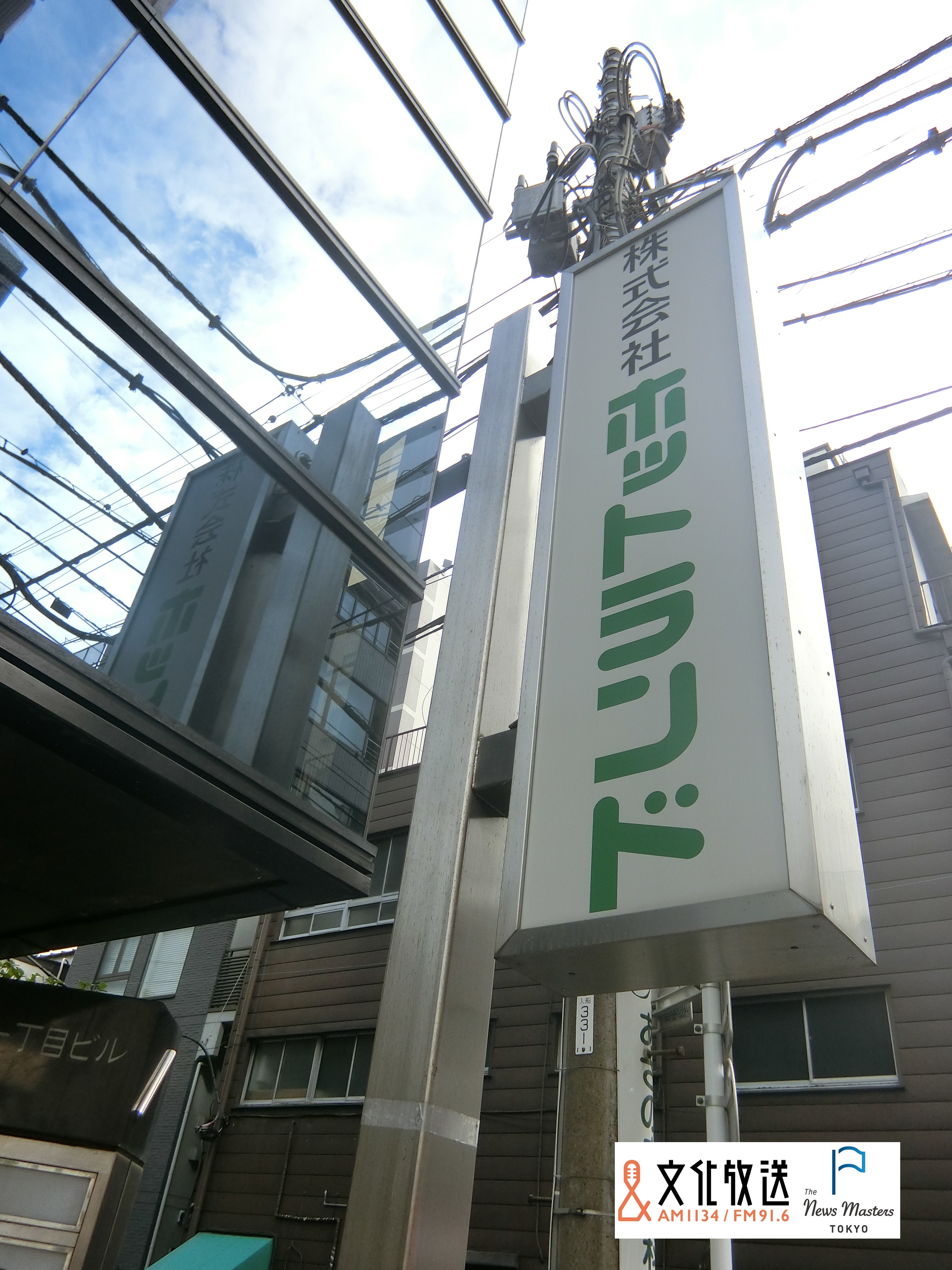
ここで、最初の話に戻る。「焼きそば一人前が350円。初日の売上は350円。つまり、一食しか売れませんでした。二日目の売り上げは、700円でしたね」と当時を思い出して笑う。買ってくれたのは近所の子どもたちだった。このままでは、家賃さえ払えない。どうしようか?と考えた佐瀬さんは宅配焼きそばを始めることを決めた。
「当時は新聞配達の仕事もしていたから、新聞を配るついでに『焼きそば届けます』と書いたチラシを配ったんです」その作戦が、見事当たった。たくさんの注文が入るようになって、焼いては配達するというのを繰り返す毎日。
お客さんの方が心配して「こんなに遠くまで持ってきて、それで350円で勘定合うの?」と言ってくれることもあったが、「暇よりはいいですから」とせっせと忙しく働く生活を2年間続けた。

そんなある日、転機となる一つの出会いがあった。「当時の彼女(=「今の嫁さん」)のお兄さんが、妹が焼きそば屋と結婚するなんて言い張っているから止めなくちゃ、と訪ねてきたんです」
その時点では「敵」とも言うべき存在だ。ところが、佐瀬さんの「マックみたいなファストフード店を『和』で作りたい」という夢を聞いて「一緒にやりたいって言ってくれたんです。止めに来たのに、乗ってくれた」と嬉しそうな笑顔で振り返る。
そこからは二人で一生懸命に働いた。「やっていることは間違っていない」という自信はあった。なのにうまくいかないのは場所が悪いせいだと考えて、銀行から借金をして桐生の駅前に2号店を出店した。
「おっ。それでどうなりました?」ここまでの展開をドキドキしながら聴いていたタケは、成功を祈る想いでその先を尋ねる。
「実は、それでも売れなくて…」と佐瀬さん。その答えに、のけぞるタケ。「朝6時から夜は12時まで店を開いてたんですが、毎日残り物ばっかり食べてました」
●商売は「あきない(=商い、飽きない)」!

だが、佐瀬さんたちはくじけない。「それからも、食べるためにいろんなことをやりました」
ある日、テレビでソフトクリームが大人気で行列ができているというニュースを見た。羽生のその店では牛乳でソフトクリームを作っているという。何度も通って製法を教えてもらい、店の商品に加えたところ、これが売れに売れた。
「ソフトクリームが売れると焼きそばもおにぎりも売れ出して、たちまち繁盛店になったんです」ようやく売れるものを見つけた!と思った佐瀬さんは、当時住んでいたアパートの一角を「ソフトクリーム工場にしたんです」と笑う。
「アパートを、工場に?」と問い返すタケに、「湯飲み茶わんを500個買ってきて、手作業でソフトクリームを絞ってあんこを入れて、アイスまんじゅうを作りました」と教えてくれた。
そのアイスまんじゅうを、横浜の中華街まで売りに行った。「中華まんを売っている隣で、中華アイスまんじゅうって名前で売ったらめちゃくちゃ売れたんです!」ようやく聞けた「売れた」という話に嬉しくなるタケだったが、話はここでは終わらない。
「桐生から横浜まで下道で片道6時間かかるんです。往復12時間かけて行って帰って、帰宅後は500個のアイスまんじゅうを作るという生活が始まりました」寝る暇もない。そんな日々を延々続けた。それでも一日の売り上げは最大500個分でしかない。
「もっとたくさん楽に作る方法は無いのか?」そう考えた時、思い浮かんだのが鉄工所を経営している兄の顔だった。「一緒に事業をやろう!」と巻き込んで「1億円くらい借金をして、べらぼうにでかいアイスまんじゅう工場を作ったんです」(「あれ、なんかイヤな予感がする…」と、小さくつぶやくタケ)

工場で大量生産したアイスまんじゅうは、30店くらいの中華街の店や全国の観光地に卸して人気を博した。「ところが、一年で全く売れなくなってしまったんです」
アイスまんじゅうでは地味すぎるのかもと、アイスキャンデーを作ってもみた。だがそれも、営業に行ったコンビニやスーパーマーケットで見向きもされない。
「借金は残る。こりゃもうダメだ!」と思った佐瀬さんたちは「自分たちで売るしかない」と心を決めた。歩行者天国を自転車で「チリンチリン」と鳴らしながら売って歩いてみたら、「これが、売れるんですよ!」とニッコリ。観光地でも、売れに売れた。「これはいける!」とアルバイトを50人くらい雇って売って回らせたという。
だが、「アイスには悲しい性(さが)があるんです」と声を落とす佐瀬さん。「冬場は全く売れないんです…」
温泉場なら売れるかもしれないと思って水上温泉などにも出かけてはみたが、大した売り上げにはならない。資金も底をつきかけた。そんな時に、ふと畑を見たらじゃがいもがたくさん収穫されていた。
「これをふかして熱々のじゃがバターを売ろう」今度はそう思いついた佐瀬さんが高速のSAやPAなどで売り始めたところ、なんと冬場は一日の売り上げが100万円を超えるほどになった。
ようやく大成功かと思いきや、ここで佐瀬さんは悩み始める。「じゃがバター売っていれば、小金持ちにはなれそうだ。でも、和のファストフードをやりたくて会社を作って借金もしてここまでやってきたのに、このままで本当にいいのか?」
そんな時期に、一緒に夢を描いてきた社員が「やりたかったことと違う」と会社を辞めたことも大きかった。「結局、一年でじゃがバター売りを止めました。少しお金が貯まっていたので、それを元手に和のファストフードに再挑戦することに決めたんです」
先が気にはなるが、ここまでの話を聞いて、どうしても確認したいことがタケにはあった。「それだけ紆余曲折があって、それでも一貫して商売を続けたのはなぜなんですか?」
その理由は、お母さんの言葉にあった。「おふくろが、一回商売を始めたら絶対に飽きちゃダメだよって。それが『あきない』なんだって。お客さんが来るから、お店は絶対に開けておきなさい、そう言い続けていたんです」だから、どんな状況にあっても商売をただひたすらに続けたのだという。
●たこ焼きは「飽きない!」

「和のファストフードをやる」そう決めた佐瀬さんたちが次の挑戦の舞台に選んだのは桐生のショッピングモールだった。焼きそば、おむすび、お好み焼き、そしてたこ焼きというラインナップでスタートを切った。順調な滑り出しにほっと息をつく。
「ところが…、最初の3か月はいいんだけど、だんだん売れなくなるんです」そうなるとあせりが生まれる。飽きられないように新しい商品に手を出すようになった。
カレーはないの?と言われてカレーを増やし、ラーメンが人気みたいだと聞けば、ラーメンを増やす。アイテムが増えるごとに、作り置きも増えていった。「作り置きしたものって、どうしても干からびるからおいしくない。結局売れなくて、あせってまたアイテムを増やす。そんなことを繰り返してしまっていました」
こんなことではいけないと危機感を持った佐瀬さんは、原点に立ち返ってこう考えたという。「僕たちの作っているものは、本当にうまいんだろうか?」食べ物屋にとって一番大切なことなのに、当時はそれを忘れていた。
さらに、こうも考えた。「ファストフードというのは、注文を受けてすぐにパッと渡すものだと思っていたけど、お客さんが望んでいるのは少々待ってでも熱々のできたてなんじゃないか」これまでは厨房を隠していたが作っているときのシズル感や匂いが大切な要素であることにも気づいた。
そして、佐瀬さんは社員を集めてこう宣言した。「全部やめる。焼きそばもやめる。おむすびもやめる。これからは、たこ焼き一本に絞る!」

当時の一日の売り上げは約3万円、たこ焼きはそのうちの3000円程度。社員は不安を隠さなかった。「なぜ、たこ焼きなんですか?そんなことしたら、つぶれちゃいますよ」だが、佐瀬さんにはかすかながら勝算があった。たこ焼きを買う客層が小さな子どもから老人まで広かったことと時間帯に関係なくコンスタントに売れていたことだ。
「ここに魅力的なパフォーマンスを加えて、本当にうまいものを作ったら、絶対に売れる!」そう決めてからは、たこ焼きを食べ歩いた。たこ焼きの本場と言えば、大阪だ。
「アイスキャンデーを売って経費を稼ぎながら、半年くらい大阪に住んで、ほぼ全店を食べ歩きました」各店の味の違いに驚き、衝撃を受けた。何より、焼き手が楽しそうなことに感銘を受けた。また、粉や天かす・青のりなどの材料についても真剣に考えるようになっていく中で、「たこ焼きは、やっぱりタコが命!」と、今度は東京に戻って築地の魚河岸に通い詰める。
「仲良くなって、毎朝タコの話を聞いてました」当時はまだ国産のタコが手に入りやすく、値段も安くて量があった。生で仕入れて、店で茹でてカットすることから始めた。ようやく「築地銀だこ」が今に続く第一歩を踏み出した。
そこから、25年。佐瀬さんは「たこ焼きは飽きない」とキッパリ明言する。「僕たちの会社は、社員全員が朝から晩までたこ焼きのことばっかり考えています」全員が、たこ焼きを焼くのが大好きで、たこ焼きを焼いているときがいちばん生き生きしている、と笑う。
●爆発的ヒット!「築地銀だこハイボール横丁」

「築地銀だこ」のたこ焼きは、たちまち人々を魅了した。ガラス越しに焼いている人の顔が見える店舗、材料もつくり方も全部丸見え。いつでも出来立て熱々のゴルフボール大の大きなたこ焼き。しかも、とびっきりおいしい。
「皮が薄くてパリッとしていて、中はとろっとしている。大きなタコが入っているけど、プチっと噛み切れて、その瞬間海の旨味が口の中に広がる」そんな「銀だこ」のたこ焼きは快進撃を続けた。
「僕がよくいくのは、たこ焼きと一緒にハイボールが飲めるお店です」と、タケ。「あのコラボはどんなきっかけで生まれたんですか?」それには2つの理由があった。一つ目は、都内に路面店を出したかったということ。もう一つは、たこ焼きだけだと夜の需要が少ないということだ。
「夏場は暑いから、たこ焼きと一緒に冷たいものが売りたいなと考えたんです。それで思いついたのがハイボールでした。当時は今ほどメジャーじゃなかったんですが、サントリーさんと組んで一緒にやることに決めました」
最初の路面店は、サラリーマンの聖地である新橋。これが大当たりしたのはいまや周知の事実だ。熱々のたこ焼きとガンガンに冷えた炭酸の切れがいいハイボール。一斉に火がついて、ウィスキーが足りなくなるほどの売れ行きとなった。
「これまではおやつだったたこ焼きが、トッピングを増やすことでランチになって、ハイボールと組み合わせたことで酒の肴になりました」

最近では、「銀だこ大衆酒場」という新業態も都内に9店舗展開している。メニューにはもつ焼きもあるし、おでんもある。お父さんはビールを飲んで、子どもはジュース。みんなが好き好きに楽しめる場所だ。「そして、団らんの真ん中にはいつもたこ焼きがあって、みんなでシェアしている」—-そんな情景を目指している。
さらにスケールを大きくした「銀だこ横丁」も五反田と浅草に作った。子どもの頃に住んでいた桐生には横丁がたくさんあって、それが大好きだった佐瀬さんはそういう場所を作りたかったという。天ぷら、串焼き、鉄板焼き、もつ焼きに、もちろん、たこ焼き。バーのようなカウンターがあって、どこに座ってもどの店のものも食べられるという仕組みになっている。

「この横丁を、アメリカでやりたいんですよ」という夢もある。
「僕たちはたこ焼き屋だから、たこ焼きから逃げられない。朝から晩まで、どうやったら売れるのか?飽きさせないのかを考えています」その答えの一つが、酒場や横丁なのだ。「たこ焼きを食べるシーンをたくさん作っていくことが大事」だと話す佐瀬さんの中で、これまでに重ねたたくさんの失敗経験が生きている。
●僕たちにできるのは、笑顔になれる場所をつくること
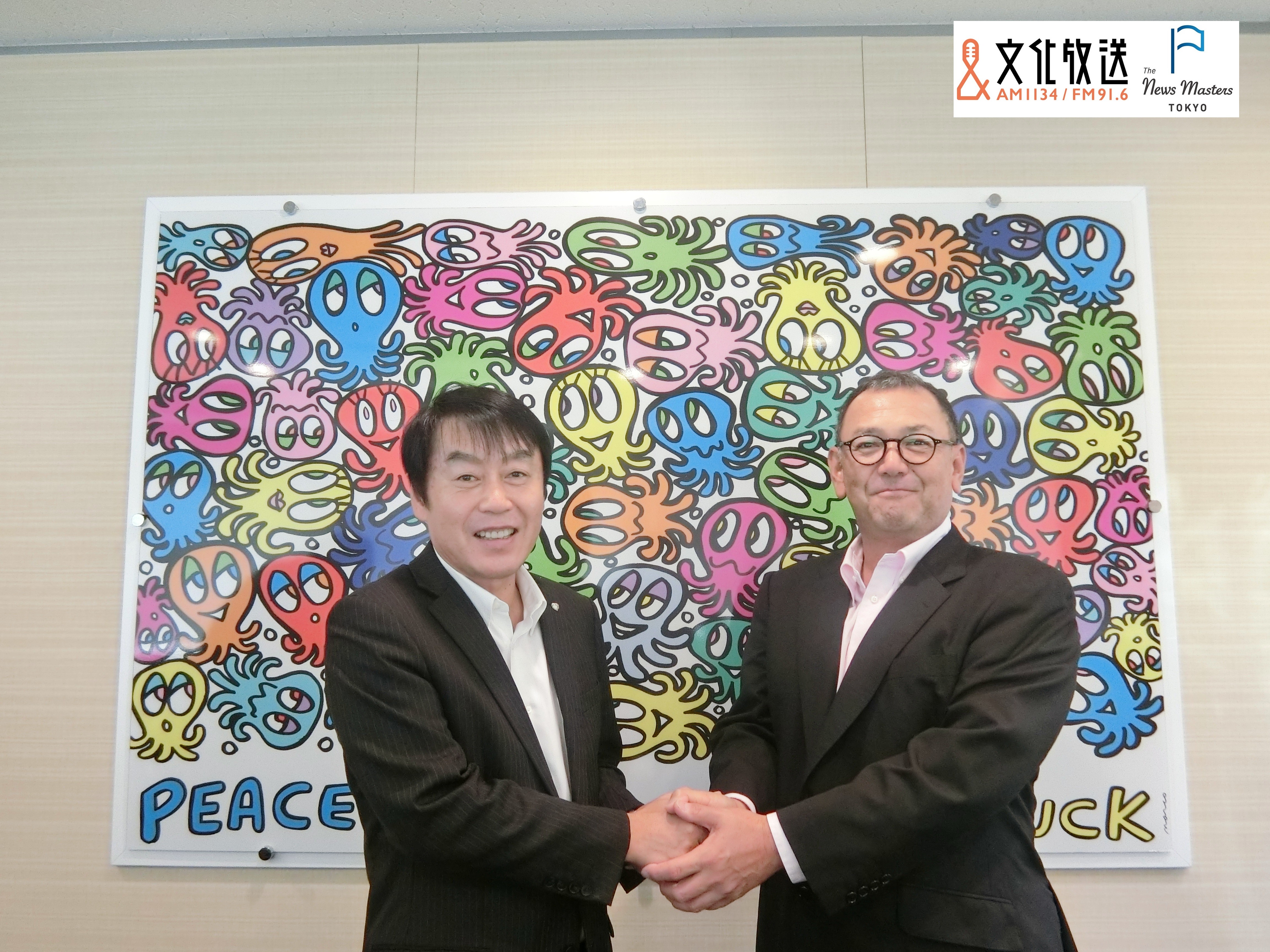
「仕事をしていて一番嬉しいのは、お客さんが楽しそうに笑っているのを見ることです」その想いは、社長の佐瀬さんだけではなく社員全員が共有している。それが形となった一つの例が、東日本大震災の後に立ち上げた「ホット横丁石巻」だ。
きっかけは、社員の家族が被害に遭ったことだった。「炊き出しに行くぞ!」と現地に乗り込んだ佐瀬さんたちは、津波によって大きく変貌してしまった町の姿を見て衝撃を受けた。
「一度の炊き出しだけで、帰ってきてしまっていいのか。もっと他にできることはないのか?」そう考え続けたという。そして、たどり着いた答えが「笑顔になれる場所をつくる」ことだった。
「僕たちには、ビルを建てたり橋を作ったりは絶対にできない。でも、笑顔になれるような場所をつくるのはできるんじゃないか」なんにもなくなった石巻。「だったら、全部、僕たちが作ろう」と決めた。
目標は、震災から100日で店を出すこと。ラーメン屋、焼き鳥屋、パン屋などそれまでやったことのないジャンルにも挑戦した。「すべてあったかいものを提供する店ばかり10軒を束ねた横丁を作りました」。横丁の中には、小さな運動場や映画館もつくった。
「取引先様にもご協力をいただいて、東京から50人くらいが現地に入って体育館みたいなところで共同生活をしながら作り込んでいきました」オープン初日、予想を上回るほどのたくさんの人がこの場所に集まった。
「お客さんたちが、わーっと近づいて『生きててよかった!』って抱き合っていました。震災以来ずっと封印していたお酒を飲んで笑って、カラオケで歌って本当に楽しそうだった。その様子を見て本当にうれしかったです」
その後も、ホットランドは全国各地の被災地で様々な支援を行っている。「僕たち会社も、生かされている存在。その中で、たこ焼きにできることは温かいものを届けることと、ひとを笑顔にすること。それしかないと思っているから、役に立てるならどこへでも行きたい。それが、ホットランドという会社なんだと思っています」
●「TAKOYAKI」を世界へ

佐瀬さんには、まだまだたくさんのかなえたい夢がある。その一つが、タコの養殖を成功させることだ。「今も一生懸命取り組んでいるんですが、まだ道半ばです」
小さいタコを捕まえて、それを大きく育てる技術はできた。大きくなったタコが産んだ卵を孵すことにも成功した。だが、孵った稚ダコを大きくする方法が確立できずにいるという。餌の問題、水質の問題。自社で熊本に研究所を作り、いくつもの大学の研究室と連携してチャレンジを続けている。
「惜しいところまで来ているんです。あともう少しだと思う」世界中で水産資源の不足が叫ばれている昨今である。このタコの養殖が成功すれば、世界にインパクトを与えるビッグニュースだ。
「一昔前は、タコを食べる国は少なかったんですが、今ではタコ料理は世界中で好まれているんです」そのため、需要が高まって、供給が追い付かない状況になっている。ホットランドでは、その状況を少しでも改善するために、養殖の研究と並行してタコ漁の指導にも乗り出している。
「南米でもタコが獲れるんですが、タコ漁の文化がなかったからいまだに素潜りで手づかみなんです。それじゃあ大変だから、熊本から漁師を連れてタコつぼ漁のやり方を指導しに行きました」アフリカのモーリタニアがタコの一大輸出国となっているのも、JICAがタコつぼ漁を教えたおかげだったという。
「タコはつぼで獲ってもらいたいんです。恐れているのが、大きな船でトロールで一気に獲ってしまうこと。それをやられると一年で生態系が変わってしまって、その後獲れなくなってしまいます」
さらに広い範囲に出店したいという夢もある。日本国内にも、まだ出していないエリアがある。ハイボール酒場や横丁も、もっと進化させていきたい。さらに、海外への出店も増やしたい。
「今回、ロスアンゼルスにアメリカでの一号店を作りました。ふうふう言いながらたこ焼きを食べて、すごく楽しそうで売れ行きも好調です」二号店は、もう少し大きめの店でお酒も売りたいと考えている。

「笑顔を提供できる会社でありたい」—-それが、社是です。穏やかな笑顔を浮かべながら、そう語る佐瀬さん。数々の失敗の後に見出した「築地銀だこ」がこれほどまでに成功したのは「人との出会いがすべてよかったから」だという。若き日に胸に抱いた夢を大切に、多くの人をその情熱で巻き込んで走り続けてきた30年。
これからの日々も、佐瀬さんの笑顔の奥にある熱い想いに共感する人たちとの出会いを積み重ねて、どれだけの夢をかなえていくのだろうか。
文化放送『The News Masters TOKYO』のタケ小山がインタビュアーとなり、社長・経営者・リーダー・マネージャー・監督など、いわゆる「リーダー」や「キーマン」を紹介するマスターズインタビュー。音声で聞くには podcast で。
The News Masters TOKYO Podcast
文化放送「The News Masters TOKYO」http://www.joqr.co.jp/nmt/ (月~金 AM7:00~9:00 生放送)
こちらから聴けます!→http://radiko.jp/#QRR
パーソナリティ:タケ小山 アシスタント:西川文野、長麻未(文化放送アナウンサー)
「マスターズインタビュー」コーナー(月~金 8:40 頃~)