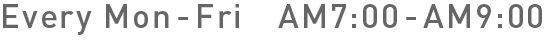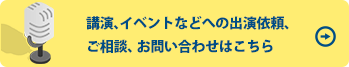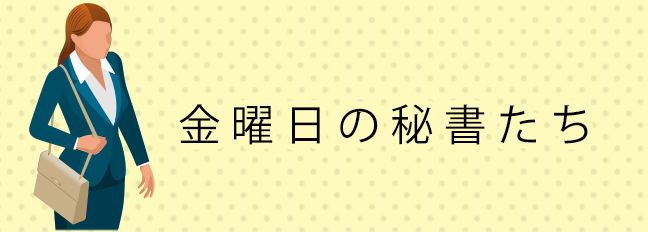文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビュー。
パーソナリティのタケ小山が今回訪ねたのは、米アップル社の新社屋に数千脚単位の椅子を納入したことで世界から熱い注目を浴びた広島の家具メーカー・マルニ木工社長の山中武さん。老舗の創業家の後継者として生まれ、子ども時代からずっと親に反抗していたという山中さんが家業を継いで世界的ヒット作となる椅子シリーズ『HIROSHIMA』を生み出すまでの紆余曲折のストーリーを追いかけてみたい。
●「将来の夢は?」という質問に泣いた子ども時代
1928年創業のマルニ木工は、今年、91年目を迎えた。
「ずっと家具を作っている会社なんです」と、山中社長は語り始める。「創業者は宮島出身で、木工の盛んな地域で育ったこともあって木が大好き。ヨーロッパへの憧れもあって、クラシック家具の製造を始めたそうです」。
その創業家一族に生まれた山中さんには今でも忘れられない小学生の頃の思い出がある。
「小学2年生くらいの時かなぁ。作文の宿題で、将来の夢を書くというのがあったんですが、どうしても書けなくて泣いちゃったんです」
「え、どうして?」と、驚くタケに「自分が将来何をやるのかが、もうわかりきっていたから」と、幼いながらに創業家の後継者ならではの複雑な感情があったことを教えてくれた。
さらに、こう続けた。
「父親と、全然合わなくて。14歳から39歳までずっと反抗期でした。25年間の反抗期」と苦笑する。当時の日本はバブル景気で高級家具がどんどん売れた。調子よく家業を営む父親と距離が置きたくて「とにかく避けていました。父親も、マルニの家具も、目に入れたくなかった。見たくないから家具売り場にも足を踏み入れないくらいに徹底していた」という。
大学卒業後は、だから、アメリカに留学をした。最初は語学留学だけのはずが、現地で出会った人たちに大学院を薦められたことがきっかけで試験を受けたら合格。「でも、入ってみたら地獄でした。英語もよくわからないのに毎日辞書を片手に分厚い本を読んで勉強しないといけない。人生で一番しんどかった2年間でした」
帰国後は叔父の紹介で銀行に入社。「どうせいつかは会社を継ぐんだから、他の世界で勉強してこい」と、背中を押された。この銀行員時代が、とても楽しかったのだという。「先輩にも後輩にも、取引先にも恵まれました。経済学部出身で数字が大好き。財務諸表を見るのが楽しかったし、いろんな取引先の方と飲みに行くといった交流も多く、たくさん人生勉強をさせてもらいました」ただ、銀行員としての業務の中で家具問屋の担当をする機会などもあり、バブル崩壊後の家具ビジネスの厳しさを身に染みて感じることがあったという。
そんなある日、ずっと父親を支えてくれていた叔父から連絡が入った。
「マルニがしんどいことになっている。これまでは『借りろ借りろ』と言ってきた銀行が、今は『返せ返せ』と言ってくる。お前も銀行員だから、どういうことかわかるじゃろ」
――もちろん、わかる。わかりすぎるほどに。
普段、債権者の立場として債務者に対して言っている言葉をマルニが受けている。いつもは強気な叔父が弱音を吐くのも初めてのことだった。これまでずっと陰になり日向になり支えてくれた叔父に恩を返せるのではないか。山中さんはずっと避け続けていたマルニ木工と向き合う決意をして、入社を決めた。2001年、30歳の時だった。
●「メーカーとして生き残る」という決意
戻ったときのマルニの置かれた状況に愕然とした。当時、国内の家具業界では高級家具の専門店は次々に倒産し、価格の安い量販店がマーケットを席巻していた。百貨店などの主要な取引先も縮小の一途をたどり、売り上げはダウンに次ぐダウン。非常に厳しい状況だった。
「いったいどこから手をつけたんですか?」と、タケ。その質問に、山中さんは少し笑いながらこう答えた。
「まだ、父親に対して反発していた時期なので僕自身は会社に対してとってもクールだったんです。とにかく儲ければいいんだろう、そう思っていました」
最初の3年間は、生き残るためにリストラクチャリングを断行した。工場は統廃合、不動産は売却。その対象は職人さんにも及んだ。
「現場を知らない、いやな奴が来たぞと思われていたと思います。数字でしか判断しないひどい奴が来たって」。ただ、マルニの技術のコアの部分を担う職人や工場は、縮小はするものの「残していこう」と思っていたという。ものづくりの本質に対して、創業家のDNAから来る勘が働いたのかもしれない。
「ただね」と、山中さんは続ける。「3年くらいリストラクチャリングをやっていく中で、だんだんほだされて、木が好きになって、ものづくりが好きになっていったんです」。どんな苦労があったとしても、「ものをつくるというのは楽しいことだ」と改めて実感した。
その頃、社内ではこんな議論が行われていたという。「マルニはメーカーで生き残りますか、それとも商社で生き残りますか」
父親や叔父はインテリアの総合サプライヤーとして商社的なポジションを探っていた。だが、山中さんはこう考えた。「うちの最大の強みはものづくりだ」。バブル崩壊後にも唯一評価され続けたのは、自社工場で職人が作っている家具だったからだ。
「メーカーとして生き残る」そう決心したことで、2004年には社名もマルニからマルニ木工に戻した。
「その後、少しずつ会社が変わり始めました」。
●「たった2ミリ」をあきらめない感性がデザイナーと職人を結んだ
「メーカーとして生き残ることを決めたことが功を奏して、2017年にアメリカのアップル社の新社屋に納入されたマルニ木工の椅子『HIROSHIMA』を生み出したんですね」と、この大快挙にまつわる話に興味津々のタケ。
「どんなふうに『HIROSHIMA』は誕生したんですか?」
その誕生の立役者はプロダクトデザイナーの深澤直人さんだ。
会社を変えよう、企業文化を変えようといろんな試行錯誤をしてはみたが、何をやってもうまくいかなかった模索の時期に出会った一人が深澤さんだ。「メーカーとして生きていくには小手先をいじっても仕方がない。川上のデザインが変わらないと会社は変わらない」と思った山中さんは、いろんな人に会いに行った。自分は経済畑の人間で、デザインも建築も勉強していない。「とにかく国内外の著名なデザイナーに会ってみようと思ったんです」
その中で、深澤さんのことが非常に強く印象に残った。
「この人としっかりひざを突き合わせてものづくりをやれば、素晴らしいものが作れるんじゃないか」
とはいえ、深澤さんは当時すでにプロダクトデザイナーの大家だった。そんなことが可能なのか?
「いったいどうやって説得したんですか?」と、タケも気になる様子。
山中さんは、その提案をする際に財務諸表を持っていったという。「こんなに大赤字です。お金もないし、残された時間もない」。そう正直に打ち明けたうえで力強くこう言った。
「でも、技術と想いだけはあります」
「で、どうなりました?」と、タケ。
「実は、意外とあっさり『うん』って言ってくれたんです」という答えにタケも小さくガッツポーズ。
実は、深澤さんの快諾にはちゃんとした理由があった。
「以前の活動でご一緒した時に、深澤さんから『この脚、あと2ミリ細くならないか』と言われたことがあって、うちの職人は『こんな無茶なこと言われたよ』と言いながら実に嬉しそうで、実際にそれに応える技術も持っていたんです。ものづくりに対する価値観、細部のこだわりを理解できる感性、そして技術力。それらがマルニ木工にあることが深澤さんの心をつかんだようです」
●ついに『HIROSHIMA』誕生

木の椅子をつくるというのは、実はとても難しいことだ。どんなにデザインがかっこよくても、座り心地が悪かったり強度が持たなかったりすると椅子としては評価されない。かといって実用一辺倒では魅力がない。デザインと実用のバランスの壁を乗り越えるためには、職人たちの長年の経験からのリーズナブルな提案が必要になる。
「そうやって練って練ってできたプロダクトには、あたかも讃岐うどんのコシのようなものが出てくる」——かつて、そう教えてくれたデザイナーがいた。「僕みたいな左脳型の人間にもわかる強烈なデザインの言葉として忘れられない」と山中さんは今もその言葉を胸に刻んでいる。
『HIROSHIMA』というネーミングを決めたのもデザイナーの深澤さんだ。
最初、山中さんは「広島で育った人間の一人としてカタカナのヒロシマを想起させるから、絶対にやめてくれ」と言った。だが、深澤さんは譲らなかった。
「一度耳にしたら忘れないし、世界に出て勝負するならこの名前がいい」。
仕方なく、しぶしぶ受け入れた名前だったが、「今は本当にいい名前を付けてもらったと思っています」。
『HIROSHIMA』は、現在マルニ木工の主力商品になっている。出荷脚数も売り上げ脚数もダントツの一位を誇る。「不思議なほど座り心地がいい」という評価を得ているのは、「身体に聴け」ということを大切にデザインして製品化してきたからだ。一脚を作るのにはオーダー後、約一か月かかる。
「非常に手間がかかるから、最初の頃は一か月に40脚以上は作れなかった。今は、ピーク時には月に800脚作っています」
量産を可能にしたのは、マルニ木工がモットーに掲げている「工芸の工業化」のおかげだ。このことは、マルニ木工の技術力の強さを表してもいる。「一脚だけ素晴らしいものを作れる職人はたくさんいますが、量産化ラインに流すためには工場の機械のプログラミングも必要。うちの会社はそれができるのが強みです」。すべて手作りだと100万円くらいになる椅子を工業化によって15万円程度で作ることができるそうだ。
●『HIROSHIMA』で世界へ

「よし、この椅子で世界に出ていこう」
胸にひそかな自信を抱きイタリアでの家具フェアに出展したのは2009年のことだった。「当時はまだヨーロッパの人たちは日本に高級家具のメーカーがあることさえ知らなかったんじゃないかな」と、山中さん。「日本と言えば畳の国のイメージですから、日本の椅子なんて考えたこともなかったと思います」
実はこの時、今に続く一つの素敵な出会いがあった。日本の商社で海外の高品質の椅子を日本に入れる仕事をしていた青年がマルニ木工の椅子を見て、こんな希望を胸にマルニの門を叩いてくれた。
「この椅子だったら、初めて世界で勝負できる可能性がある。僕がそれをやりたい。今より給料が下がっても構わない」
この時のことを「いやぁ、嬉しかったですよ」と顔をほころばせて語る山中さん。「よくうちに来てくれたと思います。うるさい奴だし、なかなか文化に馴染めないで大変だったみたいだけど、あれだけの一生懸命の想いを見せられて、ほんとうに力強かった」。強力な助っ人を得たことで、マルニ木工の椅子はいまでは30か国くらいのお得意さんから愛されている。今では月に500脚程度の注文が入るという。
●100年続くものづくりを続けたい

銀行を辞めてマルニに戻った当初は、売り上げダウンの歯止めが聞かなくてそれを一時的にでも埋めるために本来はやりたくない商品開発も山ほどやってきたという。
「でもね、そんなやり方では勝てないんです」
今ももちろんお得意先のオーダーに答えて製品を作ることもあるが、基本的には「自分たちが本当にお届けしたいもの」をつくることに徹している。
「職人さんたちは、僕がどうこう言って動く人たちではない。ただ、いざという時にはいつでも一緒にやるよというスタンスでいます」
職人さんたちのモチベーションアップに効果的なのは「売れている、お客さんが使ってくださるということ」だそうだ。その後、ちょっと笑いながらこんな話を教えてくれた。
「うちの工場は一般の見学を受け入れているのですが、お客さんがたくさん見にいらっしゃるときは職人たちもすごく嬉しそうなんです。見学客が女性ばっかりなんて日には、みんな“勝負作業服”を着て仕事していますよ」
広島県広島市内の湯来町という山間部に工場はある。
「本当に田舎です。標高は400m。冬は雪がどっさり積もります」
広島が、地元が、今ではとても大好きだという山中さんは地方へのUターンやIターンを希望する若者に向けてこんなメッセージをくれた。山中さん自身がかつて教わった言葉だ。
「やってみてから、考えろ」
悩んでないで、まず一回動いてみたらいい。やってみてダメだったら元に戻せばいい。いい加減に聞こえるかもしれないけど、やってみてから考える。この順番が大事だという。
「やってみてから考える」を繰り返しながら、確かな手ごたえを見つけてその種を育てて仲間と出会い、ともに成長してきたこれまでの日々。マルニ木工は9年後の2028年に100周年を迎える。
「100年後の後輩が、100年前の先輩がこんなのを作っていたんだな。わしらもまだおんなじもの作ってるぜ」
そんなふうにこれからもずっと続いていくことを山中さんは願っている。
文化放送『The News Masters TOKYO』のタケ小山がインタビュアーとなり、社長・経営者・リーダー・マネージャー・監督など、いわゆる「リーダー」や「キーマン」を紹介するマスターズインタビュー。音声で聞くには podcast で。The News Masters TOKYO Podcast
文化放送「The News Masters TOKYO」http://www.joqr.co.jp/nmt/ (月~金 AM7:00~9:00 生放送)
こちらから聴けます!→http://radiko.jp/#QRR
パーソナリティ:タケ小山 アシスタント:西川文野、長麻未(文化放送アナウンサー)
「マスターズインタビュー」コーナー(月~金 8:40 頃~)