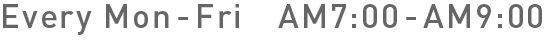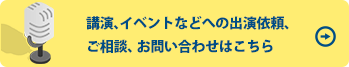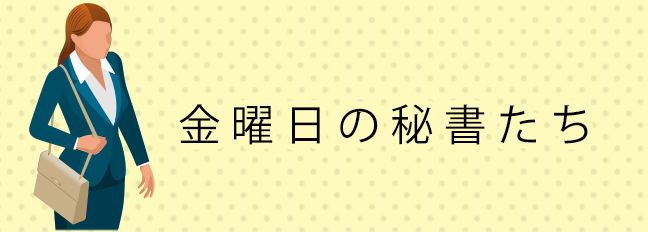マスターズインタビュー第8回は、現在奈良市立一条高等学校の校長を務める藤原和博氏にご登場いただきました。営業統括部長や新規事業担当部長を歴任し、フェローとして活躍していたリクルートから、東京都では初の事例となる公立中学校校長への転身が注目されたのは遡ること14年前の2003年。見事なマネジメント力を発揮し義務教育の場でも様々な成果を出すことに成功した藤原さんは、今度は公立高校という新たな場での挑戦を選択。私企業で培ったビジネスパーソンとしての力をどのように教育の場で発揮しているのか?場所や環境が変わっても快進撃を続ける藤原さんの”働きかた”哲学についてタケ小山が迫ります。
始まりは、リクルート
藤原さんは1955年生まれ。東京大学を卒業後、同じ大学の先輩である江副浩正氏が立ち上げた会社である株式会社リクルートに入社。「営業とプレゼンをずっとやっていたので、基本的にこの二つについては人に負けない自信がある。何を売れと言われても売れる」。東京営業統括部長、新規事業担当部長などを務めた藤原さんの力強い言葉にうなづくタケ。

「リクルートというのは、いったいどういう会社なのか?」とさらに問いを重ねるタケに、リクルートのスローガンとなっている「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」を引用したうえで「チャンスは自分でつくり出すもので、待ちの姿勢ではダメだという原則が貫かれている」と答える藤原さん。「風通しの良い風土でしたね」と。上司と部下、男性と女性、外国人と日本人、大卒と高卒…、そういう出自や歴によって差をつけないし、壁を感じさせない。肩書ではなく「さん」付けで相手を呼び合い、常にフラットな関係で仕事をしていたそうだ。
「そういうカルチャーは今も続いていると思う」との言葉の後で「今のリクルートを受けても、僕は受からないんじゃないかな」と笑う藤原さん。そこにすかさず我らがタケが、リクルートに就職したい学生さんたちに代わってこんな質問を。
「リクルートの入社面接に受かるにはどんな作戦を立てればいいですか?」
藤原さんが教えてくれたのは「ポケモンのレアカードみたいな存在になること。つまり、ちょっと変わっていて希少性がある。メッセージがある、打ち出すものがあると感じさせること」。お決まりのリクルートスーツを着て、面接塾で習ったことを言われてもよい反応はできないしどこにも引っかからない。「引っかかるところを、作ってください」
企業から教育の場へ
リクルートから公立中学(杉並区立和田中学校)の校長への”転職”を決めたとき、藤原さんは47歳。当時はリクルートで年棒制度のフェロー職に就いていた。「リクルートで経験したことや身につけたビジネスの技術を、それが通用しないかもしれない世界で勝負してみたくなったんです」。
当時、東京都では義務教育の場に民間人校長というのは前例がなかった。「第一号が好きなんです」と、藤原さん。「第一号は、いろんな人が助けようという気持ちになってくれる。他人のパワーが集まる。第二号と第一号では全然違う」
実際、藤原さんが校長として赴任した和田中学校ではノーベル賞受賞直後の小柴昌俊氏や詩人の谷川俊太郎氏なども杉並区に住んでいらしたこともあって授業に来てくれた。

「フェロー時代に教育改革にも関わっていて、審議会で意見を述べたこともあったんだけど、結局変わらなかった。やはり現場に立つことが大事なんだと思ったんです」。
リクルートで鍛えられた現場主義。「現場で何か一つ変えてみせる。それをマスコミに取り上げてもらって広めてもらえれば変わるんじゃないか」
この作戦は功を奏して、藤原さんが始めた「地域本部」や「よのなか科」は今では一万校以上に波及し実施されている。地域社会のパワーを学校に入れて、学校で教えられる知識と実際の世の中との架け橋になる授業だ。セカンドキャリアとなる公立中学の校長という仕事の場でも目覚ましい成果を上げていった藤原さんだが、ここでタケはどうしても聞いてみたかったことを投げかけてみた。
「企業と教育、全く違う環境で大変だったこともあったんじゃないですか?」
最初に感じたのは、教員のカルチャーが私企業とは全く違うということだったと語る藤原さん。「企業の社員のマネジメントは、人事権と予算権で動かすことができる。えらくなりたいなら頑張れ、と。一方、教員はえらくなりたいと思っていないから、同じようにはいかない。どんな点でリスペクトされるかが重要だった」。
そんな中、藤原さんは校長室をオープンにして生徒たちの出入りを自由にした。「生徒たちを呼び込むために、漫画を300冊くらい用意して、さらに、壊れたコンピューターを分解させたりもした」。校長室に行けば面白いことが起こる、と生徒の心を味方につけた藤原さんは次第に教師の心もつかんでいった。
和田中学校は、その後成績もぐんぐん伸ばし5年間で英語は区内のトップになり英検の成績では全国一万校の中で40位以内に入るなど大きな結果を出すことになった。それに伴い人気もうなぎのぼりで「入学したい」という親子が後を絶たず、ついには周辺の不動産相場をも動かすほどの経済波及効果を生むこととなった。
ピンチはチャンス

順風満帆にキャリアを積み上げてきたように見える藤原さんだが、実は30代であるピンチを迎えていた。「メニエール病を発症したんです。ただのめまいと違って、目の前の画像がくるっと回転するほどの気持ち悪さ。毎日注射を打たれて、後遺症が5年くらいは残りました」。この病がきっかけで藤原さんは自らの働きかたを見直すことになった。「それまでは仕事は当然ながら、飲み会も盛り上げるし接待もやり、部下の気持ちも鼓舞するとすべてに全力投球していたが、それを続けることが無理になった」。これまで歩んできた道から「”横に”どいて、モードを換えることにしたんです」。
「課長として10人のマネジメントをしてきた人が次長になって部下が30人になった。そこで行き詰る人がいる。何か工夫すれば上に上がれるというものではない。そんなときはいったん階段を下りてたとえば営業から専門職へ、工場へなどとモードを変更した方がいい。あるいは別の会社に転職するのも一つの方法です」。
「そういう状況って、まさにピンチですよね」とタケ。
「はい。年収は転職すると半分になりますね」と平然と答える藤原さん。驚くタケに「でも、そのリスクを抱えたままで続けていくと、先々には3倍のリスクが待っているかもしれませんよ」。
ここで藤原さんが教えてくれたのがすべてのサラリーマンが潜在的に抱えているリスクのことだ。「サラリーマンの唯一絶対のリスクは上司です」と、きっぱり。「上司があかんかったら、ビジネス人生の半分以上がダメになる。サラリーマンはリスクがなくて安定していると思っている人は気をつけた方がいい。自分にとってダメな上司に、自分を変えてまで合わせていくのか?」。
藤原さん自身がサラリーマンを辞めたのは40歳の時。「自分の人生のイニシアティブをとって主人公として生きるには、サラリーマンのままでは厳しいこともある」。
2020年の東京オリンピックまでは、転職市場も比較的良好だという。「チャンスはこの2、3年でしょうね」と、藤原さん。「まさに、ピンチはチャンス。時には年収が半分になる覚悟でも、新しいチャレンジをやってみた方がいい」。
「10年後、君に仕事はあるのか?」

藤原さんの新刊のタイトル『10年後、君に仕事はあるのか?』(ダイヤモンド社)を手にして、「ドキッとするタイトルですね」と苦笑いするタケ。「これからの10年で、一番大きな社会変化は世界の50億人がスマホでつながるということです」と、藤原さん。「スマホでつながるということは、映像や動画でつながる、つまり脳がつながるということ。さらにそこにAIロボットがつながっていく」。そうなると、今ある仕事の半分は無くなるか、あるいはAIと組んで進化していくことになるはずだ。
「一方で、新しく生み出される仕事もある」。それは、人間が本来しなければならない仕事に行きつくのではないか?そのようなテーマでの授業や講演を藤原さんは各地で行っている。
「それって、どんな仕事なんでしょうね」と聞くタケに、「それは生徒たちにブレストさせて考えさせたいんですが…」と前置きをしたうえで、ヒントを与えてくれた。
「高度に人間っぽい仕事でしょう。頭をやさしくなでたり、ぎゅっと抱きしめたり。保育や看護、介護の現場での対応という仕事は残っていくと思う」。意外なことに、医者の診断業務は続々とAIに取って代わられているらしい。世界中の論文を読み込んで似たような症例を探し出して診断するといった仕事は、AIにはかなわないからだ。
「知的な仕事は奪われて、人間的な仕事が残る」。手を使ったものづくりや、インスピレーションやイマジネーションを必要とする編集的な仕事、芸術的なもの、プロスポーツなど「人間の限界を超えていく姿を見せるようなものも残っていくでしょう」。
「この本はね」と、藤原さんの目がいたずらっ子のように光る。「高校生に向けて書いたようなふりをして、実はビジネスマンに、あなたの仕事はどうなの?と問いかけているんですよ」。
100万人に一人の存在になろう
藤原さんが、校長として生徒たちに一番伝えたいと思っている大事なことは「100万人に一人の存在になろう」ということだ。100万人に一人というのは、オリンピックのメダリスト級の希少性を持て、ということ。
ただし、と、こう続ける。「オリンピックのメダリスト”級”でいいんですよ。なにもピラミッドの頂点に立つメダリストになろうと言っているわけではありません」。
ひとつの世界で頂点に登ろうと思ったら、跡には屍が増える。誰にでも登れる階段ではない。それよりも大事なのは「面で考えて、自分がどこに旗を立てるか?」だと言う。分かりやすく言えば「3つのキャリアの掛け算です」。
どんな仕事も、例えば営業の仕事も一万時間くらいやれば100人に一人くらいの存在にはなれる。一万時間というのは期間でいえば、長くて10年、頑張れば5年くらい。そこで100人に一人になれたら、次は別のキャリアを積む。生産技術でも、広告でも、経理でも総務でも。そこでまた一万時間頑張って100人に一人になれれば、掛け合わせて一万人に一人の存在になれる。さらにもう一つキャリアを積めば「ほら、100万人に一人になれるでしょ」。
その話を聞いて「シャンパンタワーをイメージした」というタケ。一つのグラスがいっぱいになったらあふれて順に次々と満たされる、そんな絵が思い浮かぶ、と。

もっと具体的な例を一つ挙げるとすれば、と藤原さんが話してくれたのはこんなお話。
「ツアーコンダクターの仕事は面白いけど、大変だしずっと続けていると飽きることもあるでしょう。ツアコンの世界で一万人に一人になるのは難しいし、なったからと言って年収がそんなに上がることもない。だったら、100人に一人になれた時点で、犬系の仕事につくとします。トリマーでもブリーダーでも。いったん年収は下がりますよ、でも、そこでまた100人に一人になれれば、今度はツアコン×犬で、犬と一緒の旅の企画を立てて、自分が連れていくことができる。これはきっとニーズがあるから、収入アップにつながりますよ」。ここまでくれば最後の3つ目の掛け算も、あせらなくてもきっと発見できるはず。
ここでタケが嬉しそうにつぶやいた。「僕も掛け算できてますね。玉打ちと、ゴルフ場経営、英語、ラジオパーソナリティ…」。藤原さんも「タケさんの場合は、最後のラジオの仕事でゴルフとは別のファンを作っているところが大きいですね、最高の三角形です!」とニッコリ。
どんな場所でもリーダー力を発揮して、多くの人を魅了してやまない藤原さんに、最後にこう聞いてみた。「藤原さんにとって理想のリーダー像とは?」
その答えは、
「27歳くらいからずっとこう思ってきた。自分の上司は、世の中だ、と」。世の中を上司だと考えて、常に世の中との接点を大切に仕事をしている藤原さん。今後もますます大きなインパクトを世の中に与え続けてくれるに違いない。