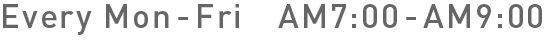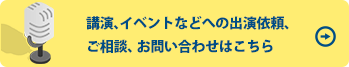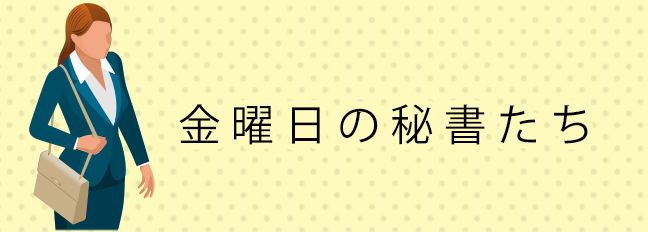『南部美人』という岩手県の地酒が、世界最大級のワイン/日本酒のオリンピックとも言えるIWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)の日本酒部門で、2017年の”チャンピオン・サケ”に選ばれた。
世界一の日本酒を造ったのは、1902年創業『南部美人』の五代目蔵元・久慈浩介社長。時代とともに変わりゆく酒造りの世界で、伝統を守りながらも新しいチャレンジを続ける久慈社長に、文化放送『The News Masters TOKYO』のパーソナリティでプロゴルファーのタケ小山がマスターズインタビュー。
元気なタケさんを圧倒するほど、パワフルで明るい久慈社長の夢は「世界中で、”日本酒”で乾杯!」
◆チャンピオン・サケ 南部美人

IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)というのは、イギリス・ロンドンで毎年4月に開催されるワインコンペ。”世界で最も大きな影響力を持つ”といわれている。日本酒部門(Sake Category)が設けられたのは2007年。
『南部美人 特別純米酒』は、2017年に出品された日本酒1,245点中のNO1″チャンピオン・サケ”に選ばれた。
日本酒部門は、純米酒や吟醸酒、本醸造酒、スパークリングなど9つのカテゴリーごとにブラインド・テイスティング審査が行われ、その成績により金メダル・銀メダル・銅メダルが授与される。(各メダルは複数表彰)2017年は9カテゴリーの合計で、金メダルは56銘柄、銀メダル225銘柄、銅メダル293銘柄が表彰された。
9カテゴリーの金メダルを獲得した酒のうち(2017年は56銘柄)、それ以上のレベルに達していると認められたものに”トロフィー”という称号が与えられ、更にその中から最も優れていると評価された酒に”チャンピオン・サケ”が与えられるという厳しいものなのだ。実は『南部美人』は、8年前まで金メダルさえ獲ったことがなかった。
「他のコンテストでは相当以上に受賞していたんですが、このIWCだけは獲れなかった」と久慈社長。
IWCの審査員の半分以上が外国人だ。「(10年以上かけて)日本酒は香りがいいだけではないということがわかってきたんじゃないでしょうか」年月と共に日本酒の正しい評価が育まれてきたのかもしれない。
「近年海外でも純米酒が評価されるようになってきました。世界が日本酒を飲むようになってきた証しです。これは凄いことです」ただ世界は、ワインの物差しで日本酒を評価する。
ワインでは肉料理には赤ワイン、魚料理には白ワインと一般に言われるように、料理とワインの組み合わせ”マリアージュ”が重要だ。それに対して日本では、酒があってそれに肴を合わせていく”酒の肴”という感覚。文化の違いを超えて広く世界で日本酒が飲まれるようになるには、”マリアージュ”や”テロワール”などが大事になってくると久慈社長は言う。
◆久慈浩介 五代目蔵元奮闘記
「実は、17歳まで酒蔵が嫌いだったんです。継ぎたいなんて思ったことなんか一度もなかったですよ」衝撃的で意外な事実が明かされた。
日本三大杜氏のひとつ、南部杜氏の里として古くから知られている岩手県。地元の二戸市に酒蔵は『南部美人』だけで、どこへ行っても「南部美人の息子」と直ぐにバレてしまう。
「エブリディ酒臭いし、エブリディ飲み会なんですよ。今ならいいですけどね(笑)」昔の酒蔵は杜氏たちが泊まり込みだった。「じっちゃん達が朝から晩まで、ずーっと一緒なわけですよ」それが思春期の辛い思い出だったそうだ。
そんな閉塞された家から飛び出したい一心で、17歳の時にアメリカ留学をさせてもらった。一生懸命に勉強をして岩手県の代表に選ばれて、オクラホマ州のタルサへ。ところが、久慈浩介少年の思惑とは逆の展開が待ち受けていた。
留学先のホストファミリーへ手土産に持っていったのが『南部美人』。飲んだパパは感激して「アメージング!」を連発。「コウスケ、酒蔵の蔵元にはなりたいと思ってもなれるもんじゃないぞ。ワイナリーでいえばオーナーの息子じゃないか。跡継ぎしたら毎日こんなに美味しい酒が飲めて、一体何が不満なんだ? お前は酒蔵を継げ!」と毎晩飲みながら同じ事を言われ続けた。
そしてホストファミリーとお別れをする晩にパパから「コウスケ、酒蔵を継ぐ気になったか?」と言われて送り出された。
留学最後の晩、エンパイアステートビルの展望階からニューヨークの夜景を見ながら酒蔵を継ぐことを決心したのだった。
東京農業大学醸造学科へ進学。「そこで出会ってしまったのが小泉武夫先生ですよ」発酵学の第一人者であり、漫画『もやしもん』のモデルとも云われている小泉先生に師事して、”泡盛”を勉強しに沖縄県石垣島へ行ったり、吟醸酒の歴史を変えた酵母”きょうかい9号酵母”発祥の地、熊本県の蔵元『香露』で勉強させてもらった。
まるでドラマのような出会いの連続で、日本酒の神様に導かれるようにして五代目蔵元となった久慈浩介社長。日本酒業界にイノベーションをおこしていく存在となっていくのだ。
◆魅惑の日本酒づくり

岩手県の酒蔵『南部美人』5代目蔵元となった久慈浩介社長。「まず手始めにやったことはなんですか?」とタケ小山。
「酒造りの見直しです。一番大変だったのは、炭素ろ過を止めることでした」炭素ろ過とは、炭で日本酒の余分な雑味や色を吸着させる技術。
「酒の味がマイナスになっちゃった時に、矯正するために作られた技術なんです。これは世界でも類を見ないほど素晴らしい技術なんですが・・・」ろ過してキレイにすると同時に、お酒の香りやいい味までも取ってしまうのだそうだ。
しかし、その当時は炭素ろ過をしない日本酒は考えられなかった。「炭素ろ過を止めて南部美人を造ろうと提案したところ、猛反対したのが親父。胸ぐらつかみ合いの喧嘩になりました」常識だと思われていた考えを改めてもらうのは難しいものだ。
「炭素ろ過をしなくても美味しいお酒を造ればいいんでしょ」というのが五代目の言い分だが、無濾過の日本酒は蔵の技術がはっきりとわかってしまうのだ。
さらに炭素ろ過を止めたとしても別のハードルがあった。無濾過の日本酒は冷蔵で貯蔵しなければならないのだ。冷蔵庫と電気代に莫大な経費がかかってしまう。
「炭素ろ過したお酒を涼しいところに置いておくほうが経営で考えれば効率的ですよね」
当時、常識と思われていた炭素ろ過だが、『十四代』をはじめ無濾過の日本酒造りこだわる蔵元が現れはじめていた。20数年前、久慈社長たち一部の蔵元が舵を切った無濾過の日本酒造りだが、今では主流となっている。
◆日本酒を海外で!

李白酒造(島根県)の田中社長と利休梅の大門酒造(大阪府)の大門社長が「日本酒は世界に通じるお酒だ。日本酒を世界に広めたいんだ」と、90年代に業界に呼びかけていた。そして97年に約20社の酒造メーカーで『日本酒輸出協会(SEA/Sake Export Association)』を設立。その中には、まだ蔵に帰ってきたばかりの久慈浩介さんが南部美人として参加していた。
「家業を継ぐなら、自分が造った酒をアメリカに持っていかなければならない。それこそが恩返しだろうと思っていたんです」17歳の時に留学したホームステイ先で人生の進路が大きく変化した久慈浩介少年。ニューヨークの夜景を見ながら世界中の人達に日本酒を飲んでもらいたいと誓ったのだ。
日本酒を海外で飲んでもらうために「まずは、日本酒というものがどういうものなのかを伝えていこうじゃないかと。それを伝えられるのは蔵元しかいない」『日本酒輸出協会』は、蔵元自らが世界中で日本酒の啓蒙普及活動をする団体だ。
初の活動となったのが、ニューヨークのジャパン・ソサエティーから「日本酒のセミナーを初開催したい」とのオファーだった。十数の蔵元がそれぞれの大吟醸を持ち寄りニューヨーカー達に飲ませたところ、あちこちのブースから「オーマイガー!」「この酒はなんなんだ?」という声が聞こえてくる。大成功だった。
◆夢は、世界中で”日本酒”で乾杯!
「実は、人生をかけて追い求めている夢というのが、世界中で”日本酒”で乾杯することなんですね」
蔵元自らが世界を回って日本酒を広めていく地道な活動は生涯続けていくという久慈社長ですが、「でも、目の前に世界中の人が、この国に集まる大きなイベントがあるじゃないですか!」2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年の東京オリンピック・パラリンピック。
「日本に来て、お寿司を食べてみたい、日本酒を飲んでみたいという外国人をちゃんとおもてなしできるようにしたい」
そして、「そのイベントに付随して各所でパーティーが開かれる際に、乾杯はシャンパンではなく是非日本酒でやって欲しい」
しかし、パーティーではウエルカムドリンクで渡されるお酒で乾杯になってしまう。「シャンパンなんですよ!なので日本酒のスパークリングをつくりました」
発泡する日本酒そのものは古くからあるが、透明で泡立ちの強いものは技術的に難しく普及していなかった。世界基準となりうる日本酒のスパークリングを、”透明であること””瓶内二次発酵であること””ガス圧がシャンパンと同じ位であること”と定めた。とは言えこの基準をクリアするのはなかなか難しい。
タケ小山は「もともとちょっと濁っている部分が発酵している訳だから、透明って難しいんじゃないですか?」
「そうなんです。でも濁っているスパークリングがパーティの場で出されることはちょっと考えづらい」
それらを可能にしたのが『一般社団法人 awa酒協会』。群馬県の永井酒造の呼びかけで久慈社長も含め9つの蔵元で構成されている。
「ステージでは鏡開きをするが、それを配る時間が無いから、手に持っているもので乾杯してしまう。そん時にawa酒、透明な日本酒のスパークリングを持っていれば、それで乾杯!となるわけですよ」
南部美人 五代目蔵元 久慈浩介社長の夢の実現が近づきつつある。