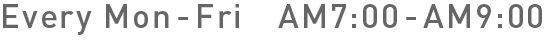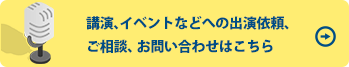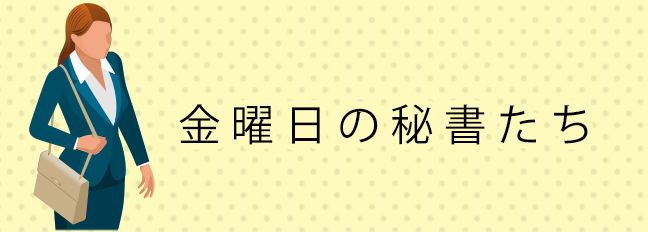文化放送「The News Masters TOKYO」マスターズインタビュー。今回のお相手は「ロック・フィールド」の代表取締役会長兼社長の岩田弘三さん。創業は1972年で、「神戸コロッケ」やサラダの「RF1」といった惣菜店を、全国に300店舗以上展開するロック・フィールド。もともと神戸で飲食店をやっていた岩田会長が、海外で見たデリカテッセンに感銘を受け、創業した。自身でもよくお世話になっているという番組パーソナリティーでありプロゴルファーのタケ小山が、創業当時の話から伺い始めた。

◆日常的なお惣菜にシフトした理由。

タケ「最初は、ローストビーフやテリーヌといった高級料理や高価なギフトがメインだったそうですが、そこからなぜ日常的な惣菜のお店を始めたのでしょう?」
岩田「社会が変化する中で、女性の社会進出、そしてアメリカでは先にミールソリューションといったムーブメントがあって、日本もきっと惣菜を求める時代がくると思いまして。」
中でも、惣菜という字は「物」に「心」、そして野菜の「菜」。このことから日本の惣菜は、野菜中心、それもサラダを選択すべきと考えたのだ。稼ぎ頭であったギフトから撤退し、日常的な惣菜に特化すると決めたのも、家庭の食をもっと豊かにする方が、将来的に可能性が高いのではと思ったからだと。岩田会長はこんなエピソードも披露してくれた。
「うちに山口という社員がいまして。彼女は惣菜を買ってきたときのお母さんが大好きだと言うんです。」
帰ってくると、調理している母に「危ないからあっちへ行っとき!」と言われた子どものころの山口さん。一方、お惣菜を買ってきたときは「ただいま~」と言って、抱きしめてくれた。そのときの温かみが本当に嬉しかったのだそうだ。それが彼女が、お惣菜の会社で、ロック・フィールドで働きたいと思った理由だった。
「ちょっと話が出来過ぎちゃう!?と思ったけど、そんなことに僕らは貢献できているのかとも思いましたね。」と話す岩田会長。
お惣菜は、こうした形で女性の社会進出の手助けにもなっていることをタケや番組スタッフは改めて知らされた。
◆トヨタをベンチマークに!?

最初は反対されつつも、事業も軌道に乗り、徐々に総菜・サラダに特化していったロック・フィールド。市場からも、それをより強く求められるようになった。そこで岩田会長の頭には一つのことが浮かんだという。
「日本の物づくり企業として、どこをライバルにしようかと考えた末、やっぱりトヨタさんなんじゃないかと。」
トヨタ自動車をベンチマークにすると表明したのだ。「なんとかご指導お願いできないでしょうか。」とお願いするも、トヨタ自動車関係者は、畑の違う業界からのお願いに戸惑ったのは想像に難くない。その後、何とか協力までこぎつけることに成功。だが、まず言われたのは、無情にも1億8000万円かけて作ったコンピューターの自動倉庫を壊すことだった。
「商品は溜めたらあかん」と。
それこそがトヨタ流、トヨタ自動車の特徴ともいえるジャストインタイム生産システム(必要な物を、必要な時に、必要な量だけ生産すること)だった。2、3日溜めるのは問題ないが、それ以上は認められなかったのだ。生産面で言うと、さらにこんなこだわりもある。
タケ「え、自分たちでジャガイモの皮を剥くんですか?」
岩田「ジャガイモはすぐに褐色化します。そうなるとポテトサラダが茶色くなります。」
品質が落ちることを考慮し、野菜の下処理は自社でやっているロック・フィールド。さらには、じゃがいもも、キュウリも人が剥いたり切ったりしている。品質を高めるためには手間を惜しまない、商品力は人が手を施したのが一番なのだ。
◆神戸コロッケに始まり、東南アジア料理へ

ロック・フィールド躍進の原点、「神戸コロッケ」はどのようにして生まれたのか?タケは、こう切り出した。
タケ「色々ある中で、なぜコロッケだったんですか?」
岩田「僕の先輩で、お菓子屋さんの方で『単品ド迫力をやれ!』と言われまして」
「単品ド迫力」この言葉をヒントに、コロッケを「神戸のコロッケ」と命名したのが「神戸コロッケ」としてヒットしたのだという。神戸コロッケ1号店開業は1989年で、そこからおよそ30年の歳月が流れた。そんな岩田会長のアンテナに今、引っかかっているものとは何なのだろうか。
「これからは、ベトナム、タイ、シンガポールなどのASEANです。」
サンフランシスコに「スランテッドドア」という人気ベトナム料理店がある。ロック・フィールドとしても、サンフランシスコにスタッフを送ってベトナム料理を教えてもらう予定なのだそうだ。さらに現在、ロック・フィールドの中にある『アジアン・サラダ 融合』というブランドでは、パクチーがよく売れている。国外・国内のこうした状況からも東南アジアから目が離せないとも説明してくれた。
加えて、岩田会長が注目しているのは、食のジャンル・食材としての東南アジアだけではない。
「本当に今、工場で働く人たちが激減していまして。ミャンマーとは、”技能実習生として学びたい”という女性を受けいれる関係を築いています。」
ミャンマーにある日本語研修学校の中に職業訓練所のような場所を提案し、そこで日本語だけでなく、惣菜企業の衛生管理や働き方に関する教育を経て、日本で働いてもらおうと考えている。食材だけでなく人材の面からも、東南アジアに熱い視線を注いでいるのだ。
◆大事にしてきた言葉

中食業界を常にリードしてきたロック・フィールドの岩田会長。彼を動かす、彼の核となる考えやポリシーとは何なのだろうか。
タケ「社員にいつも伝えていることはありますか?」
岩田「『成功体験に溺れず、常に自己イノベーションに励むこと』です。」
過去、うまくいったときに、それに溺れてしまうことがあったという。ダーウィンの言葉に「生き残るものは変化し続ける」という言葉がある。生き残ってきた人たちは、強いから、賢いからではなく、時代をしっかりみつめながら、時代の中で新しい価値を創造した。それが、生き残ってきた所以であり、そこに岩田会長は強い共感を示しているのだ。
タケ「他の言葉はいかがでしょうか?」
岩田「『マイノリティにこそ未来がある』です。」
少数派の方が多数派よりも可能性があると信じる岩田会長。もちろん、多数派になることは大事であるのに対し、少数派にはリスクも伴う。そうしたことから、とかく経営方針とは、多数派になびかせてしまいがちだ。そうは言っても、未来のビジネスの種を植えて育てるには、多数派の反対側、少数派にこそチャンスがあると考えている。その結果が、現在は成長目覚ましい中食市場を予見し、成長してきたロック・フィールドであり、「RF1」ブランドでもあるのだ。
◆今後のロック・フィールドが果たす役割

創業は1972年。当時の中食の市場は約3000億円、それが今や10兆円を超えている。成長が目覚ましい中食市場について岩田会長はどのようにとらえているのだろうか?
タケ「中食を扱う店増えていますね。これは健康志向ということでしょうか?」
岩田「健康志向ですね。一日野菜を350g食べなさいと言われてますが、生野菜でこれだけ食べるのは難しいです。加熱するとたくさん食べられるので、加熱をした中で、新しい提案をしていこうと、この一年くらいやっています。」
さらに岩田会長はこうも続ける。「高齢化社会という面もあります。」
健康上の理由において日常生活が、制限されることなく過ごせる健康寿命は、2016年、男性72.14歳、女性74.79歳である。一方、平均寿命は、男性80.98歳、女性87.14歳。不健康な時代というのが迫ってくるが、それに対して、いかに健康寿命をのばすことができるかという試みもやらなければと考えている。そうした高齢化社会が進む日本で、一企業として担う今後の役割について最後にタケが切り出した。
タケ「ロック・フィールドは今後、日本の食文化にとってどんな存在になっていくでしょうか?」
岩田「一番は健康と食。そして食卓は人間関係のコミュニケーションのツールになることは間違いないので、人間関係の絆になればいいなと思っています。」
人間関係の絆の一助となる。その中で、家庭を持つ親御さんが、最後の仕上げは、ご自身で行うような商品をだしたいとも考える岩田会長。買って帰るだけでなく、例えば最後にオーブンで焼くといった、家庭の人々が調理人として参加するものを演出したいのだそうだ。
中食業界のリーディングカンパニー「ロック・フィールド」。常にその地位に慢心することなく、次を見据えて成長を続けてきたことが分かる今回のマスターズインタビュー。ここで、タケに岩田会長が語ってくれた「東南アジア料理」や「最後の仕上げを家庭でする商品」が、定番になる社会とは20年後のことだろうか、10年後のことだろうか。それとももっと近い将来なのだろうか。それは誰にもわからない。しかし、中食業界の新たなフィールドは、確実に近づいてきている。