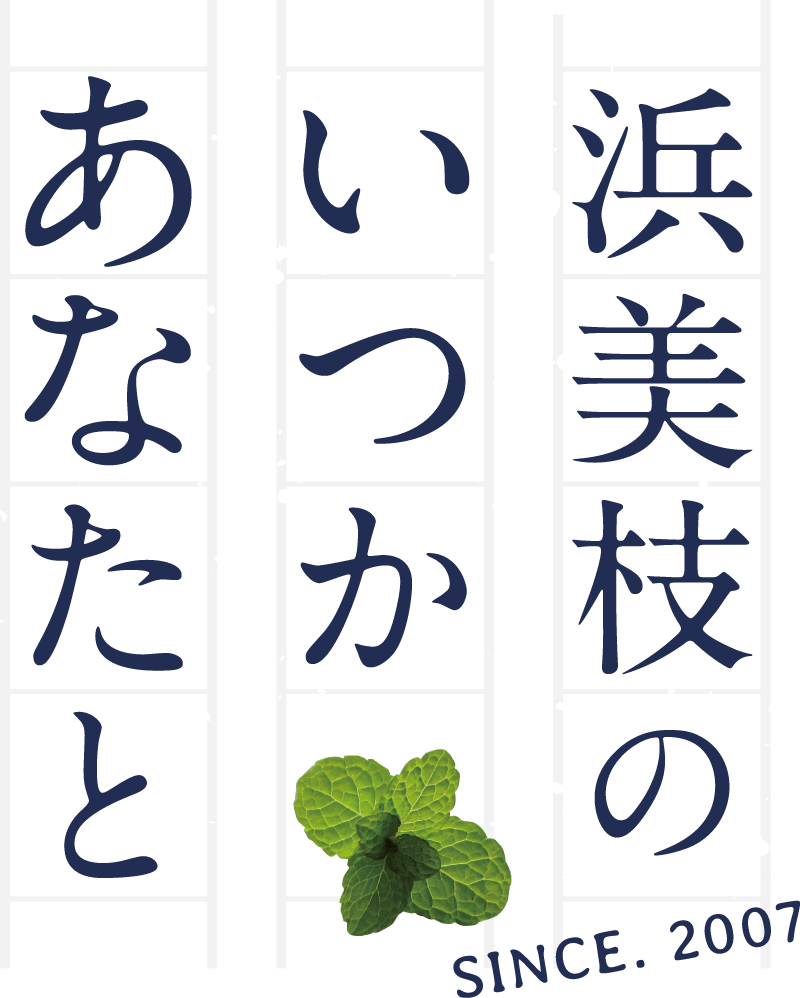寺島尚正 今日の絵日記
2025年1月20日 春遠からじ
このところ空気が乾燥している。
空気の乾燥は、とりわけ火災に繋がりやすい。住宅火災は勿論だが、山梨県の甲府市と笛吹市にまたがる山で18日、火災が発生した。
およそ1日がたっても燃え続け、こちらを記している19日夕方現在も火は尾根を挟んで甲府市側と笛吹市側に向けて延焼中だという。
今のところけがをした人はおらず、ふもとの住宅などへの延焼の危険性はないということである。
今後の雨に期待したい。
昨年末12月26日の夜、山梨県上野原市で発生した山林火災が、9日経過した1月4日の午後1時にようやく鎮火という事例もある。
一旦起きると厄介なのが山火事なのだ。
世界に視野を広げれば、アメリカでは今月7日からロサンゼルス周辺で相次いで山火事が発生し、これまでに27人が死亡したほか、一時は30万人以上に避難の指示や警告が出され、発生から10日がたった今も多くの人が避難生活を余儀なくされているのはご存じだろう。
近年世界では様々な国や地域で大規模な森林火災が起こり深刻な問題となっているが、特にカリフォルニアやオーストラリアでは大規模な火災が毎年のように発生する。
海外で報告されてる山火事は、煙草の不始末、落雷、送電線の切断による引火、焚火や野焼きの火が燃え移る以外に記録的猛暑による熱波で自然発火もあるときく。
急激な高温で山の木々が自然に燃えるのは、風で枝が擦れ合って摩擦で火が出来、それが乾燥した落ち葉に広がり山火事もなりのだ。
それに比べて、日本では山火事は少ないという。
しかしそれでも毎年1,000~2,000件程度の森林火災が起こっている。
ただし、これらの火災は通常、規模が小さく、山岳地帯などの人里離れた場所で発生することが多いため、大きな被害にはつながりにくいと聞いた。
日本の気候は、四季がはっきりとしており、特に湿度が高いため、乾燥した環境を必要とする山火事が発生しにくいという。
日本の夏は高温多湿で、冬は比較的湿度が高く、火災の原因となる乾燥状態が長期間続くことが少ない。
これに対し、カリフォルニアやオーストラリアは乾燥した気候が長期間続き、特に夏季は低湿度と高温が続くため、火災が起きやすくなる。
また海外の場合、火災が非常に広範囲にわたることがあり、住民や動物への影響も大きく、対策が難しくなる。
これが日本との大きな違いの一つだという。
林野庁によると、日本は国土の約7割が森林であり、森林は国土の保全、水源のかん養など私たちの生活に大切な役割を果たしている。
また、最近では地球温暖化防止のための二酸化炭素の吸収源として期待されている。
ところが、森林は一旦火災などで失われると、その大切な機能が回復するまでには何十年もの年月と多大なコストを要することになる。
5年間(平成30年~令和4年)の平均でみると、1年間に約1.3千件発生し、焼損面積は約7百ヘクタール、損害額は約2.4億円。
これを1日あたりにすると、全国で毎日約4件の山火事が発生し、約2ヘクタールの森林が燃え、約70万円の損害が生じていることになる。
例えば群馬県内での令和5年の山火事発生件数を調べると17件で、昨年から2件減少したが、過去5年間では2番目に多く発生した。
山火事は道路や地形の条件等から、発見が遅れたり、消火が難しい場合も多いため、ひとたび発生すると、大きな被害をもたらす恐れがある。
平成26年4月に桐生市で発生した山火事では、消火活動を開始してから完全に鎮火が確認されるまでに2週間以上を要し、190ヘクタール(東京ドーム約40個分)を超える森林が被害を受け、県内過去最大規模の被害となった。
この山火事跡地では、森林の復旧事業などが進められているが、焼けてしまった森林を再生し、災害を防止するなどの公益的機能を回復させるまでには、多くの費用と長い時間が必要になる。
このため群馬県では昨年3月1日から5月31日は、山火事予防運動実施期間とした。
例年、この時季は空気の乾燥や強風などにより、山火事が発生しやすい気象条件となることが多くなる。
また、行楽や野外での作業に適したシーズンとなり、山林への人の出入りや、野外で火を使う機会が増えることなどもあって、例年、年間の山火事発生件数の約7割が3月~5月に集中している。
山火事の発生には季節的な特徴がある。
山火事の約7割が冬から春(1月~5月)にかけて集中して発生する。
これは、冬は森林内に落ち葉が積もって燃えやすい状態になっていることや、風が強いこと、特に太平洋側は乾燥した状態になるといった自然条件が重なること、また、春先は、行楽や山菜採りのために山に入る人が増加するほか、農作業に由来する枯草焼きなどが山林に飛び火することも原因だからだ。
日本の山火事のほとんどは、人間の不注意によって起きている。
このことは、私達一人ひとりが火の取扱いに注意することで山火事を未然に防止できるということでもある。
発生した林野火災のうち原因が明らかなものについてみれば、「たき火」が32.5%で最も多く、次いで「火入れ」、「放火(疑い含む)」、「たばこ」である。一方、落雷など自然現象によるものは稀なのだ。
そのことから、
枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない
たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する
強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない
火入れを行う際、許可を必ず受ける
たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てない
火遊びはしない・・など協力が呼びかけられている。
貴重な森林を山火事から守るためにもルールはしっかり守りたい。

春遠からじ
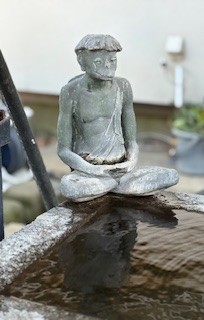
火の用心