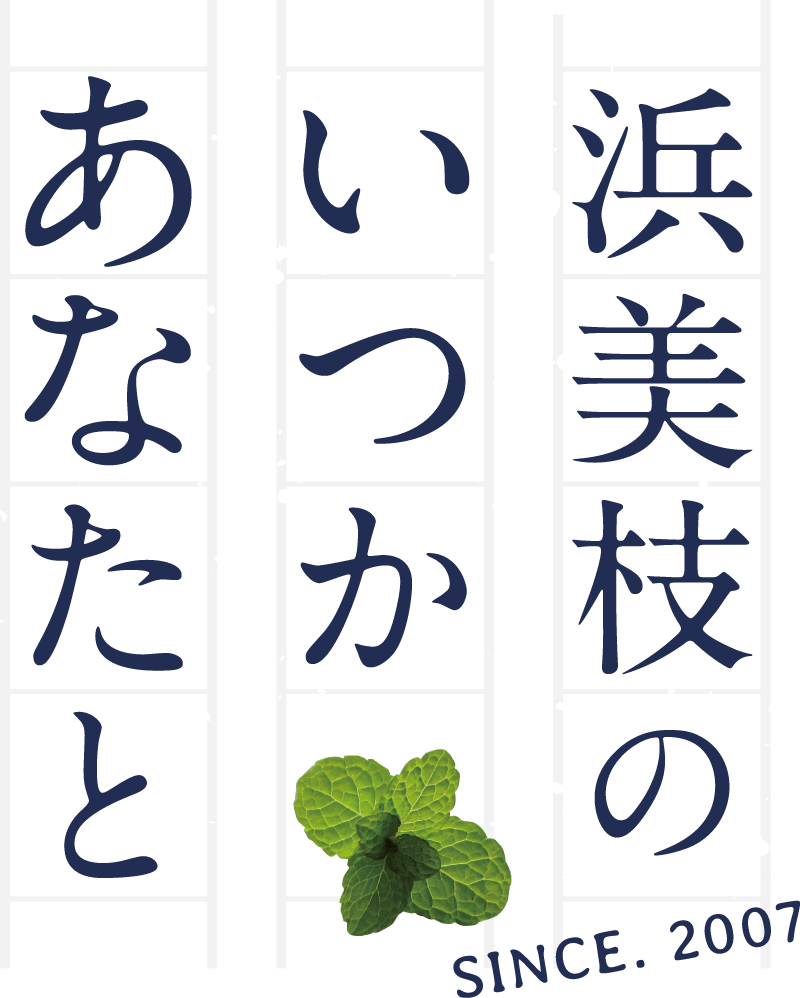寺島尚正 今日の絵日記
2024年12月9日 便利の陰に危険あり
12月も半ばに近づいてきて、朝晩は冬らしい気温になった来た。
小生、今シーズンから防寒対策として、電熱ウエアを着用している。
これが大層優れもので、背中を温め手袋やマフラー、マスクを着用すれば、寒さに負けない自信がある。電熱ウェアの電源は「リチウムバッテリー」。
そんなリチウムイオン電池が使われた製品の発火などの事故が増えているとして、消費者庁は、製品に強い衝撃や圧力を加えないなど正しい使い方をするよう注意を呼びかけている。消費者庁やNITE=製品評価技術基盤機構によると、
モバイルバッテリーやスマートフォンなどリチウムイオン電池が使われた製品の発火などの事故の件数は、去年1年間で397件に上り、増加傾向だという。
また冬の時期には、電熱ウェアや充電式カイロなど、暖める機能を持った製品に搭載されたリチウムイオン電池が、充電中に発火する事故も相次いでいると聞く。リチウムイオン電池は衝撃や熱に弱い性質があるとして、消費者庁は、製品に強い衝撃や圧力を加えないようにすること、充電は安全が確認できる時間と場所で行い、完了したらプラグを抜くこと、推奨されている充電器やバッテリーを使うこと、さらに、ごみ処理施設で発火する事故も相次いでいることから、搭載された製品を捨てるときは、自治体の指示に従って正しく捨てるように呼びかけている。
私たちの身の回りには、電気を使って動く道具が数多くある。リチウムイオン電池は小さくてパワフルというメリットを生かし、さまざまな機器に搭載されている。特にスマートフォンやパソコン、デジタルカメラなどが小型軽量化、長寿命化されたのも、リチウムイオン電池が採用されるようになったからだ。
例えば、コードレスの掃除機やアイロンなどの小型の家電、電動自転車や電動バイクなどの乗り物や、家庭で太陽光発電などを活用して昼間に発電した電気を貯めておくという用途にも、リチウムイオン電池が使われている。私達は正しい知識で正しく使わねばならない。
充電して繰り返し使える二次電池には、鉛蓄電池以外にもニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池などがある。そうした電池と比べた場合にもっとも分かりやすいリチウムイオン電池のメリットは、小さくて軽いのにパワフルであること。同じサイズでこれらの電池の特徴を比べてみると、鉛蓄電池は2.1V、ニッケル水素電池は1.2V、ニッケルカドミウム電池は1.25Vまでの電圧しか出せない。これに対して、リチウムイオン電池ならば3.2~3.7Vという高い電圧まで出せる。また、リチウムイオン電池は電気を作る時に他の二次電池のような化学反応を利用しない。そのため他の二次電池に比べて電極の劣化が少なく、充電や放電の繰り返しにも非常に強い。加えて、リチウムイオン電池には急速充電ができるという大きな特徴がある。もっとも、充電を短時間に行う急速充電は、リチウムイオン電池以外の二次電池でも可能だ。しかし、ニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池では充電の終了判定が難しかったため、実用化されなかった。リチウムイオン電池では、充電器側で終了判定が可能になったので実用化されたと聞いている。さらに電池には、使わなくても自然に放電してしまう「自己放電」という現象がある。例えば、1カ月以上乗らなかった自動車のエンジンを掛けようと思っても、電圧が低くてスターターを回せないことがある。こうした、いわゆる「バッテリーが上がった」状態を引き起こす原因が、自己放電なのである。自己放電は、放置しているだけでも少しずつ化学反応が進行することで起きる。一方、他の二次電池で起きる電池反応とは少し違った反応を用いるリチウムイオン電池では、ほとんど自己放電は起きない。ちなみに、リチウムイオン電池を搭載したスマートフォンやパソコンの場合、使っていないのに電池が減っていることがある。それは、画面が消えていても完全に電源がオフになっているのではなく、すぐに起動できるように微量の電気を消費しているからなのだ。
一方で、誤った廃棄方法などによって火災が多発するといった危険性が問題視されている。リチウムイオン電池の発火が多発する原因を調べてみた。
東京消防庁のデータを見ると、令和5年中における製品用途別の火災状況をみると、モバイルバッテリーから出火した火災が最多で、次にスマートフォン、電動アシスト付自転車となっている。出火した製品は多種にわたっている。
まれな内訳を見ると、非接触型体温測定器、センサー式手指消毒器、CO2濃度測定器、水素水生成器、掃除用電動ブラシ、ハンディターミナル、ビデオカメラ、カラオケマイク、電動グラスホルダー、電気あんま器、健康器具、ドローン用バッテリー、電動車いす用バッテリー、自動車用バッテリー、電気自動車、電気バイクもあった。つまり、ほぼ全てで起こりうるのだ。
発生した火災の製品用途別の出火要因をみると、いつも通り使用していたが出火が39件(23.4%)、衝撃等が18件(10.8%)、分解廃棄等が16件(9.6%)発生している。また、製品の欠陥により出火した火災が6件(3.6%)発生している。出火要因が特定できないものは67件(40.1%)となっている。
出火前の製品の状況をみると、出火前に何らかの異常がある製品から出火した火災は16件(9.6%)。出火時の充電状況は、充電中が82件(49.1%)、非充電中(待機中含む)が65件(38.9%)、使用中が10件(6.0%)である。
リチウムイオン電池に使われる電解液は、引火性のある有機溶媒だ。そのため、衝撃や損傷によって、電極物質同士が触れ合うと化学反応が起きて熱が発生し、電解液に引火することで発火する危険がある。
実際の例について、駅利用客が、鞄の中から煙が出ているのを利用客から知らされたため、ホーム上に鞄を置いたところ、鞄の中に入れていたモバイルバッテリーが何らかの要因で短絡し出火したケース。シアター内で映画鑑賞中の観客が所持していたリュックの中のモバイルバッテリーが何らかの要因により出火したもの。無人の事務所のデスク上で充電されていた携帯型扇風機が何らかの要因で短絡し出火した場合もあった。
電池の発火につながる、やりがちなスマホに代表される、モバイルバッテリーのやってはいけない行動例をあげてみる。
・ポケットに入れて座ってしまい、圧力が加わる
・ぶつけるなどの強い衝撃を与える
・スマホなどを分解する
・携帯カイロなどの発熱物と一緒にポケットやカバンに入れる
・熱がこもってしまう布団やタオルなどの中に入れる
・コンロ、ストーブなどの火のそばに置く
・サウナに持ち込む
・ぬれたスマホをドライヤーや電子レンジで乾かす
火災を防ぐためには・・
1.使用する前に取扱説明書をよく確認する。
2.衝撃を与えないよう適切に取り扱い、むやみに分解しない。
3.製造事業者が指定する充電器やバッテリーを使用する。
4.充電する際は整理整頓された場所や不燃性のケースに入れて充電をする。
5.充電器の接続部が合致するからといって充電電圧を確認せずに使用しない。
6.膨張、充電できない、バッテリーの減りが早くなった、充電中に熱くなるなどの異常がある場合は使用をやめ、製造事業者や販売店に相談する。
7.製造事業者の問合せ先の記載がない製品や販売店や製造事業者の連絡先に電話がつながらない製品もあるので製品を購入する際には慎重に検討する。
8.熱のこもりやすい鞄の中などでの使用を控える。
9.万が一の被害に備えて不燃性のケースなどに収納する。
10.処分する際は、製品の取扱説明書をよく確認する。
11.不用品を処分する際は、地域のごみ回収方法をよく確認する。
特に廃棄時は、発火の危険が多く潜んでおり、近年で見ても廃棄の時に往々にして発火が発生している。ゴミの分別ルールを守らず、リチウムイオン電池を含む製品を誤って廃棄した場合など、ゴミ収集車やゴミ処理施設で発火や爆発が起こる事故が多発しているのである。環境省の調査によると、リチウムイオン電池を含むリチウム蓄電池起因の火災事故件数は、年間1万件以上も発生している。事故原因の多くが、「不燃ごみ」として混入していたことによるもの。不燃ごみは処分場のスペース確保のため、細かく砕いてから処理することがある。その時にリチウムイオン電池が混ざっていると、発火などにつながる危険があると容易に想像できる。
火災事故は、処理施設等の従業員に危険を及ぼすことはもちろん、施設の損傷、清掃工場の稼働停止によって日常生活に大きな支障を与える。火災事故による損害は甚大で、損害額は数億円にも及ぶ。リチウムイオン電池は、使用時だけでなく、廃棄時も発火の危険性が潜んでいること、そして事故による被害が甚大になりやすいことを常に認識しておくことが重要である。小生も、使用する際の注意点をよく理解し、例えば充電時、留守にしないなど、もしもの際の時を考えてこれからも使用していくつもりである。
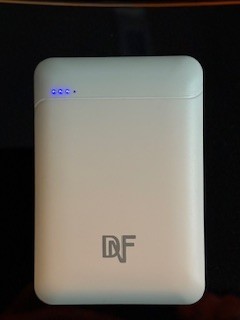
便利の陰に危険あり

防寒衣料
- 12月 2日
- 12月 9日