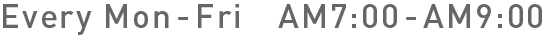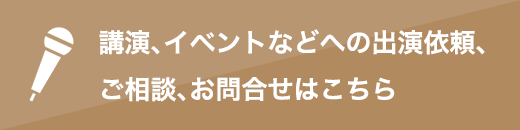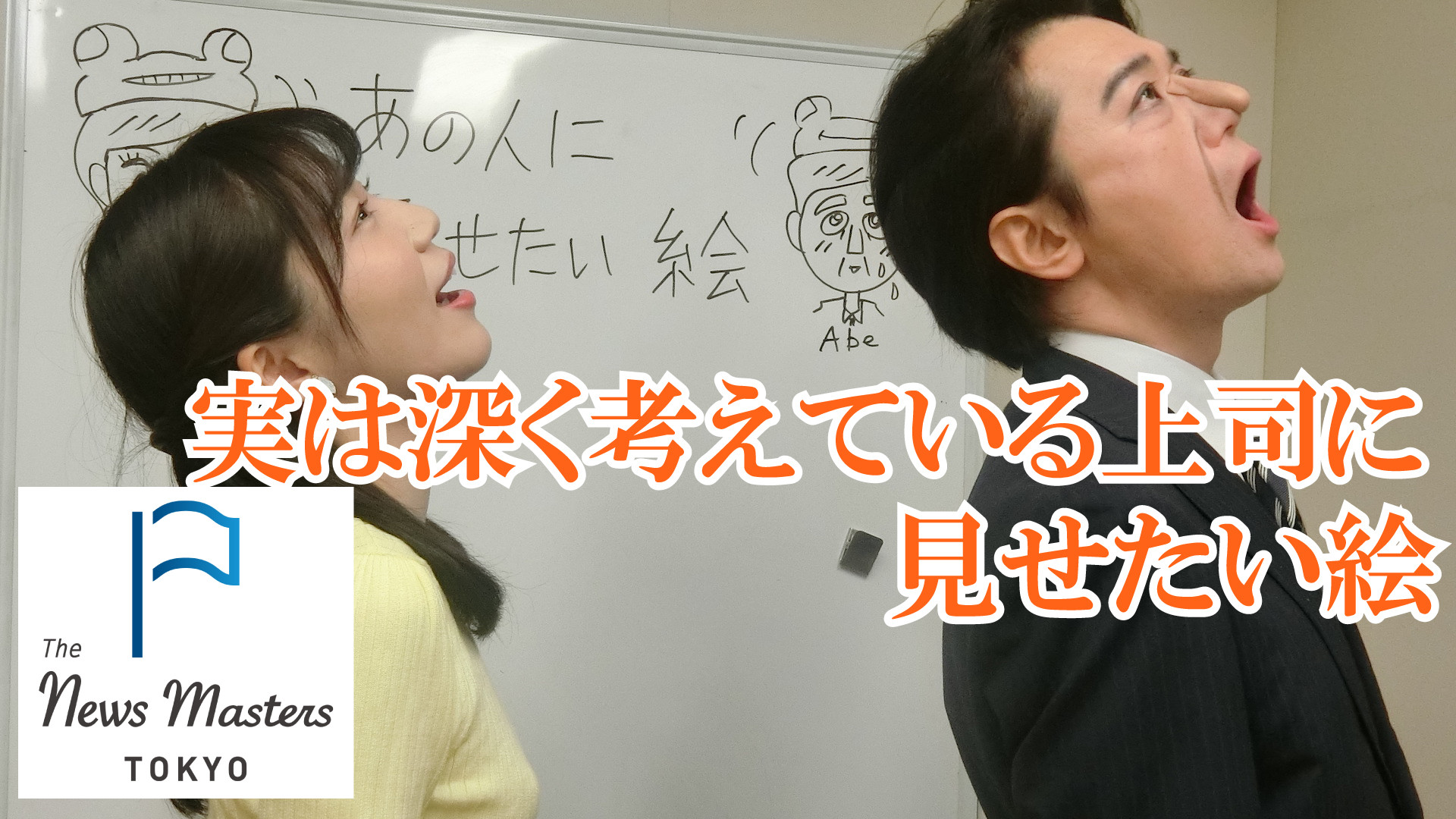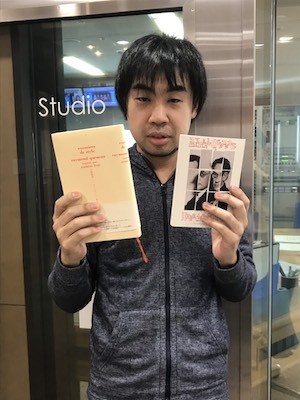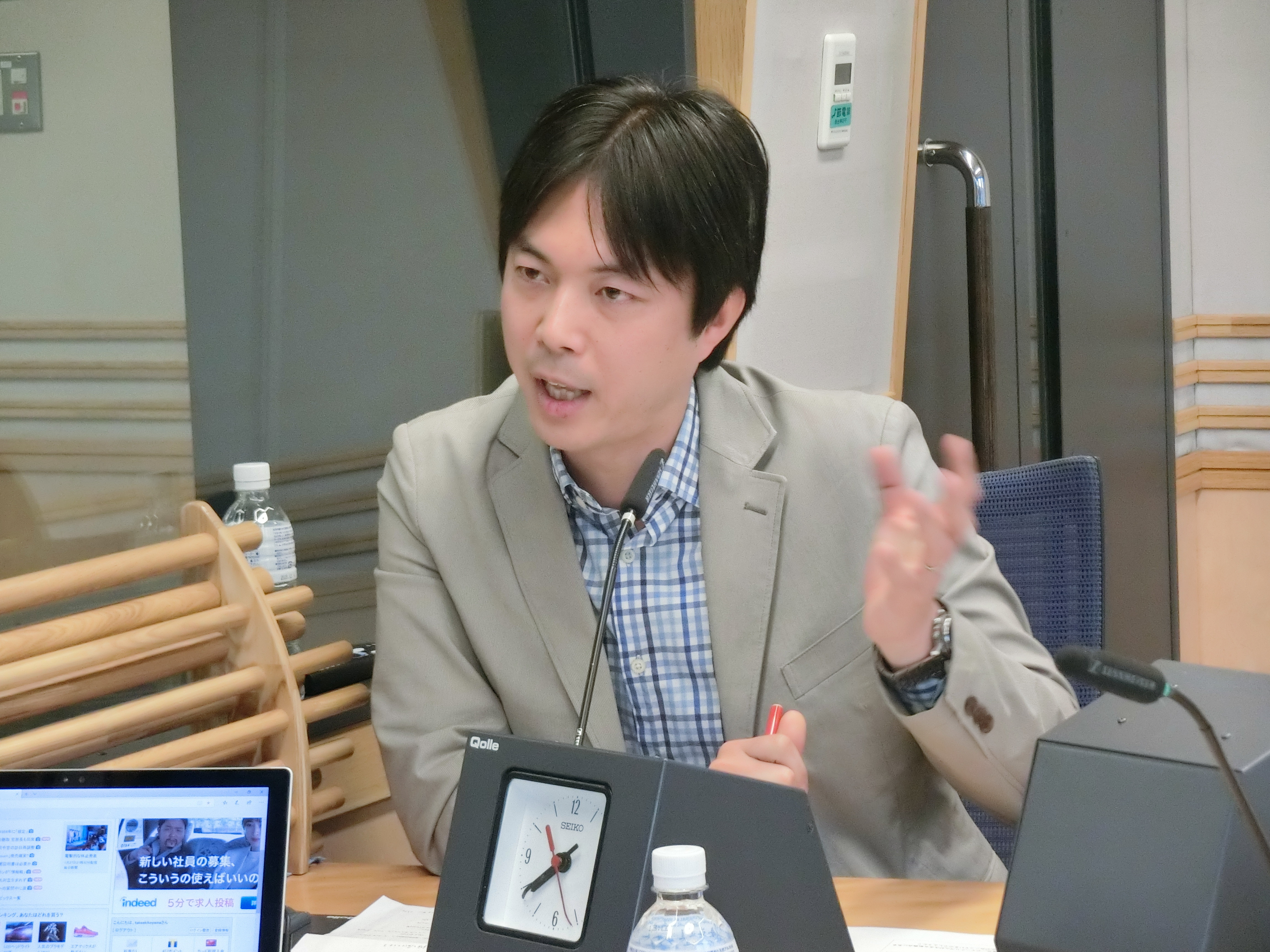「この世で一番美しいもの」のための桂由美の決断

文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビューに今回登場するのはブライダルファッションデザイナーの桂由美さん。株式会社ユミカツラインターナショナルの経営者であることと、自ら現場の第一線に立ち続けるデザイナーであること。その両立を軽やかにしなやかに、そしていつも楽しそうにこなし続ける桂さん。そのパワーの源はいったいどこにあるのか?タケ小山が、その秘密に迫ります。
「自分がやるしかなかったから」~ブライダルへの第一歩
桂由美さんが日本初のブライダルファッションデザイナーとして活動を開始したのは1964年のこと。当時、日本にはブライダルという言葉はまだ存在していなかった。「なぜ、まだ日本にはその概念さえないような新しいことをやろうと思ったんですか?」と聞くタケに、桂さんはこう答えた。「誰もやっていなかったから、自分がやるしかないかなと思ったんです」。
そもそもの始まりは、母親が経営していた洋裁学校で教鞭をとっていた頃のこんな経験だったという。「生徒たちの卒業制作でウェディングドレスを作ることになったんです。ドレを作るにはたくさんの生地を使うから値段が結構高くついてしまうので心配で、アドバイスをするために一緒に買い物についていったときに、びっくりしたことがあったんです」。
「それは、なに?」とタケが聞くと、「日本には、ウェディングドレスに必要なものが本当に何にもないな、と」。たとえば、真っ白なドレスに合わせるための白いハイヒール。花嫁が手に持つブライダルブーケ。どこを探しても見つからなかった。
もちろん銀座を歩けば、例えば森英恵さんのような有名ファッションデザイナーのオシャレな店舗はあった。だが、ウェディング用の衣装となると、「みんな、着物だったんです」。
調べてみると、その頃結婚式を挙げる女性の97%が着物を着用していたという。たった3%のシェアしかない洋装のウェディングドレス。その領域にビジネスの手を伸ばす人はいなかった。
「生徒のひとりがね、先生、みんなを助けてあげたらいいのにって言ったんですよ」と笑う桂さん。「正義感の強い性格だったから、困っている人がいるなら助けたいなって思ったんです」。
拒絶を乗り越えて
タケが今回どうしても桂さんに聞いてみたかった質問をぶつけた。「新しいことを始める、パイオニアになるというのは大変なことも多かったでしょう。どうやって切り開いていったのですか?」
「最初の関門は母だったんですよ」と笑う桂さん。「私は母が経営する学校法人の跡継ぎだったので、両立できるならという条件付きで応援してもらうことになりました」。
「ただね...」と桂さんは続ける。「私がやりたかったのはブライダルのデザイナー。経営を自分でやるつもりはなかったんです」。そこで考えたのがデパートに経営を任せるということ。「だって、どこもやっていないことなんですから、日本初のブライダルサロンが登場!って謳えば、デパートにとっても素晴らしい話題になるでしょう」。
だが、意気揚々と銀座のデパートの婦人服部長に話をしに行った桂さんは思いもかけない拒絶の言葉に驚くこととなる。「うちは呉服がドル箱なんです。ドレスを扱ってそれが売れるようになったらその分売り上げが減ることになるから困るって、そう言われたんです」。
今もその時の悲しさはありありと思いだせる。「本当に悲しくて、帰り道、銀座を泣きながら歩きました。めったに泣くことはないから、あのときだけかもしれません」。
話にすっかり引き込まれて、感情移入しながら耳を傾けていたタケは「それで、そこからどうしたんですか?」とその先が気になる様子。「経営も自分でやるしかないなって決意したんです」と桂さん。
店舗を開く費用は母親が娘の結婚式のためにと貯めていた費用を借りた。赤坂にオープンしたブライダルショップは、「一年間に30人のお客様しか来なかったんですよ」。注文自体は100くらい入ってくるのだが、とにかくキャンセルが多い。当時は花嫁の衣装の決定権を持つのは本人ではなく姑である場合が多かったので、「日本人はやっぱり着物でしょ」という鶴ならぬ姑の一声であっさりキャンセルになってしまったという。
「そんな売り上げでは4人の社員に給与を支払ったら、自分の取り分なんて残らない。それどころか、洋裁学校で午前も午後も夜間も授業をして、それで稼いだお金を店につぎ込むという状況だったんですよ」。
迷いが吹っ切れた瞬間

「そんな毎日ですからね、迷いはありましたよ。でも、ブライダルの仕事をやめようと思ったことは、なぜかなかったんです」という桂さんは、あるできごとをきっかけに、その迷いさえも吹き飛ばすこととなった。それは、世界のトップファッションデザイナー、ピエール・バルマン氏との出会いから生まれた。
「ピエール・バルマンといえば、昭和天皇の皇后様のドレスも手がけているような世界のトップでしょ。そんな方と仕事のご縁で出会って、あるとき私の店を案内することになったんです。そのときに、彼がこう言ったんです」と、桂さんは少女のように微笑みながらその言葉を教えてくれた。
「私はこの世で一番美しいものは花嫁姿だと思っている。でもオートクチュールで仕事をしていて、年に2、3回しかそんなチャンスはない。あなたは毎日ウェディングドレスを作っている。うらやましい人生だ」
「憧れのトップデザイナーからうらやましい人生だって言ってもらったんです」と繰り返した桂さんは、その後きっぱりこう言った。「どんなに身体がボロボロになっても、それ以来一度も迷ったことはありません」。
「迷わないということは、どんなときも決断できるということですよね?決断のコツってあるんですか?」と、ここでタケがみんなが知りたいことを聞いてくれた。
「明らかにどちらがいいかはっきりしているときは、誰でも迷わないで決められるでしょ。迷うのは、どちらにしたらいいかわからないときですよね。でもね、これは亡くなった主人が教えてくれたんだけど、迷ったときって結局どっちを選んでもおんなじなんですよ」
「え?それはどういうこと?」とさらに突っ込むタケに桂さんが教えてくれたのは「どちらにもメリットとデメリットはある。大事なのは、決断した方向をやりぬくことです」。
もうひとつ、経営者として大切にしているのは「重要な決断は朝に行う」ということ。「夜は疲れているからどうしてもネガティブな方向に偏ってしまうんです。前向きな決断をするのは朝がおすすめです」。
「明日、考えよう」

2003年以来、14年連続でパリオートクチュールコレクション(パリコレ)に参加している桂さん。「その継続のパワーはどこから?」と尋ねると、「デザイナー心ってそういうものなんですよ。自分の作品がファッションショーという形でお披露目できるのがとても嬉しい」。
また、「私は顧客ファーストなんです」と、ニッコリ笑う。「社員にも、お客様のことを自分の家族だと思ってアドバイスしなさいよって言っています。あれはできないとか、これはだめですって、すぐにノーと言わない。お客様の希望を実現できるように一緒に考えなさい、って」。そんな気持ちで仕事に臨んでいる桂さんは、かつて「ドレスと同じレースの靴が履きたい」という花嫁の願いをかなえるために自らレースを貼って作ったこともあるという。
「好きな道を選んだから」というのが長年この仕事を続けることができた最大の理由だと話す。「いろんな事情でそうもいかないこともあるでしょうが、やっぱり好きな道を選んだ方がいいですね。好きなことはつらいって思わないでしょ」。
ここでちょっといたずらっぽく笑ってこう付け加えた。「性格的にもとっても楽観的なんです。辛いことを辛いってあまり感じないみたい。血液型がB型のせいかしら」。
好きな言葉は、『風と共に去りぬ』のラストシーンでのスカーレット・オハラのこの言葉。「明日、考えよう」
これからの夢
「まだまだやりたいことがある」という桂さんの今後実現したいことの一つは「結婚式をもっと街中で見られるようにして、子どもたちが憧れるものにしたい」ということ。婚姻率が下がり、「結婚式を挙げないカップルも多いでしょう。挙げたとしても地味婚とか」。
昔は自宅から花嫁が支度をして、近所の方々にごあいさつをして出て行く姿を見て、子供たちはその幸せそうな姿に憧れを募らせた。今ではその習慣が無くなって、「結婚式は式場の中だけのもの。人々の目に触れなくなってしまったでしょう。それを元に戻したいなって考えています」。
「いいですね!大賛成です」とタケもその考えにはおおいに共感。「車の後ろに缶カラつけて、カラカラ音を立てて車が発車して、花嫁さんのベールが風でふわーっとなびくようなのって、いいですよね!」。海外で挙式をしたカップルが、一番うれしかったこととして語るのが「縁もゆかりもない人たちが、コングラチュレーションとかブラボーって声をかけてくれたこと」だという。「それ、海外まで行かなくても、日本でやればいいじゃないのね」。

これまでに乃木坂にある桂由美ブライダルハウスからも何組かの新郎新婦がオープンカーに乗って式場へと向かったことがある。「そのときも、一番に声をかけてくれるのは外国人の方。歩道橋の上からでも大きな声でお祝いの言葉を投げてくれる。日本人にもそういう人がもっと増えるといいな」という桂さんに、タケが胸を叩いた。「まかせてください!その時は私が大きな声を出しに参ります!」。
「その時は、よろしくお願いいたします」と、最後は桂さんによろしくお願いされちゃって、嬉しそうなタケでした。
人気コラムランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5