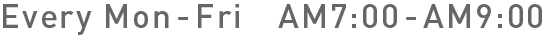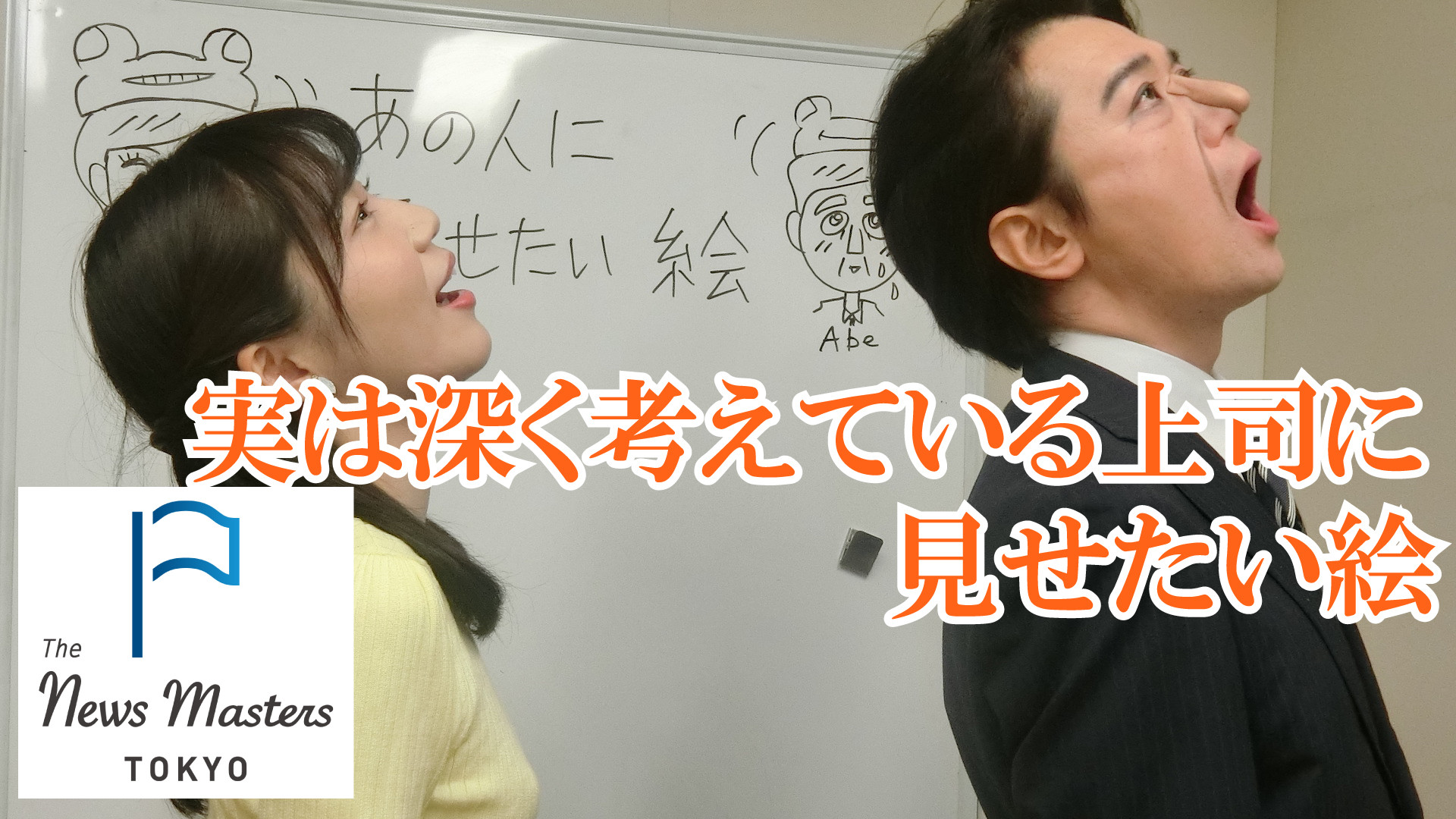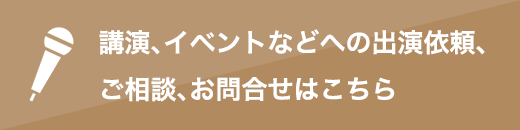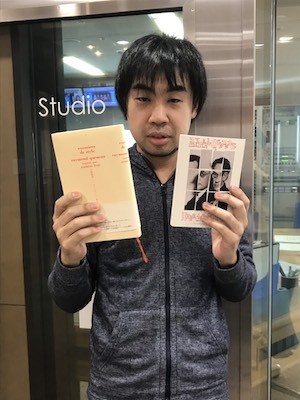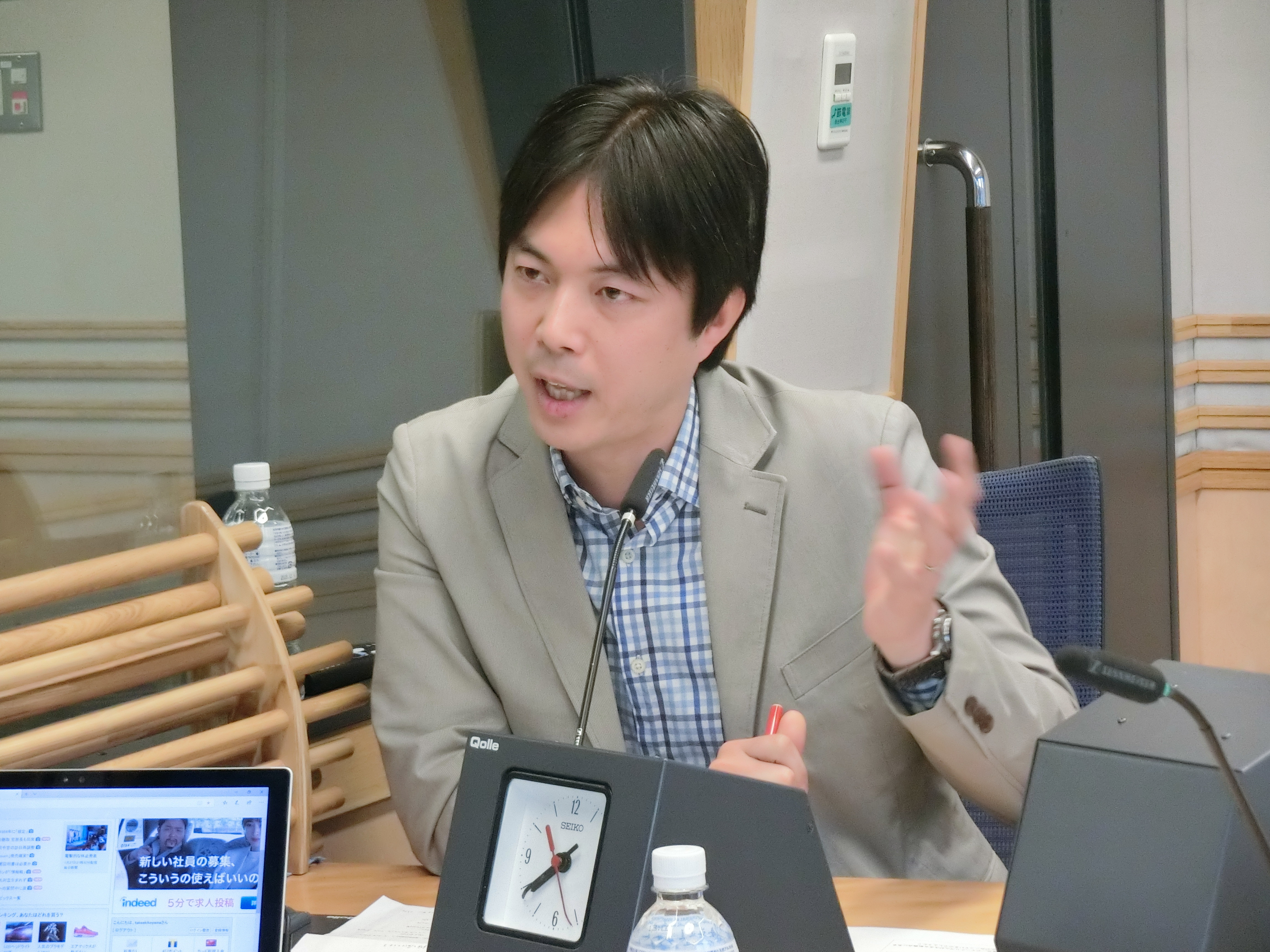チーズで世界平和。チーズのこえ・今野徹の夢

文化放送「The News Masters TOKYO」のマスターズインタビューでタケ小山が今回注目するのは、日本で初めての北海道ナチュラルチーズ専門店「チーズのこえ」を清澄白河で経営している株式会社FOOD VOICE代表の今野徹さん。「100年続くものづくり、1000年続く地域づくりを共に考える」ことを自らのミッションと決めて、さまざまな活動を通じて未来を考えるきっかけづくりを企画し、寸暇を惜しんで全国を飛び回り、多くの人とのface to faceの付き合いを大切にしている。タケ小山と今野徹さんの今回の出会いは、どんな未来につながるのだろうか。
「食べるもので、人を元気にしたい」
今野さんのご実家は代々続く医者家系。両親も医者で、幼いころから「病気を治す」という仕事をする父母に対して尊敬の気持ちを抱いていたという。だが、とにかくハードワークの日々。休日も夜も、急患が出れば家を飛び出し、クリスマスのお祝いも病院優先となり父母とともに家庭で過ごす時間は少なかった。
もちろん素晴らしい仕事だと思っていたし、自分自身も医者になるつもりであったが、「医者がこんなに忙しいのは、それだけ病気の人が多いからだ。病気の人を減らすためにはどうすればいいんだろう」と次第に考えるようになり、高校生の時にはこんな風に考えるようになった。
「食べない人はいないから、食べるもので人を健康にしたい」
病気にならない生き方。その根底にあるのは、人が毎日食べるものである。食べ物で病気を防ぐこともできるのではないか?結局は「食」こそがいちばん大事なんだ。そう気づいた今野さんは、「食のルーツをたどるということを、とことん突き詰めてみたくなったんです」。
「それで選んだのが帯広畜産大学という進路だったわけですが、それはなぜ?」と、タケ。
その質問に対する今野さんの答えは明快だった。「食卓に上るどんな食べ物にも、ルーツがあります。たとえばソーセージなら、材料は肉ですが、その肉は草を食べて、穀物を食べて育ってきた。その一連のつながりをきちんと学問として納めたかったし、そういうことを学ぶには都会の大学よりもリアルな農業や畜産の現場である帯広という土地がふさわしいと思ったんです」。
大学時代には常に全体的なシステムがどうなっているのか、どうつながっているのかを考えながら様々な体験を積み重ねていった。そんな中で、日本の農業をただ発展させるというだけでなく、世界の中でどういう立ち位置を築けるのかということを考えるようになったという。
そこには日本固有の食文化も当然含まれる。「もったいない、いただきます、ごちそうさまというような文化も海外に向けて訴えかけていきたいことのひとつです」。
「なるほど、食という大きな器の全体像を考えていたということですね」と今野さんの想いを的確にキャッチしたタケは、その後の今野さんの活動が気になる様子でどんどん質問を重ねていく。
一年目からとがり続けた公務員時代
「大学卒業後、北海道庁に入庁されたわけですが、大きな役所の新入職員。やりたかったことはできましたか?」と聞くタケに、今野さんは「一年目だから、まずは組織のことを知ることが優先...という考え方もあるんでしょうが、私の場合はこう考えたんです」と笑いながら答えた。
「一年目だから、何にも知らなくても当然なんだから、なんでもやっていいだろうって」。
「ええっ?」と驚くタケ。
「知りませんでしたと言い訳ができるのも、一年目の特権。そう腹を決めてやりたいことをどんどんやっていきました」。
それで、問題はなかったのか?という問いには、「9割の人にうとましがられても、残り1割が面白がってくれればいい。『あいつ、破天荒なこと考えてるから、こっちでも何かやらせてみよう』と思ってくれる人が現れて新しい仕事がまわってきたりもするんです」ときっぱり答えてくれた。
組織の中でコマになるのではなく、とがり続けるからこそ人の注目を集めることができるし、人がついてくる。「そうすることによって自分自身でやりたい仕事をつかんでこられたんだと思います」。
北海道庁には北海道の農業や食に関するありとあらゆる情報が集まる。大きなネットワークの中心でもある。ここを盛り上げることによって日本だけじゃなく、世界に対しても「北海道の農業ここにあり」を発信していこうと決めていた。
「ただ、どうしても2年目、3年目になると良くも悪くも慣れてきて最初の志が鈍ってしまいがち。輝きを失わないでい続けることを大事にしたい」。そんな想いで過ごした道庁時代、多種多様な仕事に携わった。思い出深い仕事の一つに洞爺湖サミットでの体験がある。「晩餐会の準備や来賓のアテンドなどもしました。各国の代表の方と至近距離で過ごすなど良い機会をいただいたな、と感謝しています」。
その後、農林水産省に生産局大豆係長として出向。「それまではずっと畜産だったので、大豆については全く知らない。出向が決まってからは毎日猛勉強しました」。
「プレッシャーも大きかったでしょう?」と気遣うタケに、「はい。三日間くらいは」と笑う今野さん。「日本の大豆のためだったら、なんでもやっていいという立場になったわけですから、プレッシャーよりも楽しさの方が大きかったんですよ!」
だが、その楽しかった農林水産省での仕事を辞めて独立する決意をする日がやってきた。
「決してイヤで辞めたわけではありません。ただ、日本の農業を取り巻く環境が、TPPへの日本の参加が決定したあたりから大きく変化していった。農林水産省として農業だけを見ての政策決定ではなくて、国全体としての判断がそこに入ってくるようになったんです。それまでは自分のやりたいことが100あって、そのうち1でも形になればそれがやがては日本の農業を大きく動かすことにつながるという実感があったが、国という大きい組織に組み込まれた状況では、それでは間に合わないのではないか?と危機感を覚えたんです」。
その危機感が今野さんの背中を押した。「100のうち100を、自分の責任と資金で解決していきたい、それが独立の理由です」。39歳の時であった。
「こえ」という言葉に込められた想い

農林水産省を辞めた時点では、具体的に次に何をするのかは「一切決めてなかったんです」という今野さん。なんと翌日には小笠原諸島へ。その後、九州から関西へと生産者と会っては話す旅を続ける。そしてバックパックを担いでヨーロッパへ。ここでも、現地の友人を通じて各国の食文化に触れながら日々を過ごした。
帰国後は、「自分の市場価値を知りたくて」中途採用を行っている会社にエントリーシートを提出したりもしたそうだ。「履歴書は、ことごとくはじかれたんですよ」と苦笑い。「でも、一方で、これまでに実際に会って関わった人たちからはたくさんのオファーをいただけたんです」。
様々な体験を重ねつつ、考え続けた結果、今野さんは「自分で実業を回していこう」と決意する。そして扱うものとして、公務員時代に長年関わってきた北海道のチーズを選んだ。

「特にチーズが好きということではないんです。その頃も今も朝ご飯は米とみそ汁と梅干と納豆という生活ですしね」。
ただ、農林水産省時代を東京で過ごして気づいたことがあった。「東京ではどこを探しても当時は北海道のチーズが見つからなかったんです」。千葉や長野のチーズは、生産者を招いたイベントなども開かれていてお店での取り扱いも多い。かたや北海道のチーズは「100以上のチーズ工房があるのに、誰もそのことを知らない。海を隔てているということはこんなにもハンディなんだなと気づいたんです」。

日本の乳牛の60%が北海道にいる。その北海道で作られたチーズの存在を、東京の人は知らない。それはつまり、北海道の酪農に関する無関心にもつながっている。「どこかで、その"知らない"連鎖に歯止めをかけたい」と、今野さんは決意した。それが清澄白河という場所に日本で唯一の北海道のナチュラルチーズ専門店「チーズのこえ」を開く原動力となった。「東京には世界各国のおいしいものが揃っている。チーズといえば、フランスでしょ!という人たちに、北海道のチーズのすばらしさを知ってもらいたかった」。
店名を「チーズのこえ」と名付けたのは、食べ物の声なき声を伝えたいと思ったから。一つの食べ物が背負っているもの、つまり、どんな人が携わり、どこで作ったのか、そこはどんな土壌でどんなふうに水が流れ、風が吹いているのか。酪農家だけでなく、牧草を育てる人、牛の蹄を直す人、完成したチーズを運ぶ人もいる。食べ物ができる土壌になるためには、何百年にもわたる開拓の歴史があったかもしれない。「そういうことを、誰かが伝えていかなければならない」と今野さんは熱く語る。「声なき声の代弁者でありたいんです」。
母体となる今野さんの会社の名前も「FOOD VOICE」。やはり「こえ」である。食卓に上がるまでに関わったすべてのひと・ものの「こえ」を大事にするとともに、「チーズのこえでチーズを買ってくださった人のこえも、ちゃんと生産者に届けたい。声の行き来ができる場でありたい」。
「ゴールはまだずっと先」

「チーズのこえは、まだ夢への第一歩です」と語る今野さん。「これまでは専門性が高くて閉鎖感があったチーズの世界を、商店街の八百屋や肉屋みたいに訪れるお客さんの日常の生活に寄り添って提案していけるものに変えていきたい。それを端的に表すものとして『コンシェルジュ』と名乗っています。こういう店のあり方が一つのチャレンジとして成功していくことが、生産地と食卓をつなぐ小売業という新しいモデルロールになることを願っています」。
今野さんにとって「チーズのこえ」はゴールではない。まだまだ先に大きな夢がある。
「その夢って何ですか?」と聞くタケに、まっすぐな視線で今野さんはこう答えた。「世界平和です」
「でかすぎないですか?」と驚くタケだが、今野さんは動じない。「食というのは、たとえば戦争になったときには兵糧攻めという言葉もあるように、重要な戦略物資となる。将来的に農業がずっと続いていって、世界中の人が飢えないようにするためには、日々の小さな買い物が大事なんですよ」。
今野さん曰く「全部つながっているんです」。世界はみんなつながっている。北海道のチーズを買うことで、北海道の酪農家を救うことになる。北海道の酪農家が育てた子牛が全国の酪農家の元に行き、生乳をつくる。全国の酪農家がいることで、飼料を育てる農家が助かる。エサを輸入する必要がなくなれば、その分のエネルギーも必要なくなる。
エネルギー用に消費されるトウモロコシを飼料に回せば、ブラジルの農家が牛を飼えるようになる...とつながっていけば、世界から貧困をなくし、やがては世界平和にもたどりつける...。北海道のチーズを買うことが、ブラジルの農家の生活に影響する。まるでわらしべ長者のようだが、すべてはつながっているのだ。
「ずっとこの食べ物が続いていってほしいな、そう思って買い物をしてほしい。買い物というのは、賛成や共感や応援の一票を投じることなんです」。
主語を「I」で語りたい

今後の夢の一つとして、今野さんは「システムから生活を取り戻すこと」を挙げる。
利便性を追求する現代のライフスタイルの中ではマニュアルが優先されて生活が空洞化している。「手触りのある生活を取り戻したいんです」。食生活においても「本来、経済発展の中ではエンゲル係数は低くなっていくというのが経済学の常識なんですが、仕込んだ味噌が出来上がるまで長期間待つというようなことが昔から行われてきた日本の食文化においては、経済が豊かになるとともに、食に対してもっと時間やお金をかけるようになるというのがあるべき姿なんじゃないでしょうか」。これは、決して「古き良き時代への懐かしさ回帰」ではない。「現代のライフスタイルに合わせた形で取り戻していきたい」
東京にすべてのものが集まるという現状も変えていきたいという。「本当においしいものは産地にしかない。作られた場所に行って初めて、五感のすべてで味わえる」という今野さんに、「あれ?今やっていること(東京に北海道チーズの専門店を開いていること)とは逆では?」と突っ込むタケ。
「そうですね」とあっさり同意して、今野さんはこう続けた。「私がやっているのは、きっかけづくりなんですよ。チーズのこえで買ったチーズがおいしかったからと、産地を訪ねてくれるひとがいる。そんなふうに、人を動かしていきたいんです」。
傍観者でいるのではなく、自ら舞台に上がって動く人になってほしい。「主語をIで話そうよ、と呼び掛けています。誰かがこう言っていたではなくて、自分はこう思う、こう考えるということを恐れずに発信していきたい」。
SNSが普及して、誰もが多弁にはなったが、そのほとんどが他人の意見の受け売りに過ぎない。「自分の意見を表明すると、当然反対意見も多く来る。だいたい5人の応援に対して95人の反対くらいの割合ですよ」。それでも、「その応援や反対というのは、その人自身の意見。思わず自分の言葉で語りたくなるような違和感を持たせるのも役割かなと思ってやっています」。
「広く深く、すべてに欲張り続けてやってきたし、いまもやっている」という今野さん。
最後にタケが聞いたのは「走り続けている今野さんが、いちばんリラックスできる時間はどんなとき?」。
少し考えた後で、こんな答えが返ってきた。「チーズを切っているときですね」
無心になれる時間だというそのひととき、どんな「こえ」を今野さんはキャッチしているのだろうか。

人気コラムランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5