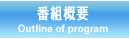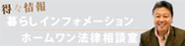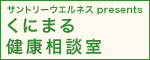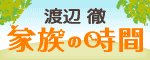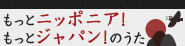11月9日(月)「花緑さんの子供時代」
戦後の落語界で最年少となる22歳で真打ち昇進した柳家花緑さん。お祖父様は人間国宝の五代目柳家小さんさん。母親は女優を目指したこともあり芸能に素養のある方で、叔父は六代目柳家小さんさんという芸能の家庭で育ちました。両親が離婚したため、お祖父様が父親代わりだったそうです。花緑さんは小学校6年生の時に落語家になることを決意したそうですが、それにはお母様の思惑があったそうです。
11月10日(火)「修行時代」
花緑さんは中学を卒業すると高校に行かず、前座生活が始まりました。寄席にも通うようになりましたが、その時すでにいくつも噺が出来たそうです。祖父である柳家小さん師匠の稽古は型の口移しから始まり「間」を重視したものでした。2年半の前座生活を経て、二つ目にスピード昇進すると自分の時間が出来るようになり、色々考えることも多くなったそうです。その頃「柳家小さんの孫」と言われることをどのように感じていたのでしょうか?
11月11日(水)「真打ち昇進そして苦悩」
落語界のサラブレットとして順風満帆だったはずの花緑さん。「柳家小さんの孫」と言われることが、どんどん辛くなってきます。22歳で真打ちに昇進されますが、プレッシャーも重なり精神状態は最悪だったそうです。躁鬱のような状態に苦しみ、自由になりたくて初めての一人暮らしを始めました。高座に上がることも苦痛になり、自殺したいと思うこともあったそうです。しかし、その後TVに出る機会が増え、すこしずつ花緑さんは変わっていきます。
11月12日(木)「新たなるチャレンジ」
花緑さんは洋服を着て椅子に座ってする新作落語にチャレンジしています。
古典落語と新作落語の二足のわらじと言いますが、それにはどのような思いが込められているのでしょうか?また、落語は冬の時代もあれば、ブームになった時代もあります。花緑さんはそれをどう感じていらっしゃるのか、お祖父様の小さん師匠が語っていた言葉を交えつつ、お話頂きました。
11月13日(金)「お芝居とこれからの花緑さん」
花緑さんはお芝居にも積極的に出演しています。芝居はひとりで完結する落語と違い、共演者との掛け合いや、立ち上がったり、駈け出したりなど、よりリアルな世界が楽しくて仕方ないそうです。また、気持ちのありようなど、落語との違いも話してくださいました。40歳代半ばになり、弟子も育てたいという思いもあるそうですが、なにを言うかよりどうあるか。お祖父様の背中を見て育ってきたからこその思いがそこにはあるようですが・・・。
<プロフィール>
1987年3月 中学卒業後、祖父・五代目柳家小さんに入門。前座名 九太郎。
1989年9月 二ツ目昇進。小緑と改名。
1994年 戦後最年少の22歳で真打昇進。柳家花緑と改名。
2003年3月に落語界の活性化を目的として結成された「六人の会」(春風亭小朝、笑福亭鶴瓶、林家正蔵、春風亭昇太、立川志の輔) のメンバー。